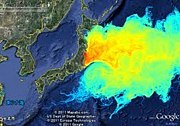首長調査、立場により認識ズレ(2012年5月2日午前7時18分)
原発再稼働アンケート
原発の再稼働に同意が必要な「地元」の範囲をどこまでとするか―。東京電力福島第1原発事故を踏まえ福井県内の17市町長のうち半数以上の9人が、立地自治体以外にも広げるべきだと考えていることが福井新聞社のアンケート調査で分かった。立地、準立地、30キロ圏内とそれぞれの立場により「地元」のとらえ方はくっきりと分かれている。(原発取材班)
現状では、県と立地市町だけが電力事業者との間で運転再開の協議を盛り込んだ原子力安全協定を結んでおり、再稼働の際に「同意」が必要な根拠になっている。
ただ、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働をめぐり京都、滋賀両府県知事は、事故があれば原発立地地域と同じく大きな被害を受ける「被害地元」と反発。政府は両府県の「理解」も得る方針で、地元の範囲について政府の認識はあいまいさを残している。また、小浜市など4市町でつくる県原発準立地市町連絡協議会は福島の事故後、安全協定を「立地並み」に見直すよう要請している。
アンケートで、地元同意は現行通り「立地自治体」に限定すべきだと回答したのは、敦賀、美浜、おおい、高浜の立地4市町と大野、永平寺の計6市町。岡田高大大野市長は「立地自治体の意見を最優先すべきだ」と指摘した。時岡忍おおい町長は同意の範囲を限定した上で「国策のため周辺地域の理解が必要」と政府の対応を求めた。
一方、「立地自治体と準立地自治体」と答えたのは小浜、若狭、南越前、越前町の4市町。福井、鯖江、池田、坂井、勝山の計5市町は「原発から30キロ圏内の自治体」と回答した。「50キロ圏内の自治体」はゼロだった。
国は福島の事故を受け防災対策の重点地域を30キロ圏に拡大する方針で、県内ではあわら、坂井、勝山、大野、永平寺の5市町を除く12市町が対象となる。さらに半径50キロが放射性ヨウ素防護地域(PPA)となる。防災面で新たな対応が必要になることが、再稼働をめぐっても「地元」としてとらえるべきだとの考え方につながっているとみられる。
敦賀原発から約55キロと県内で最も遠いあわら市の橋本達也市長が「モニタリングポストやヨウ素剤の配布を県に要望しており、広い意味では『地元』と言えるが、再稼働の条件となるような意味では判断が難しい」と答えるなど、同意の対象と防災対策を厳密に切り離して考える難しさもうかがえた。
アンケートは4月中旬に実施し、17市町長から文書で回答を得た。
■県議1/4が「30キロ圏内」■
原発の再稼働への同意が必要な「地元」の範囲については、県議全35人を対象にした福井新聞社のアンケートでも、半数以上の19人が立地自治体以外も範囲に含めるべきだと答えた。「立地自治体」に限る回答が最多の一方、ほぼ4分の1が「原発から30キロ圏内の自治体」が適当とし、意見は割れた。
調査では、12人が「立地自治体」で最も多く、「立地自治体と準立地自治体」は10人、「30キロ圏内」は9人。「50キロ圏内」はゼロだった。
立地市町が地元の4議員は全員が「立地」と回答。準立地市町の5人中4人は「準立地」「30キロ圏内」と答えた。
原発から30キロ圏内で立地、準立地を除く市町が地元の議員17人の回答をみると、4人が「立地」としたのに対し、「準立地」は5人、「30キロ圏内」6人と、拡大する考え方が大勢を占めた。
「その他」のうち1人は、県内に限定した上で準立地自治体まで広げるべきだとした。「立地」と回答した嶺北の議員は「同意(の対象)は立地自治体だが、より広い理解が必要」と指摘した。「福島の事故をみれば単純に距離で示せない」と一律の線引きに慎重な意見もあった。
原発再稼働アンケート
原発の再稼働に同意が必要な「地元」の範囲をどこまでとするか―。東京電力福島第1原発事故を踏まえ福井県内の17市町長のうち半数以上の9人が、立地自治体以外にも広げるべきだと考えていることが福井新聞社のアンケート調査で分かった。立地、準立地、30キロ圏内とそれぞれの立場により「地元」のとらえ方はくっきりと分かれている。(原発取材班)
現状では、県と立地市町だけが電力事業者との間で運転再開の協議を盛り込んだ原子力安全協定を結んでおり、再稼働の際に「同意」が必要な根拠になっている。
ただ、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働をめぐり京都、滋賀両府県知事は、事故があれば原発立地地域と同じく大きな被害を受ける「被害地元」と反発。政府は両府県の「理解」も得る方針で、地元の範囲について政府の認識はあいまいさを残している。また、小浜市など4市町でつくる県原発準立地市町連絡協議会は福島の事故後、安全協定を「立地並み」に見直すよう要請している。
アンケートで、地元同意は現行通り「立地自治体」に限定すべきだと回答したのは、敦賀、美浜、おおい、高浜の立地4市町と大野、永平寺の計6市町。岡田高大大野市長は「立地自治体の意見を最優先すべきだ」と指摘した。時岡忍おおい町長は同意の範囲を限定した上で「国策のため周辺地域の理解が必要」と政府の対応を求めた。
一方、「立地自治体と準立地自治体」と答えたのは小浜、若狭、南越前、越前町の4市町。福井、鯖江、池田、坂井、勝山の計5市町は「原発から30キロ圏内の自治体」と回答した。「50キロ圏内の自治体」はゼロだった。
国は福島の事故を受け防災対策の重点地域を30キロ圏に拡大する方針で、県内ではあわら、坂井、勝山、大野、永平寺の5市町を除く12市町が対象となる。さらに半径50キロが放射性ヨウ素防護地域(PPA)となる。防災面で新たな対応が必要になることが、再稼働をめぐっても「地元」としてとらえるべきだとの考え方につながっているとみられる。
敦賀原発から約55キロと県内で最も遠いあわら市の橋本達也市長が「モニタリングポストやヨウ素剤の配布を県に要望しており、広い意味では『地元』と言えるが、再稼働の条件となるような意味では判断が難しい」と答えるなど、同意の対象と防災対策を厳密に切り離して考える難しさもうかがえた。
アンケートは4月中旬に実施し、17市町長から文書で回答を得た。
■県議1/4が「30キロ圏内」■
原発の再稼働への同意が必要な「地元」の範囲については、県議全35人を対象にした福井新聞社のアンケートでも、半数以上の19人が立地自治体以外も範囲に含めるべきだと答えた。「立地自治体」に限る回答が最多の一方、ほぼ4分の1が「原発から30キロ圏内の自治体」が適当とし、意見は割れた。
調査では、12人が「立地自治体」で最も多く、「立地自治体と準立地自治体」は10人、「30キロ圏内」は9人。「50キロ圏内」はゼロだった。
立地市町が地元の4議員は全員が「立地」と回答。準立地市町の5人中4人は「準立地」「30キロ圏内」と答えた。
原発から30キロ圏内で立地、準立地を除く市町が地元の議員17人の回答をみると、4人が「立地」としたのに対し、「準立地」は5人、「30キロ圏内」6人と、拡大する考え方が大勢を占めた。
「その他」のうち1人は、県内に限定した上で準立地自治体まで広げるべきだとした。「立地」と回答した嶺北の議員は「同意(の対象)は立地自治体だが、より広い理解が必要」と指摘した。「福島の事故をみれば単純に距離で示せない」と一律の線引きに慎重な意見もあった。
|
|
|
|
|
|
|
|
原発を動かさないで 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-