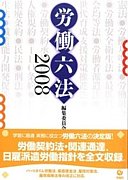こんにちは。本日加入させていただいたtomtomと申すものです。
以前『労働基準法勉強会』というコミュにはいっていたことがあるのですが、そこは管理人が事実上不在のひどく荒れたコミュでした。それに知ったかぶりをするいやなタイプのメンバーがいて、愛想がつきて退会してしまいました。私もコミュをいくつかもって管理していますが、コミュではやはり管理人がある程度の存在感を発揮していることは必要ですね。
当コミュでは管理人さんがしっかり存在感を発揮しているようです。また一つ興味を惹いたのが、コミュニティリンクに唯一『偽装請負』という名称のコミュがリンクされている点です。
私は実は、特許事務所に翻訳者として就労するとき、この「偽装請負」という就労を実体験しました。「偽装請負」が起こることを未然に防止するには、事業主側が労働法規に対してしっかりとした理解を持つことが必要ですが、一方、就労する側も、偽装請負を開始するさいの事業主との話し合いの中に発生する胡散臭さに対する感受性を研ぎ澄まして、「この就労形態は胡散臭いぞ…」ということに気付くことが必要ですね。
この感受性の研磨のためには、「偽装請負」という言葉(概念)を理解しておくだけでも役に立ちそうです。
皆さんの周辺にある偽装請負について、知っている事例があれば教えていただけませんでしょうか。
以前『労働基準法勉強会』というコミュにはいっていたことがあるのですが、そこは管理人が事実上不在のひどく荒れたコミュでした。それに知ったかぶりをするいやなタイプのメンバーがいて、愛想がつきて退会してしまいました。私もコミュをいくつかもって管理していますが、コミュではやはり管理人がある程度の存在感を発揮していることは必要ですね。
当コミュでは管理人さんがしっかり存在感を発揮しているようです。また一つ興味を惹いたのが、コミュニティリンクに唯一『偽装請負』という名称のコミュがリンクされている点です。
私は実は、特許事務所に翻訳者として就労するとき、この「偽装請負」という就労を実体験しました。「偽装請負」が起こることを未然に防止するには、事業主側が労働法規に対してしっかりとした理解を持つことが必要ですが、一方、就労する側も、偽装請負を開始するさいの事業主との話し合いの中に発生する胡散臭さに対する感受性を研ぎ澄まして、「この就労形態は胡散臭いぞ…」ということに気付くことが必要ですね。
この感受性の研磨のためには、「偽装請負」という言葉(概念)を理解しておくだけでも役に立ちそうです。
皆さんの周辺にある偽装請負について、知っている事例があれば教えていただけませんでしょうか。
|
|
|
|
コメント(63)
一般的には、労働者派遣に該当するにも関わらず、民法上の請負と称して
あるいは契約上もそのように装って、多くは集団で労務の提供をおこなうことを
偽装請負といってると思われます。
制服や資材、用具、器具、機械その他を請け負った側が用意し、
発注元の担当者の指揮命令等を排除しなければならないところを
発注元の指揮命令の下に、業務を行っていた事例が多かったようです。
※厚生労働省よりガイドラインがでていますのでご参照ください。
特に、数年前にメーカーでこの形式の就労が散見され、
労働局の勧告を受けたケースもあったように記憶しています。
従って、偽装請負に関しては主として「労働者派遣法:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」違反が問題となります。 以上
あるいは契約上もそのように装って、多くは集団で労務の提供をおこなうことを
偽装請負といってると思われます。
制服や資材、用具、器具、機械その他を請け負った側が用意し、
発注元の担当者の指揮命令等を排除しなければならないところを
発注元の指揮命令の下に、業務を行っていた事例が多かったようです。
※厚生労働省よりガイドラインがでていますのでご参照ください。
特に、数年前にメーカーでこの形式の就労が散見され、
労働局の勧告を受けたケースもあったように記憶しています。
従って、偽装請負に関しては主として「労働者派遣法:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」違反が問題となります。 以上
21番で優柔不断さんが「民法に違反する疑いがある」とおっしゃっていますよね。
派遣会社が関与している場合は、CWさんのおっしゃるとおりでよろしいと思います。ところが、私のように派遣会社が全く関与せず、個人として偽装請負をさせられた場合は、結局民法に違反するのだと思います。
民法では、人間の就労の形態は根本的には「請負」「委任」「雇用」の3つに収斂するとしています。例えば昔の奴隷的労働搾取は違法になるわけです。なぜかというと、奴隷的労働搾取は、「請負」にも「委任」にも「雇用」にも該当しないからです。
「偽装請負」も結局これと同じです。「偽装請負」は「請負」にも「委任」にも「雇用」にも該当しません。つまり、日本の法規で法的枠組みとして認定された就労の形態ではないということです。
派遣会社が関与している場合は、CWさんのおっしゃるとおりでよろしいと思います。ところが、私のように派遣会社が全く関与せず、個人として偽装請負をさせられた場合は、結局民法に違反するのだと思います。
民法では、人間の就労の形態は根本的には「請負」「委任」「雇用」の3つに収斂するとしています。例えば昔の奴隷的労働搾取は違法になるわけです。なぜかというと、奴隷的労働搾取は、「請負」にも「委任」にも「雇用」にも該当しないからです。
「偽装請負」も結局これと同じです。「偽装請負」は「請負」にも「委任」にも「雇用」にも該当しません。つまり、日本の法規で法的枠組みとして認定された就労の形態ではないということです。
本日の朝日新聞に、偽装請負の問題をめぐっての訴訟事件について、最高裁第2小法廷にて弁論が開かれる旨を伝える記事が載っていましたので、ご紹介します。
写真はその記事の切り抜きですが、読みにくいかもしれませんので、概要を紹介しますと、まず訴訟の原告は、請負会社の社員として働いていた吉岡力さんという方です。この人が請負会社を通じて被告であるパナソニック・プラズマディスプレイの工場で働いていたわけです。
これについて、原告は、吉岡さんの実際の就労の実態は、偽装請負に該当するもので違法であることの認定を求め、あわせて未払いの賃金の支払を求めていました。二審の大阪高等裁判所では、原告の主張を認める判決がでており、被告のパナソニック側が最高裁に上告していたわけです。
写真はその記事の切り抜きですが、読みにくいかもしれませんので、概要を紹介しますと、まず訴訟の原告は、請負会社の社員として働いていた吉岡力さんという方です。この人が請負会社を通じて被告であるパナソニック・プラズマディスプレイの工場で働いていたわけです。
これについて、原告は、吉岡さんの実際の就労の実態は、偽装請負に該当するもので違法であることの認定を求め、あわせて未払いの賃金の支払を求めていました。二審の大阪高等裁判所では、原告の主張を認める判決がでており、被告のパナソニック側が最高裁に上告していたわけです。
tomtomさん、いちはやく情報を載せていただいてありがとうございます。
私だけでなく、このコミュニティーに参加されている皆さんへの貴重な参考になったことと思います。
私は労働法の研究者ですが、この「松下プラズマディスプレイ事件」は、関係者の間で、「おそらく最高裁で引っくり返ってしまうだろう」と残念な予想が立てられていました。
この事件の実態は憂慮すべきもので、早急にこのような形態の違法な派遣が排除されなければばならないことは当然なのですが、高裁の判決は、現在の最高裁に受け入れられる内容ではありませんでした。
問題は、最高裁が、高裁の判断を覆すにあたってどのような論理を示すか、です。それによって、今後の偽装請負や脱法的派遣への政策対応も変わってくるのではないかと思います。
私だけでなく、このコミュニティーに参加されている皆さんへの貴重な参考になったことと思います。
私は労働法の研究者ですが、この「松下プラズマディスプレイ事件」は、関係者の間で、「おそらく最高裁で引っくり返ってしまうだろう」と残念な予想が立てられていました。
この事件の実態は憂慮すべきもので、早急にこのような形態の違法な派遣が排除されなければばならないことは当然なのですが、高裁の判決は、現在の最高裁に受け入れられる内容ではありませんでした。
問題は、最高裁が、高裁の判断を覆すにあたってどのような論理を示すか、です。それによって、今後の偽装請負や脱法的派遣への政策対応も変わってくるのではないかと思います。
「松下プラズマディスプレイ事件」の経緯は知りませんでしたが、ブログに情報がありますね(下記アドレス↓)。
http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/53991882.html
この偽装請負の問題は厄介なところがあると思います。それは偽装請負させられた人の被害をどう認定し救済するかという点です。
私の場合ですと、特許事務所の経営者から、事実上の偽装請負就労者として就労することを提案され、私としてはその提案を受け入れて、事業所内に入って就労を開始したわけですが、当初のその「提案」では、ごく大雑把な勤務の形態の説明と、報酬の金額と、その支払い方について、簡単な口約束ベースでの合意があっただけなのです。
ところが、実際に就労してみると、特許事務所側が私に対して勤労管理(あるいは指揮命令)をしようとする姿勢を見せ、そこで結果的に実質的な偽装請負就労になったのです。
もしこの特許事務所経営者の行動が違法であるとすると、どの段階で違法行為があったことになるのかという認定は結構難しいですね。最初に就労条件を提示した段階で違法行為になるのか、それとも、正規雇用していない私に対して指揮命令を下そうとした段階で違法になるのか、そのあたりです。そしてその違法行為によって私にどんな被害や不利益があったものと認定できるか、という点も難しいです。
弁護士のみなさんやこれから弁護士資格を取得してクライアントの利益のために奮闘することを志している方などは、このあたりを十分注視してください。
http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/53991882.html
この偽装請負の問題は厄介なところがあると思います。それは偽装請負させられた人の被害をどう認定し救済するかという点です。
私の場合ですと、特許事務所の経営者から、事実上の偽装請負就労者として就労することを提案され、私としてはその提案を受け入れて、事業所内に入って就労を開始したわけですが、当初のその「提案」では、ごく大雑把な勤務の形態の説明と、報酬の金額と、その支払い方について、簡単な口約束ベースでの合意があっただけなのです。
ところが、実際に就労してみると、特許事務所側が私に対して勤労管理(あるいは指揮命令)をしようとする姿勢を見せ、そこで結果的に実質的な偽装請負就労になったのです。
もしこの特許事務所経営者の行動が違法であるとすると、どの段階で違法行為があったことになるのかという認定は結構難しいですね。最初に就労条件を提示した段階で違法行為になるのか、それとも、正規雇用していない私に対して指揮命令を下そうとした段階で違法になるのか、そのあたりです。そしてその違法行為によって私にどんな被害や不利益があったものと認定できるか、という点も難しいです。
弁護士のみなさんやこれから弁護士資格を取得してクライアントの利益のために奮闘することを志している方などは、このあたりを十分注視してください。
21番優柔不断さん
>それは、単に個人事業主として、請負内容の確認不足では?請負内容以上のものを要求して
>きたなら、民法の扱いになるような気がしますが、従う義務は無いように思います。
「労働の定義について」のトピ(下記アドレス↓)
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=46778350&comm_id=592213
において、17番のメッセージを書いていて、考え付いたことがあります。このトピにおける21番において、優柔不断さんが、「偽装請負就労をさせている事業主が、事業所内で就労している個人事業主に対して指揮命令を下したとしても、その個人事業主は従う義務はないはずだ」という指摘をされています。
まさにそのとおりではあります。すなわち、安易に指揮命令に従わさせられるような環境に身を置いた私の「不覚」もたしかに問題ではありました。だが、同時に、個人事業主の身分にある者を指揮命令に服させようとしたこの事業主の行動の違法性も非難されるべきであると考えます。
そうでないと「つりあい」がとれないでしょう。いや、むしろ後者のほうが本当に問題なのです。
>それは、単に個人事業主として、請負内容の確認不足では?請負内容以上のものを要求して
>きたなら、民法の扱いになるような気がしますが、従う義務は無いように思います。
「労働の定義について」のトピ(下記アドレス↓)
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=46778350&comm_id=592213
において、17番のメッセージを書いていて、考え付いたことがあります。このトピにおける21番において、優柔不断さんが、「偽装請負就労をさせている事業主が、事業所内で就労している個人事業主に対して指揮命令を下したとしても、その個人事業主は従う義務はないはずだ」という指摘をされています。
まさにそのとおりではあります。すなわち、安易に指揮命令に従わさせられるような環境に身を置いた私の「不覚」もたしかに問題ではありました。だが、同時に、個人事業主の身分にある者を指揮命令に服させようとしたこの事業主の行動の違法性も非難されるべきであると考えます。
そうでないと「つりあい」がとれないでしょう。いや、むしろ後者のほうが本当に問題なのです。
>安易に指揮命令に従わさせられるような環境に身を置いた私の「不覚」もたしかに問題では
>ありました。だが、同時に、個人事業主の身分にある者を指揮命令に服させようとしたこの
>事業主の行動の違法性も非難されるべきであると考えます。
自己レスです。ここで私が申し上げていることはお分かりですよね。
例えばの話、AさんがBさんに、電話を使って振り込め詐欺をはたらいたとします。Bさんは騙されて100万円を振り込んでしまったとします。
これについて「Bさんは安易に人に騙されてだめじゃないか」という議論は、一応一理あります。しかし、本質的な問題行為は、やはり、振り込め詐欺をはたらいたAさんの行為であるはずです。
これと同じなんですよ。やはり、偽装請負就労が発生してしまう根本原因は、主として事業主の側にあると思います。
では、なぜ世の事業主は労働者を偽装請負就労させたいという誘惑に駆られるのでしょう。私の考えでは、人を正規に「雇用」の手続を経て就労させてしまうと、労働基準法等、労働法規に規定された被雇用者としての法的地位がその人に発生してしまうからだと思います。逆に言えば、事業主としては、労働者の法的地位を尊重する義務が発生するわけです。
事業主は、労働者の法的地位は尊重せず、指揮命令権だけは発揮したい、そういうずるい思惑があるため、人を偽装請負就労させるのでしょう。
>ありました。だが、同時に、個人事業主の身分にある者を指揮命令に服させようとしたこの
>事業主の行動の違法性も非難されるべきであると考えます。
自己レスです。ここで私が申し上げていることはお分かりですよね。
例えばの話、AさんがBさんに、電話を使って振り込め詐欺をはたらいたとします。Bさんは騙されて100万円を振り込んでしまったとします。
これについて「Bさんは安易に人に騙されてだめじゃないか」という議論は、一応一理あります。しかし、本質的な問題行為は、やはり、振り込め詐欺をはたらいたAさんの行為であるはずです。
これと同じなんですよ。やはり、偽装請負就労が発生してしまう根本原因は、主として事業主の側にあると思います。
では、なぜ世の事業主は労働者を偽装請負就労させたいという誘惑に駆られるのでしょう。私の考えでは、人を正規に「雇用」の手続を経て就労させてしまうと、労働基準法等、労働法規に規定された被雇用者としての法的地位がその人に発生してしまうからだと思います。逆に言えば、事業主としては、労働者の法的地位を尊重する義務が発生するわけです。
事業主は、労働者の法的地位は尊重せず、指揮命令権だけは発揮したい、そういうずるい思惑があるため、人を偽装請負就労させるのでしょう。
27番からの自己レスです。
>民法では、人間の就労の形態は根本的には「請負」「委任」「雇用」の3つに収斂すると
>しています。例えば昔の奴隷的労働搾取は違法になるわけです。なぜかというと、奴隷的
>労働搾取は、「請負」にも「委任」にも「雇用」にも該当しないからです。
>「偽装請負」も結局これと同じです。「偽装請負」は「請負」にも「委任」にも「雇用」にも
>該当しません。つまり、日本の法規で法的枠組みとして認定された就労の形態ではないということです。
私がある特許事務所で体験した就労形態は「請負」にも「委任」にも「雇用」にも該当しない、だから違法行為なのだということを申し上げました。このことを逆に言うと、人と人とが何か労働関係を結ぶときは、「請負」でいくか「委任」でいくか「雇用」でいくか、どれかをはっきり選択しなければならない、ということになると思います。
そして「請負」でいくなら、徹頭徹尾「請負」でいく。そして「請負」としての民法上の要件を徹底的に具備するようにする。「委任」でいくなら、徹頭徹尾「委任」でいく。そして「委任」としての民法上の要件を徹底的に具備するようにする。「雇用」でいくなら、徹頭徹尾「雇用」でいく。「雇用」としての民法上の要件および労働基準法等労働法規の要件を徹底的に具備するようにする。そういうメリハリが大事なのだということが言えると思います。
「偽装請負」は、使用者が従業者に指揮命令を下そうとする傾向があり、そうかといって、指揮命令を下すときは、労働基準法等の労働法規を遵守する形で労働者を勤労管理する姿勢は維持しないわけですから、「請負」としての徹底性もないし「雇用」としての徹底性も欠如しています。だから胡散臭いし、違法なのです。
ところで、「偽装請負」の就労形態は、「請負」としての要件を具備していないことをもって「偽装だ」と言っているわけですが、こういった胡散臭い就労形態は、雇用としての要件も具備していないし、委任としての要件も具備していないということになります。「請負」としての要件を具備していないことをもって「偽装だ」という言い方が可能ならば、これを「雇用」としての要件を具備していないことをもって「偽装だ」という言い方も可能になるような気がします。このため、「偽装雇用」という言い方も可能ではないかと思います。さらに同じ理由で「偽装委任」という言い方も可能であるように思います。
ただし、「偽装雇用」や「偽装委任」という言葉は、いまのところ私は目にしていません。だから、図に示したハッチングを付した部分については、これを「偽装請負」と言うことにするのがよろしいのでしょう。
>民法では、人間の就労の形態は根本的には「請負」「委任」「雇用」の3つに収斂すると
>しています。例えば昔の奴隷的労働搾取は違法になるわけです。なぜかというと、奴隷的
>労働搾取は、「請負」にも「委任」にも「雇用」にも該当しないからです。
>「偽装請負」も結局これと同じです。「偽装請負」は「請負」にも「委任」にも「雇用」にも
>該当しません。つまり、日本の法規で法的枠組みとして認定された就労の形態ではないということです。
私がある特許事務所で体験した就労形態は「請負」にも「委任」にも「雇用」にも該当しない、だから違法行為なのだということを申し上げました。このことを逆に言うと、人と人とが何か労働関係を結ぶときは、「請負」でいくか「委任」でいくか「雇用」でいくか、どれかをはっきり選択しなければならない、ということになると思います。
そして「請負」でいくなら、徹頭徹尾「請負」でいく。そして「請負」としての民法上の要件を徹底的に具備するようにする。「委任」でいくなら、徹頭徹尾「委任」でいく。そして「委任」としての民法上の要件を徹底的に具備するようにする。「雇用」でいくなら、徹頭徹尾「雇用」でいく。「雇用」としての民法上の要件および労働基準法等労働法規の要件を徹底的に具備するようにする。そういうメリハリが大事なのだということが言えると思います。
「偽装請負」は、使用者が従業者に指揮命令を下そうとする傾向があり、そうかといって、指揮命令を下すときは、労働基準法等の労働法規を遵守する形で労働者を勤労管理する姿勢は維持しないわけですから、「請負」としての徹底性もないし「雇用」としての徹底性も欠如しています。だから胡散臭いし、違法なのです。
ところで、「偽装請負」の就労形態は、「請負」としての要件を具備していないことをもって「偽装だ」と言っているわけですが、こういった胡散臭い就労形態は、雇用としての要件も具備していないし、委任としての要件も具備していないということになります。「請負」としての要件を具備していないことをもって「偽装だ」という言い方が可能ならば、これを「雇用」としての要件を具備していないことをもって「偽装だ」という言い方も可能になるような気がします。このため、「偽装雇用」という言い方も可能ではないかと思います。さらに同じ理由で「偽装委任」という言い方も可能であるように思います。
ただし、「偽装雇用」や「偽装委任」という言葉は、いまのところ私は目にしていません。だから、図に示したハッチングを付した部分については、これを「偽装請負」と言うことにするのがよろしいのでしょう。
>最初に提示された「就労条件」の内容次第で労働契約か否か判断できるのかなと思いました。
一般論としてはそうなりますが、私の場合ですと、契約書は全く取り交わしていないんです。このことを当初なんとなく胡散臭いと感じていましたが、当時はどこがどう胡散臭いのかを法律的観点からきっちりと同定することができず、漫然と就労してしまいました。後悔しています。
もし私が偽装請負就労した特許事務所の経営者(事業主)がその当時、頭の中で考えていたこと(思惑)を契約書の文面に忠実に反映させるとすると、その契約書の文面の実質は、いわば「偽装請負契約書」というものになっていかざるを得ないと思います。しかしこれでは、その契約書は「人を偽装請負就労させようとしていたことの証拠」として残ってしまうでしょう。
これではその事業主さんは都合が悪いわけです。だから契約書を作成しなかったのだと考えています。こういうところがずるいところなわけです。
一般論としてはそうなりますが、私の場合ですと、契約書は全く取り交わしていないんです。このことを当初なんとなく胡散臭いと感じていましたが、当時はどこがどう胡散臭いのかを法律的観点からきっちりと同定することができず、漫然と就労してしまいました。後悔しています。
もし私が偽装請負就労した特許事務所の経営者(事業主)がその当時、頭の中で考えていたこと(思惑)を契約書の文面に忠実に反映させるとすると、その契約書の文面の実質は、いわば「偽装請負契約書」というものになっていかざるを得ないと思います。しかしこれでは、その契約書は「人を偽装請負就労させようとしていたことの証拠」として残ってしまうでしょう。
これではその事業主さんは都合が悪いわけです。だから契約書を作成しなかったのだと考えています。こういうところがずるいところなわけです。
>私が聞きたかった事なんですが契約書がない場合でもその経営者が口頭で言われた「就労条件」
>なるものが内容によっては労働契約と見なせるのではないかという事なのですが・
おっしゃる意味、よく分かりますよ。ところが、実際の事情はちょっと複雑なところがございまして、説明をしだすと長くなり、その説明がまた混乱や誤解を生むかもしれません。ちょっとためらわれるのですが、少し言及してみます。
34番に図をお示ししていますね。私がこの特許事務所で就労を開始する場合、実はそれが合法的でありうる考え方の筋道が1つだけあると見ています。それは私が「委任」を受けて就労するという考え方に立つ筋道です。つまり、例えば「顧問」のような形式で就労するということです。
実際、この特許事務所には、「顧問」みたいな人がいたんですよ。その人は、職場に自分の「仲間」が欲しかったのではないでしょうか。この「顧問」みたいな人は、私の正規雇用されない就労の仕方を「あなたがこれから入ろうとしている就労形態は、私の就労形態(つまり顧問としての就労形態)と同じですよ」と言ったのです。私はその人の発言を、「自分は顧問として処遇されるんだ」と受け取ったのです。実際、この特許事務所の事業主は、私の名刺の肩書きを「○○特許事務所顧問」にしようとしていました。
顧問として就労するということは、委任を受けて就労する形態だと了解していたわけですから、私には事業主の勤労管理には服する義務は無いと考えていたのです。ところが、実際に就労しだすと、この事業主は私に次第に強く指揮命令をしてきたのです。これは私から見ると「約束違反」なんですよ。しかしこれが約束違反として同定されるためには、当初から「委任契約」なるものを締結しておくべきであったと思います。
しかし事業主の腹の中にある思惑は、「偽装請負契約」ですから、もし本気で契約書の文面作成の協議をしだすと、さぞかしもめたでしょうね。
>なるものが内容によっては労働契約と見なせるのではないかという事なのですが・
おっしゃる意味、よく分かりますよ。ところが、実際の事情はちょっと複雑なところがございまして、説明をしだすと長くなり、その説明がまた混乱や誤解を生むかもしれません。ちょっとためらわれるのですが、少し言及してみます。
34番に図をお示ししていますね。私がこの特許事務所で就労を開始する場合、実はそれが合法的でありうる考え方の筋道が1つだけあると見ています。それは私が「委任」を受けて就労するという考え方に立つ筋道です。つまり、例えば「顧問」のような形式で就労するということです。
実際、この特許事務所には、「顧問」みたいな人がいたんですよ。その人は、職場に自分の「仲間」が欲しかったのではないでしょうか。この「顧問」みたいな人は、私の正規雇用されない就労の仕方を「あなたがこれから入ろうとしている就労形態は、私の就労形態(つまり顧問としての就労形態)と同じですよ」と言ったのです。私はその人の発言を、「自分は顧問として処遇されるんだ」と受け取ったのです。実際、この特許事務所の事業主は、私の名刺の肩書きを「○○特許事務所顧問」にしようとしていました。
顧問として就労するということは、委任を受けて就労する形態だと了解していたわけですから、私には事業主の勤労管理には服する義務は無いと考えていたのです。ところが、実際に就労しだすと、この事業主は私に次第に強く指揮命令をしてきたのです。これは私から見ると「約束違反」なんですよ。しかしこれが約束違反として同定されるためには、当初から「委任契約」なるものを締結しておくべきであったと思います。
しかし事業主の腹の中にある思惑は、「偽装請負契約」ですから、もし本気で契約書の文面作成の協議をしだすと、さぞかしもめたでしょうね。
>ところで「勤労管理」とは具体的には時間拘束されるという事ですか?
もちろんそのとおりですよ。使用者が従業者を勤労管理するということは、両者の労働関係が「雇用」である場合の前提条件です。両者の関係が雇用の関係であれば、使用者は「雇用主」であり、従業者は「被雇用者」です。「被雇用者」は「雇用者」の勤労管理に服したことの対価として賃金を受け取るのです。
ところが使用者と従業者との労働関係が「委任」であれば、使用者がこの委任の対象者を勤労管理する、というのは「委任」とはなじまない行為であると考えます。この点は、最近話題となっている「名ばかり管理職」のことを思い出してください。
その人が「管理職」らしい就労形態であるといいうるためには3つほど条件があったでしょう。すなわち
?経営陣と一体的な立場にあること、
?ふさわしい報酬
?勤労管理には服さない
です。委任を受けて就労する身分と言うのは、ちょうど企業などにおける管理職のような位置づけです。
ところで、こういう管理職としての待遇の実質を満たさないのに、名称だけさも管理職のように装って、管理職であることを、残業代を支払わないことの口実として使うやりかたが「名ばかり管理職」です。
もちろんそのとおりですよ。使用者が従業者を勤労管理するということは、両者の労働関係が「雇用」である場合の前提条件です。両者の関係が雇用の関係であれば、使用者は「雇用主」であり、従業者は「被雇用者」です。「被雇用者」は「雇用者」の勤労管理に服したことの対価として賃金を受け取るのです。
ところが使用者と従業者との労働関係が「委任」であれば、使用者がこの委任の対象者を勤労管理する、というのは「委任」とはなじまない行為であると考えます。この点は、最近話題となっている「名ばかり管理職」のことを思い出してください。
その人が「管理職」らしい就労形態であるといいうるためには3つほど条件があったでしょう。すなわち
?経営陣と一体的な立場にあること、
?ふさわしい報酬
?勤労管理には服さない
です。委任を受けて就労する身分と言うのは、ちょうど企業などにおける管理職のような位置づけです。
ところで、こういう管理職としての待遇の実質を満たさないのに、名称だけさも管理職のように装って、管理職であることを、残業代を支払わないことの口実として使うやりかたが「名ばかり管理職」です。
>43番アンディーさん
>数年前は書面主義でしたがそうも言ってられない場面に遭遇する事も現実ありまして・・・。
>なんか後者の時はヤクザだなあと思う時もありますがいかがでしょう?
このトピックでは、私がある特許事務所の内部に入って就労したときの体験を中心にお話させていただいたわけですが、私が今後、ほとんど似たような体験をした場合、自分だったらどういう対応をするかをお話させていただきます。
このコミュニティでディスカッションさせていただいたおかげで、まず偽装請負の違法性は民法の規定から読む、というアプローチがほぼ正しそうだということがわかりました。そこで、就労開始にあたって、事業主が私に対して偽装請負モードで就労することを提案してきたときは、それがなぜどういうふうに違法行為になるかについて説明を試みようと思います。
その上で、自分を事務所内で働かせたいのであれば、正規雇用して欲しいとお願いします。そして、どうしても正規雇用できないのであれば、なぜ正規雇用できないのか、その理由をお尋ねすることにします。その理由が納得できるものであれば、妥協案として、例えばパートタイム労働のような就労形態で就労させてもらう方向などで交渉するかもしれません。パートタイム労働ならば、すこしも違法ではありません。
とにかく、契約書も取り交わさない、胡散臭い偽装請負就労はまっぴらごめんです!
>数年前は書面主義でしたがそうも言ってられない場面に遭遇する事も現実ありまして・・・。
>なんか後者の時はヤクザだなあと思う時もありますがいかがでしょう?
このトピックでは、私がある特許事務所の内部に入って就労したときの体験を中心にお話させていただいたわけですが、私が今後、ほとんど似たような体験をした場合、自分だったらどういう対応をするかをお話させていただきます。
このコミュニティでディスカッションさせていただいたおかげで、まず偽装請負の違法性は民法の規定から読む、というアプローチがほぼ正しそうだということがわかりました。そこで、就労開始にあたって、事業主が私に対して偽装請負モードで就労することを提案してきたときは、それがなぜどういうふうに違法行為になるかについて説明を試みようと思います。
その上で、自分を事務所内で働かせたいのであれば、正規雇用して欲しいとお願いします。そして、どうしても正規雇用できないのであれば、なぜ正規雇用できないのか、その理由をお尋ねすることにします。その理由が納得できるものであれば、妥協案として、例えばパートタイム労働のような就労形態で就労させてもらう方向などで交渉するかもしれません。パートタイム労働ならば、すこしも違法ではありません。
とにかく、契約書も取り交わさない、胡散臭い偽装請負就労はまっぴらごめんです!
>もう一つ私が大事だと思っているのは時には声を大にして主張する事です。
私もこのお考えには賛成です。
少しテーマは離れるのですが、以前にある外資系の医療機器メーカーに勤めていたとき、雇用契約書を提示され、その雇用契約書に「社内公募制に応募した場合は、その応募したという行動をもって、会社は本人(私のこと)を解雇できる」という奇妙な条項が含まれているのを発見したことがありました。
社内公募制というのは、例えば会社内のどこかの部署で欠員などが生じたとき、その部署に異動して働いてくれる人を、社内の従業員の中から公募する制度です。こういった制度自体は少しもおかしいものではありません。
なぜかというと、もし社内公募をせずに欠員補充をするとしたら、例えば新聞などに求人広告を出し、応募者の中から採用選考をし、所定の手続をして入社してもらうというかなりの手間とお金がかかるからです。そこで、もし社内で志をもって異動してくれて、活用出来る人材が調達できれば、会社としては人件費の節約にもなるし、人材資源の一層高度な活用も可能になります。
ところが、私に提示された雇用契約書には、「社内公募制に応募した場合は、その応募したという行動をもって、会社は本人(私のこと)を解雇できる」という奇妙な条項が含まれていたのです。
コミュニティのメンバーの皆さんの中で、これがおかしな話だということが分からない方、いらっしゃいますか?もしお分かりにならない場合は、一度精神病院に行って診察を受けられたほうがいいと思います。
私はこの契約書のこの条項がおかしいことを指摘して、担当の人事部長を大声で怒鳴りつけました。私は体格も大きいほうだし、声も大きいので、私にどなりつけられたことは相当こたえたらしく、半年後に会社を辞めてしまいました。しかし私のとった行動は正しかったと考えています。
私は、人間だれでも過ちは犯すので、寛容の精神はある程度必要であると考えていますが、許せないような間違ったことをする人に対しては、徹底的にバカにして非難することにしています。
私もこのお考えには賛成です。
少しテーマは離れるのですが、以前にある外資系の医療機器メーカーに勤めていたとき、雇用契約書を提示され、その雇用契約書に「社内公募制に応募した場合は、その応募したという行動をもって、会社は本人(私のこと)を解雇できる」という奇妙な条項が含まれているのを発見したことがありました。
社内公募制というのは、例えば会社内のどこかの部署で欠員などが生じたとき、その部署に異動して働いてくれる人を、社内の従業員の中から公募する制度です。こういった制度自体は少しもおかしいものではありません。
なぜかというと、もし社内公募をせずに欠員補充をするとしたら、例えば新聞などに求人広告を出し、応募者の中から採用選考をし、所定の手続をして入社してもらうというかなりの手間とお金がかかるからです。そこで、もし社内で志をもって異動してくれて、活用出来る人材が調達できれば、会社としては人件費の節約にもなるし、人材資源の一層高度な活用も可能になります。
ところが、私に提示された雇用契約書には、「社内公募制に応募した場合は、その応募したという行動をもって、会社は本人(私のこと)を解雇できる」という奇妙な条項が含まれていたのです。
コミュニティのメンバーの皆さんの中で、これがおかしな話だということが分からない方、いらっしゃいますか?もしお分かりにならない場合は、一度精神病院に行って診察を受けられたほうがいいと思います。
私はこの契約書のこの条項がおかしいことを指摘して、担当の人事部長を大声で怒鳴りつけました。私は体格も大きいほうだし、声も大きいので、私にどなりつけられたことは相当こたえたらしく、半年後に会社を辞めてしまいました。しかし私のとった行動は正しかったと考えています。
私は、人間だれでも過ちは犯すので、寛容の精神はある程度必要であると考えていますが、許せないような間違ったことをする人に対しては、徹底的にバカにして非難することにしています。
本日、ミクシィが配信しているあるニュースの中に、「偽装請負が違法行為」という文言が含まれているのを発見しました。「偽装請負」が違法であることはほぼ間違いないと考えていましたが、その違法性の読み方は、どちらかというと専門知に属すると思います。
労働法規にあまり詳しくない一般の人に、偽装請負がなぜ違法なのかを説明するのは、結構難しいといえます。しかし、こうしてニュースの文面の中に、「偽装請負が違法行為」という文言が登場することによって、この認識が社会通念化していくことが望ましいですね。
****************************************************************************
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1054626&media_id=2
労働者派遣法の改正を検討している労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は18日、仕事がある時だけ雇用する「登録型派遣」の原則禁止などを盛り込んだ改正案の原案を示した。禁止が検討されていた製造業派遣については、長期の雇用契約を結ぶ「常用型派遣」を容認するとしている。厚労省は審議会の結論を踏まえ、改正案を来年1月の通常国会に提出する方針。
原案は大学教授ら公益委員の案として示された。労働者の生活が不安定になりやすい登録型派遣については、通訳やソフトウエア開発などの専門業務を除いて禁止する。昨年から「派遣切り」が社会問題化した製造業については、常用型派遣だけを認める。
原案にはこのほか、禁止業務への派遣や偽装請負などの違法行為があった場合、派遣先が直接雇用を申し込んでいたとみなす「直接みなし雇用制度」が盛り込まれた。
改正は激変緩和措置として、公布日から3年以内の施行とした。
審議会では、抜本的な法改正を求める労働側委員と、反対する経営側委員が鋭く対立。答申のとりまとめが難航する可能性もある。また政権交代前に民主、社民、国民新の3党がまとめた改正案には含まれていた未払い賃金に関する連帯責任や団体交渉応諾義務など派遣先の責任を強化する部分は入らず、労働側にも反発がある。厚労省前では労組が集会を開き「派遣先責任を明確にしろ」などと抗議の声を上げた。
労働法規にあまり詳しくない一般の人に、偽装請負がなぜ違法なのかを説明するのは、結構難しいといえます。しかし、こうしてニュースの文面の中に、「偽装請負が違法行為」という文言が登場することによって、この認識が社会通念化していくことが望ましいですね。
****************************************************************************
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1054626&media_id=2
労働者派遣法の改正を検討している労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は18日、仕事がある時だけ雇用する「登録型派遣」の原則禁止などを盛り込んだ改正案の原案を示した。禁止が検討されていた製造業派遣については、長期の雇用契約を結ぶ「常用型派遣」を容認するとしている。厚労省は審議会の結論を踏まえ、改正案を来年1月の通常国会に提出する方針。
原案は大学教授ら公益委員の案として示された。労働者の生活が不安定になりやすい登録型派遣については、通訳やソフトウエア開発などの専門業務を除いて禁止する。昨年から「派遣切り」が社会問題化した製造業については、常用型派遣だけを認める。
原案にはこのほか、禁止業務への派遣や偽装請負などの違法行為があった場合、派遣先が直接雇用を申し込んでいたとみなす「直接みなし雇用制度」が盛り込まれた。
改正は激変緩和措置として、公布日から3年以内の施行とした。
審議会では、抜本的な法改正を求める労働側委員と、反対する経営側委員が鋭く対立。答申のとりまとめが難航する可能性もある。また政権交代前に民主、社民、国民新の3党がまとめた改正案には含まれていた未払い賃金に関する連帯責任や団体交渉応諾義務など派遣先の責任を強化する部分は入らず、労働側にも反発がある。厚労省前では労組が集会を開き「派遣先責任を明確にしろ」などと抗議の声を上げた。
このトピックの29番から31番で紹介されている訴訟のケースの最高裁判決のニュースがミクシィ内で配信されています。以下にご紹介します。この裁判の判決で重要なポイントは、
?偽装請負の事実はあったのか。
?その偽装請負を遡ってパナソニック子会社内での直接雇用であったとみなして賃金の支払という形での救済は認められるのか。
の2点であろうかと思われます。?の点では偽装請負の事実はあったと認定していますので、この点では成果はあったといえるのではないでしょうか。
?の点では、原告の吉岡さんの主張は完全には認められず、事実上の敗訴となっています。世の事業主は、この判決をもって、「派遣会社から派遣された労働者を偽装請負させてもかまわないんだ」という解釈をしないで欲しいと思います。もしそういった無節操の原因となってしまうとすると、結果的にこの最高裁判決は悲しい判決となってしまうことでしょう。
****************************************************************************
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1054971&media_id=4
パナソニック子会社の工場で働いていた元請負会社社員の男性が、「偽装請負」を内部告発した後に不当解雇されたとして、直接雇用の確認などを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)であった。同小法廷は、訴えをほぼ認めた二審大阪高裁判決の一部を破棄し、同社の雇用義務を認めず、直接雇用や未払い賃金支払いの訴えを退けた。男性側の実質的逆転敗訴が確定した。
弁護団によると、同様の訴訟は全国で60件以上起こされており、影響を与えそうだ。
男性は松下プラズマディスプレイ(現パナソニックプラズマディスプレイ)の工場で働いていた吉岡力さん(35)。
大阪高裁は昨年、吉岡さんの雇用形態を「偽装請負」と認定し、請負会社との雇用契約は無効と判断。松下プラズマ社との間に、直接雇用が成立すると認めていた。
これに対し同小法廷は、雇用形態が偽装請負であることは認めたものの、請負会社との雇用契約は有効で、松下プラズマ社との直接雇用は成立しないと判断した。
一方、松下プラズマ社が、内部告発後に、吉岡さんだけにこれまでと別の作業をさせたことを、「告発への報復」と認めた二審の判断は支持。慰謝料90万円の支払い命令を維持した。
判決後に記者会見した吉岡さんは「偽装請負という違法行為を容認した判決。最高裁の罪は大きい」と語った。
?偽装請負の事実はあったのか。
?その偽装請負を遡ってパナソニック子会社内での直接雇用であったとみなして賃金の支払という形での救済は認められるのか。
の2点であろうかと思われます。?の点では偽装請負の事実はあったと認定していますので、この点では成果はあったといえるのではないでしょうか。
?の点では、原告の吉岡さんの主張は完全には認められず、事実上の敗訴となっています。世の事業主は、この判決をもって、「派遣会社から派遣された労働者を偽装請負させてもかまわないんだ」という解釈をしないで欲しいと思います。もしそういった無節操の原因となってしまうとすると、結果的にこの最高裁判決は悲しい判決となってしまうことでしょう。
****************************************************************************
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1054971&media_id=4
パナソニック子会社の工場で働いていた元請負会社社員の男性が、「偽装請負」を内部告発した後に不当解雇されたとして、直接雇用の確認などを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)であった。同小法廷は、訴えをほぼ認めた二審大阪高裁判決の一部を破棄し、同社の雇用義務を認めず、直接雇用や未払い賃金支払いの訴えを退けた。男性側の実質的逆転敗訴が確定した。
弁護団によると、同様の訴訟は全国で60件以上起こされており、影響を与えそうだ。
男性は松下プラズマディスプレイ(現パナソニックプラズマディスプレイ)の工場で働いていた吉岡力さん(35)。
大阪高裁は昨年、吉岡さんの雇用形態を「偽装請負」と認定し、請負会社との雇用契約は無効と判断。松下プラズマ社との間に、直接雇用が成立すると認めていた。
これに対し同小法廷は、雇用形態が偽装請負であることは認めたものの、請負会社との雇用契約は有効で、松下プラズマ社との直接雇用は成立しないと判断した。
一方、松下プラズマ社が、内部告発後に、吉岡さんだけにこれまでと別の作業をさせたことを、「告発への報復」と認めた二審の判断は支持。慰謝料90万円の支払い命令を維持した。
判決後に記者会見した吉岡さんは「偽装請負という違法行為を容認した判決。最高裁の罪は大きい」と語った。
このトピックの35番、36番あたりに、私が偽装請負就労した特許事務所の経営者は、私を事務所内就労させるにあたって契約書を作成しなかった、ということについて言及しているでしょう。そして、この契約書を労働者を偽装請負をさせる事業主としては、自分の頭の中でイメージしている就労のさせ方を規定する「契約書」を作成してしまうと、それが事実上「偽装請負契約書」となってしまい、自分が人を偽装請負させたという証拠となって残るので都合が悪い、ということを申し上げています。
では仮に事業主が頭の中で考えていることを文面に具体化すると、どういう文面になるのだろうかということを試みてみました。こういう角度から考察することによって、「契約書を作らない」ということがどういう意味を持っているのか、そのいわば「不作為の罪」の意味が明らかになると思います。以下が、事業主が頭の中で考えていることを文面に具体化した一例になります。
【(パロディ版)偽装請負契約書】
1.ここに事業主「甲」と労働者「乙」とは偽装請負契約を締結する。
2.事業主「甲」は労働者「乙」を雇用しているわけではないので、事業主「甲」と労働者「乙」との関係は「雇用者−被雇用者」の関係ではなく、「偽装請負させ人」と「偽装請負人」との関係であることを確認する。
3.乙は甲が事業として営む事業所Xに内勤し、甲の指揮命令に従って就労するものとする。
4.乙は雇用されているわけではないので、「なぜ甲の指揮命令に従わなければならないのか」という疑問が生じる。しかし、乙は自営業者であり、仕事の受注に不安定さがあるという弱い立場にある。甲は乙を内勤就労させるので、常に仕事を与えられるメリットが享受できるので、乙はそのメリットと引き換えに腹をくくって甲の指揮命令に従うものとする。
5.甲の乙に対する労務提供要求が過酷であることに起因し、乙が過労死した場合であっても、甲が乙に内勤就労の場を提供し、乙が勝手に疲労困憊するまで働いた結果過労死に至ったものと解釈し、甲は乙の過労死についてはなんら責任を負わないものとする。
6.乙の労働パーフォーマンスが甲の期待水準に届かない場合は、いつでも偽装請負を解除し、事業所内就労を解除して事務所の外に出して「請負」で働かせることができるものとする。もし乙が「雇用」されているものとすると、これは甲が乙を「解雇」することに該当する行為であるが、乙の身分はあくまで「偽装請負労働者」であり、「雇用された従業員」ではないとの解釈に立脚するものとする。これゆえ乙は甲に対して「不当に解雇されない権利」等の労働基本権は主張しないものとする。
7.人間にとっての労働は、つねに労働を通じて自己をなんらかの形で向上させようとする意欲と共に営まれるものではあるが、甲が乙にどのような仕事をどれだけ与えるかは、もっぱら甲が「どのように乙を働かせれば甲の事業の利益に供するか」という観点からのみ判断するものとし、乙自身の自己啓発の意向やキャリアステップアップの意向がどのようなものであるかは全く考慮せずとも、乙には異議はないものとする。従って、甲が乙に対して教育投資等を全く行わなくとも、乙には異議はないものとする。
8.当事務所は従業員の勤怠管理にタイムカードを使用しているが、乙にタイムカードによる勤怠管理を適用すると、勤怠管理に服しつつ就労する労働者性を、乙に対して認定する際の証拠となってしまい、甲にとって都合が悪いので、タイムカードによる勤怠管理は適用しないものとする。
9・支払い調書における報酬の科目名は、実質的には「偽装請負報酬」であるが、そのように記すると、甲が乙に偽装請負をさせていることが丸見えになって甲にとって都合が悪いので、「顧問料」と表記するものとする。
○○○○年○月○日
偽装請負させ人甲:○○○○ 印
偽装請負人乙:○○○○ 印
******************************************************************
メンバーの皆さんは、上の契約書サンプルの「パロディ」としての意味はお分かりですよね。たしかに人を偽装請負させる事業主としては、こんな契約書が証拠として残ったのでは都合が悪いでしょうね。
では仮に事業主が頭の中で考えていることを文面に具体化すると、どういう文面になるのだろうかということを試みてみました。こういう角度から考察することによって、「契約書を作らない」ということがどういう意味を持っているのか、そのいわば「不作為の罪」の意味が明らかになると思います。以下が、事業主が頭の中で考えていることを文面に具体化した一例になります。
【(パロディ版)偽装請負契約書】
1.ここに事業主「甲」と労働者「乙」とは偽装請負契約を締結する。
2.事業主「甲」は労働者「乙」を雇用しているわけではないので、事業主「甲」と労働者「乙」との関係は「雇用者−被雇用者」の関係ではなく、「偽装請負させ人」と「偽装請負人」との関係であることを確認する。
3.乙は甲が事業として営む事業所Xに内勤し、甲の指揮命令に従って就労するものとする。
4.乙は雇用されているわけではないので、「なぜ甲の指揮命令に従わなければならないのか」という疑問が生じる。しかし、乙は自営業者であり、仕事の受注に不安定さがあるという弱い立場にある。甲は乙を内勤就労させるので、常に仕事を与えられるメリットが享受できるので、乙はそのメリットと引き換えに腹をくくって甲の指揮命令に従うものとする。
5.甲の乙に対する労務提供要求が過酷であることに起因し、乙が過労死した場合であっても、甲が乙に内勤就労の場を提供し、乙が勝手に疲労困憊するまで働いた結果過労死に至ったものと解釈し、甲は乙の過労死についてはなんら責任を負わないものとする。
6.乙の労働パーフォーマンスが甲の期待水準に届かない場合は、いつでも偽装請負を解除し、事業所内就労を解除して事務所の外に出して「請負」で働かせることができるものとする。もし乙が「雇用」されているものとすると、これは甲が乙を「解雇」することに該当する行為であるが、乙の身分はあくまで「偽装請負労働者」であり、「雇用された従業員」ではないとの解釈に立脚するものとする。これゆえ乙は甲に対して「不当に解雇されない権利」等の労働基本権は主張しないものとする。
7.人間にとっての労働は、つねに労働を通じて自己をなんらかの形で向上させようとする意欲と共に営まれるものではあるが、甲が乙にどのような仕事をどれだけ与えるかは、もっぱら甲が「どのように乙を働かせれば甲の事業の利益に供するか」という観点からのみ判断するものとし、乙自身の自己啓発の意向やキャリアステップアップの意向がどのようなものであるかは全く考慮せずとも、乙には異議はないものとする。従って、甲が乙に対して教育投資等を全く行わなくとも、乙には異議はないものとする。
8.当事務所は従業員の勤怠管理にタイムカードを使用しているが、乙にタイムカードによる勤怠管理を適用すると、勤怠管理に服しつつ就労する労働者性を、乙に対して認定する際の証拠となってしまい、甲にとって都合が悪いので、タイムカードによる勤怠管理は適用しないものとする。
9・支払い調書における報酬の科目名は、実質的には「偽装請負報酬」であるが、そのように記すると、甲が乙に偽装請負をさせていることが丸見えになって甲にとって都合が悪いので、「顧問料」と表記するものとする。
○○○○年○月○日
偽装請負させ人甲:○○○○ 印
偽装請負人乙:○○○○ 印
******************************************************************
メンバーの皆さんは、上の契約書サンプルの「パロディ」としての意味はお分かりですよね。たしかに人を偽装請負させる事業主としては、こんな契約書が証拠として残ったのでは都合が悪いでしょうね。
上の【(パロディ版)偽装請負契約書】を見ていただくと、どういうものが具備されていると、合法的な事業所内請負就労が成立しうるかということがわかるような気がします。
私の考えでは、合法的な事業所内請負就労が成立するための基本条件は3つあります。
1.契約書が存在すること。その名称は「個人請負契約書」でもいいし、「業務委託契約書」でもいいし「顧問契約書」でもいいのですが、とにかく契約書があること。
2.その契約内容が合法的であること。
3.契約の当事者双方がその合法的な契約内容を誠実に順守していること。
以上の3つです。
この3条件のどれか1つでも欠けると、ただちに違法になりうると思います。
繰り返しになりますが、私が体験した偽装請負就労は、そもそも契約書を作成していないわけですから、違法でないことを証明する手段が存在しないわけです。しかも私を偽装請負させた事業主は、合法的な契約書を作成する意思などはなっから無く、もし頭の中で描いている就労のさせ方を文面に具体化すると、上記の【(パロディ版)偽装請負契約書】のようなものになってしまわざるを得ないのです。事業主としてはそんな契約書など作りたくない。だから契約書は作らなかったというわけです。
私の考えでは、合法的な事業所内請負就労が成立するための基本条件は3つあります。
1.契約書が存在すること。その名称は「個人請負契約書」でもいいし、「業務委託契約書」でもいいし「顧問契約書」でもいいのですが、とにかく契約書があること。
2.その契約内容が合法的であること。
3.契約の当事者双方がその合法的な契約内容を誠実に順守していること。
以上の3つです。
この3条件のどれか1つでも欠けると、ただちに違法になりうると思います。
繰り返しになりますが、私が体験した偽装請負就労は、そもそも契約書を作成していないわけですから、違法でないことを証明する手段が存在しないわけです。しかも私を偽装請負させた事業主は、合法的な契約書を作成する意思などはなっから無く、もし頭の中で描いている就労のさせ方を文面に具体化すると、上記の【(パロディ版)偽装請負契約書】のようなものになってしまわざるを得ないのです。事業主としてはそんな契約書など作りたくない。だから契約書は作らなかったというわけです。
私が加入している『特許実務・特許事務』というコミュの「翻訳者を違法就労させる特許事務所」というトピック(下記アドレス)
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=22265180&comment_count=43&comm_id=91611
において、
「個人請負は必ずしも違法にならないし、契約書が無くとも契約は成立しているとみなせる。一体何が問題なのか」という疑問が提示されました([34]番)。この疑問は、考えようによってはあり得る素朴な疑問なので、この点を明確にしておこうと思います。
この疑問に対する私の考えはこうです。たしかに「個人請負」は違法ではありません。でも「偽装請負」は違法になるわけです。では「個人請負」と「偽装請負」はどう違うか、両者はどう区別されるかですが、もっとも違う側面のひとつは、その事業所内就労で、その請負労働者が指揮命令を受けているか否かです。端的に言うと、事業主側がその請負労働者に指揮命令をしてしまうと、その時点で違法になるといえます。
このことを逆に言うと、事業所内で就労している個人請負労働者は、「事業主から指揮命令されない権利がある」ということになります。このことを担保するために契約書が必要になると考えます。
このことをさらに逆に言うと、「契約書を作成しないで、個人請負労働者の『事業主から指揮命令されない権利』が擁護できるのか」という問題が浮上すると思います。私の考えでは、契約書も作成しないで、『事業主から指揮命令されない権利』が擁護できるとはちょっと考えられないです。
上の論理で、個人請負労働者は、「事業主から指揮命令されない権利がある」ということについて、もう一度確認してみます。
もし事業所内就労している個人請負労働者が、事業主から指揮命令されたら、両者の間に、「私命令する人、あなた命令に従う人」という関係があるということになります。すると、両者がそのような関係になければならない根拠は何なのかということが問題になります。通常は、対等な人間同士、そのような関係などありえないわけです。
ところが両者が「雇用主−被雇用者」という関係なら「命令する人−命令に従う人」という関係は法律上正当化されるわけです。この場合は、両者の関係は局部的には対等ではありませんが、その関係の内容が労働基準法等で規制されており、「命令に従う人」が「命令する人」から一方的に労働搾取されることから守っているわけです。
しかしこの関係は、両者が「雇用主−被雇用者」という関係である場合の話なのです。逆にいうと、「業務の発注者と請負業者」との関係であれば、「指揮命令」はできないのです。その場合は、「指揮命令」という形ではなく、業務の発注、依頼、受注、…といった観念で把握されることになるわけです。だから、例えば請負業者側には、例えば「諾否の権利」なども生じるはずなのです。
「諾否の権利」とは、例えばその依頼された業務を請け負うか請け負わないか、受注するか受注しないかをその都度選択する権利のことです。この「諾否の権利」の存在も、その労働関係が「雇用」なのか「請負」なのかを分ける重要な概念のひとつであるといえましょう。もしその労働者が「請負業者」と観念されるのなら、その人には当然「諾否の権利」があってしかるべきだし、逆に「諾否の権利」が存在しない労働関係で観念されているのなら、その労働者は「雇用」という概念で立場が守られる必要が出てくるということになります。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=22265180&comment_count=43&comm_id=91611
において、
「個人請負は必ずしも違法にならないし、契約書が無くとも契約は成立しているとみなせる。一体何が問題なのか」という疑問が提示されました([34]番)。この疑問は、考えようによってはあり得る素朴な疑問なので、この点を明確にしておこうと思います。
この疑問に対する私の考えはこうです。たしかに「個人請負」は違法ではありません。でも「偽装請負」は違法になるわけです。では「個人請負」と「偽装請負」はどう違うか、両者はどう区別されるかですが、もっとも違う側面のひとつは、その事業所内就労で、その請負労働者が指揮命令を受けているか否かです。端的に言うと、事業主側がその請負労働者に指揮命令をしてしまうと、その時点で違法になるといえます。
このことを逆に言うと、事業所内で就労している個人請負労働者は、「事業主から指揮命令されない権利がある」ということになります。このことを担保するために契約書が必要になると考えます。
このことをさらに逆に言うと、「契約書を作成しないで、個人請負労働者の『事業主から指揮命令されない権利』が擁護できるのか」という問題が浮上すると思います。私の考えでは、契約書も作成しないで、『事業主から指揮命令されない権利』が擁護できるとはちょっと考えられないです。
上の論理で、個人請負労働者は、「事業主から指揮命令されない権利がある」ということについて、もう一度確認してみます。
もし事業所内就労している個人請負労働者が、事業主から指揮命令されたら、両者の間に、「私命令する人、あなた命令に従う人」という関係があるということになります。すると、両者がそのような関係になければならない根拠は何なのかということが問題になります。通常は、対等な人間同士、そのような関係などありえないわけです。
ところが両者が「雇用主−被雇用者」という関係なら「命令する人−命令に従う人」という関係は法律上正当化されるわけです。この場合は、両者の関係は局部的には対等ではありませんが、その関係の内容が労働基準法等で規制されており、「命令に従う人」が「命令する人」から一方的に労働搾取されることから守っているわけです。
しかしこの関係は、両者が「雇用主−被雇用者」という関係である場合の話なのです。逆にいうと、「業務の発注者と請負業者」との関係であれば、「指揮命令」はできないのです。その場合は、「指揮命令」という形ではなく、業務の発注、依頼、受注、…といった観念で把握されることになるわけです。だから、例えば請負業者側には、例えば「諾否の権利」なども生じるはずなのです。
「諾否の権利」とは、例えばその依頼された業務を請け負うか請け負わないか、受注するか受注しないかをその都度選択する権利のことです。この「諾否の権利」の存在も、その労働関係が「雇用」なのか「請負」なのかを分ける重要な概念のひとつであるといえましょう。もしその労働者が「請負業者」と観念されるのなら、その人には当然「諾否の権利」があってしかるべきだし、逆に「諾否の権利」が存在しない労働関係で観念されているのなら、その労働者は「雇用」という概念で立場が守られる必要が出てくるということになります。
さて、偽装請負の認定にあたって、「指揮命令」という言葉は重要なキーワードになるということがお分かりいただけたと思いますが、ここでミクシィに偽装請負がらみの事件の興味深い裁判例(中身は和解ですが)が形成されたことを伝えるニュースが配信されていますのでご紹介します。こういったニュースは、しばらくすると掲載期間を終了してしまいますので、コピーして保存しておこうと思います。ミクシィ当局もたぶん許容してくれるでしょう。
*********************************************************************
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=2266183&media_id=2
キヤノン(本社・東京都大田区)の宇都宮工場での偽装請負を告発、正社員雇用などを求めていた期間労働者で作る「キヤノン非正規労働者組合」(阿久津真一委員長)とキヤノンが20日、組合員2人を関連会社で正社員として雇用することなどで和解した。偽装請負などの違法行為が認定された上で労働者が働いていた派遣先や関連会社で正社員となるのは極めて異例。
阿久津委員長は「違法な実態があっても企業の責任を問わず、非正規の権利をないがしろにする判決が相次ぐ中で、大きな成果だ」といい、キヤノンは「争いが長期化するのはお互いにとって無益であることから和解した」と話している。
阿久津委員長らは、00年ごろから、請負労働などで同工場で働いてきた。実際にはキヤノンの指揮命令を受けていた偽装請負だと告発。国会でも取り上げられ、07年には栃木労働局が偽装請負だとして是正を指導した。有期雇用で直接雇用されたが、雇い止めされた。労組は「不誠実団交や不当な解雇があった」として5人が東京都労働委員会へ救済を申し立て、東京地裁にも提訴した。今回都労委で、5人のうち2人がキヤノンの関連会社が正社員として雇用、3人は金銭解決で和解した。
***********************************************************************
このニュースを読むと、正社員となる和解が成立しています。今後はさらに一歩すすめて、「正社員として雇用することを命じる救済判決」というものが出ることが普通になると良いと思います。
そのことを推進するためにも、やはり法整備は必要でしょうね。現在の民法や労働基準法、労働者派遣法等では、こういった救済が容易には導き出せないような気がします。立法技術的にはどういう規定ぶりがいいのかわかりませんが、「偽装請負労働者救済措置法」のような法整備が行われるとよいと思います。
*********************************************************************
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=2266183&media_id=2
キヤノン(本社・東京都大田区)の宇都宮工場での偽装請負を告発、正社員雇用などを求めていた期間労働者で作る「キヤノン非正規労働者組合」(阿久津真一委員長)とキヤノンが20日、組合員2人を関連会社で正社員として雇用することなどで和解した。偽装請負などの違法行為が認定された上で労働者が働いていた派遣先や関連会社で正社員となるのは極めて異例。
阿久津委員長は「違法な実態があっても企業の責任を問わず、非正規の権利をないがしろにする判決が相次ぐ中で、大きな成果だ」といい、キヤノンは「争いが長期化するのはお互いにとって無益であることから和解した」と話している。
阿久津委員長らは、00年ごろから、請負労働などで同工場で働いてきた。実際にはキヤノンの指揮命令を受けていた偽装請負だと告発。国会でも取り上げられ、07年には栃木労働局が偽装請負だとして是正を指導した。有期雇用で直接雇用されたが、雇い止めされた。労組は「不誠実団交や不当な解雇があった」として5人が東京都労働委員会へ救済を申し立て、東京地裁にも提訴した。今回都労委で、5人のうち2人がキヤノンの関連会社が正社員として雇用、3人は金銭解決で和解した。
***********************************************************************
このニュースを読むと、正社員となる和解が成立しています。今後はさらに一歩すすめて、「正社員として雇用することを命じる救済判決」というものが出ることが普通になると良いと思います。
そのことを推進するためにも、やはり法整備は必要でしょうね。現在の民法や労働基準法、労働者派遣法等では、こういった救済が容易には導き出せないような気がします。立法技術的にはどういう規定ぶりがいいのかわかりませんが、「偽装請負労働者救済措置法」のような法整備が行われるとよいと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
労働法研究会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
労働法研究会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人