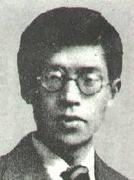『山月記』『李陵』等について語るのもいいですが、
ちょっとマイナーな作品についての情報も交換しましょう。
とりあえずamazonで、「中島敦」の検索結果↓
http://
ちょっとマイナーな作品についての情報も交換しましょう。
とりあえずamazonで、「中島敦」の検索結果↓
http://
|
|
|
|
コメント(24)
はじめまして。
マイナーコーナーかぁ。
もちろん、最初は「山月記」です。そのあと旺文社文庫(「人虎伝」読み下しつき)で、やっぱり中国種をよんで、面白い中国ものを書く人という印象を持っていました。ところがどっこい、全集(文庫)を読んで打ちのめされました。
私、江戸時代の歴史・文学・虚構みたいなことが専門なんですが、いまや『古譚』は授業に欠かせないアイテムです。
「狐憑」「文字禍」「木乃伊」は、メディア論の古典として、今でも十分通用します。
ナブ・アヘ・エリバと若い歴史家の問答は、歴史認識論争に直結するでしょう。
「狐憑」の、物語史への視点は、文学史の最初の一こまとして最も重要なものだとおいますが、残念ながら教科書に載せられるような内容ではない(「高校生のために……読本」シリーズに掲載されていますが)。
そうやって考えると、なぜ「山月記」だけが教科書に載り、我々は、それをどのような文脈で読まされてきたのか、考え直す必要がありますよね。
他に私の好きなのは、「吾が西遊記」(字、これで良いのかな)。「問うてはならない問い」という問題は重いです。
「虎狩り」。これも「文字禍」と通じている、マッチとたばこの場面にはゾクッと来ます。
こういう研究はまだ少ないみたいですね(私、実は不案内なので専門の方、解説をお願いします)。
「山月記」以外の話についても典拠はあるはずだし。
マイナーコーナーかぁ。
もちろん、最初は「山月記」です。そのあと旺文社文庫(「人虎伝」読み下しつき)で、やっぱり中国種をよんで、面白い中国ものを書く人という印象を持っていました。ところがどっこい、全集(文庫)を読んで打ちのめされました。
私、江戸時代の歴史・文学・虚構みたいなことが専門なんですが、いまや『古譚』は授業に欠かせないアイテムです。
「狐憑」「文字禍」「木乃伊」は、メディア論の古典として、今でも十分通用します。
ナブ・アヘ・エリバと若い歴史家の問答は、歴史認識論争に直結するでしょう。
「狐憑」の、物語史への視点は、文学史の最初の一こまとして最も重要なものだとおいますが、残念ながら教科書に載せられるような内容ではない(「高校生のために……読本」シリーズに掲載されていますが)。
そうやって考えると、なぜ「山月記」だけが教科書に載り、我々は、それをどのような文脈で読まされてきたのか、考え直す必要がありますよね。
他に私の好きなのは、「吾が西遊記」(字、これで良いのかな)。「問うてはならない問い」という問題は重いです。
「虎狩り」。これも「文字禍」と通じている、マッチとたばこの場面にはゾクッと来ます。
こういう研究はまだ少ないみたいですね(私、実は不案内なので専門の方、解説をお願いします)。
「山月記」以外の話についても典拠はあるはずだし。
中島敦って、ぜんぜん「戦後日本的」な作家じゃないですよね。
戦前に、「アジア主義」という思想潮流がありました。これは、アジアは一丸となって、西洋列強の干渉を排除していこう、という思潮で、いろいろな分野に影響を及ぼします。
それは結局は、日本帝国の中国や南島への植民、そして侵略という負の遺産をもたらしてしまうけど、この「アジア主義」は、もっと可能性のある思想潮流で、その部分を、わりと最後まで失ってなかったと思います(竹内好氏の指摘)。
で、中島は、朝鮮で多感な時期を送っている。その中で、朝鮮人の置かれた様々な桎梏を見ている(『虎狩』)。南島の政庁のやることに失望して、ほとんど土方久功氏とだけ付き合ったりしてる。『光と風と夢』の主人公で、本国のサモアに対する政策にたてついて孤立していくスティーブンスンは、中島の思いを代弁してはいないか、と思うんです。
中国に対する興味も、その流れで考えられます。
彼は、中国文明を優秀なものとする江戸からの漢学者の家の生まれです。その彼が、アジア主義の中にあった、「西洋列強からの中国の解放」という思想に共鳴しなかったとは考えられない。『斗南先生』で、叔父の斗南の著作を読むくだりは、その表れではないかと思います。
戦前の日本は、戦後よりはるかに国際的に開かれていたと思います。いまの日本のように、外交もマスコミの情報も偏ってはいなかった。そのなかで、中島は、おそらくもっとも「非」日本的な教養とおいたちを持ったのだと思います。『光と風と夢』は、芥川賞に漏れましたが、今回一読してみて、これは、いまの文壇でもきちんと評価できないのではないかと思いました。
それに、生前に刊行された作品集は、『南島譚』と『光と風と夢』です。中国に取材した作家というイメージではなかったし、おそらく中島敦自身も、中国ものばかり書くつもりもなかったと思います。そんなスケールの小さい作家でもない。
作家生活をはじめてすぐになくなっています。書きたいものはたくさんあったと思います。そういう意味ではこの人ほど、早世が惜しまれる人はいない。本領を発揮していない。もししていたら、と考えると、ちょっと怖いくらいです。
中国ものの作家=中島敦、という図式は、あまりにこの人を矮小化しているように思えてならないのです。
贅言失礼。ちなみに、私のフェイバリットは、「環礁」の一連の作品と、「弟子」です。
戦前に、「アジア主義」という思想潮流がありました。これは、アジアは一丸となって、西洋列強の干渉を排除していこう、という思潮で、いろいろな分野に影響を及ぼします。
それは結局は、日本帝国の中国や南島への植民、そして侵略という負の遺産をもたらしてしまうけど、この「アジア主義」は、もっと可能性のある思想潮流で、その部分を、わりと最後まで失ってなかったと思います(竹内好氏の指摘)。
で、中島は、朝鮮で多感な時期を送っている。その中で、朝鮮人の置かれた様々な桎梏を見ている(『虎狩』)。南島の政庁のやることに失望して、ほとんど土方久功氏とだけ付き合ったりしてる。『光と風と夢』の主人公で、本国のサモアに対する政策にたてついて孤立していくスティーブンスンは、中島の思いを代弁してはいないか、と思うんです。
中国に対する興味も、その流れで考えられます。
彼は、中国文明を優秀なものとする江戸からの漢学者の家の生まれです。その彼が、アジア主義の中にあった、「西洋列強からの中国の解放」という思想に共鳴しなかったとは考えられない。『斗南先生』で、叔父の斗南の著作を読むくだりは、その表れではないかと思います。
戦前の日本は、戦後よりはるかに国際的に開かれていたと思います。いまの日本のように、外交もマスコミの情報も偏ってはいなかった。そのなかで、中島は、おそらくもっとも「非」日本的な教養とおいたちを持ったのだと思います。『光と風と夢』は、芥川賞に漏れましたが、今回一読してみて、これは、いまの文壇でもきちんと評価できないのではないかと思いました。
それに、生前に刊行された作品集は、『南島譚』と『光と風と夢』です。中国に取材した作家というイメージではなかったし、おそらく中島敦自身も、中国ものばかり書くつもりもなかったと思います。そんなスケールの小さい作家でもない。
作家生活をはじめてすぐになくなっています。書きたいものはたくさんあったと思います。そういう意味ではこの人ほど、早世が惜しまれる人はいない。本領を発揮していない。もししていたら、と考えると、ちょっと怖いくらいです。
中国ものの作家=中島敦、という図式は、あまりにこの人を矮小化しているように思えてならないのです。
贅言失礼。ちなみに、私のフェイバリットは、「環礁」の一連の作品と、「弟子」です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
中島敦 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
中島敦のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90059人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208291人