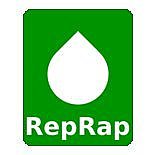|
|
|
|
コメント(42)
すごく役に立つトピックですね 思いつかなかったです
私はSketchUPとShade(バージョン7)+2DでJWWを使っています
ちょっと形状を見るだけの場合はMeshLabです
主な使い方
SketchUP
簡単で直線や円で構成な形状をモデリングするのに使用しています。プラグインでstlに変換して使用
Shade
微妙な曲線や三次曲面のものをモデリングする場合に使っています。古いShadeですのでstl出力が無いため3dsで出力し、SketchUPで読み込み面を補修してstlにしています
jww(2D_CAD)
紙に図面を書いていた世代ですので寸法入力が多くなる形状は2Dで書いてから3Dに移しています。 jww>>>DXF>>>ShadeやSketchUPにて立体化>>>stl出力
以上の使い方で使っていますが、SketchUPでの読み込み時にプラグインによってはインチとミリの違いが出るので注意が必要です。
私はSketchUPとShade(バージョン7)+2DでJWWを使っています
ちょっと形状を見るだけの場合はMeshLabです
主な使い方
SketchUP
簡単で直線や円で構成な形状をモデリングするのに使用しています。プラグインでstlに変換して使用
Shade
微妙な曲線や三次曲面のものをモデリングする場合に使っています。古いShadeですのでstl出力が無いため3dsで出力し、SketchUPで読み込み面を補修してstlにしています
jww(2D_CAD)
紙に図面を書いていた世代ですので寸法入力が多くなる形状は2Dで書いてから3Dに移しています。 jww>>>DXF>>>ShadeやSketchUPにて立体化>>>stl出力
以上の使い方で使っていますが、SketchUPでの読み込み時にプラグインによってはインチとミリの違いが出るので注意が必要です。
僕はAutodesk Inventor Fusionを使ってます。
テクノロジープレビュー版みたいですが、一応無料のようです。
123DDesignに似ています。
もしかしたらそのうち起動しなくなるのかも。。
http://labs.autodesk.com/technologies/fusion/
長所:
STEPファイルが読めます。
寸法入力できます。
STL・STEPファイルの書き出しできます。
単所:
そこそこ重い、落ちる。
スケッチで六角形がないのでナット穴空けるのが面倒。
STEPファイルは開けるけど、複数ファイルをインポートして組み合わせをみるとかできない。
123DDesignはSTEPファイルが読めない。。
正確には数回読んだ後読めなくなる。。
テクノロジープレビュー版みたいですが、一応無料のようです。
123DDesignに似ています。
もしかしたらそのうち起動しなくなるのかも。。
http://labs.autodesk.com/technologies/fusion/
長所:
STEPファイルが読めます。
寸法入力できます。
STL・STEPファイルの書き出しできます。
単所:
そこそこ重い、落ちる。
スケッチで六角形がないのでナット穴空けるのが面倒。
STEPファイルは開けるけど、複数ファイルをインポートして組み合わせをみるとかできない。
123DDesignはSTEPファイルが読めない。。
正確には数回読んだ後読めなくなる。。
そーですね、STLで、部品とか、幾何学形状を作るなら、openSCADを使ってます。
ソリッドに特化したオペレーションというか、プログラムを作るのが楽しいですよ。
基本形状は、球体、円柱、四角柱の3つ 3D形状を意識して、MM単位で設計します。そそ、私の作ったテスト用の銅鐸もこのCADです。25行程度の記述でできますよ。
reprapの部品の多くは、*.scadとついたこのCADで造られています。
マニュアルが英語なんで使いずらいかも。でもなれるとかいてきですよ。
openSCADは無料です。
例)ファイルを開いた後(open)→compileエラー確認と表示→CGAL→STL書き込み の流れです。
いちどお試しあれ。STLに落ちたら、minimagics(無料)で表示^^
ソリッドに特化したオペレーションというか、プログラムを作るのが楽しいですよ。
基本形状は、球体、円柱、四角柱の3つ 3D形状を意識して、MM単位で設計します。そそ、私の作ったテスト用の銅鐸もこのCADです。25行程度の記述でできますよ。
reprapの部品の多くは、*.scadとついたこのCADで造られています。
マニュアルが英語なんで使いずらいかも。でもなれるとかいてきですよ。
openSCADは無料です。
例)ファイルを開いた後(open)→compileエラー確認と表示→CGAL→STL書き込み の流れです。
いちどお試しあれ。STLに落ちたら、minimagics(無料)で表示^^
面白そうなので自分も投下。
メイン:ZBrush
長所
・人物や曲線的なものがモデリングしやすい。
・dynamesh(面の再生成)機能で、形状エラーが一発解決できる。
短所
・最初は概念が理解しづらいかもしれない。
・単体ではstlが吐き出せない。
サブ:Metasequoia
長所
・ものすごくわかりやすい。 初心者講座を1〜2時間見るだけで使えるようになる(http://ktg.xii.jp/mqo/)
・安い(無料版、5,250円、19,950円)
・プラグインが豊富
短所
・無料だとstlを吐き出せない
・寸法調整がちょっと面倒
万能変換ツール:Blender
長所
・完全無料
・どんな形式もインポート/エクスポートできる
短所
・個人的には使い辛かったくらい
メイン:ZBrush
長所
・人物や曲線的なものがモデリングしやすい。
・dynamesh(面の再生成)機能で、形状エラーが一発解決できる。
短所
・最初は概念が理解しづらいかもしれない。
・単体ではstlが吐き出せない。
サブ:Metasequoia
長所
・ものすごくわかりやすい。 初心者講座を1〜2時間見るだけで使えるようになる(http://ktg.xii.jp/mqo/)
・安い(無料版、5,250円、19,950円)
・プラグインが豊富
短所
・無料だとstlを吐き出せない
・寸法調整がちょっと面倒
万能変換ツール:Blender
長所
・完全無料
・どんな形式もインポート/エクスポートできる
短所
・個人的には使い辛かったくらい
皆さん、情報ありがとうございます。
やはり無料の物を使われている方が多いですね。私は3Dプリンタの部品ばかり作っているので寸法指定のできることが必須条件なので3D CADソフトを選ぶという形になるのですが、正確な寸法というよりはイメージを形にする場合、3D CGソフトの方が適しているんですね。
123D DesignはSketchUPを使い始めるときにどちらをマスターするか迷った経験があります。結局、ネットが遅いと起動その他が遅い点、試しに色々動かしていたらプログラムが終了してしまった点が不満で使うのをやめました。PCスペックの問題点かもと思っていましたが、どちらもA.Yaraさんが短所として指摘されているので、ソフトウェアの問題かもしれませんね。
Inventor fusionは私の環境だとかなり重いです。ユーザーインターフェースとかは割と好きな方に入ります。まだちょっと触っただけですが、これに乗り換えるのはありかなぁと思ってます。
FreeCADは無料なのに拘束使えたりかなり本格的で好きなのですが、視点を自由に動かす方法がわからないので困っています。この点さえ解決されたら即乗り換えてしまいたいくらいです。
3D CGソフトは今まで全く触っていませんでしたが、サンダル(ダル)さんが紹介されているShade 3Dがちょうど3Dプリンタ特集をやっている&ダウンロード版の一番安い奴がキャンペーン価格でかなり安いので魅力を感じています。とりあえず体験版をダウンロードしました。週末にでもいじってみようと思います。
これだけだと何の情報もないので私が使っているSTLビューワーについて。私はnetfabb Studio Basicというのを使っています。STLの簡単修復や反転、寸法測定等も付いていて結構便利です。
寸法測定が面と点の距離とか線と線の距離も測れて人のデータを参考に自作するときとか活躍しています。
やはり無料の物を使われている方が多いですね。私は3Dプリンタの部品ばかり作っているので寸法指定のできることが必須条件なので3D CADソフトを選ぶという形になるのですが、正確な寸法というよりはイメージを形にする場合、3D CGソフトの方が適しているんですね。
123D DesignはSketchUPを使い始めるときにどちらをマスターするか迷った経験があります。結局、ネットが遅いと起動その他が遅い点、試しに色々動かしていたらプログラムが終了してしまった点が不満で使うのをやめました。PCスペックの問題点かもと思っていましたが、どちらもA.Yaraさんが短所として指摘されているので、ソフトウェアの問題かもしれませんね。
Inventor fusionは私の環境だとかなり重いです。ユーザーインターフェースとかは割と好きな方に入ります。まだちょっと触っただけですが、これに乗り換えるのはありかなぁと思ってます。
FreeCADは無料なのに拘束使えたりかなり本格的で好きなのですが、視点を自由に動かす方法がわからないので困っています。この点さえ解決されたら即乗り換えてしまいたいくらいです。
3D CGソフトは今まで全く触っていませんでしたが、サンダル(ダル)さんが紹介されているShade 3Dがちょうど3Dプリンタ特集をやっている&ダウンロード版の一番安い奴がキャンペーン価格でかなり安いので魅力を感じています。とりあえず体験版をダウンロードしました。週末にでもいじってみようと思います。
これだけだと何の情報もないので私が使っているSTLビューワーについて。私はnetfabb Studio Basicというのを使っています。STLの簡単修復や反転、寸法測定等も付いていて結構便利です。
寸法測定が面と点の距離とか線と線の距離も測れて人のデータを参考に自作するときとか活躍しています。
>>[10]
OpenSCADは他の人が作ったデータをちょっと加工して穴の位置とか径とかを変えるだけなら簡単で、とても便利ですね。ただ何もないところから作るのはちょっと敷居が高いと感じています。
時々便利な関数やねじの大きさなどを別ファイルから読み込んでいる人を見かけますが、あれはどこかに共通の物がアップロードされているんでしょうか?
>> 内藤舞蹴さん、masayanmanさん、1gさん
DESIGN SPARK MECHANICAL始めました。
SketchUPのファイルをそのまま読み込めるのでSTLへエクスポートしたときに発生する問題がないのが、私にとっては助かります。SketchUPで大まかに作ってから細部をこれで調整とか出来そうです。
操作感がかなり違うので慣れるまでが大変そうです。色々な機能を使ってパーツ一個を作るというようなチュートリアルがあるといいのですが、今のところ発見できず…
OpenSCADは他の人が作ったデータをちょっと加工して穴の位置とか径とかを変えるだけなら簡単で、とても便利ですね。ただ何もないところから作るのはちょっと敷居が高いと感じています。
時々便利な関数やねじの大きさなどを別ファイルから読み込んでいる人を見かけますが、あれはどこかに共通の物がアップロードされているんでしょうか?
>> 内藤舞蹴さん、masayanmanさん、1gさん
DESIGN SPARK MECHANICAL始めました。
SketchUPのファイルをそのまま読み込めるのでSTLへエクスポートしたときに発生する問題がないのが、私にとっては助かります。SketchUPで大まかに作ってから細部をこれで調整とか出来そうです。
操作感がかなり違うので慣れるまでが大変そうです。色々な機能を使ってパーツ一個を作るというようなチュートリアルがあるといいのですが、今のところ発見できず…
>>[13]
OpenSCADは、皆さんに自信を持ってお勧めできるものではありません。
(その証拠に遠慮がちにあとから書き込みw)
> 時々便利な関数やねじの大きさなどを別ファイルから読み込んでいる人を見かけますが、あれはどこかに共通の物がアップロードされているんでしょうか?
Github なんか OpenSCAD達人がで公開しているようなものは、ぱっと見理解しにくいです。
普通は、プロジェクトのソースファイル群のどこかにあると思います。
Thingiverse に公開されているものを利用している場合は、同梱していないかもしれませんね。
私の場合は、せいぜい共通設定/共通関数ファイルを別にするくらいです。
OpenSCADは、皆さんに自信を持ってお勧めできるものではありません。
(その証拠に遠慮がちにあとから書き込みw)
> 時々便利な関数やねじの大きさなどを別ファイルから読み込んでいる人を見かけますが、あれはどこかに共通の物がアップロードされているんでしょうか?
Github なんか OpenSCAD達人がで公開しているようなものは、ぱっと見理解しにくいです。
普通は、プロジェクトのソースファイル群のどこかにあると思います。
Thingiverse に公開されているものを利用している場合は、同梱していないかもしれませんね。
私の場合は、せいぜい共通設定/共通関数ファイルを別にするくらいです。
久々、メタセコイア・・
MMDのミクさんのデータをSTLにしようといろいろ検討したけど、やはり、MMDのようなCG系のポリゴンモデラーのデータをSTLにするには、ポリゴンモデラーでそれなりに修正してからSTLにしないといけない感じ。
うーーん。ポリゴンモデラーで3Dデータ ばりばりにいじらないと。まさしく、力技。これには、メタセコイアは向いているような。
ちなみに、データ変換経路は、無料系だと複数迂回をするといける。
MMDの*.pmd → Blender *obj → Metasequoia *mpo か *.x → Blender *.stl
ちと ややこしいね。しかもプラグインも使うし、力技を目指す人には、挑戦しがいがあるかも。
MMDのミクさんのデータをSTLにしようといろいろ検討したけど、やはり、MMDのようなCG系のポリゴンモデラーのデータをSTLにするには、ポリゴンモデラーでそれなりに修正してからSTLにしないといけない感じ。
うーーん。ポリゴンモデラーで3Dデータ ばりばりにいじらないと。まさしく、力技。これには、メタセコイアは向いているような。
ちなみに、データ変換経路は、無料系だと複数迂回をするといける。
MMDの*.pmd → Blender *obj → Metasequoia *mpo か *.x → Blender *.stl
ちと ややこしいね。しかもプラグインも使うし、力技を目指す人には、挑戦しがいがあるかも。
ここまで商用3D CADの名前がほとんど上がっていないようですが...
僕はMac OS上でRhino OSXを使っています。
http://www.rhino3d.com/download/wenatchee/5.0/wip
Win版のRhinocerosもプロが使うCADとしてはかなり安価なものですが、
Mac版はここ数年ずっとパブリックビルドとして無料公開されています。
自由曲面を生成するのが得意なNURBSモデラーで、
エンジニアよりもプロダクトデザイナーに愛用者が多いCADです。
操作方法はYoutubeにたくさんUpされていますので、
ご興味のある方は試してみてくださいな。
僕はMac OS上でRhino OSXを使っています。
http://www.rhino3d.com/download/wenatchee/5.0/wip
Win版のRhinocerosもプロが使うCADとしてはかなり安価なものですが、
Mac版はここ数年ずっとパブリックビルドとして無料公開されています。
自由曲面を生成するのが得意なNURBSモデラーで、
エンジニアよりもプロダクトデザイナーに愛用者が多いCADです。
操作方法はYoutubeにたくさんUpされていますので、
ご興味のある方は試してみてくださいな。
>>[29]
なるほどなるほど! 最近はハード以外にもソフト面も多種に及んでますからねぇ 小さい企業や個人でも優秀なソフトが海外から溢れてきていますね。
まずソリッドな物(固形や金属系)を扱った設計する時はSolidworksですね。
Dassault社が出しているCAD郡の中の中堅あたりのソフトですが、上位にはCATIAというものがあります。
日本だとDassault社以外でもNXやら他の上位ソフトが車の設計やら飛行機の設計、カメラに電話等に使われていますね。 ザ・3DCADと言われるソフトなんで基本的にプロダクションまでやることを念頭に置いた使い方をします。
ちなみに立体型CADソフトはツリー型とそうでないものがありますが、一長一短です、使い分けたいとこです。 ちなみにRSから出たCAD、Design Sparkもツリー式、 Mechanicalと書いてあるので展開が予想されそうです。
Rhinoserosは一番有名なサーフェスモデラーですね。 面や曲面を公差させながら立体物をデザインするモデラーでソリッドな物も扱えますが、一番の機能は美しい曲線を3D空間上でデザインできるということなので外装デザインやコンセプトデザインや車のデザインや飛行機のデザイン等に使われます。 ひじょーに滑らかなラインを扱い人向け。
Ashlar Vellum社のCobaltはマイナーもマイナーなソフトなんですがソリッドとサーフェイス両方をいい感じに扱えるソフトなんですが最近は使って無いですねー でもかなり使いやすいです。
Autodesk社は3Dをやる人だったら誰でも知ってる会社でそこは地球シュミレーションまで視覚化やらんとしてるんですが一番有名なのはAutoCADです。 日本ではVectorWorksというCADソフトが有名です。
元々2Dのドローイング(製図ソフト)作ってたんですが十数年で3DガッツリでAutoCADの後継ではRevitで建築のデザインから設計、施工までできちゃいます。
AutoCADもRevitもシティプラン、建築の骨組み設計、パイプラインや電装設計やいろんなのに特化したものが用意されてますね。 なにがなにやらさっぱりです。
しかし彼らのもう一つの有名どころは統合型3Dソフトと呼ばれるものです。
3DソフトとCADの大きな違いは皆さんご存じの通り数式で面や体積、表面積を計算してグラフィック化もするCADですが、3Dは3頂点を最小としたポリゴン(メッシュ)で立体表現するかです。
3D Studio MaxもMayaも何もないところからどんな形状でも3Dモデル化して映画、アニメ、ゲーム等にプロダクションワークへ移行できる つまりいろんなものができちゃうよソフトです。
3D Studio Maxはどちらかというとゲームや建築ビジュアライゼーションに寄っていますね、プラグインやモディファイヤの扱いがそっちのモデリングに向いてるからですね。
MAYAは言わずと知れた旧Alias社から出ている映画にむいたソフトです。 今ほとんどのハリウッド映画はこれがつかわれています。 RenderMan等映画やアニメーションに対してのプラグインやプロダクションワークの親和性が非常に高いですね。 コアのプログラムが優秀な面もあります。
Autodesk InventorはSolidworksに似てますね。 ギアのエンボリュート計算もできちゃいます。
Autodesk Mudboxは最後に記述するPixologic社のZbrushの対抗馬で彫刻ソフトです。
Autodesk Softimageは旧Softimage社からでているソフトでこれも統合型3Dソフトです。 このソフトはゲームに向いているというかゲーム業界でかなり使われていますね。 三国無双やファイナルファンタジー等幅広く現役で使われています。 特に人間のアニメートやモーションが扱いやすそうですね。 あ、グラツーはMayaらしいですよ。
Autodesk MotionBuilder これは3Dモデルにモーションを与えるソフトです、Autdesk製品にブリッジするような感じでいろんなソフトで作ったモデルにモーションをつける場合これを使います。
ちなみにクラウドポイントによるMatchMoveもあります。
なるほどなるほど! 最近はハード以外にもソフト面も多種に及んでますからねぇ 小さい企業や個人でも優秀なソフトが海外から溢れてきていますね。
まずソリッドな物(固形や金属系)を扱った設計する時はSolidworksですね。
Dassault社が出しているCAD郡の中の中堅あたりのソフトですが、上位にはCATIAというものがあります。
日本だとDassault社以外でもNXやら他の上位ソフトが車の設計やら飛行機の設計、カメラに電話等に使われていますね。 ザ・3DCADと言われるソフトなんで基本的にプロダクションまでやることを念頭に置いた使い方をします。
ちなみに立体型CADソフトはツリー型とそうでないものがありますが、一長一短です、使い分けたいとこです。 ちなみにRSから出たCAD、Design Sparkもツリー式、 Mechanicalと書いてあるので展開が予想されそうです。
Rhinoserosは一番有名なサーフェスモデラーですね。 面や曲面を公差させながら立体物をデザインするモデラーでソリッドな物も扱えますが、一番の機能は美しい曲線を3D空間上でデザインできるということなので外装デザインやコンセプトデザインや車のデザインや飛行機のデザイン等に使われます。 ひじょーに滑らかなラインを扱い人向け。
Ashlar Vellum社のCobaltはマイナーもマイナーなソフトなんですがソリッドとサーフェイス両方をいい感じに扱えるソフトなんですが最近は使って無いですねー でもかなり使いやすいです。
Autodesk社は3Dをやる人だったら誰でも知ってる会社でそこは地球シュミレーションまで視覚化やらんとしてるんですが一番有名なのはAutoCADです。 日本ではVectorWorksというCADソフトが有名です。
元々2Dのドローイング(製図ソフト)作ってたんですが十数年で3DガッツリでAutoCADの後継ではRevitで建築のデザインから設計、施工までできちゃいます。
AutoCADもRevitもシティプラン、建築の骨組み設計、パイプラインや電装設計やいろんなのに特化したものが用意されてますね。 なにがなにやらさっぱりです。
しかし彼らのもう一つの有名どころは統合型3Dソフトと呼ばれるものです。
3DソフトとCADの大きな違いは皆さんご存じの通り数式で面や体積、表面積を計算してグラフィック化もするCADですが、3Dは3頂点を最小としたポリゴン(メッシュ)で立体表現するかです。
3D Studio MaxもMayaも何もないところからどんな形状でも3Dモデル化して映画、アニメ、ゲーム等にプロダクションワークへ移行できる つまりいろんなものができちゃうよソフトです。
3D Studio Maxはどちらかというとゲームや建築ビジュアライゼーションに寄っていますね、プラグインやモディファイヤの扱いがそっちのモデリングに向いてるからですね。
MAYAは言わずと知れた旧Alias社から出ている映画にむいたソフトです。 今ほとんどのハリウッド映画はこれがつかわれています。 RenderMan等映画やアニメーションに対してのプラグインやプロダクションワークの親和性が非常に高いですね。 コアのプログラムが優秀な面もあります。
Autodesk InventorはSolidworksに似てますね。 ギアのエンボリュート計算もできちゃいます。
Autodesk Mudboxは最後に記述するPixologic社のZbrushの対抗馬で彫刻ソフトです。
Autodesk Softimageは旧Softimage社からでているソフトでこれも統合型3Dソフトです。 このソフトはゲームに向いているというかゲーム業界でかなり使われていますね。 三国無双やファイナルファンタジー等幅広く現役で使われています。 特に人間のアニメートやモーションが扱いやすそうですね。 あ、グラツーはMayaらしいですよ。
Autodesk MotionBuilder これは3Dモデルにモーションを与えるソフトです、Autdesk製品にブリッジするような感じでいろんなソフトで作ったモデルにモーションをつける場合これを使います。
ちなみにクラウドポイントによるMatchMoveもあります。
続き
Maxon社のCinema 4Dは統合型3Dソフトで3dsMaxやMayaやSoftimage等と肩を並べます。ドイツ出身です。
新参かといえば意外とそうでもなくて前々からあるんですが、最近非常に優秀です。人、植物、建築、彫刻、機械系 なんでも行けるようGUIやプロセスをかなりいい感じにしています。 レンダリングも優秀。
プリセットも豊富でCM業界でも人気。 3Dメッシュモデルでもフィレットやチャンファー等の加工もかなり優秀なアルゴリズムを引っ提げてアップデートしてきました。 これでロボット系も捗る。
Luxology社のModoは新参の統合型3Dソフト、ですが内容とコアプログラムがガッチリしていて優秀です。 ちょっとGUIとショートカットに新しさと癖があるので前からやってる人はちょーっと慣れが必要。 レンダラも優秀でリアルタイムレンダも搭載、メッシュの編集の仕方も優秀。
Pixologic社のZbrushは最近非常に有名。 言わずと知れたデジタル彫刻ソフトで出た当初は2.5Dとか謳ってましたね。 ハリウッド映画、アニメ、ゲーム等で現在100%使われているんじゃないかと、そのくらい優秀な彫刻ソフトです。 Voxelという概念を取り入れたアルゴリズムでGPUがなくてもCPUだけでサクサク。
バージョンアップごとに追加される機能が鬼優秀すぎて困る。 例えばCADからSTL生成した、あまり美しくないメッシュの流れや、汚いポリゴンの流れを一気に人がちゃんとやったかのようなリトポロジー(面の流れを最適化)する機能やメッシュ分割を気にしないでモデリング出来たり、今までの技法をひっくり返す機能満載。 ロボットとかのソリッドぽい物もカッコよく作れる。
このZbrushかMudboxが無ければ今のゲーム業界はまず生きてけない状態。
ちなみにPixologicから出ているScalptoris(スペル間違ってるかも)は無料版Zbrushみたいなもの。ただ機能が面白いです。 ブラシしたところだけメッシュがリアルタイムで細分化されるという謎技術。凄い。
3DCoatはZbrushとMudboxの対抗馬、でもMudboxのことはあまりみてないかも。 個人でだされてたソフトですが非常に優秀。リトポロジーの仕方に力が注がれていてZbrushより「こう」とか違う角度からいい感じに今までのモデリングプロセスをひっくり返してくれる。 Voxel使い。
その他ファイル互換のためのソフトがあったりいろいろありますが、とりあえず有名どころを列挙してみました。
じゃあどれを買うか、とか、どれも買えないヽ(`Д´)ノ とかではなく、
これまでに出てる、そしてこれから出る無料で優秀なソフトは何に寄ってるかによって使い分けした方がきっと満足いくと思います!
Maxon社のCinema 4Dは統合型3Dソフトで3dsMaxやMayaやSoftimage等と肩を並べます。ドイツ出身です。
新参かといえば意外とそうでもなくて前々からあるんですが、最近非常に優秀です。人、植物、建築、彫刻、機械系 なんでも行けるようGUIやプロセスをかなりいい感じにしています。 レンダリングも優秀。
プリセットも豊富でCM業界でも人気。 3Dメッシュモデルでもフィレットやチャンファー等の加工もかなり優秀なアルゴリズムを引っ提げてアップデートしてきました。 これでロボット系も捗る。
Luxology社のModoは新参の統合型3Dソフト、ですが内容とコアプログラムがガッチリしていて優秀です。 ちょっとGUIとショートカットに新しさと癖があるので前からやってる人はちょーっと慣れが必要。 レンダラも優秀でリアルタイムレンダも搭載、メッシュの編集の仕方も優秀。
Pixologic社のZbrushは最近非常に有名。 言わずと知れたデジタル彫刻ソフトで出た当初は2.5Dとか謳ってましたね。 ハリウッド映画、アニメ、ゲーム等で現在100%使われているんじゃないかと、そのくらい優秀な彫刻ソフトです。 Voxelという概念を取り入れたアルゴリズムでGPUがなくてもCPUだけでサクサク。
バージョンアップごとに追加される機能が鬼優秀すぎて困る。 例えばCADからSTL生成した、あまり美しくないメッシュの流れや、汚いポリゴンの流れを一気に人がちゃんとやったかのようなリトポロジー(面の流れを最適化)する機能やメッシュ分割を気にしないでモデリング出来たり、今までの技法をひっくり返す機能満載。 ロボットとかのソリッドぽい物もカッコよく作れる。
このZbrushかMudboxが無ければ今のゲーム業界はまず生きてけない状態。
ちなみにPixologicから出ているScalptoris(スペル間違ってるかも)は無料版Zbrushみたいなもの。ただ機能が面白いです。 ブラシしたところだけメッシュがリアルタイムで細分化されるという謎技術。凄い。
3DCoatはZbrushとMudboxの対抗馬、でもMudboxのことはあまりみてないかも。 個人でだされてたソフトですが非常に優秀。リトポロジーの仕方に力が注がれていてZbrushより「こう」とか違う角度からいい感じに今までのモデリングプロセスをひっくり返してくれる。 Voxel使い。
その他ファイル互換のためのソフトがあったりいろいろありますが、とりあえず有名どころを列挙してみました。
じゃあどれを買うか、とか、どれも買えないヽ(`Д´)ノ とかではなく、
これまでに出てる、そしてこれから出る無料で優秀なソフトは何に寄ってるかによって使い分けした方がきっと満足いくと思います!
>>[31]
Hiroさん、詳しい解説ありがとうございました。最初に紹介されているSolidWorksはRepRapのデータ作成に使っているという人が結構いるようですね。価格を調べてみたら、個人ではなかなか手が出せない金額でしたが、それでも定番中の定番ということのようですね。
有料ソフトの使い分けなんて贅沢、個人ではなかなかできないので実際に両方使っている人のコメントはとても参考になりますね。最近は無料で時間制限ありの試用版も結構あるのですが、そもそもどこを比べればいいのかすら分からない状態でした。
まとめると
・CAD(数式計算で立体表現)か3D(ポリゴンで立体表現)か、(これはソリッドかサーフェスかという区別とイコールなんでしょうか?)
・CADの場合、ツリー型(ヒストリー型)かどうかでわかれるが、一長一短
・統合型3Dソフトは実装されている機能によって作る物の向き不向きがある
・定番はMudboxかZbrushでゲーム業界では必須
と言ったところでしょうか。同じソフト名でも複数の価格帯の製品が用意されているんですね。今回紹介していただいたものの中ではSculptrisがZbrushの無料版ということでとっつきやすいでしょうか。
> これまでに出てる、そしてこれから出る無料で優秀なソフトは何に寄ってるかによって使い分けした方がきっと満足いくと思います!
有料ソフトでも向き不向きがあるということなので一本のソフトでなんでもという横着は諦めて、使い分けを考えたいと思います!
Hiroさん、詳しい解説ありがとうございました。最初に紹介されているSolidWorksはRepRapのデータ作成に使っているという人が結構いるようですね。価格を調べてみたら、個人ではなかなか手が出せない金額でしたが、それでも定番中の定番ということのようですね。
有料ソフトの使い分けなんて贅沢、個人ではなかなかできないので実際に両方使っている人のコメントはとても参考になりますね。最近は無料で時間制限ありの試用版も結構あるのですが、そもそもどこを比べればいいのかすら分からない状態でした。
まとめると
・CAD(数式計算で立体表現)か3D(ポリゴンで立体表現)か、(これはソリッドかサーフェスかという区別とイコールなんでしょうか?)
・CADの場合、ツリー型(ヒストリー型)かどうかでわかれるが、一長一短
・統合型3Dソフトは実装されている機能によって作る物の向き不向きがある
・定番はMudboxかZbrushでゲーム業界では必須
と言ったところでしょうか。同じソフト名でも複数の価格帯の製品が用意されているんですね。今回紹介していただいたものの中ではSculptrisがZbrushの無料版ということでとっつきやすいでしょうか。
> これまでに出てる、そしてこれから出る無料で優秀なソフトは何に寄ってるかによって使い分けした方がきっと満足いくと思います!
有料ソフトでも向き不向きがあるということなので一本のソフトでなんでもという横着は諦めて、使い分けを考えたいと思います!
私は趣味でベータ版から使い続けているRhinocerosですね。現在は5.0を使ってます。
サブでこれまた20年近く使ってるLightwave3Dでしょうか。
・Rhinoceros
長所:長年使ってるけど使いやすい。説明書読まなくても結構いける。軽い。
短所:動作確認したいけど単体では簡単なアニメーションができない。
長く使ってますが、練度はたいしたことないです(笑。趣味の物作りの設計支援や、LWにフィレットが装備されていなかった頃の補助ツール的な使用から始めたので。スピーカーキャビネット作成を趣味にした頃から使用頻度が上がりましたが、3Dプリンタ購入後はほぼ立ち上げっぱなしです。
・Lightwave3D
長所:マニュアルいらないわかりやすさ。比較的軽い。プラグインが安い。
短所:やはりCADと比べると精度が微妙。3dsMAXやMayaと比べるとプラグイン作成の自由度が弱い。
以前はこちらがメインでしたが、今はRhinoの頻度が高いですね。Rhinoは単独でアニメーションができないので、こちらに読み込ませて動作確認、干渉のチェックなどをしています。レンダリングもこちらはフォトンマップまでできるので今も便利に使ってます。
と言うところでしょうか。3dsMAXも2008までは使ってましたが、年間保守費用が負担になってきてやめました。今はフリーでも強力なCADソフト(Genkeiのワークショップで聞いたデザインスパークメカニカルなど)もあるので、そのうちそちらにも手を出してみようか思案中です。
サブでこれまた20年近く使ってるLightwave3Dでしょうか。
・Rhinoceros
長所:長年使ってるけど使いやすい。説明書読まなくても結構いける。軽い。
短所:動作確認したいけど単体では簡単なアニメーションができない。
長く使ってますが、練度はたいしたことないです(笑。趣味の物作りの設計支援や、LWにフィレットが装備されていなかった頃の補助ツール的な使用から始めたので。スピーカーキャビネット作成を趣味にした頃から使用頻度が上がりましたが、3Dプリンタ購入後はほぼ立ち上げっぱなしです。
・Lightwave3D
長所:マニュアルいらないわかりやすさ。比較的軽い。プラグインが安い。
短所:やはりCADと比べると精度が微妙。3dsMAXやMayaと比べるとプラグイン作成の自由度が弱い。
以前はこちらがメインでしたが、今はRhinoの頻度が高いですね。Rhinoは単独でアニメーションができないので、こちらに読み込ませて動作確認、干渉のチェックなどをしています。レンダリングもこちらはフォトンマップまでできるので今も便利に使ってます。
と言うところでしょうか。3dsMAXも2008までは使ってましたが、年間保守費用が負担になってきてやめました。今はフリーでも強力なCADソフト(Genkeiのワークショップで聞いたデザインスパークメカニカルなど)もあるので、そのうちそちらにも手を出してみようか思案中です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
RepRap 更新情報
-
最新のアンケート
RepRapのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75501人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196034人
- 3位
- 独り言
- 9045人