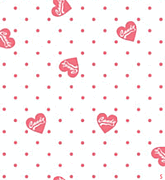埼玉県教育委員会の道徳教材「心の絆」
[PR]
東日本大震災の影響で、福島県浪江町から埼玉県ふじみ野市に避難している小学4年生の女の子が書いた作文「おにぎりとおみそしる」が注目を集めている。埼玉県教育委員会が震災に関わる出来事を題材に作った道徳教材「彩の国の道徳 心の絆」にも採用された。
--------------------------------------------------------------------------------
おにぎりとおみそしる
小さな白いおにぎりと具のないおみそしる これは、わたしにとって、わすれる事のできないごはんです。
わたしは、東日本大しんさいで、自分の家にいられなくなり、ひなん所で生活していました。その時の食事の内ようです。
それまでのわたしは、おやつを食べて、食事の時には、テーブルにはたくさんのおかずがあって、食後には、デザートまでありました。それが、あたり前だと思っていました。
とつぜんのさいがいを受け、ひなん所で生活をしてみて、わたしが食べていたものが、とてもめぐまれていた事に気が付きました。何日間も、おにぎりとおみそしるだけを食べていましたが、ふしぎとあれが、食べたい、これが、食べたいとは、思いませんでした。おなかがすいて、食べる事ができることだけで、うれしかったからです。
白いおにぎりから、中に梅ぼしが入ったおにぎりになった時は、とてもうれしかったです。
ひなん所から、東京にいどうした時に、はじめて、おかずのついたごはんを食べました。弟が大好きな野菜を見て、
「食べていいの。」
と聞きながら食べていました。とても、うれしそうでした。
今もまだ、自分の家には帰れないけれど、テーブルには、わたしの好きな食べ物がたくさんならびます。季節のフルーツもたべられるようになりました。ひなん所で、テーブルも無くて、おふとんをかたづけて、下を向いて食べた小さなおにぎりと具のないおみそしるの味は、ぜっ対にわすれません。こまっているわたし達にごはんを作ってくれた人達の事もわすれません。
ひなん所にいた時は、あまりわらう事ができませんでした。でも、今は、わらってごはんを食べています。つらい事やこわい事もたくさんありました。今は、ごはんを食べて、おふろにはいって、おふとんにねむれる事が、とてもうれしいし幸せです。
これからも、食べ物をそまつにしないで、楽しくごはんを食べていきたいと思います。 (全文)
--------------------------------------------------------------------------------
この作文を書いたのは、ふじみ野市立上野台小学校4年の常盤桃花さん(10)。震災直後、余震におびえながら避難所で食べた食事の記憶をたどり、支えてくれた人々や今の日常に感謝する内容になっている。昨年の夏休みに書き、今年度の埼玉県「食をめぐる作文」小学生の部で最優秀賞に輝いた。
自宅は、東京電力福島第一原子力発電所から北西約8キロの警戒区域内にある。震災直後、家族とともに避難した。
震災の時、桃花さんは町立大堀小の教室にいた。その夜は余震が続くなか、母親の小智江さん(44)と弟の恭平君(6)と近所の消防団の施設で過ごした。翌朝に避難指示が出されたため、車の中で朝を迎えた父親の弘幸さん(50)と合流し、約20キロ北西にある保育所に向かった。
保育所や周辺は、避難してきた人であふれていた。「すぐに帰れる」と思ったという小智江さんは、自宅からバナナ数本とあめ玉、トイレットペーパーだけしか持って来ていなかった。避難者の男性が雑貨店で買ってきたというだし用の削り節を一枚一枚、みんなで分け合って食べた。
■具は大好きな梅干し
小さなおにぎりと具のないおみそしるは、その晩に食べたものだ。保育所の先生たちが握ってくれた。
「おなかがすいていたので、とにかくうれしかった。みそ汁用の発泡スチロールのおわんとはしは捨てず、ティッシュペーパーでふいて何度も使った」
3泊した後、内陸の二本松市の避難所へ。そこで出たおにぎりも忘れられない。ほおばると、具は大好きな梅干しだった。思わず「うめだー」と叫んだ。
幼い弟も同じだった。
福島を出て、都内の親戚宅に滞在した際、レストランに行った。小智江さんから天ぷら定食の春菊を分けられた恭平君は震災後、初めてのおかずに「食べていいの?」と聞いた。そして手を震わせながら口に運んだという。
■作文を読んで先生が涙
この作文を最初に読んだ担任の松沢映子教諭は涙が止まらなかった。
「彼女の生の声がつづられていた。複雑な気持ちを秘めながらも、人とのつながりへの感謝を強めていく様子が伝わってきた」
桃花さんは昨年12月の全校朝会で発表。2月には避難者をいやす交流会「おあがんなんしょ」でも朗読し、多くの人が涙した。
市教育委員会は小中学生の全家庭に配る「子供未来カレンダー」に掲載。市教委から連絡を受けた大堀小の校長は、各地に避難しているPTA会員に送る「学校だより」でも紹介したという。
「心の絆」は、さいたま市を除く県内の公立学校の学級担任らに配られる。県教委は「日常生活を不自由なく過ごす中、支えてくれている人の存在や苦労に気づかないことが多い。この作文を通じて日常生活を見つめ直し、人々への尊敬や感謝の気持ちを育みたい」と期待を寄せる。
■いつも笑顔 帰りたい思いも胸に
桃花さんがふじみ野に避難して丸1年。4年生最後の登校日となった26日、教室で通知表を受け取ると、柔らかな笑顔を浮かべた。みんなの前で一人ずつ発表する「思い出一言コーナー」では、「この学校に来て、友達がいっぱいできて楽しかった。ありがとう」と語った。
松沢教諭は「あれだけの経験をして複雑な思いもあったはずなのに、いつもニコニコと前向きに生活し、周囲に自然といい影響を与えてくれた」とこの1年間を振り返った。
埼玉で新たな楽しみも見つけた。「一番は浦和のパルコや川越の丸広に大好きな洋服を見に行くこと」。「おあがんなんしょ」で毎月、ボランティアで参加する県立福岡高校の女子生徒と遊ぶのも楽しみだ。
でも、生まれ育った故郷を忘れることはない。
新潟県や秋田県で暮らす離ればなれの親友とは、電話やメールで頻繁に連絡を取り合っている。昨年の夏休みには再会を果たし、一緒に東京・原宿にも遊びに行った。
正月、川越市の喜多院に初詣に行った時も「たくさん会えますように」と長く手を合わせた。小智江さんも「いつか浪江に帰って新しい家を建て、子どもたちの故郷を作りたい」と強く願っている。
4月からは5年生。弟の恭平君は新1年生だ。「調理クラブに入って、チャレンジしたい」と桃花さん。
「ずっと、この学校(上野台小)に通いたい」「浪江に帰れるのなら帰りたい」――。二つの正直な思いを胸に、桃花さんは震災から2度目の春を迎える。(加藤真太郎)
[PR]
東日本大震災の影響で、福島県浪江町から埼玉県ふじみ野市に避難している小学4年生の女の子が書いた作文「おにぎりとおみそしる」が注目を集めている。埼玉県教育委員会が震災に関わる出来事を題材に作った道徳教材「彩の国の道徳 心の絆」にも採用された。
--------------------------------------------------------------------------------
おにぎりとおみそしる
小さな白いおにぎりと具のないおみそしる これは、わたしにとって、わすれる事のできないごはんです。
わたしは、東日本大しんさいで、自分の家にいられなくなり、ひなん所で生活していました。その時の食事の内ようです。
それまでのわたしは、おやつを食べて、食事の時には、テーブルにはたくさんのおかずがあって、食後には、デザートまでありました。それが、あたり前だと思っていました。
とつぜんのさいがいを受け、ひなん所で生活をしてみて、わたしが食べていたものが、とてもめぐまれていた事に気が付きました。何日間も、おにぎりとおみそしるだけを食べていましたが、ふしぎとあれが、食べたい、これが、食べたいとは、思いませんでした。おなかがすいて、食べる事ができることだけで、うれしかったからです。
白いおにぎりから、中に梅ぼしが入ったおにぎりになった時は、とてもうれしかったです。
ひなん所から、東京にいどうした時に、はじめて、おかずのついたごはんを食べました。弟が大好きな野菜を見て、
「食べていいの。」
と聞きながら食べていました。とても、うれしそうでした。
今もまだ、自分の家には帰れないけれど、テーブルには、わたしの好きな食べ物がたくさんならびます。季節のフルーツもたべられるようになりました。ひなん所で、テーブルも無くて、おふとんをかたづけて、下を向いて食べた小さなおにぎりと具のないおみそしるの味は、ぜっ対にわすれません。こまっているわたし達にごはんを作ってくれた人達の事もわすれません。
ひなん所にいた時は、あまりわらう事ができませんでした。でも、今は、わらってごはんを食べています。つらい事やこわい事もたくさんありました。今は、ごはんを食べて、おふろにはいって、おふとんにねむれる事が、とてもうれしいし幸せです。
これからも、食べ物をそまつにしないで、楽しくごはんを食べていきたいと思います。 (全文)
--------------------------------------------------------------------------------
この作文を書いたのは、ふじみ野市立上野台小学校4年の常盤桃花さん(10)。震災直後、余震におびえながら避難所で食べた食事の記憶をたどり、支えてくれた人々や今の日常に感謝する内容になっている。昨年の夏休みに書き、今年度の埼玉県「食をめぐる作文」小学生の部で最優秀賞に輝いた。
自宅は、東京電力福島第一原子力発電所から北西約8キロの警戒区域内にある。震災直後、家族とともに避難した。
震災の時、桃花さんは町立大堀小の教室にいた。その夜は余震が続くなか、母親の小智江さん(44)と弟の恭平君(6)と近所の消防団の施設で過ごした。翌朝に避難指示が出されたため、車の中で朝を迎えた父親の弘幸さん(50)と合流し、約20キロ北西にある保育所に向かった。
保育所や周辺は、避難してきた人であふれていた。「すぐに帰れる」と思ったという小智江さんは、自宅からバナナ数本とあめ玉、トイレットペーパーだけしか持って来ていなかった。避難者の男性が雑貨店で買ってきたというだし用の削り節を一枚一枚、みんなで分け合って食べた。
■具は大好きな梅干し
小さなおにぎりと具のないおみそしるは、その晩に食べたものだ。保育所の先生たちが握ってくれた。
「おなかがすいていたので、とにかくうれしかった。みそ汁用の発泡スチロールのおわんとはしは捨てず、ティッシュペーパーでふいて何度も使った」
3泊した後、内陸の二本松市の避難所へ。そこで出たおにぎりも忘れられない。ほおばると、具は大好きな梅干しだった。思わず「うめだー」と叫んだ。
幼い弟も同じだった。
福島を出て、都内の親戚宅に滞在した際、レストランに行った。小智江さんから天ぷら定食の春菊を分けられた恭平君は震災後、初めてのおかずに「食べていいの?」と聞いた。そして手を震わせながら口に運んだという。
■作文を読んで先生が涙
この作文を最初に読んだ担任の松沢映子教諭は涙が止まらなかった。
「彼女の生の声がつづられていた。複雑な気持ちを秘めながらも、人とのつながりへの感謝を強めていく様子が伝わってきた」
桃花さんは昨年12月の全校朝会で発表。2月には避難者をいやす交流会「おあがんなんしょ」でも朗読し、多くの人が涙した。
市教育委員会は小中学生の全家庭に配る「子供未来カレンダー」に掲載。市教委から連絡を受けた大堀小の校長は、各地に避難しているPTA会員に送る「学校だより」でも紹介したという。
「心の絆」は、さいたま市を除く県内の公立学校の学級担任らに配られる。県教委は「日常生活を不自由なく過ごす中、支えてくれている人の存在や苦労に気づかないことが多い。この作文を通じて日常生活を見つめ直し、人々への尊敬や感謝の気持ちを育みたい」と期待を寄せる。
■いつも笑顔 帰りたい思いも胸に
桃花さんがふじみ野に避難して丸1年。4年生最後の登校日となった26日、教室で通知表を受け取ると、柔らかな笑顔を浮かべた。みんなの前で一人ずつ発表する「思い出一言コーナー」では、「この学校に来て、友達がいっぱいできて楽しかった。ありがとう」と語った。
松沢教諭は「あれだけの経験をして複雑な思いもあったはずなのに、いつもニコニコと前向きに生活し、周囲に自然といい影響を与えてくれた」とこの1年間を振り返った。
埼玉で新たな楽しみも見つけた。「一番は浦和のパルコや川越の丸広に大好きな洋服を見に行くこと」。「おあがんなんしょ」で毎月、ボランティアで参加する県立福岡高校の女子生徒と遊ぶのも楽しみだ。
でも、生まれ育った故郷を忘れることはない。
新潟県や秋田県で暮らす離ればなれの親友とは、電話やメールで頻繁に連絡を取り合っている。昨年の夏休みには再会を果たし、一緒に東京・原宿にも遊びに行った。
正月、川越市の喜多院に初詣に行った時も「たくさん会えますように」と長く手を合わせた。小智江さんも「いつか浪江に帰って新しい家を建て、子どもたちの故郷を作りたい」と強く願っている。
4月からは5年生。弟の恭平君は新1年生だ。「調理クラブに入って、チャレンジしたい」と桃花さん。
「ずっと、この学校(上野台小)に通いたい」「浪江に帰れるのなら帰りたい」――。二つの正直な思いを胸に、桃花さんは震災から2度目の春を迎える。(加藤真太郎)
|
|
|
|
|
|
|
|
東日本地震難病障がい高齢者支援 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
東日本地震難病障がい高齢者支援のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75482人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6444人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208287人