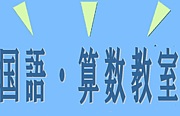20世紀までは「就職課」や「就職部」と呼ばれていた大学内組織が、ここ10年余りの間に次々と「キャリアセンター」もしくはそれと似た名称に看板を替えている。就職課時代のように就職活動生のお世話をするだけではなく、さまざまなキャリア形成支援やキャリア教育を担う新組織が必要とされてきたからだ。
そのキャリアセンター職員として複数の大学を渡り歩いてきた人物が、10月17日発売の『大学キャリアセンターのぶっちゃけ話 知的現場主義の就職活動』という新書で、現在の就職活動、大学生模様、企業の新卒採用活動、大学生の保護者の意識などについて実態を紹介、そこにある構造的課題をひも解いてみせた。
大学が受験生集めのために妙な計算式を用いて「高い就職率」をひねりだしている実例など、現役の大学キャリアセンター関係者が「ぶっちゃけ話」を書籍で明かしたのは本邦初で、発売まもなく大学人や企業人事の読者を中心にネット上でも話題となった。日経ビジネスオンラインにおいても小田嶋隆氏が10月21日のコラムで、就職活動の「現場はひどいことになっている。この本を読むと、学生がデモを起こさないでいる現状の方が、逆にSF小説の設定みたいに不自然に感じられる」と感想を述べている。
確かに就職活動の現場では、課題や難題が山積しているのだ。そこで、デビュー作の新書では書ききれなかったトピックについて、隔週ペースで著者の沢田氏に綴ってもらうことにした。まだまだキャンパスの外では知られていない「大学の実態」を、沢田氏の大学改革熱と共にお伝えしたい。
国内の大学進学率がまだ上昇を続けています。そして各大学(特に私大)は、受験者獲得競争と就職実績作りに奔走してきました。これらは引き続き過熱していくものと思われますが、ここ最近、新たな経営課題が大学関係者の頭を悩ませています。
それは、密かに増えている「中退者」の問題です。
2008年7月20日に読売新聞が、各大学の中途退学率を大々的に紹介しました。それまで中退率を公表してきた大学はごく少数で、国も各大学の中退率を把握していなかったため、教育関係者を中心に大きな反響を呼びました。
読売新聞で紹介された中退率は、世界的に見て特別高いわけではありません。OECD諸国の平均が約31%であるのに対し、日本は約10%です。
また、国公立や私立の上位大学では中退率が低く、下位大学ほど中退率が高い傾向が見られました。これは苦労して入試を突破した難関大をあえて辞める学生は少ないが、いわゆる入試偏差値の低い大学ほど簡単に学生が辞めてしまいやすい、というある意味で常識的な解釈のできる結果です。
退学理由については、「進路変更」「経済的困窮」「就学意欲の低下」が上位に挙がっており、そもそもの中退率の低さと併せて考えると、いわゆる普通の学生には縁遠い問題のようにも思えました。
しかし、入学さえできれば卒業はカンタンな日本の大学ですから、諸外国の中退率と比較して安心するのは早計です。
文部科学省が発表している学校基本調査のデータを参考に、入学者数から4年後の卒業者数を引くと、大まかな中退者数が分かります。例えば、1994年ではおよそ3万人であったものが、2004年になると5万人に膨れ上がっています。大学の設置基準の緩和によって大学数が大幅に増え、入学者数も増加したことが背景にありますが、この絶対数の大きさは見逃せるレベルじゃない。
2011年11月1日(火)
http://
日本私立学校振興・共済事業団も私立大学を対象に調査(2006年時点)した結果、1年間に5万5000人の退学者を出していることを明らかにしました。さらに、上位校においても中退者数が増えているという報告がいくつかあります。ましてや入試のハードルがないに等しい下位校の場合は、中退者が激増する危険性もあると思います。
学生タイプ別に中退理由を考えてみる
では、なぜ大学中退者が増えるのでしょうか。
経済的な理由以外にも、若者の意識や労働環境の変化など、さまざまな要因が絡んでいると考えるべきです。その詳細は専門の研究者の調査・分析を待つことにしましょう。ここでは既存の知見を参考にしつつ、大学生の「学習意欲」と「対人関係能力」という観点から、キャンパス内で私が見聞してきた実態に即して話を進めていきます。
学習意欲の高低と、対人関係能力の高低を組み合わせると、4種類の学生像が現れてきます。それぞれの学生像ごとに、抱えこみがちな悩みと中退との関係はどうなっているのか。
まず、「学習意欲が高くて、対人関係能力も高い」学生の場合。いわば「文句なし」タイプの学生なので、中退などとは無縁と思えます。ところが、このタイプの中退者も以前より増えている感触があります。
大学階層が下位にある大学ほど、「学習意欲が高くて、対人関係能力も高い」学生は不本意入学であることが多い。入学した大学に不満があるというよりかは、第1志望だった大学を諦めきれず、すべり止め大学の学生である現状の自分がなかなか受け入れられないわけです。
そうした学生が、ある日、ひょいと退学届けを出し、再受験生活に突入する。あるいは、在籍したまま大学にはほとんど来ないで、受験勉強漬けの仮面浪人生活を始める。見事に志望校に受かれば、もちろん、最初に入学した大学は中退します。
そうした動機と行動自体、別に悪いことではありません。より大学階層が上の大学で学びたい、という意志は尊重してあげるべきです。結果的に無駄となってしまう入学金や学費のことを考えると、「だったら、浪人すれば良かったのに」とも言いたくなりますが、もうずいぶん前から大学受験界では現役合格が前提なのです。高校も現役合格者数を競っており、その環境下で少数派である「浪人生になる」選択をするのには、相当な覚悟を要します。
また、大学階層の上位校、つまり高偏差値大学に入り直そうという上昇志向だけでなく、「希望の学科や専攻に入り直したい」という動機もあります。このパターンの中退は上位校の学生にも少なくない。
こちらの学生の意志も基本的には尊重してあげるべきですよね。もしそれが夢ばかりを見ていて現実を知らない勘違いだったとしても、やりたいことがあるならば、若いうちに挑戦したほうがいい。何事も実際にやってみなければ、自分とやりたいことの相性は見えてきませんから。
優秀な学生をキャリア教育が流出させる!?
いずれにせよ、そんなこんなで「文句なし」タイプの中退者も増えている。理由の1つは、先述した現役合格主義の大学受験にありそうです。過度に浪人生活を忌避する時代の気分の副産物のようなもの。
ただし、時代の気分がどうであれ、彼や彼女らも1度はすべり止め大学への入学を決めた人々ではあります。入学当初は「この大学でやっていこう」と自分に言い聞かせたはずです。それがどこで「再受験しよう」に変わるのか。
いろいろなきっかけがありますが、そのなかで私が皮肉だなと感じているのは、キャリア教育の授業が再受験の思いに火をつけた、というケースです。「将来のことを考えていたら、ここにいてはいけないと気づいた」なんて話を、ちょくちょく耳にします。
初年次のキャリア教育の目的は、入学生にその大学での有意義な4年間の過ごし方を考えさせることです。それが、「学習意欲が高くて、対人関係能力も高い」学生の中に潜在していたものを引っ張り出し、再受験≒中退の行動を取らせてしまう。
何度も繰り返しますが、学生個人にとっては悪いことじゃない。しかし、「学習意欲が高くて、対人関係能力も高い」優秀な学生に見切られた当の大学にとっては大きな痛手です。このような学生の増加は、上位校にとって恩恵を受けやすい流れですけれども、下位校からしたら経営危機に直結しかねない懸念材料にほかなりません。
機を見るに敏な一部の上位校は、既に編入学ルートの拡充を図っています。どうやら優秀な学生の流動化は進む一方の模様です。
キャリア教育に携わる者としては、皮肉な話だと感じながら、同時に「自校内で成長する」という枠を飛び越えて、自力でキャリア形成を試みようとする学生たちを興味深く見ています。そして、彼ら彼女らに何か支援ができないものか、アイデアをめぐらせているところです。
「便所飯」という生き地獄…
次は、「学習意欲は高いが、対人関係能力が低い」学生の場合を考えます。
どんな学生だって、多少の差こそあれ人間関係に悩みます。でも、根から人間関係に苦手意識を持つ学生は、ゼミナールや課題解決型の授業にも馴染みづらく、せっかく高い学習意欲を失ってしまうケースも目立ちます。
少し前に話題となった「便所飯」という大学生スラングをご存知でしょうか。これは昼食を一緒に食べるような友達が大学内にいないため、おにぎりやパンをトイレで一人こっそり食べる学生の行動を意味しています。実際にそんな学生がどれほどいるか、実は都市伝説にすぎない、とも言われていますが、人間関係にナイーブ過ぎる昨今の大学生の気質を適確に表現したスラングだと私は思います。
そして、「便所飯」状態が続くような学生の多くは、いずれキャンパスから姿を消してしまいます。学内のどこにも居場所を見つけられない状態が続けば、誰だって中退したくもなるでしょう。
勉強は好きだが、人づき合いがダメ。そうしたタイプの中には、単に性格がおとなしい学生がいる一方で、他人とのイザコザが絶えず孤立してしまう学生もいます。後者については、発達に何らかの障害があるケースも報告されています。
緩い条件の推薦やAO入試など、一般入試以外の様々な方法で大学入学できるようになり、現在のキャンパスはまさに多様な人々を抱え込んでいるわけです。
対人関係でつまずいてしまう大学生は、上位の大学にもたくさんいます。勉強にはマジメなので、みんなから離れた席でポツンと講義を聞いています。彼らや彼女の閉塞感は言葉に言い表せないものです。自分でも様子がおかしいと感じらたら、気軽にメンタルクリニックなどへ行って相談してみることも大事です。対人関係の悩みから抑うつ状態になる子も少なくないので。
「対人関係能力が低い」学生は、今後も増えていくと予想されます。そのため、大学側としても、人間関係トレーニングやアサーション(自己主張)講座など、人づきあいの基本を学ぶ取り組みに力を入れ始めています。
しかし、メンタルの問題は個々の事情です。学生ごとに異なる事情に合わせた支援をしていくには、今のマス化した大学には限界があります。入り口(入試制度)をこのままにしておく限り、何をどう支援しても、こぼれ落ちてしまう学生が出てしまうと私は考えます。
ボリューム層も大学に背を向け始めている
3番目に、「学習意欲は低いが、対人能力が高い」学生の問題を挙げます。先行研究などでは、「就学意欲の低下」ケースとして紹介されています。しかし、それは上位校(それも一部の)の学生の場合であって、中堅校以下であれば、もとより「学習意欲の無い学生」が存在しています。
こうした学生は、今になって現れたというよりは、これまでにも一定程度存在していたと考えるべきでしょう。4年間を趣味やアルバイト、サークルなどの課外活動に費やし、申し訳程度の勉強(単位取得が目的)によって何とか卒業していくタイプです。上位校にだって、普通にいましたよね。
彼ら彼女らをキャンパスにつなぎとめた要因は、友達の存在と、肩書としての「大卒」の価値です。高卒よりも大卒のほうが職業選択の幅は広く、給与面などの待遇が良く、入社後のキャリアプランにも期待が持てた。ところが、下位校を中心に、そうした大卒プレミアムが崩壊しつつあります。
大卒といっても、就職者は卒業生全体の6割程度です。日本の大学全体の平均値はそんな程度なのです。そして、その就職者のなかには非正規雇用も含まれています。就職したといっても、高卒と同じ扱いの就職先だったり、ブラック企業だったりなど、学生が就職活動前に思い描いていた就職とは大きく異なる実態があります。インターネットの掲示板などにも、「この大学を出ても△△△とかにしか就職できないよ」というリアルな書き込みが蔓延しています。
これでは学生が将来に対して、あるいは自校で学ぶことに対して、夢や希望を描けないのも責められません。周りの大人がどんなに可能性を説いても、自分の置かれている現実的な状況を直視させる大量の情報によって、ここにいる「理由」や「意義」が見出せなくなって中退するのです。
長引く不景気時代に多感な時期を過した世代ゆえに、コストと成果(得られるもの)に対する意識に敏感なのかも知れません。頑張っても将来が厳しいなら、いまさら勉強しようという気にもなれません。そして、目先の快楽や金銭的収入を得ることにのめり込んだ学生生活になっていくケースが珍しくありません。
中堅校以下でこのタイプの学生たちは、娯楽産業や飲食産業の会社に就職することになりやすい。そうした会社人事担当者ほど「人間力」や「コミュニケーション力」を重視すると言い、「何でもいいから頑張った学生」を評価するからです。
結果的に学生本人が納得した就職なら構わないのですが、「学習意欲は低いが、対人能力が高い」学生たちが自分の学生生活を、上記の人事担当者がよく発するメッセージで自己正当化すると、より一層、学業に背を向けてしまいます。その結果、大学という枠組自体からドロップアウトしてしまう者が出てきます。大学の勉強なんかバカらしいから辞めてしまうわけです。
大学は、こうした実はボリューム層の学生たちを、もう子供ではないという理由、または自己責任という言葉によって、放置してきたと言えるでしょう。
産業構造がどんどん複雑化し、これまで以上に学校社会から職業社会への移行が困難になると予想されます。学ぶことと働くことをつなぐ教育の必要性と難しさが明らかになってきます。
そんな中、大学教育にコミットメントしていない学生に対し、大学が何も提示しないのなら、大量のドロップアウトを出す覚悟が必要です。それは、大学が社会に存在する意義を問われるということにもつながると思います。
知られざる下位校の惨憺たる現実
最後に、「学習意欲が低く、対人関係能力も低い」学生の問題です。
少子化に反して大学進学率が上がっているのだから、当然、この層の学生は増えています。そして、あまり報道されないだけで、下位校において「学級崩壊」状態になっている授業はいくらでもあります。
エネルギーを持て余して教室で騒ぐくらいなら、バイトで生活費を稼いでこい、と言いたくなる学生はいっぱいいるのだけれども、なぜか大学をサボる学生は減っています。出欠を取る授業が多くなったせいもありますが、キャンパスのほかに居場所がないから来るだけは来て教室で暇を持て余している、といったしょうもない連中が本当に増えているのです。
ここで私が言いたいのは、こうした層の若者は大学生になるな、ということではありません。過剰な広報と、ゆるゆるの入試制度によって、この層を積極的に受け入れたのは大学側なのです。例えば、「本当の自分に出会える!」などと大々的にうたったりして。
この手の広報というか、大学広告・宣伝を、私は悪意に満ちたウソだとは言いませんが、白いウソだと思っています。実際は無気力ムードに支配されているキャンパスだが、まさかそうだと自らは言えない。
それに対し、進路に関する公表データは非常に作為的で黒いウソが多い。あり得ない高い就職率で受験生集めをする大学は、残念ながら、例外的存在ではありません。就職が厳しいことは、いまや高校生でさえ熟知しています。だから少しでも就職に近づけそうな大学を選んで進学するのです。「就職力」を強調する広告戦略は、そうした受験生の不安につけ入るようなやり方で、中堅校以下では常態化している大学も多い。
ウソつき大学の学生の素行が悪くたって、彼らだけを責めることはできませんよね。私が指摘したいのは、そのように以前とは明らかに質の異なる学生を受け入れるようになった大学において、肝心の中身である大学教育に変化が見られないことです。
一部の熱心な教員や問題意識のある職員は、学生の質に合わせて工夫をしていかねばならないと頑張っています。しかし、私が見る限り、ほとんどの大学教員はこれまでと同じ「研究者」としての立ち位置を堅守し、事務職員は「前年通り」の仕事スタイルを踏襲しています。
もはや「大学生」と呼べる状態にない、なぜ自分が高等教育を受けているのか理解できないコドモたちは、旧態依然とした大学内で放置されているのです。
少人数の大学であれば、問題を抱えた学生を早期に発見し、何らかの個別支援を講じることも可能だと思います。しかし、大規模大学であれば、ハッキリ言って難しいのが現状です。
それどころか、「学習意欲が低く、対人関係能力も低い」、つまり就職実績を上げられそうもない学生に限られた資源を投下するより、むしろ退学という学外への道を大学側が選択肢の1つとして提示していく流れが予想されます。企業の肩叩きや、昔から私立中高でありがちな適者生存型のガバナンスがいい例になるはずです。
本人にその気が無いのなら、大学側としても無理してまで大学に通わせる必要はない。そのような合理的判断にもとづく「退学のススメ」を口にする大学人は、すでに出始めてきています。ゆるゆるの入試で合格させた結果なのに!
何のための学問なのか
さて。一向に進まない大学教育改革。その一方で、入学者の多様化が進んでおり、学生のニーズと大学教育内容との乖離は広がるばかりです。
既に私立大学の4割近くは定員割れを起こしており、4割近くは赤字経営に陥っているとの報告があります。そのような状況下で、ここ10年間ほどの大学は入口(受験者募集)と出口(就職支援)に、経営資源を集中的に配分してきました。
その分、中身(教育)が疎かになった大学、あるいは中身が広報のパワーに追いつけなかった大学において、今後も中退者は増加していくことが予想されます。
無理をして志望者を募るのであれば、大学はこれまで以上に中身の拡充と、企業社会とのつながりを再構築し、学生たちに学ぶ意義を教えていく必要があります。キミたちの将来の何のための学問なのか。
文系学部においてことさら、これまであやふやにしてきた部分です。いま、まさにそれが社会から問われているといえます。
大学が無理をして志望者を募らないのであれば、社会が高卒でも生きていける道を明示する必要があります。それはできない話というなら、大学中退者が増えていく現実を見据え、彼ら彼女らが辞める理由から大学教育の何をどう改革すべきなのか、大学関係者が学ぶときなのだと思います。
(文/沢田健太、企画・編集/連結社)
http://
そのキャリアセンター職員として複数の大学を渡り歩いてきた人物が、10月17日発売の『大学キャリアセンターのぶっちゃけ話 知的現場主義の就職活動』という新書で、現在の就職活動、大学生模様、企業の新卒採用活動、大学生の保護者の意識などについて実態を紹介、そこにある構造的課題をひも解いてみせた。
大学が受験生集めのために妙な計算式を用いて「高い就職率」をひねりだしている実例など、現役の大学キャリアセンター関係者が「ぶっちゃけ話」を書籍で明かしたのは本邦初で、発売まもなく大学人や企業人事の読者を中心にネット上でも話題となった。日経ビジネスオンラインにおいても小田嶋隆氏が10月21日のコラムで、就職活動の「現場はひどいことになっている。この本を読むと、学生がデモを起こさないでいる現状の方が、逆にSF小説の設定みたいに不自然に感じられる」と感想を述べている。
確かに就職活動の現場では、課題や難題が山積しているのだ。そこで、デビュー作の新書では書ききれなかったトピックについて、隔週ペースで著者の沢田氏に綴ってもらうことにした。まだまだキャンパスの外では知られていない「大学の実態」を、沢田氏の大学改革熱と共にお伝えしたい。
国内の大学進学率がまだ上昇を続けています。そして各大学(特に私大)は、受験者獲得競争と就職実績作りに奔走してきました。これらは引き続き過熱していくものと思われますが、ここ最近、新たな経営課題が大学関係者の頭を悩ませています。
それは、密かに増えている「中退者」の問題です。
2008年7月20日に読売新聞が、各大学の中途退学率を大々的に紹介しました。それまで中退率を公表してきた大学はごく少数で、国も各大学の中退率を把握していなかったため、教育関係者を中心に大きな反響を呼びました。
読売新聞で紹介された中退率は、世界的に見て特別高いわけではありません。OECD諸国の平均が約31%であるのに対し、日本は約10%です。
また、国公立や私立の上位大学では中退率が低く、下位大学ほど中退率が高い傾向が見られました。これは苦労して入試を突破した難関大をあえて辞める学生は少ないが、いわゆる入試偏差値の低い大学ほど簡単に学生が辞めてしまいやすい、というある意味で常識的な解釈のできる結果です。
退学理由については、「進路変更」「経済的困窮」「就学意欲の低下」が上位に挙がっており、そもそもの中退率の低さと併せて考えると、いわゆる普通の学生には縁遠い問題のようにも思えました。
しかし、入学さえできれば卒業はカンタンな日本の大学ですから、諸外国の中退率と比較して安心するのは早計です。
文部科学省が発表している学校基本調査のデータを参考に、入学者数から4年後の卒業者数を引くと、大まかな中退者数が分かります。例えば、1994年ではおよそ3万人であったものが、2004年になると5万人に膨れ上がっています。大学の設置基準の緩和によって大学数が大幅に増え、入学者数も増加したことが背景にありますが、この絶対数の大きさは見逃せるレベルじゃない。
2011年11月1日(火)
http://
日本私立学校振興・共済事業団も私立大学を対象に調査(2006年時点)した結果、1年間に5万5000人の退学者を出していることを明らかにしました。さらに、上位校においても中退者数が増えているという報告がいくつかあります。ましてや入試のハードルがないに等しい下位校の場合は、中退者が激増する危険性もあると思います。
学生タイプ別に中退理由を考えてみる
では、なぜ大学中退者が増えるのでしょうか。
経済的な理由以外にも、若者の意識や労働環境の変化など、さまざまな要因が絡んでいると考えるべきです。その詳細は専門の研究者の調査・分析を待つことにしましょう。ここでは既存の知見を参考にしつつ、大学生の「学習意欲」と「対人関係能力」という観点から、キャンパス内で私が見聞してきた実態に即して話を進めていきます。
学習意欲の高低と、対人関係能力の高低を組み合わせると、4種類の学生像が現れてきます。それぞれの学生像ごとに、抱えこみがちな悩みと中退との関係はどうなっているのか。
まず、「学習意欲が高くて、対人関係能力も高い」学生の場合。いわば「文句なし」タイプの学生なので、中退などとは無縁と思えます。ところが、このタイプの中退者も以前より増えている感触があります。
大学階層が下位にある大学ほど、「学習意欲が高くて、対人関係能力も高い」学生は不本意入学であることが多い。入学した大学に不満があるというよりかは、第1志望だった大学を諦めきれず、すべり止め大学の学生である現状の自分がなかなか受け入れられないわけです。
そうした学生が、ある日、ひょいと退学届けを出し、再受験生活に突入する。あるいは、在籍したまま大学にはほとんど来ないで、受験勉強漬けの仮面浪人生活を始める。見事に志望校に受かれば、もちろん、最初に入学した大学は中退します。
そうした動機と行動自体、別に悪いことではありません。より大学階層が上の大学で学びたい、という意志は尊重してあげるべきです。結果的に無駄となってしまう入学金や学費のことを考えると、「だったら、浪人すれば良かったのに」とも言いたくなりますが、もうずいぶん前から大学受験界では現役合格が前提なのです。高校も現役合格者数を競っており、その環境下で少数派である「浪人生になる」選択をするのには、相当な覚悟を要します。
また、大学階層の上位校、つまり高偏差値大学に入り直そうという上昇志向だけでなく、「希望の学科や専攻に入り直したい」という動機もあります。このパターンの中退は上位校の学生にも少なくない。
こちらの学生の意志も基本的には尊重してあげるべきですよね。もしそれが夢ばかりを見ていて現実を知らない勘違いだったとしても、やりたいことがあるならば、若いうちに挑戦したほうがいい。何事も実際にやってみなければ、自分とやりたいことの相性は見えてきませんから。
優秀な学生をキャリア教育が流出させる!?
いずれにせよ、そんなこんなで「文句なし」タイプの中退者も増えている。理由の1つは、先述した現役合格主義の大学受験にありそうです。過度に浪人生活を忌避する時代の気分の副産物のようなもの。
ただし、時代の気分がどうであれ、彼や彼女らも1度はすべり止め大学への入学を決めた人々ではあります。入学当初は「この大学でやっていこう」と自分に言い聞かせたはずです。それがどこで「再受験しよう」に変わるのか。
いろいろなきっかけがありますが、そのなかで私が皮肉だなと感じているのは、キャリア教育の授業が再受験の思いに火をつけた、というケースです。「将来のことを考えていたら、ここにいてはいけないと気づいた」なんて話を、ちょくちょく耳にします。
初年次のキャリア教育の目的は、入学生にその大学での有意義な4年間の過ごし方を考えさせることです。それが、「学習意欲が高くて、対人関係能力も高い」学生の中に潜在していたものを引っ張り出し、再受験≒中退の行動を取らせてしまう。
何度も繰り返しますが、学生個人にとっては悪いことじゃない。しかし、「学習意欲が高くて、対人関係能力も高い」優秀な学生に見切られた当の大学にとっては大きな痛手です。このような学生の増加は、上位校にとって恩恵を受けやすい流れですけれども、下位校からしたら経営危機に直結しかねない懸念材料にほかなりません。
機を見るに敏な一部の上位校は、既に編入学ルートの拡充を図っています。どうやら優秀な学生の流動化は進む一方の模様です。
キャリア教育に携わる者としては、皮肉な話だと感じながら、同時に「自校内で成長する」という枠を飛び越えて、自力でキャリア形成を試みようとする学生たちを興味深く見ています。そして、彼ら彼女らに何か支援ができないものか、アイデアをめぐらせているところです。
「便所飯」という生き地獄…
次は、「学習意欲は高いが、対人関係能力が低い」学生の場合を考えます。
どんな学生だって、多少の差こそあれ人間関係に悩みます。でも、根から人間関係に苦手意識を持つ学生は、ゼミナールや課題解決型の授業にも馴染みづらく、せっかく高い学習意欲を失ってしまうケースも目立ちます。
少し前に話題となった「便所飯」という大学生スラングをご存知でしょうか。これは昼食を一緒に食べるような友達が大学内にいないため、おにぎりやパンをトイレで一人こっそり食べる学生の行動を意味しています。実際にそんな学生がどれほどいるか、実は都市伝説にすぎない、とも言われていますが、人間関係にナイーブ過ぎる昨今の大学生の気質を適確に表現したスラングだと私は思います。
そして、「便所飯」状態が続くような学生の多くは、いずれキャンパスから姿を消してしまいます。学内のどこにも居場所を見つけられない状態が続けば、誰だって中退したくもなるでしょう。
勉強は好きだが、人づき合いがダメ。そうしたタイプの中には、単に性格がおとなしい学生がいる一方で、他人とのイザコザが絶えず孤立してしまう学生もいます。後者については、発達に何らかの障害があるケースも報告されています。
緩い条件の推薦やAO入試など、一般入試以外の様々な方法で大学入学できるようになり、現在のキャンパスはまさに多様な人々を抱え込んでいるわけです。
対人関係でつまずいてしまう大学生は、上位の大学にもたくさんいます。勉強にはマジメなので、みんなから離れた席でポツンと講義を聞いています。彼らや彼女の閉塞感は言葉に言い表せないものです。自分でも様子がおかしいと感じらたら、気軽にメンタルクリニックなどへ行って相談してみることも大事です。対人関係の悩みから抑うつ状態になる子も少なくないので。
「対人関係能力が低い」学生は、今後も増えていくと予想されます。そのため、大学側としても、人間関係トレーニングやアサーション(自己主張)講座など、人づきあいの基本を学ぶ取り組みに力を入れ始めています。
しかし、メンタルの問題は個々の事情です。学生ごとに異なる事情に合わせた支援をしていくには、今のマス化した大学には限界があります。入り口(入試制度)をこのままにしておく限り、何をどう支援しても、こぼれ落ちてしまう学生が出てしまうと私は考えます。
ボリューム層も大学に背を向け始めている
3番目に、「学習意欲は低いが、対人能力が高い」学生の問題を挙げます。先行研究などでは、「就学意欲の低下」ケースとして紹介されています。しかし、それは上位校(それも一部の)の学生の場合であって、中堅校以下であれば、もとより「学習意欲の無い学生」が存在しています。
こうした学生は、今になって現れたというよりは、これまでにも一定程度存在していたと考えるべきでしょう。4年間を趣味やアルバイト、サークルなどの課外活動に費やし、申し訳程度の勉強(単位取得が目的)によって何とか卒業していくタイプです。上位校にだって、普通にいましたよね。
彼ら彼女らをキャンパスにつなぎとめた要因は、友達の存在と、肩書としての「大卒」の価値です。高卒よりも大卒のほうが職業選択の幅は広く、給与面などの待遇が良く、入社後のキャリアプランにも期待が持てた。ところが、下位校を中心に、そうした大卒プレミアムが崩壊しつつあります。
大卒といっても、就職者は卒業生全体の6割程度です。日本の大学全体の平均値はそんな程度なのです。そして、その就職者のなかには非正規雇用も含まれています。就職したといっても、高卒と同じ扱いの就職先だったり、ブラック企業だったりなど、学生が就職活動前に思い描いていた就職とは大きく異なる実態があります。インターネットの掲示板などにも、「この大学を出ても△△△とかにしか就職できないよ」というリアルな書き込みが蔓延しています。
これでは学生が将来に対して、あるいは自校で学ぶことに対して、夢や希望を描けないのも責められません。周りの大人がどんなに可能性を説いても、自分の置かれている現実的な状況を直視させる大量の情報によって、ここにいる「理由」や「意義」が見出せなくなって中退するのです。
長引く不景気時代に多感な時期を過した世代ゆえに、コストと成果(得られるもの)に対する意識に敏感なのかも知れません。頑張っても将来が厳しいなら、いまさら勉強しようという気にもなれません。そして、目先の快楽や金銭的収入を得ることにのめり込んだ学生生活になっていくケースが珍しくありません。
中堅校以下でこのタイプの学生たちは、娯楽産業や飲食産業の会社に就職することになりやすい。そうした会社人事担当者ほど「人間力」や「コミュニケーション力」を重視すると言い、「何でもいいから頑張った学生」を評価するからです。
結果的に学生本人が納得した就職なら構わないのですが、「学習意欲は低いが、対人能力が高い」学生たちが自分の学生生活を、上記の人事担当者がよく発するメッセージで自己正当化すると、より一層、学業に背を向けてしまいます。その結果、大学という枠組自体からドロップアウトしてしまう者が出てきます。大学の勉強なんかバカらしいから辞めてしまうわけです。
大学は、こうした実はボリューム層の学生たちを、もう子供ではないという理由、または自己責任という言葉によって、放置してきたと言えるでしょう。
産業構造がどんどん複雑化し、これまで以上に学校社会から職業社会への移行が困難になると予想されます。学ぶことと働くことをつなぐ教育の必要性と難しさが明らかになってきます。
そんな中、大学教育にコミットメントしていない学生に対し、大学が何も提示しないのなら、大量のドロップアウトを出す覚悟が必要です。それは、大学が社会に存在する意義を問われるということにもつながると思います。
知られざる下位校の惨憺たる現実
最後に、「学習意欲が低く、対人関係能力も低い」学生の問題です。
少子化に反して大学進学率が上がっているのだから、当然、この層の学生は増えています。そして、あまり報道されないだけで、下位校において「学級崩壊」状態になっている授業はいくらでもあります。
エネルギーを持て余して教室で騒ぐくらいなら、バイトで生活費を稼いでこい、と言いたくなる学生はいっぱいいるのだけれども、なぜか大学をサボる学生は減っています。出欠を取る授業が多くなったせいもありますが、キャンパスのほかに居場所がないから来るだけは来て教室で暇を持て余している、といったしょうもない連中が本当に増えているのです。
ここで私が言いたいのは、こうした層の若者は大学生になるな、ということではありません。過剰な広報と、ゆるゆるの入試制度によって、この層を積極的に受け入れたのは大学側なのです。例えば、「本当の自分に出会える!」などと大々的にうたったりして。
この手の広報というか、大学広告・宣伝を、私は悪意に満ちたウソだとは言いませんが、白いウソだと思っています。実際は無気力ムードに支配されているキャンパスだが、まさかそうだと自らは言えない。
それに対し、進路に関する公表データは非常に作為的で黒いウソが多い。あり得ない高い就職率で受験生集めをする大学は、残念ながら、例外的存在ではありません。就職が厳しいことは、いまや高校生でさえ熟知しています。だから少しでも就職に近づけそうな大学を選んで進学するのです。「就職力」を強調する広告戦略は、そうした受験生の不安につけ入るようなやり方で、中堅校以下では常態化している大学も多い。
ウソつき大学の学生の素行が悪くたって、彼らだけを責めることはできませんよね。私が指摘したいのは、そのように以前とは明らかに質の異なる学生を受け入れるようになった大学において、肝心の中身である大学教育に変化が見られないことです。
一部の熱心な教員や問題意識のある職員は、学生の質に合わせて工夫をしていかねばならないと頑張っています。しかし、私が見る限り、ほとんどの大学教員はこれまでと同じ「研究者」としての立ち位置を堅守し、事務職員は「前年通り」の仕事スタイルを踏襲しています。
もはや「大学生」と呼べる状態にない、なぜ自分が高等教育を受けているのか理解できないコドモたちは、旧態依然とした大学内で放置されているのです。
少人数の大学であれば、問題を抱えた学生を早期に発見し、何らかの個別支援を講じることも可能だと思います。しかし、大規模大学であれば、ハッキリ言って難しいのが現状です。
それどころか、「学習意欲が低く、対人関係能力も低い」、つまり就職実績を上げられそうもない学生に限られた資源を投下するより、むしろ退学という学外への道を大学側が選択肢の1つとして提示していく流れが予想されます。企業の肩叩きや、昔から私立中高でありがちな適者生存型のガバナンスがいい例になるはずです。
本人にその気が無いのなら、大学側としても無理してまで大学に通わせる必要はない。そのような合理的判断にもとづく「退学のススメ」を口にする大学人は、すでに出始めてきています。ゆるゆるの入試で合格させた結果なのに!
何のための学問なのか
さて。一向に進まない大学教育改革。その一方で、入学者の多様化が進んでおり、学生のニーズと大学教育内容との乖離は広がるばかりです。
既に私立大学の4割近くは定員割れを起こしており、4割近くは赤字経営に陥っているとの報告があります。そのような状況下で、ここ10年間ほどの大学は入口(受験者募集)と出口(就職支援)に、経営資源を集中的に配分してきました。
その分、中身(教育)が疎かになった大学、あるいは中身が広報のパワーに追いつけなかった大学において、今後も中退者は増加していくことが予想されます。
無理をして志望者を募るのであれば、大学はこれまで以上に中身の拡充と、企業社会とのつながりを再構築し、学生たちに学ぶ意義を教えていく必要があります。キミたちの将来の何のための学問なのか。
文系学部においてことさら、これまであやふやにしてきた部分です。いま、まさにそれが社会から問われているといえます。
大学が無理をして志望者を募らないのであれば、社会が高卒でも生きていける道を明示する必要があります。それはできない話というなら、大学中退者が増えていく現実を見据え、彼ら彼女らが辞める理由から大学教育の何をどう改革すべきなのか、大学関係者が学ぶときなのだと思います。
(文/沢田健太、企画・編集/連結社)
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
国語・算数教室 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-