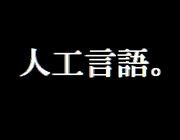人工言語作りの参考とするため、
自然言語の発音や文法を例示するためのトピックです。
随時更新します。
■/a e i o u/の5母音をもつ言語
・スペイン語
・日本語
・アイヌ語
・現代ギリシア語
α/a/ ε,αι/e/ ι,υ,η,οι/i/ ο,ω/o/ ου/u/
・スワヒリ語
・
・
・
■/a e i o u/の5母音プラス曖昧母音をもつ言語
・マレーシア語
・インドネシア語
・現代ヘブライ語
・ギリヤーク語
・
・
・
■長母音をもち、かつ書き分ける言語
・アラビア語
・ペルシア語
・ヒンディー語
・モンゴル語
・ハンガリー語
・フィンランド語
・オランダ語
・ドイツ語
・
・
・
自然言語の発音や文法を例示するためのトピックです。
随時更新します。
■/a e i o u/の5母音をもつ言語
・スペイン語
・日本語
・アイヌ語
・現代ギリシア語
α/a/ ε,αι/e/ ι,υ,η,οι/i/ ο,ω/o/ ου/u/
・スワヒリ語
・
・
・
■/a e i o u/の5母音プラス曖昧母音をもつ言語
・マレーシア語
・インドネシア語
・現代ヘブライ語
・ギリヤーク語
・
・
・
■長母音をもち、かつ書き分ける言語
・アラビア語
・ペルシア語
・ヒンディー語
・モンゴル語
・ハンガリー語
・フィンランド語
・オランダ語
・ドイツ語
・
・
・
|
|
|
|
コメント(34)
mixiは登録商標なので、mixi外で使う日のことを考えると、微妙な問題があると思います。mとxくらいをもらうなら、回避できるかもしれませんが、将来性を考えるなら、別のものにしたほうがいいかと思います。
もちろん、開発名なら、mixi内で、非営利で使うことが前提ですので、ほとんど問題は起きないと思いますが。
2ちゃん発の言語みたいに、自分を指す言葉や、エスペラントみたいに願いを表す単語ができたら、それを投票したりして決める、なんてのはどうでしょうか。
そんな流れなら、開発名として、mixicに一票入れます。
あ、でも厳密に考えると、-icはこの言語での形容詞・言語名語尾なのかどうかと、xをksの発音で使うかどうか、さらにxを使うかどうか、未定なんですが、そこはあえて見なかったことにするんでしょうか。
もちろん、開発名なら、mixi内で、非営利で使うことが前提ですので、ほとんど問題は起きないと思いますが。
2ちゃん発の言語みたいに、自分を指す言葉や、エスペラントみたいに願いを表す単語ができたら、それを投票したりして決める、なんてのはどうでしょうか。
そんな流れなら、開発名として、mixicに一票入れます。
あ、でも厳密に考えると、-icはこの言語での形容詞・言語名語尾なのかどうかと、xをksの発音で使うかどうか、さらにxを使うかどうか、未定なんですが、そこはあえて見なかったことにするんでしょうか。
参考までのお話です。
接尾辞によって、時制やアスペクトをあらわす言語が
ありますね。
どうも、多くの言語で過去時制や完了アスペクトを
あらわす接尾辞には、/t//d//n//l/などの歯茎音が
よく使われているような気がします。
◆中国語
―了le
―勒lə?(上海語)
◆印欧語
-d, -t / -de, -te (ゲルマン諸語)
-d-, -t- (完了語幹、ラテン語やギリシア語)
-d , -t (過去語幹、現代ペルシア語)
-l/-la/-lo/li (過去時制、スラブ諸語)
◆チュルク語
-di / -ti (過去時制)
◆日本語
-tu 「〜つ」/ -nu「〜ぬ」 (完了の助動詞)
-ta <tari
◆ニブフ語(ギリヤーク語)
-d (完了/過去時制?)
歯茎音が、動作の終着を「象形」しているのだ、
とかいう話を聞いたことがありますが、はたして??
接尾辞によって、時制やアスペクトをあらわす言語が
ありますね。
どうも、多くの言語で過去時制や完了アスペクトを
あらわす接尾辞には、/t//d//n//l/などの歯茎音が
よく使われているような気がします。
◆中国語
―了le
―勒lə?(上海語)
◆印欧語
-d, -t / -de, -te (ゲルマン諸語)
-d-, -t- (完了語幹、ラテン語やギリシア語)
-d , -t (過去語幹、現代ペルシア語)
-l/-la/-lo/li (過去時制、スラブ諸語)
◆チュルク語
-di / -ti (過去時制)
◆日本語
-tu 「〜つ」/ -nu「〜ぬ」 (完了の助動詞)
-ta <tari
◆ニブフ語(ギリヤーク語)
-d (完了/過去時制?)
歯茎音が、動作の終着を「象形」しているのだ、
とかいう話を聞いたことがありますが、はたして??
続けて参考用の話題です。
まとまりのない内容ですが・・・
◆人称代名詞に関して
1人称の複数形において、「包括型」と「除外(対立)型」
の2タイプを持つ言語があります。
包括型とは、「私」と「あなた」を含む「私たち」
除外型とは、「あなた」を含まずそれに対して「私ども」
ということです。この2種類の1人称複数を区別する言語は
太平洋地域に多いと聞いたことがあります。
◆人称代名詞の語形に関して
ユーラシア諸言語の人称代名詞の形は、たがいによく
似ていますね。
◇印欧語族
私:mi〜
君:ti〜tu
◇チュルク諸語
私:men〜ben
君:sen
◇モンゴル語
私:bi
君:ta
◇ツングース諸語
私:bi
君:si
◇ニブフ(ギリヤーク)語
私:nyi
君:či
◇チュクチ語(古シベリア諸語)
私:ghəm (私たち:muri)
君:ghət (君たち:turi)
◇ユカギル語(古シベリア諸語)
私:met
君:tet
まとまりのない内容ですが・・・
◆人称代名詞に関して
1人称の複数形において、「包括型」と「除外(対立)型」
の2タイプを持つ言語があります。
包括型とは、「私」と「あなた」を含む「私たち」
除外型とは、「あなた」を含まずそれに対して「私ども」
ということです。この2種類の1人称複数を区別する言語は
太平洋地域に多いと聞いたことがあります。
◆人称代名詞の語形に関して
ユーラシア諸言語の人称代名詞の形は、たがいによく
似ていますね。
◇印欧語族
私:mi〜
君:ti〜tu
◇チュルク諸語
私:men〜ben
君:sen
◇モンゴル語
私:bi
君:ta
◇ツングース諸語
私:bi
君:si
◇ニブフ(ギリヤーク)語
私:nyi
君:či
◇チュクチ語(古シベリア諸語)
私:ghəm (私たち:muri)
君:ghət (君たち:turi)
◇ユカギル語(古シベリア諸語)
私:met
君:tet
♪なるほど。複数の言語で、似たような単語が見られるわけですね。
統計的にmixicの単語を決めるのも面白そうですね。
指示代名詞は歯茎音が多く、否定詞は鼻音が多いという話もきいたことがあります。
♪認知言語学でわかっている、デフォルトの文法も取り入れられたら面白いですね。デフォルトがあるかどうかは、まだ研究中ですが、私見では、あると思います。格助詞は前置がデフォルトとか、関係代名詞は動詞句の末端に代名詞を繰り返すのがデフォルト(鞄の中のノートを取り出したvsノートが鞄の中に入っているのを取り出した)とか。この例は、小耳に挟んだ程度ですので、調べ直す必要がありますが。
♪最近、インドネシア人の友人とよく話します。インドネシア語を少し教えてもらいました。名詞句の連なりで、動詞が予測できる場合は、大学の授業のレポートくらいのきちんとした文章であっても、動詞句を省略するそうです。
例。。。書いてもらったメモをなくしてしまった。。。
日本語で「午後、友人と曽我の梅の花。そのあと、早めの夕食。」
で、「〜を鑑賞した」と「〜を食べた」という意味になります。学生による、と言っていましたが。彼はこういう省略文でレポートを通したそうで。彼が特別かどうか、一考の余地はありますが、とりあえず英語と日本語よりは許容範囲が広いことは確かです。
統計的にmixicの単語を決めるのも面白そうですね。
指示代名詞は歯茎音が多く、否定詞は鼻音が多いという話もきいたことがあります。
♪認知言語学でわかっている、デフォルトの文法も取り入れられたら面白いですね。デフォルトがあるかどうかは、まだ研究中ですが、私見では、あると思います。格助詞は前置がデフォルトとか、関係代名詞は動詞句の末端に代名詞を繰り返すのがデフォルト(鞄の中のノートを取り出したvsノートが鞄の中に入っているのを取り出した)とか。この例は、小耳に挟んだ程度ですので、調べ直す必要がありますが。
♪最近、インドネシア人の友人とよく話します。インドネシア語を少し教えてもらいました。名詞句の連なりで、動詞が予測できる場合は、大学の授業のレポートくらいのきちんとした文章であっても、動詞句を省略するそうです。
例。。。書いてもらったメモをなくしてしまった。。。
日本語で「午後、友人と曽我の梅の花。そのあと、早めの夕食。」
で、「〜を鑑賞した」と「〜を食べた」という意味になります。学生による、と言っていましたが。彼はこういう省略文でレポートを通したそうで。彼が特別かどうか、一考の余地はありますが、とりあえず英語と日本語よりは許容範囲が広いことは確かです。
●人称代名詞
> 1人称の複数形において、「包括型」と「除外(対立)型」
> の2タイプを持つ言語があります。
この区別は文意の明瞭さの点で有利だと思うんですが、日本語を含む東アジアでも印欧語でも主流ではないんですよね。
マレー語(&インドネシア語)やタミル語に存在する一方で、ヒンディーやサンスクリットにないので、その辺り(南北インド)が境界線の一つでしょうか。
●重ね言葉
マレー・インドネシア語で一つ面白いのは、複数や強調などを表わすのに単語を重複させる点。orang-orangで人々とか、pagi-pagiで朝早くとか……日本語(漢語は別として和語のみ)にも山々だの家々だのと似た形があることから、古層はやはり太平洋域の言語と共通だろうというのが定説ですけども。
> 1人称の複数形において、「包括型」と「除外(対立)型」
> の2タイプを持つ言語があります。
この区別は文意の明瞭さの点で有利だと思うんですが、日本語を含む東アジアでも印欧語でも主流ではないんですよね。
マレー語(&インドネシア語)やタミル語に存在する一方で、ヒンディーやサンスクリットにないので、その辺り(南北インド)が境界線の一つでしょうか。
●重ね言葉
マレー・インドネシア語で一つ面白いのは、複数や強調などを表わすのに単語を重複させる点。orang-orangで人々とか、pagi-pagiで朝早くとか……日本語(漢語は別として和語のみ)にも山々だの家々だのと似た形があることから、古層はやはり太平洋域の言語と共通だろうというのが定説ですけども。
チーズケーキさま
>指示代名詞は歯茎音が多く、否定詞は鼻音が多いという話もきいたことがあります。
すごい!知りませんでした。ちょっと調べてみましたが
ほんとにそうですね。びっくりです。
◆日本語
「それ」:so-(そ)
否定辞:nu(ぬ), nasi(なし), mazi(まじ)
◆漢語
「これ」:這zhe 之zhi 是shi 此ci 斯si
否定辞:不bu 没mei 莫mo<*mak 無wu<*mıua- 勿wu<*mıuət
◆満州語(ツングース諸語)
「それ」:tere
◆トルコ語
「それ」:šu
否定辞:-ma〜me
◆印欧語族
「それ」:*so, *sa, *tod
否定辞:non / ne / na
あと、これは自然なことですが、親族名称とくに「母親」「父親」をあらわす単語には「両唇音」でできているものが多いですね。たぶん、赤ちゃんが最初に発声できる音が「両唇音」で
最初に認知する対象が「母親」そして「父親」だからだと思われます。
◆漢語
ma-ma / 母mu<mo<*ma
ba-ba, die-die / 父fu<po<*pa
◆ニブフ(ギリヤーク)語
母:əmk
父:ətk
◆朝鮮語
母:omoni
父:aboji
◆満州語(ツングース諸語)
母:eme
父:ama
◆チュルク語
母:anne
父:ata
◆印欧語族
母:*mot-er
父:*pət-er
(幼児語 mama, papa)
◆アラビア語(セム語族)
母:ummu
父:abu
◆インドネシア語(オーストロネシア語族)
母:ibu
父:bapak
基本語彙を決定するさいに、こういうのをふまえながら考えるといいかもしれませんね。
>動詞句を省略
おもしろいですね。漢詩・漢文でもレトリックで似たようなことがあります。上のインドネシア語の例は対句みたいですね。
死郎さま
mixicのほうに包括/除外の2タイプの1人称複数をとりいれても面白いかとおもいますが、あまり普遍的な特徴ではないし、ちょっと奇をてらった感じになってしまいますかね。
重ね言葉が多いのは、東南アジアから太平洋地域の諸言語の特徴ですね。なんだか語族を超越した大きな基層言語のひろがりを感じます。
>指示代名詞は歯茎音が多く、否定詞は鼻音が多いという話もきいたことがあります。
すごい!知りませんでした。ちょっと調べてみましたが
ほんとにそうですね。びっくりです。
◆日本語
「それ」:so-(そ)
否定辞:nu(ぬ), nasi(なし), mazi(まじ)
◆漢語
「これ」:這zhe 之zhi 是shi 此ci 斯si
否定辞:不bu 没mei 莫mo<*mak 無wu<*mıua- 勿wu<*mıuət
◆満州語(ツングース諸語)
「それ」:tere
◆トルコ語
「それ」:šu
否定辞:-ma〜me
◆印欧語族
「それ」:*so, *sa, *tod
否定辞:non / ne / na
あと、これは自然なことですが、親族名称とくに「母親」「父親」をあらわす単語には「両唇音」でできているものが多いですね。たぶん、赤ちゃんが最初に発声できる音が「両唇音」で
最初に認知する対象が「母親」そして「父親」だからだと思われます。
◆漢語
ma-ma / 母mu<mo<*ma
ba-ba, die-die / 父fu<po<*pa
◆ニブフ(ギリヤーク)語
母:əmk
父:ətk
◆朝鮮語
母:omoni
父:aboji
◆満州語(ツングース諸語)
母:eme
父:ama
◆チュルク語
母:anne
父:ata
◆印欧語族
母:*mot-er
父:*pət-er
(幼児語 mama, papa)
◆アラビア語(セム語族)
母:ummu
父:abu
◆インドネシア語(オーストロネシア語族)
母:ibu
父:bapak
基本語彙を決定するさいに、こういうのをふまえながら考えるといいかもしれませんね。
>動詞句を省略
おもしろいですね。漢詩・漢文でもレトリックで似たようなことがあります。上のインドネシア語の例は対句みたいですね。
死郎さま
mixicのほうに包括/除外の2タイプの1人称複数をとりいれても面白いかとおもいますが、あまり普遍的な特徴ではないし、ちょっと奇をてらった感じになってしまいますかね。
重ね言葉が多いのは、東南アジアから太平洋地域の諸言語の特徴ですね。なんだか語族を超越した大きな基層言語のひろがりを感じます。
指示代名詞に少し追加します。
♪ゲルマン系
da, das, the, that
♪ラテン系
le, la, ce
歯茎音が多い理由は、舌を使って方向を示そうとするときに、たまたま出る音が歯茎音だから、という説を聞いたことがあります。いつも出典不明で申し訳ありません。不真面目な学生なので、ノートをきちんと残していません。。。
疑問詞に、口蓋音は多いのでしょうか。多くの例はわからないのですが、少し挙げてみます。
♪日本語 か [ka]
♪朝鮮語 까 [ʔka]
♪中国語 何 [hə] (もと[kə])
♪英語 who[hu] (もとquo[kwo])
♪フランス語 cuand[kuã]
♪イタリア語 cuanto
♪ゲルマン系
da, das, the, that
♪ラテン系
le, la, ce
歯茎音が多い理由は、舌を使って方向を示そうとするときに、たまたま出る音が歯茎音だから、という説を聞いたことがあります。いつも出典不明で申し訳ありません。不真面目な学生なので、ノートをきちんと残していません。。。
疑問詞に、口蓋音は多いのでしょうか。多くの例はわからないのですが、少し挙げてみます。
♪日本語 か [ka]
♪朝鮮語 까 [ʔka]
♪中国語 何 [hə] (もと[kə])
♪英語 who[hu] (もとquo[kwo])
♪フランス語 cuand[kuã]
♪イタリア語 cuanto
●親族名詞
> あと、これは自然なことですが、親族名称とくに「母親」「父親」をあらわす単語には「両唇音」でできているものが多いですね。たぶん、赤ちゃんが最初に発声できる音が「両唇音」で
> 最初に認知する対象が「母親」そして「父親」だからだと思われます。
日本語の場合は『父』『母』ですけど、/haha/については/p/→/f/→/h/という歴史的音韻変化を考えると、上古には/papa/だったとされていますね。
一方で/mama/は飯を意味します。赤ん坊が最初に発するマーマーマー……の音声を、日本では食事(=母乳)のこと、漢語や印欧語などでは母親のことと解したのでしょう。
●人称代名詞
> mixicのほうに包括/除外の2タイプの1人称複数をとりいれても面白いかとおもいますが、あまり普遍的な特徴ではないし、ちょっと奇をてらった感じになってしまいますかね。
おっと、それは残念。個人的にはさほど奇抜とも思わなかったのですが。
まあ、これについては留保ということで諒解です。
●重ね言葉
中国語の場合は基本的に一音節の繰り返しですけど、日本語やマレー語等では二音節以上が主で、語そのものが長くなりがちですね。
ただしこの冗長性が一概に不利かというと、一方では聞き取り易くなる利点もあります。また副次的に、発話に特有のリズムも加えることになります(これの好悪は美的、つまり主観的なものでしょうけれど)。
●指示代名詞『それ』
以下、疑問詞も含めてわかる範囲で追加。
サンスクリット tad (idam)
ヒンディー ye/wo
タミル語 idu/adu
マレー語 ini/itu
●疑問詞『何』
サンスクリット kim-
ヒンディー kyaa
タミル語 edu
マレー語 apa
> あと、これは自然なことですが、親族名称とくに「母親」「父親」をあらわす単語には「両唇音」でできているものが多いですね。たぶん、赤ちゃんが最初に発声できる音が「両唇音」で
> 最初に認知する対象が「母親」そして「父親」だからだと思われます。
日本語の場合は『父』『母』ですけど、/haha/については/p/→/f/→/h/という歴史的音韻変化を考えると、上古には/papa/だったとされていますね。
一方で/mama/は飯を意味します。赤ん坊が最初に発するマーマーマー……の音声を、日本では食事(=母乳)のこと、漢語や印欧語などでは母親のことと解したのでしょう。
●人称代名詞
> mixicのほうに包括/除外の2タイプの1人称複数をとりいれても面白いかとおもいますが、あまり普遍的な特徴ではないし、ちょっと奇をてらった感じになってしまいますかね。
おっと、それは残念。個人的にはさほど奇抜とも思わなかったのですが。
まあ、これについては留保ということで諒解です。
●重ね言葉
中国語の場合は基本的に一音節の繰り返しですけど、日本語やマレー語等では二音節以上が主で、語そのものが長くなりがちですね。
ただしこの冗長性が一概に不利かというと、一方では聞き取り易くなる利点もあります。また副次的に、発話に特有のリズムも加えることになります(これの好悪は美的、つまり主観的なものでしょうけれど)。
●指示代名詞『それ』
以下、疑問詞も含めてわかる範囲で追加。
サンスクリット tad (idam)
ヒンディー ye/wo
タミル語 idu/adu
マレー語 ini/itu
●疑問詞『何』
サンスクリット kim-
ヒンディー kyaa
タミル語 edu
マレー語 apa
>チーズケーキさま
>歯茎音が多い理由は、舌を使って方向を示そうとするときに、たまたま出る音が歯茎音だから、という説を聞いたことがあります。
なるほど、おもしろいですね〜。
◆疑問詞
口蓋音は多いみたいですね。
あと、鼻音もありますね。
◇日本語
「なに」:nani
◇漢語
「なんぞ」: 奈nai<*nad, nar
「いづくんぞ」:寧ning<*neng
「なに」: 那na
◇トルコ語
「なに」:ne
◇アラビア語
「なに」:ma
「だれ」man
ちょっと例が少なすぎたでしょうか。口蓋音、声門摩擦音、鼻音が多いのは、わからないことがあるとき「ハア?」とか「ウーム」と言ってしまうからなのでしょうか・・・。
>死郎さま
なるほど、「おまんま=飯」ですね。言語の発生過程を垣間見るようでおもしろい事例です。
◆包括/除外の2タイプの1人称複数
あ、いえ、奇をてらったとは主観的な感想でしたね。この特徴をもった言語をあまり知らないのでそう思ったしだいです。mixicにもし取り入れたら、正文法のレベルでは存在しても、やがて両者を区別しない話者も出てきたり、同じ意味になったり、どちらかが使われなくなったりしていくと思われます。
英語の2人称複数の主格yeと目的格youに起こった事態みたいなものでしょうか。
正文法に取り入れてみて、実際に使うかどうかは話者しだいというのが良いのかも、と思います。
ところで人称代名詞に関して思うところですが、mixicの3人称には男女(または中性)という文法上の性の区別は必ずしも必要ではないと考えています。あ、これはトピ違いだったでしょうか。
>歯茎音が多い理由は、舌を使って方向を示そうとするときに、たまたま出る音が歯茎音だから、という説を聞いたことがあります。
なるほど、おもしろいですね〜。
◆疑問詞
口蓋音は多いみたいですね。
あと、鼻音もありますね。
◇日本語
「なに」:nani
◇漢語
「なんぞ」: 奈nai<*nad, nar
「いづくんぞ」:寧ning<*neng
「なに」: 那na
◇トルコ語
「なに」:ne
◇アラビア語
「なに」:ma
「だれ」man
ちょっと例が少なすぎたでしょうか。口蓋音、声門摩擦音、鼻音が多いのは、わからないことがあるとき「ハア?」とか「ウーム」と言ってしまうからなのでしょうか・・・。
>死郎さま
なるほど、「おまんま=飯」ですね。言語の発生過程を垣間見るようでおもしろい事例です。
◆包括/除外の2タイプの1人称複数
あ、いえ、奇をてらったとは主観的な感想でしたね。この特徴をもった言語をあまり知らないのでそう思ったしだいです。mixicにもし取り入れたら、正文法のレベルでは存在しても、やがて両者を区別しない話者も出てきたり、同じ意味になったり、どちらかが使われなくなったりしていくと思われます。
英語の2人称複数の主格yeと目的格youに起こった事態みたいなものでしょうか。
正文法に取り入れてみて、実際に使うかどうかは話者しだいというのが良いのかも、と思います。
ところで人称代名詞に関して思うところですが、mixicの3人称には男女(または中性)という文法上の性の区別は必ずしも必要ではないと考えています。あ、これはトピ違いだったでしょうか。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=5845972&comment_count=4&comm_id=278775
ここから、引用。機械翻訳の前処理の話題です。
>2:
>私は、ロシア語を英語経由で翻訳かけているのですが、
>英語経由はダメみたいです、
>間に入れるのは、もっと複雑な言語じゃないとダメみたいですね、
>途中で意味が簡略化されてしまいます、。
>3:
>言われてみればそうですね。
>英語の文法は他の言語に比べ"削ぎ落とされてる"ところが
>ありますからね。
僕はmixicを自動処理でも使いたいものですから、明瞭な言語になって欲しい一方で、簡略化が進んだ言語にはなってほしくないです。詰め込める情報は多いほど良く、取り出せる情報も多いほど良く、詰め込みと取り出しの手間は少ないほど良いと思います。
ここから、引用。機械翻訳の前処理の話題です。
>2:
>私は、ロシア語を英語経由で翻訳かけているのですが、
>英語経由はダメみたいです、
>間に入れるのは、もっと複雑な言語じゃないとダメみたいですね、
>途中で意味が簡略化されてしまいます、。
>3:
>言われてみればそうですね。
>英語の文法は他の言語に比べ"削ぎ落とされてる"ところが
>ありますからね。
僕はmixicを自動処理でも使いたいものですから、明瞭な言語になって欲しい一方で、簡略化が進んだ言語にはなってほしくないです。詰め込める情報は多いほど良く、取り出せる情報も多いほど良く、詰め込みと取り出しの手間は少ないほど良いと思います。
性は人間や動物では重要ですが、それ以外ではほとんど役割がないと思いますので、皆さんおっしゃっているように、なくても問題ないと思います。
数は重要なことが多々ありますね。
名詞や動詞の指示関係はどうでしょうか。実は数と性は、指示関係を特定するのに重要だったりします。例えば英語では、同じ綴りで主語と動詞と目的語の位置に来るような単語がざらにありますが、だいたい、動詞語尾か名詞語尾で区別できます。英語の有名な例文ですが、
Fruit flies like a banana.
1.(fruit flies)subj (like)verb (a banana).
2.(fruit)subj (flies)verb (like a banana)aux.
こんな二通りの文構造が提案できたりします。性と人称で、動詞語尾がもう少し細かく変化すると、こんな基本的な解釈のズレは生じないと思うのですが。
setとかstateみたいな、動詞・名詞同形の単語が来たりすると、思考が中断されて大変な思いをします。
生成文法のツリーや括弧書きを、カジュアルな形で記述するように、格助詞や接続詞を整備するといいんじゃないかと直感的に思ったりします。検証してみないとわからないですけど。
数は重要なことが多々ありますね。
名詞や動詞の指示関係はどうでしょうか。実は数と性は、指示関係を特定するのに重要だったりします。例えば英語では、同じ綴りで主語と動詞と目的語の位置に来るような単語がざらにありますが、だいたい、動詞語尾か名詞語尾で区別できます。英語の有名な例文ですが、
Fruit flies like a banana.
1.(fruit flies)subj (like)verb (a banana).
2.(fruit)subj (flies)verb (like a banana)aux.
こんな二通りの文構造が提案できたりします。性と人称で、動詞語尾がもう少し細かく変化すると、こんな基本的な解釈のズレは生じないと思うのですが。
setとかstateみたいな、動詞・名詞同形の単語が来たりすると、思考が中断されて大変な思いをします。
生成文法のツリーや括弧書きを、カジュアルな形で記述するように、格助詞や接続詞を整備するといいんじゃないかと直感的に思ったりします。検証してみないとわからないですけど。
チーズケーキさまの視点はいつも勉強になります。
>だいたい、動詞語尾か名詞語尾で区別できます。
>性と人称で、動詞語尾がもう少し細かく変化すると、こんな基本的な解釈のズレは生じないと思うのですが。
英語でも、例文のようにあるていど区別できるなら、
ドイツ語ならさらに、ラテン語ならさらにさらに正確に
区別できることになりますね。
トルコ語のような膠着語でも、人称語尾や格語尾がきっちり
そろっているので、どれが名詞でどれが動詞だかすぐに
判別できます。
エスペラントの使いやすさは、このへんをきちんと
創り上げているからでしょうか。
>生成文法
昔、言語学の授業で習ったのですけど、
理解できませんでした…orz
>だいたい、動詞語尾か名詞語尾で区別できます。
>性と人称で、動詞語尾がもう少し細かく変化すると、こんな基本的な解釈のズレは生じないと思うのですが。
英語でも、例文のようにあるていど区別できるなら、
ドイツ語ならさらに、ラテン語ならさらにさらに正確に
区別できることになりますね。
トルコ語のような膠着語でも、人称語尾や格語尾がきっちり
そろっているので、どれが名詞でどれが動詞だかすぐに
判別できます。
エスペラントの使いやすさは、このへんをきちんと
創り上げているからでしょうか。
>生成文法
昔、言語学の授業で習ったのですけど、
理解できませんでした…orz
そうですねえ。品詞の区別がつかないというのは、英語が極めて孤立語に近くなっていることに原因があるのでしょう。同じ問題が中国語などにも、さらに顕著だったりしますし。
それよりも性・数・格を揃えるというのは、単語同士の修飾関係をはっきりさせるほうに大きな役割を担っているように理解しておりますが。例えば『大きな家の扉を叩く』という日本語の文では、“大きい”のは『家』なのか『扉』なのかが曖昧ですよね。
このへん斯波榴火さまも仰っているように、ラテン語(や古典ギリシア語・サンスクリット)等だとかなり厳密に規定されています――と言っても実のところラテン語は良く存じませんけれど。
●生成文法
こちらは僕も詳しくないのですが、たしかに性や数の一致以外の形で文構造を明確にできるなら、検討する価値がありそうに思います。
それよりも性・数・格を揃えるというのは、単語同士の修飾関係をはっきりさせるほうに大きな役割を担っているように理解しておりますが。例えば『大きな家の扉を叩く』という日本語の文では、“大きい”のは『家』なのか『扉』なのかが曖昧ですよね。
このへん斯波榴火さまも仰っているように、ラテン語(や古典ギリシア語・サンスクリット)等だとかなり厳密に規定されています――と言っても実のところラテン語は良く存じませんけれど。
●生成文法
こちらは僕も詳しくないのですが、たしかに性や数の一致以外の形で文構造を明確にできるなら、検討する価値がありそうに思います。
生成文法は、単語の修飾関係を明確に表示する例として、思いついたものです。ツリー構造か括弧構造です。
http://www.kufs.ac.jp/English/faculty/ono/hp-ono4.htm
>それよりも性・数・格を揃えるというのは、単語同士の修飾関係
>をはっきりさせるほうに大きな役割を担っているように理解して
>おりますが。
そうですね、おっしゃる通りです。
動詞と名詞の区別は副次的なものですね。
>例えば『大きな家の扉を叩く』という日本語の文では、
>“大きい”のは『家』なのか『扉』なのかが曖昧ですよね。
いま気の赴くままに、括弧を使って書くと
1.私が 叩く 扉を(大きな)-家の
2.私が 叩く 扉を-家の(大きな)
という感じで、品詞の区別はもとより、修飾関係が効果的に表示できるといいと思います。
「私は赤い花と紙をあげた」
1.私は({赤い}(花と紙))をあげた
2.私は({赤い}花)と(紙)をあげた
「私は小さな赤い花と紙をあげた」
1.私は({小さな}({赤い}(花と紙)))をあげた
2.私は({小さな}{赤い}(花))と(紙)をあげた
3.私は{小さな}(({赤い}花)と紙)をあげた
この辺が効果的に表示できないでしょうか。括弧だと、わけわからなくなります。ツリーだと、場所をとります。語尾だと、男女中の3種類が重複する組み合わせでは、曖昧さの回避はできません。これはどの言語にもあるジレンマなのでしょうか。
http://www.kufs.ac.jp/English/faculty/ono/hp-ono4.htm
>それよりも性・数・格を揃えるというのは、単語同士の修飾関係
>をはっきりさせるほうに大きな役割を担っているように理解して
>おりますが。
そうですね、おっしゃる通りです。
動詞と名詞の区別は副次的なものですね。
>例えば『大きな家の扉を叩く』という日本語の文では、
>“大きい”のは『家』なのか『扉』なのかが曖昧ですよね。
いま気の赴くままに、括弧を使って書くと
1.私が 叩く 扉を(大きな)-家の
2.私が 叩く 扉を-家の(大きな)
という感じで、品詞の区別はもとより、修飾関係が効果的に表示できるといいと思います。
「私は赤い花と紙をあげた」
1.私は({赤い}(花と紙))をあげた
2.私は({赤い}花)と(紙)をあげた
「私は小さな赤い花と紙をあげた」
1.私は({小さな}({赤い}(花と紙)))をあげた
2.私は({小さな}{赤い}(花))と(紙)をあげた
3.私は{小さな}(({赤い}花)と紙)をあげた
この辺が効果的に表示できないでしょうか。括弧だと、わけわからなくなります。ツリーだと、場所をとります。語尾だと、男女中の3種類が重複する組み合わせでは、曖昧さの回避はできません。これはどの言語にもあるジレンマなのでしょうか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
mixi発・人工言語を作ろう 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
mixi発・人工言語を作ろうのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31948人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37152人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82528人