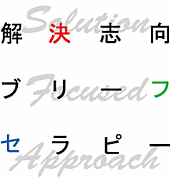|
|
|
|
コメント(30)
さて、長谷川先生は、何を盲点と考えているのか?
興味のあるところです。
学習のために予想するというのはどうでしょうか?
長所は短所であり、得意技は裏技に破られることがあります。
心理学では「自己認識」が大切であると言われます。
さて、予想その
一、「原因」は問わないとするが、如何なものか。
問うてもよい場合があるのではないか。
二、アセスメントにもっと時間をかけてもよいのではないか。
共感的な傾聴が十分できて質問がなされているだろうか。
三、問題は「関係」から生まれるが、解決のために「関係の範囲」をどこまで広げるか、あるいは広げることができるのか。
また、解決のためにクライアントの内面に入ることがあってもよいのではないか。
ハズレたら赤恥かくな〜
興味のあるところです。
学習のために予想するというのはどうでしょうか?
長所は短所であり、得意技は裏技に破られることがあります。
心理学では「自己認識」が大切であると言われます。
さて、予想その
一、「原因」は問わないとするが、如何なものか。
問うてもよい場合があるのではないか。
二、アセスメントにもっと時間をかけてもよいのではないか。
共感的な傾聴が十分できて質問がなされているだろうか。
三、問題は「関係」から生まれるが、解決のために「関係の範囲」をどこまで広げるか、あるいは広げることができるのか。
また、解決のためにクライアントの内面に入ることがあってもよいのではないか。
ハズレたら赤恥かくな〜
「自分の頭のなかでソリューションフォーカスする。一対一で対話している相手とソリューションフォーカスする。会議などで集まったときに当事者全員でソリューションフォーカスする。YES(可能性)のほうにスイッチが入ったマインドどうしがコミュニケーションを交わし、ソリューションフォーカスすることで、実現できることが飛躍的に増えることは間違いありません。」(「解決志向の実践マネジメント」
外部コミュニケーションと内部コミュニケーションの相互作用を見事に表現していますね!
クライアントさんが良くなって帰る時期に、日常生活で役立つソリューションフォーカスについて簡単な説明をサービスするとクライアントさんにとっては有り難く、再発予防にもなるのではないでしょうか。
おそらく似たような事を考えたソリューショントークのNPOがありますが、予防は人気がなさそうです。
外部コミュニケーションと内部コミュニケーションの相互作用を見事に表現していますね!
クライアントさんが良くなって帰る時期に、日常生活で役立つソリューションフォーカスについて簡単な説明をサービスするとクライアントさんにとっては有り難く、再発予防にもなるのではないでしょうか。
おそらく似たような事を考えたソリューショントークのNPOがありますが、予防は人気がなさそうです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
解決志向ブリーフセラピー 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-