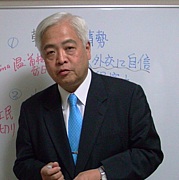国家が、国家として成立する為には、先ず何よりもその構成員である国民を結び付ける精神的な紐帯(じゅうたい)が必要である。
言い換えれば、精神共同体としての国家が成立していなければ、現実における法律制度としての国家は機能する事が出来ない。
しかし、精神共同体としての国家と、官僚制度としての国家は、永遠に一致する事がない矛盾した存在である。
精神共同体としての国家を「聖なる次元における国家」と呼ぶ事が出来る。
これに対して、官僚制度としての国家を「俗なる次元における国家」と呼ぶ事が出来る。
聖なる次元と俗なる次元の二つの次元の間における相互依存と相互対立の2つの側面から、我々の国家像を点検してみようと思う。
今回のテーマをよく理解すれば、国家と宗教の関係について、世界的な視野で考える事が出来るようになる。
国家と宗教が、完全に分離している場合は、世界においては寧ろ、例外的である。
聖なる次元、即ち、宗教を含む、精神的な次元の共同体なくして、現実における制度としての国家は成立しえないからである。
靖国神社問題や、政教分離問題の本質について、自分で考えられるようになる講義でもある。
言い換えれば、精神共同体としての国家が成立していなければ、現実における法律制度としての国家は機能する事が出来ない。
しかし、精神共同体としての国家と、官僚制度としての国家は、永遠に一致する事がない矛盾した存在である。
精神共同体としての国家を「聖なる次元における国家」と呼ぶ事が出来る。
これに対して、官僚制度としての国家を「俗なる次元における国家」と呼ぶ事が出来る。
聖なる次元と俗なる次元の二つの次元の間における相互依存と相互対立の2つの側面から、我々の国家像を点検してみようと思う。
今回のテーマをよく理解すれば、国家と宗教の関係について、世界的な視野で考える事が出来るようになる。
国家と宗教が、完全に分離している場合は、世界においては寧ろ、例外的である。
聖なる次元、即ち、宗教を含む、精神的な次元の共同体なくして、現実における制度としての国家は成立しえないからである。
靖国神社問題や、政教分離問題の本質について、自分で考えられるようになる講義でもある。
|
|
|
|
コメント(9)
1/8 【国民の為の政治学】第9講政治と文化と宗教の関係とは??[H22/4/9]
世界の多くの民主国家においては、国家と宗教は分かちがたく結びついています。デモクラシーを成立させる基盤である精神共同体。その精神共同体を支える重要な柱の1つが、国民に共通する宗教意識である。
イスラム教徒の多い国家の大部分は、イスラム教を国教(国家の宗教)と規定している。近代的デモクラシーの体制を取るスウェーデン・デンマーク・ノルウェー、そしてイギリスもキリスト教を国教としている。
ドイツでは、国家が教会税の徴収を代行して行っている。徴収された教会税は、国家の手を通してキリスト教会に分配される。日本では信じられないような国家と宗教の結びつきである。
アメリカでは、キリスト教と国家の関係は「友好的分離(Friendly Separation)」と呼ばれている。
アメリカがキリスト教精神に基づいて建国された事は、自明の理であるが、キリスト教のある特定の宗派が国の政治を支配しない為に、「国家と教会の分離」が定められている。しかしこれは敵対的な分離ではなく、「友好的な分離」と規定されているのである。
フランスやイタリアでは、国家(政治)と宗教の分離が最も厳しく定められている。
しかし、これは世界的には寧ろ、例外である。そして、フランスやイタリアにおいても、国民の大部分を占めるカトリック教徒の宗教意識が、国家共同体を形成する基盤となっている事実は否定する事が出来ない。
世界の多くの民主国家においては、国家と宗教は分かちがたく結びついています。デモクラシーを成立させる基盤である精神共同体。その精神共同体を支える重要な柱の1つが、国民に共通する宗教意識である。
イスラム教徒の多い国家の大部分は、イスラム教を国教(国家の宗教)と規定している。近代的デモクラシーの体制を取るスウェーデン・デンマーク・ノルウェー、そしてイギリスもキリスト教を国教としている。
ドイツでは、国家が教会税の徴収を代行して行っている。徴収された教会税は、国家の手を通してキリスト教会に分配される。日本では信じられないような国家と宗教の結びつきである。
アメリカでは、キリスト教と国家の関係は「友好的分離(Friendly Separation)」と呼ばれている。
アメリカがキリスト教精神に基づいて建国された事は、自明の理であるが、キリスト教のある特定の宗派が国の政治を支配しない為に、「国家と教会の分離」が定められている。しかしこれは敵対的な分離ではなく、「友好的な分離」と規定されているのである。
フランスやイタリアでは、国家(政治)と宗教の分離が最も厳しく定められている。
しかし、これは世界的には寧ろ、例外である。そして、フランスやイタリアにおいても、国民の大部分を占めるカトリック教徒の宗教意識が、国家共同体を形成する基盤となっている事実は否定する事が出来ない。
2/8 【国民の為の政治学】第9講政治と文化と宗教の関係とは??[H22/4/9]
民主国家においては、多数決により政治が決定される。それでは、多数決により敗北した少数者の側が、何故、自らの意思を屈してまで、多数者の決定に従うのであろうか。それは、国家が運命共同体であり、多数決は、この運命共同体の意志を決定する方法に過ぎないからである。
運命共同体であるとは、国家が何よりもまず精神の共同体として、成立している事を意味する。
この精神共同体の成立においては、当然、国民の共通の文化が大きな役割を果たしている。この文化の中において、有形・無形の宗教的意識が大きな役割を果たしている。多くの民主国家においては、国民共通の宗教意識が、国家と言う精神共同体を支える大きな要素になっている。
民主国家においては、多数決により政治が決定される。それでは、多数決により敗北した少数者の側が、何故、自らの意思を屈してまで、多数者の決定に従うのであろうか。それは、国家が運命共同体であり、多数決は、この運命共同体の意志を決定する方法に過ぎないからである。
運命共同体であるとは、国家が何よりもまず精神の共同体として、成立している事を意味する。
この精神共同体の成立においては、当然、国民の共通の文化が大きな役割を果たしている。この文化の中において、有形・無形の宗教的意識が大きな役割を果たしている。多くの民主国家においては、国民共通の宗教意識が、国家と言う精神共同体を支える大きな要素になっている。
3/8 【国民の為の政治学】第9講政治と文化と宗教の関係とは??[H22/4/9]
国家には、2つの次元がある。
第一は、精神の次元における精神共同体としての国家である。
第二は、現実の次元における官僚機構としての国家である。
この二つは相互に依存して存在しているが、究極的には決して、完全に一致する事がない。それはまた、二つの次元の異なった国家像という事も出来るであろう。
日本においては、精神共同体としての国家は、天皇を中心とする民族の共同体としての国家である。これに対して、現実においては、官僚機構としての国家は、古代から封建時代、そして現代へと様々な形態を取って変化してきた。
しかし、この官僚機構としての国家も、その正統性の根源を天皇と言う精神共同体の権威から引き出している点においては、全く一貫している。
日本では、官僚機構としての国家を天皇の名のもとに変革する行為を維新と呼んでいる。
国家には、2つの次元がある。
第一は、精神の次元における精神共同体としての国家である。
第二は、現実の次元における官僚機構としての国家である。
この二つは相互に依存して存在しているが、究極的には決して、完全に一致する事がない。それはまた、二つの次元の異なった国家像という事も出来るであろう。
日本においては、精神共同体としての国家は、天皇を中心とする民族の共同体としての国家である。これに対して、現実においては、官僚機構としての国家は、古代から封建時代、そして現代へと様々な形態を取って変化してきた。
しかし、この官僚機構としての国家も、その正統性の根源を天皇と言う精神共同体の権威から引き出している点においては、全く一貫している。
日本では、官僚機構としての国家を天皇の名のもとに変革する行為を維新と呼んでいる。
5/8 【国民の為の政治学】第9講政治と文化と宗教の関係とは??[H22/4/9]
聖なる次元における国家を「徳の共同体(Community of Virtue)」ととらえる事が出来る。これに対して俗なる次元における国家を「制度化された暴力(Institutionalized Violence)」と捉える事が出来る。
聖なる次元における国家と、俗なる次元における国家が一致する事は永久にあり得ない。聖なる次元における国家を理想として、俗なる次元における国家を革新してゆく事が、あらゆる国家における改革・進歩・革命の道である。
聖なる次元をもたない国家においては、例えばシナのように、俗なる次元における権力闘争が永久に続くだけである。
俗なる次元における国家を、聖なる次元に近付ける事を、日本の政治においては、「維新」と呼んでいる。
維新とはまた、天皇のもとにおける国民の平等を推進する事でもある。
聖なる次元における国家を「徳の共同体(Community of Virtue)」ととらえる事が出来る。これに対して俗なる次元における国家を「制度化された暴力(Institutionalized Violence)」と捉える事が出来る。
聖なる次元における国家と、俗なる次元における国家が一致する事は永久にあり得ない。聖なる次元における国家を理想として、俗なる次元における国家を革新してゆく事が、あらゆる国家における改革・進歩・革命の道である。
聖なる次元をもたない国家においては、例えばシナのように、俗なる次元における権力闘争が永久に続くだけである。
俗なる次元における国家を、聖なる次元に近付ける事を、日本の政治においては、「維新」と呼んでいる。
維新とはまた、天皇のもとにおける国民の平等を推進する事でもある。
6/8 【国民の為の政治学】第9講政治と文化と宗教の関係とは??[H22/4/9]
日本においては、正統性の根源である天皇制との整合性があれば、様々な政治思想や政治体制・経済体制を採用する事が出来る。現在の日本は、天皇制民主政治であり、経済体制は天皇制資本主義である。
原理的に言うならば、唯物論的でない国家社会主義を天皇制と組合わせる事も理論的には可能である。
かつての226事件の指導者達が夢想したのは、一種の天皇制国家社会主義であった。この場合の社会主義とは勿論、唯物論的なマルクス主義的な社会主義ではなく、単に経済上の社会的平等を推進するという意味における社会主義である。
日本においては、正統性の根源である天皇制との整合性があれば、様々な政治思想や政治体制・経済体制を採用する事が出来る。現在の日本は、天皇制民主政治であり、経済体制は天皇制資本主義である。
原理的に言うならば、唯物論的でない国家社会主義を天皇制と組合わせる事も理論的には可能である。
かつての226事件の指導者達が夢想したのは、一種の天皇制国家社会主義であった。この場合の社会主義とは勿論、唯物論的なマルクス主義的な社会主義ではなく、単に経済上の社会的平等を推進するという意味における社会主義である。
7/8 【国民の為の政治学】第9講政治と文化と宗教の関係とは??[H22/4/9]
今までの、講義内容がよく理解できると、日本に何故、愛国的な左翼が存在しないか、の理由もよくわかる事になる。
左翼は、マルクス主義者もそうでない者も、単純な進歩史観を有しており、この進歩史観においては、君主制は古い制度であり、社会の進歩とともに否定されるべき存在である。
ところが、日本においては、明治維新という近代化の原点において、彼らの言う「古代的王権」である天皇が、国家の最高権力者として復活し、この天皇の正統性のもとで、日本は近代化を推進していった。
これは、進歩主義史観をとるものにとっては、受け入れがたい矛盾である。
また、大東亜戦争敗戦後の日本でも、天皇の権威は全く揺らぐ事が無かった。国民は圧倒的に敗戦後の陛下の全国御巡幸を歓迎した。
これも進歩主義者にとっては、全く理解を絶するところである。
敗戦した国家の君主制は、廃止されるのが当然である、と進歩主義者は考える。ましてマルクス主義者は、敗戦後には、君主制は革命によって打倒されて当然である、と考える。しかし、日本国においては、このような変化は全くおきなかった。
明治維新以来の歴史を見るだけでも、日本人は政治的にも経済的にも社会的にも、天皇の権威のもとで、超一流の近代国家を築くことに成功して来た。これは、マルクス主義者を含む、進歩主義者(左翼)の教条(ドグマ)に全く相反する歴史上の事実である。
ここで左翼が事実を事実として受け入れれば、まともな歴史観に転向し、左翼を放棄する事になる。
事実を受け入れるのを拒絶し、ドグマを保持しようとすれば、結局、総体としての日本歴史、特に明治維新以降の近代史を完全に否定するしかなくなってしまうのである。
それ故に、日本においては左翼の愛国者は、存在しえない事になる。
今までの、講義内容がよく理解できると、日本に何故、愛国的な左翼が存在しないか、の理由もよくわかる事になる。
左翼は、マルクス主義者もそうでない者も、単純な進歩史観を有しており、この進歩史観においては、君主制は古い制度であり、社会の進歩とともに否定されるべき存在である。
ところが、日本においては、明治維新という近代化の原点において、彼らの言う「古代的王権」である天皇が、国家の最高権力者として復活し、この天皇の正統性のもとで、日本は近代化を推進していった。
これは、進歩主義史観をとるものにとっては、受け入れがたい矛盾である。
また、大東亜戦争敗戦後の日本でも、天皇の権威は全く揺らぐ事が無かった。国民は圧倒的に敗戦後の陛下の全国御巡幸を歓迎した。
これも進歩主義者にとっては、全く理解を絶するところである。
敗戦した国家の君主制は、廃止されるのが当然である、と進歩主義者は考える。ましてマルクス主義者は、敗戦後には、君主制は革命によって打倒されて当然である、と考える。しかし、日本国においては、このような変化は全くおきなかった。
明治維新以来の歴史を見るだけでも、日本人は政治的にも経済的にも社会的にも、天皇の権威のもとで、超一流の近代国家を築くことに成功して来た。これは、マルクス主義者を含む、進歩主義者(左翼)の教条(ドグマ)に全く相反する歴史上の事実である。
ここで左翼が事実を事実として受け入れれば、まともな歴史観に転向し、左翼を放棄する事になる。
事実を受け入れるのを拒絶し、ドグマを保持しようとすれば、結局、総体としての日本歴史、特に明治維新以降の近代史を完全に否定するしかなくなってしまうのである。
それ故に、日本においては左翼の愛国者は、存在しえない事になる。
8/8 【国民の為の政治学】第9講政治と文化と宗教の関係とは??[H22/4/9]
日本の「左翼(進歩主義者・平等主義者)」の教条(ドグマ)となっているのが、1932年に共産主義インターナショナル(第三インター)が発した「32年テーゼ」である。この共産主義者による闘争戦略の指示においては、日本は「前近代=半封建」と規定されている。その前近代半封建の中心が言うまでもなく、天皇である。
それ以来、日本の左翼による日本批判は、この「前近代=半封建」という一語に尽きている、と言っても良い。
戦後においても、左翼の日本批判の中心は、この「前近代=半封建」という言葉の同義語反復であり、その批判の中心は天皇制である。
東京裁判史観も、この「32年テーゼ」の焼き直しと考える事が出来る。
日本の左翼に求められるのは、ドグマとイデオロギーを捨てて、日本歴史の事実をありのままに見る勇気である。この勇気を持てば、所謂「左翼」は愛国的左翼に変身する事ができる。
そして「愛国的左翼」とは、「日本文化の中心としての天皇を受け入れた左翼」という存在である。
日本の「左翼(進歩主義者・平等主義者)」の教条(ドグマ)となっているのが、1932年に共産主義インターナショナル(第三インター)が発した「32年テーゼ」である。この共産主義者による闘争戦略の指示においては、日本は「前近代=半封建」と規定されている。その前近代半封建の中心が言うまでもなく、天皇である。
それ以来、日本の左翼による日本批判は、この「前近代=半封建」という一語に尽きている、と言っても良い。
戦後においても、左翼の日本批判の中心は、この「前近代=半封建」という言葉の同義語反復であり、その批判の中心は天皇制である。
東京裁判史観も、この「32年テーゼ」の焼き直しと考える事が出来る。
日本の左翼に求められるのは、ドグマとイデオロギーを捨てて、日本歴史の事実をありのままに見る勇気である。この勇気を持てば、所謂「左翼」は愛国的左翼に変身する事ができる。
そして「愛国的左翼」とは、「日本文化の中心としての天皇を受け入れた左翼」という存在である。
国民の為の政治学・第9講「政治と文化と宗教の関係とは?」特別補足篇
YouTubeは、http://www.youtube.com/watch?v=S6eV0OO5psc
民主国家においても、共通の宗教意識が国家を支える基盤である事が多い。
この事を最もよく物語っているのは、民主政治を称賛した事で有名な二つの歴史的演説、即ちリンカーンによるゲティスバーグ演説と古代アテネのペリクレスによる演説が、共に国家の為に命を捧げた人々に対する、追悼と顕彰の場で語られた言葉であったという事実である。
民主国家の為に命を捧げた英霊の追悼と顕彰は、当然、国家に共通の宗教意識に基いて行われる。この宗教意識こそが国家共同体の基礎となり、その基礎の上に、自らの死をも辞さぬ国民の、国家防衛への行動が存在する。これら二つの歴史的名演説において、民主国家の場合においても、国民共通の宗教意識が、国家の防衛と永続の為に如何に重要な役割を果たしているかが如実に示されている。
フランスのように、国家と宗教意識が比較的明快に分離されている場合においても、国家への自己犠牲は、一種、宗教的な色合いを帯びてくる事になる。
個人の生命を越え、永続する国家への忠誠は、自己を超えた歴史的運命共同体への信仰に近いものであり、超越的な存在への服従という点において、これを宗教的と呼ぶ事は誤りではないであろう。
YouTubeは、http://www.youtube.com/watch?v=S6eV0OO5psc
民主国家においても、共通の宗教意識が国家を支える基盤である事が多い。
この事を最もよく物語っているのは、民主政治を称賛した事で有名な二つの歴史的演説、即ちリンカーンによるゲティスバーグ演説と古代アテネのペリクレスによる演説が、共に国家の為に命を捧げた人々に対する、追悼と顕彰の場で語られた言葉であったという事実である。
民主国家の為に命を捧げた英霊の追悼と顕彰は、当然、国家に共通の宗教意識に基いて行われる。この宗教意識こそが国家共同体の基礎となり、その基礎の上に、自らの死をも辞さぬ国民の、国家防衛への行動が存在する。これら二つの歴史的名演説において、民主国家の場合においても、国民共通の宗教意識が、国家の防衛と永続の為に如何に重要な役割を果たしているかが如実に示されている。
フランスのように、国家と宗教意識が比較的明快に分離されている場合においても、国家への自己犠牲は、一種、宗教的な色合いを帯びてくる事になる。
個人の生命を越え、永続する国家への忠誠は、自己を超えた歴史的運命共同体への信仰に近いものであり、超越的な存在への服従という点において、これを宗教的と呼ぶ事は誤りではないであろう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
藤井厳喜アカデミー 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
藤井厳喜アカデミーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170675人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90053人