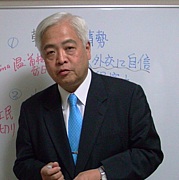さて、今回のテーマは、「革命は何故、どのように起きるのだろうか?」です。
今回は、革命という政治学の最もダイナミックなテーマを取り扱います。
通常、政治学の対象は、安定した国家内における政治現象ですが、革命というテーマを政治学が避けて通る事は出来ません。
革命に共通した現象は、既存の政治権力がその正統性を完全に失う事です。
正統性の喪失が先にあり、それが暴力行為を誘発すると考えられます。
しかし、革命が収束する時期においては、一度、失われた正統性は、必ずまた別の形で樹立されなければなりません。
そうでなければ国家は無政府状態のままに放置される事になるからです。
今回は、特に、マルクス主義的革命理論の不毛と日本的革命の論理という事について力をついてお話していますので、そこをよく学習して頂けると面白いと思います。
今回の授業をよく咀嚼してもらえれば、現在の民主党や社民党などが推し進めようとしている「家族解体法案」や子供手当の背後の思想が、ハッキリと見えてきます。
これらをシッカリと吸収し、いつでも地に足のついた、的確な理論武装や戦略立案が、自分の頭で自在に構築できるようになる事を願っています。
今回は、革命という政治学の最もダイナミックなテーマを取り扱います。
通常、政治学の対象は、安定した国家内における政治現象ですが、革命というテーマを政治学が避けて通る事は出来ません。
革命に共通した現象は、既存の政治権力がその正統性を完全に失う事です。
正統性の喪失が先にあり、それが暴力行為を誘発すると考えられます。
しかし、革命が収束する時期においては、一度、失われた正統性は、必ずまた別の形で樹立されなければなりません。
そうでなければ国家は無政府状態のままに放置される事になるからです。
今回は、特に、マルクス主義的革命理論の不毛と日本的革命の論理という事について力をついてお話していますので、そこをよく学習して頂けると面白いと思います。
今回の授業をよく咀嚼してもらえれば、現在の民主党や社民党などが推し進めようとしている「家族解体法案」や子供手当の背後の思想が、ハッキリと見えてきます。
これらをシッカリと吸収し、いつでも地に足のついた、的確な理論武装や戦略立案が、自分の頭で自在に構築できるようになる事を願っています。
|
|
|
|
コメント(8)
1/8 【国民の為の政治学】第8講革命は何故、起きるのだろうか??[H22/4/2]
革命とは、暴力的争乱を伴って、国家の体制が全く変わってしまう事を意味する。しかし、しばしば革命という言葉はこれよりも広い意味に用いられる事がある。
例えば、アメリカでは、独立戦争の事をアメリカン・レボリューションと呼んでいる。つまり、アメリカ革命である。また、1917年にロシアで起きた出来事は、首都とその周辺で起きた出来事だけに注目すれば、それは革命というよりは、クーデター(暴力による国家の転覆)と呼んだ方が正確であろう。しかし、その後、ソ連共産党が国家全体を革命的に変化させた事は歴史の事実である。
イギリスのピューリタン革命や、1789年のフランス革命や、明治維新は最も徹底的な革命の実例である。また、近年、我々はソ連邦の崩壊に伴って、ソ連のみならず、東ヨーロッパ諸国も共産主義独裁を否定して、自由な民主国家を打ち立てるという革命を目撃している。
ロシアや東ヨーロッパにおけるこれらの革命は、マルクス主義では全く説明できない出来事であり、共産主義独裁がいつかは必ず自由を求める民衆によって、打ち倒されるという良き実例となっている。
革命とは、暴力的争乱を伴って、国家の体制が全く変わってしまう事を意味する。しかし、しばしば革命という言葉はこれよりも広い意味に用いられる事がある。
例えば、アメリカでは、独立戦争の事をアメリカン・レボリューションと呼んでいる。つまり、アメリカ革命である。また、1917年にロシアで起きた出来事は、首都とその周辺で起きた出来事だけに注目すれば、それは革命というよりは、クーデター(暴力による国家の転覆)と呼んだ方が正確であろう。しかし、その後、ソ連共産党が国家全体を革命的に変化させた事は歴史の事実である。
イギリスのピューリタン革命や、1789年のフランス革命や、明治維新は最も徹底的な革命の実例である。また、近年、我々はソ連邦の崩壊に伴って、ソ連のみならず、東ヨーロッパ諸国も共産主義独裁を否定して、自由な民主国家を打ち立てるという革命を目撃している。
ロシアや東ヨーロッパにおけるこれらの革命は、マルクス主義では全く説明できない出来事であり、共産主義独裁がいつかは必ず自由を求める民衆によって、打ち倒されるという良き実例となっている。
2/8 【国民の為の政治学】第8講革命は何故、起きるのだろうか??[H22/4/2]
マルクス主義を含む、直線的な「進歩史観」では、フランス革命を非常に高く評価している。
これが日本の義務教育における歴史教育の基本線の1つになっている。ところが、フランス革命を詳しく検討してみると、それはフランス国民にとってのとんでもない悲劇であり、大災厄であり、とても称賛するような歴史的出来事ではなかった事が分かる。
フランス革命の直前には、啓蒙主義が全盛を極めた。啓蒙主義は、人間の理性に対する多大な信頼と、楽観主義をその神髄としている。理性に基く合理的な思考で、人間は社会のあらゆる問題を解決する事が出来る―という人間理性への傲慢なまでの信頼が、啓蒙主義時代を支配した。
それでは、啓蒙主義の思想的影響力のもとに起きたフランス革命が、理性的・合理的なものかと言えば、実情は全くその逆であった。人間の最も非合理的な、非理性的な側面が、社会を支配し、フランスは連続する流血の惨事に見舞われ、社会秩序は徹底的に混乱し、失われた。理性への過大な信仰が、結果として最も非理性的な現実を産出したのである。
フランス革命においては、超越的なキリスト教的神が否定される一方、抽象的な理性信仰が頂点を極め、これが一種のカルトとして一時的にしろフランス社会を支配した。
理性の信仰者が、理性信仰を拒絶するものを、徹底的に非理性的に虐殺し、弾圧するという、とんでもない逆説的な状況が現実となったのである。
絶対的に正しい信仰を手に入れた、と信ずる者は、これを受け入れない者を、徹底的に排除する。これが、ドグマ主義やファナティシズム(狂信熱狂)の繰り返されるパターンである。
フランス革命は、こういった人間の愚行と残虐の最もよき実例の宝庫である。
マルクス主義を含む、直線的な「進歩史観」では、フランス革命を非常に高く評価している。
これが日本の義務教育における歴史教育の基本線の1つになっている。ところが、フランス革命を詳しく検討してみると、それはフランス国民にとってのとんでもない悲劇であり、大災厄であり、とても称賛するような歴史的出来事ではなかった事が分かる。
フランス革命の直前には、啓蒙主義が全盛を極めた。啓蒙主義は、人間の理性に対する多大な信頼と、楽観主義をその神髄としている。理性に基く合理的な思考で、人間は社会のあらゆる問題を解決する事が出来る―という人間理性への傲慢なまでの信頼が、啓蒙主義時代を支配した。
それでは、啓蒙主義の思想的影響力のもとに起きたフランス革命が、理性的・合理的なものかと言えば、実情は全くその逆であった。人間の最も非合理的な、非理性的な側面が、社会を支配し、フランスは連続する流血の惨事に見舞われ、社会秩序は徹底的に混乱し、失われた。理性への過大な信仰が、結果として最も非理性的な現実を産出したのである。
フランス革命においては、超越的なキリスト教的神が否定される一方、抽象的な理性信仰が頂点を極め、これが一種のカルトとして一時的にしろフランス社会を支配した。
理性の信仰者が、理性信仰を拒絶するものを、徹底的に非理性的に虐殺し、弾圧するという、とんでもない逆説的な状況が現実となったのである。
絶対的に正しい信仰を手に入れた、と信ずる者は、これを受け入れない者を、徹底的に排除する。これが、ドグマ主義やファナティシズム(狂信熱狂)の繰り返されるパターンである。
フランス革命は、こういった人間の愚行と残虐の最もよき実例の宝庫である。
3/8 【国民の為の政治学】第8講革命は何故、起きるのだろうか??[H22/4/2]
フランス革命は、1789年から約10年間、フランスを徹底的な無秩序と混乱に陥れた後、1799年のナポレオンの独裁的権力の樹立をもって終結する。
ルイ王朝の絶対王政を破壊した革命は、より民主的な柔軟な政治体制を生む事は無く、新たな独裁政権の成立を持って終結したのである。
マルクス主義革命理論のキリスト教との類似性を指摘したのはイギリスの哲学者バートランド・ラッセルであった。彼は、ユダヤ教・キリスト教的な歴史観・終末観と、マルクス主義者が主張する革命理論の間には、極めて類似した論理構成がある事を見抜いていた。
マルクス主義の革命は、いくつかの国家において、現実となった。ここにおいても、マルクス主義革命が生み出したものは、独裁的硬直的な権力を打倒して後の、より民主的で柔軟な政治体制ではなく、新たな独裁体制であった。マルクス主義革命は、理論においても現実においても、新たな独裁権力(プロレタリアート独裁・共産党独裁)を生みだす為の革命である。
1991年のソ連邦崩壊に相前後して起きたロシアと東ヨーロッパの革命は、マルクス主義によって成立した独裁権力を打ち倒す、真の民主化革命であった。
フランス革命は、1789年から約10年間、フランスを徹底的な無秩序と混乱に陥れた後、1799年のナポレオンの独裁的権力の樹立をもって終結する。
ルイ王朝の絶対王政を破壊した革命は、より民主的な柔軟な政治体制を生む事は無く、新たな独裁政権の成立を持って終結したのである。
マルクス主義革命理論のキリスト教との類似性を指摘したのはイギリスの哲学者バートランド・ラッセルであった。彼は、ユダヤ教・キリスト教的な歴史観・終末観と、マルクス主義者が主張する革命理論の間には、極めて類似した論理構成がある事を見抜いていた。
マルクス主義の革命は、いくつかの国家において、現実となった。ここにおいても、マルクス主義革命が生み出したものは、独裁的硬直的な権力を打倒して後の、より民主的で柔軟な政治体制ではなく、新たな独裁体制であった。マルクス主義革命は、理論においても現実においても、新たな独裁権力(プロレタリアート独裁・共産党独裁)を生みだす為の革命である。
1991年のソ連邦崩壊に相前後して起きたロシアと東ヨーロッパの革命は、マルクス主義によって成立した独裁権力を打ち倒す、真の民主化革命であった。
4/8 【国民の為の政治学】第8講革命は何故、起きるのだろうか??[H22/4/2]
【マルクス主義革命理論の破綻】
マルクス主義革命理論は、完全に誤まったものである事が、今日、完全に証明されている。そもそもマルクス主義革命は、先進国においては起こらなかった。この点において、マルクスの予言は完全に外れたのである。
先進国においては、穏健な非マルクス主義的社会主義の考え方が広まり、労働者の人権を重んじる方向に社会は改革されていった。
経済学的に見ても、資本主義の構造的な欠陥である、供給過剰を正す為に、勤労者階級一般の需要を拡大しようという動きが、現実の政策を動かした。
これは、ケインズ主義の名のもとで呼ばれる事もあり、また修正資本主義という呼び方もされている。
資本主義先進国においては、一般勤労者の需要が拡大し、中産階級が増え、これによって「供給過剰と需要過少から恐慌に陥る」という資本主義の構造的欠陥を、解決する事が出来たのである。
一部のマルクス主義者は、寧ろ、南北関係(先進資本主義国と低開発国との関係)において、マルクス主義理論の応用を試みた。
つまり、先進資本主義国(北)が低開発国(南)を構造的に搾取し、低開発国の国民が半永久的に貧困であり続けるという批難を行ったのである。ところが、南北間マルクス主義モデルも、1970年代以来、現実性を失い、特に1991年のソ連邦崩壊以後は、このような主張も信頼性を喪失して来た。
低開発諸国の中から、既存の資本主義経済の枠内で、工業化を行い、輸出を伸ばし、国民の所得を増大させる事に成功した国々が生まれてきたからである。
皮肉な事に、今や、シナやロシアというかつての共産主義大国も又、世界の資本主義的枠組みの中での経済発展を実現しつつある。
【マルクス主義革命理論の破綻】
マルクス主義革命理論は、完全に誤まったものである事が、今日、完全に証明されている。そもそもマルクス主義革命は、先進国においては起こらなかった。この点において、マルクスの予言は完全に外れたのである。
先進国においては、穏健な非マルクス主義的社会主義の考え方が広まり、労働者の人権を重んじる方向に社会は改革されていった。
経済学的に見ても、資本主義の構造的な欠陥である、供給過剰を正す為に、勤労者階級一般の需要を拡大しようという動きが、現実の政策を動かした。
これは、ケインズ主義の名のもとで呼ばれる事もあり、また修正資本主義という呼び方もされている。
資本主義先進国においては、一般勤労者の需要が拡大し、中産階級が増え、これによって「供給過剰と需要過少から恐慌に陥る」という資本主義の構造的欠陥を、解決する事が出来たのである。
一部のマルクス主義者は、寧ろ、南北関係(先進資本主義国と低開発国との関係)において、マルクス主義理論の応用を試みた。
つまり、先進資本主義国(北)が低開発国(南)を構造的に搾取し、低開発国の国民が半永久的に貧困であり続けるという批難を行ったのである。ところが、南北間マルクス主義モデルも、1970年代以来、現実性を失い、特に1991年のソ連邦崩壊以後は、このような主張も信頼性を喪失して来た。
低開発諸国の中から、既存の資本主義経済の枠内で、工業化を行い、輸出を伸ばし、国民の所得を増大させる事に成功した国々が生まれてきたからである。
皮肉な事に、今や、シナやロシアというかつての共産主義大国も又、世界の資本主義的枠組みの中での経済発展を実現しつつある。
5/8 【国民の為の政治学】第8講革命は何故、起きるのだろうか??[H22/4/2]
古典的なマルクス革命理論は、今日完全に破綻している。
これに対して、文化マルクス主義とでも言うべき革命理論が、先進国では猛威をふるっている。
これは、直接の政治闘争や経済闘争によって、革命を実現するのではなく、長期的に家族や社会の伝統的道徳を破壊する事によって、マルクス主義的唯物論的革命を達成しようという方法論である。
このイデオロギーによれば、家族こそは、階級社会を支える根源的な単位であり、家族を破壊する事こそが、伝統的道徳観を破壊し、ついに階級社会や国家そのものを解体する事に繋がる、という。
このような虚妄のイデオロギーに基づいて、現在の日本における「家族解体法案(選択的夫婦別姓など)」が提出されているのである。
また、子供手当法案も、その基本になる考えは「家族が子供を育てる」のではなく「社会が子供を育てる」という考え方であり、そこに文化マルクス主義のイデオロギーが、確実に埋め込まれているのである。
古典的なマルクス革命理論は、今日完全に破綻している。
これに対して、文化マルクス主義とでも言うべき革命理論が、先進国では猛威をふるっている。
これは、直接の政治闘争や経済闘争によって、革命を実現するのではなく、長期的に家族や社会の伝統的道徳を破壊する事によって、マルクス主義的唯物論的革命を達成しようという方法論である。
このイデオロギーによれば、家族こそは、階級社会を支える根源的な単位であり、家族を破壊する事こそが、伝統的道徳観を破壊し、ついに階級社会や国家そのものを解体する事に繋がる、という。
このような虚妄のイデオロギーに基づいて、現在の日本における「家族解体法案(選択的夫婦別姓など)」が提出されているのである。
また、子供手当法案も、その基本になる考えは「家族が子供を育てる」のではなく「社会が子供を育てる」という考え方であり、そこに文化マルクス主義のイデオロギーが、確実に埋め込まれているのである。
6/8 【国民の為の政治学】第8講革命は何故、起きるのだろうか??[H22/4/2]
【ルサンチマンについて】
それではそもそも、文化マルクス主義などのイデオロギーに後押しされて、日本社会を解体しようという人々は、何故そのような動機を持つのだろうか?
一言でいえば、ルサンチマン(怨念、恨み、特に弱者が強者に対して抱く憎悪感)という事であろう。
それはまた、劣等感の裏返しとしての復讐心とも言いかえる事が出来るであろう。
社会の少数者が、多数者に対して抱く劣等感や、被疎外感などが、不健全な形で内向し、憎悪心に転じたものがこのルサンチマン感情である。
現在の家族解体論者や、国家解体論者の最も基本的な行動の動機(モチベーション)は、このルサンチマン以外の何ものでもない。
しかし、日本社会は伝統的に本来、同性愛者などの少数者に対しても、常に寛容であり続けて来た。
これが、同性愛者を完全に宗教的異端とみなしてきたキリスト教社会等とは根本的に異なるところである。
このような伝統的な日本社会の柔軟な文化の下では、少数者は必ずしも声高に人権を主張しなくても、その存在を許されている。
彼らのルサンチマンを扇動しているところに、今日の反日主義者の最も狡猾な戦略がある。
【ルサンチマンについて】
それではそもそも、文化マルクス主義などのイデオロギーに後押しされて、日本社会を解体しようという人々は、何故そのような動機を持つのだろうか?
一言でいえば、ルサンチマン(怨念、恨み、特に弱者が強者に対して抱く憎悪感)という事であろう。
それはまた、劣等感の裏返しとしての復讐心とも言いかえる事が出来るであろう。
社会の少数者が、多数者に対して抱く劣等感や、被疎外感などが、不健全な形で内向し、憎悪心に転じたものがこのルサンチマン感情である。
現在の家族解体論者や、国家解体論者の最も基本的な行動の動機(モチベーション)は、このルサンチマン以外の何ものでもない。
しかし、日本社会は伝統的に本来、同性愛者などの少数者に対しても、常に寛容であり続けて来た。
これが、同性愛者を完全に宗教的異端とみなしてきたキリスト教社会等とは根本的に異なるところである。
このような伝統的な日本社会の柔軟な文化の下では、少数者は必ずしも声高に人権を主張しなくても、その存在を許されている。
彼らのルサンチマンを扇動しているところに、今日の反日主義者の最も狡猾な戦略がある。
7/8 【国民の為の政治学】第8講革命は何故、起きるのだろうか??[H22/4/2]
日本における革命を考える時、最も重要なのは、日本の政治文化の二重構造に気がつく事である。
天皇は、聖なる次元に属し、民族の司祭としての権威を持ち、日本史を貫いて常に権力の正統性を担保する存在であり続けて来た。
俗の次元に属する権力者は、(それが摂政・関白であれ、将軍であれ、内閣総理大臣であれ)現実の政治権力を操るが、常にその地位を天皇から賜り、その権力の正統性を天皇に依存して来た。
これが日本における政治文化の二重構造である。
天皇は、日本民族全体の代表者として君臨し、現実の行政権力を時の最高権力者にゆだね、権力者はその委任に応え、国民の民政の充実を図る。というのが本来あるべき日本政治の姿である。
権力の正統性の根源が、常に天皇にあるという点については、皇国史観は捏造物ではなく、日本の歴史の現実そのものであり続けて来た。
日本における革命を考える時、最も重要なのは、日本の政治文化の二重構造に気がつく事である。
天皇は、聖なる次元に属し、民族の司祭としての権威を持ち、日本史を貫いて常に権力の正統性を担保する存在であり続けて来た。
俗の次元に属する権力者は、(それが摂政・関白であれ、将軍であれ、内閣総理大臣であれ)現実の政治権力を操るが、常にその地位を天皇から賜り、その権力の正統性を天皇に依存して来た。
これが日本における政治文化の二重構造である。
天皇は、日本民族全体の代表者として君臨し、現実の行政権力を時の最高権力者にゆだね、権力者はその委任に応え、国民の民政の充実を図る。というのが本来あるべき日本政治の姿である。
権力の正統性の根源が、常に天皇にあるという点については、皇国史観は捏造物ではなく、日本の歴史の現実そのものであり続けて来た。
8/8 【国民の為の政治学】第8講革命は何故、起きるのだろうか??[H22/4/2]
このような聖俗の二重構造をもつ日本の政治文化においては、革命(徹底した国家の改造)はどのように成し遂げられるのであろうか。
天皇の正統性という権威を頂いた革命のみが、日本における唯一の革命の形である。
これを「錦旗革命」と言い換えてもよいだろう。
時の政権が、あまりに天皇の本意から外れて、暴政を行ない、あるいは無能に陥った場合、本来の国の形に戻す為に、天皇の権威のもとに時の権力者は征伐され、体制は確信されるのである。
西洋のキリスト教国の革命を支えた考え方に、神の自然法という思想がある。
自然法とは、紙に書かれた法律ではないが、世界中の時とところとを超越して、有効であるような普遍的な法の事である。
謂わば、神が設定したとしか言いようのない普遍的な法という意味である。
西洋においては、時の権力者が、この自然法に背いた場合、人民は革命を起こして、神の定めたもうた自然法を復活させる事が出来る。
これこそが、あるべき革命である、とキリスト教徒は考える。
日本においては、この用語を用いるならば、天皇こそは、目に見える自然法なのである。
国民全体の安寧を祈る天皇の本意に反する権力者は、国民によって更迭されなければならない。
これが日本的革命の論理である。
(※詳しくは、『「国家」なき国ニッポン』藤井厳喜・著 http://www.amazon.co.jp/gp/product/4829501618 を参照)
このような聖俗の二重構造をもつ日本の政治文化においては、革命(徹底した国家の改造)はどのように成し遂げられるのであろうか。
天皇の正統性という権威を頂いた革命のみが、日本における唯一の革命の形である。
これを「錦旗革命」と言い換えてもよいだろう。
時の政権が、あまりに天皇の本意から外れて、暴政を行ない、あるいは無能に陥った場合、本来の国の形に戻す為に、天皇の権威のもとに時の権力者は征伐され、体制は確信されるのである。
西洋のキリスト教国の革命を支えた考え方に、神の自然法という思想がある。
自然法とは、紙に書かれた法律ではないが、世界中の時とところとを超越して、有効であるような普遍的な法の事である。
謂わば、神が設定したとしか言いようのない普遍的な法という意味である。
西洋においては、時の権力者が、この自然法に背いた場合、人民は革命を起こして、神の定めたもうた自然法を復活させる事が出来る。
これこそが、あるべき革命である、とキリスト教徒は考える。
日本においては、この用語を用いるならば、天皇こそは、目に見える自然法なのである。
国民全体の安寧を祈る天皇の本意に反する権力者は、国民によって更迭されなければならない。
これが日本的革命の論理である。
(※詳しくは、『「国家」なき国ニッポン』藤井厳喜・著 http://www.amazon.co.jp/gp/product/4829501618 を参照)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
藤井厳喜アカデミー 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
藤井厳喜アカデミーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6473人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19251人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人