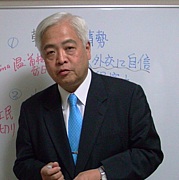今回の講義は、「国内政治と国際政治の違いについて」です。
(※ これら映像は、2010年2月19日に公開されたものです。)
一番大事な点は、国際政治においては、主権国家は全く並列的に平等な存在であり、その点から言えば、世界は慢性的な戦争状態にあると言っても過言ではありません。
主権国家が国益の増大を求めて戦争を起こす事は、国際法上は全く合法的な行動なのです。
国内政治と違い、世界に単一の法秩序は存在しません。
また、現在存在する秩序を破って戦争を始めたとしても、これを罰する法的執行力をもった世界政府は存在しません。
俗な言い方をすれば、国際政治においては、秩序を破壊し、悪い事をやっても、警察はこないのです。
主権国家の悪は、他の主権国家が実力によって正さねばなりません。
これもまた、国家間の戦争を呼び起こします。
国内政治には、単一の法的秩序が存在し、この法的秩序を破れば、それは即、犯罪行為となります。
犯罪行為を犯せば、国家の法的執行力(多くの場合、警察権力)が行使されます。
悪い事をすれば、警察が来て、牢屋に入れられ、裁判にかけられるのです。
このようなプロセスは国際政治には存在しません。
全ての主権国家は相互に平等であり、世界は潜在的な無秩序状態にあります。
以上の様な点が、国内政治と国際政治の最も大きな違いです。
このような、主権国家の並存という体制は、ヨーロッパにおける1648年のウェストファリア条約の締結から始まっています。
主権国家は相互に平等であり、内政干渉はしないのが原則です。
しかし近年では、環境問題や人権問題に関しては、内政干渉も許されるべきだ、との新しい考え方も浮上しています。
主権国家が相互に平等であるという事は、それぞれの国家にそれぞれの正義がある事を認める事です。
国際法はこのような完全に相対主義的な理念に基づいて構成されています。
伝統的な国際法の考え方では、A国の正義とB国の正義の間には何ら正邪・善悪・優劣の差はありません。
それ故に、日本が自らの国益の拡大の為に、英米に宣戦を布告した大東亜戦争は、それ自体、全く何ら批難される事のない国際法上の行為でした。
国際法上、国家には戦争をする権利が認められているのです。
通常、言われる「国際法違反」とは、正しく言えば、「戦時国際法の違反」の事です。
それは主に、「非戦闘員の組織的計画的殺戮」の事です。
戦場において、戦闘員同士が殺し合う事は、国際法上、全く合法的な行為です。
国内政治と国際政治の違いが分かれば、「国内法と国際法の違い」も自ずから分かるでしょう。
国際法とは、国内法で言われているような制度的な法執行権力によって守られていない存在です。
国際法は主に、二つの部分から構成されています。
第一は、国際的な外交慣習法であり、第二は国家間の条約です。
慣習法の方は、主にヨーロッパ諸国間で発達してきた暗黙のルールです。
例えば、日本にあるイギリス大使館の土地は、日本にとっては治外法権であり、イギリスの領土と見なされている事などです。
国家間の条約については、改めて説明する必要もないでしょう。
重要な事は、外交慣習法が革命等によって破られる事は度々あるし、条約違反が行われる事も稀ではないということです。
この場合、懲罰を与える国際的な執行権力(世界政府)は存在しません。
ルールを破られ、被害を被った国が自らの力でルールを破った国を制裁するしかありません。
しばしばこれは国家間の戦争となります。
そもそも国際条約とは、自国に利益がある為に締結するものです。
自国の国益にならないと思えば、それを破棄するのは当然の事です。
それ故に、国際政治学は、「全ての国際条約は暫定法である」と教えています。
また例えば、IMFやWTO等の多国間組織の協定をある国が破ったとします。
この場合、考えられる最大のIMFやWTOの制裁措置は、これらの国際組織から当該国を追放する事です。
別の言い方をすれば、それ以上の制裁は考えられません。
それ故に、もし「核拡散防止条約(NPT)」からある国が離脱して核武装を行おうと思えば、それを原理的に防ぐ事はできません。
それに伴う様々な国際的な制裁(ウラン燃料の入手が困難になる事など)を受け入れる覚悟があれば、国連やIAEA(国際原子力機関)もそれ以上の制裁を加える事は出来ません。
これが今の北朝鮮やイランの核武装を取り巻く国際情勢の基本になっています。
要は、世界というところは極めて不安定なところであって、究極的には自国の安全は自国の力で守るしかないのです。
では、今回の本講義をご覧ください。
尚、今回もまた、補講(約30分を予定)を配信致しますので、此方も合わせて受講頂ければと思います。
(※ これら映像は、2010年2月19日に公開されたものです。)
一番大事な点は、国際政治においては、主権国家は全く並列的に平等な存在であり、その点から言えば、世界は慢性的な戦争状態にあると言っても過言ではありません。
主権国家が国益の増大を求めて戦争を起こす事は、国際法上は全く合法的な行動なのです。
国内政治と違い、世界に単一の法秩序は存在しません。
また、現在存在する秩序を破って戦争を始めたとしても、これを罰する法的執行力をもった世界政府は存在しません。
俗な言い方をすれば、国際政治においては、秩序を破壊し、悪い事をやっても、警察はこないのです。
主権国家の悪は、他の主権国家が実力によって正さねばなりません。
これもまた、国家間の戦争を呼び起こします。
国内政治には、単一の法的秩序が存在し、この法的秩序を破れば、それは即、犯罪行為となります。
犯罪行為を犯せば、国家の法的執行力(多くの場合、警察権力)が行使されます。
悪い事をすれば、警察が来て、牢屋に入れられ、裁判にかけられるのです。
このようなプロセスは国際政治には存在しません。
全ての主権国家は相互に平等であり、世界は潜在的な無秩序状態にあります。
以上の様な点が、国内政治と国際政治の最も大きな違いです。
このような、主権国家の並存という体制は、ヨーロッパにおける1648年のウェストファリア条約の締結から始まっています。
主権国家は相互に平等であり、内政干渉はしないのが原則です。
しかし近年では、環境問題や人権問題に関しては、内政干渉も許されるべきだ、との新しい考え方も浮上しています。
主権国家が相互に平等であるという事は、それぞれの国家にそれぞれの正義がある事を認める事です。
国際法はこのような完全に相対主義的な理念に基づいて構成されています。
伝統的な国際法の考え方では、A国の正義とB国の正義の間には何ら正邪・善悪・優劣の差はありません。
それ故に、日本が自らの国益の拡大の為に、英米に宣戦を布告した大東亜戦争は、それ自体、全く何ら批難される事のない国際法上の行為でした。
国際法上、国家には戦争をする権利が認められているのです。
通常、言われる「国際法違反」とは、正しく言えば、「戦時国際法の違反」の事です。
それは主に、「非戦闘員の組織的計画的殺戮」の事です。
戦場において、戦闘員同士が殺し合う事は、国際法上、全く合法的な行為です。
国内政治と国際政治の違いが分かれば、「国内法と国際法の違い」も自ずから分かるでしょう。
国際法とは、国内法で言われているような制度的な法執行権力によって守られていない存在です。
国際法は主に、二つの部分から構成されています。
第一は、国際的な外交慣習法であり、第二は国家間の条約です。
慣習法の方は、主にヨーロッパ諸国間で発達してきた暗黙のルールです。
例えば、日本にあるイギリス大使館の土地は、日本にとっては治外法権であり、イギリスの領土と見なされている事などです。
国家間の条約については、改めて説明する必要もないでしょう。
重要な事は、外交慣習法が革命等によって破られる事は度々あるし、条約違反が行われる事も稀ではないということです。
この場合、懲罰を与える国際的な執行権力(世界政府)は存在しません。
ルールを破られ、被害を被った国が自らの力でルールを破った国を制裁するしかありません。
しばしばこれは国家間の戦争となります。
そもそも国際条約とは、自国に利益がある為に締結するものです。
自国の国益にならないと思えば、それを破棄するのは当然の事です。
それ故に、国際政治学は、「全ての国際条約は暫定法である」と教えています。
また例えば、IMFやWTO等の多国間組織の協定をある国が破ったとします。
この場合、考えられる最大のIMFやWTOの制裁措置は、これらの国際組織から当該国を追放する事です。
別の言い方をすれば、それ以上の制裁は考えられません。
それ故に、もし「核拡散防止条約(NPT)」からある国が離脱して核武装を行おうと思えば、それを原理的に防ぐ事はできません。
それに伴う様々な国際的な制裁(ウラン燃料の入手が困難になる事など)を受け入れる覚悟があれば、国連やIAEA(国際原子力機関)もそれ以上の制裁を加える事は出来ません。
これが今の北朝鮮やイランの核武装を取り巻く国際情勢の基本になっています。
要は、世界というところは極めて不安定なところであって、究極的には自国の安全は自国の力で守るしかないのです。
では、今回の本講義をご覧ください。
尚、今回もまた、補講(約30分を予定)を配信致しますので、此方も合わせて受講頂ければと思います。
|
|
|
|
コメント(9)
国民の為の政治学・第2講・補足版「国内政治と国際政治の違いとは何だろう?」(YouTubeでは全3本)
※ 2010,02,21配信分
今回の講義は、藤井厳喜アカデミー「国民の為の政治学」講座、第2回「国内政治と国際政治の違いとは何だろう?」(既に2月19日配信済)のより詳しい補足解説版として、お送りさせて頂くものとなります。
先ず、アテネの民主制の発達においては、兵役の拡大が、そのままに参政権の拡大であった事を、やや掘り下げて講義します。
「兵役の義務」と「参政の権利」は、一対のものです。
この点から考えれば、外国人参政権が如何に理不尽なものかが分かります。
次に、『主権国家とは何か』、特に「主権」という言葉を使う意味は何なのか?
簡単に言えば、主権とは、国家を統括している単一の権力の事です。
主権が分割されるという事は、実は国家が分裂しているという事に他なりません。
また、国防の中心である「抑止力」という言葉の意味するところについても、正確な議論を展開しています。
日本の現在の政府が言う「専守防衛」では、抑止力が持ち得ない事を論証しています。
3番目の補講映像では、フランス人思想家・モンテスキューが主張した『三権分立』の考え方について、その中身を検討しています。
モンテスキューは衆愚制に陥りやすい民主政治の欠点についても十分把握しており、国家を如何にバランスよく運営するかとの観点から、三権分立を主張しました。
「三権分立」の考え方は、独裁制、貴族性、民主制の三つの体制の良いところを組み合わせようという基本理念に発していると言ってもよいでしょう。
アメリカの三権分立は、モンテスキューの三権分立の考え方を比較的そのまま現実に移したものです。
「大統領制」は独裁制的であり、「連邦最高裁」は貴族制的であり、「連邦議会」は民主制的です。
この三者にチェック&バランス(抑制と均衡)が働くように、アメリカ憲法は構成されています。
では、本日の講義をご覧ください。
※ 2010,02,21配信分
今回の講義は、藤井厳喜アカデミー「国民の為の政治学」講座、第2回「国内政治と国際政治の違いとは何だろう?」(既に2月19日配信済)のより詳しい補足解説版として、お送りさせて頂くものとなります。
先ず、アテネの民主制の発達においては、兵役の拡大が、そのままに参政権の拡大であった事を、やや掘り下げて講義します。
「兵役の義務」と「参政の権利」は、一対のものです。
この点から考えれば、外国人参政権が如何に理不尽なものかが分かります。
次に、『主権国家とは何か』、特に「主権」という言葉を使う意味は何なのか?
簡単に言えば、主権とは、国家を統括している単一の権力の事です。
主権が分割されるという事は、実は国家が分裂しているという事に他なりません。
また、国防の中心である「抑止力」という言葉の意味するところについても、正確な議論を展開しています。
日本の現在の政府が言う「専守防衛」では、抑止力が持ち得ない事を論証しています。
3番目の補講映像では、フランス人思想家・モンテスキューが主張した『三権分立』の考え方について、その中身を検討しています。
モンテスキューは衆愚制に陥りやすい民主政治の欠点についても十分把握しており、国家を如何にバランスよく運営するかとの観点から、三権分立を主張しました。
「三権分立」の考え方は、独裁制、貴族性、民主制の三つの体制の良いところを組み合わせようという基本理念に発していると言ってもよいでしょう。
アメリカの三権分立は、モンテスキューの三権分立の考え方を比較的そのまま現実に移したものです。
「大統領制」は独裁制的であり、「連邦最高裁」は貴族制的であり、「連邦議会」は民主制的です。
この三者にチェック&バランス(抑制と均衡)が働くように、アメリカ憲法は構成されています。
では、本日の講義をご覧ください。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
藤井厳喜アカデミー 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
藤井厳喜アカデミーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6470人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19247人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208304人