ソース:http://
【6月10日 AFP】オリオン座の赤い一等星「ベテルギウス(Betelgeuse)」の大きさが過去15年間で15%以上も縮小しているとの研究結果が、米カリフォルニア(California)州パサディナ(Pasadena)で9日開催された米天文学会(American Astronomical Society、AAS)の会合で発表された。縮小の理由はまだ解明されていないという。
ベテルギウスは赤色超巨星で、その直径は太陽から木星軌道にまで及ぶ長さになるとされる。だが、1993年以降の15年間で太陽から金星軌道までに相当する距離が縮小したことが、南カリフォルニアのウィルソン山(Mount Wilson)頂上にある米カリフォルニア大学バークレー校(University of California, Berkeley)の赤外空間干渉計(Infrared Spatial Interferometer、ISI)による計測で明らかになった。
1964年にレーザーの発明でノーベル物理学賞を受賞した同大のチャールズ・タウンズ(Charles Townes)教授によると、縮小は徐々に進んでいるが、年がたつにつれその速度は速まっているという。また教授は、近年になってこの星の表面に非常に明るい部分を確認しているが、星の変形は今のところ観測されていないという。
また、縮小にもかかわらず、光度の大幅な減少は見られないという。
赤色超巨星は、質量の大きい星が内部崩壊を起こして大爆発を起こす、いわゆるタイプ2型の超新星になると考えられている。
ベテルギウスは、全天で最も明るい星のベスト8に入るが、こうした星で測定が行われたのは、ベテルギウスが初めて。ハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope、HST)による観測も行われている。(c)AFP
【6月10日 AFP】オリオン座の赤い一等星「ベテルギウス(Betelgeuse)」の大きさが過去15年間で15%以上も縮小しているとの研究結果が、米カリフォルニア(California)州パサディナ(Pasadena)で9日開催された米天文学会(American Astronomical Society、AAS)の会合で発表された。縮小の理由はまだ解明されていないという。
ベテルギウスは赤色超巨星で、その直径は太陽から木星軌道にまで及ぶ長さになるとされる。だが、1993年以降の15年間で太陽から金星軌道までに相当する距離が縮小したことが、南カリフォルニアのウィルソン山(Mount Wilson)頂上にある米カリフォルニア大学バークレー校(University of California, Berkeley)の赤外空間干渉計(Infrared Spatial Interferometer、ISI)による計測で明らかになった。
1964年にレーザーの発明でノーベル物理学賞を受賞した同大のチャールズ・タウンズ(Charles Townes)教授によると、縮小は徐々に進んでいるが、年がたつにつれその速度は速まっているという。また教授は、近年になってこの星の表面に非常に明るい部分を確認しているが、星の変形は今のところ観測されていないという。
また、縮小にもかかわらず、光度の大幅な減少は見られないという。
赤色超巨星は、質量の大きい星が内部崩壊を起こして大爆発を起こす、いわゆるタイプ2型の超新星になると考えられている。
ベテルギウスは、全天で最も明るい星のベスト8に入るが、こうした星で測定が行われたのは、ベテルギウスが初めて。ハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope、HST)による観測も行われている。(c)AFP
|
|
|
|
コメント(16)
直径が15%小さくなったというと一見取るに足りない変化のように思われがちですが、体積では実に40%近く減っていることになります。
ベテルギウスは質量が太陽の20倍以上もあります。水素やヘリウムは遠い昔に使い尽くして今ではネオンやナトリウム、または珪素が燃えていると考えられます。
太陽の位置に置くと木星軌道に達するような巨大なサイズを保っていられるのは核反応が莫大なエネルギーを生み出しているからです。
それが異常な収縮を始めたということは中心で生成されるエネルギーの量が低下したからだと考えられます。
原因としては燃料が不足し始めていることが挙げられます。燃料が不足してエネルギーが減ると星は重力によって収縮し、それによって中心部温度は高くなります。
中心温度が上がると燃えカスだったものが次の燃料として利用可能になり、再び勢いを盛り返して膨張します。
しかし鉄まで核反応が進んだ場合それ以上は吸熱反応になるので燃料として利用することができず、際限なく収縮しようとした反動で大爆発を起こします。これが超新星爆発です。
超新星になった場合地球への影響は距離が離れているので心配ありませんが、満月以上に明るくなるのでお祭り騒ぎになることは間違いないと思われます。
今回の収縮が単なる恒星周期による正常な営みのひとつなのか、燃料切れによるものなのかはわかりません。
燃料切れの場合、前者だったとしても重元素の核反応はそう長くは続かないので生きている間に爆発が見られる可能性は低くないでしょう。
生きている間に爆発を見れたらそれはとても素敵なことです。一日一日を大切に生きましょう。
ベテルギウスは質量が太陽の20倍以上もあります。水素やヘリウムは遠い昔に使い尽くして今ではネオンやナトリウム、または珪素が燃えていると考えられます。
太陽の位置に置くと木星軌道に達するような巨大なサイズを保っていられるのは核反応が莫大なエネルギーを生み出しているからです。
それが異常な収縮を始めたということは中心で生成されるエネルギーの量が低下したからだと考えられます。
原因としては燃料が不足し始めていることが挙げられます。燃料が不足してエネルギーが減ると星は重力によって収縮し、それによって中心部温度は高くなります。
中心温度が上がると燃えカスだったものが次の燃料として利用可能になり、再び勢いを盛り返して膨張します。
しかし鉄まで核反応が進んだ場合それ以上は吸熱反応になるので燃料として利用することができず、際限なく収縮しようとした反動で大爆発を起こします。これが超新星爆発です。
超新星になった場合地球への影響は距離が離れているので心配ありませんが、満月以上に明るくなるのでお祭り騒ぎになることは間違いないと思われます。
今回の収縮が単なる恒星周期による正常な営みのひとつなのか、燃料切れによるものなのかはわかりません。
燃料切れの場合、前者だったとしても重元素の核反応はそう長くは続かないので生きている間に爆発が見られる可能性は低くないでしょう。
生きている間に爆発を見れたらそれはとても素敵なことです。一日一日を大切に生きましょう。
このニュースには私も注目しています。
<オリオン座の赤色超巨星「ベテルギウス」に異変、15年間で15%縮小 >
2009/6/11 18:53 - オリオン座α星の赤色超巨星「ベテルギウス」の大きさが急激に縮小するなど異変が生じていることが9日、カリフォルニア大学バークレー校の発表により明らかとなった。
カリフォルニアのウィルソン山にある同校の赤外空間干渉計(Infrared Spatial Interferometer)を使った観測により明らかとなったもので、5天文単位(地球と太陽の間の平均距離を1)もある赤色超巨星の大きさは1993年以来の15年で15%も縮小するなど、明らかな異常が生じていることが判ったとしている。
大きさが縮小しているのにも関わらず明るさには変化が生じていないことが特徴の一つとなっており、同大学のエドワード・ウィシュナウ研究員は「何が起きているのか、まったく説明が付かない」とベテルギウスの異変に首をかしげている。
ベテルギウスに何が起きているのはまだ明らかとなっていないが急激な縮小は、超新星爆発の前触れではないかとする見方もでている。
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906111853
過去の例のひとつ、おうし座かに座星雲は1056年の超新星爆発による残骸といわれていますが、
その時は、「金星のように昼間でも見えた。23日間昼間にも見え、約1年間で夜でも見えなくなった」と宋史に記録として残っています。
(他コミュに書いたものと重複しますが)
もしべテルギウスが超新星爆発するなら、興味深いです。
1987年のSN1987Aの超新星爆発の時は、ニュートリノ振動のフラックス測定で大発見がなされていますし、 素粒子の分野でも注目したいですね。
昔と違ってハッブルやジェームス・ウェブ宇宙望遠鏡(2013年運用予定)もありますし、地上の観測装置も光学望遠鏡、電波望遠鏡、シンチレーターや重力波測定装置などもありますから、このイベントはかなりのデータが取れるものと期待しています。
宇宙の謎の解明に、また一歩前進できるのではないでしょうか。
私達世代でこのイベントが起こるかどうかは解りませんが、もともと天文年はヒトの一生で捉えるには大きすぎるスケールなので、
私たちにできるのは、今起こっていることを、余すことなく記録して、後世に残すことかもしれませんね。
<オリオン座の赤色超巨星「ベテルギウス」に異変、15年間で15%縮小 >
2009/6/11 18:53 - オリオン座α星の赤色超巨星「ベテルギウス」の大きさが急激に縮小するなど異変が生じていることが9日、カリフォルニア大学バークレー校の発表により明らかとなった。
カリフォルニアのウィルソン山にある同校の赤外空間干渉計(Infrared Spatial Interferometer)を使った観測により明らかとなったもので、5天文単位(地球と太陽の間の平均距離を1)もある赤色超巨星の大きさは1993年以来の15年で15%も縮小するなど、明らかな異常が生じていることが判ったとしている。
大きさが縮小しているのにも関わらず明るさには変化が生じていないことが特徴の一つとなっており、同大学のエドワード・ウィシュナウ研究員は「何が起きているのか、まったく説明が付かない」とベテルギウスの異変に首をかしげている。
ベテルギウスに何が起きているのはまだ明らかとなっていないが急激な縮小は、超新星爆発の前触れではないかとする見方もでている。
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906111853
過去の例のひとつ、おうし座かに座星雲は1056年の超新星爆発による残骸といわれていますが、
その時は、「金星のように昼間でも見えた。23日間昼間にも見え、約1年間で夜でも見えなくなった」と宋史に記録として残っています。
(他コミュに書いたものと重複しますが)
もしべテルギウスが超新星爆発するなら、興味深いです。
1987年のSN1987Aの超新星爆発の時は、ニュートリノ振動のフラックス測定で大発見がなされていますし、 素粒子の分野でも注目したいですね。
昔と違ってハッブルやジェームス・ウェブ宇宙望遠鏡(2013年運用予定)もありますし、地上の観測装置も光学望遠鏡、電波望遠鏡、シンチレーターや重力波測定装置などもありますから、このイベントはかなりのデータが取れるものと期待しています。
宇宙の謎の解明に、また一歩前進できるのではないでしょうか。
私達世代でこのイベントが起こるかどうかは解りませんが、もともと天文年はヒトの一生で捉えるには大きすぎるスケールなので、
私たちにできるのは、今起こっていることを、余すことなく記録して、後世に残すことかもしれませんね。
もし、ベテルギウス星が超新星爆発を起こした場合、
有史以来、最も近距離(640光年)でのになりますよね。
(今までの距離とは桁が違う!)
その明るさも、想像を絶する事でしょう。
貴重なデータが多く得られる事に期待します。
<補足>・・・距離・光度の一覧表
最古の観測記録である『SN 185』が3300光年。(マイナス8等星)
史上最も明るく輝いた『SN 1006』が7175光年。(マイナス9等星)
有名な『かに星雲・SN 1054』が7000光年。(マイナス6等星)
天文学者による最初の観測である『チコの星・SN 1572』が7500光年。(マイナス4等星)
銀河系内最後の観測である『ケプラーの星・SN 1604』が2万光年。(マイナス2・5等星)
有史以来、最も近距離(640光年)でのになりますよね。
(今までの距離とは桁が違う!)
その明るさも、想像を絶する事でしょう。
貴重なデータが多く得られる事に期待します。
<補足>・・・距離・光度の一覧表
最古の観測記録である『SN 185』が3300光年。(マイナス8等星)
史上最も明るく輝いた『SN 1006』が7175光年。(マイナス9等星)
有名な『かに星雲・SN 1054』が7000光年。(マイナス6等星)
天文学者による最初の観測である『チコの星・SN 1572』が7500光年。(マイナス4等星)
銀河系内最後の観測である『ケプラーの星・SN 1604』が2万光年。(マイナス2・5等星)
久しぶりにベテルギウスの話題がありました。
あまり変化はないようですが、画像は面白いですね。
それにしても、約600光年先・・・今現在あるのかな〜、ないのかなあ〜
今夜オリオンを見る時、不思議な気持ちになりそうです。
【ベテルギウスに爆発の兆候 大きさ急減、表面でこぼこ】
(2010年1月10日0時27分 asahi.com)
オリオン座の1等星「ベテルギウス」で、超新星爆発へ向かうと見られる兆候が観測されている。米航空宇宙局(NASA)が6日に公開した画像には、星の表面の盛り上がりとみられる二つの大きな白い模様が写っていた。この15年で大きさが15%減ったという報告もあり、専門家は「爆発は数万年後かもしれないが、明日でもおかしくない」と話す。もし爆発すれば、満月ほどの明るさになり、昼でも見えるようになる。
冬の大三角の一つでもあるベテルギウスは、赤色超巨星と呼ばれる巨大な星。直径は太陽の1千倍で、太陽系にあるとしたら、地球や火星はおろか木星までが覆われる大きさだ。重いため一生は短く、まだ数百万歳(太陽は46億歳)だが、すでに寿命に近い。最後は超新星爆発を起こし、ブラックホールなどになるとされる。
地球からの距離は約600光年。地球からベテルギウスを見ると、東京から大阪に置いてあるソフトボールくらいの大きさにしか見えず、これまでは大きな望遠鏡でも点程度にしか見えなかった。だが近年は、複数の望遠鏡を組み合わせて解像度を上げることにより、その表面や周囲のガスの流れまで撮影できるようになった。
昨年、米欧の研究者がほぼ同時に3本の論文を発表し、ベテルギウスが大量のガスを放出していることや大きさの急減が示された。ガスの放出によって星の表面が梅干しのようにでこぼこに膨らんでいるらしい。
ただ、その後の別の観測では、大きさの変化はあまりないという報告も出ているという。3本の論文のうちの1本の著者で、独マックスプランク電波天文学研究所の大仲圭一研究員は「爆発がいつかは分からないが、死の直前を見ているのは間違いない。今まで想像するしかなかった星表面の様子も、実際に見て確かめられるようになってきた」と話す。
http://www.asahi.com/science/update/0109/TKY201001090278.html
あまり変化はないようですが、画像は面白いですね。
それにしても、約600光年先・・・今現在あるのかな〜、ないのかなあ〜
今夜オリオンを見る時、不思議な気持ちになりそうです。
【ベテルギウスに爆発の兆候 大きさ急減、表面でこぼこ】
(2010年1月10日0時27分 asahi.com)
オリオン座の1等星「ベテルギウス」で、超新星爆発へ向かうと見られる兆候が観測されている。米航空宇宙局(NASA)が6日に公開した画像には、星の表面の盛り上がりとみられる二つの大きな白い模様が写っていた。この15年で大きさが15%減ったという報告もあり、専門家は「爆発は数万年後かもしれないが、明日でもおかしくない」と話す。もし爆発すれば、満月ほどの明るさになり、昼でも見えるようになる。
冬の大三角の一つでもあるベテルギウスは、赤色超巨星と呼ばれる巨大な星。直径は太陽の1千倍で、太陽系にあるとしたら、地球や火星はおろか木星までが覆われる大きさだ。重いため一生は短く、まだ数百万歳(太陽は46億歳)だが、すでに寿命に近い。最後は超新星爆発を起こし、ブラックホールなどになるとされる。
地球からの距離は約600光年。地球からベテルギウスを見ると、東京から大阪に置いてあるソフトボールくらいの大きさにしか見えず、これまでは大きな望遠鏡でも点程度にしか見えなかった。だが近年は、複数の望遠鏡を組み合わせて解像度を上げることにより、その表面や周囲のガスの流れまで撮影できるようになった。
昨年、米欧の研究者がほぼ同時に3本の論文を発表し、ベテルギウスが大量のガスを放出していることや大きさの急減が示された。ガスの放出によって星の表面が梅干しのようにでこぼこに膨らんでいるらしい。
ただ、その後の別の観測では、大きさの変化はあまりないという報告も出ているという。3本の論文のうちの1本の著者で、独マックスプランク電波天文学研究所の大仲圭一研究員は「爆発がいつかは分からないが、死の直前を見ているのは間違いない。今まで想像するしかなかった星表面の様子も、実際に見て確かめられるようになってきた」と話す。
http://www.asahi.com/science/update/0109/TKY201001090278.html
明日のNHK・BS「コズミックフロント」はベテルギウスを取り上げるようです。
201○年という噂もあるけど、どうなんでしょうね
「爆発直前!?赤い巨星ベテルギウス」
オリオン座の赤い一等星「ベテルギウス」。その大きさは太陽の1000倍と巨大で、表面は紅蓮の炎で覆われている。しかも最新の観測から、太陽のような丸い形の星ではないことも見えてきた。さらに、一生のほとんどを終えたベテルギウスは、間もなく大爆発し壮絶な最期をとげるという。超新星爆発だ。その時、地球では何が起きるのか? 世界中の科学者が注目する赤い巨星ベテルギウスに迫る。
http://www.nhk.or.jp/space/program/cosmic.html
201○年という噂もあるけど、どうなんでしょうね
「爆発直前!?赤い巨星ベテルギウス」
オリオン座の赤い一等星「ベテルギウス」。その大きさは太陽の1000倍と巨大で、表面は紅蓮の炎で覆われている。しかも最新の観測から、太陽のような丸い形の星ではないことも見えてきた。さらに、一生のほとんどを終えたベテルギウスは、間もなく大爆発し壮絶な最期をとげるという。超新星爆発だ。その時、地球では何が起きるのか? 世界中の科学者が注目する赤い巨星ベテルギウスに迫る。
http://www.nhk.or.jp/space/program/cosmic.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
宇宙の外ってどうなってるの? 更新情報
-
最新のアンケート
宇宙の外ってどうなってるの?のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6474人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19244人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208299人
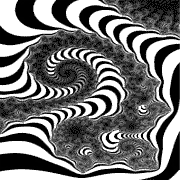






![[異説] 超古代文明 [オカルト]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/64/96/26496_6s.jpg)
















