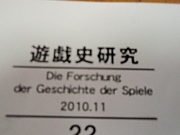|
|
|
|
コメント(44)
同じゲームでもコマはそれぞれの言語で表記
今日のミニ研究会で十六武蔵を商品化した遊具を拝見。
武蔵は宮本武蔵であり、他のコマは佐々木小次郎その他となっていました。
武蔵野両側の武士を切ることから、二刀流をイメージしたのでしょう。
武蔵に当たるコマをたこくでは、虎、狼、狐など、切られる側は 犬、羊、ガチョウなど・・・
日本の将棋の金将、銀将、銅将(いづれも鉱物)など、オリジナルは別の呼称なのでしょう。
玉将なのか王将なのか? 将はキングとひとしいのか疑問を呈しておきました。
王(キング)と将軍とは異なるとおもいましたので。
シャンチーでは 帥と将。チャンギでは 楚王と漢王。これらは明快納得できます。
今日のミニ研究会で十六武蔵を商品化した遊具を拝見。
武蔵は宮本武蔵であり、他のコマは佐々木小次郎その他となっていました。
武蔵野両側の武士を切ることから、二刀流をイメージしたのでしょう。
武蔵に当たるコマをたこくでは、虎、狼、狐など、切られる側は 犬、羊、ガチョウなど・・・
日本の将棋の金将、銀将、銅将(いづれも鉱物)など、オリジナルは別の呼称なのでしょう。
玉将なのか王将なのか? 将はキングとひとしいのか疑問を呈しておきました。
王(キング)と将軍とは異なるとおもいましたので。
シャンチーでは 帥と将。チャンギでは 楚王と漢王。これらは明快納得できます。
娘の名前で出ています。溝口です。
22日の研究会にそなえて予習をしておこうと『ものと人間の文化史59碁』(増川宏一)を再読、今まで気づかなかったことが2つありました。
一つは大発見かもしれないので、発表の機会ができれば目玉にしようと思っています。
もう一つは大型の将棋類はどれくらい流行したかについての手がかりです。
新参者の私と違い皆様には周知のことかもしれませんが、
P240「この三の巻に「俗手直鑑」として碁打の名前が多数記されている。」
P242「第二に、名簿は氏名の頭に印をつけ、○印は碁、将棋をともに能くする者で、とくに将棋は六、七段から三段程度までの優れた相手、△印は碁、将棋、双六(文字代替)に秀でた者、□印は中将棋、摩訶大将棋、泰将棋のできるものとしている。」
六種といわれる将棋のうち「大将棋」「大大将棋」の名前が出てこない!
駒の動きからの私の予想(ブログ:将棋の歴史(妄想))が裏付けられた気がします。
22日の研究会にそなえて予習をしておこうと『ものと人間の文化史59碁』(増川宏一)を再読、今まで気づかなかったことが2つありました。
一つは大発見かもしれないので、発表の機会ができれば目玉にしようと思っています。
もう一つは大型の将棋類はどれくらい流行したかについての手がかりです。
新参者の私と違い皆様には周知のことかもしれませんが、
P240「この三の巻に「俗手直鑑」として碁打の名前が多数記されている。」
P242「第二に、名簿は氏名の頭に印をつけ、○印は碁、将棋をともに能くする者で、とくに将棋は六、七段から三段程度までの優れた相手、△印は碁、将棋、双六(文字代替)に秀でた者、□印は中将棋、摩訶大将棋、泰将棋のできるものとしている。」
六種といわれる将棋のうち「大将棋」「大大将棋」の名前が出てこない!
駒の動きからの私の予想(ブログ:将棋の歴史(妄想))が裏付けられた気がします。
こんなシンポジウムがあります。ご興味のあるかたどうぞ
以前、将棋の歴史のシンポジウムのあった場所です
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[sigch:00022] 「日本の歴史的時空間情報の現在」
YAMADA Shoji <shoji@nichibun.ac.jp>
SIGCHメーリングリストのみなさま
日文研の山田です。
来週末のシンポジウムについて、再度のご案内をいたします。厳しい気候がつづ
いておりますが、ご参加くだされば幸いです。
シンポジウム「日本の歴史的時空間情報の現在」
開催趣旨:
地理情報システム(GIS)が社会の各方面で活用されていくなか、
歴史や文化の研究にその技術を適用することで研究の新しい地平を
拓く、歴史地理情報システム(H-GIS)の試みが芽生えつつありま
す。H-GIS研究をさらに展開するためには、その基盤となる歴史的
地理情報を電子化し、情報資源として共有していかなければなりま
せん。その上に立って、H-GISでどのような研究が可能になるのか
を議論する必要があるでしょう。本シンポジウムでは、日本の歴史
的時空間情報に焦点を当て、H-GISのための情報資源作成の動向と、
電子化された情報をもとにした研究事例を紹介し、これからの方向
性について議論します。
日時:平成22年9月11日(土)13:30〜18:05
会場:国際日本文化研究センター・第1セミナー室
交通案内:http://www.nichibun.ac.jp/info/access.html
事前申込み不要・聴講無料
プログラム
13:30〜13:35
13:35〜14:15
基調講演:村山 祐司(筑波大)
「GISを活用した歴史統計の時空間分析」
(地理情報システム(GIS)が社会の各方面で活用されていくなか、
歴史や文化の研究にその技術を適用することで研究の新しい地平
を拓く、歴史地理情報システム(H-GIS)の試みが芽生えつつあ
る。H-GIS研究をさらに展開するためには、その基盤となる歴史的
地理情報を電子化し、情報資源として共有していかなければなら
ない。その上に立って、H-GISでどのような研究が可能になるのか
を議論する必要があろう。本シンポジウムでは、日本の歴史的時
空間情報に焦点を当て、H-GISのための情報資源作成の動向と、電
子化された情報をもとにした研究事例を紹介し、これからの方向
性について議論する。)
14:20〜16:00
第1部 歴史的地理情報の作成
司会:川口 洋(帝塚山大)
発表者:
山田 奨治(日文研)「近代地図の電子化の状況について」
(日文研・山田研究室にて進めてきた、近代地図の電子化の進行
状況について発表する。)
森 洋久(日文研)「日文研の時空間情報をベースとしたデータ
ベース構築」
(長年にわたって様々な手法で構築されてきた日文研の数十種類
のデータベースを、時空間情報をベースに統一的な手法で再構築
を行う計画である。その目標と方法について発表する。)
関野 樹(地球研)「研究資源共有化事業(人文機構)の時空間
システムについて」
(人間文化研究機構の研究資源共有化事業および関連事業で構築
が進められている地名辞書等の基盤情報および時空間解析ツール
について報告する。)
コメンテータ:矢野 桂司(立命館大)、小方 登(京都大)
16:00〜16:20 休憩
16:20〜18:00 第2部 情報資源の分析からみえてくること
司会:尾方隆幸(琉球大)
発表者:中西 和子(日文研)「編纂経緯からみる古事類苑・地部―2人
の編集者、三浦千畝と加藤才次郎―」
(古事類苑・地部は、明治38〜40に三浦千畝・加藤才次郎により
作成された。2名の担当部分、および頻出典拠文献について報告
する。)
相田 満(国文研)「歴史地名のオントロジとGIS―『大日本
地名辞書』を腑分けして見えてくるもの―」
(文化的産物たる「地名」の分析には、オントロジにおける上位
概念の「場所」とは、位相の異なる発想が必要で、時に意外な様
相も見せてくれる。)
出田 和久(奈良女子大)「条里・条坊関連史料データベースに
ついて」
(GISを利用し、条里・条坊関連文献史料に含まれる地理情報を
統合したデータベースの構築の目的と現況について報告する。)
コメンテータ:柴山 守(京大)、波江 彰彦(大阪大)
18:00〜18:05
間データマイニングのための基盤
整備」(代表者:山田奨治)
問い合わせ先:
国際日本文化研究センター・研究部・山田研究室(担当:中西)
電話:075−335−2100(内線3405)
ファックス:075−335−2090
YAMADA Shoji, Ph.D.
Associate Professor
山田 奨治
大学共同利用機関法人・人間文化研究機構
国際日本文化研究センター・研究部
〒610-1192 京都市西京区御陵大枝山町3−2
以前、将棋の歴史のシンポジウムのあった場所です
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[sigch:00022] 「日本の歴史的時空間情報の現在」
YAMADA Shoji <shoji@nichibun.ac.jp>
SIGCHメーリングリストのみなさま
日文研の山田です。
来週末のシンポジウムについて、再度のご案内をいたします。厳しい気候がつづ
いておりますが、ご参加くだされば幸いです。
シンポジウム「日本の歴史的時空間情報の現在」
開催趣旨:
地理情報システム(GIS)が社会の各方面で活用されていくなか、
歴史や文化の研究にその技術を適用することで研究の新しい地平を
拓く、歴史地理情報システム(H-GIS)の試みが芽生えつつありま
す。H-GIS研究をさらに展開するためには、その基盤となる歴史的
地理情報を電子化し、情報資源として共有していかなければなりま
せん。その上に立って、H-GISでどのような研究が可能になるのか
を議論する必要があるでしょう。本シンポジウムでは、日本の歴史
的時空間情報に焦点を当て、H-GISのための情報資源作成の動向と、
電子化された情報をもとにした研究事例を紹介し、これからの方向
性について議論します。
日時:平成22年9月11日(土)13:30〜18:05
会場:国際日本文化研究センター・第1セミナー室
交通案内:http://www.nichibun.ac.jp/info/access.html
事前申込み不要・聴講無料
プログラム
13:30〜13:35
13:35〜14:15
基調講演:村山 祐司(筑波大)
「GISを活用した歴史統計の時空間分析」
(地理情報システム(GIS)が社会の各方面で活用されていくなか、
歴史や文化の研究にその技術を適用することで研究の新しい地平
を拓く、歴史地理情報システム(H-GIS)の試みが芽生えつつあ
る。H-GIS研究をさらに展開するためには、その基盤となる歴史的
地理情報を電子化し、情報資源として共有していかなければなら
ない。その上に立って、H-GISでどのような研究が可能になるのか
を議論する必要があろう。本シンポジウムでは、日本の歴史的時
空間情報に焦点を当て、H-GISのための情報資源作成の動向と、電
子化された情報をもとにした研究事例を紹介し、これからの方向
性について議論する。)
14:20〜16:00
第1部 歴史的地理情報の作成
司会:川口 洋(帝塚山大)
発表者:
山田 奨治(日文研)「近代地図の電子化の状況について」
(日文研・山田研究室にて進めてきた、近代地図の電子化の進行
状況について発表する。)
森 洋久(日文研)「日文研の時空間情報をベースとしたデータ
ベース構築」
(長年にわたって様々な手法で構築されてきた日文研の数十種類
のデータベースを、時空間情報をベースに統一的な手法で再構築
を行う計画である。その目標と方法について発表する。)
関野 樹(地球研)「研究資源共有化事業(人文機構)の時空間
システムについて」
(人間文化研究機構の研究資源共有化事業および関連事業で構築
が進められている地名辞書等の基盤情報および時空間解析ツール
について報告する。)
コメンテータ:矢野 桂司(立命館大)、小方 登(京都大)
16:00〜16:20 休憩
16:20〜18:00 第2部 情報資源の分析からみえてくること
司会:尾方隆幸(琉球大)
発表者:中西 和子(日文研)「編纂経緯からみる古事類苑・地部―2人
の編集者、三浦千畝と加藤才次郎―」
(古事類苑・地部は、明治38〜40に三浦千畝・加藤才次郎により
作成された。2名の担当部分、および頻出典拠文献について報告
する。)
相田 満(国文研)「歴史地名のオントロジとGIS―『大日本
地名辞書』を腑分けして見えてくるもの―」
(文化的産物たる「地名」の分析には、オントロジにおける上位
概念の「場所」とは、位相の異なる発想が必要で、時に意外な様
相も見せてくれる。)
出田 和久(奈良女子大)「条里・条坊関連史料データベースに
ついて」
(GISを利用し、条里・条坊関連文献史料に含まれる地理情報を
統合したデータベースの構築の目的と現況について報告する。)
コメンテータ:柴山 守(京大)、波江 彰彦(大阪大)
18:00〜18:05
間データマイニングのための基盤
整備」(代表者:山田奨治)
問い合わせ先:
国際日本文化研究センター・研究部・山田研究室(担当:中西)
電話:075−335−2100(内線3405)
ファックス:075−335−2090
YAMADA Shoji, Ph.D.
Associate Professor
山田 奨治
大学共同利用機関法人・人間文化研究機構
国際日本文化研究センター・研究部
〒610-1192 京都市西京区御陵大枝山町3−2
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
元・遊戯史学会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
元・遊戯史学会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90040人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6421人
- 3位
- 独り言
- 9045人