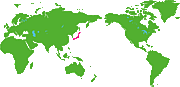・地域政党・大阪維新の会代表の橋下徹・前大阪府知事
http://
橋下氏が圧勝で、大阪市長となりました。
これで、大阪都構想が実現しやすくなると予想されます。
大阪はどうなるのでしょうか!!
アフリカの春じゃないですが、(規模は府、県ですが)京都、兵庫にも波及するかも!?
何れにせよ、しっかり議論してよりよい方向へ進んでいきたいですね。
【日本維新の会】
公約原案
【基本理念】
・「自立」個人、地域、国家の自立。「自由」あらゆる既得権益を打破。「保守」皇室を尊び、日本の歴史と伝統を尊重する。
【憲法改正による統治機構改革】
・任期4年の首相公選制。道州制によるガバナンス改革を行い、道州に課税権を移譲する。政権公約など重要項目以外は政党の党議拘束を外す。
【行財政改革】
・衆院定数を240人に削減、歳費などの経費も3割削減。キャリア官僚の40歳定年制。各省庁の課長級以上の幹部も年俸制の政治任用。
【外交・防衛】
・日本固有領土の竹島、尖閣諸島、北方4島については、妥協しない。国連安全保障理事会の常任理事国入り。集団的自衛権の憲法解釈を変更し、法整備を行う。2045年を目標に外国軍の国内駐留を全廃。日本全体で沖縄負担の軽減を図るロードマップを作成する。
【経済・雇用・税制】
・日銀に100兆円規模の「経済復興基金」設置。環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉に参加、自由貿易協定(FTA)拡大。法人税率を半減。負の所得税・ベーシックインカム(国民への最低生活保障)的な考え方を導入。
【社会保障制度改革】
・年金は積み立て方式に移行。高齢者向けの社会保障関係費の圧縮。歳入庁を設置。
【農業】
・農業版整理回収機構の設置。戸別所得補償制度は専業農家に限定。
【エネルギー】
・既設の原子炉を持つ原発は2030年代までに全廃。安全性の高い「世界最高水準の原発」は輸出。
【教育改革】
・日本の歴史と伝統に誇りを持てる歴史教育を行う。教育委員会制度の廃止。
http://
http://
橋下氏が圧勝で、大阪市長となりました。
これで、大阪都構想が実現しやすくなると予想されます。
大阪はどうなるのでしょうか!!
アフリカの春じゃないですが、(規模は府、県ですが)京都、兵庫にも波及するかも!?
何れにせよ、しっかり議論してよりよい方向へ進んでいきたいですね。
【日本維新の会】
公約原案
【基本理念】
・「自立」個人、地域、国家の自立。「自由」あらゆる既得権益を打破。「保守」皇室を尊び、日本の歴史と伝統を尊重する。
【憲法改正による統治機構改革】
・任期4年の首相公選制。道州制によるガバナンス改革を行い、道州に課税権を移譲する。政権公約など重要項目以外は政党の党議拘束を外す。
【行財政改革】
・衆院定数を240人に削減、歳費などの経費も3割削減。キャリア官僚の40歳定年制。各省庁の課長級以上の幹部も年俸制の政治任用。
【外交・防衛】
・日本固有領土の竹島、尖閣諸島、北方4島については、妥協しない。国連安全保障理事会の常任理事国入り。集団的自衛権の憲法解釈を変更し、法整備を行う。2045年を目標に外国軍の国内駐留を全廃。日本全体で沖縄負担の軽減を図るロードマップを作成する。
【経済・雇用・税制】
・日銀に100兆円規模の「経済復興基金」設置。環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉に参加、自由貿易協定(FTA)拡大。法人税率を半減。負の所得税・ベーシックインカム(国民への最低生活保障)的な考え方を導入。
【社会保障制度改革】
・年金は積み立て方式に移行。高齢者向けの社会保障関係費の圧縮。歳入庁を設置。
【農業】
・農業版整理回収機構の設置。戸別所得補償制度は専業農家に限定。
【エネルギー】
・既設の原子炉を持つ原発は2030年代までに全廃。安全性の高い「世界最高水準の原発」は輸出。
【教育改革】
・日本の歴史と伝統に誇りを持てる歴史教育を行う。教育委員会制度の廃止。
http://
|
|
|
|
コメント(52)
まさはるさん
>橋下氏は大阪を変えるためのステップとして選挙をとらえているが平松氏は
>どうやって当選するかしか考えていないように感じる。
自分もそう思います。
今回の選挙は維新の会の政策がどうかを問う選挙かなと思いました。
自分の理解が間違っているかもしれないのでその時はご指摘頂きたいですが、
橋本氏が言っている大阪都構想とは、
大阪府が大阪府機能と大阪市機能の両方の機能を持つということでしょうか。
で大阪市は8〜9区として大阪府の管轄になる。
つまり東京都と同じで、
東京都は23区の市役所になるし、東京都の市の県庁の機能にもなる。
大きいことをするにも大阪府と大阪市の2つの勢力により進みにくい。
といったところでしょうか。
確かに大阪府(都?)のリーダシップが問われますが、
自分は、
責任があいまい民主主義よりは、選んだ自分の責任が見えやすい民主主義の方が
今後の日本にとって良い方向かと思います。
近年、政治が庶民から遠ざかっていた(ざけていた、ざかるをえなかった!?)
のを身近にしていく良い機会とも思います。
>橋下氏は大阪を変えるためのステップとして選挙をとらえているが平松氏は
>どうやって当選するかしか考えていないように感じる。
自分もそう思います。
今回の選挙は維新の会の政策がどうかを問う選挙かなと思いました。
自分の理解が間違っているかもしれないのでその時はご指摘頂きたいですが、
橋本氏が言っている大阪都構想とは、
大阪府が大阪府機能と大阪市機能の両方の機能を持つということでしょうか。
で大阪市は8〜9区として大阪府の管轄になる。
つまり東京都と同じで、
東京都は23区の市役所になるし、東京都の市の県庁の機能にもなる。
大きいことをするにも大阪府と大阪市の2つの勢力により進みにくい。
といったところでしょうか。
確かに大阪府(都?)のリーダシップが問われますが、
自分は、
責任があいまい民主主義よりは、選んだ自分の責任が見えやすい民主主義の方が
今後の日本にとって良い方向かと思います。
近年、政治が庶民から遠ざかっていた(ざけていた、ざかるをえなかった!?)
のを身近にしていく良い機会とも思います。
どうも大規模自治体と小規模自治体でのインフラ整備やらで揉めてるみたいですね。
僕個人の考えは小規模自治体の方が効率良くできると思います。
各都道府県が都市化していくに連れて、市町村の合併が出てくることがありますが、合併を行うと都市部の問題に行政が追われて、末端部分を放置せざるを得ない(若い人は上京して老人ばかりが残り廃村になるなど)。という状態が頻発している印象があります。
また、合併を持ちかけられて断った村として姫島村を例に挙げますが、この島では住民の12人に1人が村の職員で、(1970年代当時としてはかなり新しい手法)ワークシェアリングを行い雇用を守り、インフラ整備も自治体が小規模だからこそ管理しやすい状態です。この村では互いが互いの顔を知っている人も多く、横の繋がりも幅広いです。ゆえに、いわゆる無縁社会などの現代社会特有の問題も少なく、介護などの一部も住民が支える状態です。
こういったことはやはり小規模自治体ならではの為せることだと思います。同時に、ある程度の能力を有する指導者が必要であるという条件が求められるのが一つの課題だと思います。
また、地域再生型の政治として、加藤紘一議員の話を参考に取り上げます。ハト派と言われ売国奴と罵られた方ですが、この点においてはかなりしっかりしたビジョンを持っていたのでその一部を紹介します。
加藤議員は、私が先ほども述べた横のつながりというものを重視しています。例えば、昔であれば橋梁が壊れたならばそこの住民たちが、そこの大工と協力して橋を直したりしていたわけですが、今ではそれが国の仕事になっています。加藤議員はこれを「国が地域のつながりをなくした」と捉えていました。
実際、橋梁の修理だけでなく文化財の保管や川の治水などといったものは、昔はかなり自治体と住民の間に密接な関係がありましたが、現在では希薄であるように思います。社会がアノミー化し、自己が画一化されている現代において重要なことだと思います。
ちなみに加藤議員はこの対策としてNPO法人の活動を盛んにすることを挙げていました。
私の考えとしてはもう一つあって、社会学において「社会水準の法則」というものがあります。これは、「集団はその人数に比例して質が落ちる」というものです。
これらのことから、都道府県という単位で見た時の地方分権でも、大阪という単位で見れば中央集権的で大規模なため、都構想に反対します。
僕個人の考えは小規模自治体の方が効率良くできると思います。
各都道府県が都市化していくに連れて、市町村の合併が出てくることがありますが、合併を行うと都市部の問題に行政が追われて、末端部分を放置せざるを得ない(若い人は上京して老人ばかりが残り廃村になるなど)。という状態が頻発している印象があります。
また、合併を持ちかけられて断った村として姫島村を例に挙げますが、この島では住民の12人に1人が村の職員で、(1970年代当時としてはかなり新しい手法)ワークシェアリングを行い雇用を守り、インフラ整備も自治体が小規模だからこそ管理しやすい状態です。この村では互いが互いの顔を知っている人も多く、横の繋がりも幅広いです。ゆえに、いわゆる無縁社会などの現代社会特有の問題も少なく、介護などの一部も住民が支える状態です。
こういったことはやはり小規模自治体ならではの為せることだと思います。同時に、ある程度の能力を有する指導者が必要であるという条件が求められるのが一つの課題だと思います。
また、地域再生型の政治として、加藤紘一議員の話を参考に取り上げます。ハト派と言われ売国奴と罵られた方ですが、この点においてはかなりしっかりしたビジョンを持っていたのでその一部を紹介します。
加藤議員は、私が先ほども述べた横のつながりというものを重視しています。例えば、昔であれば橋梁が壊れたならばそこの住民たちが、そこの大工と協力して橋を直したりしていたわけですが、今ではそれが国の仕事になっています。加藤議員はこれを「国が地域のつながりをなくした」と捉えていました。
実際、橋梁の修理だけでなく文化財の保管や川の治水などといったものは、昔はかなり自治体と住民の間に密接な関係がありましたが、現在では希薄であるように思います。社会がアノミー化し、自己が画一化されている現代において重要なことだと思います。
ちなみに加藤議員はこの対策としてNPO法人の活動を盛んにすることを挙げていました。
私の考えとしてはもう一つあって、社会学において「社会水準の法則」というものがあります。これは、「集団はその人数に比例して質が落ちる」というものです。
これらのことから、都道府県という単位で見た時の地方分権でも、大阪という単位で見れば中央集権的で大規模なため、都構想に反対します。
> まさはるさん
明確に書くべきでしたね。
総合的な意味での質です。
例えば労働で言えば、就労態度が真面目か不真面目か、無断遅刻・欠勤の有無、管理は行き届いているか。
みたいな話になりますね。
労働に限定した話ではありませんが。
多数の働きアリの7割がサボっているのと似た仕組みです。
勉強で言えば、1人の教員につく生徒数が増すほど、生徒の成績が下がりやすい傾向などもあります(下限はあるそうですが)。
簡潔に説明するとこういった仕組みがあらゆる社会集団に適用されるように示されたのが社会水準の法則です。
なので、小規模な自治体を多数作ってそれらに権限を与え、互いに監視できるシステムが理想だと思います。
明確に書くべきでしたね。
総合的な意味での質です。
例えば労働で言えば、就労態度が真面目か不真面目か、無断遅刻・欠勤の有無、管理は行き届いているか。
みたいな話になりますね。
労働に限定した話ではありませんが。
多数の働きアリの7割がサボっているのと似た仕組みです。
勉強で言えば、1人の教員につく生徒数が増すほど、生徒の成績が下がりやすい傾向などもあります(下限はあるそうですが)。
簡潔に説明するとこういった仕組みがあらゆる社会集団に適用されるように示されたのが社会水準の法則です。
なので、小規模な自治体を多数作ってそれらに権限を与え、互いに監視できるシステムが理想だと思います。
> まさはるさん
島根県と大阪や東京を比較したのは県議会や府議会などの議員数でしょうか?
もしそうでしたら今私が論じたい部分と意味合いが異なるのでコメントは差し控えます。
私の話したい部分は、府や市より更に小さい単位の自治体に権限を与えるとよいのではないか、ということです。
集団の規模が小さいほど、(自治体に限らず)個人差はあれど集団を構成する要素が互いの関係を密にしやすく、管理も届きやすいです。
逆に合併などで大きくなれば、>015で述べたように、管理の行き届かない末端の部分が廃れやすくなっていきます。
橋梁の修理の例など、実行しようとすれば必然的に住民への負担は大きくなりがちですが、そこで自治体と住民が協力できるような関係を築くことが重要だと思います。
島根県と大阪や東京を比較したのは県議会や府議会などの議員数でしょうか?
もしそうでしたら今私が論じたい部分と意味合いが異なるのでコメントは差し控えます。
私の話したい部分は、府や市より更に小さい単位の自治体に権限を与えるとよいのではないか、ということです。
集団の規模が小さいほど、(自治体に限らず)個人差はあれど集団を構成する要素が互いの関係を密にしやすく、管理も届きやすいです。
逆に合併などで大きくなれば、>015で述べたように、管理の行き届かない末端の部分が廃れやすくなっていきます。
橋梁の修理の例など、実行しようとすれば必然的に住民への負担は大きくなりがちですが、そこで自治体と住民が協力できるような関係を築くことが重要だと思います。
> KGBtokyoさん
まあ、地方交付税の使い方にもこれまで問題がありましたから、今が当たり前なのかもしれません。10年くらい前は国に金がないと陳情しながら、自らは国の1割増しくらいの給与を得ていたわけですから。今は東京都以外は国の水準に近付いていますが、大阪市をはじめとする政令指定都市の職員給与だけがやたら高いという現象が未だに続いています。ちなみに大阪府の人件費に対する自主財源率は40%程度にとどまっています。一方の大阪市は24%程度とふざけたことになっていますが、他の政令指定都市も似たりよったり。自治労をバックに持つ地方公務員天国を改革することはまだまだ難しそうですね。
ただ、それを考えると、都道府県に権限を集中させるやり方は中央集権よりも遥かに問題が多いように思います。
まあ、地方交付税の使い方にもこれまで問題がありましたから、今が当たり前なのかもしれません。10年くらい前は国に金がないと陳情しながら、自らは国の1割増しくらいの給与を得ていたわけですから。今は東京都以外は国の水準に近付いていますが、大阪市をはじめとする政令指定都市の職員給与だけがやたら高いという現象が未だに続いています。ちなみに大阪府の人件費に対する自主財源率は40%程度にとどまっています。一方の大阪市は24%程度とふざけたことになっていますが、他の政令指定都市も似たりよったり。自治労をバックに持つ地方公務員天国を改革することはまだまだ難しそうですね。
ただ、それを考えると、都道府県に権限を集中させるやり方は中央集権よりも遥かに問題が多いように思います。
> シモーネさん
基本的に日本のような小さな国であれば国と市町村で成り立つと思います。元々、都道府県は国が地方を監視するために設けた制度であり、旧内務省(戦後自治省、現在総務省)の管轄にあった機関です。しかしながら戦後の地方分権の流れで国からは独立しましたが、未だに国の下請業務(法定受託事務)がかなりのウェートを占めています。つまり住民自治を行うための組織ではないわけです。一方市町村はまさに住民に身近な行政であり、住民自治を行うための組織です。
都道府県では国のような広域的な行政にも、市町村のような自治行政にも馴染まず単なる権力闘争の温床になっているように思います。都道府県同士の権益争いはよくありますし。これを主役にし、市町村の権限及び国の出先機関の権限を集中させることは無意味であり、権益争いの頻発を招くだけではないかと思います。以上のことから、中途半端な存在である都道府県を廃止し、国と市町村の2層化にすることは合理的であると思います。
基本的に日本のような小さな国であれば国と市町村で成り立つと思います。元々、都道府県は国が地方を監視するために設けた制度であり、旧内務省(戦後自治省、現在総務省)の管轄にあった機関です。しかしながら戦後の地方分権の流れで国からは独立しましたが、未だに国の下請業務(法定受託事務)がかなりのウェートを占めています。つまり住民自治を行うための組織ではないわけです。一方市町村はまさに住民に身近な行政であり、住民自治を行うための組織です。
都道府県では国のような広域的な行政にも、市町村のような自治行政にも馴染まず単なる権力闘争の温床になっているように思います。都道府県同士の権益争いはよくありますし。これを主役にし、市町村の権限及び国の出先機関の権限を集中させることは無意味であり、権益争いの頻発を招くだけではないかと思います。以上のことから、中途半端な存在である都道府県を廃止し、国と市町村の2層化にすることは合理的であると思います。
都構想は争点ではあるがあくまで争点のひとつでしかない。
自治体として大がいいのか小がいいのかってことと誰に投票するかを関連させて考えてる人はそう多くないと思います。
公務員改革をもっと進めてほしいと考えてたり正義感の強い人は橋下氏を好むだろうし一方、市職員はたいてい平松氏に投票するでしょう。
個人的には平松氏への不信感が強い。
もともとは民主党の後ろ楯で公務員を味方にして当選したのに民主党の風向きが悪くなれば完全無所属で出馬すると言い出し、それでは勝てないと思ったら民主党どころか自民党や共産党まで手を伸ばす。
なんなんだ。この一貫性の無さは。見事なまでの節操の無さ。
自民党と民主党と共産党の共通点は難しいですよ。もし当選したらどうやってやりくりするのか見てみたいが(笑)
当選することに必死になる男と大阪をよくすることに必死になる男の戦い。
選挙の目的が違うんだよなあ。
自治体として大がいいのか小がいいのかってことと誰に投票するかを関連させて考えてる人はそう多くないと思います。
公務員改革をもっと進めてほしいと考えてたり正義感の強い人は橋下氏を好むだろうし一方、市職員はたいてい平松氏に投票するでしょう。
個人的には平松氏への不信感が強い。
もともとは民主党の後ろ楯で公務員を味方にして当選したのに民主党の風向きが悪くなれば完全無所属で出馬すると言い出し、それでは勝てないと思ったら民主党どころか自民党や共産党まで手を伸ばす。
なんなんだ。この一貫性の無さは。見事なまでの節操の無さ。
自民党と民主党と共産党の共通点は難しいですよ。もし当選したらどうやってやりくりするのか見てみたいが(笑)
当選することに必死になる男と大阪をよくすることに必死になる男の戦い。
選挙の目的が違うんだよなあ。
>たけさん
なるほどです。
そういうことであれば都構想など意味はないという考えに至りますね。
市は自治体として市役所だと事務処理等ありますが、
逆に県は何をしているんでしょうか?
市の役割、県の役割ってなんなのかなってwikiってもちょっとわかりにくかったですね。
県ってアメリカとかなら州にあたるのでしょうか。
>まさはるさん
おっしゃられる通り、
正直、今回の選挙は維新の会の政策がどうかを問う選挙かなと思いました。
平松氏を選ぶ=今までと変えない。 みたいな感じですかね。
で、自分は平松氏を選びません。
自分は政党政治もあまり良いとは思ってません。
結論を出す際に多数決に勝つ為に思えるからです。民主主義をうまく出来てない感じです。
できるなら議論をして星取り表等を作り考えを詰め込んだ上で対応策を選ぶ
ように出来たらなぁと思います。政党関係なしに正しいと思った方向を選ぶ。
政党で考えをまとめてもわかりますが、政党で勝つ為に議会をやっているわけではなく、
よりよい方向へ進める為の議論の場であるべきかなと思います。
横道それますが民主(首相)がTPP参加とした時に自民はで反対姿勢を出したと
思いますが、自民が与党だったとしてもTPP参加をしたように思います。
うまく説明出来ないですがなんかそんな気がします。
なるほどです。
そういうことであれば都構想など意味はないという考えに至りますね。
市は自治体として市役所だと事務処理等ありますが、
逆に県は何をしているんでしょうか?
市の役割、県の役割ってなんなのかなってwikiってもちょっとわかりにくかったですね。
県ってアメリカとかなら州にあたるのでしょうか。
>まさはるさん
おっしゃられる通り、
正直、今回の選挙は維新の会の政策がどうかを問う選挙かなと思いました。
平松氏を選ぶ=今までと変えない。 みたいな感じですかね。
で、自分は平松氏を選びません。
自分は政党政治もあまり良いとは思ってません。
結論を出す際に多数決に勝つ為に思えるからです。民主主義をうまく出来てない感じです。
できるなら議論をして星取り表等を作り考えを詰め込んだ上で対応策を選ぶ
ように出来たらなぁと思います。政党関係なしに正しいと思った方向を選ぶ。
政党で考えをまとめてもわかりますが、政党で勝つ為に議会をやっているわけではなく、
よりよい方向へ進める為の議論の場であるべきかなと思います。
横道それますが民主(首相)がTPP参加とした時に自民はで反対姿勢を出したと
思いますが、自民が与党だったとしてもTPP参加をしたように思います。
うまく説明出来ないですがなんかそんな気がします。
小規模自治体の何が良いのですか?
まだ強力な中央集権の下、日常的末梢的問題だけ行うなら判りますが、地方分権+小規模自治体というのは最悪のパターンでしょう。
まずコスト面で言えば、市町村議会始め管理部門のコスト負担は小規模ほど負担が大きくなりますし、人員の効果的運用〔配置転換)も可能になります。
また江戸時代とは比較ならない交通通信情報の発達により、人の活動範囲は拡大しております。
少なくとも自治体単位と言うのは住にプラス職・学が同一地域に含まれることが重要です。
さらに行政監視にしても、小規模自治体ではマスメディアはもとより、ネット情報も極めて限られ一般住民のよる監視もできない。
結局は暇な左右プロ市民や特定団体と行政の癒着が起きる。
まだ強力な中央集権の下、日常的末梢的問題だけ行うなら判りますが、地方分権+小規模自治体というのは最悪のパターンでしょう。
まずコスト面で言えば、市町村議会始め管理部門のコスト負担は小規模ほど負担が大きくなりますし、人員の効果的運用〔配置転換)も可能になります。
また江戸時代とは比較ならない交通通信情報の発達により、人の活動範囲は拡大しております。
少なくとも自治体単位と言うのは住にプラス職・学が同一地域に含まれることが重要です。
さらに行政監視にしても、小規模自治体ではマスメディアはもとより、ネット情報も極めて限られ一般住民のよる監視もできない。
結局は暇な左右プロ市民や特定団体と行政の癒着が起きる。
> シモーネさん
はい。自分はこの国には政党政治は無理だと思います。
政策や思想が同じ人が集まるのではなく、ただ人数を増やしたいってのがこの国の政党政治です。
もっと言えば政治家には年俸制を導入したい。
当選をスタートだと考える橋下氏のような人と当選をゴールだと考える平松一味みたいな輩がいるからです。
自分はこれまで日本人に政治は無理だと考えてました。
アメリカの大統領に日本の総理を兼務してもらう方がマシじゃないかとまで思ったこともありました。
今までの政治家で信用できる国会議員は西川きよしだけでしたから。
そこに出てきた橋下さん。期待しない方がおかしいでしょ。
ところで平松一味に所属する倉田候補って橋下氏の方向性に最初は賛成って言ってなかったっけ?
はい。自分はこの国には政党政治は無理だと思います。
政策や思想が同じ人が集まるのではなく、ただ人数を増やしたいってのがこの国の政党政治です。
もっと言えば政治家には年俸制を導入したい。
当選をスタートだと考える橋下氏のような人と当選をゴールだと考える平松一味みたいな輩がいるからです。
自分はこれまで日本人に政治は無理だと考えてました。
アメリカの大統領に日本の総理を兼務してもらう方がマシじゃないかとまで思ったこともありました。
今までの政治家で信用できる国会議員は西川きよしだけでしたから。
そこに出てきた橋下さん。期待しない方がおかしいでしょ。
ところで平松一味に所属する倉田候補って橋下氏の方向性に最初は賛成って言ってなかったっけ?
>>シモーネさん
都道府県の事務はおおまかに分類すれば二種類あります。上記で都道府県は自治事務に馴染まないと申し上げましたが、都道府県でも自治事務を行っています。この自治事務とは本来地方公共団体(都道府県)が行うべき事務を指します。しかしながら都道府県の場合はこの自治事務よりも法定受託事務が上回っています。この法定受託事務とは本来、国が行うべき事務を都道府県に委託しているものです。都道府県の設立経緯からしても、都道府県ではどちらかというと国からの法定受託事務(かつての機関委任事務)を行っていることでお馴染であると思います。
この事務の具体例は、例えば国政選挙に関する事務、旅券(パスポート)の発券事務、生活保護事務、家畜伝染病防止、治水・治山・砂防、都市計画関係、国道管理、一級・二級管理、自衛隊広報、国定公園管理、環境に関する事務など色々あります。
ちなみに都道府県から市町村に委託している事務もあります。しかしながら市町村は都道府県の下請けとして設置されているものではないため、どちらかというと住民自治に根付いた自治事務の色彩が強いと言えるでしょう。
要するに都道府県は国と市町村の間の調整役であり、市町村では力が足りない部分の調整や国で行う程の規模でない比較的小規模な事務を執行している機関です。しかしながら実際には、都道府県では規模が中途半端であるため、大規模な事業や災害等に対応できず、しばしば権益争いを起こしているようです。かつては国と市町村が直接やりとりすることがなかったようですが、平成12年で形式上は国と市町村も対等になりましたので、都道府県の存在意義はいよいよ薄れました。そこで生まれた議論が都道府県廃止のための道州制だったわけです。これを権限にしがみつく知事会の連中が国の出先機関廃止とすり替え、地域主権というよく分からない方針に転換させたわけです。
以上のことから、都道府県では広域的な行政には不適であり、住民自治を行うには規模が大きく、非常に中途半端な存在となっているのが現状です。
東北大震災の際の件でも被災地の市長さんなどが都道府県が大規模な災害に全く機能しなかったことを発言しておられます。
都道府県の事務はおおまかに分類すれば二種類あります。上記で都道府県は自治事務に馴染まないと申し上げましたが、都道府県でも自治事務を行っています。この自治事務とは本来地方公共団体(都道府県)が行うべき事務を指します。しかしながら都道府県の場合はこの自治事務よりも法定受託事務が上回っています。この法定受託事務とは本来、国が行うべき事務を都道府県に委託しているものです。都道府県の設立経緯からしても、都道府県ではどちらかというと国からの法定受託事務(かつての機関委任事務)を行っていることでお馴染であると思います。
この事務の具体例は、例えば国政選挙に関する事務、旅券(パスポート)の発券事務、生活保護事務、家畜伝染病防止、治水・治山・砂防、都市計画関係、国道管理、一級・二級管理、自衛隊広報、国定公園管理、環境に関する事務など色々あります。
ちなみに都道府県から市町村に委託している事務もあります。しかしながら市町村は都道府県の下請けとして設置されているものではないため、どちらかというと住民自治に根付いた自治事務の色彩が強いと言えるでしょう。
要するに都道府県は国と市町村の間の調整役であり、市町村では力が足りない部分の調整や国で行う程の規模でない比較的小規模な事務を執行している機関です。しかしながら実際には、都道府県では規模が中途半端であるため、大規模な事業や災害等に対応できず、しばしば権益争いを起こしているようです。かつては国と市町村が直接やりとりすることがなかったようですが、平成12年で形式上は国と市町村も対等になりましたので、都道府県の存在意義はいよいよ薄れました。そこで生まれた議論が都道府県廃止のための道州制だったわけです。これを権限にしがみつく知事会の連中が国の出先機関廃止とすり替え、地域主権というよく分からない方針に転換させたわけです。
以上のことから、都道府県では広域的な行政には不適であり、住民自治を行うには規模が大きく、非常に中途半端な存在となっているのが現状です。
東北大震災の際の件でも被災地の市長さんなどが都道府県が大規模な災害に全く機能しなかったことを発言しておられます。
>たけさん
色々情報ありがとうございます。知らないこと(ワード)がいっぱいありました。
国も結局は組織で会社も一緒かなと。組織化する目的は指揮系統を統合し効率よく物事を進めるため。
会社でも組織の枠組みについてもベストを目標にしますが全てうまくいくことは先ずありません。ただその形はとりあえずはベターであって、徐々によりよくしていくしかありません。ま、何れにせよ完成はありませんが。
組織をうまく動かす為にはtopからしっかりしないといけない。
1.国政(対外、対内)がんばらないと(笑)
次に地方にどれだけの権限を委任するか
2.地方分権をどうするか。
権限が中央に集中しすぎはダメですが、
中央が弱くなりすぎてもまとまりがなくなる。
自分は組織である以上、top(国、中央)はしっかりするべきと考えます。
その上で、その下にある組織としては小さすぎず(県)、それなりの大きな組織、道州制がよいかと思います。
国規模での政策、州単位での政策、市単位での政策、町単位での政策という感じで。
理由としては、
1.国とそれなりに対等な位置になる為にそれなりの規模。
2.インフラも整ってることによる公務の最適化。
3.ある程度大きめの単位での最適化出来る。
心配点は、州都に行政を集中させないことかな。
国政も分散化を考えてみては?
何れにしても枠組みを変えてもよい政治が出来るかですけど。
何をするか。都構想とというか維新の会ではもし選挙に勝って枠組みを返れたとして、次に民衆にかかわるとことで何をするんでしょうかね。
色々情報ありがとうございます。知らないこと(ワード)がいっぱいありました。
国も結局は組織で会社も一緒かなと。組織化する目的は指揮系統を統合し効率よく物事を進めるため。
会社でも組織の枠組みについてもベストを目標にしますが全てうまくいくことは先ずありません。ただその形はとりあえずはベターであって、徐々によりよくしていくしかありません。ま、何れにせよ完成はありませんが。
組織をうまく動かす為にはtopからしっかりしないといけない。
1.国政(対外、対内)がんばらないと(笑)
次に地方にどれだけの権限を委任するか
2.地方分権をどうするか。
権限が中央に集中しすぎはダメですが、
中央が弱くなりすぎてもまとまりがなくなる。
自分は組織である以上、top(国、中央)はしっかりするべきと考えます。
その上で、その下にある組織としては小さすぎず(県)、それなりの大きな組織、道州制がよいかと思います。
国規模での政策、州単位での政策、市単位での政策、町単位での政策という感じで。
理由としては、
1.国とそれなりに対等な位置になる為にそれなりの規模。
2.インフラも整ってることによる公務の最適化。
3.ある程度大きめの単位での最適化出来る。
心配点は、州都に行政を集中させないことかな。
国政も分散化を考えてみては?
何れにしても枠組みを変えてもよい政治が出来るかですけど。
何をするか。都構想とというか維新の会ではもし選挙に勝って枠組みを返れたとして、次に民衆にかかわるとことで何をするんでしょうかね。
> シモーネさん
まずは公務員改革でしょう。
毎日のように市営地下鉄を利用していると私鉄との違いがよくわかります。
市営地下鉄の駅員は「御乗車ありがとうございます」とか「おはようございます」などはまず言わない。
私鉄は朝なんかうるさいくらいに叫んでいます。
地下鉄の「言わない」っていうレベルは言う駅員が少ないってレベルじゃない。私鉄の駅員はたいてい言いますが市営地下鉄はゼロに近い。
ただ突っ立っているだけって感じです。
彼らは地下鉄に乗る人を「乗客」とは見ていない。「利用者」だと捉えているのでしょう。
こんなことから改めないといけないのは情けない限りです。
大阪マラソンのときに平松市長は「地下鉄であちこち見て回った」と言ってましたが彼は気付かないんでしょうか。
見てる人は見てるとよく言いますが見えない人に市長を任せたくはないですねぇ。
まずは公務員改革でしょう。
毎日のように市営地下鉄を利用していると私鉄との違いがよくわかります。
市営地下鉄の駅員は「御乗車ありがとうございます」とか「おはようございます」などはまず言わない。
私鉄は朝なんかうるさいくらいに叫んでいます。
地下鉄の「言わない」っていうレベルは言う駅員が少ないってレベルじゃない。私鉄の駅員はたいてい言いますが市営地下鉄はゼロに近い。
ただ突っ立っているだけって感じです。
彼らは地下鉄に乗る人を「乗客」とは見ていない。「利用者」だと捉えているのでしょう。
こんなことから改めないといけないのは情けない限りです。
大阪マラソンのときに平松市長は「地下鉄であちこち見て回った」と言ってましたが彼は気付かないんでしょうか。
見てる人は見てるとよく言いますが見えない人に市長を任せたくはないですねぇ。
>>まさはるさん
まあ、公務員改革も必要ですが、難しいですよね。例えば東北大震災における自衛隊、警察、消防、海上保安庁、地方整備局などは国の管轄下で凄まじい奮闘をしました。特に自衛隊の活躍や東北地方整備局の道路復旧の早さは海外でも話題になったくらいです。官民が連携すれば凄まじい威力を発揮する。公務員もマイナスばかりではありません。公務員にしかできないサービス、役割があり、民間でしかできないものもあります。単純に官民比較することは難しいのではないでしょうか。
これと逆に同じ国の組織でありながら、経済産業省とその外局の保安院、東電は初動体制の遅れ、隠蔽などで混乱を招きました。官民連携と官民癒着ではこれだけ違うわけです。
腐った役所、腐った民間がある限り、どちらが正しいかってのは分かりませんよね。ただ、交通機関については確かに民営化した方が妥当かもしれません。国鉄も民営化されてサービスがかなり向上しました。おまけに職員の給与も跳ね上がったみたいです。逆に郵便局・・・これは民営化して不便になったように思いますね。
まあ、公務員改革も必要ですが、難しいですよね。例えば東北大震災における自衛隊、警察、消防、海上保安庁、地方整備局などは国の管轄下で凄まじい奮闘をしました。特に自衛隊の活躍や東北地方整備局の道路復旧の早さは海外でも話題になったくらいです。官民が連携すれば凄まじい威力を発揮する。公務員もマイナスばかりではありません。公務員にしかできないサービス、役割があり、民間でしかできないものもあります。単純に官民比較することは難しいのではないでしょうか。
これと逆に同じ国の組織でありながら、経済産業省とその外局の保安院、東電は初動体制の遅れ、隠蔽などで混乱を招きました。官民連携と官民癒着ではこれだけ違うわけです。
腐った役所、腐った民間がある限り、どちらが正しいかってのは分かりませんよね。ただ、交通機関については確かに民営化した方が妥当かもしれません。国鉄も民営化されてサービスがかなり向上しました。おまけに職員の給与も跳ね上がったみたいです。逆に郵便局・・・これは民営化して不便になったように思いますね。
>>シモーネさん
地方分権でどれだけ国から都道府県、都道府県から市町村へ権限を移譲するかは難しい問題ですね。
ちなみに今問題となっている大阪府と大阪市の件ですが、本来は都道府県と市町村というのは国と都道府県の関係にやや似ており、形式上は上下関係にありませんが、暗黙の上下関係にあります。国と都道府県の上下関係よりもそれは明確であると言えます。しかしそれでは住民自治に支障をきたすという意味で、住民数が一定数以上の大規模な市を政令指定都市、やや大規模なものを中核市、中規模なものを特例市に格上げし、都道府県の権限を移譲しているわけです。特に政令指定都市の場合は完全に道府県と同格であり、政令指定都市は本来府県が行うべき行政を独自に行うことができ、道府県はその他の市町村の管理を行うことになります。よって、実質的には政令指定都市の存在する道府県については政令指定都市の方が花形であり、権限も強いと言えるでしょう。このことからも道府県は形骸化しつつあります。ちなみに職員待遇も圧倒的に政令指定都市が上です。待遇面だけを考えるなら東京都>政令指定都市>特別区>その他市町村>道府県>国といった感じかもしれません。
こういうことから道府県の存在意義は次第に失われており、国と市町村の調整機能も失いつつあります。(今は国と市町村が対等になっていますので、中央とのパイプ役は国の出先機関と直接やりとりができるわけです。確か今回の震災でも県があてにならないということで、被災市町村が直接国とやり取りしたとの内容をどこかで見ました。)
一番良いのは市町村を合併し、政令指定都市や中核市を増加させ、行政の効率化を図ることです。そうすれば道府県は不要となります。そして広域的な利害調整が必要な案件については国が行えばよいというわけです。
地方分権でどれだけ国から都道府県、都道府県から市町村へ権限を移譲するかは難しい問題ですね。
ちなみに今問題となっている大阪府と大阪市の件ですが、本来は都道府県と市町村というのは国と都道府県の関係にやや似ており、形式上は上下関係にありませんが、暗黙の上下関係にあります。国と都道府県の上下関係よりもそれは明確であると言えます。しかしそれでは住民自治に支障をきたすという意味で、住民数が一定数以上の大規模な市を政令指定都市、やや大規模なものを中核市、中規模なものを特例市に格上げし、都道府県の権限を移譲しているわけです。特に政令指定都市の場合は完全に道府県と同格であり、政令指定都市は本来府県が行うべき行政を独自に行うことができ、道府県はその他の市町村の管理を行うことになります。よって、実質的には政令指定都市の存在する道府県については政令指定都市の方が花形であり、権限も強いと言えるでしょう。このことからも道府県は形骸化しつつあります。ちなみに職員待遇も圧倒的に政令指定都市が上です。待遇面だけを考えるなら東京都>政令指定都市>特別区>その他市町村>道府県>国といった感じかもしれません。
こういうことから道府県の存在意義は次第に失われており、国と市町村の調整機能も失いつつあります。(今は国と市町村が対等になっていますので、中央とのパイプ役は国の出先機関と直接やりとりができるわけです。確か今回の震災でも県があてにならないということで、被災市町村が直接国とやり取りしたとの内容をどこかで見ました。)
一番良いのは市町村を合併し、政令指定都市や中核市を増加させ、行政の効率化を図ることです。そうすれば道府県は不要となります。そして広域的な利害調整が必要な案件については国が行えばよいというわけです。
> たけさん
はい。もちろん官と民のすべてを単純比較はできません。
しかし比較できる部分は比較すればいいですし官が民に劣る部分は改めればいいわけです。
例えば個人情報の流出みたいな話でもデータを持ち帰ってなくしたなんて話は報道を見る限り公務員が圧倒的に多い。
僕があげた地下鉄職員の例で何が言いたいかと言うと、基本的に民と同じことをやっている場合は見習って改めなさいと言いたいのです。
ごく一部ですが民間との差を理解できている公務員さんもいらっしゃるようですが。
郵便局が民営化して不便になったというよりは普通になったと自分は考えています。
そりゃあコストと収支を無視して独占的に事業やっていればなんでも便利になりますよ。
それよりも民営化できるものはすべて民営化して不当な規制も取り払い、適正な価格を導入して法人税を納めさせたほうが国民の税負担が小さくなると思います。
試算はないので感覚的な話ですが。
郵便局に関しては民営化に反対していたのは郵政職員とその家族がほとんどでしたよ。
でもありえませんが身分は公務員のままで民営化するなら反対は減ったはずです。
それだけ今の公務員はおいしい。
会社員辞めて公務員になった人はたくさんいますが公務員辞めて会社員になった人には会ったことがありません。
はい。もちろん官と民のすべてを単純比較はできません。
しかし比較できる部分は比較すればいいですし官が民に劣る部分は改めればいいわけです。
例えば個人情報の流出みたいな話でもデータを持ち帰ってなくしたなんて話は報道を見る限り公務員が圧倒的に多い。
僕があげた地下鉄職員の例で何が言いたいかと言うと、基本的に民と同じことをやっている場合は見習って改めなさいと言いたいのです。
ごく一部ですが民間との差を理解できている公務員さんもいらっしゃるようですが。
郵便局が民営化して不便になったというよりは普通になったと自分は考えています。
そりゃあコストと収支を無視して独占的に事業やっていればなんでも便利になりますよ。
それよりも民営化できるものはすべて民営化して不当な規制も取り払い、適正な価格を導入して法人税を納めさせたほうが国民の税負担が小さくなると思います。
試算はないので感覚的な話ですが。
郵便局に関しては民営化に反対していたのは郵政職員とその家族がほとんどでしたよ。
でもありえませんが身分は公務員のままで民営化するなら反対は減ったはずです。
それだけ今の公務員はおいしい。
会社員辞めて公務員になった人はたくさんいますが公務員辞めて会社員になった人には会ったことがありません。
>>まさはるさん
確かに官が民に劣るべきところは見直すべきでしょうね。日本の官僚機構は優秀だが、有事に弱い。これは太平洋戦争の敗因の一つですね。そのひずみは今も残っています。。
そういえば公務員を辞めて民間って人、けっこういますよ。逆程いないのは当たり前でしょうね。わざわざ高倍率の難関試験合格したのに辞めたくないのではないですかね。
国家公務員、自衛隊、警察官→民間は知り合いにもいますね。逆にパターンとして多いのが、民間→地方公務員、国家公務員→地方公務員ですね。転勤がないのに準一流企業待遇ってのが地方公務員の魅力なのかもしれません。ただ、民間転職組の数人は県庁がけっこうきついってぼやいてましたよ。逆に国から民間に転職した人は転職後の方が楽だって喜んでますし。人によって向き不向きがあり、組織によりけりの部分があるので、単純比較できないように思えます。
ところで郵便局の件、反対は郵政関係以外にもたくさんいましたよ。私も郵政とは無関係ですし、周囲も無関係。でもみんな反対していました。理由は日本の資本がアメリカに流れること。アメリカの狙いで郵政を民営化、分解したのは目に見えていました。これが今のTPPにも繋がっています。
余談ですが、国鉄も電電公社も専売公社も民営化してからの方が遥かに待遇が良く、高給取り。そう考えると、郵政民営化に反対していた人達ってよほど仕事をしていなかった危機的状況の人達だったのでしょうか(笑)
まあ、日本の組織って官民問わずぬるま湯だと思いますね。特に大手企業や役所ってのは・・・友達や知り合いでも休みがちだったり、仕事ができなかったりしても一人たりともクビになってません。中小企業ですらクビになった奴がいない。だから不要な社員を抱え、優秀な新人社員採用を逃すのではないかと!
個人情報流出は民間企業でも頻発しているように思えます。しかもけっこう大手企業。酷いものにはそれを売っている会社もありましたよね?。
何でもかんでも官民二極化で語ることは危険であると思います。
ちなみに官公庁の民営化には私も賛成です。その方が組織が活性化するでしょうし、サービスが向上するでしょう。ただ、その見極めが非常に難しいように思いますが、私の意見では試行で可能な限り民間導入し、それが不可能なもののみを官公庁の業務に残すってのが良いと思います。これからの日本は弱者切り捨ても前提の上で行政サービスをカットしなければ増税してもとても成り立たないと思います。生活保護者多すぎですし。また年金も高過ぎ。
公務員の数は先進国一少なく、効率的だとは言われていますが、まだまだ合理化できると思いますね。ただ、そのためには私たちも官頼みではなく、自分たちでできることをやることが必要ですね。日本の税金はサービスと比べてただでさえ安いのですから、増税は嫌だけど、サービスは今まで通りお願いしたいでは単なる我儘になってしまいます。
確かに官が民に劣るべきところは見直すべきでしょうね。日本の官僚機構は優秀だが、有事に弱い。これは太平洋戦争の敗因の一つですね。そのひずみは今も残っています。。
そういえば公務員を辞めて民間って人、けっこういますよ。逆程いないのは当たり前でしょうね。わざわざ高倍率の難関試験合格したのに辞めたくないのではないですかね。
国家公務員、自衛隊、警察官→民間は知り合いにもいますね。逆にパターンとして多いのが、民間→地方公務員、国家公務員→地方公務員ですね。転勤がないのに準一流企業待遇ってのが地方公務員の魅力なのかもしれません。ただ、民間転職組の数人は県庁がけっこうきついってぼやいてましたよ。逆に国から民間に転職した人は転職後の方が楽だって喜んでますし。人によって向き不向きがあり、組織によりけりの部分があるので、単純比較できないように思えます。
ところで郵便局の件、反対は郵政関係以外にもたくさんいましたよ。私も郵政とは無関係ですし、周囲も無関係。でもみんな反対していました。理由は日本の資本がアメリカに流れること。アメリカの狙いで郵政を民営化、分解したのは目に見えていました。これが今のTPPにも繋がっています。
余談ですが、国鉄も電電公社も専売公社も民営化してからの方が遥かに待遇が良く、高給取り。そう考えると、郵政民営化に反対していた人達ってよほど仕事をしていなかった危機的状況の人達だったのでしょうか(笑)
まあ、日本の組織って官民問わずぬるま湯だと思いますね。特に大手企業や役所ってのは・・・友達や知り合いでも休みがちだったり、仕事ができなかったりしても一人たりともクビになってません。中小企業ですらクビになった奴がいない。だから不要な社員を抱え、優秀な新人社員採用を逃すのではないかと!
個人情報流出は民間企業でも頻発しているように思えます。しかもけっこう大手企業。酷いものにはそれを売っている会社もありましたよね?。
何でもかんでも官民二極化で語ることは危険であると思います。
ちなみに官公庁の民営化には私も賛成です。その方が組織が活性化するでしょうし、サービスが向上するでしょう。ただ、その見極めが非常に難しいように思いますが、私の意見では試行で可能な限り民間導入し、それが不可能なもののみを官公庁の業務に残すってのが良いと思います。これからの日本は弱者切り捨ても前提の上で行政サービスをカットしなければ増税してもとても成り立たないと思います。生活保護者多すぎですし。また年金も高過ぎ。
公務員の数は先進国一少なく、効率的だとは言われていますが、まだまだ合理化できると思いますね。ただ、そのためには私たちも官頼みではなく、自分たちでできることをやることが必要ですね。日本の税金はサービスと比べてただでさえ安いのですから、増税は嫌だけど、サービスは今まで通りお願いしたいでは単なる我儘になってしまいます。
> たけさん
びっくりしました。
公務員を辞めて会社員になった人が身の回りにたくさんいるとのことで。
地域性もあるんでしょうか?
自分は大阪市民であり、仕事柄、様々な年齢職業の人を3000人以上みてきましたが公務員を辞めて会社員になった人は記憶にありません。
もちろんクビや任期満了で会社員にならざるをえなくなった人は除きますが。
民営化して待遇があがるというのは知りませんでしたが完全な民営化ではないということでしょうか?
民営化された会社の実情は知りませんが、大手企業のほとんどは55歳でいったん定年となります。最近は60歳まで延長されてきましたが55歳で肩書がはずれたりして収入が減少するのは変わらないようです。
ところが公務員は60歳定年まで下がらないそうです。自分て調べたわけではないですが。
おまけに官と民では退職金や年金に雲泥の差があります。
ですから公務員の給与は少なくて当然。倒産しないという安心料が差し引かれるべきですから。
いま公務員の給与を一律3割カットしても応募は来ますよ。
僕が以前から不思議に思うのは、公務員改革の話が出ると、待遇が低下したら優秀な人材が集まらないと言って抵抗するじゃないですか。
府庁や市役所の優秀な人材ってなんだろう。
得意先開拓能力が必要でしょうか?
商品開発能力が必要でしょうか?
営業マンのような交渉力が必要でしょうか?
そう考えるとマジメで健康ならいいんじゃないの?って思うんですよ。
少し話がそれてすみません(笑)
びっくりしました。
公務員を辞めて会社員になった人が身の回りにたくさんいるとのことで。
地域性もあるんでしょうか?
自分は大阪市民であり、仕事柄、様々な年齢職業の人を3000人以上みてきましたが公務員を辞めて会社員になった人は記憶にありません。
もちろんクビや任期満了で会社員にならざるをえなくなった人は除きますが。
民営化して待遇があがるというのは知りませんでしたが完全な民営化ではないということでしょうか?
民営化された会社の実情は知りませんが、大手企業のほとんどは55歳でいったん定年となります。最近は60歳まで延長されてきましたが55歳で肩書がはずれたりして収入が減少するのは変わらないようです。
ところが公務員は60歳定年まで下がらないそうです。自分て調べたわけではないですが。
おまけに官と民では退職金や年金に雲泥の差があります。
ですから公務員の給与は少なくて当然。倒産しないという安心料が差し引かれるべきですから。
いま公務員の給与を一律3割カットしても応募は来ますよ。
僕が以前から不思議に思うのは、公務員改革の話が出ると、待遇が低下したら優秀な人材が集まらないと言って抵抗するじゃないですか。
府庁や市役所の優秀な人材ってなんだろう。
得意先開拓能力が必要でしょうか?
商品開発能力が必要でしょうか?
営業マンのような交渉力が必要でしょうか?
そう考えるとマジメで健康ならいいんじゃないの?って思うんですよ。
少し話がそれてすみません(笑)
> まさはるさん
まあ、警察官とか国家公務員はやや特殊ですから例外的だと思います。特に中央勤務はめちゃくちゃ激務、薄給と言います。世の中の公務員の中で国家公務員は1割少々ですし、警察官を含めてもわずかなもの。大半は都道府県、市町村の一般公務員なので離職しないかと。転勤がなくて大手企業待遇。
ちなみに公務員志望者のクオリティは国家公務員については既に下がり始めていると聞きます。大企業並の転勤がありながら、給与はそれ未満、激務、待遇悪化、リストラ危機。優秀な人材は大手企業や地方自治体に流れるでしょう。最近では東大卒で県庁、市役所も珍しくありません。
公務員の給料は3割下げたら生活できない水準ではないかと。40代未満は安いみたいですから。
ちなみに公務員待遇は政令指定都市が断トツ、都道府県、中核市が次点、国家公務員や市町村が最低と。意外なんですが。要するに目立たない職員の待遇がよく、自治労に守られているという問題があります。国家公務員が矢面に立っている影で地方公務員は権益を維持しているというのは週刊ダイヤモンドにありましたよ。それに目をつけたのが橋下かもしれませんね。
日本の公務員が優秀かと言えば現場はやはり世界一優秀なのでないかと。もちろん自浄作用に乏しい世界ですから、その影には無能連中もたくさんいるのでしょうけどね。
日本公務員の震災対応では世界が驚いたと言われます。ただ、政府が無能なので、台なしになりましたね。
日本では官民ともに現場優秀、上層部無能。太平洋戦争の時代と変わってませんよね。
ただ、一つ言えるのは公務員といっても職種、組織で大差があるでしょうからみんなが恵まれているとか激務とか楽とは言えないのではないかと思います。
まあ、警察官とか国家公務員はやや特殊ですから例外的だと思います。特に中央勤務はめちゃくちゃ激務、薄給と言います。世の中の公務員の中で国家公務員は1割少々ですし、警察官を含めてもわずかなもの。大半は都道府県、市町村の一般公務員なので離職しないかと。転勤がなくて大手企業待遇。
ちなみに公務員志望者のクオリティは国家公務員については既に下がり始めていると聞きます。大企業並の転勤がありながら、給与はそれ未満、激務、待遇悪化、リストラ危機。優秀な人材は大手企業や地方自治体に流れるでしょう。最近では東大卒で県庁、市役所も珍しくありません。
公務員の給料は3割下げたら生活できない水準ではないかと。40代未満は安いみたいですから。
ちなみに公務員待遇は政令指定都市が断トツ、都道府県、中核市が次点、国家公務員や市町村が最低と。意外なんですが。要するに目立たない職員の待遇がよく、自治労に守られているという問題があります。国家公務員が矢面に立っている影で地方公務員は権益を維持しているというのは週刊ダイヤモンドにありましたよ。それに目をつけたのが橋下かもしれませんね。
日本の公務員が優秀かと言えば現場はやはり世界一優秀なのでないかと。もちろん自浄作用に乏しい世界ですから、その影には無能連中もたくさんいるのでしょうけどね。
日本公務員の震災対応では世界が驚いたと言われます。ただ、政府が無能なので、台なしになりましたね。
日本では官民ともに現場優秀、上層部無能。太平洋戦争の時代と変わってませんよね。
ただ、一つ言えるのは公務員といっても職種、組織で大差があるでしょうからみんなが恵まれているとか激務とか楽とは言えないのではないかと思います。
> まさはるさん
そういえば民営化をした役所、専売公社、電電公社、国鉄については国家公務員より遥かに高給になっていますね。理由は半官半民のイイトコ取り、独占企業のおいしさ、サービス残業廃止ですかね。郵政省、国力大学については官庁時代のサービス残業代を遡及して支給という記事がありましたね。サービス残業No.1、過労No.1と言われる厚労省が親玉だけあって、事情に詳しい労働基準監督署がすぐに入ったのでしょう。
官公庁天国神話もマスゴミによる偏向報道もありますから必ずしも全て役人がおいしいとは言えない部分もあるのではないですかね。中小企業、零細企業の非正規社員を水準に叩いている場合もありますので、マスゴミの報道には注意が必要です。そしてそれは格差社会を構築した市場原理主義の経団連が後で操っていますね。経団連はとにかく人件費を削減したい、そのために公務員に矛先を持って行き、人件費削減の準備を進めます。だから政治家に矛先がいかないでしょう?議員歳費は既に元の水準になっており、カットについても議論していません。
経団連と政治家とマスゴミは癒着しており、私達は知らず知らずに誘導されていることが最近顕著になってきたように思います。
リストラ、派遣問題は全てそこからきてますね。
TPPについても私は懸念しています。
そういえば民営化をした役所、専売公社、電電公社、国鉄については国家公務員より遥かに高給になっていますね。理由は半官半民のイイトコ取り、独占企業のおいしさ、サービス残業廃止ですかね。郵政省、国力大学については官庁時代のサービス残業代を遡及して支給という記事がありましたね。サービス残業No.1、過労No.1と言われる厚労省が親玉だけあって、事情に詳しい労働基準監督署がすぐに入ったのでしょう。
官公庁天国神話もマスゴミによる偏向報道もありますから必ずしも全て役人がおいしいとは言えない部分もあるのではないですかね。中小企業、零細企業の非正規社員を水準に叩いている場合もありますので、マスゴミの報道には注意が必要です。そしてそれは格差社会を構築した市場原理主義の経団連が後で操っていますね。経団連はとにかく人件費を削減したい、そのために公務員に矛先を持って行き、人件費削減の準備を進めます。だから政治家に矛先がいかないでしょう?議員歳費は既に元の水準になっており、カットについても議論していません。
経団連と政治家とマスゴミは癒着しており、私達は知らず知らずに誘導されていることが最近顕著になってきたように思います。
リストラ、派遣問題は全てそこからきてますね。
TPPについても私は懸念しています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
日本の将来像を真剣に考える 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-