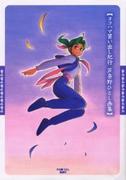皆様、初めまして、
他に言及しているトピックが無い様ですので立てさせて頂きます。ほのぼのとろとろとした作風にいつも騙されそうになりますが、ヨコハマ買い出し紀行って、実はハードな設定のSFマンガですよね?
地球温暖化の影響で海進が進み、日々水没していく世界、アルファさんもココネも拳銃を持ってる事から、かつて大規模な暴動があった世界なのかも知れません。
少子高齢化が極端に進み、若者の多くが定着せずに彷徨いながらくらしている世界。しばしば石像の様にあちこちに佇む人間ともロボットともつかない異形のもの達は、なにか化学的な異変があった事を想像させます。
アルファさんたちはロボットを自称していますが、高度なAIと、生体パーツを使った自立型アンドロイドに見えます。そもそもそんな高度な技術で作られたロボット達が、流行らない喫茶店をやってたり、お家賃払ってアパートに住み、宅配便に勤めてたりしてるのも不思議です。アルファさんに至っては、かつて初瀬野先生が私物化していたふしもあります。
成層圏をひたすら飛び続ける巨大なターポンと、その乗務員のM1も謎めいています。彼女らは人類の文化遺産を衛星の様に周回する巨大な機体に積み、軌道上に保管する書庫の番人なのでしょうか?
アルファ型ロボットが作られた目的は?野生化したロボットの様に見えるミサゴもいます。もしかして彼女たちは、衰退し絆を失いつつある人類の介添えとして開発されたのでしょうか?
そもそもアルファさんの型式であるA7M2って第二次大戦中の零戦の開発コードにそっくりです。と言うことはアルファさんは三菱重工製?
あんまり深く考えて読むべきではないのかも知れませんが、あまりにちりばめられた謎が多すぎて、知的好奇心をひたすらかきたてられる物語です。
皆さんは、どんな風にこの物語を読まれているのでしょうか?
他に言及しているトピックが無い様ですので立てさせて頂きます。ほのぼのとろとろとした作風にいつも騙されそうになりますが、ヨコハマ買い出し紀行って、実はハードな設定のSFマンガですよね?
地球温暖化の影響で海進が進み、日々水没していく世界、アルファさんもココネも拳銃を持ってる事から、かつて大規模な暴動があった世界なのかも知れません。
少子高齢化が極端に進み、若者の多くが定着せずに彷徨いながらくらしている世界。しばしば石像の様にあちこちに佇む人間ともロボットともつかない異形のもの達は、なにか化学的な異変があった事を想像させます。
アルファさんたちはロボットを自称していますが、高度なAIと、生体パーツを使った自立型アンドロイドに見えます。そもそもそんな高度な技術で作られたロボット達が、流行らない喫茶店をやってたり、お家賃払ってアパートに住み、宅配便に勤めてたりしてるのも不思議です。アルファさんに至っては、かつて初瀬野先生が私物化していたふしもあります。
成層圏をひたすら飛び続ける巨大なターポンと、その乗務員のM1も謎めいています。彼女らは人類の文化遺産を衛星の様に周回する巨大な機体に積み、軌道上に保管する書庫の番人なのでしょうか?
アルファ型ロボットが作られた目的は?野生化したロボットの様に見えるミサゴもいます。もしかして彼女たちは、衰退し絆を失いつつある人類の介添えとして開発されたのでしょうか?
そもそもアルファさんの型式であるA7M2って第二次大戦中の零戦の開発コードにそっくりです。と言うことはアルファさんは三菱重工製?
あんまり深く考えて読むべきではないのかも知れませんが、あまりにちりばめられた謎が多すぎて、知的好奇心をひたすらかきたてられる物語です。
皆さんは、どんな風にこの物語を読まれているのでしょうか?
|
|
|
|
コメント(21)
1: 福井 脳内会議 さん、
早速のコメントありがとうございます。
人工知能が長期存在する世界では、人間は短期間その人工知能の前を通り過ぎて行く存在に過ぎないと言う事ですね。なるほど〜
そう言う世界を描くには、その人工知能を創出した技術の喪失と言う前提が必要になる訳ですね。確かに現状の様にプロセサが数ヶ月おきにクロックや処理能力を上げ、OSやアプリが短期間でバージョンアップされる世界では、そう言う逆の時間差は表現できませんね。
ある意味、人類の技術と進歩が止まった世界なら、そう言う現象も起こり得るかもしれませんね。スローライフ・スローカントリーな世界は、やはり先端技術をある程度諦めないと実現しないのかも知れませんね。
早速のコメントありがとうございます。
人工知能が長期存在する世界では、人間は短期間その人工知能の前を通り過ぎて行く存在に過ぎないと言う事ですね。なるほど〜
そう言う世界を描くには、その人工知能を創出した技術の喪失と言う前提が必要になる訳ですね。確かに現状の様にプロセサが数ヶ月おきにクロックや処理能力を上げ、OSやアプリが短期間でバージョンアップされる世界では、そう言う逆の時間差は表現できませんね。
ある意味、人類の技術と進歩が止まった世界なら、そう言う現象も起こり得るかもしれませんね。スローライフ・スローカントリーな世界は、やはり先端技術をある程度諦めないと実現しないのかも知れませんね。
2: Ko Yuuseさん、
コメントありがとうございます。
>…話、逸れました?(汗)
いえいえ、こういうお話を伺いたかったのです。いくらほんわかしたストリーとは言え、背景にある「静かな衰退や滅び」を無視して読める様な物語ではないと思うからです。
変わって行くものと変わらないものを対比させる(物語)世界と言うのは、私も気がつかなかった視点です。確かにそうですね。
AIが人間の姿で暮らす社会を描いた物語では、映画の「AI」とか、エイミートムスンのSF小説「バーチャルガール」などがありますが、なぜかどちらも、AIやロボットを「後まで残るもの」として描き、人類社会をいずれ変化し滅んで行くものと捉えている様な気がします。
「ヨコハマ買い出し紀行」も確かに似通った認識が背景に見え隠れします。作中アルファさんがマッキに「あたしはみんなと同じ船に乗っていない」と言う言い方で彼女の嫉妬心を和らげるシーンがありますが、あれなんか「自分はあなたが成長し、やがて死んでも変わらずここにいるのよ」と暗に言っている様な気がしました。なんと言うか、そう言うロボットの悲哀って「八百比丘尼」に繋がる哀しさがあります。
来て欲しくないけど「ヨコハマ買い出し紀行」の世界は、このまま人間が地球温暖化を止める事が出来なければ、遅くとも来世紀前には訪れる世界です。願わくば今回のハリケーン被害でアメリカの政治家達が温暖化が自分たちにも甚大な影響を与える事に気づき、京都議定書への参加を表明してくれるとよいのですが・・・すいません、こちらこそ、全然関係ない話になってしまいました。
でもそのくらい深いテーマと予言を秘めた物語だと思います「ヨコハマ買い出し紀行」
コメントありがとうございます。
>…話、逸れました?(汗)
いえいえ、こういうお話を伺いたかったのです。いくらほんわかしたストリーとは言え、背景にある「静かな衰退や滅び」を無視して読める様な物語ではないと思うからです。
変わって行くものと変わらないものを対比させる(物語)世界と言うのは、私も気がつかなかった視点です。確かにそうですね。
AIが人間の姿で暮らす社会を描いた物語では、映画の「AI」とか、エイミートムスンのSF小説「バーチャルガール」などがありますが、なぜかどちらも、AIやロボットを「後まで残るもの」として描き、人類社会をいずれ変化し滅んで行くものと捉えている様な気がします。
「ヨコハマ買い出し紀行」も確かに似通った認識が背景に見え隠れします。作中アルファさんがマッキに「あたしはみんなと同じ船に乗っていない」と言う言い方で彼女の嫉妬心を和らげるシーンがありますが、あれなんか「自分はあなたが成長し、やがて死んでも変わらずここにいるのよ」と暗に言っている様な気がしました。なんと言うか、そう言うロボットの悲哀って「八百比丘尼」に繋がる哀しさがあります。
来て欲しくないけど「ヨコハマ買い出し紀行」の世界は、このまま人間が地球温暖化を止める事が出来なければ、遅くとも来世紀前には訪れる世界です。願わくば今回のハリケーン被害でアメリカの政治家達が温暖化が自分たちにも甚大な影響を与える事に気づき、京都議定書への参加を表明してくれるとよいのですが・・・すいません、こちらこそ、全然関係ない話になってしまいました。
でもそのくらい深いテーマと予言を秘めた物語だと思います「ヨコハマ買い出し紀行」
>アルファさんに至っては、かつて初瀬野先生が私物化していたふしもあります。
私物化というよりも、アルファさんやM1の回想や夢、マルコさんとの会話から思うに、ロボットたちは特定の人(オーナー)たちのもとで世間というか世界を学んで、やがて自立して社会にとけこんでいく、というのがスタイルなような気がします。
はじめから一般常識、情報をすり込んで世に送り出すのではなく、人間のように個々の経験により成長していくことでしっかりとした個性・人間性を確立させるのではないでしょうか。
そうして、やがて人の間に溶け込んでいくことで、激減した人口のコミュニケーションの間を埋めていく…つまり、人間たちの「寂しさ」を和らげる目的があるかもしれない。
などと埒もなく考えながら、今日もぼんやり読んでます(^^;
あの欠けた富士山をアルファさんが眺めるシーンなんかも色々なことを想わせますね。好きなシーンのひとつです。
私物化というよりも、アルファさんやM1の回想や夢、マルコさんとの会話から思うに、ロボットたちは特定の人(オーナー)たちのもとで世間というか世界を学んで、やがて自立して社会にとけこんでいく、というのがスタイルなような気がします。
はじめから一般常識、情報をすり込んで世に送り出すのではなく、人間のように個々の経験により成長していくことでしっかりとした個性・人間性を確立させるのではないでしょうか。
そうして、やがて人の間に溶け込んでいくことで、激減した人口のコミュニケーションの間を埋めていく…つまり、人間たちの「寂しさ」を和らげる目的があるかもしれない。
などと埒もなく考えながら、今日もぼんやり読んでます(^^;
あの欠けた富士山をアルファさんが眺めるシーンなんかも色々なことを想わせますね。好きなシーンのひとつです。
横槍的な投稿で恐縮なのですが、
「ハードな設定のSF」というのは、いわゆる「ハードSF」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89SF
という意味で使っていらっしゃるのでしょうか?
もし仮にそうではないなら、どのような意味で「ハード」という言葉を
使っていらっしゃいますでしょうか?
(私はSFについてはあまり知らないので「ハードなSF」と言った場合に
すんなりイメージ出来ないものですから...)
このトピックの最初を読ませて頂いた時、初めは
「『ヨコハマ買い出し紀行』は単なる『SF』以上に『ハードSF』ではあるまいか?」
という感じのところに力点があるように思ったのですが、
続く投稿を見ると
「『ヨコハマ買い出し紀行』は単なる『ファンタジックな物語』以上に『SF』ではあるまいか?」
という所に力点があるように読め、よく分からなくなりました。
私はSFに関しては大御所的な作品をいくつか読んだだけですが
個人的に「ファンタジー」と「SF」の境界線や、
SFの中での「ハードSF」の切り分けなどに少し興味があるため、
上のような点に関して皆様の御意見を聞ければ
楽しいなと思ったので投稿させて頂きました。
もし話の流れに不適切な質問でしたら適当に流して下さいませ(_o_)
「ハードな設定のSF」というのは、いわゆる「ハードSF」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89SF
という意味で使っていらっしゃるのでしょうか?
もし仮にそうではないなら、どのような意味で「ハード」という言葉を
使っていらっしゃいますでしょうか?
(私はSFについてはあまり知らないので「ハードなSF」と言った場合に
すんなりイメージ出来ないものですから...)
このトピックの最初を読ませて頂いた時、初めは
「『ヨコハマ買い出し紀行』は単なる『SF』以上に『ハードSF』ではあるまいか?」
という感じのところに力点があるように思ったのですが、
続く投稿を見ると
「『ヨコハマ買い出し紀行』は単なる『ファンタジックな物語』以上に『SF』ではあるまいか?」
という所に力点があるように読め、よく分からなくなりました。
私はSFに関しては大御所的な作品をいくつか読んだだけですが
個人的に「ファンタジー」と「SF」の境界線や、
SFの中での「ハードSF」の切り分けなどに少し興味があるため、
上のような点に関して皆様の御意見を聞ければ
楽しいなと思ったので投稿させて頂きました。
もし話の流れに不適切な質問でしたら適当に流して下さいませ(_o_)
5: こうた さん、
なるほど、高度なAIをもったロボットを社会化させるために、一般家庭で個性や人間性を育てたと言うのはありそうですね。これは僕も感じてました。なんだか盲導犬のパピーウオーカーににてます(笑)盲導犬も一般家庭で暮らす事で人間社会への社会化を促し家族への帰属意識を育てるのだと思います。何より家庭生活を知らないと良い盲導犬になれないのだそうです。
実は、連載開始前の序章みたいなところで、アルファさんの独り言みたいな語りがありましたよね?
「何年か前、私のオーナーは、私に店を預けて一人でどこかに行ってしまった」
この言い方、凄く哀しくて好きなんですが、僕は「喫茶店のオーナー」ではなくて「アルファさんのオーナー」という印象を持ったので、初瀬野先生がアルファさんを私物化(悪い意味では無くて)して保護していた時期があったのかな?と思ったのでした。
もっと想像を逞しくすると、初瀬野先生はアルファ型の開発に関わったメンバーの一人で、なにか大きな社会変動があって研究が頓挫した時に、アルファさんをひきとって保護し、自分も隠遁したのではないかと想像したのです。まあ、考えすぎだと思いますが、そう言う想像をかき立てるニュアンスが感じられたのでした。
なるほど、高度なAIをもったロボットを社会化させるために、一般家庭で個性や人間性を育てたと言うのはありそうですね。これは僕も感じてました。なんだか盲導犬のパピーウオーカーににてます(笑)盲導犬も一般家庭で暮らす事で人間社会への社会化を促し家族への帰属意識を育てるのだと思います。何より家庭生活を知らないと良い盲導犬になれないのだそうです。
実は、連載開始前の序章みたいなところで、アルファさんの独り言みたいな語りがありましたよね?
「何年か前、私のオーナーは、私に店を預けて一人でどこかに行ってしまった」
この言い方、凄く哀しくて好きなんですが、僕は「喫茶店のオーナー」ではなくて「アルファさんのオーナー」という印象を持ったので、初瀬野先生がアルファさんを私物化(悪い意味では無くて)して保護していた時期があったのかな?と思ったのでした。
もっと想像を逞しくすると、初瀬野先生はアルファ型の開発に関わったメンバーの一人で、なにか大きな社会変動があって研究が頓挫した時に、アルファさんをひきとって保護し、自分も隠遁したのではないかと想像したのです。まあ、考えすぎだと思いますが、そう言う想像をかき立てるニュアンスが感じられたのでした。
6: がおち改め高崎 さん、
僕はすこし古い時代のSF以外あまりSFを読んでいないし、今回の「ハードなSF」にあまり厳密な意味を持たせて書いていません。あるいはそう言う質問をする人がいるかもしれないので、あえてハードSFと明言しなかったとも言えます(笑)
個人的に、ハードSFはしばしば科学的な予言書にあたるのではないか?と思ってます。ジュールベルヌの古典SF「海底二万マイル」みたいに今はほぼ実現されてしまっているSFもあるわけです。「このまま現在の既存の科学的知見が累積して、技術開発が進めば、あるいは状況が進展すれば、実現する可能性がある物語」あるいはご紹介頂いた定義にあるような「科学的知見および科学的論理」に主眼をおいたSF作品がハードSFなのだと思います。
「ヨコハマ買い出し紀行」はそう言う意味では、このまま地球温暖化を人類が放置し、米国が京都議定書を無視し続ければ、好むと好まざるとに関わらず実現してしまう世界の物語に見えます。そう言う意味では舞台はハードSFそのものだと思います。
むしろ、ハードSF〜ファンタジーの間のどのあたりに位置づけて、みなさんが読んでいるのか?という他人様の視点に興味があって、このトピックを立てたつもりです。がおち改め高崎 さんは、どの様な感じをお持ちでしょうか?
現時点では、ハードSFの舞台でファンタジーに近い事をやっているのか?物語そのものが、アルファさんや登場人物個々の視点で描かれているために、社会としての全体像が見えず、そのためハードSFの域に達していないのか?まだ判断出来ずにいます。
僕自身、最初はテクニカルファンタジーの様に読んでいましたが、今は「ソフトな皮をかぶってるけど、実はかなりハードなSFなんじゃないか」と思う様になりました。あるいはハードSFとして読んだ方が、ほのぼのと物語の中にちりばめられた、未来の話のはずなのに、なぜか懐かしい諸々の事象が、より美しく感じられるのでは無いかと思い始めています。
すいません、なんか答えになっていない様な答えで(汗)
僕はすこし古い時代のSF以外あまりSFを読んでいないし、今回の「ハードなSF」にあまり厳密な意味を持たせて書いていません。あるいはそう言う質問をする人がいるかもしれないので、あえてハードSFと明言しなかったとも言えます(笑)
個人的に、ハードSFはしばしば科学的な予言書にあたるのではないか?と思ってます。ジュールベルヌの古典SF「海底二万マイル」みたいに今はほぼ実現されてしまっているSFもあるわけです。「このまま現在の既存の科学的知見が累積して、技術開発が進めば、あるいは状況が進展すれば、実現する可能性がある物語」あるいはご紹介頂いた定義にあるような「科学的知見および科学的論理」に主眼をおいたSF作品がハードSFなのだと思います。
「ヨコハマ買い出し紀行」はそう言う意味では、このまま地球温暖化を人類が放置し、米国が京都議定書を無視し続ければ、好むと好まざるとに関わらず実現してしまう世界の物語に見えます。そう言う意味では舞台はハードSFそのものだと思います。
むしろ、ハードSF〜ファンタジーの間のどのあたりに位置づけて、みなさんが読んでいるのか?という他人様の視点に興味があって、このトピックを立てたつもりです。がおち改め高崎 さんは、どの様な感じをお持ちでしょうか?
現時点では、ハードSFの舞台でファンタジーに近い事をやっているのか?物語そのものが、アルファさんや登場人物個々の視点で描かれているために、社会としての全体像が見えず、そのためハードSFの域に達していないのか?まだ判断出来ずにいます。
僕自身、最初はテクニカルファンタジーの様に読んでいましたが、今は「ソフトな皮をかぶってるけど、実はかなりハードなSFなんじゃないか」と思う様になりました。あるいはハードSFとして読んだ方が、ほのぼのと物語の中にちりばめられた、未来の話のはずなのに、なぜか懐かしい諸々の事象が、より美しく感じられるのでは無いかと思い始めています。
すいません、なんか答えになっていない様な答えで(汗)
8: sffffz さん、
そうですね、「ヨコハマ買い出し紀行」は、やっぱり大変な事が起こったあとの世界を描いてますよね。
海面上昇は現在の知見では、温室効果による地球温暖化の影響と思われますから、現状があまり修正されずに、京都議定書の発効も虚しく、大気中の二酸化炭素が増え続け、温室効果で両極の氷は溶け続け、ある意味で間氷期の状況が極端に進んだ世界なのでしょう。
富士山の変化の原因は、なにか作中で言及がありましたっけ?
確かにカフェアルファから見える富士山も、アルファさんがトウモロコシ焼きのアルバイトしている富士山の近くでも、富士山が噴火して山容が変わった様に描かれています。それもアルファさんがかつての富士山の姿を覚えているのですから、それほど昔の事では無いように思われます。
地球温暖化による海面上昇を物語の背景にしたSF作品は、他にもいくつかあります。「機動警察パトレイバー」のバビロンプロジェクトもそうだし、「攻殻機動隊」の背景でも、旧市街が水没したりしてます。デビットハミルトンの「マインドスターライジング」に至っては、かなり悲惨で陰惨な世界になっている様に読めます。土地所有を是とする国民にとって、その土地が水没する事態は富の崩壊に他ならないから、残された土地の争奪で戦争が起きると言うのはあり得る事でしょう。
でも、大災厄が通り過ぎた後の長い黄昏の時代を描いている「ヨコハマ買い出し紀行」の世界には、そう言う暗さはあまり感じられません。人間が滅びを受け入れた世界なのか、あるいは少子高齢化が進み過ぎて、もはや土地や財産すら取り合う必要が無くなった世界なのか、あの世界には時間が過去に回帰して行くような、ひたすら懐かしい旋律が感じられます。
カフェアルファも、もう少し経つと岬が海に呑まれ、建物自体無くなってしまうのかも知れません。そう言うほのかな危機感は常にあるのに、なぜか、一読後は毎回ほのぼのとさせられてしまいます。それが何故なのか、僕は知りたいと思うのです。
そうですね、「ヨコハマ買い出し紀行」は、やっぱり大変な事が起こったあとの世界を描いてますよね。
海面上昇は現在の知見では、温室効果による地球温暖化の影響と思われますから、現状があまり修正されずに、京都議定書の発効も虚しく、大気中の二酸化炭素が増え続け、温室効果で両極の氷は溶け続け、ある意味で間氷期の状況が極端に進んだ世界なのでしょう。
富士山の変化の原因は、なにか作中で言及がありましたっけ?
確かにカフェアルファから見える富士山も、アルファさんがトウモロコシ焼きのアルバイトしている富士山の近くでも、富士山が噴火して山容が変わった様に描かれています。それもアルファさんがかつての富士山の姿を覚えているのですから、それほど昔の事では無いように思われます。
地球温暖化による海面上昇を物語の背景にしたSF作品は、他にもいくつかあります。「機動警察パトレイバー」のバビロンプロジェクトもそうだし、「攻殻機動隊」の背景でも、旧市街が水没したりしてます。デビットハミルトンの「マインドスターライジング」に至っては、かなり悲惨で陰惨な世界になっている様に読めます。土地所有を是とする国民にとって、その土地が水没する事態は富の崩壊に他ならないから、残された土地の争奪で戦争が起きると言うのはあり得る事でしょう。
でも、大災厄が通り過ぎた後の長い黄昏の時代を描いている「ヨコハマ買い出し紀行」の世界には、そう言う暗さはあまり感じられません。人間が滅びを受け入れた世界なのか、あるいは少子高齢化が進み過ぎて、もはや土地や財産すら取り合う必要が無くなった世界なのか、あの世界には時間が過去に回帰して行くような、ひたすら懐かしい旋律が感じられます。
カフェアルファも、もう少し経つと岬が海に呑まれ、建物自体無くなってしまうのかも知れません。そう言うほのかな危機感は常にあるのに、なぜか、一読後は毎回ほのぼのとさせられてしまいます。それが何故なのか、僕は知りたいと思うのです。
12: 神 雅紀 さん、
興味深いお話をありがとうございます。課題以外にも考えさせられるお話です。
お考えでは大災厄(天変地異または戦争どちらでも)の後、現行の世界が崩壊して、一旦ある種の平衡状態が訪れ、さらなる終末にゆっくり向かっているのが「ヨコハマ買い出し紀行」の世界と言う事になるのでしょうか?
M1アルファ室長の独白にも、世界のあちこちで人間の痕跡が消えていく、と言った記述が見られます。日本はその過程が極ゆっくり進んでいると言うことでしょうか?
日本は、その特有の「ムラ社会の構造」によって、日本が神奈川の国、武蔵の国の様に小国家群に分断されても、その平衡状態は長い間続き、数世代の間では容易に消滅しない地域社会が再形成される。それが「ヨコハマ買い出し紀行」の描いている「時代の穏やかな黄昏」なのでしょうか?
ヨコハマ買い出し紀行の初期の物語の中に、アルファの友人であるトモヒロやマッキが、親戚のおじさんに系統だった(と思われる)教育を個人的に受けている様子が描かれています。例によってほのぼのとしたシーンですが、ある意味学校制度が崩壊した社会でも、次世代に教育を続けている人々がいる事を象徴的に描いたシーンだと思います。
神 雅紀さんのお話は、物語の舞台に関しては良く理解出来るのですが、それでは主人公であるアルファ型ロボットの位置づけ、または開発意図、物語の中での役割にはどんな事が想定されるのでしょう?できればご専門の立場からどんな風に読めるか聞かせて頂きたいです。
ご指摘にあった様に、阪神淡路大震災、先の新潟中越地震でも、日本の地域社会は理性を保った人々に最後まで支えられ、大規模な暴動も略奪も起こらず、短期間で驚異的な地域復興を成し遂げました。これは日本の社会や民族が持つ特性によるものとお考えなのでしょうか?
これに対してハリケーン・カトリーナに蹂躙されたアメリカのニューオリンズでは、警官すら略奪に参加し、世界一強大なはずのアメリカのしかも大都市で、100万人を越える人々が十分な保護も受けずに非難生活を送っている様です。
主題からは離れてしまいますが、私は今回の大規模な気象災害は、地球温暖化のフェーズが一つ進んだ事によって、必然的に起こった人災なのではないか、と考えています。ある意味、京都議定書に批准しなかったアメリカ政府は、その結果である地球温暖化の「ツケ」を、今回のカトリーナによって、初めて自国民に払わせる事になったのではないか?とさえ思っています。
確かに、あの国を舞台にしたら「宇宙戦争」は描けても「ヨコハマ買い出し紀行」は描けそうにありませんね。
引き続き、ご意見をお聞かせ頂ければ嬉しいです。
興味深いお話をありがとうございます。課題以外にも考えさせられるお話です。
お考えでは大災厄(天変地異または戦争どちらでも)の後、現行の世界が崩壊して、一旦ある種の平衡状態が訪れ、さらなる終末にゆっくり向かっているのが「ヨコハマ買い出し紀行」の世界と言う事になるのでしょうか?
M1アルファ室長の独白にも、世界のあちこちで人間の痕跡が消えていく、と言った記述が見られます。日本はその過程が極ゆっくり進んでいると言うことでしょうか?
日本は、その特有の「ムラ社会の構造」によって、日本が神奈川の国、武蔵の国の様に小国家群に分断されても、その平衡状態は長い間続き、数世代の間では容易に消滅しない地域社会が再形成される。それが「ヨコハマ買い出し紀行」の描いている「時代の穏やかな黄昏」なのでしょうか?
ヨコハマ買い出し紀行の初期の物語の中に、アルファの友人であるトモヒロやマッキが、親戚のおじさんに系統だった(と思われる)教育を個人的に受けている様子が描かれています。例によってほのぼのとしたシーンですが、ある意味学校制度が崩壊した社会でも、次世代に教育を続けている人々がいる事を象徴的に描いたシーンだと思います。
神 雅紀さんのお話は、物語の舞台に関しては良く理解出来るのですが、それでは主人公であるアルファ型ロボットの位置づけ、または開発意図、物語の中での役割にはどんな事が想定されるのでしょう?できればご専門の立場からどんな風に読めるか聞かせて頂きたいです。
ご指摘にあった様に、阪神淡路大震災、先の新潟中越地震でも、日本の地域社会は理性を保った人々に最後まで支えられ、大規模な暴動も略奪も起こらず、短期間で驚異的な地域復興を成し遂げました。これは日本の社会や民族が持つ特性によるものとお考えなのでしょうか?
これに対してハリケーン・カトリーナに蹂躙されたアメリカのニューオリンズでは、警官すら略奪に参加し、世界一強大なはずのアメリカのしかも大都市で、100万人を越える人々が十分な保護も受けずに非難生活を送っている様です。
主題からは離れてしまいますが、私は今回の大規模な気象災害は、地球温暖化のフェーズが一つ進んだ事によって、必然的に起こった人災なのではないか、と考えています。ある意味、京都議定書に批准しなかったアメリカ政府は、その結果である地球温暖化の「ツケ」を、今回のカトリーナによって、初めて自国民に払わせる事になったのではないか?とさえ思っています。
確かに、あの国を舞台にしたら「宇宙戦争」は描けても「ヨコハマ買い出し紀行」は描けそうにありませんね。
引き続き、ご意見をお聞かせ頂ければ嬉しいです。
>Ko Yuuseさん
大規模災害時に略奪や暴動がまったく発生しない事は人間の精神構造上無理でしょう。
しかし、日本の場合はアメリカほど大騒ぎ(警官まで略奪をする事態)にならない民族性はあるのではないでしょうか?
関東大震災でのデマ暴行は当時の朝鮮支配と朝鮮人差別の問題になるのでとりあえず割愛
>史嶋 桂さん
私も大筋では同じ解釈です。
さて、アルファ型の存在理由ですが。
これは個別ケースに分けて考える方が良いと思います。
では
室長:ターポン内部に巨大なライブラリーを思わせる設備があります。また、乗員の人間が高齢者しか目撃されていません。
このことから、ターポンは「大災厄」のさいに人類の知的財産や生物のDNAなどの情報を積んで離陸した「ノアの箱船」なのではないかと考えます。室長はアルファタイプの機能を使ったメインコントロールシステムとの端末ユニットなのではないでしょうか。
ココネ、ナイ:ごくごく普通の人間と同じように働き、生活している彼らは現在の工業ロボットの延長、つまり不足してきた労働力の補填を行っているのでしょう。
丸子:彼女は創作活動を主として行っています。しかし、作中の描写から想像するに風景画が中心と思われます。
アルファさん:彼女は周囲の人々とふれあい、カメラで写真(?)を取りながらゆっくりゆっくり生きています。
さて、この二人には共通点があります。
二人とも「今」を記憶している点です。
思うに、この二人は「思い出」なのではないでしょうか?
遠い未来にこの時代を生きた人たちの思い出を伝える事、それがこの二人のアルファタイプの存在理由だと思います。
大規模災害時に略奪や暴動がまったく発生しない事は人間の精神構造上無理でしょう。
しかし、日本の場合はアメリカほど大騒ぎ(警官まで略奪をする事態)にならない民族性はあるのではないでしょうか?
関東大震災でのデマ暴行は当時の朝鮮支配と朝鮮人差別の問題になるのでとりあえず割愛
>史嶋 桂さん
私も大筋では同じ解釈です。
さて、アルファ型の存在理由ですが。
これは個別ケースに分けて考える方が良いと思います。
では
室長:ターポン内部に巨大なライブラリーを思わせる設備があります。また、乗員の人間が高齢者しか目撃されていません。
このことから、ターポンは「大災厄」のさいに人類の知的財産や生物のDNAなどの情報を積んで離陸した「ノアの箱船」なのではないかと考えます。室長はアルファタイプの機能を使ったメインコントロールシステムとの端末ユニットなのではないでしょうか。
ココネ、ナイ:ごくごく普通の人間と同じように働き、生活している彼らは現在の工業ロボットの延長、つまり不足してきた労働力の補填を行っているのでしょう。
丸子:彼女は創作活動を主として行っています。しかし、作中の描写から想像するに風景画が中心と思われます。
アルファさん:彼女は周囲の人々とふれあい、カメラで写真(?)を取りながらゆっくりゆっくり生きています。
さて、この二人には共通点があります。
二人とも「今」を記憶している点です。
思うに、この二人は「思い出」なのではないでしょうか?
遠い未来にこの時代を生きた人たちの思い出を伝える事、それがこの二人のアルファタイプの存在理由だと思います。
はじめまして。
「ヨコハマ買い出し紀行 芦奈野ひとし画集」(2003)
の作者インタビューに、ある程度の設定とか、どんなつもりで描いているかとか、ある程度は書いてありますね。
最初から各種設定があったわけでなくて、断片的なシーンから、なりゆきで世界が広がっていった、というところのようです。
基本的にはイメージ先行で描いてる作品ですし、あれこれ突っ込むと、もともと設定の整合性が無いのでどうしようもなくなります。それでもいろいろ考えるのは楽しいものですけど。(苦笑)
そういえば、地球上の氷が全部溶けても、海面上昇はあと80mそこそこなのですが、80mでも日本にとっては厳しいですね。あの世界の日本の人口なら、なんとかやっていけるかもしれませんが。大陸の国家なら致命的なダメージにはならないかもしれません。
「ヨコハマ買い出し紀行 芦奈野ひとし画集」(2003)
の作者インタビューに、ある程度の設定とか、どんなつもりで描いているかとか、ある程度は書いてありますね。
最初から各種設定があったわけでなくて、断片的なシーンから、なりゆきで世界が広がっていった、というところのようです。
基本的にはイメージ先行で描いてる作品ですし、あれこれ突っ込むと、もともと設定の整合性が無いのでどうしようもなくなります。それでもいろいろ考えるのは楽しいものですけど。(苦笑)
そういえば、地球上の氷が全部溶けても、海面上昇はあと80mそこそこなのですが、80mでも日本にとっては厳しいですね。あの世界の日本の人口なら、なんとかやっていけるかもしれませんが。大陸の国家なら致命的なダメージにはならないかもしれません。
>7: 金髪高耳×傷 様
> ハードSFは、SFでも新発見や新発明に頼らず。
> "既出(既知)の技術"で説明しきれる物。としています。
私も似たようなイメージですが、個人的には(ハードSFというのは)
「ところどころ理系の教科書を読んでいるかのようで、
部分的に読み飛ばしたくなる作品」
とか(笑)。
具体的には、ジェイムズ・P・ホーガンの「創世記機械」(だったかな?)とか、
ヴェルヌの「海底2万海里」(子供向けのジャナイヨ、
完訳を読むと水中生物の列記に嫌になる)とか。
さてヨコハマがハードSFかはとりあえずおいといて、ヨコハマ買い出し紀行が
「厳しい現実が舞台背景としてあるSF作品」
ということなら、私もまさしくそういう感じを当初の頃から受けてまして
その部分も、かつては(!)結構魅力and楽しみでした。
拳銃の件は治安の悪さを示す以外には考えられませんでしたし、
ターポン(大鵬)の存在は一旦地上の文明を見捨て、
再度地上が安定する時に向けての避難部隊というイメージがありました。
ここらあたりの話題、こういう部分に関して注目する話題に関しては
「ヨコハマ買い出し紀行メーリングリスト」
でかなり昔に意見交換されたのを見たことがあります。
(なお、このMLは他の趣味系のMLの最近の動向に漏れず、
残念ながら現在の流通量はごくわずかになっています。)
当時の自分の投稿を読んでみると、私のヨコハマ買い出し紀行の第一印象は
エヴァンゲリオンを知った後だったこともあって
「あっ、セカンドインパクトの後の世界だ」というものだったようです。
(実際にはヨコハマはエヴァより先立ったような....。)
その時の情報によると、芦奈野先生自身、どこかの雑誌のインタビューか何かで
「(背後の設定は)“エヴァの世界より辛かったり...”」
みたいなコメントを述べたこともあったとか。
また、漫画版ナウシカの連載終了から遠くない頃のこともあって
私個人的にはターポンが漫画版ナウシカの墓所に重なって見え、
それが前述のようなイメージに結びついていたように思います。
ただ、その後のストーリーでも、そのような
「大局的に厳しい現実」に焦点が当たることは極めて少なかったように思います。
ですからそのような謎めいた部分に関心を持った人の中には
その後の「進展のなさ」に飽きてしまった人もいるかもしれません。
ここ最近の数巻の話では物語の「切なさ」が加速しているような気はしますし、
その原因の一つには海岸線の後退などによる
「見慣れた風景の消失」
なども確かにあるわけですが、それよりも、限りある生を持つ人間と、
(比較的?)長い命を持つアンドロイドとの交流から生じる悲哀が
メインであるように思われ、その点では史嶋桂様がお書きになっているように
民話の「八百比丘尼伝説」などとも繋がるものですが、
しかしSFにありがちな「厳しい現実の舞台背景」とは
あまりリンクしないもののように感じます。
加えて芦名野氏のコミックに書かれた所々のコメントと
10年以上の連載の進展具合とその内容から思うに
>2: Ko Yuuse 様
が指摘して下さっている
「厳しい現実世界(舞台背景)」はあくまで「背景」、
という意見は私としては非常に納得してしまうものがあり、
それらの厳しい舞台背景は、
あまり、前面として注目or期待されるべきものではないのかもしれない、
と私は思ったりしています。
まさしく
>17: 土竜 様
がお書きになっている
> 基本的にはイメージ先行で描いてる作品ですし、
> あれこれ突っ込むと、もともと設定の整合性が
> 無いのでどうしようもなくなります。
に肯いてしまいます。
いや、だからこそ物語のなかでそれが明らかになるのを期待するのではなく、
このような場でファンがいろいろ推測を楽しむべき部分であり
楽しむのが面白い部分と言えるのでしょう(笑)。それに関しては大賛成です。
> ハードSFは、SFでも新発見や新発明に頼らず。
> "既出(既知)の技術"で説明しきれる物。としています。
私も似たようなイメージですが、個人的には(ハードSFというのは)
「ところどころ理系の教科書を読んでいるかのようで、
部分的に読み飛ばしたくなる作品」
とか(笑)。
具体的には、ジェイムズ・P・ホーガンの「創世記機械」(だったかな?)とか、
ヴェルヌの「海底2万海里」(子供向けのジャナイヨ、
完訳を読むと水中生物の列記に嫌になる)とか。
さてヨコハマがハードSFかはとりあえずおいといて、ヨコハマ買い出し紀行が
「厳しい現実が舞台背景としてあるSF作品」
ということなら、私もまさしくそういう感じを当初の頃から受けてまして
その部分も、かつては(!)結構魅力and楽しみでした。
拳銃の件は治安の悪さを示す以外には考えられませんでしたし、
ターポン(大鵬)の存在は一旦地上の文明を見捨て、
再度地上が安定する時に向けての避難部隊というイメージがありました。
ここらあたりの話題、こういう部分に関して注目する話題に関しては
「ヨコハマ買い出し紀行メーリングリスト」
でかなり昔に意見交換されたのを見たことがあります。
(なお、このMLは他の趣味系のMLの最近の動向に漏れず、
残念ながら現在の流通量はごくわずかになっています。)
当時の自分の投稿を読んでみると、私のヨコハマ買い出し紀行の第一印象は
エヴァンゲリオンを知った後だったこともあって
「あっ、セカンドインパクトの後の世界だ」というものだったようです。
(実際にはヨコハマはエヴァより先立ったような....。)
その時の情報によると、芦奈野先生自身、どこかの雑誌のインタビューか何かで
「(背後の設定は)“エヴァの世界より辛かったり...”」
みたいなコメントを述べたこともあったとか。
また、漫画版ナウシカの連載終了から遠くない頃のこともあって
私個人的にはターポンが漫画版ナウシカの墓所に重なって見え、
それが前述のようなイメージに結びついていたように思います。
ただ、その後のストーリーでも、そのような
「大局的に厳しい現実」に焦点が当たることは極めて少なかったように思います。
ですからそのような謎めいた部分に関心を持った人の中には
その後の「進展のなさ」に飽きてしまった人もいるかもしれません。
ここ最近の数巻の話では物語の「切なさ」が加速しているような気はしますし、
その原因の一つには海岸線の後退などによる
「見慣れた風景の消失」
なども確かにあるわけですが、それよりも、限りある生を持つ人間と、
(比較的?)長い命を持つアンドロイドとの交流から生じる悲哀が
メインであるように思われ、その点では史嶋桂様がお書きになっているように
民話の「八百比丘尼伝説」などとも繋がるものですが、
しかしSFにありがちな「厳しい現実の舞台背景」とは
あまりリンクしないもののように感じます。
加えて芦名野氏のコミックに書かれた所々のコメントと
10年以上の連載の進展具合とその内容から思うに
>2: Ko Yuuse 様
が指摘して下さっている
「厳しい現実世界(舞台背景)」はあくまで「背景」、
という意見は私としては非常に納得してしまうものがあり、
それらの厳しい舞台背景は、
あまり、前面として注目or期待されるべきものではないのかもしれない、
と私は思ったりしています。
まさしく
>17: 土竜 様
がお書きになっている
> 基本的にはイメージ先行で描いてる作品ですし、
> あれこれ突っ込むと、もともと設定の整合性が
> 無いのでどうしようもなくなります。
に肯いてしまいます。
いや、だからこそ物語のなかでそれが明らかになるのを期待するのではなく、
このような場でファンがいろいろ推測を楽しむべき部分であり
楽しむのが面白い部分と言えるのでしょう(笑)。それに関しては大賛成です。
いろいろと興味深いお話をありがとうございます。申し訳ありませんが、長文並びにまとめレスで失礼させて頂きます。
まず複数の方がおっしゃっているのと同じように、僕はヨコハマ買い出し紀行のあら探しをするつもりでこのトピックを立てたつもりはありません。ただ一世を風靡したエヴァンゲリオン以上に「説明されない物語の背景や謎」が多い作品なので、その語られない部分を自分で補って読む事が快感になってさえいます。そういう意味では、読者であるみなさんが、私と少しずつ違う視点で、色々な想いを寄せているのがわかりうれしい限りです。
14: Ko Yuuse さん、
やはり、そう読めますよね。ロボット・アンドロイド・AIをあつかったSF作品は多いですが、近年の作品では、それを個人や企業が所有したり、廃棄したりする行為や、自意識をもったAIが、逆に独立を図ろうとする事が物語の発端になっている例が多いので、敢えてこだわってみました。でもオーナーとアルファさんの関係は所有者と所有物と言うより、初期量産型または試作型に近いAIを持つA7M2を、オーナーが自宅で人間として独立した暮らしを営める様に個人的な訓育や教育を行うための物だった様に感じます。その上で「イノセンス」でも語られた「人工的な人型を愛でる感情」もほの見える様な気がします。あるいは自分の義理の娘や姪に対する様な庇護の情なのかも知れません。こういう年長者の男性が年下の女性に見せる愛情は「ハンニバル」にも描かれていました。そう言うのなんとなく好きです。
15: Algernonさん、
終末に向かう物悲しい感情と、それに反すると言うより対応する人間関係から描かれる、一種の癒しが、ヨコハマ買い出し紀行の主題の一つなのかも知れません。人間はいつかは滅びる生き物だと想います。もしその滅びの姿を選べるのなら、僕はヨコハマ買い出し紀行の様な世界を選びたいと想います。
16: 神 雅紀 さん、
専門家の方が同じようなとらえ方をされていたのはおもしろいと思いました。ご指摘の様にアルファ型ロボットは、初期型と量産型で大分開発意図というか、目的が変わって来ているようですね。
A7M1と思われるアルファ室長の勤務先は、確かに空飛ぶ箱船の様です。それも生きた動物を載せるのではなく、大量の書籍や資料を積んでいることから、過去の文化遺産を天変地異から守る、空飛ぶ資料室なのではないかと思います。室長と言う肩書きに上司が存在するのかどうか不明ですが、僕は他の乗員が老人ばかりなのは、アルファさんを治療した医師の先生と同世代の人たちが、自ら志願して「帰れないかも知れない知的財産を守る旅」に出たからだと思っています。ですからM1自身の実年齢も相当高いのではないでしょうか?
ターポン自身も純粋な機械と言うより、生体部品を使った半生命体なのでは無いかと思います。M1のコントロールによって、新しいマズルか何かを発芽させるシーンがありましたよね?
A7M2のアルファさんは、M1と同じですが、もっと実用的に、もしかしたら兵器や乗り物の制御に使う意図もあって開発されたのでは無いかと考えたりしています。表面効果翼艇のリモートコントロールや同化が出来たりしますし、ナイのテキサンに乗った時にも自身が飛行機そのものになった様な状況さえ経験しました。ああいう360℃の視野を持つコントロール系は、兵器に搭載するAIに最適のものなのでは無いでしょうか?ちょっと嫌な想像ですが。短銃心の自動拳銃で荒れ地の標的を撃つ射撃の腕も一流ですよね。
A7M3のココネの世代になると、ある意味人口の減少を半永久的に補う労働力として作り出された汎用機である可能性が高い様に思います。ココネ自身「研修所を出る時に自分で名前を決めた」と述べていますから、ロボットを社会で運用し、人間社会を補佐する様な存在として、大量に作られた世代なのかも知れません。友人知人とのつきあいを見ていると、年齢差も余り感じられませんし。ただしココネも丸子に脅された時の反応を考えると、射撃管制能力は相当高そうに感じます。あれだと「抜き打ち零コンマ何秒」のファーストドロウできますよね。しかもトリガーガードに人差し指をかけるあたりがリアルで良いです。
ナイに関しては、これも想像ですがA7M2つまり量産試作機の一台なのではと想像します。彼自身が述べている様に、男性のロボットの生存率が余りに低いイメージがある事から、途中で生産を打ち切った可能性が感じられるのです。ナイは初期型だから、どこかでメンテナンスを受け、かろうじて生き延びる事が出来た数少ない男性型ロボットなのでは無いでしょうか?
丸子は僕もよく分かりません。でも豊な創造性と人擦れした態度から、ココネより旧型である様な気もします。このあたりは、いずれ物語りが進むに連れて自然に決まり、また語られて行くことでしょう。アルファさんと丸子が現在の記録者であると言う見解も興味深いです。それより、僕はアルファ型の情報コネクタがディープキスを行った時の「舌」にあるらしい事に興味を持っています。カメラの視線をインターフェースケーブルの玉をくわえる事で見る事ができたり、表面効果翼艇や飛行機の外部センサーとリンク出来たり。
何よりココネが丸子にナイの撮った写真の情報を「お届け」する様子を見て思ったのですが、あれが唯一の情報伝達手段なら、ナイも武蔵野宅配便の営業所にいるであろう、おそらくは女性職員のロボットとキスを交わして情報を送っているんでしょうね(笑)このシーンはいつか本編で見てみたいものの一つです。
17: 土竜 さん のおっしゃる事はよく分かりますし、私もその画集の解説読んでます。でも好きな物語であるが故に、好きな女の子の事を思うのに似た感情で、色々想像を巡らせ、その事を他の方とも話し合って見たいものなのですよ(笑)
本題からはずれますが、海面上昇80cmは裕福な国なら、オランダが長年やってきた様に、大堤防を築く事でなんとか耐えられる事なのかも知れません。でもアメリカのハリケーン被害のを見る限り、世界でもっとも裕福(借金は別として)なアメリカでさえ、その海面上昇には耐えられないだろうと僕は想像します。ちなみに東京の近郊ですと多摩川の河口から20数km上流の狛江のあたりが、縄文海進の時の海岸線に近い様です。狛江の中州からは、浅海に棲む二枚貝の、まだ死んでそんなに経っていない様にさえ見える化石がたくさん出ます。日本も河口から20km内陸に海岸線が入り込んだら、ほとんど多島海の様になってしまうでしょうね。まさにヨコハマ買い出し紀行の世界はそういう世界なのだと思います。
18: がおち改め高崎 さん、
僕も実は、エヴァンゲリオンと比較したり、ナウシカと比べたり、時にはパトレイバーの時代背景に想いをはせたりしました。エヴァの世界も滅びゆく世界ですし、海進が進んでいる様な描写が目につきます。ナウシカも一端火の七日間で全地球的な社会崩壊があった世界だと想います。もっともヨコハマ買い出し紀行の様に、現在の延長線上にある当たり前の世界を描いていませんので、単純な比較は難しいと想いました。
ヨコハマ買い出し紀行で一つだけ不満なのは、動物の描写が鳥と昆虫と魚介類以外ほとんどない事です。特に人口が減り一時期暴動が起こった様な世界なら増えるはずの大型犬が全くいないのが気になります。作者の目線には入っていないからなのか、それとも極端は食糧不足から家畜などが飼えない状態がつづいた世界だからなのでしょうか?個人的には、一人暮らしの老人が老犬や老描を飼っていると、ヨコハマ買い出し紀行の世界にはしっくりくると想うのですが。
僕も今まで感じてきた謎や疑問は、敢えて物語の中で説明されなくても構わないと想います。むしろ今の少し温い遠浅の海の水の様な感触のまま、様々な断片情報が少しずつ語られて行き、できるだけ長い間、こうした空想や思いこみで物語りが楽しめれば良いなと想っています。
まず複数の方がおっしゃっているのと同じように、僕はヨコハマ買い出し紀行のあら探しをするつもりでこのトピックを立てたつもりはありません。ただ一世を風靡したエヴァンゲリオン以上に「説明されない物語の背景や謎」が多い作品なので、その語られない部分を自分で補って読む事が快感になってさえいます。そういう意味では、読者であるみなさんが、私と少しずつ違う視点で、色々な想いを寄せているのがわかりうれしい限りです。
14: Ko Yuuse さん、
やはり、そう読めますよね。ロボット・アンドロイド・AIをあつかったSF作品は多いですが、近年の作品では、それを個人や企業が所有したり、廃棄したりする行為や、自意識をもったAIが、逆に独立を図ろうとする事が物語の発端になっている例が多いので、敢えてこだわってみました。でもオーナーとアルファさんの関係は所有者と所有物と言うより、初期量産型または試作型に近いAIを持つA7M2を、オーナーが自宅で人間として独立した暮らしを営める様に個人的な訓育や教育を行うための物だった様に感じます。その上で「イノセンス」でも語られた「人工的な人型を愛でる感情」もほの見える様な気がします。あるいは自分の義理の娘や姪に対する様な庇護の情なのかも知れません。こういう年長者の男性が年下の女性に見せる愛情は「ハンニバル」にも描かれていました。そう言うのなんとなく好きです。
15: Algernonさん、
終末に向かう物悲しい感情と、それに反すると言うより対応する人間関係から描かれる、一種の癒しが、ヨコハマ買い出し紀行の主題の一つなのかも知れません。人間はいつかは滅びる生き物だと想います。もしその滅びの姿を選べるのなら、僕はヨコハマ買い出し紀行の様な世界を選びたいと想います。
16: 神 雅紀 さん、
専門家の方が同じようなとらえ方をされていたのはおもしろいと思いました。ご指摘の様にアルファ型ロボットは、初期型と量産型で大分開発意図というか、目的が変わって来ているようですね。
A7M1と思われるアルファ室長の勤務先は、確かに空飛ぶ箱船の様です。それも生きた動物を載せるのではなく、大量の書籍や資料を積んでいることから、過去の文化遺産を天変地異から守る、空飛ぶ資料室なのではないかと思います。室長と言う肩書きに上司が存在するのかどうか不明ですが、僕は他の乗員が老人ばかりなのは、アルファさんを治療した医師の先生と同世代の人たちが、自ら志願して「帰れないかも知れない知的財産を守る旅」に出たからだと思っています。ですからM1自身の実年齢も相当高いのではないでしょうか?
ターポン自身も純粋な機械と言うより、生体部品を使った半生命体なのでは無いかと思います。M1のコントロールによって、新しいマズルか何かを発芽させるシーンがありましたよね?
A7M2のアルファさんは、M1と同じですが、もっと実用的に、もしかしたら兵器や乗り物の制御に使う意図もあって開発されたのでは無いかと考えたりしています。表面効果翼艇のリモートコントロールや同化が出来たりしますし、ナイのテキサンに乗った時にも自身が飛行機そのものになった様な状況さえ経験しました。ああいう360℃の視野を持つコントロール系は、兵器に搭載するAIに最適のものなのでは無いでしょうか?ちょっと嫌な想像ですが。短銃心の自動拳銃で荒れ地の標的を撃つ射撃の腕も一流ですよね。
A7M3のココネの世代になると、ある意味人口の減少を半永久的に補う労働力として作り出された汎用機である可能性が高い様に思います。ココネ自身「研修所を出る時に自分で名前を決めた」と述べていますから、ロボットを社会で運用し、人間社会を補佐する様な存在として、大量に作られた世代なのかも知れません。友人知人とのつきあいを見ていると、年齢差も余り感じられませんし。ただしココネも丸子に脅された時の反応を考えると、射撃管制能力は相当高そうに感じます。あれだと「抜き打ち零コンマ何秒」のファーストドロウできますよね。しかもトリガーガードに人差し指をかけるあたりがリアルで良いです。
ナイに関しては、これも想像ですがA7M2つまり量産試作機の一台なのではと想像します。彼自身が述べている様に、男性のロボットの生存率が余りに低いイメージがある事から、途中で生産を打ち切った可能性が感じられるのです。ナイは初期型だから、どこかでメンテナンスを受け、かろうじて生き延びる事が出来た数少ない男性型ロボットなのでは無いでしょうか?
丸子は僕もよく分かりません。でも豊な創造性と人擦れした態度から、ココネより旧型である様な気もします。このあたりは、いずれ物語りが進むに連れて自然に決まり、また語られて行くことでしょう。アルファさんと丸子が現在の記録者であると言う見解も興味深いです。それより、僕はアルファ型の情報コネクタがディープキスを行った時の「舌」にあるらしい事に興味を持っています。カメラの視線をインターフェースケーブルの玉をくわえる事で見る事ができたり、表面効果翼艇や飛行機の外部センサーとリンク出来たり。
何よりココネが丸子にナイの撮った写真の情報を「お届け」する様子を見て思ったのですが、あれが唯一の情報伝達手段なら、ナイも武蔵野宅配便の営業所にいるであろう、おそらくは女性職員のロボットとキスを交わして情報を送っているんでしょうね(笑)このシーンはいつか本編で見てみたいものの一つです。
17: 土竜 さん のおっしゃる事はよく分かりますし、私もその画集の解説読んでます。でも好きな物語であるが故に、好きな女の子の事を思うのに似た感情で、色々想像を巡らせ、その事を他の方とも話し合って見たいものなのですよ(笑)
本題からはずれますが、海面上昇80cmは裕福な国なら、オランダが長年やってきた様に、大堤防を築く事でなんとか耐えられる事なのかも知れません。でもアメリカのハリケーン被害のを見る限り、世界でもっとも裕福(借金は別として)なアメリカでさえ、その海面上昇には耐えられないだろうと僕は想像します。ちなみに東京の近郊ですと多摩川の河口から20数km上流の狛江のあたりが、縄文海進の時の海岸線に近い様です。狛江の中州からは、浅海に棲む二枚貝の、まだ死んでそんなに経っていない様にさえ見える化石がたくさん出ます。日本も河口から20km内陸に海岸線が入り込んだら、ほとんど多島海の様になってしまうでしょうね。まさにヨコハマ買い出し紀行の世界はそういう世界なのだと思います。
18: がおち改め高崎 さん、
僕も実は、エヴァンゲリオンと比較したり、ナウシカと比べたり、時にはパトレイバーの時代背景に想いをはせたりしました。エヴァの世界も滅びゆく世界ですし、海進が進んでいる様な描写が目につきます。ナウシカも一端火の七日間で全地球的な社会崩壊があった世界だと想います。もっともヨコハマ買い出し紀行の様に、現在の延長線上にある当たり前の世界を描いていませんので、単純な比較は難しいと想いました。
ヨコハマ買い出し紀行で一つだけ不満なのは、動物の描写が鳥と昆虫と魚介類以外ほとんどない事です。特に人口が減り一時期暴動が起こった様な世界なら増えるはずの大型犬が全くいないのが気になります。作者の目線には入っていないからなのか、それとも極端は食糧不足から家畜などが飼えない状態がつづいた世界だからなのでしょうか?個人的には、一人暮らしの老人が老犬や老描を飼っていると、ヨコハマ買い出し紀行の世界にはしっくりくると想うのですが。
僕も今まで感じてきた謎や疑問は、敢えて物語の中で説明されなくても構わないと想います。むしろ今の少し温い遠浅の海の水の様な感触のまま、様々な断片情報が少しずつ語られて行き、できるだけ長い間、こうした空想や思いこみで物語りが楽しめれば良いなと想っています。
ええっと、一応「ハードSF」の用語に拘っておきたいのですが
>10: 史嶋 桂 様
> あえてハードSFと明言しなかったとも言えます(笑)
と書いておられますが、しかしこのトピックのタイトルは
「ヨコハマ買い出し紀行ってハードSF?」
となっているわけですので、一応書いておきたいのですが
> ハードSFの舞台でファンタジーに近い事をやっているのか?
> 物語そのものが、アルファさんや登場人物個々の視点で描かれているために、
> 社会としての全体像が見えず、そのためハードSFの域に達していないのか?
ここら辺を読むと、どうも史嶋桂様の「ハードSF」の定義は
一般的なものと異なるように読めます。
Wikipediaでの「ハードSF」定義を改めて紹介すると
|「ハードSF」とされる作品群においては、科学技術、とくに
|天文学・物理学・化学・数学・工学技術などの正確な描写と、
|これらの科学知識に裏付けられたアイデアが中心となる。
|なお、ここで言う「科学」は「自然科学」であり、
|人文科学や社会科学は含まれない。また、医学や心理学など
|「ソフト」な科学を取り入れたSFは、通常、「ハードSF」とは呼ばれない。
となっており、私自身もそういうイメージがありまして
社会全体の描写が克明であるかどうか
(もしくは「深刻な」社会状況を扱っているかどうか)は必ずしも
『一般的な』「ハードSF」の定義には関係してこない気がします。
史嶋桂様の今までの投稿内容から推察させて頂くと、
史嶋桂様の「ハードSF」の言葉で表現したいものというのは
「現実的にある(場合によっては深刻な)社会問題
(この中には政治問題、経済問題、地球環境問題など様々なものを含む)を、
かなりリアリティのある形でSF作品の中に取り入れ、
その行く末を想像して舞台背景や物語の中に色濃く盛り込んだSF作品」
というような感じであるかのように読めます。
これは一般的な「ハードSF」を定義する視点とかなり次元が異なる感じを受けます。
私個人的な感覚からすれば、
アルファさん達アンドロイドが脳内データを
「経口転写」する理由が明らかにされていない、
そして恐らくは今後も明らかにされない時点で
「ハードSF」と言い難い思いでいます(笑)
具体的な作品としては
私が読んだ小説の中ではジェイムズ・P・ホーガンの作品、
コミックはあまりSFは読んでいませんが
岡崎二郎の「国立博物館物語」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4091846017/
に「いかにもハードSF」って感じを受けています。
もっと雑に言えば、少しでもファンタジックな要素が入るのは
ハードSFには入れ難く、ヨコハマはやはりハードSFとは呼び難いです。
揚げ足取り的な発言で恐縮なんですが、
このトピックで初めて「ハードSF」という言葉を聞いた方が
誤解をなさるとちょっとアレなことと、
何より私自身がSF小説を比較的読み始めたばかりで
上の単語も比較的最近知ったものですから
確認のために書かせて頂きました。
細かいことで不快に思われた方がおられたらすみません。
>10: 史嶋 桂 様
> あえてハードSFと明言しなかったとも言えます(笑)
と書いておられますが、しかしこのトピックのタイトルは
「ヨコハマ買い出し紀行ってハードSF?」
となっているわけですので、一応書いておきたいのですが
> ハードSFの舞台でファンタジーに近い事をやっているのか?
> 物語そのものが、アルファさんや登場人物個々の視点で描かれているために、
> 社会としての全体像が見えず、そのためハードSFの域に達していないのか?
ここら辺を読むと、どうも史嶋桂様の「ハードSF」の定義は
一般的なものと異なるように読めます。
Wikipediaでの「ハードSF」定義を改めて紹介すると
|「ハードSF」とされる作品群においては、科学技術、とくに
|天文学・物理学・化学・数学・工学技術などの正確な描写と、
|これらの科学知識に裏付けられたアイデアが中心となる。
|なお、ここで言う「科学」は「自然科学」であり、
|人文科学や社会科学は含まれない。また、医学や心理学など
|「ソフト」な科学を取り入れたSFは、通常、「ハードSF」とは呼ばれない。
となっており、私自身もそういうイメージがありまして
社会全体の描写が克明であるかどうか
(もしくは「深刻な」社会状況を扱っているかどうか)は必ずしも
『一般的な』「ハードSF」の定義には関係してこない気がします。
史嶋桂様の今までの投稿内容から推察させて頂くと、
史嶋桂様の「ハードSF」の言葉で表現したいものというのは
「現実的にある(場合によっては深刻な)社会問題
(この中には政治問題、経済問題、地球環境問題など様々なものを含む)を、
かなりリアリティのある形でSF作品の中に取り入れ、
その行く末を想像して舞台背景や物語の中に色濃く盛り込んだSF作品」
というような感じであるかのように読めます。
これは一般的な「ハードSF」を定義する視点とかなり次元が異なる感じを受けます。
私個人的な感覚からすれば、
アルファさん達アンドロイドが脳内データを
「経口転写」する理由が明らかにされていない、
そして恐らくは今後も明らかにされない時点で
「ハードSF」と言い難い思いでいます(笑)
具体的な作品としては
私が読んだ小説の中ではジェイムズ・P・ホーガンの作品、
コミックはあまりSFは読んでいませんが
岡崎二郎の「国立博物館物語」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4091846017/
に「いかにもハードSF」って感じを受けています。
もっと雑に言えば、少しでもファンタジックな要素が入るのは
ハードSFには入れ難く、ヨコハマはやはりハードSFとは呼び難いです。
揚げ足取り的な発言で恐縮なんですが、
このトピックで初めて「ハードSF」という言葉を聞いた方が
誤解をなさるとちょっとアレなことと、
何より私自身がSF小説を比較的読み始めたばかりで
上の単語も比較的最近知ったものですから
確認のために書かせて頂きました。
細かいことで不快に思われた方がおられたらすみません。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ヨコハマ買い出し紀行 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート