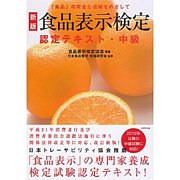http://
加工食品品質表示基準
制定平成12年3月31日農林水産省告示第513号
改正平成12年12月19日農林水産省告示第1630号
改正平成13年9月28日農林水産省告示第1336号
改正平成15年7月31日農林水産省告示第1108号
改正平成15年9月10日農林水産省告示第1402号
改正平成16年7月14日農林水産省告示第1360号
改正平成16年9月14日農林水産省告示第1705号
改正平成17年10月5日農林水産省告示第1512号
改正平成18年2月28日農林水産省告示第210号
改正平成18年6月30日農林水産省告示第909号
改正平成18年8月1日農林水産省告示第1051号
改正平成18年10月27日農林水産省告示第1463号
改正平成18年10月27日農林水産省告示第1464号
改正平成19年10月1日農林水産省告示第1172号
改正平成19年11月6日農林水産省告示第1370号
改正平成19年11月27日農林水産省告示第1488号
改正平成20年1月31日農林水産省告示第125号
改正平成20年7月23日農林水産省告示第1167号
最終改正平成21年4月9日農林水産省告示第487号
(適用の範囲)
第1条この基準は、加工食品(業務用加工食品以外の加工食品については、容器に入れ、又は包装
されたものに限る。)に適用する。
(定義)
第2条この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお
りとする。
用語定義
加工食品製造又は加工された飲食料品として別表1に掲げるものをいう。
業務用加工食品加工食品のうち、一般消費者に販売される形態となっているもの以外のもの
をいう。
賞味期限定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保
持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該
期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるも
のとする。
消費期限定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣
化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月
日をいう。
(加工食品の義務表示事項)
第3条加工食品(業務用加工食品を除く。以下この条から第4条の2までにおいて同じ。)の品質
に関し、製造業者、加工包装業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)が加工
食品の容器又は包装に表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、飲食料品を製造し、若しく
は加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合はこの限り
でない。
(1) 名称
(2) 原材料名
(3) 内容量
(4) 賞味期限
(5) 保存方法
(6) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
2 固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(固形量の管理が困難なものを除く。)にあっ
ては、製造業者等がその缶又は瓶に表示すべき事項は、前項第3号に掲げる事項に代えて、固形量
及び内容総量とする。ただし、内容総量については、固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は
充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためのものである場合は、この限りでない。
3 固形物に充てん液を加え缶及び瓶以外の容器又は包装に密封したものにあっては、製造業者等が
その缶及び瓶以外の容器又は包装に表示すべき事項は、第1項第3号に掲げる事項に代えて、固形
量とすることができる。
4 品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきものにあっては、製造業者等がその容器又
は包装に表示すべき事項は、第1項第4号に掲げる事項に代えて、消費期限とする。
5 別表2に掲げる加工食品(輸入品を除く。以下「対象加工食品」という。)にあっては、製造業
者等がその容器又は包装に表示すべき事項は、第1項各号に掲げるもののほか、原料原産地名とす
る。
6 輸入品にあっては、製造業者等がその容器又は包装に表示すべき事項は、第1項各号に掲げるも
ののほか、原産国名とする。
7 第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっては、同表の右欄
に掲げる表示事項を省略することができる。
区分表示事項
容器又は包装の面積が30á以下であるもの原材料名、賞味期限又は消費期限
、保存方法及び原料原産地名
原材料が1種類のみであるもの(缶詰及び食肉製品を除く。) 原材料名
内容量を外見上容易に識別できるもの(特定商品の販売に係内容量
る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第5条に掲
げる特定商品を除く。)
品質の変化が極めて少ないものとして別表3に掲げるもの賞味期限及び保存方法
常温で保存すること以外にその保存方法に関し留意すべき特保存方法
段の事項がないもの
(加工食品の表示の方法)
第4条前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項、同条第2項の固形量及び内容総量、同条第
3項の固形量、同条第4項の消費期限並びに同条第5項の原料原産地名の表示に際しては、製造業
者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(1) 名称
その内容を表す一般的な名称を記載すること。ただし、別表4の左欄に掲げる加工食品以外の
ものにあっては、それぞれ同表の右欄に掲げる規定により定められた名称を記載してはならない
。
(2) 原材料名
使用した原材料を、ア及びイの区分により、次に定めるところにより記載すること。
ア食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般
的な名称をもって記載すること。ただし、2種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原
材料」という。)については、次に定めるところにより記載すること。
(ア) 複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材
料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。
ただし、当該複合原材料の原材料が3種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材
料に占める重量の割合の多い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材
料について、「その他」と記載することができる。
(イ) 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名
称からその原材料が明らかである場合には、当該複合原材料の原材料の記載を省略すること
ができる。
イ食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和
23年厚生省令第23号)第21条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規
定に従い記載すること。
ウアの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっては、同表の右欄
に掲げる名称をもって記載することができる。
区分名称
食用油脂「植物油」、「植物脂」若しくは
「植物油脂」、「動物油」、「動
物脂」若しくは「動物油脂」又は
「加工油」、「加工脂」若しくは
「加工油脂」
でん粉「でん粉」
魚類及び魚肉(特定の種類の魚類の名称を表示していない場「魚」又は「魚肉」
合に限る。)
家きん肉(食肉製品を除き、特定の種類の家きんの名称を表「鳥肉」
示していない場合に限る。)
無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び全糖ぶどう糖「ぶどう糖」
ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖「異性化液糖」
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び「砂糖混合異性化液糖」又は「砂
砂糖混合高果糖液糖糖・異性化液糖」
香辛料及び香辛料エキス(既存添加物名簿(平成8年厚生省「香辛料」又は「混合香辛料」
告示第120号)に掲げる食品添加物に該当するものを除き
、原材料に占める重量の割合が2%以下のものに限る。)
香辛野菜及びつまもの類並びにその加工品(原材料に占める「香草」又は「混合香草」
重量の割合が2%以下のものに限る。)
糖液をしん透させた果実(原材料に占める重量の割合が10 「糖果」
%以下のものに限る。)
弁当に含まれる副食物(外観からその原材料が明らかなもの「おかず」
に限る。)
エ農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「
法」という。)第14条の規定により格付された有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平
成17年10月27日農林水産省告示第1605号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。
)又は有機加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示
第1606号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)を原材料とする場合には、当該原
材料が有機農産物又は有機農産物加工食品である旨を記載することができる。
(3) 内容量
特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品については、計量法(平成4
年法律第51号)の規定により表示することとし、その他にあっては内容重量、内容体積又は内
容数量を表示することとし、内容重量はグラム又はキログラムの単位で、内容体積はミリリット
ル又はリットルの単位で、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して記載すること。
(4) 固形量
固形量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。
(5) 内容総量
内容総量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。
(6) 消費期限又は賞味期限
消費期限又は賞味期限を、次に定めるところにより記載すること。
ア製造から消費期限又は賞味期限までの期間が3月以内のものにあっては、次の例のいずれか
により記載すること。ただし、(イ)、(ウ)又は(エ)の場合であって、「.」を印字することが困
難であるときは、「.」を省略することができる。この場合において、月又は日が1桁の場合
は、2桁目は「0」と記載すること。
(ア)平成12年4月1日
(イ)12.4.1
(ウ)2000.4.1
(エ)00.4.1
イ製造から賞味期限までの期間が3月を超えるものにあっては、次に定めるところにより記載
すること。
(ア)次の例のいずれかにより記載すること。ただし、b、c又はdの場合であって、「.」を
印字することが困難であるときは、「.」を省略することができる。この場合において、月
が1桁の場合は、2桁目は「0」と記載すること。
a 平成12年4月
b 12.4
c 2000.4
d 00.4
(イ)(ア)の規定にかかわらず、アに定めるところにより記載することができる。
(7) 保存方法
製品の特性に従って、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存するこ
と」等と記載すること。
(8) 原料原産地名
対象加工食品にあっては、主な原材料(原材料に占める重量の割合が最も多い生鮮食品(生鮮
食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)第2条に規定するものを
いう。以下同じ。)で、かつ、当該割合が50%以上であるものをいう。以下同じ。)の原産地
を、次に定めるところにより事実に即して記載すること。
ア国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国
産品にあっては、国産である旨の記載に代えて次に掲げる地名を記載することができる。
(ア)農産物にあっては、都道府県名その他一般に知られている地名
(イ)畜産物にあっては、主たる飼養地が属する都道府県名その他一般に知られている地名
(ウ)水産物にあっては、生産(採取及び採捕を含む。)した水域の名称(以下「水域名」とい
う。)、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県名その他一般に
知られている地名
イ輸入された水産物にあっては、原産国名に水域名を併記することができる。
ウ主な原材料の原産地が2以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものか
ら順に記載すること。
エ主な原材料の原産地が3以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものか
ら順に2以上記載し、その他の原産地を「その他」と記載することができる。
オ主な原材料の性質等により特別の事情がある場合には、おおむね特定された原産地をアから
エまでの規定により記載することができる。この場合には、その旨が認識できるよう、必要な
表示をすること。
(9) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
製造業者等のうち表示内容に責任を有するものの氏名又は名称及び住所を記載すること。
2 前条に規定する事項の表示は、次に定めるところにより、容器又は包装の見やすい箇所にしなけ
ればならない。ただし、容器又は包装を包装紙等で包装する場合又は紙箱等に入れる場合にあって
は、包装紙等若しくは紙箱等に必要な表示をし、容器若しくは包装の表示が包装紙等若しくは紙箱
等を透かして見えるようにし、又は包装紙等若しくは紙箱等で覆われないようにすること。
(1) 表示は、別記様式により行うこと。ただし、義務表示事項を別記様式による表示と同等程度に
分かりやすく一括して記載する場合は、この限りでない。
(2) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
(3) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上
の大きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね150á以下のもの
にあっては、日本工業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイント以上の大きさの活
字とすることができる。
(4) 名称については、第1号の規定にかかわらず、商品の主要面に記載することができる。この場
合において、内容量についても、名称と同じ面に記載することができる。
(5) 原材料名を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合には、第1号の規定にかか
わらず、義務表示事項を一括して表示する箇所にその記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載す
ることができる。
(6) 内容量を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合には、第1号の規定にかかわ
らず、義務表示事項を一括して表示する箇所にその記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載する
ことができる。
(7) 消費期限又は賞味期限を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合には、第1号
の規定にかかわらず、義務表示事項を一括して表示する箇所にそれらの記載箇所を表示すれば、
他の箇所に記載することができる。この場合において、保存方法についても、義務表示事項を一
括して表示する箇所にその記載箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の記載箇所に近接して
記載することができる。
(8) 原料原産地名については、主な原材料名に対応させて記載することとし、必要に応じ、主な原
材料名の次に括弧を付して記載することができる。
(9) 原料原産地名を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合には、第1号の規定に
かかわらず、義務表示事項を一括して表示する箇所にその記載箇所を表示すれば、他の箇所に記
載することができる。
3 対象加工食品にあっては主な原材料以外の原材料の原産地を、対象加工食品以外の加工食品にあ
っては原材料の原産地を第1項第8号アからオまでの規定により記載することができる。この場合
において、同号ウからオまでの規定中「主な原材料」とあるのは、「原材料」と読み替えるものと
する。
4 第2項の規定は、前項の原材料の原産地の記載について準用する。この場合において、第2項第
8号中「主な原材料名」とあるのは、「原材料名」と読み替えるものとする。
(業務用加工食品の義務表示事項及び表示の方法)
第4条の2 業務用加工食品の品質に関し、製造業者等が業務用加工食品の容器若しくは包装、送り
状、納品書等(製品に添付されるものに限る。以下同じ。)又は規格書等(製品に添付されないも
のであって、当該製品を識別できるものに限る。以下同じ。)に表示すべき事項は、次のとおりと
する。ただし、製造若しくは加工された場所で一般消費者に販売される加工食品の用に供する業務
用加工食品又は飲食料品を調理して供与する施設において飲食させる加工食品の用に供する業務用
加工食品については、この限りでない。
(1) 名称
(2) 原材料名
(3) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
2 対象加工食品の用に供する業務用加工食品(製造若しくは加工された場所で一般消費者に販売さ
れる加工食品の用に供する業務用加工食品又は飲食料品を調理して供与する施設において飲食させ
る加工食品の用に供する業務用加工食品を除く。以下「表示対象業務用加工食品」という。)であ
って当該対象加工食品の主な原材料を含むものにあっては、製造業者等がその容器若しくは包装、
送り状、納品書等又は規格書等に表示すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、原料原産地名
とする。
3 第1項の規定にかかわらず、計量法第13条第1項、食品衛生法施行規則第21条又は乳及び乳
製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第7条の規定により表示すること
とされているものにあっては、これらの規定により表示しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、加工食品(容器又は包装の面積が30cm2以下であるものに限る。
)の用に供する表示対象業務用加工食品にあっては第1項第2号の原材料名及び第2項の原料原産
地名の表示を、原材料が1種類である表示対象業務用加工食品にあっては第1項第2号の原材料名
の表示を省略することができる。
5 製造業者等は、表示対象業務用加工食品の原材料を、次に定めるところにより記載しなければな
らない。
(1) 食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多い順がわかるように、その最も一
般的な名称をもって記載すること。ただし、前条第1項第2号アの(ア)ただし書の規定により「
その他」と記載される加工食品の複合原材料の原材料となるものについては、「その他」と記載
することができる。
(2) 前条第1項第2号アの(イ)の規定により原材料の記載が省略される加工食品の複合原材料の原
材料となるものについては、その原材料の記載を省略することができる。
(3) 食品添加物以外の複合原材料については、次に定めるところにより記載すること。
ア複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料
に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。ただ
し、当該複合原材料の原材料のうち、前条第1項第2号アの(ア)ただし書の規定により「その
他」と記載される加工食品の複合原材料の原材料となるものについては、「その他」と記載す
ることができる。
イ複合原材料の原材料のうち、前条第1項第2号アの(イ)の規定により原材料の記載が省略さ
れる加工食品の複合原材料の原材料となるものについては、その原材料の記載を省略すること
ができる。
(4) 食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多い順がわかるように、食品衛生法施行規則第2
1条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。
(5) 第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっ
ては、同表の右欄に掲げる名称をもって記載することができる。
区分名称
食用油脂「植物油」、「植物脂」若しくは
「植物油脂」、「動物油」、「動
物脂」若しくは「動物油脂」又は
「加工油」、「加工脂」若しくは
「加工油脂」
でん粉「でん粉」
魚類及び魚肉(特定の種類の魚類の名称を表示していない場「魚」又は「魚肉」
合に限る。)
家きん肉(食肉製品を除き、特定の種類の家きんの名称を表「鳥肉」
示していない場合に限る。)
無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び全糖ぶどう糖「ぶどう糖」
ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖「異性化液糖」
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び「砂糖混合異性化液糖」又は「砂
砂糖混合高果糖液糖糖・異性化液糖」
香辛料及び香辛料エキス(第4条第1項第2号ウの規定によ「香辛料」又は「混合香辛料」
り「香辛料」又は「混合香辛料」と記載される加工食品の原
材料となるものに限る。)
香辛野菜及びつまもの類並びにその加工品(第4条第1項第「香草」又は「混合香草」
2号ウの規定により「香草」又は「混合香草」と記載される
加工食品の原材料となるものに限る。)
糖液をしん透させた果実(第4条第1項第2号ウの規定によ「糖果」
り「糖果」と記載される加工食品の原材料となるものに限
る。)
弁当に含まれる副食物(外観からその原材料が明らかなもの「おかず」
に限る。)
(6) 法第14条の規定により格付された有機農産物又は有機加工食品を原材料とする場合には、当
該原材料が有機農産物又は有機農産物加工食品である旨を記載することができる。
加工食品品質表示基準
制定平成12年3月31日農林水産省告示第513号
改正平成12年12月19日農林水産省告示第1630号
改正平成13年9月28日農林水産省告示第1336号
改正平成15年7月31日農林水産省告示第1108号
改正平成15年9月10日農林水産省告示第1402号
改正平成16年7月14日農林水産省告示第1360号
改正平成16年9月14日農林水産省告示第1705号
改正平成17年10月5日農林水産省告示第1512号
改正平成18年2月28日農林水産省告示第210号
改正平成18年6月30日農林水産省告示第909号
改正平成18年8月1日農林水産省告示第1051号
改正平成18年10月27日農林水産省告示第1463号
改正平成18年10月27日農林水産省告示第1464号
改正平成19年10月1日農林水産省告示第1172号
改正平成19年11月6日農林水産省告示第1370号
改正平成19年11月27日農林水産省告示第1488号
改正平成20年1月31日農林水産省告示第125号
改正平成20年7月23日農林水産省告示第1167号
最終改正平成21年4月9日農林水産省告示第487号
(適用の範囲)
第1条この基準は、加工食品(業務用加工食品以外の加工食品については、容器に入れ、又は包装
されたものに限る。)に適用する。
(定義)
第2条この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお
りとする。
用語定義
加工食品製造又は加工された飲食料品として別表1に掲げるものをいう。
業務用加工食品加工食品のうち、一般消費者に販売される形態となっているもの以外のもの
をいう。
賞味期限定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保
持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該
期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるも
のとする。
消費期限定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣
化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月
日をいう。
(加工食品の義務表示事項)
第3条加工食品(業務用加工食品を除く。以下この条から第4条の2までにおいて同じ。)の品質
に関し、製造業者、加工包装業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)が加工
食品の容器又は包装に表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、飲食料品を製造し、若しく
は加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合はこの限り
でない。
(1) 名称
(2) 原材料名
(3) 内容量
(4) 賞味期限
(5) 保存方法
(6) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
2 固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(固形量の管理が困難なものを除く。)にあっ
ては、製造業者等がその缶又は瓶に表示すべき事項は、前項第3号に掲げる事項に代えて、固形量
及び内容総量とする。ただし、内容総量については、固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は
充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためのものである場合は、この限りでない。
3 固形物に充てん液を加え缶及び瓶以外の容器又は包装に密封したものにあっては、製造業者等が
その缶及び瓶以外の容器又は包装に表示すべき事項は、第1項第3号に掲げる事項に代えて、固形
量とすることができる。
4 品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきものにあっては、製造業者等がその容器又
は包装に表示すべき事項は、第1項第4号に掲げる事項に代えて、消費期限とする。
5 別表2に掲げる加工食品(輸入品を除く。以下「対象加工食品」という。)にあっては、製造業
者等がその容器又は包装に表示すべき事項は、第1項各号に掲げるもののほか、原料原産地名とす
る。
6 輸入品にあっては、製造業者等がその容器又は包装に表示すべき事項は、第1項各号に掲げるも
ののほか、原産国名とする。
7 第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっては、同表の右欄
に掲げる表示事項を省略することができる。
区分表示事項
容器又は包装の面積が30á以下であるもの原材料名、賞味期限又は消費期限
、保存方法及び原料原産地名
原材料が1種類のみであるもの(缶詰及び食肉製品を除く。) 原材料名
内容量を外見上容易に識別できるもの(特定商品の販売に係内容量
る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第5条に掲
げる特定商品を除く。)
品質の変化が極めて少ないものとして別表3に掲げるもの賞味期限及び保存方法
常温で保存すること以外にその保存方法に関し留意すべき特保存方法
段の事項がないもの
(加工食品の表示の方法)
第4条前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項、同条第2項の固形量及び内容総量、同条第
3項の固形量、同条第4項の消費期限並びに同条第5項の原料原産地名の表示に際しては、製造業
者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(1) 名称
その内容を表す一般的な名称を記載すること。ただし、別表4の左欄に掲げる加工食品以外の
ものにあっては、それぞれ同表の右欄に掲げる規定により定められた名称を記載してはならない
。
(2) 原材料名
使用した原材料を、ア及びイの区分により、次に定めるところにより記載すること。
ア食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般
的な名称をもって記載すること。ただし、2種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原
材料」という。)については、次に定めるところにより記載すること。
(ア) 複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材
料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。
ただし、当該複合原材料の原材料が3種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材
料に占める重量の割合の多い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材
料について、「その他」と記載することができる。
(イ) 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名
称からその原材料が明らかである場合には、当該複合原材料の原材料の記載を省略すること
ができる。
イ食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和
23年厚生省令第23号)第21条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規
定に従い記載すること。
ウアの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっては、同表の右欄
に掲げる名称をもって記載することができる。
区分名称
食用油脂「植物油」、「植物脂」若しくは
「植物油脂」、「動物油」、「動
物脂」若しくは「動物油脂」又は
「加工油」、「加工脂」若しくは
「加工油脂」
でん粉「でん粉」
魚類及び魚肉(特定の種類の魚類の名称を表示していない場「魚」又は「魚肉」
合に限る。)
家きん肉(食肉製品を除き、特定の種類の家きんの名称を表「鳥肉」
示していない場合に限る。)
無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び全糖ぶどう糖「ぶどう糖」
ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖「異性化液糖」
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び「砂糖混合異性化液糖」又は「砂
砂糖混合高果糖液糖糖・異性化液糖」
香辛料及び香辛料エキス(既存添加物名簿(平成8年厚生省「香辛料」又は「混合香辛料」
告示第120号)に掲げる食品添加物に該当するものを除き
、原材料に占める重量の割合が2%以下のものに限る。)
香辛野菜及びつまもの類並びにその加工品(原材料に占める「香草」又は「混合香草」
重量の割合が2%以下のものに限る。)
糖液をしん透させた果実(原材料に占める重量の割合が10 「糖果」
%以下のものに限る。)
弁当に含まれる副食物(外観からその原材料が明らかなもの「おかず」
に限る。)
エ農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「
法」という。)第14条の規定により格付された有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平
成17年10月27日農林水産省告示第1605号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。
)又は有機加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示
第1606号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)を原材料とする場合には、当該原
材料が有機農産物又は有機農産物加工食品である旨を記載することができる。
(3) 内容量
特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品については、計量法(平成4
年法律第51号)の規定により表示することとし、その他にあっては内容重量、内容体積又は内
容数量を表示することとし、内容重量はグラム又はキログラムの単位で、内容体積はミリリット
ル又はリットルの単位で、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して記載すること。
(4) 固形量
固形量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。
(5) 内容総量
内容総量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。
(6) 消費期限又は賞味期限
消費期限又は賞味期限を、次に定めるところにより記載すること。
ア製造から消費期限又は賞味期限までの期間が3月以内のものにあっては、次の例のいずれか
により記載すること。ただし、(イ)、(ウ)又は(エ)の場合であって、「.」を印字することが困
難であるときは、「.」を省略することができる。この場合において、月又は日が1桁の場合
は、2桁目は「0」と記載すること。
(ア)平成12年4月1日
(イ)12.4.1
(ウ)2000.4.1
(エ)00.4.1
イ製造から賞味期限までの期間が3月を超えるものにあっては、次に定めるところにより記載
すること。
(ア)次の例のいずれかにより記載すること。ただし、b、c又はdの場合であって、「.」を
印字することが困難であるときは、「.」を省略することができる。この場合において、月
が1桁の場合は、2桁目は「0」と記載すること。
a 平成12年4月
b 12.4
c 2000.4
d 00.4
(イ)(ア)の規定にかかわらず、アに定めるところにより記載することができる。
(7) 保存方法
製品の特性に従って、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存するこ
と」等と記載すること。
(8) 原料原産地名
対象加工食品にあっては、主な原材料(原材料に占める重量の割合が最も多い生鮮食品(生鮮
食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)第2条に規定するものを
いう。以下同じ。)で、かつ、当該割合が50%以上であるものをいう。以下同じ。)の原産地
を、次に定めるところにより事実に即して記載すること。
ア国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国
産品にあっては、国産である旨の記載に代えて次に掲げる地名を記載することができる。
(ア)農産物にあっては、都道府県名その他一般に知られている地名
(イ)畜産物にあっては、主たる飼養地が属する都道府県名その他一般に知られている地名
(ウ)水産物にあっては、生産(採取及び採捕を含む。)した水域の名称(以下「水域名」とい
う。)、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県名その他一般に
知られている地名
イ輸入された水産物にあっては、原産国名に水域名を併記することができる。
ウ主な原材料の原産地が2以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものか
ら順に記載すること。
エ主な原材料の原産地が3以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものか
ら順に2以上記載し、その他の原産地を「その他」と記載することができる。
オ主な原材料の性質等により特別の事情がある場合には、おおむね特定された原産地をアから
エまでの規定により記載することができる。この場合には、その旨が認識できるよう、必要な
表示をすること。
(9) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
製造業者等のうち表示内容に責任を有するものの氏名又は名称及び住所を記載すること。
2 前条に規定する事項の表示は、次に定めるところにより、容器又は包装の見やすい箇所にしなけ
ればならない。ただし、容器又は包装を包装紙等で包装する場合又は紙箱等に入れる場合にあって
は、包装紙等若しくは紙箱等に必要な表示をし、容器若しくは包装の表示が包装紙等若しくは紙箱
等を透かして見えるようにし、又は包装紙等若しくは紙箱等で覆われないようにすること。
(1) 表示は、別記様式により行うこと。ただし、義務表示事項を別記様式による表示と同等程度に
分かりやすく一括して記載する場合は、この限りでない。
(2) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
(3) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上
の大きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね150á以下のもの
にあっては、日本工業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイント以上の大きさの活
字とすることができる。
(4) 名称については、第1号の規定にかかわらず、商品の主要面に記載することができる。この場
合において、内容量についても、名称と同じ面に記載することができる。
(5) 原材料名を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合には、第1号の規定にかか
わらず、義務表示事項を一括して表示する箇所にその記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載す
ることができる。
(6) 内容量を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合には、第1号の規定にかかわ
らず、義務表示事項を一括して表示する箇所にその記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載する
ことができる。
(7) 消費期限又は賞味期限を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合には、第1号
の規定にかかわらず、義務表示事項を一括して表示する箇所にそれらの記載箇所を表示すれば、
他の箇所に記載することができる。この場合において、保存方法についても、義務表示事項を一
括して表示する箇所にその記載箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の記載箇所に近接して
記載することができる。
(8) 原料原産地名については、主な原材料名に対応させて記載することとし、必要に応じ、主な原
材料名の次に括弧を付して記載することができる。
(9) 原料原産地名を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合には、第1号の規定に
かかわらず、義務表示事項を一括して表示する箇所にその記載箇所を表示すれば、他の箇所に記
載することができる。
3 対象加工食品にあっては主な原材料以外の原材料の原産地を、対象加工食品以外の加工食品にあ
っては原材料の原産地を第1項第8号アからオまでの規定により記載することができる。この場合
において、同号ウからオまでの規定中「主な原材料」とあるのは、「原材料」と読み替えるものと
する。
4 第2項の規定は、前項の原材料の原産地の記載について準用する。この場合において、第2項第
8号中「主な原材料名」とあるのは、「原材料名」と読み替えるものとする。
(業務用加工食品の義務表示事項及び表示の方法)
第4条の2 業務用加工食品の品質に関し、製造業者等が業務用加工食品の容器若しくは包装、送り
状、納品書等(製品に添付されるものに限る。以下同じ。)又は規格書等(製品に添付されないも
のであって、当該製品を識別できるものに限る。以下同じ。)に表示すべき事項は、次のとおりと
する。ただし、製造若しくは加工された場所で一般消費者に販売される加工食品の用に供する業務
用加工食品又は飲食料品を調理して供与する施設において飲食させる加工食品の用に供する業務用
加工食品については、この限りでない。
(1) 名称
(2) 原材料名
(3) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
2 対象加工食品の用に供する業務用加工食品(製造若しくは加工された場所で一般消費者に販売さ
れる加工食品の用に供する業務用加工食品又は飲食料品を調理して供与する施設において飲食させ
る加工食品の用に供する業務用加工食品を除く。以下「表示対象業務用加工食品」という。)であ
って当該対象加工食品の主な原材料を含むものにあっては、製造業者等がその容器若しくは包装、
送り状、納品書等又は規格書等に表示すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、原料原産地名
とする。
3 第1項の規定にかかわらず、計量法第13条第1項、食品衛生法施行規則第21条又は乳及び乳
製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第7条の規定により表示すること
とされているものにあっては、これらの規定により表示しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、加工食品(容器又は包装の面積が30cm2以下であるものに限る。
)の用に供する表示対象業務用加工食品にあっては第1項第2号の原材料名及び第2項の原料原産
地名の表示を、原材料が1種類である表示対象業務用加工食品にあっては第1項第2号の原材料名
の表示を省略することができる。
5 製造業者等は、表示対象業務用加工食品の原材料を、次に定めるところにより記載しなければな
らない。
(1) 食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多い順がわかるように、その最も一
般的な名称をもって記載すること。ただし、前条第1項第2号アの(ア)ただし書の規定により「
その他」と記載される加工食品の複合原材料の原材料となるものについては、「その他」と記載
することができる。
(2) 前条第1項第2号アの(イ)の規定により原材料の記載が省略される加工食品の複合原材料の原
材料となるものについては、その原材料の記載を省略することができる。
(3) 食品添加物以外の複合原材料については、次に定めるところにより記載すること。
ア複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料
に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。ただ
し、当該複合原材料の原材料のうち、前条第1項第2号アの(ア)ただし書の規定により「その
他」と記載される加工食品の複合原材料の原材料となるものについては、「その他」と記載す
ることができる。
イ複合原材料の原材料のうち、前条第1項第2号アの(イ)の規定により原材料の記載が省略さ
れる加工食品の複合原材料の原材料となるものについては、その原材料の記載を省略すること
ができる。
(4) 食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多い順がわかるように、食品衛生法施行規則第2
1条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。
(5) 第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっ
ては、同表の右欄に掲げる名称をもって記載することができる。
区分名称
食用油脂「植物油」、「植物脂」若しくは
「植物油脂」、「動物油」、「動
物脂」若しくは「動物油脂」又は
「加工油」、「加工脂」若しくは
「加工油脂」
でん粉「でん粉」
魚類及び魚肉(特定の種類の魚類の名称を表示していない場「魚」又は「魚肉」
合に限る。)
家きん肉(食肉製品を除き、特定の種類の家きんの名称を表「鳥肉」
示していない場合に限る。)
無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び全糖ぶどう糖「ぶどう糖」
ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖「異性化液糖」
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び「砂糖混合異性化液糖」又は「砂
砂糖混合高果糖液糖糖・異性化液糖」
香辛料及び香辛料エキス(第4条第1項第2号ウの規定によ「香辛料」又は「混合香辛料」
り「香辛料」又は「混合香辛料」と記載される加工食品の原
材料となるものに限る。)
香辛野菜及びつまもの類並びにその加工品(第4条第1項第「香草」又は「混合香草」
2号ウの規定により「香草」又は「混合香草」と記載される
加工食品の原材料となるものに限る。)
糖液をしん透させた果実(第4条第1項第2号ウの規定によ「糖果」
り「糖果」と記載される加工食品の原材料となるものに限
る。)
弁当に含まれる副食物(外観からその原材料が明らかなもの「おかず」
に限る。)
(6) 法第14条の規定により格付された有機農産物又は有機加工食品を原材料とする場合には、当
該原材料が有機農産物又は有機農産物加工食品である旨を記載することができる。
|
|
|
|
|
|
|
|
「食品表示検定試験」初級〜上級 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
「食品表示検定試験」初級〜上級のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75489人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6452人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208289人