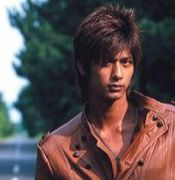|
|
|
|
コメント(72)
>>[36] 復刻版時刻表で調べて見る限りほぼ仰る通りで、夜行急行・普通列車のダイヤは特に荷物=特に新聞、郵便=特に小包の積み下ろしや積み込みに必要な停車時間を取るダイヤ編成の仕方でした。
だから国鉄の時の夜行急行・普通列車の停車時間が長く所要時間が長いのもそういった理由があるといえます。
もう1つは客車列車の場合は動力集中式の為に牽引する機関車の交換作業にも当然だけど時間が掛かります。
特に急行列車が全盛期だった昭和43年の頃はこの典型だといえます。
鉄道がこうした輸送を担っていた背景にはその当時は名神高速道路しか開通していないからそういった手段しかなかったからです。
昭和43年のダイヤ改正のもう1つの特徴は夜行列車でも急行列車の寝台特急格上げが横行した原因は高速鉄道である新幹線との連携に加えて北海道連絡による速達輸送が必要だったからです。
だから国鉄の時の夜行急行・普通列車の停車時間が長く所要時間が長いのもそういった理由があるといえます。
もう1つは客車列車の場合は動力集中式の為に牽引する機関車の交換作業にも当然だけど時間が掛かります。
特に急行列車が全盛期だった昭和43年の頃はこの典型だといえます。
鉄道がこうした輸送を担っていた背景にはその当時は名神高速道路しか開通していないからそういった手段しかなかったからです。
昭和43年のダイヤ改正のもう1つの特徴は夜行列車でも急行列車の寝台特急格上げが横行した原因は高速鉄道である新幹線との連携に加えて北海道連絡による速達輸送が必要だったからです。
国鉄時代のダイヤの引き方は速達型が特急列車、主要駅停車型が急行列車、各駅停車型が普通列車というパターンでさらに車両性能を加味しながらダイヤを引いていたといえます。
夜行列車の場合は元々からして有効時間帯で起点と終点を決定している所があることから寝台車と座席車の違いであげる方が解りやすいといえます。
全車寝台車の場合はバーター出来る座席車があることが基本パターンといえます。
もう1つは車両運用の効率の問題から昼の列車で共通運用が出来る列車は電車もしくは気動車による共通運用だったといえます。
583系電車は青森系は夜は特急はくつる・ゆうづるで昼は特急はつかり・みちのく・ひばり辺りで共通運用だったのに対して京都系は夜は特急明星・なは・彗星・金星で昼は特急有明・雷鳥・しらさぎと共通運用だったのは夜は寝台車、昼は座席車で開発した高価な交流&直流両用の電車で基本的に車庫で寝台車を解体して座席車として運用する為、そのための作業時間があるから運用出来る列車は限定される欠点がありました。
急行型電車・気動車は座席車でグリーン車連結の列車ですがこちらも共通運用するのは同じ線区の昼行便の列車で基本的に夜行便は夜間回送を兼務した営業列車扱いともいえます。
急行出羽と共通運用する昼行列車は急行いいで=磐越西線、急行おがの昼行便、季節急行ざおう=編成の波動輸送を決める列車、急行月山=陸羽西線と比較的性格が似たような線区と共通運用が組まれていました。
夜行列車の場合は元々からして有効時間帯で起点と終点を決定している所があることから寝台車と座席車の違いであげる方が解りやすいといえます。
全車寝台車の場合はバーター出来る座席車があることが基本パターンといえます。
もう1つは車両運用の効率の問題から昼の列車で共通運用が出来る列車は電車もしくは気動車による共通運用だったといえます。
583系電車は青森系は夜は特急はくつる・ゆうづるで昼は特急はつかり・みちのく・ひばり辺りで共通運用だったのに対して京都系は夜は特急明星・なは・彗星・金星で昼は特急有明・雷鳥・しらさぎと共通運用だったのは夜は寝台車、昼は座席車で開発した高価な交流&直流両用の電車で基本的に車庫で寝台車を解体して座席車として運用する為、そのための作業時間があるから運用出来る列車は限定される欠点がありました。
急行型電車・気動車は座席車でグリーン車連結の列車ですがこちらも共通運用するのは同じ線区の昼行便の列車で基本的に夜行便は夜間回送を兼務した営業列車扱いともいえます。
急行出羽と共通運用する昼行列車は急行いいで=磐越西線、急行おがの昼行便、季節急行ざおう=編成の波動輸送を決める列車、急行月山=陸羽西線と比較的性格が似たような線区と共通運用が組まれていました。
夜行急行列車の使命は寝台特急列車の補完輸送と荷物=特に新聞輸送・郵便輸送であるといえます。
夜行急行列車の多くは周遊券の需要もあったといえます。
ワイド・ミニ周遊券なら周遊券の入口までの経路指定の往復急行列車の自由席と周遊区間の急行自由席乗り放題だったから急行列車の需要が多かったといえます。
もう1つは一般周遊券は国鉄や観光地までの民鉄・バスが割引運賃だったことからその接続駅まで行く夜行列車の需要もまた多かったといえます。
夜行列車の編成にもそれが表れているといえます。特急列車は全車寝台車で編成されているのは起点付近から終点付近までの直行旅客前提であり、客層からしてビジネス旅客や大口の団体観光旅客が中心だからです。
急行列車は寝台車は特急同様に目的地までの直行旅客前提で座席車は途中での乗降客やワイド・ミニ周遊券での利用や夏は登山で冬はスキーの特殊輸送前提で荷物車は荷物輸送、郵便車は郵便輸送が前提条件だといえます。
普通列車は荷物輸送次いでの旅客扱いか昼行列車の夜間回送扱いが基本で寝台車やグリーン車は特別な接客設備でのサービス扱いだといえます。
夜行急行列車の多くは周遊券の需要もあったといえます。
ワイド・ミニ周遊券なら周遊券の入口までの経路指定の往復急行列車の自由席と周遊区間の急行自由席乗り放題だったから急行列車の需要が多かったといえます。
もう1つは一般周遊券は国鉄や観光地までの民鉄・バスが割引運賃だったことからその接続駅まで行く夜行列車の需要もまた多かったといえます。
夜行列車の編成にもそれが表れているといえます。特急列車は全車寝台車で編成されているのは起点付近から終点付近までの直行旅客前提であり、客層からしてビジネス旅客や大口の団体観光旅客が中心だからです。
急行列車は寝台車は特急同様に目的地までの直行旅客前提で座席車は途中での乗降客やワイド・ミニ周遊券での利用や夏は登山で冬はスキーの特殊輸送前提で荷物車は荷物輸送、郵便車は郵便輸送が前提条件だといえます。
普通列車は荷物輸送次いでの旅客扱いか昼行列車の夜間回送扱いが基本で寝台車やグリーン車は特別な接客設備でのサービス扱いだといえます。
アメリカ (O型社会)は、貨物列車優先で、旅客輸送は、メインターゲットにしている客層に対するサービス(オマケ)だといえます。
(O型社会)は、貨物列車優先で、旅客輸送は、メインターゲットにしている客層に対するサービス(オマケ)だといえます。
日本 ・ドイツ
・ドイツ (A型社会)は、旅客列車優先が基本であるといえます。
(A型社会)は、旅客列車優先が基本であるといえます。
インド(B型社会)は、旅客列車と貨物列車は、ほぼ同等の扱いだといえます。
韓国 (AB型社会)は、運営する側の都合が、全てにおいて優先であるといえます。
(AB型社会)は、運営する側の都合が、全てにおいて優先であるといえます。
これは、アメリカ の鉄道が、獲物の輸送という考え方から来ているといえます。
の鉄道が、獲物の輸送という考え方から来ているといえます。
日本 ・ドイツ
・ドイツ の鉄道が旅客優先なのは、土地に利益を落としてくれる旅客が大事だといえます。
の鉄道が旅客優先なのは、土地に利益を落としてくれる旅客が大事だといえます。
インドの鉄道は、変な言い方すると、運搬が何よりも重要だからである。
韓国 の鉄道は、運営する側の都合が優先なのは、出来る限り効率重視の考え方だからである。
の鉄道は、運営する側の都合が優先なのは、出来る限り効率重視の考え方だからである。
日本
インド(B型社会)は、旅客列車と貨物列車は、ほぼ同等の扱いだといえます。
韓国
これは、アメリカ
日本
インドの鉄道は、変な言い方すると、運搬が何よりも重要だからである。
韓国
公共交通機関のサービスは、大概にして、その地域の民度や客層が反映されているように、その国の代表的な鉄道のダイヤ構成は、その国の国民性がやはり反映されているといえます。
アメリカ(O型社会)は、鉄道は獲物を運ぶ手段という大雑把なダイヤ構成。
日本・ドイツ(A型社会)は、快適性重視の料金の必要な列車(特急列車)と地域輸送重視の料金不要な列車(普通列車)の極端なダイヤ構成。
インド(B型社会)は、色んな種別や色んな運転系統が入り乱れて走る、カオスなダイヤ構成。
韓国(AB型社会)は、出発地から目的地までのスピード(速達性)重視のダイヤ構成。
このことにも、やはり社会のカラーが解るといえます。
アメリカ(O型社会)は、鉄道は獲物を運ぶ手段という大雑把なダイヤ構成。
日本・ドイツ(A型社会)は、快適性重視の料金の必要な列車(特急列車)と地域輸送重視の料金不要な列車(普通列車)の極端なダイヤ構成。
インド(B型社会)は、色んな種別や色んな運転系統が入り乱れて走る、カオスなダイヤ構成。
韓国(AB型社会)は、出発地から目的地までのスピード(速達性)重視のダイヤ構成。
このことにも、やはり社会のカラーが解るといえます。
日本(A型社会)と韓国(AB型社会)は夜行列車のダイヤの引き方にも、違いが表れているともいえます。
日本の寝台特急の典型的な事例は北陸(上野〜金沢)で、下りは富山・金沢、上りは大宮・上野で有効時間帯(5時〜6時)に入るように、途中の機関車交換する長岡で運転停車して時間調整するのは、有名でした。
韓国の夜行列車はそんなこと一切なしで、終着駅を朝の3時〜5時の時間帯に到着するようなダイヤが組まれていた点に大きな違いがあります。
旅客優先の日本と運営する側の都合優先の韓国の違いがよく表れている事例だといえます。
韓国の場合は、通勤列車の時間帯を確保する為に、夜行列車を有効時間帯に一切入れない所でも解る位です。
日本の寝台特急の典型的な事例は北陸(上野〜金沢)で、下りは富山・金沢、上りは大宮・上野で有効時間帯(5時〜6時)に入るように、途中の機関車交換する長岡で運転停車して時間調整するのは、有名でした。
韓国の夜行列車はそんなこと一切なしで、終着駅を朝の3時〜5時の時間帯に到着するようなダイヤが組まれていた点に大きな違いがあります。
旅客優先の日本と運営する側の都合優先の韓国の違いがよく表れている事例だといえます。
韓国の場合は、通勤列車の時間帯を確保する為に、夜行列車を有効時間帯に一切入れない所でも解る位です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
悪いか?鉄道マニアで… 更新情報
-
最新のアンケート
悪いか?鉄道マニアで…のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170675人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90052人