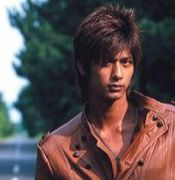|
|
|
|
コメント(57)
>>[18] 寝台特急に関しては、昭和57年のダイヤ改正から、車両を三段式から二段式に変更したり、二段式に改造する特急が相次ぎました。
その中でも、車両運用の乱れは皮肉なことに、出世列車の伝統から、急行津軽のA寝台の需要の高さの絡みで急行十和田で余剰になった、20系を転用した所からだといえます。
これが大誤算となり、積み残しが相次ぎ、その結果として、季節急行おが(14系座席車)と編成を丸ごと交換しましたが、その結果として、客からのブーイングが起きて、特急紀伊の廃止で余剰になった寝台車を譲り受けましたが、多客期には、臨時特急あけぼのとの編成交換したりと、車両運用が完全に乱れていました。
もう1つは、20系客車をいくら臨時とはいっても、種別を特急にすることからして、間違っているといえます。
その中でも、車両運用の乱れは皮肉なことに、出世列車の伝統から、急行津軽のA寝台の需要の高さの絡みで急行十和田で余剰になった、20系を転用した所からだといえます。
これが大誤算となり、積み残しが相次ぎ、その結果として、季節急行おが(14系座席車)と編成を丸ごと交換しましたが、その結果として、客からのブーイングが起きて、特急紀伊の廃止で余剰になった寝台車を譲り受けましたが、多客期には、臨時特急あけぼのとの編成交換したりと、車両運用が完全に乱れていました。
もう1つは、20系客車をいくら臨時とはいっても、種別を特急にすることからして、間違っているといえます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
悪いか?鉄道マニアで… 更新情報
-
最新のアンケート