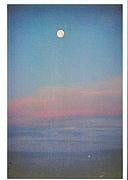私が調べた概略です。付け加える点、エピソードなどよろしくお願いします。
・峰崎勾当(みねざき こうとう)
生没年不詳。天明寛政(1781〜1801)ごろ、大阪で活躍した。
『虚実柳巷方言』(1794)であげるうた上手の法師たちのなかに「みね崎」の名がみえる。
「長うた一挺弾の達人」といわれた豊賀検校の弟子で、
大阪系地歌歌本、享和 1(1801)年版『新大成糸のしらべ』の校訂者のひとり。
大阪系の端歌物・手事物(てごともの)の完成に貢献した。
特に「雪」は端歌物の、「残月」は手事物の、それぞれ大阪系の頂点とされる。
主要作品
・手事物
「残月」
「越後獅子」
「吾妻獅子」
「都獅子」
「有馬獅子」
「玉椿」
「梅の月」
「月」
「翁」
・端歌もの
「雪」
「袖香炉」
「小簾の戸」
「袖の露」
「別世界」
「花の旅」
「忍び駒」
「大仏」
「新縁の綱」
[参考:「筝曲地歌大系」解説書(平野健次)、朝日日本歴史人物事典(大貫紀子)、
邦楽百科事典(監修:吉川英史)、Wikipedia]
・峰崎勾当(みねざき こうとう)
生没年不詳。天明寛政(1781〜1801)ごろ、大阪で活躍した。
『虚実柳巷方言』(1794)であげるうた上手の法師たちのなかに「みね崎」の名がみえる。
「長うた一挺弾の達人」といわれた豊賀検校の弟子で、
大阪系地歌歌本、享和 1(1801)年版『新大成糸のしらべ』の校訂者のひとり。
大阪系の端歌物・手事物(てごともの)の完成に貢献した。
特に「雪」は端歌物の、「残月」は手事物の、それぞれ大阪系の頂点とされる。
主要作品
・手事物
「残月」
「越後獅子」
「吾妻獅子」
「都獅子」
「有馬獅子」
「玉椿」
「梅の月」
「月」
「翁」
・端歌もの
「雪」
「袖香炉」
「小簾の戸」
「袖の露」
「別世界」
「花の旅」
「忍び駒」
「大仏」
「新縁の綱」
[参考:「筝曲地歌大系」解説書(平野健次)、朝日日本歴史人物事典(大貫紀子)、
邦楽百科事典(監修:吉川英史)、Wikipedia]
|
|
|
|
コメント(12)
白水社出版の『よくわかる筝曲地歌の基礎知識』(久保田敏子著)の峰崎の項には「薄雪」という作品もあるようです。また「根曳の松」の筝手付けもしているそうです。
「翁」「梅の月」「有馬獅子」なんかは遠くなってしまったんじゃないかと思います。
「翁」は富崎春昇、菊茂琴昇、「有馬獅子」は富山清翁が音源を残しています。
http://jiuta.at.webry.info/200809/index.html
↑「有馬獅子」など、良い演奏家の地歌が沢山アップされています。
「花の旅」はどうしたことか山田流へいったとのことで地歌筝曲大系に中田博之が残しています。
「雪」「小簾の戸」あたりは色々な演奏家が残していますが、「玉椿」「梅の月」「忍び駒」 「大仏」 「新縁の綱」 は楽譜を見たことも、曲を聴いたこともありません。是非知りたいものです。
「翁」「梅の月」「有馬獅子」なんかは遠くなってしまったんじゃないかと思います。
「翁」は富崎春昇、菊茂琴昇、「有馬獅子」は富山清翁が音源を残しています。
http://jiuta.at.webry.info/200809/index.html
↑「有馬獅子」など、良い演奏家の地歌が沢山アップされています。
「花の旅」はどうしたことか山田流へいったとのことで地歌筝曲大系に中田博之が残しています。
「雪」「小簾の戸」あたりは色々な演奏家が残していますが、「玉椿」「梅の月」「忍び駒」 「大仏」 「新縁の綱」 は楽譜を見たことも、曲を聴いたこともありません。是非知りたいものです。
>ありすさん
だけど、こういう伝承は異説もままありますから、「根曳の松」の筝…う〜ん、あるのでしょうか…。
ちなみにこの本では「都獅子」は京都の津山検校作曲となっていますが、う〜んこちらもどういうことでしょうね。
それから『邦楽』(日本音楽叢書6、音楽の友社、1990)の「峰崎勾当と松浦検校について」(執筆は久保田敏子氏)という項に、峰崎の作品は「異説も含めて34曲を数える」というので、菊岡、松浦に並ぶ多作ですね。全部伝承されているのか気になります。
名古屋の国風音楽会の演奏家の、あるCDに、松浦の、珍しい、名前も聞いたことのない端唄が収録されていたので、びっくりしました。峰崎の作品もガラパゴスかシーラカンスみたいに存在してないでしょうかね〜。
だけど、こういう伝承は異説もままありますから、「根曳の松」の筝…う〜ん、あるのでしょうか…。
ちなみにこの本では「都獅子」は京都の津山検校作曲となっていますが、う〜んこちらもどういうことでしょうね。
それから『邦楽』(日本音楽叢書6、音楽の友社、1990)の「峰崎勾当と松浦検校について」(執筆は久保田敏子氏)という項に、峰崎の作品は「異説も含めて34曲を数える」というので、菊岡、松浦に並ぶ多作ですね。全部伝承されているのか気になります。
名古屋の国風音楽会の演奏家の、あるCDに、松浦の、珍しい、名前も聞いたことのない端唄が収録されていたので、びっくりしました。峰崎の作品もガラパゴスかシーラカンスみたいに存在してないでしょうかね〜。
その豊賀検校も玉岡検校と共作で「口切」という追善物を作っていますね。
大学の頃、ある教授(仮にH先生)の古文書の授業で、鎌倉時代の古文書は、ほぼ整理できている。室町時代の古文書の収集も、かなり進んでいる。しかし江戸時代というのはまだまだ未発見の物が多いと仰っていました。
そのH先生は、東日本の農家などの古文書をかなり収集・整理された方だとあとで人づてに聞きました。
それで、H先生の仰るには、古文書というのは我々にとってはなんでもないようでも、その家の人間にとって良い記録ばかりでない、プライバシーに関わることがかなりあって、いくら先祖のことでも、出し渋る人がかなりいた、それを頂戴するのに大分骨を折ったということでした。
何を申し上げたいかというと、峰崎は「残月」に関わる記録から、商家の子女を弟子にとっていたり、勾当でありながら、菊崎検校と『新大成糸のしらべ』の編纂に関わったりしたことが分かるくらいですから、もしかしたら、まだ記録が出てくる可能性があるのではないかと思うのです。
検校くらいになれば、いつ登官したかとか、大名屋敷に出入りすれば必ず記録に残りますが、勾当で終わった人々、石川、藤尾、三橋、在原、そして峰崎は、今後の史家の発見を待ちます。
まぁ峰崎くらいの人であれば、検校になれなくとも、商家や花街の弟子に教えたり、そこまで不自由なく悠々と暮らしていけたでしょうから、平気だったかも知れませんね。
大学の頃、ある教授(仮にH先生)の古文書の授業で、鎌倉時代の古文書は、ほぼ整理できている。室町時代の古文書の収集も、かなり進んでいる。しかし江戸時代というのはまだまだ未発見の物が多いと仰っていました。
そのH先生は、東日本の農家などの古文書をかなり収集・整理された方だとあとで人づてに聞きました。
それで、H先生の仰るには、古文書というのは我々にとってはなんでもないようでも、その家の人間にとって良い記録ばかりでない、プライバシーに関わることがかなりあって、いくら先祖のことでも、出し渋る人がかなりいた、それを頂戴するのに大分骨を折ったということでした。
何を申し上げたいかというと、峰崎は「残月」に関わる記録から、商家の子女を弟子にとっていたり、勾当でありながら、菊崎検校と『新大成糸のしらべ』の編纂に関わったりしたことが分かるくらいですから、もしかしたら、まだ記録が出てくる可能性があるのではないかと思うのです。
検校くらいになれば、いつ登官したかとか、大名屋敷に出入りすれば必ず記録に残りますが、勾当で終わった人々、石川、藤尾、三橋、在原、そして峰崎は、今後の史家の発見を待ちます。
まぁ峰崎くらいの人であれば、検校になれなくとも、商家や花街の弟子に教えたり、そこまで不自由なく悠々と暮らしていけたでしょうから、平気だったかも知れませんね。
>鰯(かたくち)さん
古文書というのは確かにプライバシーですね。考えてもみませんでした。
いくら歴史的に重要とはいえ、古文書が残っているような家はそれなりの名門でしょうから、
体面を気にされるのもわかるような気が致します。
そうなんですよね、検校に登官していれば、公的な記録に残りやすいのですが、
勾当だと、どうしてもそうした私的な古文書が頼りになりますね。
今でも眠っている記録の中にいろいろ新事実があるかもしれません。期待したいです。
ところで、勾当だからといって、必ずしも貧しいわけではないのはそのとおりだと思いますよ。
三つ橋などは、「松竹梅」「根曳の松」が許し物の最高ランクである「三役」として扱われたため、
かなりの収入があったという話です。大ヒット曲が生まれたら当時でもお金になったんですね。
峰崎も、おそらく裕福な商家とつながりがあったことから、
パトロンのような存在も考えれれますし、そう貧しくはなかったでしょうね。
古文書というのは確かにプライバシーですね。考えてもみませんでした。
いくら歴史的に重要とはいえ、古文書が残っているような家はそれなりの名門でしょうから、
体面を気にされるのもわかるような気が致します。
そうなんですよね、検校に登官していれば、公的な記録に残りやすいのですが、
勾当だと、どうしてもそうした私的な古文書が頼りになりますね。
今でも眠っている記録の中にいろいろ新事実があるかもしれません。期待したいです。
ところで、勾当だからといって、必ずしも貧しいわけではないのはそのとおりだと思いますよ。
三つ橋などは、「松竹梅」「根曳の松」が許し物の最高ランクである「三役」として扱われたため、
かなりの収入があったという話です。大ヒット曲が生まれたら当時でもお金になったんですね。
峰崎も、おそらく裕福な商家とつながりがあったことから、
パトロンのような存在も考えれれますし、そう貧しくはなかったでしょうね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
峰崎勾当 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
峰崎勾当のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 171647人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209264人
- 3位
- 朝ドラで話そ♪あんぱん
- 1019人