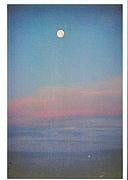|
|
|
|
コメント(17)
個々の作品の魅力の前に、私が感じる峰崎の魅力は、
本当に三絃のための作品を書いた方だな、と言う事です。
師である豊賀検校は、「鎌倉八景」「月見」「木遣」などの長歌物の
三絃一挺弾の達人といわれ、おそらくその影響ではないかと思います。
私は尺八吹きですが、「残月」はともかく、峰崎作品は、吹けば吹くほどに
「ああ、三絃の曲だよな」と、悲しくなってしまいます。
それどころか、箏でさえ受け付けないくらい、三絃特有の語法を活かした曲作りだと思います。
手事物の場合は、本手・替手による三絃二挺での演奏が一番いいなと思います。
端歌物は言わずもがな、三絃一挺弾ですよね。
私は端歌物は西松文一さん、手事物は矢木敬二さんの演奏が好きです。
本当に三絃のための作品を書いた方だな、と言う事です。
師である豊賀検校は、「鎌倉八景」「月見」「木遣」などの長歌物の
三絃一挺弾の達人といわれ、おそらくその影響ではないかと思います。
私は尺八吹きですが、「残月」はともかく、峰崎作品は、吹けば吹くほどに
「ああ、三絃の曲だよな」と、悲しくなってしまいます。
それどころか、箏でさえ受け付けないくらい、三絃特有の語法を活かした曲作りだと思います。
手事物の場合は、本手・替手による三絃二挺での演奏が一番いいなと思います。
端歌物は言わずもがな、三絃一挺弾ですよね。
私は端歌物は西松文一さん、手事物は矢木敬二さんの演奏が好きです。
>鰯(かたくち)さん
そうなんですよね。伊達に「集大成者」といわれているわけではないですよね。
おっしゃるとおり、動機単位では先行する規範作品である三味線組歌や長歌物の
作り方を凄く忍ばせますね。特に一の糸の使い方が効果バツグンで、
サワリの音が実に心地いい。弾いている方はどれほどか、と思います。
「吾妻獅子」は、峰崎の手事物の中では最も好きな作品なのですが、
私は石川勾当手付による三絃替手との三絃二挺の演奏が一番だと思います。
業平を気取った田舎者が、格好をつけて後朝の舞を踊る手事、
マジメに作曲しつつも、その滑稽さを表現するには、箏や尺八は適さないと考えます。
手事二段目になり、二上がりになって、ますます調子に乗るその男、
着物の着崩れにも目もくれず、自分では最高の舞を踊ったつもりが、
周りの失笑を買う様が眼前に浮かぶようです。
これは峰崎の本手の作曲技術はもちろん、さすが天才石川勾当と思わせる、
替手でのその演出ぶり、これに他の楽器が入る余地はないような気がします。
そういえばお説の砧地は他の作品でもよく出てきますよね。
確かに「憧憬」という言葉はふさわしいのかもしれません。
そうなんですよね。伊達に「集大成者」といわれているわけではないですよね。
おっしゃるとおり、動機単位では先行する規範作品である三味線組歌や長歌物の
作り方を凄く忍ばせますね。特に一の糸の使い方が効果バツグンで、
サワリの音が実に心地いい。弾いている方はどれほどか、と思います。
「吾妻獅子」は、峰崎の手事物の中では最も好きな作品なのですが、
私は石川勾当手付による三絃替手との三絃二挺の演奏が一番だと思います。
業平を気取った田舎者が、格好をつけて後朝の舞を踊る手事、
マジメに作曲しつつも、その滑稽さを表現するには、箏や尺八は適さないと考えます。
手事二段目になり、二上がりになって、ますます調子に乗るその男、
着物の着崩れにも目もくれず、自分では最高の舞を踊ったつもりが、
周りの失笑を買う様が眼前に浮かぶようです。
これは峰崎の本手の作曲技術はもちろん、さすが天才石川勾当と思わせる、
替手でのその演出ぶり、これに他の楽器が入る余地はないような気がします。
そういえばお説の砧地は他の作品でもよく出てきますよね。
確かに「憧憬」という言葉はふさわしいのかもしれません。
連続投稿の上に私事で恐縮ですが、今井慶松の「越後獅子」「吾妻獅子」をブログにアップしました。
http://music.geocities.yahoo.co.jp/gl/fortunatissimo89/view/201002
2月と3月にまたがってしまいましたが、3月を開いて頂ければ、「吾妻獅子」がお聴き頂けます。
やはり華やか過ぎて、今井慶松の何々という感じですが、往時を偲ぶには参考になるかと思います。
他にかなりランダム(乱雑)な掲載になりましたが、「六段」「八段」「乱れ」があります。何分SPレコードから起こしたもので、まとまった形にできないのですがお暇があればどうぞ、お聴き下さい。
http://music.geocities.yahoo.co.jp/gl/fortunatissimo89/view/201002
2月と3月にまたがってしまいましたが、3月を開いて頂ければ、「吾妻獅子」がお聴き頂けます。
やはり華やか過ぎて、今井慶松の何々という感じですが、往時を偲ぶには参考になるかと思います。
他にかなりランダム(乱雑)な掲載になりましたが、「六段」「八段」「乱れ」があります。何分SPレコードから起こしたもので、まとまった形にできないのですがお暇があればどうぞ、お聴き下さい。
>鰯(かたくち)さん
上のサイトはたしか吉沢コミュで鰯(かたくち)さんが紹介されたサイトではなかったでしょうか。
本当に昔の名人の演奏はSP収録の都合もあるのでしょうから速いのですが、味わいがあります。
今井慶松さんの「吾妻獅子」、確かにかなり華やかですね。
古い録音だからでしょうか、ちょっと音量レベルが低いので聞き取りづらいですが、十分に伝わります。
しかし、今井慶松さんが演奏されると、箏のきらびやかさが本当に特徴的で、
峰崎の作品、という感じはあまりしないことも確かですね。
しかし演奏が見事なことは確かだと思います。
まあ、それほどまでの名人、ということなのだと思います。
上のサイトはたしか吉沢コミュで鰯(かたくち)さんが紹介されたサイトではなかったでしょうか。
本当に昔の名人の演奏はSP収録の都合もあるのでしょうから速いのですが、味わいがあります。
今井慶松さんの「吾妻獅子」、確かにかなり華やかですね。
古い録音だからでしょうか、ちょっと音量レベルが低いので聞き取りづらいですが、十分に伝わります。
しかし、今井慶松さんが演奏されると、箏のきらびやかさが本当に特徴的で、
峰崎の作品、という感じはあまりしないことも確かですね。
しかし演奏が見事なことは確かだと思います。
まあ、それほどまでの名人、ということなのだと思います。
>ありすさん
音量が小さいのは、恥ずかしながら横着の故でして、この今井の「吾妻獅子」「越後獅子」は、一度MDに録音したのをソニーのウォークマンに再録したのです。
つまり又録りで音質をさげてしまっているのです。
大分華やかで江戸っ子の好みなのでしょうね。この「越後獅子」は、なんとなく長唄の方を思い浮かべます。
でも峰崎はきっと越後の角兵衛獅子を実際に見物したか、その話を聞いたのでしょうね。「牡丹は持たねど越後の獅子は己が姿を花と見て」という文句は、現実の角兵衛獅子をやっている子どもがどういう境遇か知っていたことを表していると思います。こういう文句は、他の作品、「残月」や「別世界」のような、峰崎の暖かい眼差しが感じられます。
そういえば歌詞についてはあまり専門書でも云々されないようですが、私は作曲者と作詞者は(他のジャンルでもそうだし)かなり話合って作ったのではないかと思うのですよ。
義太夫節の豊竹麓太夫(1730-1822)が『絵本大功記』の十段目を初演する折、自分の女房に、作者も連れて聴いてもらい、女房が感動するまで、三度書き直させた、という逸話があります。
そこまでかどうかは分かりませんが、地歌筝曲演奏者が作詞に関わることはあり得ることだと思います。
たとえば名詞などの抽象性が低い、逆に言えば具体性が高いと思います。「東下りのまめ男」とか「越路潟」など、場所やどういう人間かを特定しているのは長歌もの以外の手事物で、源氏物語に取材した作品以外では、こういう歌詞を用いている例は少ないと思います。
それから庶民的な平明な語彙、たとえば「花の姿の吉原なまり」「七つか八目鰻まで」ですね。端唄では具体性が高い(というのは、端歌は、文学系統でいえば俳諧から来ていると指摘している方がいました)のですが、やはり手事物ではあまりないことかと思います。
それから、重複しますが全体が、直截的な表現であることがいえると思います。言いかえれば、誰がどうしているか割合はっきりしている文章であると思えます。
そのあたりはやはり長歌物と類似点を多く見出せると思います。
たとえば「残月」と、追善物に分類される松浦検校の「里の暁」をくらべた場合、前者は格調高い文章ですが、枕詞や縁語は多用しておらず、磯辺の松から月が見えている風景に、亡き人を仮託しているとすぐに分かります。
ところが「里の暁」の場合「梓弓」の枕詞から始まり、「いるかたゆかし」、「烏羽玉」「蛍」「かげろう」のように、掛詞、枕詞、縁語など、かなり和歌の技法を駆使していることがわかります。
松浦の「里の暁」の場合その歌詞の抽象度の高さや飛躍が音楽的イメージを膨らませるのに役に立っていると思います。文学的にはあくまで比喩ですが前唄が、「もろこしの」に向かう入れ子式の枕詞のようです。
峰崎においては、おそらくそのような抽象的な表現よりも、もっと初期の(組歌や長歌のような、旅や恋を率直に歌った)三弦音楽の持っていた具体的なイメージが好きだったのではないか、と思えます。
なので、「吾妻獅子」「越後獅子」では主人公の旅をしたり、踊る様子が、「残月」では瞑想的にじっと月を眺める主人公の様子が、伺えるような気がします。
音量が小さいのは、恥ずかしながら横着の故でして、この今井の「吾妻獅子」「越後獅子」は、一度MDに録音したのをソニーのウォークマンに再録したのです。
つまり又録りで音質をさげてしまっているのです。
大分華やかで江戸っ子の好みなのでしょうね。この「越後獅子」は、なんとなく長唄の方を思い浮かべます。
でも峰崎はきっと越後の角兵衛獅子を実際に見物したか、その話を聞いたのでしょうね。「牡丹は持たねど越後の獅子は己が姿を花と見て」という文句は、現実の角兵衛獅子をやっている子どもがどういう境遇か知っていたことを表していると思います。こういう文句は、他の作品、「残月」や「別世界」のような、峰崎の暖かい眼差しが感じられます。
そういえば歌詞についてはあまり専門書でも云々されないようですが、私は作曲者と作詞者は(他のジャンルでもそうだし)かなり話合って作ったのではないかと思うのですよ。
義太夫節の豊竹麓太夫(1730-1822)が『絵本大功記』の十段目を初演する折、自分の女房に、作者も連れて聴いてもらい、女房が感動するまで、三度書き直させた、という逸話があります。
そこまでかどうかは分かりませんが、地歌筝曲演奏者が作詞に関わることはあり得ることだと思います。
たとえば名詞などの抽象性が低い、逆に言えば具体性が高いと思います。「東下りのまめ男」とか「越路潟」など、場所やどういう人間かを特定しているのは長歌もの以外の手事物で、源氏物語に取材した作品以外では、こういう歌詞を用いている例は少ないと思います。
それから庶民的な平明な語彙、たとえば「花の姿の吉原なまり」「七つか八目鰻まで」ですね。端唄では具体性が高い(というのは、端歌は、文学系統でいえば俳諧から来ていると指摘している方がいました)のですが、やはり手事物ではあまりないことかと思います。
それから、重複しますが全体が、直截的な表現であることがいえると思います。言いかえれば、誰がどうしているか割合はっきりしている文章であると思えます。
そのあたりはやはり長歌物と類似点を多く見出せると思います。
たとえば「残月」と、追善物に分類される松浦検校の「里の暁」をくらべた場合、前者は格調高い文章ですが、枕詞や縁語は多用しておらず、磯辺の松から月が見えている風景に、亡き人を仮託しているとすぐに分かります。
ところが「里の暁」の場合「梓弓」の枕詞から始まり、「いるかたゆかし」、「烏羽玉」「蛍」「かげろう」のように、掛詞、枕詞、縁語など、かなり和歌の技法を駆使していることがわかります。
松浦の「里の暁」の場合その歌詞の抽象度の高さや飛躍が音楽的イメージを膨らませるのに役に立っていると思います。文学的にはあくまで比喩ですが前唄が、「もろこしの」に向かう入れ子式の枕詞のようです。
峰崎においては、おそらくそのような抽象的な表現よりも、もっと初期の(組歌や長歌のような、旅や恋を率直に歌った)三弦音楽の持っていた具体的なイメージが好きだったのではないか、と思えます。
なので、「吾妻獅子」「越後獅子」では主人公の旅をしたり、踊る様子が、「残月」では瞑想的にじっと月を眺める主人公の様子が、伺えるような気がします。
>鰯(かたくち)さん
音量はそういうことでしたか。でも十分特徴は伝わってきましたし、
貴重な音源をありがとうございました。機会がありましたらまたよろしくお願いします。
作品の歌詞面からのご考察、非常に興味をそそられました。
たしかに、音楽面だけでなく、そうした比較的平明な歌詞というものも、
先行規範作品である長歌物の特徴と言えますね。全く頭から抜けていました。
>峰崎の暖かい眼差し
慧眼だと思います。峰崎作品は、曲中の登場人物への暖かいまなざし、
人間愛、そういったものが感じられますね。
「別世界」は、年が明けたと思われる遊女という珍しい題材で、
直接的に人情を感じさせる歌詞ですし、
「袖香炉」は師への追善物でありながら、大規模な手事物ではなく、
煙草好きだったという師の生前の様子が眼前に浮かぶような、
なにか生前親しかった方だけでの密葬のような趣がします。
逆に「残月」では、愛弟子の生前の様子が、大規模かつ華やかな手事で、
いかに故人が魅力的な女性であったか、伝わってくるようです。
「吾妻獅子」においても、非常に人間観察が優れているというか、
この業平気取りの男がなにか憎めない様子が伝わってきます。
こうして歌詞の傾向から伺うに、結構人間が好きだった人だったのではないでしょうか。
峰崎勾当自身の人柄まで伺えるような気がします。
そう考えると、歌詞選択の傾向というものも、作曲家を考える上では
やはり大切な観点であるといえるでしょうね。
そう考えると、「里の暁」での技巧を凝らした歌詞、
いかにも知的な作風の松浦が好みそうな歌詞であり、
そこがまた、松浦の創作意欲をかきたてている、
そんなことが感じられて面白いですね。
音量はそういうことでしたか。でも十分特徴は伝わってきましたし、
貴重な音源をありがとうございました。機会がありましたらまたよろしくお願いします。
作品の歌詞面からのご考察、非常に興味をそそられました。
たしかに、音楽面だけでなく、そうした比較的平明な歌詞というものも、
先行規範作品である長歌物の特徴と言えますね。全く頭から抜けていました。
>峰崎の暖かい眼差し
慧眼だと思います。峰崎作品は、曲中の登場人物への暖かいまなざし、
人間愛、そういったものが感じられますね。
「別世界」は、年が明けたと思われる遊女という珍しい題材で、
直接的に人情を感じさせる歌詞ですし、
「袖香炉」は師への追善物でありながら、大規模な手事物ではなく、
煙草好きだったという師の生前の様子が眼前に浮かぶような、
なにか生前親しかった方だけでの密葬のような趣がします。
逆に「残月」では、愛弟子の生前の様子が、大規模かつ華やかな手事で、
いかに故人が魅力的な女性であったか、伝わってくるようです。
「吾妻獅子」においても、非常に人間観察が優れているというか、
この業平気取りの男がなにか憎めない様子が伝わってきます。
こうして歌詞の傾向から伺うに、結構人間が好きだった人だったのではないでしょうか。
峰崎勾当自身の人柄まで伺えるような気がします。
そう考えると、歌詞選択の傾向というものも、作曲家を考える上では
やはり大切な観点であるといえるでしょうね。
そう考えると、「里の暁」での技巧を凝らした歌詞、
いかにも知的な作風の松浦が好みそうな歌詞であり、
そこがまた、松浦の創作意欲をかきたてている、
そんなことが感じられて面白いですね。
今井勉師と三品千代子師の「月」は大変結構でございます。
ただ聴いていて思ったのは、本当に峰崎の作品なのか知らん?という疑問で、その理由は…
1.歌の音域が広い
端歌以外の峰崎の作品(というか手事物)は、音域が狭い物ばかりだと思うのですが、かなり高音の箇所がありますね。
2・歌詞
かなり上品で、恋愛について一貫性のある文章で、割合長文です。京都系の作曲家が好みそうな趣です。
3.手事
楽譜がないのでなんともいえないのですが、段構成ではないのでは?
以上、「月」に関する疑問点です。まぁ作品は作曲者の一面を表しているに過ぎないとは思いますが、どなたかご教示下さい。
それから、筝手付けは小松検校とのことで、三弦を食ってしまいかねない流麗な旋律です。う〜ん、今のわたしでは善悪わかりませんねぇ。
ただ聴いていて思ったのは、本当に峰崎の作品なのか知らん?という疑問で、その理由は…
1.歌の音域が広い
端歌以外の峰崎の作品(というか手事物)は、音域が狭い物ばかりだと思うのですが、かなり高音の箇所がありますね。
2・歌詞
かなり上品で、恋愛について一貫性のある文章で、割合長文です。京都系の作曲家が好みそうな趣です。
3.手事
楽譜がないのでなんともいえないのですが、段構成ではないのでは?
以上、「月」に関する疑問点です。まぁ作品は作曲者の一面を表しているに過ぎないとは思いますが、どなたかご教示下さい。
それから、筝手付けは小松検校とのことで、三弦を食ってしまいかねない流麗な旋律です。う〜ん、今のわたしでは善悪わかりませんねぇ。
「月」に関しましては、私も異例の作品だとは感じました。
手事は段構成というより、チラシを持つもう少し後の時代の様式を
確かに偲ばせるものですよね。
伝承過程であるいは少し変容した、ということも考えれれますが、
吉沢の「古今組」をかたくなまでに原典どおり伝えている
名古屋の方々を考えると、その可能性も低いように思います。
長文の歌詞については、峰崎はともかく、大阪の作曲家のほうが
好んでいるような気もしますがどうでしょう?
ただ、確かに峰崎の他の歌詞選択の傾向とは色合いが違うかもしれませんね。
ところでいきなりですが「袖の露」なのですが、数曲同名曲があります。
峰崎作の「白糸の〜」で始まる二上りのものは、
文化文政(西暦1804〜1818)年間の作品と思われ、文化6(西暦1809)年刊の
「大成よしの山」に詞章が初出なので、これが峰崎作品とすると
この頃までは存命だった、と考えることが出来ます。
とすると、作風変化も考慮でき、「月」は晩年の作品だったのでは?
と、私は考えています。
手事は段構成というより、チラシを持つもう少し後の時代の様式を
確かに偲ばせるものですよね。
伝承過程であるいは少し変容した、ということも考えれれますが、
吉沢の「古今組」をかたくなまでに原典どおり伝えている
名古屋の方々を考えると、その可能性も低いように思います。
長文の歌詞については、峰崎はともかく、大阪の作曲家のほうが
好んでいるような気もしますがどうでしょう?
ただ、確かに峰崎の他の歌詞選択の傾向とは色合いが違うかもしれませんね。
ところでいきなりですが「袖の露」なのですが、数曲同名曲があります。
峰崎作の「白糸の〜」で始まる二上りのものは、
文化文政(西暦1804〜1818)年間の作品と思われ、文化6(西暦1809)年刊の
「大成よしの山」に詞章が初出なので、これが峰崎作品とすると
この頃までは存命だった、と考えることが出来ます。
とすると、作風変化も考慮でき、「月」は晩年の作品だったのでは?
と、私は考えています。
>ありすさん
それは藤尾勾当なんかにも当てはまるような気がしますね。
簡潔な語法で効果をあげるので、替手も三弦がいいような気がします。まぁ人によっては本手も替手も三弦はいやだという人はいますが(笑)。ああいった旋律は、これは私の勝手な憶測ですが芝居系の匂いがしますね。何となく。藤尾なんかは確実にそうだと言いたいくらいですね。
最初地歌を聴きはじめたころは、峰崎はあんまり面白くないな、特徴が分からないなと思ってたのですが、最近やっと曲風が感じられてきました。
本当に淡白に感じますね。地歌作曲者の中でも一番飄々とした作風に思えます。それが立派な演奏家の手にかかると、この淡白な曲節が、どうも言われない風格に満ちるわけですから、不思議ですね。それでいてちっとも気障でなし、俗でなし、親しみのある大らかな世界が現れてくるのですから、すごいものです。「翁」なんかも、最初はやはり淡々と運ぶのですが、それが段々尊く感じられてくるから、なんとも言えませんね、ああいう作風は。不思議です。
それは藤尾勾当なんかにも当てはまるような気がしますね。
簡潔な語法で効果をあげるので、替手も三弦がいいような気がします。まぁ人によっては本手も替手も三弦はいやだという人はいますが(笑)。ああいった旋律は、これは私の勝手な憶測ですが芝居系の匂いがしますね。何となく。藤尾なんかは確実にそうだと言いたいくらいですね。
最初地歌を聴きはじめたころは、峰崎はあんまり面白くないな、特徴が分からないなと思ってたのですが、最近やっと曲風が感じられてきました。
本当に淡白に感じますね。地歌作曲者の中でも一番飄々とした作風に思えます。それが立派な演奏家の手にかかると、この淡白な曲節が、どうも言われない風格に満ちるわけですから、不思議ですね。それでいてちっとも気障でなし、俗でなし、親しみのある大らかな世界が現れてくるのですから、すごいものです。「翁」なんかも、最初はやはり淡々と運ぶのですが、それが段々尊く感じられてくるから、なんとも言えませんね、ああいう作風は。不思議です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
峰崎勾当 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
峰崎勾当のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 171647人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209264人
- 3位
- 朝ドラで話そ♪あんぱん
- 1019人