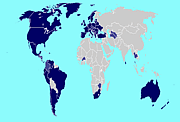キャンベル国務次官補の発言によるハーグ条約加盟について一部で
"拉致"と"奪取"は同意であるという言説が出ていますので、
一応トピを立てて認識の共通化が図れたらいいかと思います。
まずキャンベル国務次官補の発言について
以下、2010/02/07 共同ニュースより
http://
---------------------------------------
米が日本にハーグ条約加盟迫る 「拉致問題支援に悪影響」
キャンベル米国務次官補が今月初めに訪日した際、国際結婚の破綻による子どもの連れ去りに対処する「ハーグ条約」未加盟の日本の対応について「北朝鮮拉致問題での米政府の対日支援に悪影響を及ぼす恐れがある」と外務省幹部に警告、加盟を強く求めていたことが6日、分かった。複数の日米外交筋が明らかにした。
米国では、国際結婚の破綻を受け「日本人配偶者が子どもを連れて帰国し、親権を侵害された」と救済を求める事例が増えている。こうしたケースを「子の奪取」と位置付ける米側は条約加盟を要求。英国、フランスなども働き掛けを強めている。
条約加盟国は子どもを返すよう求められた場合、居場所を調べ、元の在住国に戻す義務を負う。日本政府内には慎重派が多いが、外務、法務両省の人権担当部局は条約加盟の可能性について検討を始めた。
関係者によると、キャンベル氏は、子の連れ去りは米国で「拉致」と呼ばれ、対日批判が強まっていると説明。北朝鮮に子どもを拉致された日本人被害者と、日本人の親に子を連れ去られた米国人の悲しみには「共通点がある」とし、早急な対応を求めた。
2010/02/07 02:02 【共同通信
---------------------------------------
キャンベル米国務次官補については、米国日本大使館より
http://
個人的には、「子を失った親の気持ちは同じ」という意味で情に訴えてきただけのことで、
北朝鮮の拉致事件と離婚後の子の奪取は全く意味が違うと考えます。
また米次官補の発言もそういった意図かと思います。
逆に、共同親権下では親権者が連れ去るのに比べ、日本のような単独親権の場合
全く親権を持たない親が連れ去るということもあり、その方が問題とも言えます。
(共同親権の場合でも、連れ去りによって親権を失うことになり得ますが)
いずれにせよ、外的組織による連れ去りと、肉親によるそれはその意味も目的も違い、
子供自身への影響も全く違ってきます。
よって、今回の発言をあまり問題視する必要はないかと考えますがいかがでしょうか。
ただし「外圧」という意味で重要視する観点はあり得るかと思いますが、それについてもいかがでしょうか。
"拉致"と"奪取"は同意であるという言説が出ていますので、
一応トピを立てて認識の共通化が図れたらいいかと思います。
まずキャンベル国務次官補の発言について
以下、2010/02/07 共同ニュースより
http://
---------------------------------------
米が日本にハーグ条約加盟迫る 「拉致問題支援に悪影響」
キャンベル米国務次官補が今月初めに訪日した際、国際結婚の破綻による子どもの連れ去りに対処する「ハーグ条約」未加盟の日本の対応について「北朝鮮拉致問題での米政府の対日支援に悪影響を及ぼす恐れがある」と外務省幹部に警告、加盟を強く求めていたことが6日、分かった。複数の日米外交筋が明らかにした。
米国では、国際結婚の破綻を受け「日本人配偶者が子どもを連れて帰国し、親権を侵害された」と救済を求める事例が増えている。こうしたケースを「子の奪取」と位置付ける米側は条約加盟を要求。英国、フランスなども働き掛けを強めている。
条約加盟国は子どもを返すよう求められた場合、居場所を調べ、元の在住国に戻す義務を負う。日本政府内には慎重派が多いが、外務、法務両省の人権担当部局は条約加盟の可能性について検討を始めた。
関係者によると、キャンベル氏は、子の連れ去りは米国で「拉致」と呼ばれ、対日批判が強まっていると説明。北朝鮮に子どもを拉致された日本人被害者と、日本人の親に子を連れ去られた米国人の悲しみには「共通点がある」とし、早急な対応を求めた。
2010/02/07 02:02 【共同通信
---------------------------------------
キャンベル米国務次官補については、米国日本大使館より
http://
個人的には、「子を失った親の気持ちは同じ」という意味で情に訴えてきただけのことで、
北朝鮮の拉致事件と離婚後の子の奪取は全く意味が違うと考えます。
また米次官補の発言もそういった意図かと思います。
逆に、共同親権下では親権者が連れ去るのに比べ、日本のような単独親権の場合
全く親権を持たない親が連れ去るということもあり、その方が問題とも言えます。
(共同親権の場合でも、連れ去りによって親権を失うことになり得ますが)
いずれにせよ、外的組織による連れ去りと、肉親によるそれはその意味も目的も違い、
子供自身への影響も全く違ってきます。
よって、今回の発言をあまり問題視する必要はないかと考えますがいかがでしょうか。
ただし「外圧」という意味で重要視する観点はあり得るかと思いますが、それについてもいかがでしょうか。
|
|
|
|
コメント(4)
この件につきましては、以前日記で書いたことがあります。
「拉致に甘い日本人」
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1299285719&owner_id=2699752
ここにも書きましたが、北朝鮮拉致問題と子どもの奪取を同列に論じられないのは、当然のことです。
ですが、同じ「拉致」という言葉が使われるのには、どこかしら共通する要素があるからと考えてよいのではないでしょうか。
私としては、その「共通するところ」に注目するか、「違い」を強調するか、そこにその人個人の見方考え方があらわれるように思います。
個人の考え方の相違ですから、どちらが正しい間違っていると論じるのは、ある意味「意味のない」ことではないでしょうか。
ということを前提に、私の意見を書きます。
あらかた日記で書いたので、そこからの引用をあげますが、
>上に辞書の定義を書いたとおり、拉致には「強制的に連れ去る」という意味があります。その行為によって「失われたもの・損なわれたもの」とは、いったいなんでしょうか。
ひととして一番根源的な「親子の絆」ではないでしょうか。
だからこそ、拉致被害者家族の「親子を生き別れにする北朝鮮は許せない」という叫びが、国民の共感を呼んだものと思われます。
>ですが、この二つのケースでは、国民の関心、共感の度合いがかなり違います。
はっきり言えば、「温度差」があるように思われます。
じつは私には、それがどうにも釈然としない思いがあるのです。
それが、上の日記を書いた奥底にあった「私の思い」でした。
>ですが、「親子の絆が失われた」という側面は、共通すると思います。
はたして、
「北朝鮮によって断たれた”親子の絆”」と、
「国際結婚の破綻によって断たれた”親子の絆”」と、
絆に軽重の差をつけられるものでしょうか。
>子どもの思いとしては、
「大切な親から強制的に引き離された」という事実こそがまず圧倒的で、
「自分が受けたこの傷は、国家犯罪によるものか、それとも文化慣習の違いからで、致し方ないものなのか?」と問うことは、無意味であろうと思います。
「拉致に甘い日本人」
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1299285719&owner_id=2699752
ここにも書きましたが、北朝鮮拉致問題と子どもの奪取を同列に論じられないのは、当然のことです。
ですが、同じ「拉致」という言葉が使われるのには、どこかしら共通する要素があるからと考えてよいのではないでしょうか。
私としては、その「共通するところ」に注目するか、「違い」を強調するか、そこにその人個人の見方考え方があらわれるように思います。
個人の考え方の相違ですから、どちらが正しい間違っていると論じるのは、ある意味「意味のない」ことではないでしょうか。
ということを前提に、私の意見を書きます。
あらかた日記で書いたので、そこからの引用をあげますが、
>上に辞書の定義を書いたとおり、拉致には「強制的に連れ去る」という意味があります。その行為によって「失われたもの・損なわれたもの」とは、いったいなんでしょうか。
ひととして一番根源的な「親子の絆」ではないでしょうか。
だからこそ、拉致被害者家族の「親子を生き別れにする北朝鮮は許せない」という叫びが、国民の共感を呼んだものと思われます。
>ですが、この二つのケースでは、国民の関心、共感の度合いがかなり違います。
はっきり言えば、「温度差」があるように思われます。
じつは私には、それがどうにも釈然としない思いがあるのです。
それが、上の日記を書いた奥底にあった「私の思い」でした。
>ですが、「親子の絆が失われた」という側面は、共通すると思います。
はたして、
「北朝鮮によって断たれた”親子の絆”」と、
「国際結婚の破綻によって断たれた”親子の絆”」と、
絆に軽重の差をつけられるものでしょうか。
>子どもの思いとしては、
「大切な親から強制的に引き離された」という事実こそがまず圧倒的で、
「自分が受けたこの傷は、国家犯罪によるものか、それとも文化慣習の違いからで、致し方ないものなのか?」と問うことは、無意味であろうと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ハーグ条約 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ハーグ条約のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人