はじめまして。三日ほど前から参加させていただいてます。
公文は長女(11)がやっております。
小学校1年生から算数をやっていますが、今Eの分数の計算のところです。
公文はやっている本人ができるところから繰り返し行えて、本人のペースでできるので、少しずつでも確実に身に付いて先に進めるのがいいと思っています。
ところが、うちの長女はケアレスミスが多すぎます。やり方はわかっているけど、最後まで約分しないだの、引き算なのに足し算したり、途中の計算で簡単な計算ミスをしたり・・。
単に集中力の問題でしょうか。
それと、同じ形式の問題を何度もやって、次の段階にいくと、その後また少し前にやった形式の問題をやろうとしても、すぐに忘れてしまって、「これ、どうやるんだっけ・・・」と立ち往生することも多々あります。
今は分数の計算で、もぼEが終わったのですが、テストをやって、分数の四則計算が次々に出てきて、頭がごちゃごちゃになてパニくってました。
もっと前には、足し算、引き算、掛け算、割り算、多分どのときも、桁が大きくなる度に、それまでとちょっと違うだけでやり方がわからなくて戸惑ってました。
カンが鈍いというか・・・。
ひたすら何度もやるしかないのでしょうか。
同じような経験されてるかたいらっしゃいませんか?
もしくはご指導されていらっしゃる方で、どのような対処されたか経験ございませんか?
公文は長女(11)がやっております。
小学校1年生から算数をやっていますが、今Eの分数の計算のところです。
公文はやっている本人ができるところから繰り返し行えて、本人のペースでできるので、少しずつでも確実に身に付いて先に進めるのがいいと思っています。
ところが、うちの長女はケアレスミスが多すぎます。やり方はわかっているけど、最後まで約分しないだの、引き算なのに足し算したり、途中の計算で簡単な計算ミスをしたり・・。
単に集中力の問題でしょうか。
それと、同じ形式の問題を何度もやって、次の段階にいくと、その後また少し前にやった形式の問題をやろうとしても、すぐに忘れてしまって、「これ、どうやるんだっけ・・・」と立ち往生することも多々あります。
今は分数の計算で、もぼEが終わったのですが、テストをやって、分数の四則計算が次々に出てきて、頭がごちゃごちゃになてパニくってました。
もっと前には、足し算、引き算、掛け算、割り算、多分どのときも、桁が大きくなる度に、それまでとちょっと違うだけでやり方がわからなくて戸惑ってました。
カンが鈍いというか・・・。
ひたすら何度もやるしかないのでしょうか。
同じような経験されてるかたいらっしゃいませんか?
もしくはご指導されていらっしゃる方で、どのような対処されたか経験ございませんか?
|
|
|
|
コメント(9)
はじめまして。人生の半分以上公文式とともにあった者です。今は助手をしています。
前半は、ケアレスミスのお話でしょうか。私の経験ですと、同じようなケアレスミスがずっと続いていく生徒さんはいません。
今、分数と言うことなので、分数の計算の仕方がまだ良くわからなかったり、慣れてなかったりすることによるのかもしれません。この場合たとえば、生徒さんが分数の計算の仕方(足し算など)に不安があるので、計算(足し算)さえ出来れば安心してしまい、約分などを忘れてしまうといったことが考えられます。
単純な分数の約分の問題や、2桁同士の足し算・引き算ができない訳では無いと思いますので、そんなに気にすることも無いかと思います。私の教室の生徒さんも、分数の計算に入った頃は、間違いが連続してしまうこともありますが、一人の例外もなく、皆さん乗り越えてますよ〜。
後半は、応用力のお話でしょうか。公文式の教材は、前の問題が解けるなら、この問題も解けるはず、と思わせてくれます。ところが、「然うは問屋が卸さない」のです。。。
割り算の筆算で、30÷2はできる、40÷2もできる。ところが50÷2はできない、なんてケースは珍しく無いかもしれませんね。「30÷2が出来たなら、これも出来るでしょう。」と言ってみても、出来ないのです。しょうがない?ので、割り算のやり方をもう一度説明すると、できるようになります。
やり方を忘れた、うまく出来ないときには、きちっと最初から教えれば出来ると思いますので、それでよいと思います。実際に私の公文式の経験上、前の問題を見て、今の問題に活かせるな、と思い始めたのはG教材以降だったと記憶しています。
明らかに約分が出来ない、足し算が出来ない、なんていうことは指導者も分かるはずなので、その場合は、戻ることもあるでしょうが、教えれば分かるのであれば、問題は無いと思っています。
それから、一助手が言う身分ではありませんが、お子さんが問題を解けるのは当たり前だとは思わずに、問題が解けたら、褒める・認めるということを、言葉には出さなくとも、態度で示してみてはどうでしょうか。分数あたりから1枚あたりにかかる時間は延びてしまいますので、苦しくなるとは思いますが、次第に解ける喜びを感じるのも事実です。
長くなって、要領を得ていません。あくまで参考までにどうぞ。
前半は、ケアレスミスのお話でしょうか。私の経験ですと、同じようなケアレスミスがずっと続いていく生徒さんはいません。
今、分数と言うことなので、分数の計算の仕方がまだ良くわからなかったり、慣れてなかったりすることによるのかもしれません。この場合たとえば、生徒さんが分数の計算の仕方(足し算など)に不安があるので、計算(足し算)さえ出来れば安心してしまい、約分などを忘れてしまうといったことが考えられます。
単純な分数の約分の問題や、2桁同士の足し算・引き算ができない訳では無いと思いますので、そんなに気にすることも無いかと思います。私の教室の生徒さんも、分数の計算に入った頃は、間違いが連続してしまうこともありますが、一人の例外もなく、皆さん乗り越えてますよ〜。
後半は、応用力のお話でしょうか。公文式の教材は、前の問題が解けるなら、この問題も解けるはず、と思わせてくれます。ところが、「然うは問屋が卸さない」のです。。。
割り算の筆算で、30÷2はできる、40÷2もできる。ところが50÷2はできない、なんてケースは珍しく無いかもしれませんね。「30÷2が出来たなら、これも出来るでしょう。」と言ってみても、出来ないのです。しょうがない?ので、割り算のやり方をもう一度説明すると、できるようになります。
やり方を忘れた、うまく出来ないときには、きちっと最初から教えれば出来ると思いますので、それでよいと思います。実際に私の公文式の経験上、前の問題を見て、今の問題に活かせるな、と思い始めたのはG教材以降だったと記憶しています。
明らかに約分が出来ない、足し算が出来ない、なんていうことは指導者も分かるはずなので、その場合は、戻ることもあるでしょうが、教えれば分かるのであれば、問題は無いと思っています。
それから、一助手が言う身分ではありませんが、お子さんが問題を解けるのは当たり前だとは思わずに、問題が解けたら、褒める・認めるということを、言葉には出さなくとも、態度で示してみてはどうでしょうか。分数あたりから1枚あたりにかかる時間は延びてしまいますので、苦しくなるとは思いますが、次第に解ける喜びを感じるのも事実です。
長くなって、要領を得ていません。あくまで参考までにどうぞ。
書き込みありがとうございます。
小原直美さん、素敵ですね。
「ほら、ゆっくり丁寧にやればできるでしょ!大丈夫!あせらなくてもいいんだよ。」と言ってあげてました。
そうですね。こうやって言ってあげると子どもも違うでしょうね。でもここまでの余裕が私に無かったですね。
今、こうやってMixiに参加できていること自体、私に周りを見る、知る余裕が少し出来たということなんです。
こうやって他の方のお話を伺うと、自分の固まっているものの見方が揺さぶられて、少しやわらかくなりそうです。
公文に長く携わっていらっしゃったきょうゆさん、体験からのお話はとてもわかりやすく、客観的なご意見で、自分の考えが修正出来そうです。
そうです。私の質問。二つありますね。
ケアレスミスについて。
分数の計算に関しては、確かに現在やっているところだし、四則計算を駆使して行わなければいけないので、大変かと思っています。ただ、同じ間違いではありませんが、はじめたときからケアレスミスが多くて、直しが大変です。
でも本人いたってそれを気にしないとか、100点を取ってやろうという気持ちがなくて、ただ、やっているだけ・・という態度に親があせってしまうのかもしれません。
ケアレスミスに関しては、もう少し寛大な気持ちを持ってみてみます。
応用について。
「公文式の教材は、前の問題が解けるなら、この問題も解けるはず、と思わせてくれます。ところが、「然うは問屋が卸さない」のです。。。 」
そうなんです。公文の教材って、一つ一つのステップが低くて、これができたら次もできるでしょう・・・・って思わせてくれます。でも子どもってだめなんですね。そのお言葉一つだけでも随分楽になりました。
ましてやきょうゆさんの経験から、そう考えられるようになったのがG教材なんて・・・、は〜、先は長いですね。でも目安ができて親としてはよりどころが出来ました。
だからと言って、うちの子がG教材でそうならなくても、あまり焦らないと思います。これがこの子のペースなんだと思えます。
褒める・認める。
なかなか親子の関係では、難しいですね。
実践している方もいらっしゃるでしょうし、自然とそうされてらっしゃる方もいると思いますが、できるできないより、子どもの態度に腹を立てるほうが多いかも。
ところで、トピックとは少し変わってしまいますが、算数の教材は、普通同じ問題を何回ぐらいやるものですか?
一つの教材は200枚ありますが、うちの子は3回繰り返しやっています。それでもミスが多いようならもう一回、必要な部部をやっているようです。
小原直美さん、素敵ですね。
「ほら、ゆっくり丁寧にやればできるでしょ!大丈夫!あせらなくてもいいんだよ。」と言ってあげてました。
そうですね。こうやって言ってあげると子どもも違うでしょうね。でもここまでの余裕が私に無かったですね。
今、こうやってMixiに参加できていること自体、私に周りを見る、知る余裕が少し出来たということなんです。
こうやって他の方のお話を伺うと、自分の固まっているものの見方が揺さぶられて、少しやわらかくなりそうです。
公文に長く携わっていらっしゃったきょうゆさん、体験からのお話はとてもわかりやすく、客観的なご意見で、自分の考えが修正出来そうです。
そうです。私の質問。二つありますね。
ケアレスミスについて。
分数の計算に関しては、確かに現在やっているところだし、四則計算を駆使して行わなければいけないので、大変かと思っています。ただ、同じ間違いではありませんが、はじめたときからケアレスミスが多くて、直しが大変です。
でも本人いたってそれを気にしないとか、100点を取ってやろうという気持ちがなくて、ただ、やっているだけ・・という態度に親があせってしまうのかもしれません。
ケアレスミスに関しては、もう少し寛大な気持ちを持ってみてみます。
応用について。
「公文式の教材は、前の問題が解けるなら、この問題も解けるはず、と思わせてくれます。ところが、「然うは問屋が卸さない」のです。。。 」
そうなんです。公文の教材って、一つ一つのステップが低くて、これができたら次もできるでしょう・・・・って思わせてくれます。でも子どもってだめなんですね。そのお言葉一つだけでも随分楽になりました。
ましてやきょうゆさんの経験から、そう考えられるようになったのがG教材なんて・・・、は〜、先は長いですね。でも目安ができて親としてはよりどころが出来ました。
だからと言って、うちの子がG教材でそうならなくても、あまり焦らないと思います。これがこの子のペースなんだと思えます。
褒める・認める。
なかなか親子の関係では、難しいですね。
実践している方もいらっしゃるでしょうし、自然とそうされてらっしゃる方もいると思いますが、できるできないより、子どもの態度に腹を立てるほうが多いかも。
ところで、トピックとは少し変わってしまいますが、算数の教材は、普通同じ問題を何回ぐらいやるものですか?
一つの教材は200枚ありますが、うちの子は3回繰り返しやっています。それでもミスが多いようならもう一回、必要な部部をやっているようです。
はじめまして。
私自身も子どもの頃に公文をやっていて、現在はスタッフをしています。
「算数の教材で、同じ問題を何回くらいやるのか?」というご質問に対してですが・・・。
私たちは、その子が次の番号に進む基準として、3つの柱を持っています。
1.プリントの完成時間
2.正答率
3.学習姿勢
1.はどの番号のプリントにも、「この時間でできたら、もう大丈夫」という基準の時間が設けられています。
その時間はたとえば1〜2分となっています。
(「教材内容一覧表」に載っています。よければ、教室の先生に見せていただいてください。)
これは、プリント1枚あたりにかける時間のことで、
たとえば5枚なら5〜10分でできるようになることを目安にしています。
2.はだいたい9割以上の点数をとれているかを見ます。
3.はその子が質問なしで、自分でできたかという学習姿勢をみます。
この3つがすべて満たされていれば、次の番号に進めるようになっているので、
一度で次の番号に進める場合もありますし、3回以上繰り返して、進める場合もあります。
同じ3回やるにしても、その子なりの進歩が必ずありますので、「時間が早くなったね」とか「間違いが少なくなったね」とか・・・お子さんと一緒にふりかえって、ほめる材料にしていただけたらいいなと思います。
私自身も子どもの頃に公文をやっていて、現在はスタッフをしています。
「算数の教材で、同じ問題を何回くらいやるのか?」というご質問に対してですが・・・。
私たちは、その子が次の番号に進む基準として、3つの柱を持っています。
1.プリントの完成時間
2.正答率
3.学習姿勢
1.はどの番号のプリントにも、「この時間でできたら、もう大丈夫」という基準の時間が設けられています。
その時間はたとえば1〜2分となっています。
(「教材内容一覧表」に載っています。よければ、教室の先生に見せていただいてください。)
これは、プリント1枚あたりにかける時間のことで、
たとえば5枚なら5〜10分でできるようになることを目安にしています。
2.はだいたい9割以上の点数をとれているかを見ます。
3.はその子が質問なしで、自分でできたかという学習姿勢をみます。
この3つがすべて満たされていれば、次の番号に進めるようになっているので、
一度で次の番号に進める場合もありますし、3回以上繰り返して、進める場合もあります。
同じ3回やるにしても、その子なりの進歩が必ずありますので、「時間が早くなったね」とか「間違いが少なくなったね」とか・・・お子さんと一緒にふりかえって、ほめる材料にしていただけたらいいなと思います。
こんにちは。
公文式においては「何回繰り返したか」ということは、はっきり言うと、重要では無いと思います。あくまで、現場にいる者から見てですが。理解しているかどうかが、進むためのポイントです。そのチェック方法としては、公文式では、さとみっちさんのコメントの通りです。
ただ、例えば2Aの足し算なら、20回近く繰り返すこともあるでしょう。私の教室に限ってだとは思いますが、「この部分は、どんどん先に進んでいくうちにできるようになる」という指導者の判断から、出来て無くても?進ませるケースもあります。
分数では、経験上、1回目は良い点数では無いはずですので、3回の繰り返しなら、まったく問題ないと思いますよ。もう少し進むと、復習せずに進むことになると思います。どの教材かは、お子さんの理解しだいですから、明記できませんが、あくまでの目安としてはHあるいはIくらいでしょうかね。
小学校などでは、どうしても他人と成績を比較されがちですが、公文式では他のお子さんとの比較をするといったことはほとんど無いと思います。もちろん、そこが親心としては、気になるところかもしれませんが、現場にいると、理解出来ていないお子さんより、集中出来ていないお子さんのほうが、気がかりだったりします。つまり、きちんと宿題をやって、教室で集中できていれば、伸びるのは時間の問題、だという認識でいます。
公文式においては「何回繰り返したか」ということは、はっきり言うと、重要では無いと思います。あくまで、現場にいる者から見てですが。理解しているかどうかが、進むためのポイントです。そのチェック方法としては、公文式では、さとみっちさんのコメントの通りです。
ただ、例えば2Aの足し算なら、20回近く繰り返すこともあるでしょう。私の教室に限ってだとは思いますが、「この部分は、どんどん先に進んでいくうちにできるようになる」という指導者の判断から、出来て無くても?進ませるケースもあります。
分数では、経験上、1回目は良い点数では無いはずですので、3回の繰り返しなら、まったく問題ないと思いますよ。もう少し進むと、復習せずに進むことになると思います。どの教材かは、お子さんの理解しだいですから、明記できませんが、あくまでの目安としてはHあるいはIくらいでしょうかね。
小学校などでは、どうしても他人と成績を比較されがちですが、公文式では他のお子さんとの比較をするといったことはほとんど無いと思います。もちろん、そこが親心としては、気になるところかもしれませんが、現場にいると、理解出来ていないお子さんより、集中出来ていないお子さんのほうが、気がかりだったりします。つまり、きちんと宿題をやって、教室で集中できていれば、伸びるのは時間の問題、だという認識でいます。
さとみっちさん、きょうゆさん、アドバイスありがとうございます。週末少々忙しくしてまして、書き込みできませんでした。
お二方ともに、何回やったかは問題ではない、とのこと。もちろんこれはわかっております。本人がきちんとできていないのに先に進んでも、あとで大変になるのもわかっております。
先に進むための基準の三つの柱。
どの教材ならどのくらい・・というような数字的目安はもちろんわかりませんが、本人がやっている様子をみるだけで親としてはだいたいわかります。
同じ問題を最低三回はしますので、少し早くなったな・・というのもわかります。でも正答率に関しては、ケアレスミスが多くて、わかってはいるみたいなんだけど・・・・、と帰ってくるプリントを見ながらため息です。やったプリントの80%は直しがあって戻ってきますね。
他人と比較をするつもりはないのですが、公文のだいたいの様子というか、どういう感じで他の子供達は進んでいるのか、公文の進み方というのはどういうものなのか・・・という、全体の様子が把握したいのです。
・・・・というのも、耳に入ってくることは、「公文をやっていて、二年も三年も先の教材をやっている・・」とか、「幼稚園児なのに小学校の問題を・・」などと、特出した子の話なのです。スムーズに行っているときはいいけれど、そうでないときは、やはり気弱になるというか・・。
もちろん一回で先に進めるときもあると思いますし、教材によってはどの子もつまづきやすい(たとえば分数とか・・)物もあると思います。2,3回で先に進めるなら普通だし、難しい(その子にとって)教材のところなら、5、6回やっても普通とか、10回やる子もいるなど・・と少々具体的な数字があると、目安になるというか・・・。
ですので、きょうゆさんが書かれているように、20回も繰り返す子がいる・・というのはびっくりしましたし、それを伺うと、3回やって先に進めなくても、難しいところみたいだからもう少しやっておかないと・・・とポジティブに考えられます。
今のところ全体の様子がわからないので、「3回もやってわからないの・・・!!」と思ってしまうのが今の私であり、そういう自分にも、心が狭いな〜、と自己嫌悪になります。
きょうゆさんの「現場にいると、理解出来ていないお子さんより、集中出来ていないお子さんのほうが、気がかりだったりします。つまり、きちんと宿題をやって、教室で集中できていれば、伸びるのは時間の問題、だという認識でいます。」
はとても心強く感じました。
実際のところ、うちの娘はお教室に通えないので通信で公文を続けています。お教室に行くと雰囲気に影響されて気も引き締まってやりやすいようですが、仕方ありません・・。
今回いろいろお話を伺いながら、「能力的にできるできないは、続けることによって克服することはもちろん、本人がもう少しがんぱろ〜、と思う気持ちが湧き出るのも、本人のペースで気長に待つしかないのかな・・・」という私のスタンスが少しずつハッキリしてきそうです。
お二方ともに、何回やったかは問題ではない、とのこと。もちろんこれはわかっております。本人がきちんとできていないのに先に進んでも、あとで大変になるのもわかっております。
先に進むための基準の三つの柱。
どの教材ならどのくらい・・というような数字的目安はもちろんわかりませんが、本人がやっている様子をみるだけで親としてはだいたいわかります。
同じ問題を最低三回はしますので、少し早くなったな・・というのもわかります。でも正答率に関しては、ケアレスミスが多くて、わかってはいるみたいなんだけど・・・・、と帰ってくるプリントを見ながらため息です。やったプリントの80%は直しがあって戻ってきますね。
他人と比較をするつもりはないのですが、公文のだいたいの様子というか、どういう感じで他の子供達は進んでいるのか、公文の進み方というのはどういうものなのか・・・という、全体の様子が把握したいのです。
・・・・というのも、耳に入ってくることは、「公文をやっていて、二年も三年も先の教材をやっている・・」とか、「幼稚園児なのに小学校の問題を・・」などと、特出した子の話なのです。スムーズに行っているときはいいけれど、そうでないときは、やはり気弱になるというか・・。
もちろん一回で先に進めるときもあると思いますし、教材によってはどの子もつまづきやすい(たとえば分数とか・・)物もあると思います。2,3回で先に進めるなら普通だし、難しい(その子にとって)教材のところなら、5、6回やっても普通とか、10回やる子もいるなど・・と少々具体的な数字があると、目安になるというか・・・。
ですので、きょうゆさんが書かれているように、20回も繰り返す子がいる・・というのはびっくりしましたし、それを伺うと、3回やって先に進めなくても、難しいところみたいだからもう少しやっておかないと・・・とポジティブに考えられます。
今のところ全体の様子がわからないので、「3回もやってわからないの・・・!!」と思ってしまうのが今の私であり、そういう自分にも、心が狭いな〜、と自己嫌悪になります。
きょうゆさんの「現場にいると、理解出来ていないお子さんより、集中出来ていないお子さんのほうが、気がかりだったりします。つまり、きちんと宿題をやって、教室で集中できていれば、伸びるのは時間の問題、だという認識でいます。」
はとても心強く感じました。
実際のところ、うちの娘はお教室に通えないので通信で公文を続けています。お教室に行くと雰囲気に影響されて気も引き締まってやりやすいようですが、仕方ありません・・。
今回いろいろお話を伺いながら、「能力的にできるできないは、続けることによって克服することはもちろん、本人がもう少しがんぱろ〜、と思う気持ちが湧き出るのも、本人のペースで気長に待つしかないのかな・・・」という私のスタンスが少しずつハッキリしてきそうです。
BeBeさんのお気持ちが手に取るように伝わってきます。
本当にお会いして直接お話したいくらいです。
さて・・・。
「ケアレスミスが多い・・・」ということですが。
まず、質問せずに自分の力で直せるところがポイントです。
そして、次に一度で直せるか。
二度三度続くことがあれば、その回数がだんだん減っているかどうかを見てあげてください。
お子さんの伸び方は子どもの数だけのパターンがあると思います。
子どもたちの学習状況を継続的に見ていると、
悪くなるのは徐々に・・・なのですが、よくなるのは急にだったりします。
それは、本当に日々の積み重ねにつきます。
昨日まで苦戦していたことが、今日はすんなりできたとか、自分でやり方に気づいたとか・・・奇跡のようなことがたくさ起こります。
もしかして、お子さんに対して
「あなたは、どうしてこんなケアレスミスばかりするの???」という声かけをされることはありませんか?
言葉に出ないまでも、態度に出てしまってはいませんか???
子どもたちは、お母さんのそういう雰囲気を敏感にキャッチします。
そして、それがやる気につながったりします。
私たちは「「惜しいんだけど、どこが間違っているか自分で見つけられるかな?」と励まし、できたときは大いに褒めます。
「あなたはすぐに間違えを見つけられる力をもっているんだから、次は満点めざすよ!」と声かけします。
褒められ認められることが、やる気につながる・・・その繰り返しです。
それと、直しの手順です。
よければ手元を見てあげてください。
まちがっているからと言ってすべてを消しゴムで消されてないでしょうか?
まず、どこが間違っているかをみつけ、その箇所だけ消すようにすることも上達するポイントです。
教材には「導入箇所でおさえるところ」と「経験的に数回やるところ」とありますが、
例えば「分数のたしざん1」という単元で、「1」や「2」はすらすらできるまで何度も繰り返します。(つまり正答率と時間をクリアしないと進めないところ。)
きょうゆうさんが20回繰り返すことがあると言われていたところは、こういう部分です。
私の教室のある子は去年夏休み1ヶ月かけてE41(分数のたしざん1)を克服しました。
今Fの四則混合をやっていますが、1ヶ月頑張り通したのが見事底力になっています。
通信だと親子でのやりとりが多くなると思うので、心配になられることがあると思います。
私も公文に育てられ、そのよさを体感しているので、今かかわっている大人として、できる限りお力になりたいと思っています。
また、いつでも書き込みくださいね。
(長々と書きましたが、お答えになっているでしょうか。またピントがずれていたら、遠慮なくお返しください。)
本当にお会いして直接お話したいくらいです。
さて・・・。
「ケアレスミスが多い・・・」ということですが。
まず、質問せずに自分の力で直せるところがポイントです。
そして、次に一度で直せるか。
二度三度続くことがあれば、その回数がだんだん減っているかどうかを見てあげてください。
お子さんの伸び方は子どもの数だけのパターンがあると思います。
子どもたちの学習状況を継続的に見ていると、
悪くなるのは徐々に・・・なのですが、よくなるのは急にだったりします。
それは、本当に日々の積み重ねにつきます。
昨日まで苦戦していたことが、今日はすんなりできたとか、自分でやり方に気づいたとか・・・奇跡のようなことがたくさ起こります。
もしかして、お子さんに対して
「あなたは、どうしてこんなケアレスミスばかりするの???」という声かけをされることはありませんか?
言葉に出ないまでも、態度に出てしまってはいませんか???
子どもたちは、お母さんのそういう雰囲気を敏感にキャッチします。
そして、それがやる気につながったりします。
私たちは「「惜しいんだけど、どこが間違っているか自分で見つけられるかな?」と励まし、できたときは大いに褒めます。
「あなたはすぐに間違えを見つけられる力をもっているんだから、次は満点めざすよ!」と声かけします。
褒められ認められることが、やる気につながる・・・その繰り返しです。
それと、直しの手順です。
よければ手元を見てあげてください。
まちがっているからと言ってすべてを消しゴムで消されてないでしょうか?
まず、どこが間違っているかをみつけ、その箇所だけ消すようにすることも上達するポイントです。
教材には「導入箇所でおさえるところ」と「経験的に数回やるところ」とありますが、
例えば「分数のたしざん1」という単元で、「1」や「2」はすらすらできるまで何度も繰り返します。(つまり正答率と時間をクリアしないと進めないところ。)
きょうゆうさんが20回繰り返すことがあると言われていたところは、こういう部分です。
私の教室のある子は去年夏休み1ヶ月かけてE41(分数のたしざん1)を克服しました。
今Fの四則混合をやっていますが、1ヶ月頑張り通したのが見事底力になっています。
通信だと親子でのやりとりが多くなると思うので、心配になられることがあると思います。
私も公文に育てられ、そのよさを体感しているので、今かかわっている大人として、できる限りお力になりたいと思っています。
また、いつでも書き込みくださいね。
(長々と書きましたが、お答えになっているでしょうか。またピントがずれていたら、遠慮なくお返しください。)
さとみっちさん、アドバイスありがとうございます。
とっても的を得ていて、そうなんだ〜・・・の一言です。
今まで何をそんなに不安がっていたのだろう〜っていうぐらい、ふ〜っと肩の力が抜けました。
ーもしかして、お子さんに対して
ー「あなたは、どうしてこんなケアレスミスばかりする
ーの???」という声かけをされることはありませんか?
ー言葉に出ないまでも、態度に出てしまってはいません
ーか???
お恥ずかしながら、思いっきりそのまんまです。
親子は難しいですね。公文のことだけでなく、他のことも含めて毎日一緒にいるので、なかなかゆったりした気持ちで付き合ってあげられることは少ないです。
ただ、おかげさまで公文に関しては今後、もう少し寛大な気持ちで見てあげることが出来そうです。
いろいろなお話を伺っていると、もう公文はやめようかと思うことが多々ありましたが、やっぱり続けていて正解だったかな・・と自信もつきました。
いま現在の教材が難しそうだったら、先にすすまず、また少し戻ってでも続けて行こうと思います。その先にあるものを想像すると、楽しみです。
とっても的を得ていて、そうなんだ〜・・・の一言です。
今まで何をそんなに不安がっていたのだろう〜っていうぐらい、ふ〜っと肩の力が抜けました。
ーもしかして、お子さんに対して
ー「あなたは、どうしてこんなケアレスミスばかりする
ーの???」という声かけをされることはありませんか?
ー言葉に出ないまでも、態度に出てしまってはいません
ーか???
お恥ずかしながら、思いっきりそのまんまです。
親子は難しいですね。公文のことだけでなく、他のことも含めて毎日一緒にいるので、なかなかゆったりした気持ちで付き合ってあげられることは少ないです。
ただ、おかげさまで公文に関しては今後、もう少し寛大な気持ちで見てあげることが出来そうです。
いろいろなお話を伺っていると、もう公文はやめようかと思うことが多々ありましたが、やっぱり続けていて正解だったかな・・と自信もつきました。
いま現在の教材が難しそうだったら、先にすすまず、また少し戻ってでも続けて行こうと思います。その先にあるものを想像すると、楽しみです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
公文式 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
公文式のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208311人
- 3位
- 酒好き
- 170692人
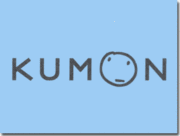



![[T02]東西線落合駅コミュ](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/27/3/12703_35s.png)



















