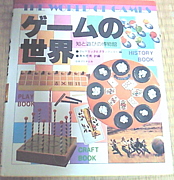盤上ゲームの魅力はプレーだけではなく、そのゲームについて書かれた極上の書籍を読むことにある…なんてことは改めて云わなくてもこのコミュに入っている方はその魅力にとりつかれた人ばかりでしょうが…
それにしても盤上ゲームの本で優れた本は実に少ないように思います。ハウツー本として役に立つものはいくらでもありますが、“本”として面白く読ませて、そのゲームの魅力が伝わるものは数えるほどしかないのではないでしょうか。
ジャンルは観戦記、実戦集、戦術書、詰物、入門書、随筆、ルールや歴史などの研究書など何でもいいですし、私個人はそれらの枠にとらわれない横断的な内容のものが好みですが、とにかくこれはという本にぶつかることはめったにないですね。
これはひとえにいいライターが少ないせいではないでしょうか?
そしてライターというのはそのゲームの魅力の伝道者として、トッププレーヤー以上に重要な存在だと思います。
ということで盤上ゲームのライターについて語り合うトピックを立ててみました。
個人的な感覚では、やはりブリッジと並んで世界のゲーム書の大半を占めると云われているチェスの世界には少数ながらいいライターがいるようです。
特に超一流だと思うのは
Irving Chernev(1900-1981 米国)
Tim Krabbe(1943- オランダ)
John Nunn(1955- 英国)
の3人です。日本ではこれに匹敵する筆力といえば将棋の若島正くらいでしょうが、若島氏の本は少し詰物に偏っているし、何よりも彼の本が書店の将棋コーナーに並ぶ状況になっていないのが悲しいですね。なお上記3人の本はチェスの本を100種類以上並べている大型書店なら古典というか定番としてだいたい何冊かあります(ありましたかな…私も最近は書籍漁りをしていないもので)。
私が一番好きだしゲームとして一番面白いと感じる囲碁では、残念ながら超一流のライターはいないように思われ、個人的に好きなのは安永一と前田陳爾ですが、やはり“囲碁ライター”の域からは出ていない気がします。
それにしても盤上ゲームの本で優れた本は実に少ないように思います。ハウツー本として役に立つものはいくらでもありますが、“本”として面白く読ませて、そのゲームの魅力が伝わるものは数えるほどしかないのではないでしょうか。
ジャンルは観戦記、実戦集、戦術書、詰物、入門書、随筆、ルールや歴史などの研究書など何でもいいですし、私個人はそれらの枠にとらわれない横断的な内容のものが好みですが、とにかくこれはという本にぶつかることはめったにないですね。
これはひとえにいいライターが少ないせいではないでしょうか?
そしてライターというのはそのゲームの魅力の伝道者として、トッププレーヤー以上に重要な存在だと思います。
ということで盤上ゲームのライターについて語り合うトピックを立ててみました。
個人的な感覚では、やはりブリッジと並んで世界のゲーム書の大半を占めると云われているチェスの世界には少数ながらいいライターがいるようです。
特に超一流だと思うのは
Irving Chernev(1900-1981 米国)
Tim Krabbe(1943- オランダ)
John Nunn(1955- 英国)
の3人です。日本ではこれに匹敵する筆力といえば将棋の若島正くらいでしょうが、若島氏の本は少し詰物に偏っているし、何よりも彼の本が書店の将棋コーナーに並ぶ状況になっていないのが悲しいですね。なお上記3人の本はチェスの本を100種類以上並べている大型書店なら古典というか定番としてだいたい何冊かあります(ありましたかな…私も最近は書籍漁りをしていないもので)。
私が一番好きだしゲームとして一番面白いと感じる囲碁では、残念ながら超一流のライターはいないように思われ、個人的に好きなのは安永一と前田陳爾ですが、やはり“囲碁ライター”の域からは出ていない気がします。
|
|
|
|
コメント(44)
これまでの本をどうやって収集・保存するかという問題とならんで、これからの本をどうするかという問題もありますね。
解決策としては、ファイルにしてネット上で流通させてしまうことが考えられます。無料で公開してもいいし、その本により収入を得たければ有料でダウンロードさせるシステムでもいいでしょう。クレジットカードサービスの代行業者は10−20%程度の手数料でやってくれるみたいですので、紙の本の印税が10−20%というのと比べると著者のうまみは大きいですし、何より“出版”というハードルが低くなります。
そしてこれは過去の本にも応用できます。一時Googleが過去のすべての(といっても著作権の問題とかはありますが)本を電子情報化するプロジェクトを推進中といったニュースが流れましたが、私は基本的にはいいことだと思います。アレクサンドリアのムセイオンの現代版ですね。
個人的な事情としては歳のせいか最近目が悪くなり、書籍の細かい字を読むのがめんどうになったということもあります。それに比べると液晶のバックライトで明るい画面は実に見やすいですね。
昔は私もビブリオマニアだったのですが、最近はファイルで充分という考えになり“本”というものに対する執着がほとんどなくなりました。保管方法がいい加減だから昔の本はすぐボロボロになってしまうというのもあります。特に米国のペーパーバックは紙質が悪いのでひどい状態です。
…と棋書に限らない一般論になってしまったので、このトピックの最初に取り上げたチェスのライターであるTim Krabbeの”Chess Curiosities”という本を取り上げると、私がこれまで読んだ盤上ゲーム書で一番面白いと思った本のひとつです。
ところがKrabbeは最近この本の内容の一部をネットで以下のように公開してしまいました。
http://www.xs4all.nl/~timkr/chess/chess.html
内容の一部といってもむしろ加筆されているくらいです。
これは何を狙っているのか?
もうこの本は充分ベストセラーになったから、このあたりで公開してファンを増やし、次の本を売ろうというのか?
そんな下種のかんぐりではなく、純粋自分の作品を広く皆に読んでもらいたいという願望なのでしょうが、紙からネットの時代になるとこのような流れが加速してくるだろうと思います。
解決策としては、ファイルにしてネット上で流通させてしまうことが考えられます。無料で公開してもいいし、その本により収入を得たければ有料でダウンロードさせるシステムでもいいでしょう。クレジットカードサービスの代行業者は10−20%程度の手数料でやってくれるみたいですので、紙の本の印税が10−20%というのと比べると著者のうまみは大きいですし、何より“出版”というハードルが低くなります。
そしてこれは過去の本にも応用できます。一時Googleが過去のすべての(といっても著作権の問題とかはありますが)本を電子情報化するプロジェクトを推進中といったニュースが流れましたが、私は基本的にはいいことだと思います。アレクサンドリアのムセイオンの現代版ですね。
個人的な事情としては歳のせいか最近目が悪くなり、書籍の細かい字を読むのがめんどうになったということもあります。それに比べると液晶のバックライトで明るい画面は実に見やすいですね。
昔は私もビブリオマニアだったのですが、最近はファイルで充分という考えになり“本”というものに対する執着がほとんどなくなりました。保管方法がいい加減だから昔の本はすぐボロボロになってしまうというのもあります。特に米国のペーパーバックは紙質が悪いのでひどい状態です。
…と棋書に限らない一般論になってしまったので、このトピックの最初に取り上げたチェスのライターであるTim Krabbeの”Chess Curiosities”という本を取り上げると、私がこれまで読んだ盤上ゲーム書で一番面白いと思った本のひとつです。
ところがKrabbeは最近この本の内容の一部をネットで以下のように公開してしまいました。
http://www.xs4all.nl/~timkr/chess/chess.html
内容の一部といってもむしろ加筆されているくらいです。
これは何を狙っているのか?
もうこの本は充分ベストセラーになったから、このあたりで公開してファンを増やし、次の本を売ろうというのか?
そんな下種のかんぐりではなく、純粋自分の作品を広く皆に読んでもらいたいという願望なのでしょうが、紙からネットの時代になるとこのような流れが加速してくるだろうと思います。
書籍のファイル化とネットでの流通・閲覧の問題で避けて通れないのは言葉の問題である。
上記書き込みのTim Krabbeのサイトは英語であるが、彼はオランダ人であるのでオランダ国内で出版される著書は当然オランダ語で書かれている。なおオランダはアリョーヒンから一時世界チャンピオンの座を奪ったオイヴェの母国でチェスが非常に盛んである。
しかしながらKrabbeくらいになると、著書のオランダ国内の売上は全体の数%であろうから、他は当然英語で出版され、特に人気のある作品については現地語の翻訳版が出るというスタイルとなる。
おそらく彼は英訳も自分で手がけるのであろうし、最初から英語で書いてオランダ語版は出さない場合もあると思われ、上記サイトもオランダ語版が存在する様子はない。
チェスの世界では、数十年前はロシア語が優勢であり真に優れた本はロシア語でしか書かれていないといわれていて、チェスを学ぶためにロシア語を学ぶ人も多かった。
しかし今はそんな時代ではない。競技チェスにおける旧ソ連圏の優位が崩れているわけではないが、少なくとも書籍チェスにおいては英語が圧倒的に優勢になっている。
余談になるが、私が専門としている自然科学のある分野は私の学生時代はドイツ語が優勢であり、ドイツ語の文献を読むのに苦労したものである。
しかしながら英語化の波には逆らいようもなく、ここ百数十年にわたりその分野での最高権威であったドイツの雑誌は、使用言語をドイツ語から英語に変えてしまった。日本の雑誌も英語化に踏み切るものが増えてきたし、オーラルの世界はまだ日本語が中心であるがこれも時間の問題かもしれない。
こういう状況を考えると、書籍の英語化の問題は避けて通れないと思われ、ネットの時代になって世界中から簡単に閲覧されるようになれば、その必要性は一段と大きくなるだろう。
英語の時代がいつまで続くかはわからない。過去の世界語ともいえるアッカド語、ギリシア語、ラテン語、アラビア語、中国語の時代が数百年から千数百年続いたのに比べると、英語の時代はわずか数十年しか続いていない。しかしながらネットの時代が始まったときに、英語が世界語であった(これは話が逆であってネット時代が始まることによって英語の世界語としての地位が確立したというべきかも)という“先行者利益”は大きく、私見では最低でもあと50年は“英語時代”が続くと思う。
こういう時代においては、盤上ゲームの世界においても英語化を念頭に置いた情報発信と情報の整理・保管は重要であると思われる。
私が最も没頭した囲碁においては、競技の世界では残念ながら江戸時代初期からの400年にわたる日本の優位が覆され、日本の囲碁は韓国・中国の後塵を拝する状態になってしまった。
しかしながらこれは逆の意味でチャンスと考えることもできる。現在は囲碁を学びたければ日本語を勉強しなさいとは云えない時代なのであるから、日本がイニシアチブをとって英語化による囲碁の普及を考えるべきであろう。
それは入門書を英語で出版するというレベルではなく、文化としての囲碁をアピールしてその魅力を伝えることが重要になるだろう。
将棋や連珠のような国外ではほとんど知られていないゲームも同様…というかそれ以上に力を注ぐべきであろう。
上記書き込みのTim Krabbeのサイトは英語であるが、彼はオランダ人であるのでオランダ国内で出版される著書は当然オランダ語で書かれている。なおオランダはアリョーヒンから一時世界チャンピオンの座を奪ったオイヴェの母国でチェスが非常に盛んである。
しかしながらKrabbeくらいになると、著書のオランダ国内の売上は全体の数%であろうから、他は当然英語で出版され、特に人気のある作品については現地語の翻訳版が出るというスタイルとなる。
おそらく彼は英訳も自分で手がけるのであろうし、最初から英語で書いてオランダ語版は出さない場合もあると思われ、上記サイトもオランダ語版が存在する様子はない。
チェスの世界では、数十年前はロシア語が優勢であり真に優れた本はロシア語でしか書かれていないといわれていて、チェスを学ぶためにロシア語を学ぶ人も多かった。
しかし今はそんな時代ではない。競技チェスにおける旧ソ連圏の優位が崩れているわけではないが、少なくとも書籍チェスにおいては英語が圧倒的に優勢になっている。
余談になるが、私が専門としている自然科学のある分野は私の学生時代はドイツ語が優勢であり、ドイツ語の文献を読むのに苦労したものである。
しかしながら英語化の波には逆らいようもなく、ここ百数十年にわたりその分野での最高権威であったドイツの雑誌は、使用言語をドイツ語から英語に変えてしまった。日本の雑誌も英語化に踏み切るものが増えてきたし、オーラルの世界はまだ日本語が中心であるがこれも時間の問題かもしれない。
こういう状況を考えると、書籍の英語化の問題は避けて通れないと思われ、ネットの時代になって世界中から簡単に閲覧されるようになれば、その必要性は一段と大きくなるだろう。
英語の時代がいつまで続くかはわからない。過去の世界語ともいえるアッカド語、ギリシア語、ラテン語、アラビア語、中国語の時代が数百年から千数百年続いたのに比べると、英語の時代はわずか数十年しか続いていない。しかしながらネットの時代が始まったときに、英語が世界語であった(これは話が逆であってネット時代が始まることによって英語の世界語としての地位が確立したというべきかも)という“先行者利益”は大きく、私見では最低でもあと50年は“英語時代”が続くと思う。
こういう時代においては、盤上ゲームの世界においても英語化を念頭に置いた情報発信と情報の整理・保管は重要であると思われる。
私が最も没頭した囲碁においては、競技の世界では残念ながら江戸時代初期からの400年にわたる日本の優位が覆され、日本の囲碁は韓国・中国の後塵を拝する状態になってしまった。
しかしながらこれは逆の意味でチャンスと考えることもできる。現在は囲碁を学びたければ日本語を勉強しなさいとは云えない時代なのであるから、日本がイニシアチブをとって英語化による囲碁の普及を考えるべきであろう。
それは入門書を英語で出版するというレベルではなく、文化としての囲碁をアピールしてその魅力を伝えることが重要になるだろう。
将棋や連珠のような国外ではほとんど知られていないゲームも同様…というかそれ以上に力を注ぐべきであろう。
これは田村竜騎兵個人に関することではなく、囲碁・将棋の観戦記者全般について感じていることですが…
囲碁・将棋欄が各新聞にあって棋譜が連載されているというのは日本独自のシステムであり、あれはよく考えると連載されているのは観戦記であって棋譜はその説明資料(mixiで言えば、本文と図表貼り付けみたいなもの)という位置づけでしょう。
その観戦記システムそのものは、私は日本が世界に誇りうる文化だと思いますが、どうも今ひとつピンとこないのは観戦記“者”システムです。
この制度下では“観戦記者”という一種の職種・職業ができてしまいますが、これは如何なものでしょう。もちろん大棋戦などでたまに起用される囲碁・将棋をろくに知らない文士観戦記者は論外ですが、どうも観戦記が本業というのはよくわかりません。なぜかというのはちょっと説明しにくいのですが、要は観戦記者がライターになるのではなくライターが観戦記者になるべきかと…
私が一番好きなのは毎日新聞に連載されていた前田陳爾の観戦記です。独特の長文であり、その文体をめぐって毎日新聞社とトラブルになり絶縁してしまったのは残念です。リアルタイムでは読んでいないのですが、父が新聞の切り抜きをスクラップしていたので読むことができたのは幸運でした。
そういえば囲碁の前田陳爾、将棋の若島正、チェスのJohn Nunnと一流のライターは詰め物が得意な人が多いですね。その昔にはサム・ロイドなんて大御所もいたし。
チェスをはじめとして、盤上ゲームの本場?がスラブ圏とみなされているのはなぜか?
19世紀まではアングロサクソンはじめゲルマン圏が本場とされていたはずであり、これは比較的最近の現象であると思います。
その時期がロシア革命と重なるため、共産主義体制と何か関係があるのかという気もしますが、ソ連崩壊以後もスラブ人の優位は続いています。
発展途上国の人口増加に歯止めがかからないのは、彼らには“それ”くらいしか愉しみがないのだろうと失言した政治家がいましたが、これは盤上ゲームについてもあてはまるのか?
それとも寒い地方では盤上ゲームくらいしかすることがないからか? もっとも寒いのはスラブ圏だけとは限りませんが…
あるいは陰険な(よくいえば緻密な)国民性か? 相手が困るように困るように指すのが盤上ゲームですから陰険な人の方が向いているかもしれませんが…
それともスラブ圏とはいうものの、その多くはユダヤ人でありアシュケナージの本場?はスラブ圏であるためか?
まあおそらくはそれらの理由が少しずつミックスしたものだろうと思います。
どの理由も日本人にはあてはまらない要素ですね。
(囲碁で)日本人が勝てなくなったのも当然かな。
もっとも偉大なプレーヤーは出なくなっても、偉大なライターなら…
囲碁・将棋欄が各新聞にあって棋譜が連載されているというのは日本独自のシステムであり、あれはよく考えると連載されているのは観戦記であって棋譜はその説明資料(mixiで言えば、本文と図表貼り付けみたいなもの)という位置づけでしょう。
その観戦記システムそのものは、私は日本が世界に誇りうる文化だと思いますが、どうも今ひとつピンとこないのは観戦記“者”システムです。
この制度下では“観戦記者”という一種の職種・職業ができてしまいますが、これは如何なものでしょう。もちろん大棋戦などでたまに起用される囲碁・将棋をろくに知らない文士観戦記者は論外ですが、どうも観戦記が本業というのはよくわかりません。なぜかというのはちょっと説明しにくいのですが、要は観戦記者がライターになるのではなくライターが観戦記者になるべきかと…
私が一番好きなのは毎日新聞に連載されていた前田陳爾の観戦記です。独特の長文であり、その文体をめぐって毎日新聞社とトラブルになり絶縁してしまったのは残念です。リアルタイムでは読んでいないのですが、父が新聞の切り抜きをスクラップしていたので読むことができたのは幸運でした。
そういえば囲碁の前田陳爾、将棋の若島正、チェスのJohn Nunnと一流のライターは詰め物が得意な人が多いですね。その昔にはサム・ロイドなんて大御所もいたし。
チェスをはじめとして、盤上ゲームの本場?がスラブ圏とみなされているのはなぜか?
19世紀まではアングロサクソンはじめゲルマン圏が本場とされていたはずであり、これは比較的最近の現象であると思います。
その時期がロシア革命と重なるため、共産主義体制と何か関係があるのかという気もしますが、ソ連崩壊以後もスラブ人の優位は続いています。
発展途上国の人口増加に歯止めがかからないのは、彼らには“それ”くらいしか愉しみがないのだろうと失言した政治家がいましたが、これは盤上ゲームについてもあてはまるのか?
それとも寒い地方では盤上ゲームくらいしかすることがないからか? もっとも寒いのはスラブ圏だけとは限りませんが…
あるいは陰険な(よくいえば緻密な)国民性か? 相手が困るように困るように指すのが盤上ゲームですから陰険な人の方が向いているかもしれませんが…
それともスラブ圏とはいうものの、その多くはユダヤ人でありアシュケナージの本場?はスラブ圏であるためか?
まあおそらくはそれらの理由が少しずつミックスしたものだろうと思います。
どの理由も日本人にはあてはまらない要素ですね。
(囲碁で)日本人が勝てなくなったのも当然かな。
もっとも偉大なプレーヤーは出なくなっても、偉大なライターなら…
日本棋院は将棋連盟と違って組織上はプロの団体ではなく、プロの組織はその内部に“棋士会”なるもの(あまり詳しくないので実態は良く知らないのですが)を作っているのかもしれません。
ただその実態はどうでしょうか? 私が最近の組織の変化に疎いのかもしれませんが、日本棋院は将棋連盟とほぼ同様にプロの利益を代表するプロの組織であるというイメージが強いのですが…
これは明治以来の、あるいはもっと古く江戸時代からの棋界の伝統であって、その時代の要求にはマッチしていた世界に先駆けた制度なのでしょうが、少なくとも現代社会において囲碁人口を増やすのには向いていないし、それでは結果的にプロの懐も潤わないことになります。
私はアマもプロもないチェスの国際組織FIDEの仕組みはよくできていると思います。
あと20年もすれば囲碁もこんな風になると思いますし、そのときには現在のプロ棋士やプロ棋戦の制度も根本的に変わっているでしょう。
ソ連の崩壊で、ロシア人とそれ以外のスラブ系、そしてトルコ系などの区別?がついてわかりやすくなりました。
特にウクライナ人は強く、ウクライナ人同士のチェスの世界タイトルマッチなんてこともありました。またロシア人に対するイメージのうち、かなりの部分がウクライナ人のイメージと混同されていると思います。
ビルマの数字がモンゴル語とは?
タイ・ビルマはサンスクリット系かと思っていましたが・・・
ただその実態はどうでしょうか? 私が最近の組織の変化に疎いのかもしれませんが、日本棋院は将棋連盟とほぼ同様にプロの利益を代表するプロの組織であるというイメージが強いのですが…
これは明治以来の、あるいはもっと古く江戸時代からの棋界の伝統であって、その時代の要求にはマッチしていた世界に先駆けた制度なのでしょうが、少なくとも現代社会において囲碁人口を増やすのには向いていないし、それでは結果的にプロの懐も潤わないことになります。
私はアマもプロもないチェスの国際組織FIDEの仕組みはよくできていると思います。
あと20年もすれば囲碁もこんな風になると思いますし、そのときには現在のプロ棋士やプロ棋戦の制度も根本的に変わっているでしょう。
ソ連の崩壊で、ロシア人とそれ以外のスラブ系、そしてトルコ系などの区別?がついてわかりやすくなりました。
特にウクライナ人は強く、ウクライナ人同士のチェスの世界タイトルマッチなんてこともありました。またロシア人に対するイメージのうち、かなりの部分がウクライナ人のイメージと混同されていると思います。
ビルマの数字がモンゴル語とは?
タイ・ビルマはサンスクリット系かと思っていましたが・・・
ウクライナとベラルーシ…所謂小ロシアと白ロシア。
(現)ウクライナ人にとってみればロシアは恨み骨髄で、もともとはロシアというのはキエフ大公国以来のウクライナのことを指していた(ルーシ)のに、いつの間にか名前ごと乗っ取ってしまって、自分たちを(大)ロシア人と呼びウクライナ人(国名を取られてしまったのでやむを得ず地方・地域というような意味のウクライナと名乗った)のことを小ロシア人なんて呼んで蔑んだのですから。スウェーデンやドイツと組んでロシアから独立しようとしたこともあるし、黒海沿岸の要地を占めて農工業も盛んですからロシアとは永久に絶縁したいところでしょうね。
べラルーシは逆にもともとポーランド(+リトアニア)の文化圏だったのを第二次大戦後ほとんどの住民をポーランドに追放して(ポーランドは玉突きのようにドイツ人を“現”ドイツに追放した)そのあとにロシア人が入ってきたんですから、ほぼロシアと一体といってもいいと思いますが、近親憎悪のようなものですかね。
いずれにせよこのあたりは盤上ゲームを得意とするスラブ系ですが、ソ連の崩壊で、各スラブ族の“顔”が見えるようになったのはいいことです。
(現)ウクライナ人にとってみればロシアは恨み骨髄で、もともとはロシアというのはキエフ大公国以来のウクライナのことを指していた(ルーシ)のに、いつの間にか名前ごと乗っ取ってしまって、自分たちを(大)ロシア人と呼びウクライナ人(国名を取られてしまったのでやむを得ず地方・地域というような意味のウクライナと名乗った)のことを小ロシア人なんて呼んで蔑んだのですから。スウェーデンやドイツと組んでロシアから独立しようとしたこともあるし、黒海沿岸の要地を占めて農工業も盛んですからロシアとは永久に絶縁したいところでしょうね。
べラルーシは逆にもともとポーランド(+リトアニア)の文化圏だったのを第二次大戦後ほとんどの住民をポーランドに追放して(ポーランドは玉突きのようにドイツ人を“現”ドイツに追放した)そのあとにロシア人が入ってきたんですから、ほぼロシアと一体といってもいいと思いますが、近親憎悪のようなものですかね。
いずれにせよこのあたりは盤上ゲームを得意とするスラブ系ですが、ソ連の崩壊で、各スラブ族の“顔”が見えるようになったのはいいことです。
連珠がもう日本人は勝てなくなりましたか・・・
そして次は将棋ですか。将棋系のゲームでは日本将棋が一番よくできていると思うので、世界に普及するにはいいことかもしれませんが・・・ 米長が”世界一将棋が強い男”とジョークで名乗っていましたが、ついにジョークでなくなる時代がそのうち。
囲碁ではもう日本が一番強かった時代のことなど知らないファンやプロが増えてきました。
イングランドにおけるサッカーがいいお手本かもしれません。サッカーの母国でありながらワールドカップの出場権すらとれない時代が続きましたが、外国人選手を積極的に誘致した結果、プレミアリーグは世界でも最もハイレベルのリーグとみなされるようになり、それに伴いイングランド選手の実力も上がってきて、最近では一応ワールドカップの優勝候補の一角にはあげられるようになりました。
そして次は将棋ですか。将棋系のゲームでは日本将棋が一番よくできていると思うので、世界に普及するにはいいことかもしれませんが・・・ 米長が”世界一将棋が強い男”とジョークで名乗っていましたが、ついにジョークでなくなる時代がそのうち。
囲碁ではもう日本が一番強かった時代のことなど知らないファンやプロが増えてきました。
イングランドにおけるサッカーがいいお手本かもしれません。サッカーの母国でありながらワールドカップの出場権すらとれない時代が続きましたが、外国人選手を積極的に誘致した結果、プレミアリーグは世界でも最もハイレベルのリーグとみなされるようになり、それに伴いイングランド選手の実力も上がってきて、最近では一応ワールドカップの優勝候補の一角にはあげられるようになりました。
言葉はわからなくても、譜面表記システムが共通語であれば理解できますね。
将棋・中国将棋は漢字・漢数字がネックでしょうか。
英語はスペルの正記法を決めておいて、発音は地域・時代によって異なるのが当然とするのがベストだと思いますが、どちらかというと発音の変化につれてスペルも変わるのが英語ですから。
ウィンブルドン現象によって英国のテニスのレベルは上がったとはいえませんが、プレミアのハイレベル化にしたがい英国(人)サッカーのレベルは確実に上がりました。これは名選手が試合のときにしか来英しないテニスとチームの一員として英国に居住するサッカーの違いだと思います。
これは囲碁に関しても同様ですね。門戸を開放するときが来ているような気がします。
将棋・中国将棋は漢字・漢数字がネックでしょうか。
英語はスペルの正記法を決めておいて、発音は地域・時代によって異なるのが当然とするのがベストだと思いますが、どちらかというと発音の変化につれてスペルも変わるのが英語ですから。
ウィンブルドン現象によって英国のテニスのレベルは上がったとはいえませんが、プレミアのハイレベル化にしたがい英国(人)サッカーのレベルは確実に上がりました。これは名選手が試合のときにしか来英しないテニスとチームの一員として英国に居住するサッカーの違いだと思います。
これは囲碁に関しても同様ですね。門戸を開放するときが来ているような気がします。
若島正さんの文章は好きです。この人の名前だけで売れるような時代になるといいんですが。
盛栄さんには学生時代から一度も勝てずじまい(まだしばらく現役ですから一度くらい・・・)でしたが、毎日で書いていますか。入社時は囲碁関係にはあまり関りたくないと云っていたようですが、やはり好きな題材で書くのが一番ですから。
チェスと将棋のサイマルテニアスはあまり意義があるとは思えませんが、話題作りにはいいのでしょうね。ちなみに将棋盤で将棋とチェスの一組の駒で戦ったらどちらが勝つのかな。もちろんチェス側は捕獲駒の再使用は無しですが、将棋は獲ったチェス駒を貼るのはアリでポーンだけは歩の動きでクイーンではなく金に成るというルールでいい勝負のようが気が。
盛栄さんには学生時代から一度も勝てずじまい(まだしばらく現役ですから一度くらい・・・)でしたが、毎日で書いていますか。入社時は囲碁関係にはあまり関りたくないと云っていたようですが、やはり好きな題材で書くのが一番ですから。
チェスと将棋のサイマルテニアスはあまり意義があるとは思えませんが、話題作りにはいいのでしょうね。ちなみに将棋盤で将棋とチェスの一組の駒で戦ったらどちらが勝つのかな。もちろんチェス側は捕獲駒の再使用は無しですが、将棋は獲ったチェス駒を貼るのはアリでポーンだけは歩の動きでクイーンではなく金に成るというルールでいい勝負のようが気が。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
盤上ゲーム図書資料館 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
盤上ゲーム図書資料館のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77278人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209399人
- 3位
- 福岡 ソフトバンクホークス
- 42914人