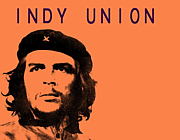インディユニオンの情報管理担当者 フリーライターの松沢です。
昨日、東京は日比谷公園内の「派遣村」を取材してきました。記者章がない取材ですので、活動は制限されましたが、個人の目から見て、この問題が我々個人自営業者フリーランス・SOHO・委託労働者で構成するインディユニオンをはじめ、現在正社員として働いている方も含めた他人事ではない問題だと痛感しました。
以下、当方の文責でできるだけ個人の客観的な視点を保った上で取材を重ねたレポートを記載させていただきます。
本文と照らし合わせると、メディア報道では浮かんでこなかった問題も見えてくるかと思われます。
是非ご一読いただいて、皆様で問題提起をしていただければと思います。
1・5 13時に、東京・日比谷の派遣村を取材に回ってみた。
既にメディア報道されている現場をフリーランスのジャーナリストが取材するのは、非常に難しい。顔写真入りの記者章が無ければ、奥まで突っ込んだ取材を行うのが難しいことは分かっている。
おそらく、今から行っても掘り下げた取材は難しいだろう。
だが、どうしても気になる点がある。この問題をTVなどのメディアを通して見つめた場合、腑に落ちない点が多いのだ。
いわゆるホームレス風の人がメディアのインタビューに応えて、「派遣村のおかげで助かった」というような発言をしているシーンに、不自然さを感じてしまうのだ。
大変失礼だが、職と住居を失って相応の時間が過ぎた方が、一体どうやって日比谷公園にたどりついたのだろうか?
派遣村で年を過ごした人は、東京近郊で仕事をしていた方ばかりではあるまい。
数日前の派遣村の報道を知って、何とか日比谷公園にたどりついたという人がいたというニュースを読んだ。
そういう方が助かるなら、それは非常に有意義なことだと思う。
しかしながら、メディアで署名原稿を書いている身としては、意図せずとも、メディアが事実から解離させた形で報道しているように思えてならなかった。
メディア報道は、「事実の一部」を切り取る形で作られる。
特に映像での報道は、事実の一部を切り取る報道関係者の有意識・無意識の意図が必ず介在する。
そこを読み取れなければ、事実やこの問題の根源は見えてこない。
現場を見れば、何か見えてくるかもしれない。時間的に難しいかもしれないが、午後からの取材をキャンセルして、日比谷に向かうことにした。
12:45分に営団地下鉄の日比谷駅に降りた。
案内図にある日比谷公園の位置をたどりながら地上に出る。
ちょうど、霞ヶ関と道路を隔てた反対側にある派遣村には、公園を横切る形で移動しなければならない。
幸いにも、公園の入り口に派遣村の地図が啓示されていたので、その地図を頼りに移動する。
公園は、仕事始めのサラリーマンの方がくつろいだり、(おそらく)霞ヶ関の官庁街から移動してきたと思われる公務員らしき人もいて、非常に穏やかな雰囲気だった。
派遣村のテントらしきものがあった場所にたどりついたのが、ちょうど13時
既に閉村式が行われていて、ボランティアの若い方(腕章代わりに、ボランティアと書かれたバンダナを腕に巻いていたのですぐにわかった)や、労組の関係者らしき方が後片付けに奔走していた。
その間を、昼休みのサラリーマンや道路を隔てた霞ヶ関の公務員が通り過ぎていく。
仕事はじめの日ということもあって、正月独特の雰囲気が残っている。一月の陽射しにしては穏やかで、日向にいると気分がほころぶ。
その中で、荷物の後片付けや、道路の清掃がてきぱきと行われていく。
その姿だけを見ていると、まるで有志の方が公園の清掃を行っているような錯覚を覚えそうになる。少なくともテレビ報道などで見た現場のような空気は存在しない。
メディア報道で、ちょうど派遣村から道路を隔てた厚生労働省の講堂に年越しの居を求めた方たちが移動したと聞いていたので、そちらに回ってみた。
だが、警備員と公安関係者らしい私服警察官が壁を作っている。
とても、記者パスなしでは取材できそうにないので、日比谷公園の派遣村後に戻って、一般市民を装った形で取材を続ける。
(上の写真は、その際に撮影した一枚である)
レンタカー会社のトラックがあることを見ると、資金ないし物資を提供した方がいるのだろう。
ボランティアの方含め、幕の内弁当が支給されていたのも、どこから支給されているのか、とりあえず尋ねるのは避けた。(客観的に俯瞰して、集まっている人たちがどういう人たちかを確認したかったためである)
いわゆる労組系の方もいるが、どうみても大学生のボランティアらしき人が、かなりの数確認できた。
文字通り、ボランタリー(自発的な)意思で集まった方のようで、清掃や片付けをしながら、役割分担でもめていたりする光景も見えた。
(表情に疲れが映っていたから、相当な時間、奉仕活動に携わっていたのではないか?)
そのうち、事前告知されていたデモが、公園の外周に沿って列を作って遠くに歩いているのを見つけて追いかけた。
そこで気付いたのは、「派遣村」と呼ばれているのは、必ずしも正確な表現ではないということである。
派遣意外の労働環境に従事していて、住居の確保が困難な方も含めた救済活動を展開しているらしいということだった。
メディア報道で見た映像は、年末に派遣の仕事を失ってしまった方たちではなく、以前から正当な労働報酬を得られなくて、住居の問題で困窮していた方だったのではないか?
そういう方たちを選んでTV報道関係者が撮影を行っていたとしたら、意図の介在の有無はさておいて、事実とは離れたイメージを誘導する報道を行っていたということになる。
だが、一方的にメディア関係者を責めることもできないように思う。
実際、事前の知識を得ずに取材に向かうと、一体誰が派遣村で年越しの居を得ている人なのか、さっぱりわからない。
たまたま隣に座って話しかけてきたボランティアの大学生かと思っていた若い人が、派遣村で年越しの居を得たということを聞いて驚いた。
「本当は2月末までの契約の予定だったんです。それが年末になって、契約がいきなり破棄されて、寮を追い出される形になって、数人でここに来ました」
身分を明かして、詳しくインタビューすると、若い男性が応じてくれた。不思議に悲壮感が感じられない。その理由を尋ねてみた。
「悲しいとか悔しいとか言ってる前に、仕事がほしいんですよ。契約を守らない形でいきなり解雇されたのは、今回が初めてじゃないんです。」
彼の意見をもって、派遣村で過ごした人たちの全ての意見とするわけにはいかない。
ただ、私が見た限りでは、事前通告なしの契約解除ということに慣れているものの、これからどうしていいか表情にも出せないほど、途方に暮れているように思えた。
弁当を食べ終わると、張っていた気がほどけたらしく、彼は箸を置いて空の弁当箱に視線を落とした。
「両親が名古屋にいるんですけど、正月は帰れなかったんですよ。
電話かけたら両親は正月くらい帰ってこいって言ってくれるんですけど、交通費も満足にない中で、帰るわけにいかないじゃないですか。
あっちに帰っても仕事が見つかるとも限らないし、このまま実家に帰ったら、年金で暮らしている両親の負担になるだけなのは、眼に見えてるんです。」
なるほど、もっともである。
困っている時ほど、自分でなんとかしようとして、より苦しい立場に立たされてしまう人をよく見る。彼もそのような状態にあるらしい。
私はフリーランスという、いつ仕事が無くなってもおかしくない中で、15年ほど働いている。
そのため、いわゆる「派遣切り」と呼ばれる問題について、世間よりは冷徹なまなざしで見つめていたように思う。
(いわゆる会社を経営している方や、個人自営業者の方も同様だろう。事業に失敗すれば、無限責任を背負うこともあるからだ。)
だが、彼の話を引き出してみると、必ずしも自己責任とは言えないケースが存在するのは否定できないように思う。
少なくともインタビューに応じてくれた彼は、自分の生活設計にだらしがなかったのではなく、予期せぬ事態に遭遇することを重ねる中で、こういった選択肢の仕事を選ばざるを得なかったように思えた。
また、選択肢がどんどん無くなっていく中で、社会人としての責任を彼なりに全うしようとしていたように思う。
一人の年長者として、「これからどうしたらいいか?」という、アドバイスを求められて困ったが、仕事が見つかってからでもいいから、両親には今の状態をありのままに話した方がいいと告げた。
やはり、親は親である。
いくら自分が経済的に困窮していても、わが子が離れた場所で苦しんでいるということを知らないままだったら、そのことを知った時、いたたまれなくなるだろう。
丁寧な礼で見送ってくれた彼と別れて、再び厚労省へ向かう。やはり壁が厚くて中は取材できそうにない。
デモを取材しているライターに電話を入れてみたら、どうやら厚労省の講堂に人が入るのを制限されたらしく、ほとんどの人が警視庁に程近い社会民主党の本部のホールにいるという。
事前のアポを取らずに取材できるか確認してみたら、特にセキュリティもないということだった。意を決して、制服・私服警官が道に配置されている中をくぐる形で社民党本部に向かう。
基本的にノンポリなので、政治団体の本部を見学するというのは初めてである。
また、社民党を支持してはいないので(私は自衛隊擁護派のため)非常に貴重な機会だと思い、本部内のホールへ向かう。
たどりついてみると、玄関先は全くセキュリティが存在しない。いささか不安になりつつ、ホールを目指し、携帯電話で連絡を取り合う。
ちょうど映画館かコンサートホールのような肘掛のある赤い椅子が並ぶホールに着くと、200名前後の人が集まっていた。
こちらは、若い人が圧倒的に多い。やはり、TVで見た報道とはずいぶん違った印象を受ける。
中には60代以上と思われる方もいたが、大体が20代から40代前後の方たちばかりだった。一旦入り口から出て、ホールの外側をぐるりと一周してみたが、やはり状況は同じだった。
産経やテレビ朝日といった左右取材陣の間を縫って、再びホールの中に入る。
合流したライターの友人に尋ねると、やはり詳しい情報が取れていないという。ここでも日比谷公園で見た幕の内弁当と同じものを見かけた。
社民党本部のホールは、事前に用意されていたのか? 弁当もそうなのか? という疑問が湧いたが、それは正確な情報を得ることができなかった。
私は、ホールの最前列に近い位置に陣取った。そのうち、活動の代表の方が現れて、デモ開始以降の経緯について説明を始めた。
説明をはじめるに当たって、代表の方が、ホール内の報道陣の退室を求めた。
(このことから察するに、活動の意図するところではない形でイメージを作られたり、恣意的な報道を避けたいという意図があったのではないだろうか。
もし、そうだとしたら、以前のテレビ報道で見た映像は、マスコミ側が事実の一部を切り取った、意見を誘導しかねない映像だということになる)
説明によると、厚労省への陳情デモは、当初200人前後が入れるということだったが、70人以下にしてほしいという話になり、やむをえず他の方を入れてもらうため、社民党のホールを借りるような経緯に至ったことが説明された。
この説明から、政治団体の協力が事前に用意されていたものではないかと考えたが、必ずしもそうではないような心象を受けた。
若いボランティアの方が、他の用事を理由に退席を求める声をあげるシーンもあった。
また、多くのボランティアの方が、献身的に様々な分担された役割をこなしていた。
疲れが見えるその表情から察するに、政治的な意図は感じられない。日比谷公園で会ったボランティアの方たちと同じだろう。
そのうち、前列の男性が眺めているプリントが眼に入った。
雇用を求める方が今日以降入居する住宅は、ハローワークを通じて入居できることが説明してあった。
どうやら、ボランティアの方や活動団体が主体になって行政を動かした中で、野党側の政治団体が超党派の形で賛同したように見えた。(このあたりは裏が取れていないが、そう見ていいように思える)
また、今日以降、雇用を求めて公営の住宅に入ることを希望される方は、生活保護を受け、その費用から家賃を支払う形で入居することが説明されていた。
ただ、それらの住宅は東京からかなり離れた千葉や神奈川の住宅で、入居を検討している方からは、生活が様変わりしてしまうのは避けられないが、現状を打破するには仕方がないといった声が聞かれた。
この時点で、進展も無くなったことと、記者パスもないことから、これ以上の詳細な取材が難しいと判断し、友人のライターと社民党本部から抜け出る形で取材を終了した。
個人的な視点では、職と住を失ってしまう人たちを等しくサポートしたいという、ボランタリズムの色合いが濃い活動のように見えた。
ところで、「派遣切り」と言われたこの一連の問題だが、一つ疑問に思うことがある。
我が国が劣悪な経済状態に陥り、雇用はおろか住を失う問題に直面しているのは、終身雇用制のシステムを破壊し、金融恐慌を起こしたアメリカ政府の失策ではないのか?
ふだんは、右派左派問わず、反米の意見が聞かれるはずなのに、ことこの問題に限っては、アメリカ政府を非難する意見が聞こえてこないのはなぜだろう?
ブッシュを弾劾訴追するのは当然だが、オバマが新大統領に正式に就任した後、アメリカ発の金融問題の責任を、世界に対してどのように取るのか?
日本人である以上、日本の国益を考えるのは当然だが、同盟国である日本に対してこれだけの損害をもたらした責任については、どのような具体的な措置を行うつもりなのか?
答えは「何もしない」というはずである。
生活の環境を脅かされ、挙句の果ては銃とドルで攻撃を受けていることに、なぜこの国の人たちが気付かないのか、私は不思議でならない。
昨日、東京は日比谷公園内の「派遣村」を取材してきました。記者章がない取材ですので、活動は制限されましたが、個人の目から見て、この問題が我々個人自営業者フリーランス・SOHO・委託労働者で構成するインディユニオンをはじめ、現在正社員として働いている方も含めた他人事ではない問題だと痛感しました。
以下、当方の文責でできるだけ個人の客観的な視点を保った上で取材を重ねたレポートを記載させていただきます。
本文と照らし合わせると、メディア報道では浮かんでこなかった問題も見えてくるかと思われます。
是非ご一読いただいて、皆様で問題提起をしていただければと思います。
1・5 13時に、東京・日比谷の派遣村を取材に回ってみた。
既にメディア報道されている現場をフリーランスのジャーナリストが取材するのは、非常に難しい。顔写真入りの記者章が無ければ、奥まで突っ込んだ取材を行うのが難しいことは分かっている。
おそらく、今から行っても掘り下げた取材は難しいだろう。
だが、どうしても気になる点がある。この問題をTVなどのメディアを通して見つめた場合、腑に落ちない点が多いのだ。
いわゆるホームレス風の人がメディアのインタビューに応えて、「派遣村のおかげで助かった」というような発言をしているシーンに、不自然さを感じてしまうのだ。
大変失礼だが、職と住居を失って相応の時間が過ぎた方が、一体どうやって日比谷公園にたどりついたのだろうか?
派遣村で年を過ごした人は、東京近郊で仕事をしていた方ばかりではあるまい。
数日前の派遣村の報道を知って、何とか日比谷公園にたどりついたという人がいたというニュースを読んだ。
そういう方が助かるなら、それは非常に有意義なことだと思う。
しかしながら、メディアで署名原稿を書いている身としては、意図せずとも、メディアが事実から解離させた形で報道しているように思えてならなかった。
メディア報道は、「事実の一部」を切り取る形で作られる。
特に映像での報道は、事実の一部を切り取る報道関係者の有意識・無意識の意図が必ず介在する。
そこを読み取れなければ、事実やこの問題の根源は見えてこない。
現場を見れば、何か見えてくるかもしれない。時間的に難しいかもしれないが、午後からの取材をキャンセルして、日比谷に向かうことにした。
12:45分に営団地下鉄の日比谷駅に降りた。
案内図にある日比谷公園の位置をたどりながら地上に出る。
ちょうど、霞ヶ関と道路を隔てた反対側にある派遣村には、公園を横切る形で移動しなければならない。
幸いにも、公園の入り口に派遣村の地図が啓示されていたので、その地図を頼りに移動する。
公園は、仕事始めのサラリーマンの方がくつろいだり、(おそらく)霞ヶ関の官庁街から移動してきたと思われる公務員らしき人もいて、非常に穏やかな雰囲気だった。
派遣村のテントらしきものがあった場所にたどりついたのが、ちょうど13時
既に閉村式が行われていて、ボランティアの若い方(腕章代わりに、ボランティアと書かれたバンダナを腕に巻いていたのですぐにわかった)や、労組の関係者らしき方が後片付けに奔走していた。
その間を、昼休みのサラリーマンや道路を隔てた霞ヶ関の公務員が通り過ぎていく。
仕事はじめの日ということもあって、正月独特の雰囲気が残っている。一月の陽射しにしては穏やかで、日向にいると気分がほころぶ。
その中で、荷物の後片付けや、道路の清掃がてきぱきと行われていく。
その姿だけを見ていると、まるで有志の方が公園の清掃を行っているような錯覚を覚えそうになる。少なくともテレビ報道などで見た現場のような空気は存在しない。
メディア報道で、ちょうど派遣村から道路を隔てた厚生労働省の講堂に年越しの居を求めた方たちが移動したと聞いていたので、そちらに回ってみた。
だが、警備員と公安関係者らしい私服警察官が壁を作っている。
とても、記者パスなしでは取材できそうにないので、日比谷公園の派遣村後に戻って、一般市民を装った形で取材を続ける。
(上の写真は、その際に撮影した一枚である)
レンタカー会社のトラックがあることを見ると、資金ないし物資を提供した方がいるのだろう。
ボランティアの方含め、幕の内弁当が支給されていたのも、どこから支給されているのか、とりあえず尋ねるのは避けた。(客観的に俯瞰して、集まっている人たちがどういう人たちかを確認したかったためである)
いわゆる労組系の方もいるが、どうみても大学生のボランティアらしき人が、かなりの数確認できた。
文字通り、ボランタリー(自発的な)意思で集まった方のようで、清掃や片付けをしながら、役割分担でもめていたりする光景も見えた。
(表情に疲れが映っていたから、相当な時間、奉仕活動に携わっていたのではないか?)
そのうち、事前告知されていたデモが、公園の外周に沿って列を作って遠くに歩いているのを見つけて追いかけた。
そこで気付いたのは、「派遣村」と呼ばれているのは、必ずしも正確な表現ではないということである。
派遣意外の労働環境に従事していて、住居の確保が困難な方も含めた救済活動を展開しているらしいということだった。
メディア報道で見た映像は、年末に派遣の仕事を失ってしまった方たちではなく、以前から正当な労働報酬を得られなくて、住居の問題で困窮していた方だったのではないか?
そういう方たちを選んでTV報道関係者が撮影を行っていたとしたら、意図の介在の有無はさておいて、事実とは離れたイメージを誘導する報道を行っていたということになる。
だが、一方的にメディア関係者を責めることもできないように思う。
実際、事前の知識を得ずに取材に向かうと、一体誰が派遣村で年越しの居を得ている人なのか、さっぱりわからない。
たまたま隣に座って話しかけてきたボランティアの大学生かと思っていた若い人が、派遣村で年越しの居を得たということを聞いて驚いた。
「本当は2月末までの契約の予定だったんです。それが年末になって、契約がいきなり破棄されて、寮を追い出される形になって、数人でここに来ました」
身分を明かして、詳しくインタビューすると、若い男性が応じてくれた。不思議に悲壮感が感じられない。その理由を尋ねてみた。
「悲しいとか悔しいとか言ってる前に、仕事がほしいんですよ。契約を守らない形でいきなり解雇されたのは、今回が初めてじゃないんです。」
彼の意見をもって、派遣村で過ごした人たちの全ての意見とするわけにはいかない。
ただ、私が見た限りでは、事前通告なしの契約解除ということに慣れているものの、これからどうしていいか表情にも出せないほど、途方に暮れているように思えた。
弁当を食べ終わると、張っていた気がほどけたらしく、彼は箸を置いて空の弁当箱に視線を落とした。
「両親が名古屋にいるんですけど、正月は帰れなかったんですよ。
電話かけたら両親は正月くらい帰ってこいって言ってくれるんですけど、交通費も満足にない中で、帰るわけにいかないじゃないですか。
あっちに帰っても仕事が見つかるとも限らないし、このまま実家に帰ったら、年金で暮らしている両親の負担になるだけなのは、眼に見えてるんです。」
なるほど、もっともである。
困っている時ほど、自分でなんとかしようとして、より苦しい立場に立たされてしまう人をよく見る。彼もそのような状態にあるらしい。
私はフリーランスという、いつ仕事が無くなってもおかしくない中で、15年ほど働いている。
そのため、いわゆる「派遣切り」と呼ばれる問題について、世間よりは冷徹なまなざしで見つめていたように思う。
(いわゆる会社を経営している方や、個人自営業者の方も同様だろう。事業に失敗すれば、無限責任を背負うこともあるからだ。)
だが、彼の話を引き出してみると、必ずしも自己責任とは言えないケースが存在するのは否定できないように思う。
少なくともインタビューに応じてくれた彼は、自分の生活設計にだらしがなかったのではなく、予期せぬ事態に遭遇することを重ねる中で、こういった選択肢の仕事を選ばざるを得なかったように思えた。
また、選択肢がどんどん無くなっていく中で、社会人としての責任を彼なりに全うしようとしていたように思う。
一人の年長者として、「これからどうしたらいいか?」という、アドバイスを求められて困ったが、仕事が見つかってからでもいいから、両親には今の状態をありのままに話した方がいいと告げた。
やはり、親は親である。
いくら自分が経済的に困窮していても、わが子が離れた場所で苦しんでいるということを知らないままだったら、そのことを知った時、いたたまれなくなるだろう。
丁寧な礼で見送ってくれた彼と別れて、再び厚労省へ向かう。やはり壁が厚くて中は取材できそうにない。
デモを取材しているライターに電話を入れてみたら、どうやら厚労省の講堂に人が入るのを制限されたらしく、ほとんどの人が警視庁に程近い社会民主党の本部のホールにいるという。
事前のアポを取らずに取材できるか確認してみたら、特にセキュリティもないということだった。意を決して、制服・私服警官が道に配置されている中をくぐる形で社民党本部に向かう。
基本的にノンポリなので、政治団体の本部を見学するというのは初めてである。
また、社民党を支持してはいないので(私は自衛隊擁護派のため)非常に貴重な機会だと思い、本部内のホールへ向かう。
たどりついてみると、玄関先は全くセキュリティが存在しない。いささか不安になりつつ、ホールを目指し、携帯電話で連絡を取り合う。
ちょうど映画館かコンサートホールのような肘掛のある赤い椅子が並ぶホールに着くと、200名前後の人が集まっていた。
こちらは、若い人が圧倒的に多い。やはり、TVで見た報道とはずいぶん違った印象を受ける。
中には60代以上と思われる方もいたが、大体が20代から40代前後の方たちばかりだった。一旦入り口から出て、ホールの外側をぐるりと一周してみたが、やはり状況は同じだった。
産経やテレビ朝日といった左右取材陣の間を縫って、再びホールの中に入る。
合流したライターの友人に尋ねると、やはり詳しい情報が取れていないという。ここでも日比谷公園で見た幕の内弁当と同じものを見かけた。
社民党本部のホールは、事前に用意されていたのか? 弁当もそうなのか? という疑問が湧いたが、それは正確な情報を得ることができなかった。
私は、ホールの最前列に近い位置に陣取った。そのうち、活動の代表の方が現れて、デモ開始以降の経緯について説明を始めた。
説明をはじめるに当たって、代表の方が、ホール内の報道陣の退室を求めた。
(このことから察するに、活動の意図するところではない形でイメージを作られたり、恣意的な報道を避けたいという意図があったのではないだろうか。
もし、そうだとしたら、以前のテレビ報道で見た映像は、マスコミ側が事実の一部を切り取った、意見を誘導しかねない映像だということになる)
説明によると、厚労省への陳情デモは、当初200人前後が入れるということだったが、70人以下にしてほしいという話になり、やむをえず他の方を入れてもらうため、社民党のホールを借りるような経緯に至ったことが説明された。
この説明から、政治団体の協力が事前に用意されていたものではないかと考えたが、必ずしもそうではないような心象を受けた。
若いボランティアの方が、他の用事を理由に退席を求める声をあげるシーンもあった。
また、多くのボランティアの方が、献身的に様々な分担された役割をこなしていた。
疲れが見えるその表情から察するに、政治的な意図は感じられない。日比谷公園で会ったボランティアの方たちと同じだろう。
そのうち、前列の男性が眺めているプリントが眼に入った。
雇用を求める方が今日以降入居する住宅は、ハローワークを通じて入居できることが説明してあった。
どうやら、ボランティアの方や活動団体が主体になって行政を動かした中で、野党側の政治団体が超党派の形で賛同したように見えた。(このあたりは裏が取れていないが、そう見ていいように思える)
また、今日以降、雇用を求めて公営の住宅に入ることを希望される方は、生活保護を受け、その費用から家賃を支払う形で入居することが説明されていた。
ただ、それらの住宅は東京からかなり離れた千葉や神奈川の住宅で、入居を検討している方からは、生活が様変わりしてしまうのは避けられないが、現状を打破するには仕方がないといった声が聞かれた。
この時点で、進展も無くなったことと、記者パスもないことから、これ以上の詳細な取材が難しいと判断し、友人のライターと社民党本部から抜け出る形で取材を終了した。
個人的な視点では、職と住を失ってしまう人たちを等しくサポートしたいという、ボランタリズムの色合いが濃い活動のように見えた。
ところで、「派遣切り」と言われたこの一連の問題だが、一つ疑問に思うことがある。
我が国が劣悪な経済状態に陥り、雇用はおろか住を失う問題に直面しているのは、終身雇用制のシステムを破壊し、金融恐慌を起こしたアメリカ政府の失策ではないのか?
ふだんは、右派左派問わず、反米の意見が聞かれるはずなのに、ことこの問題に限っては、アメリカ政府を非難する意見が聞こえてこないのはなぜだろう?
ブッシュを弾劾訴追するのは当然だが、オバマが新大統領に正式に就任した後、アメリカ発の金融問題の責任を、世界に対してどのように取るのか?
日本人である以上、日本の国益を考えるのは当然だが、同盟国である日本に対してこれだけの損害をもたらした責任については、どのような具体的な措置を行うつもりなのか?
答えは「何もしない」というはずである。
生活の環境を脅かされ、挙句の果ては銃とドルで攻撃を受けていることに、なぜこの国の人たちが気付かないのか、私は不思議でならない。
|
|
|
|
|
|
|
|
インディユニオン 公式コミュ 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-