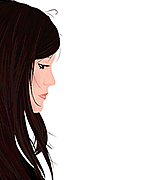イラク戦争から米軍が完全に撤退しました。
イラク戦争で問題になった物の一つにクラスター爆弾があります。
クラスター爆弾は、たくさんの小さな爆弾を入れた爆弾を目標の上空で爆発させて小さい爆弾をその周辺にばらまき、その爆弾たちが地表に到達すると一斉に爆発するように設計されている兵器です。
つまり、ばら撒かれた小さい爆弾のどれかが目標に当たればよいというものですので、目標の近くの一般市民が巻添えになりますし、目標に命中しなかった小さな爆弾は不発弾として、戦争終了後にも市民を脅かしつづけます。
無差別な攻撃という意味ではテロと変わらないと僕は思います。
クラスター爆弾の説明を上でしましたが似ている兵器が昔からありますよね。
地雷です。
地雷は世界で今1億個以上が地面に残っていると言われています。
1年間で撤去できる地雷の数は10万個。
1年間に新しく埋められる地雷の数は約6万個。
このままのペースでいくと全て撤去するのに1000年以上はかかると言われています。
どれだけ撤去しても今現在も内戦が続く地域などでは埋められ続けているのが
現状です。
その被害は年に3万人。20分に一人が地雷の被害にあっている計算です。
そのうちの1割が戦争中の軍人。9割が農作業や買い物帰りなどの民間人です。
その9割のうちの4割が本当に何の罪もない子供たちです。
地雷の一番憎むべき所は殺傷能力がそれほど強くない事です。
これだけ聞いたら死ぬ事はないんや、と思われるかも知れないですが
ひどいところでは1メートル四方に10個の地雷が埋まっている事もあるのです。
つまり脚を失ったり視力を失った人達が再び同じ被害に合う可能性が残されているのです。
地雷の開発された目的はけが人を増やして敵の軍の医療施設を地雷のけが人でいっぱいにして敵の戦意を無くすことにありました。皆さんもひどい怪我をした人達を見ると自分はそうはなりたくないって思いますよね?
その心理を利用するために、外見はひどい怪我になるように爆薬を調整してあるのです。
そんな地雷ですが国際機関は何もしていないのかと思われるかも知れませんが
しっかり動いています。
1997年に地雷の製造、使用の中止、撤廃、廃棄等の条文をもりこんだ
オタワ条約というのが発行されました。
しかし、このオタワ条約は2010年1月時点でアメリカ、ロシア、中国といった軍事大国や、対人地雷を実際に使用してきたスリランカ、韓国、イスラエル、インド、パキスタンといった国は加盟していません。
これらの国々が一日も早く条約に加盟しない事には地雷問題の解決は訪れません。
日本の自衛隊はオタワ条約に加盟するまでは100万個の地雷を保有していました。
しかし加盟してから順に廃棄を進めていき2003年に全ての対人地雷を廃棄しました。
国際的に地雷撤去を行っている機関等に対する国別の援助では日本が世界の5割を占めています。
そんな地雷ですが日本には個人でも撤去の為の活動をなさっている方がおられます。
雨宮清さんです。
何度かメディアにも紹介されているのでご存知の方も多いと思います。
1947年山梨県生まれで、1970年4月、23歳で故郷の山梨市に車両工業所を設立します。
幼い頃から憧れていた海外でのビジネスを求めてカンボジアへ旅行した雨宮さんは対人地雷被害者との出会いに強い衝撃を受け、対人地雷除去機を作ることを決意します。
『悪魔の兵器』と呼ばれる地雷を実際にカンボジアに行くまではそれほど知らなかった雨宮さん。安価なその兵器は、人々の手足を奪い、生かさず殺さず傷つけることによって長期に渡る苦しみを与えることを目的として開発されました。
身体の自由を奪い、仕事を奪い、経済的な負担を負わせ、被害者が子どもの場合には成長ごとに行われる骨を削りとる手術の痛みが待っているのです。
さらに、被害にあった当事者だけでなく、それを支える家族や、しいては国全体を疲弊させ、復興への意欲を削ぐという人類史上稀に見る卑劣な兵器です。
その地雷が世界で一番多く埋まっているのはどこか?
カンボジアもしくはアンゴラです。
ベトナムも介入した激しい内戦によって国内で、ポル・ポト政権により行われた200万人ともいわれる途方もない規模の大虐殺が行われたカンボジア。
それ以降も戦火が絶えず、20年に渡る泥沼の内戦が続きました。
1990年にようやく戦争が終わった思われた後にも、対人地雷のほか、不発弾や対戦車地雷などが数限りなく放置されています。
雨宮さんがはじめて『地雷』の恐ろしさを目の当たりにしたのも、そのカンボジアを訪れた時のことです。内戦が終わった直後の1994年、まだ内戦の傷跡も癒えない頃の事です。
『当時は東南アジアに建設機械の輸出を行ったりしていましたから、戦後復興を目指すカンボジアに中古の建設機械の販売のチャンスがないかと思ったんですよ。カンボジアの首都プノンペンは、当時はまだ瓦礫の山がうず高く積まれ、戦後の傷跡は否めませんでしたが、市場には活気があり、ようやく訪れた平和を謳歌しているように見えました』
しかし、そこで雨宮さんは、いまだに続く戦争の爪痕を突きつけられました。
市場の周りには凄まじい数の避難民が集まっており、その中で物乞いをするまだ幼い少女に目をとめると、脇にはその母親であろう、顔に酷い火傷を負い、膝から下を失った年老いた女性がうずくまっていました。
『現地の案内人に尋ねてはじめて、それが対人地雷によるものだと知りました。そして戦争が終わった後もその数はどんどん増えているというんです。その女性に1ドル札を渡すと『ありがとう、ありがとう』と涙を流すんですよ。でも、見渡せば、ほかにも足や手のない人がいる。すべての人を救えるわけでなく、無力感にさいなまれてその場を去りました』
カンボジアからの帰路、飛行機の中で雨宮さんは、若い頃に死別した母親の言葉をかみしめていたそうです。
『陰日向のない人間になりなさい。人のためになるような人間になりなさい。』
日本に戻った雨宮さんは国内外の対人地雷専門家や日本政府、関係機関などを訪ね、あらゆる場所に赴き、対人地雷についての勉強を始めました。
そして、数ヵ月後、社内に対人地雷除去機の開発プロジェクトを設置しました。当時の社員はわずかに60名です。あまりに大きな夢と、それに比例した経営リスクに、社員の中からは不安視する声もあったそうです。全て自分で責任を取ると雨宮さんが言った時、ある社員が
『雨宮さん、そんな良い仕事を独り占めはずるいですよ。僕らにも責任ある仕事をさせて下さい』
と言われ涙したそうです。
『まだ誰も取り組んでいないこと、技術屋として何かできないか。それも世界の人々に感謝されるすばらしい仕事だと力説したんです。今となっては、よくもまぁ、任せてくれたものだと思いますよ。でも、社員とその家族は、私の思いに共感し、協力を誓ってくれたんです』
それでも、通常業務と平行して扱うにはこの仕事は負担が大きすぎました。
そこで、雨宮さんをはじめとする6人の担当者が、営業時間外の早朝や深夜、休日を使ってコツコツと開発に取り組みました。
『何しろ、まったく何も資料がないわけですから、開発は手探りでした。世界トップレベルという自負があった油圧ショベルの技術を、応用することまではすぐに思いついたのですが、その後は失敗ばかり』
たとえば、カンボジアは生い茂る木や草の下に対人地雷が隠れています。
ショベルの先にカッターをつけて刈り込んだ上で、対人地雷を爆発させて除去しなければならないのです。
はじめは他社から部品を購入したりしていたものの満足できず、ついには小さなねじに至るまで自社開発で取り組みました
また、爆発の際の温度は800度〜1000度にもなるのですが、その衝撃に耐えるのはもちろん、岩に対する耐性、切削性など、クリアしなければならない基準は山のようにありました。
『正直、そのころにはビジネスという言葉は忘れていましたね。かなりの開発費用もかかっていましたし、とにかく早く完成させて、早くカンボジアに持っていきたい。早くカンボジアの人々を危険から解放したい。でも一方で、いや、これは仕事なんだと、だからこそ、ちゃんと費用対効果が得られて、メンテナンスがしやすくて、使いやすい機械でなくてはと何度も自分にいい聞かせていました』
そして試作を繰り返した結果、一号機の「ロータリーカッタ式対人地雷除去機」が完成します。プロジェクトの開始から実に3 年以上もの月日が経っていました。
ところが、完成の喜びも束の間。開発した対人地雷除去機が、日本政府による武器輸出規制の原則「武器輸出三原則」に觝触するという指摘がなされてしまいます。
しかし、雨宮さんはあきらめることなく何度も何度も足を運びついに日本政府の許可を得る事が出来ました。
社員数60名の小さな企業が、どんな大企業もなし得なかった対人地雷除去機の開発という難事業を実現し、国内外から多くの賞賛が寄せられます。しかし、それは決して無償の奉仕活動でなかったからこそ実現し得たと雨宮さんはいう。
『私たちの対人地雷除去作業は、あくまでビジネスなのです。ボランティアやチャリティを決して否定するわけではないのですが、無償だったらここまでのクオリティを提供できていたかわかりません。お金をもらえるかどうかということではなく、どこまでお互いが対等に魂をぶつけ合えるかということが重要なのです』
確かに、『施し』だとしたら施される側は引け目に感じて遠慮がちになるかもしれません。提供する側もどこまで真剣にニーズに対応しようとするかは分かりません。
ビジネスだからこそ対等になれるし、要望や意見を戦わせることができるのだと振り返って雨宮さんは言います。
たとえば、熱帯に位置するカンボジアの土地は草木が茂り、雨期には足下がぬかるみ、そうした場所では、草木を刈り込みながら対人地雷除去作業をしなければいけません。
一方、乾燥地帯のアフガニスタンでは、乾いた砂の下は固い岩盤地層になっており、板状の歯では、すぐに欠けてしまって使い物にならなくなってしまいます。
通常は、提供された機械をその土地、土地に合わせて、使う側が工夫しながら使うしかありません。そのため、カンボジアでは対人地雷除去前に灌木を刈り込む際の爆発事故が絶えず、アフガニスタンでは故障した機械が放置されたままになっていたようです。
一方、雨宮さんはあくまで日本で顧客のニーズに応える時と同じように、真摯に1つひとつの要望に応えていきました。
『大量生産する自動車などとは違って、交換用の部品が高額になり、輸送コストや修理費の負担も無視できない。ですから、できるだけ交換用の部品は共有できるように工夫し、日本から送るにしてもできるだけコストがかからないようにしたわけです。』
さらには、現地でメンテナンスや修理ができるよう、そのノウハウもセットで提供しています。提供したからには、「費用対効果」を実感してほしいと雨宮さんは語ります。
いわば自分たちがやっている事業は、技術を仲立ちとしたビジネス・ソリューションだといいます。人道支援は、一過性のものではならない。継続して、その地域が自立できるよう手を貸すことが重要だと考えておられます。
『よく人道支援の方法として『人・物・金』といういい方をするけれど、物も金も使えば消えるもの。そんなものをばらまいても、一時的な気休めにしかならないでしょう。自立を促すには『人』を育てることが一番大切です。だから、我々は現地に自ら赴き、現地の人々に機械の使い方を教え、修理の仕方まで教えるんです。そうすれば、対人地雷除去機を操作する人、メンテナンスを行う人は仕事を得て、自立できるわけです』
現地での指導に限界を感じはじめた雨宮さんは、対人地雷埋設国の若者たちを日本に招き、山梨で対人地雷除去機の訓練を施す取り組みも2006年からスタートさせました。
まず来日したのは、世界でも最悪のレベルの対人地雷埋設国といわれるアンゴラから、政府によって派遣されてきた研修生の若者たちです。
アンゴラの人々は、2002年に終結するまで40年にも渡る長い間、内戦によって傷つけられてきました。
いまだ約1,500万個もの対人地雷が埋まり、その数はカンボジアと並び世界最多といわれています。来日した研修生のほとんどが、肉親や友人など身近な人を対人地雷によって傷つけられた経験を持っており、対人地雷の恐ろしさを肌身で知っていました。
だからこそ、1人ひとりが、国として自立していくために対人地雷の除去が不可欠であることを強く意識し、強い使命感に燃えていたといいます。
『大型機械を操縦したことがないという若者ばかりで、はじめはかなり戸惑っていました。しかし、彼らのまなざしときたら、なんとも真剣で。その気持ちに応えるつもりで、こちらも必死になって取り組みましたよ。しかし、もっとも苦慮したのは、現場に出たいと願う若者たちのはやる気持ちを抑えることでした。』
一刻も早く自国の対人地雷を1つでも多く除去したい。そう願うのは自然なことです。しかし、雨宮さんは黙々と基礎的な操作を行わせ、確実に技術が身につくまで徹底させました。
そして、ようやく2007年の夏、アンゴラに2台の対人地雷除去機が導入され、稼働が始まった時、雨宮さんはアンゴラの若者たちの横顔に誇りと使命感を見て、胸が熱くなったといいます。
『対人地雷埋設国の人々は、私たちに『支援してくれてありがとう』というけれど、たとえばアンゴラの若者たちの真剣さを見ていると、自分たちは支援させていただいているという気持ちになってくる。受ける側も提供する側も心が通っているからこそ、そこに何かが生まれる。日々の仕事の中で、『させていただいている』という敬虔な気持ちになることの重要性を学んだように思いますね』
今後はさらに長期的なプロジェクトを立ち上げ、雨宮さんの生涯をかけて取り組んでいくつもりだと仰っています。
『技術屋っていうのは、ものづくりの挑戦者だと思ってきました。しかし今、それに加えて、技術の根源は物づくりだけではなくて、人づくりにもあることを理解しつつあります。たとえ1人になってもやり遂げなくては、と気負っていた時期もありますが、気がつけば、家族や社員、地域の人々、政府やNPO関係者、そして地雷埋設国の人々、あらゆる人に支えられている。そして、真剣になれば必ず受け止めてくれる人がいて、思いが広がっていく。それが人を育くむということなんだと実感しています』
イラク戦争で問題になった物の一つにクラスター爆弾があります。
クラスター爆弾は、たくさんの小さな爆弾を入れた爆弾を目標の上空で爆発させて小さい爆弾をその周辺にばらまき、その爆弾たちが地表に到達すると一斉に爆発するように設計されている兵器です。
つまり、ばら撒かれた小さい爆弾のどれかが目標に当たればよいというものですので、目標の近くの一般市民が巻添えになりますし、目標に命中しなかった小さな爆弾は不発弾として、戦争終了後にも市民を脅かしつづけます。
無差別な攻撃という意味ではテロと変わらないと僕は思います。
クラスター爆弾の説明を上でしましたが似ている兵器が昔からありますよね。
地雷です。
地雷は世界で今1億個以上が地面に残っていると言われています。
1年間で撤去できる地雷の数は10万個。
1年間に新しく埋められる地雷の数は約6万個。
このままのペースでいくと全て撤去するのに1000年以上はかかると言われています。
どれだけ撤去しても今現在も内戦が続く地域などでは埋められ続けているのが
現状です。
その被害は年に3万人。20分に一人が地雷の被害にあっている計算です。
そのうちの1割が戦争中の軍人。9割が農作業や買い物帰りなどの民間人です。
その9割のうちの4割が本当に何の罪もない子供たちです。
地雷の一番憎むべき所は殺傷能力がそれほど強くない事です。
これだけ聞いたら死ぬ事はないんや、と思われるかも知れないですが
ひどいところでは1メートル四方に10個の地雷が埋まっている事もあるのです。
つまり脚を失ったり視力を失った人達が再び同じ被害に合う可能性が残されているのです。
地雷の開発された目的はけが人を増やして敵の軍の医療施設を地雷のけが人でいっぱいにして敵の戦意を無くすことにありました。皆さんもひどい怪我をした人達を見ると自分はそうはなりたくないって思いますよね?
その心理を利用するために、外見はひどい怪我になるように爆薬を調整してあるのです。
そんな地雷ですが国際機関は何もしていないのかと思われるかも知れませんが
しっかり動いています。
1997年に地雷の製造、使用の中止、撤廃、廃棄等の条文をもりこんだ
オタワ条約というのが発行されました。
しかし、このオタワ条約は2010年1月時点でアメリカ、ロシア、中国といった軍事大国や、対人地雷を実際に使用してきたスリランカ、韓国、イスラエル、インド、パキスタンといった国は加盟していません。
これらの国々が一日も早く条約に加盟しない事には地雷問題の解決は訪れません。
日本の自衛隊はオタワ条約に加盟するまでは100万個の地雷を保有していました。
しかし加盟してから順に廃棄を進めていき2003年に全ての対人地雷を廃棄しました。
国際的に地雷撤去を行っている機関等に対する国別の援助では日本が世界の5割を占めています。
そんな地雷ですが日本には個人でも撤去の為の活動をなさっている方がおられます。
雨宮清さんです。
何度かメディアにも紹介されているのでご存知の方も多いと思います。
1947年山梨県生まれで、1970年4月、23歳で故郷の山梨市に車両工業所を設立します。
幼い頃から憧れていた海外でのビジネスを求めてカンボジアへ旅行した雨宮さんは対人地雷被害者との出会いに強い衝撃を受け、対人地雷除去機を作ることを決意します。
『悪魔の兵器』と呼ばれる地雷を実際にカンボジアに行くまではそれほど知らなかった雨宮さん。安価なその兵器は、人々の手足を奪い、生かさず殺さず傷つけることによって長期に渡る苦しみを与えることを目的として開発されました。
身体の自由を奪い、仕事を奪い、経済的な負担を負わせ、被害者が子どもの場合には成長ごとに行われる骨を削りとる手術の痛みが待っているのです。
さらに、被害にあった当事者だけでなく、それを支える家族や、しいては国全体を疲弊させ、復興への意欲を削ぐという人類史上稀に見る卑劣な兵器です。
その地雷が世界で一番多く埋まっているのはどこか?
カンボジアもしくはアンゴラです。
ベトナムも介入した激しい内戦によって国内で、ポル・ポト政権により行われた200万人ともいわれる途方もない規模の大虐殺が行われたカンボジア。
それ以降も戦火が絶えず、20年に渡る泥沼の内戦が続きました。
1990年にようやく戦争が終わった思われた後にも、対人地雷のほか、不発弾や対戦車地雷などが数限りなく放置されています。
雨宮さんがはじめて『地雷』の恐ろしさを目の当たりにしたのも、そのカンボジアを訪れた時のことです。内戦が終わった直後の1994年、まだ内戦の傷跡も癒えない頃の事です。
『当時は東南アジアに建設機械の輸出を行ったりしていましたから、戦後復興を目指すカンボジアに中古の建設機械の販売のチャンスがないかと思ったんですよ。カンボジアの首都プノンペンは、当時はまだ瓦礫の山がうず高く積まれ、戦後の傷跡は否めませんでしたが、市場には活気があり、ようやく訪れた平和を謳歌しているように見えました』
しかし、そこで雨宮さんは、いまだに続く戦争の爪痕を突きつけられました。
市場の周りには凄まじい数の避難民が集まっており、その中で物乞いをするまだ幼い少女に目をとめると、脇にはその母親であろう、顔に酷い火傷を負い、膝から下を失った年老いた女性がうずくまっていました。
『現地の案内人に尋ねてはじめて、それが対人地雷によるものだと知りました。そして戦争が終わった後もその数はどんどん増えているというんです。その女性に1ドル札を渡すと『ありがとう、ありがとう』と涙を流すんですよ。でも、見渡せば、ほかにも足や手のない人がいる。すべての人を救えるわけでなく、無力感にさいなまれてその場を去りました』
カンボジアからの帰路、飛行機の中で雨宮さんは、若い頃に死別した母親の言葉をかみしめていたそうです。
『陰日向のない人間になりなさい。人のためになるような人間になりなさい。』
日本に戻った雨宮さんは国内外の対人地雷専門家や日本政府、関係機関などを訪ね、あらゆる場所に赴き、対人地雷についての勉強を始めました。
そして、数ヵ月後、社内に対人地雷除去機の開発プロジェクトを設置しました。当時の社員はわずかに60名です。あまりに大きな夢と、それに比例した経営リスクに、社員の中からは不安視する声もあったそうです。全て自分で責任を取ると雨宮さんが言った時、ある社員が
『雨宮さん、そんな良い仕事を独り占めはずるいですよ。僕らにも責任ある仕事をさせて下さい』
と言われ涙したそうです。
『まだ誰も取り組んでいないこと、技術屋として何かできないか。それも世界の人々に感謝されるすばらしい仕事だと力説したんです。今となっては、よくもまぁ、任せてくれたものだと思いますよ。でも、社員とその家族は、私の思いに共感し、協力を誓ってくれたんです』
それでも、通常業務と平行して扱うにはこの仕事は負担が大きすぎました。
そこで、雨宮さんをはじめとする6人の担当者が、営業時間外の早朝や深夜、休日を使ってコツコツと開発に取り組みました。
『何しろ、まったく何も資料がないわけですから、開発は手探りでした。世界トップレベルという自負があった油圧ショベルの技術を、応用することまではすぐに思いついたのですが、その後は失敗ばかり』
たとえば、カンボジアは生い茂る木や草の下に対人地雷が隠れています。
ショベルの先にカッターをつけて刈り込んだ上で、対人地雷を爆発させて除去しなければならないのです。
はじめは他社から部品を購入したりしていたものの満足できず、ついには小さなねじに至るまで自社開発で取り組みました
また、爆発の際の温度は800度〜1000度にもなるのですが、その衝撃に耐えるのはもちろん、岩に対する耐性、切削性など、クリアしなければならない基準は山のようにありました。
『正直、そのころにはビジネスという言葉は忘れていましたね。かなりの開発費用もかかっていましたし、とにかく早く完成させて、早くカンボジアに持っていきたい。早くカンボジアの人々を危険から解放したい。でも一方で、いや、これは仕事なんだと、だからこそ、ちゃんと費用対効果が得られて、メンテナンスがしやすくて、使いやすい機械でなくてはと何度も自分にいい聞かせていました』
そして試作を繰り返した結果、一号機の「ロータリーカッタ式対人地雷除去機」が完成します。プロジェクトの開始から実に3 年以上もの月日が経っていました。
ところが、完成の喜びも束の間。開発した対人地雷除去機が、日本政府による武器輸出規制の原則「武器輸出三原則」に觝触するという指摘がなされてしまいます。
しかし、雨宮さんはあきらめることなく何度も何度も足を運びついに日本政府の許可を得る事が出来ました。
社員数60名の小さな企業が、どんな大企業もなし得なかった対人地雷除去機の開発という難事業を実現し、国内外から多くの賞賛が寄せられます。しかし、それは決して無償の奉仕活動でなかったからこそ実現し得たと雨宮さんはいう。
『私たちの対人地雷除去作業は、あくまでビジネスなのです。ボランティアやチャリティを決して否定するわけではないのですが、無償だったらここまでのクオリティを提供できていたかわかりません。お金をもらえるかどうかということではなく、どこまでお互いが対等に魂をぶつけ合えるかということが重要なのです』
確かに、『施し』だとしたら施される側は引け目に感じて遠慮がちになるかもしれません。提供する側もどこまで真剣にニーズに対応しようとするかは分かりません。
ビジネスだからこそ対等になれるし、要望や意見を戦わせることができるのだと振り返って雨宮さんは言います。
たとえば、熱帯に位置するカンボジアの土地は草木が茂り、雨期には足下がぬかるみ、そうした場所では、草木を刈り込みながら対人地雷除去作業をしなければいけません。
一方、乾燥地帯のアフガニスタンでは、乾いた砂の下は固い岩盤地層になっており、板状の歯では、すぐに欠けてしまって使い物にならなくなってしまいます。
通常は、提供された機械をその土地、土地に合わせて、使う側が工夫しながら使うしかありません。そのため、カンボジアでは対人地雷除去前に灌木を刈り込む際の爆発事故が絶えず、アフガニスタンでは故障した機械が放置されたままになっていたようです。
一方、雨宮さんはあくまで日本で顧客のニーズに応える時と同じように、真摯に1つひとつの要望に応えていきました。
『大量生産する自動車などとは違って、交換用の部品が高額になり、輸送コストや修理費の負担も無視できない。ですから、できるだけ交換用の部品は共有できるように工夫し、日本から送るにしてもできるだけコストがかからないようにしたわけです。』
さらには、現地でメンテナンスや修理ができるよう、そのノウハウもセットで提供しています。提供したからには、「費用対効果」を実感してほしいと雨宮さんは語ります。
いわば自分たちがやっている事業は、技術を仲立ちとしたビジネス・ソリューションだといいます。人道支援は、一過性のものではならない。継続して、その地域が自立できるよう手を貸すことが重要だと考えておられます。
『よく人道支援の方法として『人・物・金』といういい方をするけれど、物も金も使えば消えるもの。そんなものをばらまいても、一時的な気休めにしかならないでしょう。自立を促すには『人』を育てることが一番大切です。だから、我々は現地に自ら赴き、現地の人々に機械の使い方を教え、修理の仕方まで教えるんです。そうすれば、対人地雷除去機を操作する人、メンテナンスを行う人は仕事を得て、自立できるわけです』
現地での指導に限界を感じはじめた雨宮さんは、対人地雷埋設国の若者たちを日本に招き、山梨で対人地雷除去機の訓練を施す取り組みも2006年からスタートさせました。
まず来日したのは、世界でも最悪のレベルの対人地雷埋設国といわれるアンゴラから、政府によって派遣されてきた研修生の若者たちです。
アンゴラの人々は、2002年に終結するまで40年にも渡る長い間、内戦によって傷つけられてきました。
いまだ約1,500万個もの対人地雷が埋まり、その数はカンボジアと並び世界最多といわれています。来日した研修生のほとんどが、肉親や友人など身近な人を対人地雷によって傷つけられた経験を持っており、対人地雷の恐ろしさを肌身で知っていました。
だからこそ、1人ひとりが、国として自立していくために対人地雷の除去が不可欠であることを強く意識し、強い使命感に燃えていたといいます。
『大型機械を操縦したことがないという若者ばかりで、はじめはかなり戸惑っていました。しかし、彼らのまなざしときたら、なんとも真剣で。その気持ちに応えるつもりで、こちらも必死になって取り組みましたよ。しかし、もっとも苦慮したのは、現場に出たいと願う若者たちのはやる気持ちを抑えることでした。』
一刻も早く自国の対人地雷を1つでも多く除去したい。そう願うのは自然なことです。しかし、雨宮さんは黙々と基礎的な操作を行わせ、確実に技術が身につくまで徹底させました。
そして、ようやく2007年の夏、アンゴラに2台の対人地雷除去機が導入され、稼働が始まった時、雨宮さんはアンゴラの若者たちの横顔に誇りと使命感を見て、胸が熱くなったといいます。
『対人地雷埋設国の人々は、私たちに『支援してくれてありがとう』というけれど、たとえばアンゴラの若者たちの真剣さを見ていると、自分たちは支援させていただいているという気持ちになってくる。受ける側も提供する側も心が通っているからこそ、そこに何かが生まれる。日々の仕事の中で、『させていただいている』という敬虔な気持ちになることの重要性を学んだように思いますね』
今後はさらに長期的なプロジェクトを立ち上げ、雨宮さんの生涯をかけて取り組んでいくつもりだと仰っています。
『技術屋っていうのは、ものづくりの挑戦者だと思ってきました。しかし今、それに加えて、技術の根源は物づくりだけではなくて、人づくりにもあることを理解しつつあります。たとえ1人になってもやり遂げなくては、と気負っていた時期もありますが、気がつけば、家族や社員、地域の人々、政府やNPO関係者、そして地雷埋設国の人々、あらゆる人に支えられている。そして、真剣になれば必ず受け止めてくれる人がいて、思いが広がっていく。それが人を育くむということなんだと実感しています』
|
|
|
|
コメント(7)
クラスター爆弾を禁止するオスロ条約は今年の8月に発布されました。
批准している国は47カ国。しかしアメリカは署名していません。
今朝のニュースで知っておられる方もいると思いますがwikileaksでアメリカがアフガン政府に送った公文書が明らかになりました。
内容は
アフガニスタンがオスロ条約に署名しているにも関わらず
『アフガン国内でのクラスター爆弾の使用、備蓄、移動を認めるように。またアフガン国内でのクラスター爆弾使用、備蓄、移動を認めなければアメリカ軍の兵や同盟国の兵、アフガンの兵に敵対勢力から攻撃があった場合、死者が多数出るだろう。
もし第3者機関がクラスター爆弾の使用状況を確認する動きに出た時はアメリカ政府とアフガン政府は共同の意思を持ってクラスター爆弾の使用は人道の問題が提起されて以降は使用していない、と足並みを揃えて宣言する事。』
という内容でした。
思いっきりアフガン政府に圧力をかける内容でした。
ただ、この文書はブッシュ政権の時にアフガン政府に送られたものであって現在のオバマ政権はクラスター爆弾を廃棄する動きを見せているのが唯一の救いです。
しかしブッシュは本当に非人道的な大統領でしたがまだまだ何か出てきそうですね。あの人は本当に何がしたかったのか振り返ってもよく分かりません。軍需産業の言いなりだったのは確かですが…それはオバマさんも変わらないのかな…。
批准している国は47カ国。しかしアメリカは署名していません。
今朝のニュースで知っておられる方もいると思いますがwikileaksでアメリカがアフガン政府に送った公文書が明らかになりました。
内容は
アフガニスタンがオスロ条約に署名しているにも関わらず
『アフガン国内でのクラスター爆弾の使用、備蓄、移動を認めるように。またアフガン国内でのクラスター爆弾使用、備蓄、移動を認めなければアメリカ軍の兵や同盟国の兵、アフガンの兵に敵対勢力から攻撃があった場合、死者が多数出るだろう。
もし第3者機関がクラスター爆弾の使用状況を確認する動きに出た時はアメリカ政府とアフガン政府は共同の意思を持ってクラスター爆弾の使用は人道の問題が提起されて以降は使用していない、と足並みを揃えて宣言する事。』
という内容でした。
思いっきりアフガン政府に圧力をかける内容でした。
ただ、この文書はブッシュ政権の時にアフガン政府に送られたものであって現在のオバマ政権はクラスター爆弾を廃棄する動きを見せているのが唯一の救いです。
しかしブッシュは本当に非人道的な大統領でしたがまだまだ何か出てきそうですね。あの人は本当に何がしたかったのか振り返ってもよく分かりません。軍需産業の言いなりだったのは確かですが…それはオバマさんも変わらないのかな…。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
THE 感動する話 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-