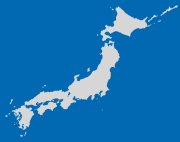すいません。
忙しくて自分の日記を更新するのに手一杯で、中々こちらのコミュニティーの更新にまで手が回らない状態です。
にも関わらず、先月から今月にかけて新規にご加入して頂けたお客様が複数いらっしゃったことに対しては大変感謝致しております。
いたらないコミュの管理人ながら、よろしくお願い致します。
ということで、ご挨拶はさておき、
10年先までに、今の中国に対する経済依存度を下げる為には日本政府や日本企業はどうするべきか?考察して行きたいと思います。
中国をマーケットとして見た場合は、確かに表面上は13億人の市場ということになっていますが、実態は、中国人に売れるモノは沢山あるものの、そのいずれもが、激しい価格競争の為に低い利益に甘んじていて、手間隙の割には継続して儲からないというのが過半数ではないか?と思われます。
唯一、中国を組み立て加工工場として使う場合に限り、
中国へ輸出する部品はなるべく高く輸出して、中国国内で労働集約的に手を掛けて製品化したものを、今度は出来るだけ安く輸出させることにより、「売り」と「買い」の両方で日本国内の利益を確保する。というやり方を取ることにより、一定の儲けを出すことが出来ています。
中国市場でうまく儲けられている内は何の問題も無いものの、中国マーケットは、他国のマーケットに比べて極端にニセモノが横行するマーケットであることから、
これは儲かるとなった途端、日本製の部品がすぐさま「リバース・エンジニアリング」されてしまって、コピー商品が出回るハメになります。
最終的な消耗製品とかエンド品であれば、その被害も限定的なものがら、
最近では、工具とか工作機械に至るまで、生産財や資本財までもがニセモノにさらされて、そのまま第三国に輸出されてしまうことにより、日本製品の市場シェアを落とすばかりではなく、日本の将来のメシのタネまでもが奪われつつあります。
中国企業における日本製品の技術侵害や、マーケットの荒らし行為については、他の先進国のように法律はあるものの、現実問題として司法に訴えても解決がほとんど望めない以上、このまま中国市場に深入りするのには危険が多く、なるべく早い時点で、中国市場への投資案件ほ減らす必用があると自分は考えております。
そこで、これ以上日本企業を深入りさせないようにする為、
将来の日本企業のメシのタネを中国に潰させないようにする為に、
あの国と距離を置くには何をしたら良いのか?
具体的な方法をどのように取ったら良いのか、考えて行きたいと思います。
まず、自分は政府が保証している対中貿易保険の掛け率を、事故事例と損害金額に応じて都度見直すシステムを導入してもらいたいと考えております。
民間ビジネスについては、本来であれば、民間同士のリスクであるので、政府が介入するべき問題ではないものの、現実問題として、中国市場への輸出のリスクの大半がこの保険の存在により、リスクがリスクと認識されなくなる「甘え」を生んでいる元凶ではないか?と考えております。
対中国の保険リスクについては、日本政府には早急に掛け率の見直しをしてもらうと共に、中国以外に輸出や投資案件を向かわせるインセンティブとする為に、たとえばインド向けに関して、上限幅の広い優遇保険の適用を進める。などするべきであろう。と考えます。
他にも、保険以外で、日本の海外投資を中国に一極集中させないようにする良い方法など思い付かれたメンバーの方がいらっしゃいましたら、コメントとして下に繋げて行ってもらいたいと存知ます。
忙しくて自分の日記を更新するのに手一杯で、中々こちらのコミュニティーの更新にまで手が回らない状態です。
にも関わらず、先月から今月にかけて新規にご加入して頂けたお客様が複数いらっしゃったことに対しては大変感謝致しております。
いたらないコミュの管理人ながら、よろしくお願い致します。
ということで、ご挨拶はさておき、
10年先までに、今の中国に対する経済依存度を下げる為には日本政府や日本企業はどうするべきか?考察して行きたいと思います。
中国をマーケットとして見た場合は、確かに表面上は13億人の市場ということになっていますが、実態は、中国人に売れるモノは沢山あるものの、そのいずれもが、激しい価格競争の為に低い利益に甘んじていて、手間隙の割には継続して儲からないというのが過半数ではないか?と思われます。
唯一、中国を組み立て加工工場として使う場合に限り、
中国へ輸出する部品はなるべく高く輸出して、中国国内で労働集約的に手を掛けて製品化したものを、今度は出来るだけ安く輸出させることにより、「売り」と「買い」の両方で日本国内の利益を確保する。というやり方を取ることにより、一定の儲けを出すことが出来ています。
中国市場でうまく儲けられている内は何の問題も無いものの、中国マーケットは、他国のマーケットに比べて極端にニセモノが横行するマーケットであることから、
これは儲かるとなった途端、日本製の部品がすぐさま「リバース・エンジニアリング」されてしまって、コピー商品が出回るハメになります。
最終的な消耗製品とかエンド品であれば、その被害も限定的なものがら、
最近では、工具とか工作機械に至るまで、生産財や資本財までもがニセモノにさらされて、そのまま第三国に輸出されてしまうことにより、日本製品の市場シェアを落とすばかりではなく、日本の将来のメシのタネまでもが奪われつつあります。
中国企業における日本製品の技術侵害や、マーケットの荒らし行為については、他の先進国のように法律はあるものの、現実問題として司法に訴えても解決がほとんど望めない以上、このまま中国市場に深入りするのには危険が多く、なるべく早い時点で、中国市場への投資案件ほ減らす必用があると自分は考えております。
そこで、これ以上日本企業を深入りさせないようにする為、
将来の日本企業のメシのタネを中国に潰させないようにする為に、
あの国と距離を置くには何をしたら良いのか?
具体的な方法をどのように取ったら良いのか、考えて行きたいと思います。
まず、自分は政府が保証している対中貿易保険の掛け率を、事故事例と損害金額に応じて都度見直すシステムを導入してもらいたいと考えております。
民間ビジネスについては、本来であれば、民間同士のリスクであるので、政府が介入するべき問題ではないものの、現実問題として、中国市場への輸出のリスクの大半がこの保険の存在により、リスクがリスクと認識されなくなる「甘え」を生んでいる元凶ではないか?と考えております。
対中国の保険リスクについては、日本政府には早急に掛け率の見直しをしてもらうと共に、中国以外に輸出や投資案件を向かわせるインセンティブとする為に、たとえばインド向けに関して、上限幅の広い優遇保険の適用を進める。などするべきであろう。と考えます。
他にも、保険以外で、日本の海外投資を中国に一極集中させないようにする良い方法など思い付かれたメンバーの方がいらっしゃいましたら、コメントとして下に繋げて行ってもらいたいと存知ます。
|
|
|
|
コメント(17)
私も、支那への投資集中は日本国にとって益よりも害・リスクのほうが大きいのではないかと考えます。
現地での投資計画を認めてもらうために、ヤマハ発動機のように軍事転用可能な製品を輸出するばかりでなく、技術移転までしてしまうという国賊企業が出てくるでしょう。
北京−上海の高速鉄道に関しても、別の路線で川崎重工から車両技術を移転させ、本当のドル箱の北京上海線は独自技術を開発するような恩知らずの国です。もっとも、川重もバカではないし、一部は技術移転しても肝心要の部分は秘匿するでしょうね。日本の鉄道技術を使わないで北上線を建設したところで、人身事故・車両故障・運行遅延など、とても実用には耐えないと思いますが。
さて支那への依存を避ける政策としては、支那からの逆輸入品に対して関税を高めることが考えられるのではないかと。農作物や百円ショップで売られている汎用廉価品、高額なデジタル製品までいろいろありますが、技術の流出を抑え、国内労働市場を保護するためにも、先端技術を駆使する製品に関しては逆輸入品に高関税をかけ、逆に国内への大規模工場投資には補助金や5年程度の優遇税制を適用する。
また親日国や支那の膨張に警戒感を強めている国、たとえばインドや東南アジア諸国への投資を政府が後押しする。
産業政策を戦略的に外交に用いるべき時期が来ているのかもしれませんね。
ところで、また貿易保険に関するエルトリューム氏のご意見に対しては、既に支那のデフォルトリスクはインドネシア等より低いのではないかと思います。国営企業や国有銀行の財務体質はまったく信用できませんが、国全体としてみれば外貨準備高はついに世界最大です。また一党独裁の強権国家というだけあって、政情も比較的安定しています。貿易は門外漢なので詳しいことはわかりませんが。
もしそうだとすると、貿易保険の保険料というツールでは、他のアジア諸国への投資を優遇するという戦略を実現できないことになります。
カネのかからない政策としては、クールビズ運動のようなキャンペーンもいいでしょう。「国産品を見直そう」運動です。優遇税制・補助金などは資金の手当てが大変ですし、外交問題にもなりかねない。
その点、経産省あたりが旗を振って「国産品奨励キャンペーン」をやれば、繊維産業から電機産業まで、恩恵は大きいと思いますよ。
今はまだ、「支那製は安かろう悪かろう」「日本製は高品質」といった神話が生きています。だからシャープ亀山工場製の液晶は産地ブランドがついているのです。
「支那製は安くて高品質」というイメージが定着しないうちに、こうしたキャンペーンを行ったり、子供達への日本のものづくり教育を徹底したりして、日本の製造業を発揚していく必要があると感じます。
現地での投資計画を認めてもらうために、ヤマハ発動機のように軍事転用可能な製品を輸出するばかりでなく、技術移転までしてしまうという国賊企業が出てくるでしょう。
北京−上海の高速鉄道に関しても、別の路線で川崎重工から車両技術を移転させ、本当のドル箱の北京上海線は独自技術を開発するような恩知らずの国です。もっとも、川重もバカではないし、一部は技術移転しても肝心要の部分は秘匿するでしょうね。日本の鉄道技術を使わないで北上線を建設したところで、人身事故・車両故障・運行遅延など、とても実用には耐えないと思いますが。
さて支那への依存を避ける政策としては、支那からの逆輸入品に対して関税を高めることが考えられるのではないかと。農作物や百円ショップで売られている汎用廉価品、高額なデジタル製品までいろいろありますが、技術の流出を抑え、国内労働市場を保護するためにも、先端技術を駆使する製品に関しては逆輸入品に高関税をかけ、逆に国内への大規模工場投資には補助金や5年程度の優遇税制を適用する。
また親日国や支那の膨張に警戒感を強めている国、たとえばインドや東南アジア諸国への投資を政府が後押しする。
産業政策を戦略的に外交に用いるべき時期が来ているのかもしれませんね。
ところで、また貿易保険に関するエルトリューム氏のご意見に対しては、既に支那のデフォルトリスクはインドネシア等より低いのではないかと思います。国営企業や国有銀行の財務体質はまったく信用できませんが、国全体としてみれば外貨準備高はついに世界最大です。また一党独裁の強権国家というだけあって、政情も比較的安定しています。貿易は門外漢なので詳しいことはわかりませんが。
もしそうだとすると、貿易保険の保険料というツールでは、他のアジア諸国への投資を優遇するという戦略を実現できないことになります。
カネのかからない政策としては、クールビズ運動のようなキャンペーンもいいでしょう。「国産品を見直そう」運動です。優遇税制・補助金などは資金の手当てが大変ですし、外交問題にもなりかねない。
その点、経産省あたりが旗を振って「国産品奨励キャンペーン」をやれば、繊維産業から電機産業まで、恩恵は大きいと思いますよ。
今はまだ、「支那製は安かろう悪かろう」「日本製は高品質」といった神話が生きています。だからシャープ亀山工場製の液晶は産地ブランドがついているのです。
「支那製は安くて高品質」というイメージが定着しないうちに、こうしたキャンペーンを行ったり、子供達への日本のものづくり教育を徹底したりして、日本の製造業を発揚していく必要があると感じます。
まず、「グローバリズム」の定義について、その本質はインターネットでもWTOでもなくて、「世界中に米軍の武威が及んでいるからどこの国に投資しても大丈夫」という事であった、ということを再確認する必要があると思います。
つまり、冷戦時代になぜ欧米や日本の企業が発展途上国に工場を移さなかったかというと、ある企業がどっかの国に工場作って何年もかけてようやく儲かる状態になったとしても、ソ連が背後にいる「人民革命軍」とやらがやってきてカラシニコフを突きつけて「人民を搾取するおまいの工場を接収する」と言われるかも知れなかったからです。
それが、冷戦が崩壊してついでに湾岸戦争で米軍の圧倒的な強さが知れ渡って、世界中に米軍の武威がとどろいた結果、経営者やら経済学者やらが「世界中どんなヘンな国に投資しても大丈夫。いざとなればアメリカがその武威で『人民革命軍』とやらを鎮圧してくれる」と考えて、「そんじゃ世界一材料の安い国から買って世界一給料の安い国で加工して世界一物価の高い国で売ろう」と安直に考えるようになったのが、「グローバリズム」とやらの正体です。
それに便乗したのが中国で、WTOだの改革開放だのとグローバリズムに乗っ取ったふりをして世界中の投資を呼び込んだ。ところが、その大前提となっている「米軍の武威」が中国政府にまで及んでいたかというと、正直疑問があります。
海洋においてはともかく、陸上において米軍が中国全土を制圧できる状態にはまったく無い。核戦力も、少数ではあるが一応ICBMを持っていてアメリカとはMAD状態を維持している。ということは、中国は「米軍の武威に従って外国からの投資を保護する」という本来のグローバリズムに則った状態ではなくて、「従ったフリをしていた」だけと言うことです。
ところが、経営者だの投資家だのは自分の商売には詳しくても、地政学の専門家ではないから騙されてしまう。あんだけ頭のいい人間を集めていたはずのLTCMが、「ロシア人に金を貸す」という常識的に考えたらどう見ても無謀な行為をやってしまったあげく大失敗したのがいい例です。
つまり、「世界には米軍の武威が及ばない国がある」ということ、「そういう国に進出するのは知的・物的所有権が保障されるとは限らない」ということを経営者に知らしめる必要があるんでしょうな。
もっとシンプルに言えば、「中国に進出した企業はいつ北京政府の都合で潰されてもおかしくない」、ということを日本政府はきっちり経営者に伝えておくべきだなということです。上海や大連とかの沿岸部なら、せめて人間だけなら空母とヘリで拾えるかも知れないけど、重慶など内陸部に進出した場合にはもう助けようも無いということも。「沿岸から500km以上離れた地域への進出は生命財産の保証をしかねる」と言わんといかんでしょうな。
つまり、冷戦時代になぜ欧米や日本の企業が発展途上国に工場を移さなかったかというと、ある企業がどっかの国に工場作って何年もかけてようやく儲かる状態になったとしても、ソ連が背後にいる「人民革命軍」とやらがやってきてカラシニコフを突きつけて「人民を搾取するおまいの工場を接収する」と言われるかも知れなかったからです。
それが、冷戦が崩壊してついでに湾岸戦争で米軍の圧倒的な強さが知れ渡って、世界中に米軍の武威がとどろいた結果、経営者やら経済学者やらが「世界中どんなヘンな国に投資しても大丈夫。いざとなればアメリカがその武威で『人民革命軍』とやらを鎮圧してくれる」と考えて、「そんじゃ世界一材料の安い国から買って世界一給料の安い国で加工して世界一物価の高い国で売ろう」と安直に考えるようになったのが、「グローバリズム」とやらの正体です。
それに便乗したのが中国で、WTOだの改革開放だのとグローバリズムに乗っ取ったふりをして世界中の投資を呼び込んだ。ところが、その大前提となっている「米軍の武威」が中国政府にまで及んでいたかというと、正直疑問があります。
海洋においてはともかく、陸上において米軍が中国全土を制圧できる状態にはまったく無い。核戦力も、少数ではあるが一応ICBMを持っていてアメリカとはMAD状態を維持している。ということは、中国は「米軍の武威に従って外国からの投資を保護する」という本来のグローバリズムに則った状態ではなくて、「従ったフリをしていた」だけと言うことです。
ところが、経営者だの投資家だのは自分の商売には詳しくても、地政学の専門家ではないから騙されてしまう。あんだけ頭のいい人間を集めていたはずのLTCMが、「ロシア人に金を貸す」という常識的に考えたらどう見ても無謀な行為をやってしまったあげく大失敗したのがいい例です。
つまり、「世界には米軍の武威が及ばない国がある」ということ、「そういう国に進出するのは知的・物的所有権が保障されるとは限らない」ということを経営者に知らしめる必要があるんでしょうな。
もっとシンプルに言えば、「中国に進出した企業はいつ北京政府の都合で潰されてもおかしくない」、ということを日本政府はきっちり経営者に伝えておくべきだなということです。上海や大連とかの沿岸部なら、せめて人間だけなら空母とヘリで拾えるかも知れないけど、重慶など内陸部に進出した場合にはもう助けようも無いということも。「沿岸から500km以上離れた地域への進出は生命財産の保証をしかねる」と言わんといかんでしょうな。
>らいてふ さん コメントありがとうございました。
一ヶ月以上も自分のコミュニティーをほおりっぱなしにしている至らない管理人ではありますが、今後も気が付いたことがあれば、ご指摘の段、よろしくお願い致します。
その上で、中国におけるデフォルトリスクについてですが、
貿易保険の支払い対象をよく見てみると、広義の意味での国のカントリーリスク(財政破綻など)においては、確かに、今の中国は世界最高の外貨準備を誇り、破綻の可能性は極端に低いのですが、支払い件数は、外貨準備がそれほど無い南アメリカ辺りの途上国と比較しても、取り扱い件数当たりでは負けていないのが実態です。
つまり、詐欺・泥棒・商品の紛失などがとても多いので、それに伴う保険申請も多いのです。
当然、「商品が行方不明になる事故??」は何も中国だけの専売特許ではなく、他所の国でも良く見られる事例ではあるものの、この点を声高に叫ぶことにより、もう日本政府は中国との商取引について今までのような「保護」は止める。と知らしめるだけで、少なくとも高額品についての取引は減らせるのではないか?と考えております。
単価の安い軽工業品である衣料品や食器・おもちゃなどについては、そんなに簡単には減らないでしょうが、工作機械やソフトウェアーなどの高額商品を減らすことが出来れば、かならず中国との貿易総額は大きく減らせると思います。
まずは金額ベースで、中国以外の国へのシフトを強め、代替市場自体を日本自身が育てることから始めないと行けないのだと思います。
先はかなり長そうですが、中国とて、ここまでになれたのも、わずかここ20年のお話に過ぎません。
個人的にはインドにもう少し頑張ってもらいたいところですね。
一ヶ月以上も自分のコミュニティーをほおりっぱなしにしている至らない管理人ではありますが、今後も気が付いたことがあれば、ご指摘の段、よろしくお願い致します。
その上で、中国におけるデフォルトリスクについてですが、
貿易保険の支払い対象をよく見てみると、広義の意味での国のカントリーリスク(財政破綻など)においては、確かに、今の中国は世界最高の外貨準備を誇り、破綻の可能性は極端に低いのですが、支払い件数は、外貨準備がそれほど無い南アメリカ辺りの途上国と比較しても、取り扱い件数当たりでは負けていないのが実態です。
つまり、詐欺・泥棒・商品の紛失などがとても多いので、それに伴う保険申請も多いのです。
当然、「商品が行方不明になる事故??」は何も中国だけの専売特許ではなく、他所の国でも良く見られる事例ではあるものの、この点を声高に叫ぶことにより、もう日本政府は中国との商取引について今までのような「保護」は止める。と知らしめるだけで、少なくとも高額品についての取引は減らせるのではないか?と考えております。
単価の安い軽工業品である衣料品や食器・おもちゃなどについては、そんなに簡単には減らないでしょうが、工作機械やソフトウェアーなどの高額商品を減らすことが出来れば、かならず中国との貿易総額は大きく減らせると思います。
まずは金額ベースで、中国以外の国へのシフトを強め、代替市場自体を日本自身が育てることから始めないと行けないのだと思います。
先はかなり長そうですが、中国とて、ここまでになれたのも、わずかここ20年のお話に過ぎません。
個人的にはインドにもう少し頑張ってもらいたいところですね。
>一閃 さん コメントありがとうございました。
日記に引き続き、当コミュニティーにも書き込みを頂き感謝致します。
ベトナムですが、すでに中国を撤退した日本企業と、
それよりも前から大挙して進出していた台湾と、
なぜか、中国人がベトナムに会社を作って、それを「外資」ということにして、中国本土で税制上での優遇を受けたいダミー企業が入り乱れて、現地は大変な好景気だそうです。
賃金もここ最近かなり上がってきていて、衣料品などの労働集約産業は、国際競争力を保てなくなってきたので、一部は、ラオスだの、カンボジアだの、ミヤンマーだのに生産拠点を移し始めているとか。
ただし、それら周辺諸国はいずれもインフラの整備が追い付いていないので、ちゃんと事業を続けていけるだけの進出可能な工業団地はどこも手狭で設備も悪く、自前の発電設備や水源の確保は当たり前だとか。
一見、日本のODAの出番のような気もしますが、仮にODAで発電所や上水道の設備を作ってあげた所で、その恩恵を利用するのは中国系の企業ばっかり。ということにならないよう、日本側としては、たとえ批判を受けても、きちんとヒモを付けて、本当に日本企業や当事国の企業にその恩恵が行き渡るような監視するようにしてもらいたいものですね。
従来のような雇用の場さえ確保出来れば、どこの国の企業が使おうと問題にしない。というやり方では、結局日本が出した金は中国企業を助けるだけに使われ、しかも進出先の国の国民がそれら中国企業に所得を搾取されてしまうだけに終わってしまうような気がしています。
日記に引き続き、当コミュニティーにも書き込みを頂き感謝致します。
ベトナムですが、すでに中国を撤退した日本企業と、
それよりも前から大挙して進出していた台湾と、
なぜか、中国人がベトナムに会社を作って、それを「外資」ということにして、中国本土で税制上での優遇を受けたいダミー企業が入り乱れて、現地は大変な好景気だそうです。
賃金もここ最近かなり上がってきていて、衣料品などの労働集約産業は、国際競争力を保てなくなってきたので、一部は、ラオスだの、カンボジアだの、ミヤンマーだのに生産拠点を移し始めているとか。
ただし、それら周辺諸国はいずれもインフラの整備が追い付いていないので、ちゃんと事業を続けていけるだけの進出可能な工業団地はどこも手狭で設備も悪く、自前の発電設備や水源の確保は当たり前だとか。
一見、日本のODAの出番のような気もしますが、仮にODAで発電所や上水道の設備を作ってあげた所で、その恩恵を利用するのは中国系の企業ばっかり。ということにならないよう、日本側としては、たとえ批判を受けても、きちんとヒモを付けて、本当に日本企業や当事国の企業にその恩恵が行き渡るような監視するようにしてもらいたいものですね。
従来のような雇用の場さえ確保出来れば、どこの国の企業が使おうと問題にしない。というやり方では、結局日本が出した金は中国企業を助けるだけに使われ、しかも進出先の国の国民がそれら中国企業に所得を搾取されてしまうだけに終わってしまうような気がしています。
>緑川だむ さん どうも。
グローバリズムによる恩恵を一番受けてきたのは他ならぬアメリカであり、今までは世界中で一番安い商品を大量に消費することによる豊かな生活を享受してくきました。
ただし、今後、中国の台頭が続き、しかも、中国の一党独裁体制が続くようならば、いずれアメリカ国民はその豊かな生活を一部切り捨ててでも、中国とは対決姿勢を鮮明にして一線を引くことになるのではないでしょうか?
たとえ中国が一時的に混乱するようになったとしても、不安定化するのは極東アジア地域だけあって、ヨーロッパもアメリカも、正直貿易面でのわすかな金銭的影響を蒙る他は、元々極東からのエネルギー供給といった要素も無いので、これといって国家に死活的な不利益はありません。
日本はその真っ只中に置き去りにされることとなりますが、それもこれも、たまたま地政学的な位置関係にあるからゆえであって、小手先の政策でどうこうなるものじゃありません。
ゆえに、中国の台頭は台頭として、中国と今以上に経済関係を結ぶのではなく、保険を掛けるつもりで、中国以外の国との補完関係を強化する必要があるのだと思います。
冷戦期、アメリカがソビエトの封じ込めに曲りなりにも成功したのは、そもそもアメリカの西側経済システムと、ソビエトのコメコン経済が相互依存関係になく、独立したクローズ経済で成り立っていたからですが、
中国の経済については、アメリカの、というより、西側の経済システムに乗った形で発展してきているだけに、これを封じ込めるのは容易なことではありません。
そこで、経済システムのルールを中国に都合の悪い方式に変える必要が出てくるのですが、
先日のNHK特集を見ていて、中国が 京都議定書 を批准しないばっかりに、排気ガスを出せば出すだけ、国際的な排出権ビジネスで大儲け出来てしまう現実を目の当たりにして、
この産業(具体的には中国自前の石炭資源を大量消費する製造業)を規制する「環境保護」を経済にリンクさせた形での西側の国際ルールを作り直し、そこで環境規制に従えない中国企業を国際取引の世界から排除することにより、中国の台頭を遅らせるのが妥当な選択ではないか?と考えております。
※中国国内における消費エネルギーは未だに7割が石炭ですので、
これが使いづらくなるだけで、中国は代替エネルギーの入手に
高負担を強いられ、結果とて国際競争力は間違いなく低下します。
地球環境保護は、自称「市民団体」だの「地球市民」だのとことあるこどにデモ行進をする連中の大好きな言葉ですので、連中も今までのドグマがある以上、迂闊に反対も出来ないでしょう。
使い方を誤れば、これは諸刃の剣となり、日本は今以上の限界を超えた排出削減目標を押し付けられる結果となる可能性もありますが、基本的な考え方とすれば、「地球環境保護」の大義名分がある以上、以外とすんなり国際社会で同意が得られるような気もします。
日本はこの方法で中国の国や企業から徐々に距離を置くようにして行くのが良いのではないか?と考えます。
グローバリズムによる恩恵を一番受けてきたのは他ならぬアメリカであり、今までは世界中で一番安い商品を大量に消費することによる豊かな生活を享受してくきました。
ただし、今後、中国の台頭が続き、しかも、中国の一党独裁体制が続くようならば、いずれアメリカ国民はその豊かな生活を一部切り捨ててでも、中国とは対決姿勢を鮮明にして一線を引くことになるのではないでしょうか?
たとえ中国が一時的に混乱するようになったとしても、不安定化するのは極東アジア地域だけあって、ヨーロッパもアメリカも、正直貿易面でのわすかな金銭的影響を蒙る他は、元々極東からのエネルギー供給といった要素も無いので、これといって国家に死活的な不利益はありません。
日本はその真っ只中に置き去りにされることとなりますが、それもこれも、たまたま地政学的な位置関係にあるからゆえであって、小手先の政策でどうこうなるものじゃありません。
ゆえに、中国の台頭は台頭として、中国と今以上に経済関係を結ぶのではなく、保険を掛けるつもりで、中国以外の国との補完関係を強化する必要があるのだと思います。
冷戦期、アメリカがソビエトの封じ込めに曲りなりにも成功したのは、そもそもアメリカの西側経済システムと、ソビエトのコメコン経済が相互依存関係になく、独立したクローズ経済で成り立っていたからですが、
中国の経済については、アメリカの、というより、西側の経済システムに乗った形で発展してきているだけに、これを封じ込めるのは容易なことではありません。
そこで、経済システムのルールを中国に都合の悪い方式に変える必要が出てくるのですが、
先日のNHK特集を見ていて、中国が 京都議定書 を批准しないばっかりに、排気ガスを出せば出すだけ、国際的な排出権ビジネスで大儲け出来てしまう現実を目の当たりにして、
この産業(具体的には中国自前の石炭資源を大量消費する製造業)を規制する「環境保護」を経済にリンクさせた形での西側の国際ルールを作り直し、そこで環境規制に従えない中国企業を国際取引の世界から排除することにより、中国の台頭を遅らせるのが妥当な選択ではないか?と考えております。
※中国国内における消費エネルギーは未だに7割が石炭ですので、
これが使いづらくなるだけで、中国は代替エネルギーの入手に
高負担を強いられ、結果とて国際競争力は間違いなく低下します。
地球環境保護は、自称「市民団体」だの「地球市民」だのとことあるこどにデモ行進をする連中の大好きな言葉ですので、連中も今までのドグマがある以上、迂闊に反対も出来ないでしょう。
使い方を誤れば、これは諸刃の剣となり、日本は今以上の限界を超えた排出削減目標を押し付けられる結果となる可能性もありますが、基本的な考え方とすれば、「地球環境保護」の大義名分がある以上、以外とすんなり国際社会で同意が得られるような気もします。
日本はこの方法で中国の国や企業から徐々に距離を置くようにして行くのが良いのではないか?と考えます。
ただまあ、さらにもう一段深い話をすると、「日本がアメリカを敵としないためには、共通の敵を必要とする」という状況はあるわけで、そのための道具として使われる連中がイスラム原理主義程度だと、とても「共通の敵」を演じるには力不足すぎる。
少なくとも中国人は「自分の力で宇宙へ行った」連中であって、それくらいの実力を持っていれば今後数十年に渡って日本の安全を保障する=冷戦体制を作り上げるに値する、とある意味私は中国の実力を高く評価してるんですよな。
だから、中国との対立状態は望んでいても戦争になることは望んでいない。向こう数十年、東シナ海を挟んでにらみ合い続けることが日本の繁栄を保証しうる。そうすると、ある意味「冷戦崩壊以来十数年かけて、『アメリカとの共通の敵』たりうる相手をようやく育成できた」とも言えるわけです。
最近になって、WW2が終わった後もロールスロイスのジェットエンジンをソ連に売っていたイギリス人の考えがちょっとわかるようになって来ましたよ。
少なくとも中国人は「自分の力で宇宙へ行った」連中であって、それくらいの実力を持っていれば今後数十年に渡って日本の安全を保障する=冷戦体制を作り上げるに値する、とある意味私は中国の実力を高く評価してるんですよな。
だから、中国との対立状態は望んでいても戦争になることは望んでいない。向こう数十年、東シナ海を挟んでにらみ合い続けることが日本の繁栄を保証しうる。そうすると、ある意味「冷戦崩壊以来十数年かけて、『アメリカとの共通の敵』たりうる相手をようやく育成できた」とも言えるわけです。
最近になって、WW2が終わった後もロールスロイスのジェットエンジンをソ連に売っていたイギリス人の考えがちょっとわかるようになって来ましたよ。
皆様、はじめまして。
どう言う人間かは、こちらのホームをトレースしていただければ幸いです。
まず、このスレッドの問題提起の前提にあるモノが、規定されていないと思いますので指摘したいと思います。
それは、「何故中国を忌避する必要があるのか」ということです。
確かに、中国には色々な状況証拠が存在します。
が、それが全て一概に中国を拒絶するに値するものであると断言するに至る根拠としては十分ではない、と考えます。
次に、一つだけ疑問になっているポイントがあるのでご説明いただければ幸いです。
戦略構築の前提として、それが短期的戦略であるのか長期的戦略であるのかという指標が必要であることは戦略設計の初歩的な基礎概念です。
10年先、という規定が見受けられましたが「中国への経済依存度を下げる」という命題に対してその時間設定で有効であると判断されて提起されたのでしょうか?というのが質問です。
スレッドの命題に個人的な考えを述べさせていただくと、中国を拒絶するよりも有効に利用するべきであると考えます。
ただ、安全保障上の利害関係が対立していること、共産独裁体制の国家であることから、軍事上の対立点をどう処理するか、また中国の軍事戦略をどう分析するかで大きく異なると思われます。
また、経済的な分野の技術盗用の可能性についてですが、おそらく今後中国は、国際協調と平和的台頭という自身の打ち出した戦略スローガンに自縄自縛されていく事になるでしょう。
そうなると必然的に国際環境下での中国の対外イメージ構築は格段に難しくなるために、少なくとも自浄作用を働かさざるを得ないという道筋しかなくなります。
このあたりは、オリンピックに向けての国内活動を見ていただければ想像しやすいのではないでしょうか。
軍事的な技術盗用の可能性についてですが、残念ながら日本ルートを遮断しても効果はほとんどありません。
現に、アメリカ→イスラエル→中国というルートでAWACS技術の漏洩未遂事件が過去にあります。
それら以外のルートを構築している可能性は捨てきれませんから、日本がやれることには限界があります。
このようなグローバルな視点で日本の対中経済戦略を覗いてみると実は狡猾以外の何物でもないと思います。
中国進出が日本企業は遅れたと報道されていますが、そうではなくて現実は台湾経由、シンガポール経由という華僑ルートと間接的なルートからの実験的資本注入というステップを踏んでリスク回避に動いていた傾向も見られます。
それともう一つは、財界・霞ヶ関の動向を見ても中国を消費市場化しようという動きが明白です。それはハイレベル技術の移転はなされていない事を見ればおわかりいただけると思います。
そのような動向から、むしろ以下の視点の検討も必要ではないでしょうか?
1:中国市場における日本製品への依存度の増加
2:中国製品の流入比率の抑制と高度技術の移転回避
そう考えると、中国と経済的には距離を縮め技術的には間を置くという選択肢が、安全保障上・経済上有効ではないでしょうか?
どう言う人間かは、こちらのホームをトレースしていただければ幸いです。
まず、このスレッドの問題提起の前提にあるモノが、規定されていないと思いますので指摘したいと思います。
それは、「何故中国を忌避する必要があるのか」ということです。
確かに、中国には色々な状況証拠が存在します。
が、それが全て一概に中国を拒絶するに値するものであると断言するに至る根拠としては十分ではない、と考えます。
次に、一つだけ疑問になっているポイントがあるのでご説明いただければ幸いです。
戦略構築の前提として、それが短期的戦略であるのか長期的戦略であるのかという指標が必要であることは戦略設計の初歩的な基礎概念です。
10年先、という規定が見受けられましたが「中国への経済依存度を下げる」という命題に対してその時間設定で有効であると判断されて提起されたのでしょうか?というのが質問です。
スレッドの命題に個人的な考えを述べさせていただくと、中国を拒絶するよりも有効に利用するべきであると考えます。
ただ、安全保障上の利害関係が対立していること、共産独裁体制の国家であることから、軍事上の対立点をどう処理するか、また中国の軍事戦略をどう分析するかで大きく異なると思われます。
また、経済的な分野の技術盗用の可能性についてですが、おそらく今後中国は、国際協調と平和的台頭という自身の打ち出した戦略スローガンに自縄自縛されていく事になるでしょう。
そうなると必然的に国際環境下での中国の対外イメージ構築は格段に難しくなるために、少なくとも自浄作用を働かさざるを得ないという道筋しかなくなります。
このあたりは、オリンピックに向けての国内活動を見ていただければ想像しやすいのではないでしょうか。
軍事的な技術盗用の可能性についてですが、残念ながら日本ルートを遮断しても効果はほとんどありません。
現に、アメリカ→イスラエル→中国というルートでAWACS技術の漏洩未遂事件が過去にあります。
それら以外のルートを構築している可能性は捨てきれませんから、日本がやれることには限界があります。
このようなグローバルな視点で日本の対中経済戦略を覗いてみると実は狡猾以外の何物でもないと思います。
中国進出が日本企業は遅れたと報道されていますが、そうではなくて現実は台湾経由、シンガポール経由という華僑ルートと間接的なルートからの実験的資本注入というステップを踏んでリスク回避に動いていた傾向も見られます。
それともう一つは、財界・霞ヶ関の動向を見ても中国を消費市場化しようという動きが明白です。それはハイレベル技術の移転はなされていない事を見ればおわかりいただけると思います。
そのような動向から、むしろ以下の視点の検討も必要ではないでしょうか?
1:中国市場における日本製品への依存度の増加
2:中国製品の流入比率の抑制と高度技術の移転回避
そう考えると、中国と経済的には距離を縮め技術的には間を置くという選択肢が、安全保障上・経済上有効ではないでしょうか?
そのあたりでもう一つ指摘しておかなければいけないのは、「北京の中国共産党政府」と「上海・香港を中心にした工業地帯」とはどこまで一蓮托生でいられるんだろうと言う疑問があるということです。
他のトピでも既に指摘していますが、中国共産党の戦略は基本的に「全面核戦争になっても人口密度の低い農村部を基盤として戦争を継続する」です。米軍が陸上に大兵力を展開できないのを見越した上で、唯一米軍が内陸部に対して持つ攻撃手段である全面核攻撃を行った場合でも、農村部に分散させた兵力で共産党政権を維持する。なおかつ報復用のICBMを少数でも維持してアメリカの大都市に対して核攻撃を行う能力を保持することで、アメリカの先制攻撃を抑止するという戦略です。
ところが、この戦略は20年前までの農業国家だった中国においてはおおむね全国民の利害と一致したでしょうが、最近になると異なってくる。核シェルターと農村部に分散した中国共産党は全面核戦争を生き残れるかも知れませんが、上海・香港など沿岸部を中心にした、ここ20年で成長してきた工業地帯は核戦争に耐えられないということです。
つまり、共産党の戦略において実は沿岸部工業地帯というのは、「核戦争の時にはまっさきに大損害を受ける」事が確定しており、ある意味北京政府から見捨てられているという事です。むろん、近年になって中国は海軍建設を進めて「沿岸部工業地帯を防衛する」という姿勢を見せていますが、「陸軍国と海軍国を兼ねることは出来ない」という原則から、ガチ勝負すれば所詮日米海軍に勝つことは出来ない。海上輸送に依存した沿岸部工業地帯は、海上封鎖を喰らえば核攻撃されなくても日干しです。
つまり、沿岸部の工業地帯と北京の共産党政府というのは、米中・日中冷戦が今後激しくなるに連れて利害が一致しなくなると言う事です。ところが、中国の発言力増大も海外進出を支える国力も、全ては貧乏人がいるだけの農村部ではなくて沿岸部の工業地帯に支えられている。このねじれ現象が、今後どう影響してくるかがよくわからん所ですが。
他のトピでも既に指摘していますが、中国共産党の戦略は基本的に「全面核戦争になっても人口密度の低い農村部を基盤として戦争を継続する」です。米軍が陸上に大兵力を展開できないのを見越した上で、唯一米軍が内陸部に対して持つ攻撃手段である全面核攻撃を行った場合でも、農村部に分散させた兵力で共産党政権を維持する。なおかつ報復用のICBMを少数でも維持してアメリカの大都市に対して核攻撃を行う能力を保持することで、アメリカの先制攻撃を抑止するという戦略です。
ところが、この戦略は20年前までの農業国家だった中国においてはおおむね全国民の利害と一致したでしょうが、最近になると異なってくる。核シェルターと農村部に分散した中国共産党は全面核戦争を生き残れるかも知れませんが、上海・香港など沿岸部を中心にした、ここ20年で成長してきた工業地帯は核戦争に耐えられないということです。
つまり、共産党の戦略において実は沿岸部工業地帯というのは、「核戦争の時にはまっさきに大損害を受ける」事が確定しており、ある意味北京政府から見捨てられているという事です。むろん、近年になって中国は海軍建設を進めて「沿岸部工業地帯を防衛する」という姿勢を見せていますが、「陸軍国と海軍国を兼ねることは出来ない」という原則から、ガチ勝負すれば所詮日米海軍に勝つことは出来ない。海上輸送に依存した沿岸部工業地帯は、海上封鎖を喰らえば核攻撃されなくても日干しです。
つまり、沿岸部の工業地帯と北京の共産党政府というのは、米中・日中冷戦が今後激しくなるに連れて利害が一致しなくなると言う事です。ところが、中国の発言力増大も海外進出を支える国力も、全ては貧乏人がいるだけの農村部ではなくて沿岸部の工業地帯に支えられている。このねじれ現象が、今後どう影響してくるかがよくわからん所ですが。
緑川だむさんのおっしゃる指摘は正しいと思います。
共産政権下の社会において富裕層や中産階層が、彼等の利益を要求し始めた時に政府がそれと対立した場合どうなるのか?というところは非常に大きいポイントです。
これは、今まで中国の政権体制は共産党一党支配でしたからそれまでは党と官僚が政策設計をしてきていたわけです。
ところが、そうした新興階層が出現した事によって「世論」が政治に影響を与えようとしています。
誤解の無いようにしておきますと、それまで世論が全く無かったわけで無く、新興階層の経済力が大きく彼らの世論が無視できないまでに成長しつつあり、政治に影響を及ぼし始めたという意味です。
そう考えると、本当に中国と経済的関係を切り離す、もしくは低減させる事が必ずしも日本の利益になるのか?という指摘も重要になるといえるでしょう
言いかえれば、むしろ中国の富裕層や中産層を増やす事が実は中国国内の内部矛盾を増幅させ、彼等自身で内部改革を起こさせる契機にも成り得ることはないだろうか?という問題提起でもあると思います。
また、海軍国家論と陸軍国家論の性質共存不可のご指摘も全くそのとおりです。
その点からすれば、すでに中国はアメリカの張り巡らせた網に囲まれているが為に必死になってもがいているとも思えます。
ただ、今現状を思うに中国は日本がかつて誤った間違いに気付くかどうかというところもポイントの一つなのかもしれません。
それは日本はかつて海軍国家でなければならないのに大陸国家思想を展開してしまった、そして緑川だむさんのおっしゃった両論共存の可能性を模索して失敗した、というところです。
彼等は今その逆を展開しようとしていると言えるのかもしれません、もちろんあくまで仮説ですので検証する必要性はあります。
経済的な視点から見ると少なくとも言える事は方法論は二つあって、拒絶か依存関係の深化という相反する様で実は日本の実益を導く上では大差がないという選択肢が存在しているということでしょう。
もっとも、その二つのどちらかを選ぶにしても、政策を操作する人間即ち通産官僚と政治家の腕次第ということになります。
共産政権下の社会において富裕層や中産階層が、彼等の利益を要求し始めた時に政府がそれと対立した場合どうなるのか?というところは非常に大きいポイントです。
これは、今まで中国の政権体制は共産党一党支配でしたからそれまでは党と官僚が政策設計をしてきていたわけです。
ところが、そうした新興階層が出現した事によって「世論」が政治に影響を与えようとしています。
誤解の無いようにしておきますと、それまで世論が全く無かったわけで無く、新興階層の経済力が大きく彼らの世論が無視できないまでに成長しつつあり、政治に影響を及ぼし始めたという意味です。
そう考えると、本当に中国と経済的関係を切り離す、もしくは低減させる事が必ずしも日本の利益になるのか?という指摘も重要になるといえるでしょう
言いかえれば、むしろ中国の富裕層や中産層を増やす事が実は中国国内の内部矛盾を増幅させ、彼等自身で内部改革を起こさせる契機にも成り得ることはないだろうか?という問題提起でもあると思います。
また、海軍国家論と陸軍国家論の性質共存不可のご指摘も全くそのとおりです。
その点からすれば、すでに中国はアメリカの張り巡らせた網に囲まれているが為に必死になってもがいているとも思えます。
ただ、今現状を思うに中国は日本がかつて誤った間違いに気付くかどうかというところもポイントの一つなのかもしれません。
それは日本はかつて海軍国家でなければならないのに大陸国家思想を展開してしまった、そして緑川だむさんのおっしゃった両論共存の可能性を模索して失敗した、というところです。
彼等は今その逆を展開しようとしていると言えるのかもしれません、もちろんあくまで仮説ですので検証する必要性はあります。
経済的な視点から見ると少なくとも言える事は方法論は二つあって、拒絶か依存関係の深化という相反する様で実は日本の実益を導く上では大差がないという選択肢が存在しているということでしょう。
もっとも、その二つのどちらかを選ぶにしても、政策を操作する人間即ち通産官僚と政治家の腕次第ということになります。
もう一つ可能性として指摘するのは、中国が「共産党を中心にした北京政府」と「上海・香港を中心にした沿岸部工業地帯」に分裂する可能性があると言うことですな。
前者とはまったく共有する価値観はないが、後者の方はある意味台湾などと同様の「アジア先進諸国」の一角となるかもしれないということです。工業地帯が海上交通路に依存している以上、この国の海洋戦略は日本と同様に沿岸警備+米海軍の補完戦力という方向性になる。もっと言えば、台湾との政治的統合の可能性も否定できません。
もっとも、この「上海共和国」が生まれるまでの内戦で、そもそも今の沿岸部工業力を残すことが出来るのかも疑問があるのですが。
前者とはまったく共有する価値観はないが、後者の方はある意味台湾などと同様の「アジア先進諸国」の一角となるかもしれないということです。工業地帯が海上交通路に依存している以上、この国の海洋戦略は日本と同様に沿岸警備+米海軍の補完戦力という方向性になる。もっと言えば、台湾との政治的統合の可能性も否定できません。
もっとも、この「上海共和国」が生まれるまでの内戦で、そもそも今の沿岸部工業力を残すことが出来るのかも疑問があるのですが。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
10年先の国家戦略 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
10年先の国家戦略のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6475人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19252人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人