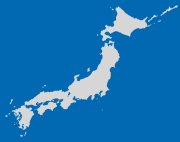コミュニティーの管理人ながら、忙しくて、忙しくて、トピを立てている暇もありません。(笑)
まあ何か書かねばならないと思っているのですが、10年先のお話として、その頃までにもし、中国が深刻な不況に突入してなかったり、分裂していなかったり、内戦していなかったりした場合、今のペースでの原油の輸入拡大をやられたら、とてもじゃないけど、世界中の石油を集めた所で、アメリカ・日本・中国のすべての必要分を賄うことは出来ません。
また、仮に、増産に次ぐ増産で何とか対応が出来たとしても、もし何らかの事故なり、大型産油国での内戦勃発なりが始まった場合、アメリカや中国のように、そもそも自国の領土内で、一定量の油田を持っている訳じゃない、自前の油田が全くと言っていいほど無い日本は、一番影響を受ける可能性があります。
そこで、10年先を見越して、本当に自前のエネルギー確保の為に、何をしたら良いのかを考えてみたいと思います。
ただし、関連する分野が、「原油」だけでなく、石油や石炭を含む化石燃料系や、
原子力
核融合
自然エネルギー
省エネルギー
と多岐に渡りますので、一つづつ取り上げて行きたいと思います。
まずは、「原油」についてですが、産地が中東方面に集中している以上、どうやってもあの地域まで出かけて行って、日本の権益が優先される工区を確保する必要があるのは明白です。
その点から言えば、今のイラクに対する自衛隊の人道援助や、ODAの集中投入によるイラク暫定政府への貸しを作る行為は、はっきり言って、やり方としてはまだまだ「甘い」ものがありますが、とりあえずは是としたいと思います。
原油価格そのものはスポット価格や先物で値段が決まってしまう以上、あまり手を打てる余地は少ないものの、何とか日本企業が独自で原油を手配出きるようにしてやる仕組みを日本政府は考えてやらなければいけないだろうと思います。
その具体的な仕組みにですが、自分は中東地域に限って、日本製の武器輸出を認める。というのが一番相手に対して効果のある方法ではないか?と考えております。
日本がODAの他に、途上国や中東諸国に対して、ロクな影響力を発揮し得ない元凶は、まさに日本の武器輸出禁止の国会決議にあると思うのですが、ご意見・ご質問があれば、何かご発言をお願いしたいと存じます。
まあ何か書かねばならないと思っているのですが、10年先のお話として、その頃までにもし、中国が深刻な不況に突入してなかったり、分裂していなかったり、内戦していなかったりした場合、今のペースでの原油の輸入拡大をやられたら、とてもじゃないけど、世界中の石油を集めた所で、アメリカ・日本・中国のすべての必要分を賄うことは出来ません。
また、仮に、増産に次ぐ増産で何とか対応が出来たとしても、もし何らかの事故なり、大型産油国での内戦勃発なりが始まった場合、アメリカや中国のように、そもそも自国の領土内で、一定量の油田を持っている訳じゃない、自前の油田が全くと言っていいほど無い日本は、一番影響を受ける可能性があります。
そこで、10年先を見越して、本当に自前のエネルギー確保の為に、何をしたら良いのかを考えてみたいと思います。
ただし、関連する分野が、「原油」だけでなく、石油や石炭を含む化石燃料系や、
原子力
核融合
自然エネルギー
省エネルギー
と多岐に渡りますので、一つづつ取り上げて行きたいと思います。
まずは、「原油」についてですが、産地が中東方面に集中している以上、どうやってもあの地域まで出かけて行って、日本の権益が優先される工区を確保する必要があるのは明白です。
その点から言えば、今のイラクに対する自衛隊の人道援助や、ODAの集中投入によるイラク暫定政府への貸しを作る行為は、はっきり言って、やり方としてはまだまだ「甘い」ものがありますが、とりあえずは是としたいと思います。
原油価格そのものはスポット価格や先物で値段が決まってしまう以上、あまり手を打てる余地は少ないものの、何とか日本企業が独自で原油を手配出きるようにしてやる仕組みを日本政府は考えてやらなければいけないだろうと思います。
その具体的な仕組みにですが、自分は中東地域に限って、日本製の武器輸出を認める。というのが一番相手に対して効果のある方法ではないか?と考えております。
日本がODAの他に、途上国や中東諸国に対して、ロクな影響力を発揮し得ない元凶は、まさに日本の武器輸出禁止の国会決議にあると思うのですが、ご意見・ご質問があれば、何かご発言をお願いしたいと存じます。
|
|
|
|
コメント(12)
>3tako3 さん
コメントありがとうございます。
さて、
>その内、アメリカの下請け工場に成り下がる事も有り得ます。
について、現在でもパソコンにおいては、マイクロソフトの「窓」ソフトと、インテルにCPUを押さえられてしまっている為、日本も含めて世界のバソコンメーカーはアメリカの下請けになってしまっているようなものでしょうね。
ただ、日本においても、CDやDVDにおける読み取り装置の心臓部=ピックアップレンズや、VTRにおけるヘッドの独占特許がありますので、中国や韓国で、いくらCDプレーヤーや、DVDレコーダーを作られようと、日本からの基幹部品の提供や、VTRの特許使用料を支払わない限り、商品になりませんので、アメリカと同じ立場を作り出せている企業が多いのも事実です。
武器の面に関しては、巡航・弾道の両ミサイルの推進器部分、ジェットエンジンの出力性能や、イージス艦搭載のフェイズドアンドアレイレーダーにおける対象飛行物体の電波特性、潜水艦のソナーにおける各種船舶や、世界各国の潜水艦の音紋特性などは、米軍しか基礎データを持っていないので、アメリカの下請けに甘んじるのは仕方の無いことながら、それよりお手軽な武器(たとえば短距離誘導弾や、水雷・地雷・重砲・戦車搭載の測敵装置)などは、日本のものでも十分な国際競争力を発揮出来ると思います。
弾薬については、アメリカが大量生産する安さに対して、日本全国にわずか1社しか残っていない職人作業で生産している弾では、とてもじゃないけど値段でかなうはずもありませんが、消耗品以外の分野で競争が出来るのであれば、是非チャレンジするべきだろうと思います。
武器の部分に手を出さないのは、「世間体」という面では確かに良い点があるものの、
反面、世界の中での国家安全保障という観点に立てば、生きるか死ぬかの瀬戸際の時であっても、頼んでもお金しかくれない国に対して、いったいどこまでの「信」を置いてもらえるのか?
中東戦争において、イスラエルが負けそうになった時、アメリカの戦車の現物援助がなければ、イスラエルという国は今地上に存在していませんし、
それより前の欧州大陸での大戦の時も、ドイツの無制限潜水艦作戦の時に、武器貸与法でアメリカから中古の駆逐艦の供与が無ければイギリスは間違いなく降伏していました。
中東においてのイスラム国家同士のイラン・イラク戦争においても、ソビエト製の武器で大挙して攻めて来るイランに対して、アメリカはイランの大使館員人質事件がありましたから、武器の援助はしなかったので、この時、もし、フランスやドイツや、中国からの武器購入が成功していなければ、イランはネブカドネザル大王の再来を自称するフセイン大統領の統治する一地域になっていました。
日本はイザという時に何の頼りにもならない。と、世界の紛争を抱える途上国にそう考えさせる元凶が、日本は武器を売らない(売ってもくれない)ということがあるのではないでしょうか?
国連加盟の独立国は世界に190カ国以上存在するものの、天下泰平で、毎日TVで、一日のほとんどの時間を、お笑い番組を流していられるほど平和な国は、実は数えるほどしかない。という冷徹な現実を、もっと受け入れる必用があると思います。
原子力と核融合の研究については、日本こそ、その技術を必要としている国は無いので、マスコミを含めて、地元住民とは全く何の関係も無い、単なるイデオロギーがらみの赤い旗を振っている反対派連中に対する封じ込めを、しっかりと推進するべきだと思います。
コメントありがとうございます。
さて、
>その内、アメリカの下請け工場に成り下がる事も有り得ます。
について、現在でもパソコンにおいては、マイクロソフトの「窓」ソフトと、インテルにCPUを押さえられてしまっている為、日本も含めて世界のバソコンメーカーはアメリカの下請けになってしまっているようなものでしょうね。
ただ、日本においても、CDやDVDにおける読み取り装置の心臓部=ピックアップレンズや、VTRにおけるヘッドの独占特許がありますので、中国や韓国で、いくらCDプレーヤーや、DVDレコーダーを作られようと、日本からの基幹部品の提供や、VTRの特許使用料を支払わない限り、商品になりませんので、アメリカと同じ立場を作り出せている企業が多いのも事実です。
武器の面に関しては、巡航・弾道の両ミサイルの推進器部分、ジェットエンジンの出力性能や、イージス艦搭載のフェイズドアンドアレイレーダーにおける対象飛行物体の電波特性、潜水艦のソナーにおける各種船舶や、世界各国の潜水艦の音紋特性などは、米軍しか基礎データを持っていないので、アメリカの下請けに甘んじるのは仕方の無いことながら、それよりお手軽な武器(たとえば短距離誘導弾や、水雷・地雷・重砲・戦車搭載の測敵装置)などは、日本のものでも十分な国際競争力を発揮出来ると思います。
弾薬については、アメリカが大量生産する安さに対して、日本全国にわずか1社しか残っていない職人作業で生産している弾では、とてもじゃないけど値段でかなうはずもありませんが、消耗品以外の分野で競争が出来るのであれば、是非チャレンジするべきだろうと思います。
武器の部分に手を出さないのは、「世間体」という面では確かに良い点があるものの、
反面、世界の中での国家安全保障という観点に立てば、生きるか死ぬかの瀬戸際の時であっても、頼んでもお金しかくれない国に対して、いったいどこまでの「信」を置いてもらえるのか?
中東戦争において、イスラエルが負けそうになった時、アメリカの戦車の現物援助がなければ、イスラエルという国は今地上に存在していませんし、
それより前の欧州大陸での大戦の時も、ドイツの無制限潜水艦作戦の時に、武器貸与法でアメリカから中古の駆逐艦の供与が無ければイギリスは間違いなく降伏していました。
中東においてのイスラム国家同士のイラン・イラク戦争においても、ソビエト製の武器で大挙して攻めて来るイランに対して、アメリカはイランの大使館員人質事件がありましたから、武器の援助はしなかったので、この時、もし、フランスやドイツや、中国からの武器購入が成功していなければ、イランはネブカドネザル大王の再来を自称するフセイン大統領の統治する一地域になっていました。
日本はイザという時に何の頼りにもならない。と、世界の紛争を抱える途上国にそう考えさせる元凶が、日本は武器を売らない(売ってもくれない)ということがあるのではないでしょうか?
国連加盟の独立国は世界に190カ国以上存在するものの、天下泰平で、毎日TVで、一日のほとんどの時間を、お笑い番組を流していられるほど平和な国は、実は数えるほどしかない。という冷徹な現実を、もっと受け入れる必用があると思います。
原子力と核融合の研究については、日本こそ、その技術を必要としている国は無いので、マスコミを含めて、地元住民とは全く何の関係も無い、単なるイデオロギーがらみの赤い旗を振っている反対派連中に対する封じ込めを、しっかりと推進するべきだと思います。
>しかし、武装しても近隣諸国との緊張が高まるだけで、国民の安心にはつながらないと思います。
世の中には、拳法9条があったから、日本は戦争にならなかった?
などと、地政学の基本や、軍事戦略の常識や、相手国の弱体な国力・軍事力、同盟関係の存在を一切かえりみることなく、非武装を説く政党も確かに存在しています。
武装をほとんどかえりみず、お経と、仏様及び、ブッダの生まれ変わりの尊いご僧侶のお慈悲にすがったチベットは、隣国の中国に攻められ、たった数日間で植民地化しました。
ハワイの王朝は、大した武装はしていませんでしたが、それでもアメリカに征服されて植民地となりました。
当時ハワイの王様は、太平洋を隔てた隣国日本に支援を求めましたが、日本はその要請を蹴ってしまいました。
世界の常識として、自ら武装・自衛する者(国家)に対しては、助ける味方が後から出てくる可能性があるものの、
自ら武装・自衛を放棄してしまっている者(国家)に対しては、たとえ味方をしてみても、得る所はほとんど無いし、防衛の素地が無い中での支援・テコ入れは、はっきり言って手間が掛かって大変なだけで、得るものも少ないので、それならば、攻める方と組んで、一緒になって弱い方を侵略して滅ぼした方が、国益を考えれば、貴重な兵を損することもなく、得るものの方が大きい。という判断をされます。
かつてヨーロッパにおけるイギリスの外交の基本は、バランス・オブ・パワー(勢力均衡)でしたが、当時の東欧地域の小国に対しては、バランスを取ってテコ入れするよりは、さっさと潰してしまって、周辺のより大きな国に吸収させた方が、外交の場におけるプレイヤーを減らして、状況を単純化出来る。という理由で、助けの手を差し伸べませんでした。
これが国際政治の現実です。
イタチごっこに終わりは無い。との言葉は良く聞きますが、イタチごっこで、勢力を均衡させたからこそ、うかつな戦争を防止し、長期間に渡る にらみ合いの平和 を享受出来ました。
ヨーロッパでの戦争に関しては、その発生原因をさかのぼって見れば、軍備(常備軍)のイタチごっこを中断して、対抗勢力の一方が、これで間違いなく勝てる。と確信して戦端を開いた結果ではなかったでしょうか?
歴史上、長期の平和の維持は、イギリス式のバランス・オブ・パワーの状態を作り出すか、
さもなければ、ローマ帝国のように、強大な覇権国家が、その圧倒的な軍事力で、周囲の国々を押さえつけてしまった期間にのみ存在しています。
第二次大戦以来、アメリカの単独覇権が弱まりつつある今、歴史の上からも、平和を望むのであれば、勢力均衡方式に戻すべきだと自分は考えております。
その為の必用な手段として、日本もその勢力均衡の状態を作り出す手段を持つこと。すなわち国産の競争力のある武器を輸出出来るようになること。が有効な手段ではないか?と提案させて頂いております。
「憲法残って国滅ぶ」という事態だけは絶対に避けねばなりません。
>営利が目的ですから、国産のミサイルで国民が死ぬ事も想定しなければなりません。
>まずは、徴兵制から始まるのでしょうね。
日本が輸出したミサイルで日本人が死ぬ場合がありえるのは否定しません。そういう場合も多々出るでしょう。
アメリカ・フランス・ドイツ・イギリス・イタリア・イスラエル・ロシア・中国・南アフリカも同じように自国で生産した武器・弾薬・ミサイルで、自国が派遣した兵士が死ぬというケースを経験しています。
あえて暴論を申し上げると、
自国の生産した武器で、他国領内で自国民が撃ち殺されるのと、
自国が生産した自動車で他国領内で自国民がひき殺されるのと、
との程度の差を付けて死亡損害という同じ事件を評価するのか?
この判断でしょうね。
なお、現代の戦争(領空防御・領海防衛)においては、徴兵制は無用でしょう。無用と言うより、今の戦争は専門技術の塊のようなものですから、頭数だけ兵隊をそろえてみても、ほとんど役に立ちません。
ですから、憲法改正=徴兵制の復活 はまずありえないのではないでしょうか?
兵が沢山必要な状況は、日本国内に敵兵が多数上陸してしまい、そいつらを排除する場合に限られます。
ですから、敵の連中。日本の仮想敵国と言えば、中国や朝鮮半島の連中ですが、あいつらを日本の領空・領海に好き勝手に近づけさせない為にも、それを可能にする武装が最低限必要になるのです。
この日本と同じ状況(実際にはもっと深刻な状況)が発生しているのが中東であり、だからこそ、そのニーズを的確に満たして上げられる輸出品である軽火器や武器を輸出することにより、日本が持ち得ない石油資源を確実に引き換えに渡してもらう方法を取るべきではないか?と思っております。
>毎度毎度、否定的な意見で申し訳ございません。
同じ意見ばかりが並ぶのであれば、進歩はありません。
赤い旗を振っている連中があこがれていた、旧ソビエト連邦や、北朝鮮や、中国では、反対意見を言う輩は、粛清されるか、投獄されるか、精神病扱いで隔離されたそうですので、
そういう社会にならない為にも多様な意見は尊重しつつ、最後は民主的な多数決には従ってもらう「良識」だけは大切にしてもらいたいものだと思っております。
以上
世の中には、拳法9条があったから、日本は戦争にならなかった?
などと、地政学の基本や、軍事戦略の常識や、相手国の弱体な国力・軍事力、同盟関係の存在を一切かえりみることなく、非武装を説く政党も確かに存在しています。
武装をほとんどかえりみず、お経と、仏様及び、ブッダの生まれ変わりの尊いご僧侶のお慈悲にすがったチベットは、隣国の中国に攻められ、たった数日間で植民地化しました。
ハワイの王朝は、大した武装はしていませんでしたが、それでもアメリカに征服されて植民地となりました。
当時ハワイの王様は、太平洋を隔てた隣国日本に支援を求めましたが、日本はその要請を蹴ってしまいました。
世界の常識として、自ら武装・自衛する者(国家)に対しては、助ける味方が後から出てくる可能性があるものの、
自ら武装・自衛を放棄してしまっている者(国家)に対しては、たとえ味方をしてみても、得る所はほとんど無いし、防衛の素地が無い中での支援・テコ入れは、はっきり言って手間が掛かって大変なだけで、得るものも少ないので、それならば、攻める方と組んで、一緒になって弱い方を侵略して滅ぼした方が、国益を考えれば、貴重な兵を損することもなく、得るものの方が大きい。という判断をされます。
かつてヨーロッパにおけるイギリスの外交の基本は、バランス・オブ・パワー(勢力均衡)でしたが、当時の東欧地域の小国に対しては、バランスを取ってテコ入れするよりは、さっさと潰してしまって、周辺のより大きな国に吸収させた方が、外交の場におけるプレイヤーを減らして、状況を単純化出来る。という理由で、助けの手を差し伸べませんでした。
これが国際政治の現実です。
イタチごっこに終わりは無い。との言葉は良く聞きますが、イタチごっこで、勢力を均衡させたからこそ、うかつな戦争を防止し、長期間に渡る にらみ合いの平和 を享受出来ました。
ヨーロッパでの戦争に関しては、その発生原因をさかのぼって見れば、軍備(常備軍)のイタチごっこを中断して、対抗勢力の一方が、これで間違いなく勝てる。と確信して戦端を開いた結果ではなかったでしょうか?
歴史上、長期の平和の維持は、イギリス式のバランス・オブ・パワーの状態を作り出すか、
さもなければ、ローマ帝国のように、強大な覇権国家が、その圧倒的な軍事力で、周囲の国々を押さえつけてしまった期間にのみ存在しています。
第二次大戦以来、アメリカの単独覇権が弱まりつつある今、歴史の上からも、平和を望むのであれば、勢力均衡方式に戻すべきだと自分は考えております。
その為の必用な手段として、日本もその勢力均衡の状態を作り出す手段を持つこと。すなわち国産の競争力のある武器を輸出出来るようになること。が有効な手段ではないか?と提案させて頂いております。
「憲法残って国滅ぶ」という事態だけは絶対に避けねばなりません。
>営利が目的ですから、国産のミサイルで国民が死ぬ事も想定しなければなりません。
>まずは、徴兵制から始まるのでしょうね。
日本が輸出したミサイルで日本人が死ぬ場合がありえるのは否定しません。そういう場合も多々出るでしょう。
アメリカ・フランス・ドイツ・イギリス・イタリア・イスラエル・ロシア・中国・南アフリカも同じように自国で生産した武器・弾薬・ミサイルで、自国が派遣した兵士が死ぬというケースを経験しています。
あえて暴論を申し上げると、
自国の生産した武器で、他国領内で自国民が撃ち殺されるのと、
自国が生産した自動車で他国領内で自国民がひき殺されるのと、
との程度の差を付けて死亡損害という同じ事件を評価するのか?
この判断でしょうね。
なお、現代の戦争(領空防御・領海防衛)においては、徴兵制は無用でしょう。無用と言うより、今の戦争は専門技術の塊のようなものですから、頭数だけ兵隊をそろえてみても、ほとんど役に立ちません。
ですから、憲法改正=徴兵制の復活 はまずありえないのではないでしょうか?
兵が沢山必要な状況は、日本国内に敵兵が多数上陸してしまい、そいつらを排除する場合に限られます。
ですから、敵の連中。日本の仮想敵国と言えば、中国や朝鮮半島の連中ですが、あいつらを日本の領空・領海に好き勝手に近づけさせない為にも、それを可能にする武装が最低限必要になるのです。
この日本と同じ状況(実際にはもっと深刻な状況)が発生しているのが中東であり、だからこそ、そのニーズを的確に満たして上げられる輸出品である軽火器や武器を輸出することにより、日本が持ち得ない石油資源を確実に引き換えに渡してもらう方法を取るべきではないか?と思っております。
>毎度毎度、否定的な意見で申し訳ございません。
同じ意見ばかりが並ぶのであれば、進歩はありません。
赤い旗を振っている連中があこがれていた、旧ソビエト連邦や、北朝鮮や、中国では、反対意見を言う輩は、粛清されるか、投獄されるか、精神病扱いで隔離されたそうですので、
そういう社会にならない為にも多様な意見は尊重しつつ、最後は民主的な多数決には従ってもらう「良識」だけは大切にしてもらいたいものだと思っております。
以上
>理想は、高く。現実は、・・・
そう。
自分が最重要視しているのは、理想ではありません。
現実問題としての日本の生き残りと、繁栄です。
日教組の連中が支配している小学校の運動会のように、
おててつないで、みんなで走って、みんな一緒の一等賞。という「まやかし」は、現実世界の日本国民を不幸にするだけのお話だと思っております。
>統治者に恵まれれば、困らないです。
その恵まれた統治者に運良く当たる可能性は、3tako3 さんの推定ではどのくらい(何%程度)と判断されるのでしょうか?
有史以来、大国に支配された地域や異民族は多々ありました。
・ローマ帝国と争って地中海世界の覇権を目指したカルタゴはどうなったのでしょうか?
・ヨーロッパ大陸にそれまで自分達の方からは一度も介入したこともないのに、スペイン軍に上陸された中米のインカ帝国は?
・チンギスハーンのモンゴル軍による統治を拒否したホラズム王国は?
つい最近の1990年、イラクにいきなり攻め込まれたクェートはどうなりましたか?
何の略奪もされずに、食料や不足物資をイラクのフセイン大統領から恵んでもらったのでしょうか?
過去の数千例の戦争を分析して、「統治者に恵まれた例」が、統治者に恵まれなかった例よりもはるかに多いものであるならば、3tako3 さんの お説 にも説得力が出るように思えるのですが・・・・・
>−−−多数決で、ナチスのヒトラーは生まれました・・・
民主的に成立した政権が、きわめて非民主的な政治をしたり、
非民主的に成立した政権が、きわめて民主的な政治を行う例は、長い歴史の中では当然あります。
ただ、さきほどの「統治者に恵まれれば、困らない」確率と同様、民主的に成立した政権が民主的な政治をする確立が高ければ、ヒットラーの存在は例外的事象としてカウントするべきでしょう。
そう言い切れるのは、3tako3 さんが、「国敗れて山河あり」と書いたように、人間はその世代1代のみで終わってしまう訳ではないからです。
過去の日本人の存在を認識するのと同じように、未来の日本人の存在も否定しないのであれば、工場の生産ラインと同様、毎日同じ作業をしていたとしても、例外的な不良品が出る事があるのと同様、不良品の発生率を許容した上で、製造ラインのシステムは守るべきであろうと存じます。
まあ、そういうシステムを持たない共産中国が、何の言いがかりやでっち上げを外交カードにしてきたとしても、そういうことにいちいち反応するだけ無駄なことだと思っております。
今までの日本政府は、馬鹿丁寧に対応していましたが、そろそろ無視しても何らの不都合はなくなってきたと思います。
そう。
自分が最重要視しているのは、理想ではありません。
現実問題としての日本の生き残りと、繁栄です。
日教組の連中が支配している小学校の運動会のように、
おててつないで、みんなで走って、みんな一緒の一等賞。という「まやかし」は、現実世界の日本国民を不幸にするだけのお話だと思っております。
>統治者に恵まれれば、困らないです。
その恵まれた統治者に運良く当たる可能性は、3tako3 さんの推定ではどのくらい(何%程度)と判断されるのでしょうか?
有史以来、大国に支配された地域や異民族は多々ありました。
・ローマ帝国と争って地中海世界の覇権を目指したカルタゴはどうなったのでしょうか?
・ヨーロッパ大陸にそれまで自分達の方からは一度も介入したこともないのに、スペイン軍に上陸された中米のインカ帝国は?
・チンギスハーンのモンゴル軍による統治を拒否したホラズム王国は?
つい最近の1990年、イラクにいきなり攻め込まれたクェートはどうなりましたか?
何の略奪もされずに、食料や不足物資をイラクのフセイン大統領から恵んでもらったのでしょうか?
過去の数千例の戦争を分析して、「統治者に恵まれた例」が、統治者に恵まれなかった例よりもはるかに多いものであるならば、3tako3 さんの お説 にも説得力が出るように思えるのですが・・・・・
>−−−多数決で、ナチスのヒトラーは生まれました・・・
民主的に成立した政権が、きわめて非民主的な政治をしたり、
非民主的に成立した政権が、きわめて民主的な政治を行う例は、長い歴史の中では当然あります。
ただ、さきほどの「統治者に恵まれれば、困らない」確率と同様、民主的に成立した政権が民主的な政治をする確立が高ければ、ヒットラーの存在は例外的事象としてカウントするべきでしょう。
そう言い切れるのは、3tako3 さんが、「国敗れて山河あり」と書いたように、人間はその世代1代のみで終わってしまう訳ではないからです。
過去の日本人の存在を認識するのと同じように、未来の日本人の存在も否定しないのであれば、工場の生産ラインと同様、毎日同じ作業をしていたとしても、例外的な不良品が出る事があるのと同様、不良品の発生率を許容した上で、製造ラインのシステムは守るべきであろうと存じます。
まあ、そういうシステムを持たない共産中国が、何の言いがかりやでっち上げを外交カードにしてきたとしても、そういうことにいちいち反応するだけ無駄なことだと思っております。
今までの日本政府は、馬鹿丁寧に対応していましたが、そろそろ無視しても何らの不都合はなくなってきたと思います。
初めまして、よろしくお願い致します。
まずお尋ねの件に付きましてご回答させて頂きます。
「国益」とはなんぞや?とのお尋ねですね。
正直、大変範疇が広い概念で、一言では言い表せないものの、自分個人としては、日本国民が「今の世界のトップレベル経済状態を維持しつつ、将来に希望の持てる暮らしが続けられる事」だと思っております。
ですから、お尋ねの「国益」の中には、何が含まれるのか?という点についても、日本の独立を維持し続ける為の軍備を含む安全保障も含まれますし、経済的な自国権益の擁護や、国民のまっとうな暮らしに関係する各種の規制や、政治的に皇室の存在による国家の二重統治体制の維持、及び政治家のリーダーシップも含まれます。
短期的には、今の日本が持つ国富を守ることであり、
長期的には、自由貿易体制を維持しつつ、その中にあって、日本の国際競争力を維持することです。
次に「パワー」に関してのご質問ですが、
これも定義する上での概念が広い問題かと存じます。
一般的には、軍事力を指す場合が多いのでしょうが、
日本の場合は、軍事力以上の経済力や、
伝統的な言葉の後ろに「道」の付くお稽古ごとに加え、
最近ではサブカルチャーに代表されるような日本で独自に発展した音楽・映像文化もあるでしょう。
パワーは、国内向けに使うものと対外向け(外国向け)に使うものがありますが、対外向けでの定義となれば、その影響力を数値化するのが難しい雑多な文化の力よりは、
歴史的に重要視されて来ており、お互いが「数」で計れる軍事力と、経済力。ということになるのだと思います。
自分の認識は以上ですが、
せっかくですから参考までに、matou さん の「ご定義」もご披露頂ければ幸いに存じます。
まずお尋ねの件に付きましてご回答させて頂きます。
「国益」とはなんぞや?とのお尋ねですね。
正直、大変範疇が広い概念で、一言では言い表せないものの、自分個人としては、日本国民が「今の世界のトップレベル経済状態を維持しつつ、将来に希望の持てる暮らしが続けられる事」だと思っております。
ですから、お尋ねの「国益」の中には、何が含まれるのか?という点についても、日本の独立を維持し続ける為の軍備を含む安全保障も含まれますし、経済的な自国権益の擁護や、国民のまっとうな暮らしに関係する各種の規制や、政治的に皇室の存在による国家の二重統治体制の維持、及び政治家のリーダーシップも含まれます。
短期的には、今の日本が持つ国富を守ることであり、
長期的には、自由貿易体制を維持しつつ、その中にあって、日本の国際競争力を維持することです。
次に「パワー」に関してのご質問ですが、
これも定義する上での概念が広い問題かと存じます。
一般的には、軍事力を指す場合が多いのでしょうが、
日本の場合は、軍事力以上の経済力や、
伝統的な言葉の後ろに「道」の付くお稽古ごとに加え、
最近ではサブカルチャーに代表されるような日本で独自に発展した音楽・映像文化もあるでしょう。
パワーは、国内向けに使うものと対外向け(外国向け)に使うものがありますが、対外向けでの定義となれば、その影響力を数値化するのが難しい雑多な文化の力よりは、
歴史的に重要視されて来ており、お互いが「数」で計れる軍事力と、経済力。ということになるのだと思います。
自分の認識は以上ですが、
せっかくですから参考までに、matou さん の「ご定義」もご披露頂ければ幸いに存じます。
>matou さん の「ご定義」もご披露頂ければ幸いに存じます。
私は、この「定義」ということに関して、それは時代によって変るものであると考えています。またそれは国や地域によっても変ってきてしまうでしょう。また、それを考える人によってももちろん変ってくるのだと思います。
例えば、政府が考える「国益」と、国民が考える「国益」が違う場合があります。さらには、それは長期的に考えたときと、短期的に考えたときでも、違ってくるのです。
明治期の国民が考えていた「国益」と、現代の日本国民が多く考えているところの「国益」も、おそらく違うものでしょう。であれば、とりわけ現代の日本国民や政府が、どのように「国益」を考えているのか、について、過去と比較したりしながら探求しなければならないと思っています。それが、今後の国際政治の流れを予測するに当たって、不可欠になるだろうと思います。
もう一つは、他国の国々が自らの「国益」についてどう考えているのかということでしょう。とりわけ政府は何を目的として行動しているのか、ということが重要です。アメリカの国防省と国務省の意見が食い違うことはしばしばで、それについても慎重を期すべきだと思います。自国の国益について、アメリカはどう考えており、将来的にはどう考えていきそうなのか。
これは同じで、日本でも農林水産省と経済産業省では、自国の「国益」の考え方が違ってくるので、外交もどちらに転ぶのか、大変分析がやっかいになってきます。あるいは、外務省は、経団連はどう考えているのか、といった問いの複雑さです。
外務省内部でも意見の食い違いがあります。有名なのは両大戦間に、吉田茂と重光葵の対中関係に関する自国の「国益」ということについて、対照的な考えをしていたということです。さらに、「国益」については同じことを考えていても、それを達成する手段について何が有効なものになるのか、ということについても、大きく意見の食い違いが出てくるでしょう。
だから、一般的に「国家はこれを求めて行動する」とは言い難いところがあると思います。どうなのでしょうか。エルトリュームさんは、「こうあるべき国益」としての「国益」について書かれたように思いました。「現在日本国民が考えている国益」「現在日本政府が考えている国益」「現在アメリカが考えている国益」「現在中国が考えている国益」について、それぞれ論じていただけないでしょうか。
私としては、今私が思っている「そうであるべき国益」とは、「国民が充実した生を送ることができること」であると思っています。何も、GNPを増加させればいいのではなく、それは単に上記の目標のための手段になるのだろうと思います。失業率が高くなり、上記の目標がおびやかされるようなときは、これは「国益」が危ぶまれているのだと思っています。
私は、この「定義」ということに関して、それは時代によって変るものであると考えています。またそれは国や地域によっても変ってきてしまうでしょう。また、それを考える人によってももちろん変ってくるのだと思います。
例えば、政府が考える「国益」と、国民が考える「国益」が違う場合があります。さらには、それは長期的に考えたときと、短期的に考えたときでも、違ってくるのです。
明治期の国民が考えていた「国益」と、現代の日本国民が多く考えているところの「国益」も、おそらく違うものでしょう。であれば、とりわけ現代の日本国民や政府が、どのように「国益」を考えているのか、について、過去と比較したりしながら探求しなければならないと思っています。それが、今後の国際政治の流れを予測するに当たって、不可欠になるだろうと思います。
もう一つは、他国の国々が自らの「国益」についてどう考えているのかということでしょう。とりわけ政府は何を目的として行動しているのか、ということが重要です。アメリカの国防省と国務省の意見が食い違うことはしばしばで、それについても慎重を期すべきだと思います。自国の国益について、アメリカはどう考えており、将来的にはどう考えていきそうなのか。
これは同じで、日本でも農林水産省と経済産業省では、自国の「国益」の考え方が違ってくるので、外交もどちらに転ぶのか、大変分析がやっかいになってきます。あるいは、外務省は、経団連はどう考えているのか、といった問いの複雑さです。
外務省内部でも意見の食い違いがあります。有名なのは両大戦間に、吉田茂と重光葵の対中関係に関する自国の「国益」ということについて、対照的な考えをしていたということです。さらに、「国益」については同じことを考えていても、それを達成する手段について何が有効なものになるのか、ということについても、大きく意見の食い違いが出てくるでしょう。
だから、一般的に「国家はこれを求めて行動する」とは言い難いところがあると思います。どうなのでしょうか。エルトリュームさんは、「こうあるべき国益」としての「国益」について書かれたように思いました。「現在日本国民が考えている国益」「現在日本政府が考えている国益」「現在アメリカが考えている国益」「現在中国が考えている国益」について、それぞれ論じていただけないでしょうか。
私としては、今私が思っている「そうであるべき国益」とは、「国民が充実した生を送ることができること」であると思っています。何も、GNPを増加させればいいのではなく、それは単に上記の目標のための手段になるのだろうと思います。失業率が高くなり、上記の目標がおびやかされるようなときは、これは「国益」が危ぶまれているのだと思っています。
>matou さん
ものすごく忙しくて、コメントが遅れて申し訳ございませんでした。
まず整理すると、「国益」に対する定義に関して
エルトリュームの定義は
{日本国民が「今の世界のトップレベル経済状態を維持しつつ、将来に希望の持てる暮らしが続けられる事}
であるのに対して
matou さんの ご定義 は
{「国民が充実した生を送ることができること」}
ということですね。
一見すると大した違いは見られないようですが、
自分の定義が、「未来」に対して志向しているのに比べて、
matou さんのご定義は、「今現在」の生を志向されていらっしゃるように見えました。
現在志向と未来志向 どちらを重視するべきなのか?これもその時々に生きている国民にとっては、意見の分かれる所であり、老い先短い年寄りであれば、現在の残された時間を大切にしたい。と思う人が多い一方、平均寿命までまだだいぶある若い人にとっては、より良い未来とか、子供がいる人にとっては、自分よりも子供の時代こそ重要と考える人が多くなるのではないか?と思っております。また個人の職業や、生活スタイルによっても違うものと思います。
さて、次にリクエストとして、
>「現在日本国民が考えている国益」
>「現在日本政府が考えている国益」
>「現在アメリカが考えている国益」
>「現在中国が考えている国益」について、それぞれ論じていただけないでしょうか。
とのこと。
話を前に戻すようで恐縮ですが、つい先ほど、「国民」にとっての国益=優先政策事項は世代や年齢、個人のライフスタイルによって異なる。と書いたばかりですので、「これこそ日本国民の望む国益」というものを一つに絞るのは難しいかと存じます。
しかしなから、「日本政府が考えている国益」であるならば、日本政府は、間接的な意思の表示ながら、とりあえず公平な選挙制度によって選ばれた政治家が国を代表している以上、今の政府の目指す政策が国益の追求である。と仮定してもよろしいかと思います。
この仮定を生かすのであれば、
アメリカも民主的な選挙制度で国の代表が選ばれている以上、過半数の賛同(信任)を通しての、今のアメリカ政府の推し進める政策こそが、アメリカの目指す国益と仮定してもよろしいのではないか?と思います。
ただし、中国については、歴史上、一度も国民からの選挙の洗礼を受けない連中が、政治家として国家の代表に居座っている以上、中国政府の政策が中国人の国益かどうかは疑問の残る所ではあります。
ただ、中国における世論調査というサンプル抽出を少しは信用するのであれば、今の自分たちが直接笑んだわけでもなんでもない共産政府を支持している国民が圧倒的に多いという現実は、中国人たちの民意に従った地域覇権と軍事的な勢力拡大を目指しているのは、中国国民の本音の要求であろうと推定致しております。
ものすごく忙しくて、コメントが遅れて申し訳ございませんでした。
まず整理すると、「国益」に対する定義に関して
エルトリュームの定義は
{日本国民が「今の世界のトップレベル経済状態を維持しつつ、将来に希望の持てる暮らしが続けられる事}
であるのに対して
matou さんの ご定義 は
{「国民が充実した生を送ることができること」}
ということですね。
一見すると大した違いは見られないようですが、
自分の定義が、「未来」に対して志向しているのに比べて、
matou さんのご定義は、「今現在」の生を志向されていらっしゃるように見えました。
現在志向と未来志向 どちらを重視するべきなのか?これもその時々に生きている国民にとっては、意見の分かれる所であり、老い先短い年寄りであれば、現在の残された時間を大切にしたい。と思う人が多い一方、平均寿命までまだだいぶある若い人にとっては、より良い未来とか、子供がいる人にとっては、自分よりも子供の時代こそ重要と考える人が多くなるのではないか?と思っております。また個人の職業や、生活スタイルによっても違うものと思います。
さて、次にリクエストとして、
>「現在日本国民が考えている国益」
>「現在日本政府が考えている国益」
>「現在アメリカが考えている国益」
>「現在中国が考えている国益」について、それぞれ論じていただけないでしょうか。
とのこと。
話を前に戻すようで恐縮ですが、つい先ほど、「国民」にとっての国益=優先政策事項は世代や年齢、個人のライフスタイルによって異なる。と書いたばかりですので、「これこそ日本国民の望む国益」というものを一つに絞るのは難しいかと存じます。
しかしなから、「日本政府が考えている国益」であるならば、日本政府は、間接的な意思の表示ながら、とりあえず公平な選挙制度によって選ばれた政治家が国を代表している以上、今の政府の目指す政策が国益の追求である。と仮定してもよろしいかと思います。
この仮定を生かすのであれば、
アメリカも民主的な選挙制度で国の代表が選ばれている以上、過半数の賛同(信任)を通しての、今のアメリカ政府の推し進める政策こそが、アメリカの目指す国益と仮定してもよろしいのではないか?と思います。
ただし、中国については、歴史上、一度も国民からの選挙の洗礼を受けない連中が、政治家として国家の代表に居座っている以上、中国政府の政策が中国人の国益かどうかは疑問の残る所ではあります。
ただ、中国における世論調査というサンプル抽出を少しは信用するのであれば、今の自分たちが直接笑んだわけでもなんでもない共産政府を支持している国民が圧倒的に多いという現実は、中国人たちの民意に従った地域覇権と軍事的な勢力拡大を目指しているのは、中国国民の本音の要求であろうと推定致しております。
「(日本)政府の目指す政策」
「アメリカ政府の推し進める政策」
「中国政府の政策」
がそれぞれ各国の国益である、ということですね。であれば、およそ次のような疑問が出てくると思います。つまり、「各国において、なぜ、そのような政策が打ち出されるに至ったのか」ということです。
各国が自らの政策を打ち出しているならば、各国はそれを手段として何らかの目的を達成しようとしているわけですから、その目的を把握することが必要でありましょう。
とりわけ中国において、その「地域覇権と軍事的な勢力拡大」ということによって、中国政府はどのような目的を達成しようとしているのでしょうか。エルトリュームさんはどうお考えですか?
「アメリカ政府の推し進める政策」
「中国政府の政策」
がそれぞれ各国の国益である、ということですね。であれば、およそ次のような疑問が出てくると思います。つまり、「各国において、なぜ、そのような政策が打ち出されるに至ったのか」ということです。
各国が自らの政策を打ち出しているならば、各国はそれを手段として何らかの目的を達成しようとしているわけですから、その目的を把握することが必要でありましょう。
とりわけ中国において、その「地域覇権と軍事的な勢力拡大」ということによって、中国政府はどのような目的を達成しようとしているのでしょうか。エルトリュームさんはどうお考えですか?
コメントありがとうございました。
さて、さらにご質問を頂いた部分について、
すなわち
「各国において、なぜ、そのような政策が打ち出されるに至ったのか」についてですが、
選挙という国民の多数意思の選択の結果選ばれた政権が追求する国益は、そもそも選挙期間中から公約に掲げていたものが大半であって、後からいきなり打ち出されたものはほとんどありません。
どれもこれも、以前から おおまかな方向性 だけは明示されていたものゆえ、それに沿った国益の追求(狭い意味での政府の政策の実行)がなされているのだと自分は考えております。
具体的には、アメリカの進める「テロとの戦い」についてだって、ちょっと資料を探せば、現ブッシュ大統領のお父さんの頃から、そういう方向性は明確に示されておりましたし、
日本の政治における郵政民営化を含む、
小さな政府を志向する方針についても、
憲法の改正も、
日本独自の戦力の保持も、
何も今の小泉政権になってから初めて言い出したものでは絶対にありません。
いずれも何十年もの昔から選挙公約とか、政策として掲げられていたものです。
選挙を通じて有権者が政治家を選んだ以上、当然背景にある昔からの政策の流れも含めての信認であるべきでしょう。
そういう意味では、今度の選挙で、旧社会党の残党連中が多数逃げ込んでいる「民主党」なんかに政権が移譲されなくて本当に良かったと思っております。
共産中国政府や反日韓国政府との「国家主権の共有」などという日本国の主権の放棄や、日本のエネルギー安全保障の根幹を為す原油国家備蓄分を、中国に自由に使ってもらうなどという日本国の死活的な財産を、中国の政府の無策の穴埋めの為に惜しげもなく注ぎ込むという売国行為を、堂々と選挙のマニフェストに謳っているような連中に政権が渡るようなことだけは絶対に避けなければならないと思っております。
次に matou さんご質問の
>とりわけ中国において、その「地域覇権と軍事的な勢力拡大」ということによって、中国政府はどのような目的を達成しようとしているのでしょうか
について
中国政府が望むのは、突き詰めれば歴史上の中華帝国の再興であり、
具体的には「華・夷 秩序」の再構築でしょう。
歴史上、中華だけが人の扱いを受けられるべき場所であり、その他は、東夷・西戎・北テキ・南蛮と、人間じゃない連中扱いをして、朝貢を復活させることでしょう。
ちなみに中国人の大半が、中国政府の歴史教育を通じて自分達こそ「中華の民」というプライドを持たされていますが、歴史上「中華」の世界で、本当に「人」たりえたのは、政府の役人だけ。で、他の国民は外国人のような「獣」ではないものの、単なる「奴隷」に過ぎないという現実はすっかり忘れられているようですけどね。(笑)
話が少しそれましたが、アジア地域において、中国だけが尋常ではないスピードで軍備を拡張しているのは、自国の防衛という面以外に、いずれはアメリカとの前面対決をするつもりでやっていることであり、そういう方針なり報告なりは、中国の国内向けの専門雑誌「解放軍報」なり、中国政府のシンクタンク「社会科学院」等の報告書でも過去何度も出てきます。
また中国政府要人の発言を丹念に追って行けば、軍の制服組の高官連中も、たびたびメディアに向けて公言しております。
ですから、この点は間違いないと自分は思っております。
また、こういう中国政府監修の出版物や、中国政府要人のコメント・軍の中枢連中からの発言に対して、賛同意見の表明はたびたび目にするものの、中国国内で反対意見や反論は一切確認出来ませんので、中国の国民もそういう考え方を支持していると分析するのが妥当と判断致しております。
なお、日本の外務省のように中国政府が口にする対外的に都合の悪い発言については、
無かったものにするとか
別な意見も存在している、とかを引き合いに出して、中国の真意をわざとねじまげようとする連中も存在していますが、
基本的に、中国のような巨大国家を日本人ややっていたような異心伝心で統治することは歴史上も不可能でした。
人口の巨大な国、又は国土の広い国は、インドも、アメリカも、ロシアも、カナダも、国が公表している文章によって、国民の意思の統一を計り、国家を一定の方向に向けて誘導する以外、コントロールする方法はありません。
従って、中国政府が国内向けに様々な文章で公表しているこどく、中国がアジアにおける地域覇権を目指して、海洋の未開の資源の独占を計り、いずれ台湾を支配下において、日本の海上輸送ルートを分断した上、将来的にアメリカと世界の覇権を賭けて戦う。という基本方針にはウソ偽りは無いと存じます。
さて、さらにご質問を頂いた部分について、
すなわち
「各国において、なぜ、そのような政策が打ち出されるに至ったのか」についてですが、
選挙という国民の多数意思の選択の結果選ばれた政権が追求する国益は、そもそも選挙期間中から公約に掲げていたものが大半であって、後からいきなり打ち出されたものはほとんどありません。
どれもこれも、以前から おおまかな方向性 だけは明示されていたものゆえ、それに沿った国益の追求(狭い意味での政府の政策の実行)がなされているのだと自分は考えております。
具体的には、アメリカの進める「テロとの戦い」についてだって、ちょっと資料を探せば、現ブッシュ大統領のお父さんの頃から、そういう方向性は明確に示されておりましたし、
日本の政治における郵政民営化を含む、
小さな政府を志向する方針についても、
憲法の改正も、
日本独自の戦力の保持も、
何も今の小泉政権になってから初めて言い出したものでは絶対にありません。
いずれも何十年もの昔から選挙公約とか、政策として掲げられていたものです。
選挙を通じて有権者が政治家を選んだ以上、当然背景にある昔からの政策の流れも含めての信認であるべきでしょう。
そういう意味では、今度の選挙で、旧社会党の残党連中が多数逃げ込んでいる「民主党」なんかに政権が移譲されなくて本当に良かったと思っております。
共産中国政府や反日韓国政府との「国家主権の共有」などという日本国の主権の放棄や、日本のエネルギー安全保障の根幹を為す原油国家備蓄分を、中国に自由に使ってもらうなどという日本国の死活的な財産を、中国の政府の無策の穴埋めの為に惜しげもなく注ぎ込むという売国行為を、堂々と選挙のマニフェストに謳っているような連中に政権が渡るようなことだけは絶対に避けなければならないと思っております。
次に matou さんご質問の
>とりわけ中国において、その「地域覇権と軍事的な勢力拡大」ということによって、中国政府はどのような目的を達成しようとしているのでしょうか
について
中国政府が望むのは、突き詰めれば歴史上の中華帝国の再興であり、
具体的には「華・夷 秩序」の再構築でしょう。
歴史上、中華だけが人の扱いを受けられるべき場所であり、その他は、東夷・西戎・北テキ・南蛮と、人間じゃない連中扱いをして、朝貢を復活させることでしょう。
ちなみに中国人の大半が、中国政府の歴史教育を通じて自分達こそ「中華の民」というプライドを持たされていますが、歴史上「中華」の世界で、本当に「人」たりえたのは、政府の役人だけ。で、他の国民は外国人のような「獣」ではないものの、単なる「奴隷」に過ぎないという現実はすっかり忘れられているようですけどね。(笑)
話が少しそれましたが、アジア地域において、中国だけが尋常ではないスピードで軍備を拡張しているのは、自国の防衛という面以外に、いずれはアメリカとの前面対決をするつもりでやっていることであり、そういう方針なり報告なりは、中国の国内向けの専門雑誌「解放軍報」なり、中国政府のシンクタンク「社会科学院」等の報告書でも過去何度も出てきます。
また中国政府要人の発言を丹念に追って行けば、軍の制服組の高官連中も、たびたびメディアに向けて公言しております。
ですから、この点は間違いないと自分は思っております。
また、こういう中国政府監修の出版物や、中国政府要人のコメント・軍の中枢連中からの発言に対して、賛同意見の表明はたびたび目にするものの、中国国内で反対意見や反論は一切確認出来ませんので、中国の国民もそういう考え方を支持していると分析するのが妥当と判断致しております。
なお、日本の外務省のように中国政府が口にする対外的に都合の悪い発言については、
無かったものにするとか
別な意見も存在している、とかを引き合いに出して、中国の真意をわざとねじまげようとする連中も存在していますが、
基本的に、中国のような巨大国家を日本人ややっていたような異心伝心で統治することは歴史上も不可能でした。
人口の巨大な国、又は国土の広い国は、インドも、アメリカも、ロシアも、カナダも、国が公表している文章によって、国民の意思の統一を計り、国家を一定の方向に向けて誘導する以外、コントロールする方法はありません。
従って、中国政府が国内向けに様々な文章で公表しているこどく、中国がアジアにおける地域覇権を目指して、海洋の未開の資源の独占を計り、いずれ台湾を支配下において、日本の海上輸送ルートを分断した上、将来的にアメリカと世界の覇権を賭けて戦う。という基本方針にはウソ偽りは無いと存じます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
10年先の国家戦略 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
10年先の国家戦略のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90068人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208325人
- 3位
- 酒好き
- 170698人