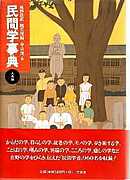http://
「ミーム」という用語はギリシア語の翻字であり、1904年、ドイツの進化生物学者 Richard Semon が自著 Die Mnemische Empfindungen in ihren Beziehungen zu den Originalenempfindungen で使用したのが起源である。これが1921年に英語に翻訳された際に The Mneme という書名になった。
動物行動学者リチャード・ドーキンスは、自著 The Selfish Gene (1976) で、遺伝子 "gene" の若干綴りを変えた "meme" という用語で人類の社会文化的進化と遺伝子の類似性を表し、感覚的には違いがあるものの、文化においても複製が発生していると主張した。ドーキンスは自著の中でミームを脳内の情報の単位と定義し、人類の社会文化的進化における突然変異自己複製子(mutating replicator)であるとした。それは、周囲に影響を与えるパターンであり、因子として伝播する。この考え方は社会学者/生物学者らの論争を巻き起こした。というのもドーキンスは、著書の中で脳内での情報単位の複製がどのように人間の振る舞いを制御し、ひいては文化に影響を与えるのかを詳しく説明しなかったからである(同書の主題は遺伝子であったため)。ドーキンスはThe Selfish Geneの中で「ミーム学」の理論を包括的に構築しようとしたのではなく、思索の結果として「ミーム」という用語を作り出したのである。その後、「情報の単位」を表す用語を様々な科学者が様々に定義するようになった。
「ミーム学」自体の起源は1980年代である(1983年1月の Scientific American 誌上でのダグラス・ホフスタッターのコラム Metamagical Themas が影響を与えた)。主流の社会文化的進化の研究とは異なり、ミーム学を研究する人々は人類学者や社会学者でないことが多く、学者ですらないことが多い。ドーキンスのThe Selfish Geneが一般大衆に与えた影響が、様々な知的背景を持つ人々がミーム学を志す主な要因となったことは確かである。もう1つの重要な要因は1992年にタフツ大学の哲学者ダニエル・デネットが出版した Consciousness Explained である。同書では、ミームの概念を精神に関する有力な理論に導入した。リチャード・ドーキンスは、1993年の論文 Viruses of the Mind でミーム学を活用して宗教的信念という現象や様々な宗教団体の性質を説明した。
しかしながら、現代ミーム学の確立は1996年に出版された2つの書籍、それも学界の主流からは離れていた著者によるものであった。1つはマイクロソフトの前重役でプロのポーカープレイヤーでもあるリチャード・ブロディの Virus of the Mind: The New Science of the Meme(ミーム—心を操るウイルス)であり、もう1つはフェルミ研究所で長年に渡って技師として働いていた数学者にして哲学者である Aaron Lynch の Thought Contagion: How Belief Spreads Through Society である。Lynch は社会文化的進化に関する学界とは全く接触することなく独力で理論を構築し、ドーキンスの著書のことも自著の出版が間近となるまで知らなかった。
Lynch とブロディの著書が出版されるのと時を同じくして、Web上に新たな電子雑誌が登場した。マンチェスターメトロポリタン大学の Centre for Policy Modelling が主催する Journal of Memetics – Evolutionary Models of Information Transmission である。同雑誌はその後 Francis Heylighen 率いるCLEA研究所(ブリュッセル自由大学)が発行するようになった。この電子雑誌は初期のミーム学に関する出版や論争の中心的立場を担った。なお、1990年に短期間だけ存在したミーム学に関する雑誌があった。Elan Moritz の編集による Journal of Ideas である[1]。1999年、心理学者スーザン・ブラックモアの著書 The Meme Machine(ミーム・マシーンとしての私)が出版された。同書は、デネット、Lynch、ブロディの考えを完成させ、それを社会文化的進化の主流と様々な面で比較するとともに、ミーム学に基づいて言語と人間の自我の発達に関する斬新で物議をかもす理論を提唱した。
「ミーム」という用語はギリシア語の翻字であり、1904年、ドイツの進化生物学者 Richard Semon が自著 Die Mnemische Empfindungen in ihren Beziehungen zu den Originalenempfindungen で使用したのが起源である。これが1921年に英語に翻訳された際に The Mneme という書名になった。
動物行動学者リチャード・ドーキンスは、自著 The Selfish Gene (1976) で、遺伝子 "gene" の若干綴りを変えた "meme" という用語で人類の社会文化的進化と遺伝子の類似性を表し、感覚的には違いがあるものの、文化においても複製が発生していると主張した。ドーキンスは自著の中でミームを脳内の情報の単位と定義し、人類の社会文化的進化における突然変異自己複製子(mutating replicator)であるとした。それは、周囲に影響を与えるパターンであり、因子として伝播する。この考え方は社会学者/生物学者らの論争を巻き起こした。というのもドーキンスは、著書の中で脳内での情報単位の複製がどのように人間の振る舞いを制御し、ひいては文化に影響を与えるのかを詳しく説明しなかったからである(同書の主題は遺伝子であったため)。ドーキンスはThe Selfish Geneの中で「ミーム学」の理論を包括的に構築しようとしたのではなく、思索の結果として「ミーム」という用語を作り出したのである。その後、「情報の単位」を表す用語を様々な科学者が様々に定義するようになった。
「ミーム学」自体の起源は1980年代である(1983年1月の Scientific American 誌上でのダグラス・ホフスタッターのコラム Metamagical Themas が影響を与えた)。主流の社会文化的進化の研究とは異なり、ミーム学を研究する人々は人類学者や社会学者でないことが多く、学者ですらないことが多い。ドーキンスのThe Selfish Geneが一般大衆に与えた影響が、様々な知的背景を持つ人々がミーム学を志す主な要因となったことは確かである。もう1つの重要な要因は1992年にタフツ大学の哲学者ダニエル・デネットが出版した Consciousness Explained である。同書では、ミームの概念を精神に関する有力な理論に導入した。リチャード・ドーキンスは、1993年の論文 Viruses of the Mind でミーム学を活用して宗教的信念という現象や様々な宗教団体の性質を説明した。
しかしながら、現代ミーム学の確立は1996年に出版された2つの書籍、それも学界の主流からは離れていた著者によるものであった。1つはマイクロソフトの前重役でプロのポーカープレイヤーでもあるリチャード・ブロディの Virus of the Mind: The New Science of the Meme(ミーム—心を操るウイルス)であり、もう1つはフェルミ研究所で長年に渡って技師として働いていた数学者にして哲学者である Aaron Lynch の Thought Contagion: How Belief Spreads Through Society である。Lynch は社会文化的進化に関する学界とは全く接触することなく独力で理論を構築し、ドーキンスの著書のことも自著の出版が間近となるまで知らなかった。
Lynch とブロディの著書が出版されるのと時を同じくして、Web上に新たな電子雑誌が登場した。マンチェスターメトロポリタン大学の Centre for Policy Modelling が主催する Journal of Memetics – Evolutionary Models of Information Transmission である。同雑誌はその後 Francis Heylighen 率いるCLEA研究所(ブリュッセル自由大学)が発行するようになった。この電子雑誌は初期のミーム学に関する出版や論争の中心的立場を担った。なお、1990年に短期間だけ存在したミーム学に関する雑誌があった。Elan Moritz の編集による Journal of Ideas である[1]。1999年、心理学者スーザン・ブラックモアの著書 The Meme Machine(ミーム・マシーンとしての私)が出版された。同書は、デネット、Lynch、ブロディの考えを完成させ、それを社会文化的進化の主流と様々な面で比較するとともに、ミーム学に基づいて言語と人間の自我の発達に関する斬新で物議をかもす理論を提唱した。
|
|
|
|
コメント(3)
〔続き〕
2005年、Journal of Memetics – Evolutionary Models of Information Transmission は廃刊となり、ミーム学の「死亡記事」が発表された。これはミーム学が今後すべきことがないという意味ではなく、むしろ1996年から始まったミーム学の波乱の幼年期が終わり、社会文化的進化について結果を残すことで生き残っていかなければならないという宣言であった。社会的かつインターネットを舞台とする大衆的科学運動としてのミーム学は終結したと言える。初期に活躍した人々の多くは離れていった。リチャード・ドーキンスとダニエル・デネットはミーム学の適用可能性について限界があることを表明した[要出典]。スーザン・ブラックモアは大学を離れてサイエンスライターとなり、認知科学に集中するようになった。Derek Gatherer は製薬業者でプログラマとして働くようになったが、時折ミーム学に関する文章を発表している。リチャード・ブロディは、世界のポーカーランキングで上位にランキングされるようになっている。Aaron Lynch はミーム学との関わりを絶ち、2005年にドラッグの事故で亡くなった。
2005年、Journal of Memetics – Evolutionary Models of Information Transmission は廃刊となり、ミーム学の「死亡記事」が発表された。これはミーム学が今後すべきことがないという意味ではなく、むしろ1996年から始まったミーム学の波乱の幼年期が終わり、社会文化的進化について結果を残すことで生き残っていかなければならないという宣言であった。社会的かつインターネットを舞台とする大衆的科学運動としてのミーム学は終結したと言える。初期に活躍した人々の多くは離れていった。リチャード・ドーキンスとダニエル・デネットはミーム学の適用可能性について限界があることを表明した[要出典]。スーザン・ブラックモアは大学を離れてサイエンスライターとなり、認知科学に集中するようになった。Derek Gatherer は製薬業者でプログラマとして働くようになったが、時折ミーム学に関する文章を発表している。リチャード・ブロディは、世界のポーカーランキングで上位にランキングされるようになっている。Aaron Lynch はミーム学との関わりを絶ち、2005年にドラッグの事故で亡くなった。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
民間学 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
民間学のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90068人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208325人
- 3位
- 酒好き
- 170698人