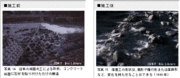阿部武という戦前の東京新聞記者が昭和40年代に出版した本です。
「東北の温泉と渓流(つり人社)
・・・川の下にも川がある。川の横にも川があった。・・・」
釣りの本だから馬鹿にされるかもしれませんが、川の構造と生物の関係が書かれていて名著だと思います。
日本は石灰岩が少ないから地下に水流がないと思われてますが、違った形で地下水が流れてるようです。
昭和40年代という列島改造論前夜にこのようなことを言えた人は学者にもほぼ皆無なのではないでしょうか?
ちなみに、この本は釣り人の間に幻の本と言われていましたが、2001年ぐらいに同社より復刻しました。しかし、あっと言う間に底を尽きましたが、楽天でなんとか買えました。
上記の名言をぜひ河川環境保護のキーワードとしてより多くの人に知っていただきたいです。
「東北の温泉と渓流(つり人社)
・・・川の下にも川がある。川の横にも川があった。・・・」
釣りの本だから馬鹿にされるかもしれませんが、川の構造と生物の関係が書かれていて名著だと思います。
日本は石灰岩が少ないから地下に水流がないと思われてますが、違った形で地下水が流れてるようです。
昭和40年代という列島改造論前夜にこのようなことを言えた人は学者にもほぼ皆無なのではないでしょうか?
ちなみに、この本は釣り人の間に幻の本と言われていましたが、2001年ぐらいに同社より復刻しました。しかし、あっと言う間に底を尽きましたが、楽天でなんとか買えました。
上記の名言をぜひ河川環境保護のキーワードとしてより多くの人に知っていただきたいです。
|
|
|
|
コメント(4)
>TOYOさん
釣りの世界では今、様々な議論が行われてます。
かなり急進的な意見もあって水中の将来が不安です。
銅山があるんですか。閉山したのはいつ頃でしょうか?
地元近くの川でイワナ釣りで大変有名なところがあります。
そこの上流にかなり古い坑道がありましたが数年前に老朽化のためか毒水流失防止の蓋が吹き飛んで鉱毒が流れでました。結果死の川となってしまいました。原因を知ってるのはごく一部のイワナマニアのみ。普通の釣り師は単に魚影が薄くなっただけと思ってます。夏になれば子供が水浴びもします。行政のチェックは入りません。鉱毒は水が濁るわけでもないので目につきません。
同様のことが全国の古い鉱山で起きる可能性もあるのではないでしょうか?平成のイタイイタイ病でも起こらねばよいが。
河口の段差とは、いわゆる河口堰でしょうか?
昨年も建設中河口堰を見ました。まったく反対運動は起きてなかったようでした。
長良川のようにそもそも大河でしかも有名な川ならメディアにも載りますが、田舎の小河川に何が起きても露出することはほとんどありません。
僕が思うに、田舎の小規模河川の方が高度経済成長以前の姿を残してることが多いと思います。しかも規模からしてプロテクトにお金が大河に比べて掛からないはずだから、小さい川ももっと重要視されてもよいような。特に小さい単独河川。
それから役所でせっかく近自然なものを作っても住人がいやがることがあるようです。事実地元近くの小さな川で金網の中に石ころを突っ込んだ堤防(すみません工法名は知りません)があったけど新興住宅が建って、都会から一戸建てを求めてやってきた住人達から石の間に蛇が住み着くと非難続出。警察の地域課は連日パンク状態。
市民にも啓蒙が必要なようです。
そうそう、先に述べた本はレアものかも知れませんが、『渓流(つり人社/季刊誌)』はまたまた釣りの本かも知れませんが、かなりリベラルで河川工法の話も沢山でてよい読み物だと思います。結構、行政の人まで登場しますし、ダム問題も沢山載ってます。これなら大手釣り具屋で立ち読みができます。
釣りの世界では今、様々な議論が行われてます。
かなり急進的な意見もあって水中の将来が不安です。
銅山があるんですか。閉山したのはいつ頃でしょうか?
地元近くの川でイワナ釣りで大変有名なところがあります。
そこの上流にかなり古い坑道がありましたが数年前に老朽化のためか毒水流失防止の蓋が吹き飛んで鉱毒が流れでました。結果死の川となってしまいました。原因を知ってるのはごく一部のイワナマニアのみ。普通の釣り師は単に魚影が薄くなっただけと思ってます。夏になれば子供が水浴びもします。行政のチェックは入りません。鉱毒は水が濁るわけでもないので目につきません。
同様のことが全国の古い鉱山で起きる可能性もあるのではないでしょうか?平成のイタイイタイ病でも起こらねばよいが。
河口の段差とは、いわゆる河口堰でしょうか?
昨年も建設中河口堰を見ました。まったく反対運動は起きてなかったようでした。
長良川のようにそもそも大河でしかも有名な川ならメディアにも載りますが、田舎の小河川に何が起きても露出することはほとんどありません。
僕が思うに、田舎の小規模河川の方が高度経済成長以前の姿を残してることが多いと思います。しかも規模からしてプロテクトにお金が大河に比べて掛からないはずだから、小さい川ももっと重要視されてもよいような。特に小さい単独河川。
それから役所でせっかく近自然なものを作っても住人がいやがることがあるようです。事実地元近くの小さな川で金網の中に石ころを突っ込んだ堤防(すみません工法名は知りません)があったけど新興住宅が建って、都会から一戸建てを求めてやってきた住人達から石の間に蛇が住み着くと非難続出。警察の地域課は連日パンク状態。
市民にも啓蒙が必要なようです。
そうそう、先に述べた本はレアものかも知れませんが、『渓流(つり人社/季刊誌)』はまたまた釣りの本かも知れませんが、かなりリベラルで河川工法の話も沢山でてよい読み物だと思います。結構、行政の人まで登場しますし、ダム問題も沢山載ってます。これなら大手釣り具屋で立ち読みができます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
近自然河川工法 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-