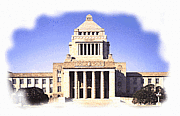はじめましての方ははじめまして。
なおやといいます。
まず必須3項目を消化しようと思います。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
総論の部分が怪しいのですが、ご容赦願います。
さて、本題に入ろうと思います。
このトピックでの目的は、一種の思考実験です。
まず前提条件ですが、
●消費税増税を前提とする。(必然的に政府における消費税からの増収も意味する。%は任意)
●新しいセーフガードなど、他の政策の同時施行するといった仮定は可とする。
●思考実験の舞台は現代の日本国とする。また、政策は極めて速く施行されるとする。
次にルールです。
●論拠としてのURLの提示は極力避けてください。(信憑性の問題)
●論拠となるデータが手元にある場合は参考文献を提示して下さい。
●これはディベートではなく、ディスカッションです。(審判がいない為)
ここまでで何か質問がありましたら受け付けます。
トピ主の意見と論点の提示に移ります。
まず、日本国の財政難が叫ばれ始めて久しい今日この頃ですが、基本的にこの事項は無視してかまいません。繰り返しますが、「消費税の増税」を前提とした思考実験ですので。
ちなみにこのトピックは、別のコミュニティに存在する似たようなトピックを少しいじったものです。ですので、そこで出てきた論点を(抜粋の形になりますが)まずここで提示しておきます。
●逆進性の問題
新しい税率では逆進性の問題を解決とはいかないまでも緩和した方が良いのでは?といった議論です。
●どのような形の増税が望ましいか
価格別の累進性、品目別の複数税率、一律の消費税。他にもありましたらどうぞ提示して下さい。
●消費税増税による消費の冷え込み
まず、増税による影響で消費が冷え込むことは間違いないとしておきます。
ですので私たちは、前提条件をクリアしつつどのような税制を施行するか考えなければいけません。この問題は上記の二つにリンクしますので、個別に答える必要はありませんが、意見を述べる際にはこのことを必ず背景においてください。
上記3つが大体大きな論点となりました。
この3つから派生させてもいいですし、このトピックの趣旨に合うようであればまったく別の角度からのアプローチもまた歓迎します。
では上記の論点に答える形でまずは私が先陣を切ろうと思います。
●逆進性の問題
私自身はこれを特に問題と考えていません。多くの低所得者層は、高所得者層に比べて貯蓄率が低く、また、可処分所得の中の生活必需品の割合は、高所得者層に比べ低所得者層が圧倒的に大きくなります。特にここまででは問題性を感じません。低所得者層が(絶対的な数値で)高所得者層よりも多くの消費税を払っているのであれば問題ですが、そのようなことはありえません。
●どのような税制が望ましいか
まず価格別の累進性については断固反対します。
何故ならば、価格の高い商品は相対的に弾力性の大きいものが多いことから生まれる、前提条件のクリアが難しくなることと、高価格の商品を生産している人々の環境悪化を懸念するからです。
次に一律税率については特に問題はないように思えます。
ですが、二極化が進んでいる現代日本で、セーフガードをもう少し充実させることが望まれるかもしれません。
最後に、品目別についてですが、可能であれば非常に魅力的であるように思います。エコ商品の税率を現行よりも下げてしまうとか、生活必需品については現行通りでいくとか…アイデアを募集します。
とりあえずは以上です。
反論があれば反論をどうぞ。
また、繰り返すようですが違ったアプローチも歓迎です。
なおやといいます。
まず必須3項目を消化しようと思います。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
総論の部分が怪しいのですが、ご容赦願います。
さて、本題に入ろうと思います。
このトピックでの目的は、一種の思考実験です。
まず前提条件ですが、
●消費税増税を前提とする。(必然的に政府における消費税からの増収も意味する。%は任意)
●新しいセーフガードなど、他の政策の同時施行するといった仮定は可とする。
●思考実験の舞台は現代の日本国とする。また、政策は極めて速く施行されるとする。
次にルールです。
●論拠としてのURLの提示は極力避けてください。(信憑性の問題)
●論拠となるデータが手元にある場合は参考文献を提示して下さい。
●これはディベートではなく、ディスカッションです。(審判がいない為)
ここまでで何か質問がありましたら受け付けます。
トピ主の意見と論点の提示に移ります。
まず、日本国の財政難が叫ばれ始めて久しい今日この頃ですが、基本的にこの事項は無視してかまいません。繰り返しますが、「消費税の増税」を前提とした思考実験ですので。
ちなみにこのトピックは、別のコミュニティに存在する似たようなトピックを少しいじったものです。ですので、そこで出てきた論点を(抜粋の形になりますが)まずここで提示しておきます。
●逆進性の問題
新しい税率では逆進性の問題を解決とはいかないまでも緩和した方が良いのでは?といった議論です。
●どのような形の増税が望ましいか
価格別の累進性、品目別の複数税率、一律の消費税。他にもありましたらどうぞ提示して下さい。
●消費税増税による消費の冷え込み
まず、増税による影響で消費が冷え込むことは間違いないとしておきます。
ですので私たちは、前提条件をクリアしつつどのような税制を施行するか考えなければいけません。この問題は上記の二つにリンクしますので、個別に答える必要はありませんが、意見を述べる際にはこのことを必ず背景においてください。
上記3つが大体大きな論点となりました。
この3つから派生させてもいいですし、このトピックの趣旨に合うようであればまったく別の角度からのアプローチもまた歓迎します。
では上記の論点に答える形でまずは私が先陣を切ろうと思います。
●逆進性の問題
私自身はこれを特に問題と考えていません。多くの低所得者層は、高所得者層に比べて貯蓄率が低く、また、可処分所得の中の生活必需品の割合は、高所得者層に比べ低所得者層が圧倒的に大きくなります。特にここまででは問題性を感じません。低所得者層が(絶対的な数値で)高所得者層よりも多くの消費税を払っているのであれば問題ですが、そのようなことはありえません。
●どのような税制が望ましいか
まず価格別の累進性については断固反対します。
何故ならば、価格の高い商品は相対的に弾力性の大きいものが多いことから生まれる、前提条件のクリアが難しくなることと、高価格の商品を生産している人々の環境悪化を懸念するからです。
次に一律税率については特に問題はないように思えます。
ですが、二極化が進んでいる現代日本で、セーフガードをもう少し充実させることが望まれるかもしれません。
最後に、品目別についてですが、可能であれば非常に魅力的であるように思います。エコ商品の税率を現行よりも下げてしまうとか、生活必需品については現行通りでいくとか…アイデアを募集します。
とりあえずは以上です。
反論があれば反論をどうぞ。
また、繰り返すようですが違ったアプローチも歓迎です。
|
|
|
|
コメント(108)
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
>れいじ さん
>現実問題として、消費税増税は実際に行われそうですし、
そうですね。
では特に前提条件の変更は必要ないかと思います。
またこれによって、「消費税増税の是非」も論点から外れます。
>「満足感が低い(もしくは極めて低い)」という状態のことを述べており、
議論前にここを皆の共通見解としませんか?
事実としては特に問題はありませんが、それを問題とすることにはいくつか異論を挟む必要があります。
●個人の能力や努力に本当にその環境が見合っていないのか
●個人がそれを判断するだけの知識を持っているのか
>これは、上記の例のような各ケースで「国に対する満足度」が違ってくるだろう?
といった想像から出てきているものでしょうか?
これは
>「所得定義」手法での関連付けが適切に成立しないのでは?
という意味合いでしかありません。
>でも、ここについて突き詰めて考えることが、
このトピでの議論目的である「最適な消費税増税の手段」を
考えることと同義なのかもしれないとも想像しております。
私もそのように思っています。
>確かに国民の消費は変化するのでしょうが、それは消費税が「一律」で増税になったからです。
これは低所得者層が購入する財の全てが課税対象から外れたときのみ使える前提条件ですよね?
>あくまでもこのトピ上で議論をすすめるにあたっては
この両者のどちらかに前提をおく必要はありますので、
これは何故でしょう?
どちらかに前提を置く必要性が私にはわかりません。
>国民からすれば、国家の安定が最優先事項ではないと思います。
この部分で既に私の考え方と違うのです。
またこの部分は特に論点としても意味がないように思えますがどうでしょう。
上記したように、多くの国民が飢えている状況では国家の安定はありえません。
つまり国家の安定を目指すプロセスに、多くの国民の安定は内包されているわけです。
>自分個人の生活安定の為に社会の安定(国家の安定)「も」求めているに過ぎない
との認識です。
同意します。
ですが、「それが正しいのだ」とは断じて思えませんし、その前提の下から生まれる不満もまた議論に値しないものと考えています。
>「国民の多くが飢えで苦しんだりする状況を発生させる可能性が生まれる」
何の考えもない一律での消費税増税が望ましい手段ではないことに
問題は、これ以上に良い政策があるかどうかです。
これが最善の手段と結論が出るのであれば、いくら国民が飢えて死のうがこの手段を取るほかないわけです。
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
>れいじ さん
>現実問題として、消費税増税は実際に行われそうですし、
そうですね。
では特に前提条件の変更は必要ないかと思います。
またこれによって、「消費税増税の是非」も論点から外れます。
>「満足感が低い(もしくは極めて低い)」という状態のことを述べており、
議論前にここを皆の共通見解としませんか?
事実としては特に問題はありませんが、それを問題とすることにはいくつか異論を挟む必要があります。
●個人の能力や努力に本当にその環境が見合っていないのか
●個人がそれを判断するだけの知識を持っているのか
>これは、上記の例のような各ケースで「国に対する満足度」が違ってくるだろう?
といった想像から出てきているものでしょうか?
これは
>「所得定義」手法での関連付けが適切に成立しないのでは?
という意味合いでしかありません。
>でも、ここについて突き詰めて考えることが、
このトピでの議論目的である「最適な消費税増税の手段」を
考えることと同義なのかもしれないとも想像しております。
私もそのように思っています。
>確かに国民の消費は変化するのでしょうが、それは消費税が「一律」で増税になったからです。
これは低所得者層が購入する財の全てが課税対象から外れたときのみ使える前提条件ですよね?
>あくまでもこのトピ上で議論をすすめるにあたっては
この両者のどちらかに前提をおく必要はありますので、
これは何故でしょう?
どちらかに前提を置く必要性が私にはわかりません。
>国民からすれば、国家の安定が最優先事項ではないと思います。
この部分で既に私の考え方と違うのです。
またこの部分は特に論点としても意味がないように思えますがどうでしょう。
上記したように、多くの国民が飢えている状況では国家の安定はありえません。
つまり国家の安定を目指すプロセスに、多くの国民の安定は内包されているわけです。
>自分個人の生活安定の為に社会の安定(国家の安定)「も」求めているに過ぎない
との認識です。
同意します。
ですが、「それが正しいのだ」とは断じて思えませんし、その前提の下から生まれる不満もまた議論に値しないものと考えています。
>「国民の多くが飢えで苦しんだりする状況を発生させる可能性が生まれる」
何の考えもない一律での消費税増税が望ましい手段ではないことに
問題は、これ以上に良い政策があるかどうかです。
これが最善の手段と結論が出るのであれば、いくら国民が飢えて死のうがこの手段を取るほかないわけです。
>国民からすれば、国家の安定が最優先事項ではないと思います。
ここはまた、哲学や国家観、世界観の相違になるので、ディスカッションしても不毛だとは思いますが、私は、国家は不安定で弱体でも国民が幸福で安定している場合は、理論上だけではなく、現実にも存在してきたと思っています。その意味で、「国家の安定」とか、「国家を安定させるための低所得者層の保護(セーフティネット構築)」といった議論には組しません。
つい最近までのイタリアは多党連立で常に政権は不安定で、イタリアリラは弱体、イタリア政府の財政状態、格付もOECD諸国内で低迷していましたが、国民は豊かな(経済的なものに限りません)生活を享受してきました。経済的、軍事的に強大なアメリカや、少なくとも経済的にはイタリアよりは豊かであったであろう日本より、イタリア国民の方が幸せな生活(無論主観的な要素が多いのは確かだし、相対的な議論にならざるを得ませんが)を営んできたのではないかと考えています。
ここはまた、哲学や国家観、世界観の相違になるので、ディスカッションしても不毛だとは思いますが、私は、国家は不安定で弱体でも国民が幸福で安定している場合は、理論上だけではなく、現実にも存在してきたと思っています。その意味で、「国家の安定」とか、「国家を安定させるための低所得者層の保護(セーフティネット構築)」といった議論には組しません。
つい最近までのイタリアは多党連立で常に政権は不安定で、イタリアリラは弱体、イタリア政府の財政状態、格付もOECD諸国内で低迷していましたが、国民は豊かな(経済的なものに限りません)生活を享受してきました。経済的、軍事的に強大なアメリカや、少なくとも経済的にはイタリアよりは豊かであったであろう日本より、イタリア国民の方が幸せな生活(無論主観的な要素が多いのは確かだし、相対的な議論にならざるを得ませんが)を営んできたのではないかと考えています。
>れいじさん (74〜5)
>「何故消費税が増税されたのか?」という背景と
「何の解決を図るのか」という目的の設定は必要だと考えます。
仰るとおりです。して、どのような設定が望ましいとお考えでしょうか?
現実味を出すなら財政難ということになりますが。
ただこれは政府のバランスシートを検証する必要が出てくるかもしれません。
>補足をお願いします。
一律で増税した場合との比較対象である前提が、低所得者優遇の品目別非課税方式であるわけですが、これまで通りの消費を彼らに期待するには、彼らの消費する財全てがその非課税対象にならないといけない、という意味です。
>・「国家の安定を図る施策」
・「国民の生活の安定を図る施策」
この両者で採用する施策は違ってきますから。
私はこれをほぼ=と考えています。詳細は以下で。
>「国家の安定」で物事を考えるのであれば、
少子化対策(年収○○以上は3名以上の子作りを義務化)等
人権問題ともなりそうな政策だって可となってしまいます。
基本的に「望まれない子供」は犯罪者になる確率が非常に高くなります。
即ち国家の安定のためにはやってはいけない政策ということになります。
勿論これはひとつの例でしかないでしょうが、他の例に対しても反論する自信はありますので、何かあれば例示をお願いします。
>そのことを議論の前提とすることには今のところ反対の立場です。
特に同意したいただく必要はありませんし、むしろそうであってほしいと個人的には思っています。これは私個人の立場であり、皆さんに強制するつもりはありません。ただ、皆さんの立場の考え方が「正しいのだ」と言われても、素直に同意できないだけです。
>できれば、ここを突き詰めて議論したいと考えますがいかがでしょうか?
反対まではしませんがこれは非常に危険であるように考えます。
結局のところお互いの哲学をつらつら語って結論が出ない可能性が非常に高いのと、それはこのトピックの趣旨に合わないからです。
「国家のために」「国民のために」(極論ですが)この二つの考え方は議論を進めるにあたって両者とも存在して良いと考えています。例えば低所得者に与える影響を懸念しているという部分では共通の認識が得られているようです。
>私は「一律での税率アップ」より
「生活必需品は非課税式で」という案の方が
良い案だと考えています(今の時点では)。
基本的に私は最後の結論に至るまでニュートラルで構えようと考えています。
ですので同意も批判もしません(勿論質問や揚げ足取りは嫌というほどします)
ただ、多数の人間がどちらかよりになってしまった場合はその逆につくことを先に言っておきます。似たような考えの人々がそのままそっちに突っ走るのは非常によくないと考えるからです。おそらく、あのトピックもそれがあるから私は気に食わなかったのでしょう。
>「何故消費税が増税されたのか?」という背景と
「何の解決を図るのか」という目的の設定は必要だと考えます。
仰るとおりです。して、どのような設定が望ましいとお考えでしょうか?
現実味を出すなら財政難ということになりますが。
ただこれは政府のバランスシートを検証する必要が出てくるかもしれません。
>補足をお願いします。
一律で増税した場合との比較対象である前提が、低所得者優遇の品目別非課税方式であるわけですが、これまで通りの消費を彼らに期待するには、彼らの消費する財全てがその非課税対象にならないといけない、という意味です。
>・「国家の安定を図る施策」
・「国民の生活の安定を図る施策」
この両者で採用する施策は違ってきますから。
私はこれをほぼ=と考えています。詳細は以下で。
>「国家の安定」で物事を考えるのであれば、
少子化対策(年収○○以上は3名以上の子作りを義務化)等
人権問題ともなりそうな政策だって可となってしまいます。
基本的に「望まれない子供」は犯罪者になる確率が非常に高くなります。
即ち国家の安定のためにはやってはいけない政策ということになります。
勿論これはひとつの例でしかないでしょうが、他の例に対しても反論する自信はありますので、何かあれば例示をお願いします。
>そのことを議論の前提とすることには今のところ反対の立場です。
特に同意したいただく必要はありませんし、むしろそうであってほしいと個人的には思っています。これは私個人の立場であり、皆さんに強制するつもりはありません。ただ、皆さんの立場の考え方が「正しいのだ」と言われても、素直に同意できないだけです。
>できれば、ここを突き詰めて議論したいと考えますがいかがでしょうか?
反対まではしませんがこれは非常に危険であるように考えます。
結局のところお互いの哲学をつらつら語って結論が出ない可能性が非常に高いのと、それはこのトピックの趣旨に合わないからです。
「国家のために」「国民のために」(極論ですが)この二つの考え方は議論を進めるにあたって両者とも存在して良いと考えています。例えば低所得者に与える影響を懸念しているという部分では共通の認識が得られているようです。
>私は「一律での税率アップ」より
「生活必需品は非課税式で」という案の方が
良い案だと考えています(今の時点では)。
基本的に私は最後の結論に至るまでニュートラルで構えようと考えています。
ですので同意も批判もしません(勿論質問や揚げ足取りは嫌というほどします)
ただ、多数の人間がどちらかよりになってしまった場合はその逆につくことを先に言っておきます。似たような考えの人々がそのままそっちに突っ走るのは非常によくないと考えるからです。おそらく、あのトピックもそれがあるから私は気に食わなかったのでしょう。
>76 れいじ さん
1)努力していない人間と言いますが、
こうした人がいること自体がゆるせないという考えですか?
それともある程度の数が存在するから
そのこと(ある程度の数が存在すること)に問題があるということですか?
私事ですが、人間はあるべくしてあるべきだと考えています。能力のある人間やそれを生かして努力した人間はそれ相応の対価を得るべきですし、能力がなくとも努力した人間もそれに見合った対価を得るべきですし、何もない者は何も得てはいけないと考えています。
ですので、存在自体を許せないといった感情は持ち合わせていません。
ただそういった人々が文句だけを垂れるのであれば話は別です。
また数の問題では、労働力が無駄になっているという面では問題と考えています。
2)その人が努力をしていないという根拠を提示願います
(できれば多くの事例があればありがたいです。
少ないと、個別の施策で改善・対処ができるので、
適切な行政運営をすれば基本問題にならないと考えます)。
すいません無理です。
3)もし許容の余地があるのであれば、
その許容数とその数であれば許容できるという根拠を教えて下さい。
国家が崩壊しないまでが限界値ではないでしょうか。
4)現在は上記の許容数を超えていると思いますか?許容内だと思いますか?
その許容を超えるとお考えであれば、
その許容数を超える数がいるという根拠を教えて下さい。
3の基であれば許容内ということになります。
ですが、不合理であることは間違いがないでしょう。
ところで東京都が面白いセーフガードを考えましたね。
ネットカフェ難民に住宅初期費用を含めた60万円を援助するそうです。
1)努力していない人間と言いますが、
こうした人がいること自体がゆるせないという考えですか?
それともある程度の数が存在するから
そのこと(ある程度の数が存在すること)に問題があるということですか?
私事ですが、人間はあるべくしてあるべきだと考えています。能力のある人間やそれを生かして努力した人間はそれ相応の対価を得るべきですし、能力がなくとも努力した人間もそれに見合った対価を得るべきですし、何もない者は何も得てはいけないと考えています。
ですので、存在自体を許せないといった感情は持ち合わせていません。
ただそういった人々が文句だけを垂れるのであれば話は別です。
また数の問題では、労働力が無駄になっているという面では問題と考えています。
2)その人が努力をしていないという根拠を提示願います
(できれば多くの事例があればありがたいです。
少ないと、個別の施策で改善・対処ができるので、
適切な行政運営をすれば基本問題にならないと考えます)。
すいません無理です。
3)もし許容の余地があるのであれば、
その許容数とその数であれば許容できるという根拠を教えて下さい。
国家が崩壊しないまでが限界値ではないでしょうか。
4)現在は上記の許容数を超えていると思いますか?許容内だと思いますか?
その許容を超えるとお考えであれば、
その許容数を超える数がいるという根拠を教えて下さい。
3の基であれば許容内ということになります。
ですが、不合理であることは間違いがないでしょう。
ところで東京都が面白いセーフガードを考えましたね。
ネットカフェ難民に住宅初期費用を含めた60万円を援助するそうです。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
>れいじ さん
>「行革の推進と公務員(議員含む)の意識改革が進み、
(中略)
というのはどうでしょうか?
良いと思います。異論が出なければ、次のステップの際にそのまま前提条件として採用します。
>この点についてはここから再度仕切り直ししませんか?
そうですね、少しごちゃついてしまいました。
では、れいじさんに返答する形でここからまた始めましょう。
>「国民の消費の変化が、実際に消費税増税によるものなのか」の証明であること。
これは以前同意いただいた、予測の際、経済状況は増税以前と同一とするといった前提条件がキーになるでしょう。
>「低所得者への負担増を考慮し一部品目を非課税にした税制により増税された」場合には
低所得者の消費構造には影響が殆ど現れないので
問題はここです。本当に影響がほとんど現れないのかどうか。
そういった税制を目指すことも可能ですが、高所得者層ほどではないにしろ彼らは様々な財を消費します。それら全て(もしくはそれに近いくらいの多くの割合)を非課税対象にするのでしょうか?
また、ここでいう低所得者層とはどれくらいのケースを想定されていますか?
>それらの子供が望まれない子供であるという根拠はありません。
要は国民側の意識の持ちようです。
確かに根拠はありませんし仰る通りなのですが、望まれない子供と判断する人々は必ず出てくるのではないでしょうか?現在の日本国民がそこまで啓蒙的とは思えませんが。
>「子供3人義務化」といった施策自体が制定される社会には
念のためにですが、国家の安定を第一に考える立場からしてもこれは望ましくないことです。犯罪率の増加もそうですが、例えばあの政策の対象は比較的豊かな家計です。そして彼らの多くは都心部もしくはその郊外に住んでいると考えられます。するとただえさえ都心部に人間が集中している状況に拍車をかけ、交通機関のマヒ。事故の多発、事件の多発が容易に予測できます。
>何故「国家の安定=国民の生活安定」なのか?ということの説明を求めている訳です)。
これは以下と内容がかぶるでしょうから以下で返答します。
>「前提」を決める必要があるということだと思っています。
前提は確かに必要であると思います。
ですが、今論点に挙がっている両者の考え方の相違について前提を決める必要があるのでしょうか?低所得者層への影響を懸念していることは共通の認識ですし、例の子供3人の政策には私の立場でも反対しているわけですが。特に弊害が認められない以上、放っておいてもいいのではないでしょうか。
そしておそらく、
>関係ないもの(たまたま同じ問題に見えているだけ)を
一緒くたに議論するのは危険であると考えます。
これを強く問題視されているわけですね。
とりあえず我々は現実の政治家でも官僚でもなく、議論の失敗もまた一つの礎となるでしょうから、弊害が認められた後でも遅くはないのではないでしょうか。
>「前提」を決めるにあたって、ということでです。
そもそもこの相違点で前提が必要なのかどうかが疑問なわけです。
>目的が違うと、それまでは同じ意見だと見えていたものが、
ある判断をした時に正反対の結論を出す、といったことが起こるからです。
双方の考え方の相違はあるしにろ、「目的」は同一であると考えます。
私たちはお互いの哲学を基にして、「最適な政策」を考えるわけですから。
そして国家のメリットが大きいか、国民のメリットが大きいかで割れることを恐れておられると思うのですが、(もしそうなったとしても)そこにきて客観的な数字や歴史を助けに結論を出せばいいのではないでしょうか。
>なおやさんの理論だと、(中略)これには同意いただけますでしょうか?
同意しかねます。
以前私は、「ほぼ」=と述べたのですが、これはその逆が=でないからです。
つまり、国民のため=国家のために必ずしもならないと考えている訳です。
例えば国家が最低限の生活を国民の為に用意したとしましょう。
こうすると明らかにモラルハザードが発生すると考えられます。
逆に、以前指摘されたように国民あっての国家ですので軍事力や財政だけを考えては、クーデターや犯罪率の増加が予見できることからも国家のため→国民のためというのは筋が通っていると私は考えています。
勿論、何をもって「ため」とするのかで議論の余地が多分に残されていますが、抽象論の応酬となるかと思われます。あまりこういった議論をしたくないのですが、そういったものが根底にあります。
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
>れいじ さん
>「行革の推進と公務員(議員含む)の意識改革が進み、
(中略)
というのはどうでしょうか?
良いと思います。異論が出なければ、次のステップの際にそのまま前提条件として採用します。
>この点についてはここから再度仕切り直ししませんか?
そうですね、少しごちゃついてしまいました。
では、れいじさんに返答する形でここからまた始めましょう。
>「国民の消費の変化が、実際に消費税増税によるものなのか」の証明であること。
これは以前同意いただいた、予測の際、経済状況は増税以前と同一とするといった前提条件がキーになるでしょう。
>「低所得者への負担増を考慮し一部品目を非課税にした税制により増税された」場合には
低所得者の消費構造には影響が殆ど現れないので
問題はここです。本当に影響がほとんど現れないのかどうか。
そういった税制を目指すことも可能ですが、高所得者層ほどではないにしろ彼らは様々な財を消費します。それら全て(もしくはそれに近いくらいの多くの割合)を非課税対象にするのでしょうか?
また、ここでいう低所得者層とはどれくらいのケースを想定されていますか?
>それらの子供が望まれない子供であるという根拠はありません。
要は国民側の意識の持ちようです。
確かに根拠はありませんし仰る通りなのですが、望まれない子供と判断する人々は必ず出てくるのではないでしょうか?現在の日本国民がそこまで啓蒙的とは思えませんが。
>「子供3人義務化」といった施策自体が制定される社会には
念のためにですが、国家の安定を第一に考える立場からしてもこれは望ましくないことです。犯罪率の増加もそうですが、例えばあの政策の対象は比較的豊かな家計です。そして彼らの多くは都心部もしくはその郊外に住んでいると考えられます。するとただえさえ都心部に人間が集中している状況に拍車をかけ、交通機関のマヒ。事故の多発、事件の多発が容易に予測できます。
>何故「国家の安定=国民の生活安定」なのか?ということの説明を求めている訳です)。
これは以下と内容がかぶるでしょうから以下で返答します。
>「前提」を決める必要があるということだと思っています。
前提は確かに必要であると思います。
ですが、今論点に挙がっている両者の考え方の相違について前提を決める必要があるのでしょうか?低所得者層への影響を懸念していることは共通の認識ですし、例の子供3人の政策には私の立場でも反対しているわけですが。特に弊害が認められない以上、放っておいてもいいのではないでしょうか。
そしておそらく、
>関係ないもの(たまたま同じ問題に見えているだけ)を
一緒くたに議論するのは危険であると考えます。
これを強く問題視されているわけですね。
とりあえず我々は現実の政治家でも官僚でもなく、議論の失敗もまた一つの礎となるでしょうから、弊害が認められた後でも遅くはないのではないでしょうか。
>「前提」を決めるにあたって、ということでです。
そもそもこの相違点で前提が必要なのかどうかが疑問なわけです。
>目的が違うと、それまでは同じ意見だと見えていたものが、
ある判断をした時に正反対の結論を出す、といったことが起こるからです。
双方の考え方の相違はあるしにろ、「目的」は同一であると考えます。
私たちはお互いの哲学を基にして、「最適な政策」を考えるわけですから。
そして国家のメリットが大きいか、国民のメリットが大きいかで割れることを恐れておられると思うのですが、(もしそうなったとしても)そこにきて客観的な数字や歴史を助けに結論を出せばいいのではないでしょうか。
>なおやさんの理論だと、(中略)これには同意いただけますでしょうか?
同意しかねます。
以前私は、「ほぼ」=と述べたのですが、これはその逆が=でないからです。
つまり、国民のため=国家のために必ずしもならないと考えている訳です。
例えば国家が最低限の生活を国民の為に用意したとしましょう。
こうすると明らかにモラルハザードが発生すると考えられます。
逆に、以前指摘されたように国民あっての国家ですので軍事力や財政だけを考えては、クーデターや犯罪率の増加が予見できることからも国家のため→国民のためというのは筋が通っていると私は考えています。
勿論、何をもって「ため」とするのかで議論の余地が多分に残されていますが、抽象論の応酬となるかと思われます。あまりこういった議論をしたくないのですが、そういったものが根底にあります。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
>83〜 れいじ さん
>ちょっと他コミュにかまけ過ぎました(反省)。
ゆっくりいきましょう。
>生活保護等を不当に得ている人が相当数いても、
あくまでも「労働力の無駄」という観点でのみ
問題だと捉えるわけですか?
この場合はそれに加えて公的資金の不合理が問題として浮上します。
>それは「何もない者は何も得てはいけないと考えています」が
実現している社会であるという前提でのお話でしょうか?
家庭環境・運の要素を無視していますのでなんとも言い難いですね。
ただそういった現実味の欠けていることからもそういった前提はありません。
あくまで私事の理想論としてご理解ください。
>であれば、少なくとも施策の柱を作り上げる段階では、
不当に請求する人間はいない前提で考えるべきだと思います
反対です。
どうしてもこういった不正は行われることからも、ある一定の人々がこう言ったことを「したがっている」として、方法論の際はそれをさせないようなツールを考えるべきではないでしょうか。
>ちょっとあいまいですねw
仰るとおりです。ですが限界値はどこか?といった議論は非常に難しいため、横に置いておくことを提案します。
>でも、他の方からは意見出てきませんねぇ(苦笑)
そうですね(苦笑)
彼らの言いたいことは既にれいじさんが代弁してしまっているか、この議論に興味があまりないか、時間があまりないかでしょうね。
>○が変わらずとも△が変われば◇も変わるということが言いたいだけですので。
ええ、理解しているつもりです。ただ、
>「生活への影響が少ない」
つまり以前とは完璧に=ではないということでしょう。
まだ具体的な案を練っていない段階ですので何とも言えませんが、何を「生活必需品」とするかでその差は変化すると思われます。また、ここでは他のマクロ経済については考慮していません。
>「子供3人義務化」となった場合に (以下略)
どうしても社会学のことになると、対照実験がほぼ不可能に近いので、実際どうなのかは難しいところです。ですが、
>国民の意識さえ変われば
意識を変える要因が必要なわけですが、これは非常に難しいと思われます。
例えばどのような方法を想定されていますか?
後気になるところが一つあります。
すでに弊害が生まれているとれいじさんは感じておられるようですので、私もそのつもりで反論しようと思います。
国家OR国民の議論で、私は「国家の為に」側の人間となっていますが、憲法違反をすることを良しとしていません。
ですので、
>・子供3人以上の義務化
・居住区域の指定
・職業の指定
・税制への賛同
・国債の債権放棄
これは私のいう「国家の為」から外れているとお考えください。
憲法は国家を縛り、法律は民衆を縛るものであると私は考えております。
ただ国債の債権放棄については考えものですね。
放棄という形を取らずとも、円の価値を捨てて発行量を増やしてしまえば、一気に返済することは可能ですから。
また、
>、「主権は国民。政治は国民の為にこそある」という
暗黙の了解(=前提)があるためだと思います。
また私事の見解になってしまうのですが、主権を国民に置いたのも実は国家のためであると私は考えています。ただ、表には奇麗事を並べなければいけませんので「国民のために」といった語句が歴史上も出てきます(リンカーンの有名なセリフにもありますね)
過去、様々な形で独裁政治や特権階級による支配がこの世界では行われてきました。しかし、ひと時の平和があったケースはあるにしろ、民衆の不満が爆発したり、特権を欲しがる者たちによる反逆で国家は致命的なダメージを受けることがほとんどです。それらの問題を解決するために民主主義といったシステムが考案されたのではないでしょうか。
決して、人は自由に生きる権利があるといった甘甘な哲学だけが、現在の民主主義を構築したのではないと思います。
ただ民主主義が政治体系の最終形なのかどうかはわかりません。
もしかすると問題の起きない独裁制(もしくはリヴァイアサンが現れる)を考え出すかもしれません。
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
>83〜 れいじ さん
>ちょっと他コミュにかまけ過ぎました(反省)。
ゆっくりいきましょう。
>生活保護等を不当に得ている人が相当数いても、
あくまでも「労働力の無駄」という観点でのみ
問題だと捉えるわけですか?
この場合はそれに加えて公的資金の不合理が問題として浮上します。
>それは「何もない者は何も得てはいけないと考えています」が
実現している社会であるという前提でのお話でしょうか?
家庭環境・運の要素を無視していますのでなんとも言い難いですね。
ただそういった現実味の欠けていることからもそういった前提はありません。
あくまで私事の理想論としてご理解ください。
>であれば、少なくとも施策の柱を作り上げる段階では、
不当に請求する人間はいない前提で考えるべきだと思います
反対です。
どうしてもこういった不正は行われることからも、ある一定の人々がこう言ったことを「したがっている」として、方法論の際はそれをさせないようなツールを考えるべきではないでしょうか。
>ちょっとあいまいですねw
仰るとおりです。ですが限界値はどこか?といった議論は非常に難しいため、横に置いておくことを提案します。
>でも、他の方からは意見出てきませんねぇ(苦笑)
そうですね(苦笑)
彼らの言いたいことは既にれいじさんが代弁してしまっているか、この議論に興味があまりないか、時間があまりないかでしょうね。
>○が変わらずとも△が変われば◇も変わるということが言いたいだけですので。
ええ、理解しているつもりです。ただ、
>「生活への影響が少ない」
つまり以前とは完璧に=ではないということでしょう。
まだ具体的な案を練っていない段階ですので何とも言えませんが、何を「生活必需品」とするかでその差は変化すると思われます。また、ここでは他のマクロ経済については考慮していません。
>「子供3人義務化」となった場合に (以下略)
どうしても社会学のことになると、対照実験がほぼ不可能に近いので、実際どうなのかは難しいところです。ですが、
>国民の意識さえ変われば
意識を変える要因が必要なわけですが、これは非常に難しいと思われます。
例えばどのような方法を想定されていますか?
後気になるところが一つあります。
すでに弊害が生まれているとれいじさんは感じておられるようですので、私もそのつもりで反論しようと思います。
国家OR国民の議論で、私は「国家の為に」側の人間となっていますが、憲法違反をすることを良しとしていません。
ですので、
>・子供3人以上の義務化
・居住区域の指定
・職業の指定
・税制への賛同
・国債の債権放棄
これは私のいう「国家の為」から外れているとお考えください。
憲法は国家を縛り、法律は民衆を縛るものであると私は考えております。
ただ国債の債権放棄については考えものですね。
放棄という形を取らずとも、円の価値を捨てて発行量を増やしてしまえば、一気に返済することは可能ですから。
また、
>、「主権は国民。政治は国民の為にこそある」という
暗黙の了解(=前提)があるためだと思います。
また私事の見解になってしまうのですが、主権を国民に置いたのも実は国家のためであると私は考えています。ただ、表には奇麗事を並べなければいけませんので「国民のために」といった語句が歴史上も出てきます(リンカーンの有名なセリフにもありますね)
過去、様々な形で独裁政治や特権階級による支配がこの世界では行われてきました。しかし、ひと時の平和があったケースはあるにしろ、民衆の不満が爆発したり、特権を欲しがる者たちによる反逆で国家は致命的なダメージを受けることがほとんどです。それらの問題を解決するために民主主義といったシステムが考案されたのではないでしょうか。
決して、人は自由に生きる権利があるといった甘甘な哲学だけが、現在の民主主義を構築したのではないと思います。
ただ民主主義が政治体系の最終形なのかどうかはわかりません。
もしかすると問題の起きない独裁制(もしくはリヴァイアサンが現れる)を考え出すかもしれません。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
>れいじ さん
>またこの「ある一定の人々」というのは、
事柄によってその「比率」も違ってくるでしょう。
ええ、ですので無視していいケースもあると思います。
逆に、無視すべきではなくともそれに対応する際のコスト面などもまた議論の対象になるでしょう。
>「寒い時代だとは思わんか(ワッケイン司令風に)」
ガンダムはSEEDシリーズしか見たことがないとです・w・;
後は特に問題はなさそうですが、最後のひと山ですね。
>「債権の放棄」はなおやさんの述べる例のように「実質的に」
国家の為にされ得てしまうことでしょうし
国家の為というか、このような事態になったら日本は終わりですね。
>「国家安定の為と称すれば(そして憲法違反さえしていなければ)
何でもしてもいいのか?」
良いか悪いか、ではありません。
例えば人は権力をもつと人間性が変わってしまう傾向があります。
これを縛る手段として憲法があったり、権力の分散が図られている訳ですし。
>>主権を国民に置いたのも実は国家のためであると私は考えています。
確かに綺麗事かもしれませんが、
決めた以上はそうあるように努力する必要があると思います。
ここについては補足をお願いします。
「そうである」とは何についてでしょうか?
また、国家の為に主権を国民に置くと「そうではない」ことになるのでしょうか?
>「今の国会議員を選んだのは国民である。結果的に悪いのは国民である」
これはどうでしょうか?
確かに国民に落ち度があることは確かでしょうが、「悪い」とまではいかないのではないでしょうか。別トピでの国民ネットでの議論も然り。システムをうまく動かすシステムがないことが問題であるように私は思います。
ところで今更ですが、れいじさんは現時点でどのへんに弊害を感じておられるのでしょうか?確かに将来的に議論が割れることはあるでしょうが、現時点でここを論点にしすぎて本題からそれまくっているように感じます。
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
>れいじ さん
>またこの「ある一定の人々」というのは、
事柄によってその「比率」も違ってくるでしょう。
ええ、ですので無視していいケースもあると思います。
逆に、無視すべきではなくともそれに対応する際のコスト面などもまた議論の対象になるでしょう。
>「寒い時代だとは思わんか(ワッケイン司令風に)」
ガンダムはSEEDシリーズしか見たことがないとです・w・;
後は特に問題はなさそうですが、最後のひと山ですね。
>「債権の放棄」はなおやさんの述べる例のように「実質的に」
国家の為にされ得てしまうことでしょうし
国家の為というか、このような事態になったら日本は終わりですね。
>「国家安定の為と称すれば(そして憲法違反さえしていなければ)
何でもしてもいいのか?」
良いか悪いか、ではありません。
例えば人は権力をもつと人間性が変わってしまう傾向があります。
これを縛る手段として憲法があったり、権力の分散が図られている訳ですし。
>>主権を国民に置いたのも実は国家のためであると私は考えています。
確かに綺麗事かもしれませんが、
決めた以上はそうあるように努力する必要があると思います。
ここについては補足をお願いします。
「そうである」とは何についてでしょうか?
また、国家の為に主権を国民に置くと「そうではない」ことになるのでしょうか?
>「今の国会議員を選んだのは国民である。結果的に悪いのは国民である」
これはどうでしょうか?
確かに国民に落ち度があることは確かでしょうが、「悪い」とまではいかないのではないでしょうか。別トピでの国民ネットでの議論も然り。システムをうまく動かすシステムがないことが問題であるように私は思います。
ところで今更ですが、れいじさんは現時点でどのへんに弊害を感じておられるのでしょうか?確かに将来的に議論が割れることはあるでしょうが、現時点でここを論点にしすぎて本題からそれまくっているように感じます。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
>れいじ さん
>うーん。ですが、実態がこのようになっている訳で、
その実態に不満という考えなので、
(運用する側の意識が変わらないとう前提であれば)現在の制度に
落ち度があるということなんでしょうね。
少なくとも「このままでは」運用する側の意識が変わらないという前提条件を提案します。そして運用する側の意識の改善を求めるのであればそういった対策案を我々は出すべきでしょう。
>また「人間性が変わってしまう傾向がある」から、
国家安定の為と称して(そして憲法違反さえしていなければ)
何でもしてもいい、とは私には許容はできないです。
私は傾向はその論拠とすべきではないと考えます。
極論ですが、憲法違反さえしていなければ国家は何をしてもいいと考えています。
もし国家が何かしらの問題のある行為(憲法範囲内で)をしてしまった場合、私たち国民は憲法で保障された言論の自由をもって対処する義務が生じるでしょう。
>なおやさんは、
この辺りの点について、何か改善案のようなものを持っていますか?
また、このトピでの争点にしますか?
私たちがこのような場で議論することが、改善案そのものだと考えています。
直接的な国民の意識改善案は別トピックに譲ったほうが良さそうです。
ですので私個人としては、このトピでの争点とする必要はないとの結論をもっています。もしどなたかが私とは違ったアプローチで改善案を出し、尚且つ有用性があると認められた場合は争点にしてもかまわないでしょう。ですが多分、このケースでは争点が少し違ったものになるかもしれません。
>あくまでも「国家の為」というのであれば、
何故そうした視点を持つ必要があるのか、を、
「国家の為=国民生活の為」ではないという
前提の上で(これは過去レスのとおりですので)
提示いただきたいと思います。
私のいう「国家のため」というのはもう少しマクロで、しかも大雑把で単純なものなのです。これまで人間は独裁者による独裁、特権階級による支配、宗教による支配でことごとく失敗をしてきました。これらはあまり良くないシステムだということが分かってきたわけです。じゃあ他に何があるか?ということで出てきたのが民主主義であるわけです。(これは前にも述べましたねそう言えば)
このシステムでは、
>いや、正確に言うと、国民の為=国家の為かな?
この傾向を期待している訳です。
そして上手くいかない理由としては
>民度の低さ
が提示されるわけなのですが。
・・・なんてこった。ここまで議論しておいて実は同じことを言ってたのでしょうか私たちは。まぁトピックの主旨ではないし良しとしましょう。
最後に「国家のために」という視点を持つ必要がどこにあるのか、ですが。
前にも述べたとおり、皆がこの視点に立つ必要はありません。あくまで私個人の見解ですので。
後の部分はほぼ同意しますが、返答が必要なところにのみ返答します。
>単に「財政的な事情」から必要だとするのであれば
「消費税もあげる」で話は済むと思います。
経済が悪化してしまえばいくら消費税を上げても歳入が増える保証がありません。そうした場合の最終段階が生活必需品からのみの消費税歳入なのですが、もはやその段階では国家としては後発展途上国以下でしょう。
>共通する「目的」
いずれ新しく出てきた前提条件・論点をまとめたコメントをします。
ただおそらく、このトピックにコメントして下さった方々全員が、低所得者層への負担軽減(最悪でも現状維持)を想定していることでしょう。ただ、財政難も途中のコメントで背景として取り入れるとの前提条件がありますので(採用されないのであれば話は別ですが・・。採決も取りますね)、低所得者層への負担軽減が第一目標ではないかもしれません。
・【職業】 大学生
・【総論】 消費税を増税するとして、どのような政策が一番好ましいか
>れいじ さん
>うーん。ですが、実態がこのようになっている訳で、
その実態に不満という考えなので、
(運用する側の意識が変わらないとう前提であれば)現在の制度に
落ち度があるということなんでしょうね。
少なくとも「このままでは」運用する側の意識が変わらないという前提条件を提案します。そして運用する側の意識の改善を求めるのであればそういった対策案を我々は出すべきでしょう。
>また「人間性が変わってしまう傾向がある」から、
国家安定の為と称して(そして憲法違反さえしていなければ)
何でもしてもいい、とは私には許容はできないです。
私は傾向はその論拠とすべきではないと考えます。
極論ですが、憲法違反さえしていなければ国家は何をしてもいいと考えています。
もし国家が何かしらの問題のある行為(憲法範囲内で)をしてしまった場合、私たち国民は憲法で保障された言論の自由をもって対処する義務が生じるでしょう。
>なおやさんは、
この辺りの点について、何か改善案のようなものを持っていますか?
また、このトピでの争点にしますか?
私たちがこのような場で議論することが、改善案そのものだと考えています。
直接的な国民の意識改善案は別トピックに譲ったほうが良さそうです。
ですので私個人としては、このトピでの争点とする必要はないとの結論をもっています。もしどなたかが私とは違ったアプローチで改善案を出し、尚且つ有用性があると認められた場合は争点にしてもかまわないでしょう。ですが多分、このケースでは争点が少し違ったものになるかもしれません。
>あくまでも「国家の為」というのであれば、
何故そうした視点を持つ必要があるのか、を、
「国家の為=国民生活の為」ではないという
前提の上で(これは過去レスのとおりですので)
提示いただきたいと思います。
私のいう「国家のため」というのはもう少しマクロで、しかも大雑把で単純なものなのです。これまで人間は独裁者による独裁、特権階級による支配、宗教による支配でことごとく失敗をしてきました。これらはあまり良くないシステムだということが分かってきたわけです。じゃあ他に何があるか?ということで出てきたのが民主主義であるわけです。(これは前にも述べましたねそう言えば)
このシステムでは、
>いや、正確に言うと、国民の為=国家の為かな?
この傾向を期待している訳です。
そして上手くいかない理由としては
>民度の低さ
が提示されるわけなのですが。
・・・なんてこった。ここまで議論しておいて実は同じことを言ってたのでしょうか私たちは。まぁトピックの主旨ではないし良しとしましょう。
最後に「国家のために」という視点を持つ必要がどこにあるのか、ですが。
前にも述べたとおり、皆がこの視点に立つ必要はありません。あくまで私個人の見解ですので。
後の部分はほぼ同意しますが、返答が必要なところにのみ返答します。
>単に「財政的な事情」から必要だとするのであれば
「消費税もあげる」で話は済むと思います。
経済が悪化してしまえばいくら消費税を上げても歳入が増える保証がありません。そうした場合の最終段階が生活必需品からのみの消費税歳入なのですが、もはやその段階では国家としては後発展途上国以下でしょう。
>共通する「目的」
いずれ新しく出てきた前提条件・論点をまとめたコメントをします。
ただおそらく、このトピックにコメントして下さった方々全員が、低所得者層への負担軽減(最悪でも現状維持)を想定していることでしょう。ただ、財政難も途中のコメントで背景として取り入れるとの前提条件がありますので(採用されないのであれば話は別ですが・・。採決も取りますね)、低所得者層への負担軽減が第一目標ではないかもしれません。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
一旦、前提条件を整理します。
尚、基本的な前提条件は1で述べたとおりですが、増税に至る背景として日本国の財政難を加えます。ですので、財政の健全化の1ステップとしてこの増税が行われたとの認識でお願いします。またその際に財政の合理化が行われいくらかは支出が減っていると仮定します。
●経済学のモデルを使う際は、それだけを述べるだけではいけない。噛み砕いて皆の理解を求めることが必要である。
●逆進性はそれ自体が問題であるという明確な定義ができていないため、それ自体を問題として扱ってはいけない。
●消費税の大義名分は福祉面への再分配であるが、ここでは特定財源のような例外を除いて考える為、特に気にする必要はない。
●政府が増税を決断する際、マクロ経済指標を悪い意味で簡潔に論拠としているとする。(低所得者層の家計は良くなっていないが、経済成長が認められているケース)
●この政治決断の際、選挙は考慮されていないとする。
●消費税自体を弱者救済のシステムとはしない。
●政府は「公平」を目指す。(ここでの「公平」の定義は62参照のこと)
おおまかではありますが、これらを前提条件とします。
尚、意義は認めますが期間を今月中とします。
また、私の総論を変更しました。ニュートラルの時間は終わりです。
とりあえず、しばらく意義が出ないかを見た後に、方法論に入っていこうと考えています。
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
一旦、前提条件を整理します。
尚、基本的な前提条件は1で述べたとおりですが、増税に至る背景として日本国の財政難を加えます。ですので、財政の健全化の1ステップとしてこの増税が行われたとの認識でお願いします。またその際に財政の合理化が行われいくらかは支出が減っていると仮定します。
●経済学のモデルを使う際は、それだけを述べるだけではいけない。噛み砕いて皆の理解を求めることが必要である。
●逆進性はそれ自体が問題であるという明確な定義ができていないため、それ自体を問題として扱ってはいけない。
●消費税の大義名分は福祉面への再分配であるが、ここでは特定財源のような例外を除いて考える為、特に気にする必要はない。
●政府が増税を決断する際、マクロ経済指標を悪い意味で簡潔に論拠としているとする。(低所得者層の家計は良くなっていないが、経済成長が認められているケース)
●この政治決断の際、選挙は考慮されていないとする。
●消費税自体を弱者救済のシステムとはしない。
●政府は「公平」を目指す。(ここでの「公平」の定義は62参照のこと)
おおまかではありますが、これらを前提条件とします。
尚、意義は認めますが期間を今月中とします。
また、私の総論を変更しました。ニュートラルの時間は終わりです。
とりあえず、しばらく意義が出ないかを見た後に、方法論に入っていこうと考えています。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
さてさて皆さん、お久しぶりですなおやです。
期限を2月いっぱいと言っておきながら、その後が遅くなってしまい申し訳ありません。
まず訂正をば。95の「意義」は「異議」の変換ミスです。2回ミスがありますが変換ミスです、ええ。
さて、本題に入らせていただきます。
ここからは私は一律増税派として議論に参加していくつもりです。
ただ、本心から一律増税が正しい選択とはあまり思っていません。
品目別の課税というのは非常に魅力的な提案であると私は考えています。が、これまでの議論で指摘してきた問題が自分の中でまだ解決していないため、一律増税派として意見する所存です。
ですのでとりあえずは、一律増税VS品目別増税といった構図で議論を進めていき、方法論を含めた具体的な問題をあぶりだし、このトピックでの回答を出そうかと考えています。ぶっちゃけこれまでと同じです。ニュートラルの立場というのは難しいものですね・・・w
無能なトピ主をお許しください。
以下、一律増税派としての意見に入ります。
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
さてさて皆さん、お久しぶりですなおやです。
期限を2月いっぱいと言っておきながら、その後が遅くなってしまい申し訳ありません。
まず訂正をば。95の「意義」は「異議」の変換ミスです。2回ミスがありますが変換ミスです、ええ。
さて、本題に入らせていただきます。
ここからは私は一律増税派として議論に参加していくつもりです。
ただ、本心から一律増税が正しい選択とはあまり思っていません。
品目別の課税というのは非常に魅力的な提案であると私は考えています。が、これまでの議論で指摘してきた問題が自分の中でまだ解決していないため、一律増税派として意見する所存です。
ですのでとりあえずは、一律増税VS品目別増税といった構図で議論を進めていき、方法論を含めた具体的な問題をあぶりだし、このトピックでの回答を出そうかと考えています。ぶっちゃけこれまでと同じです。ニュートラルの立場というのは難しいものですね・・・w
無能なトピ主をお許しください。
以下、一律増税派としての意見に入ります。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
まず、一律で増税を行うことについてのメリットについで。
というよりも、これは品目別で増税する際のリスクの指摘にあたる。
現在の日本国では、消費財には等しく5%の税金がかけられている。
品目別に税金をかけるということは、間違いなく消費動向に変化が起きるのではなかろうか。
消費動向に変化が起きるのは一律で増税しても同じことであるが、問題はそれと比べて何がどう変化することが予想されるかである。
消費動向の一般的な傾向として、ある財の価格が上昇した際、それの代替財の価格が変化していないのであれば、代替財を多く消費する。税金をかけるという行為は政府が市場に対して影響を持つということであり、この行為がある特定の企業を攻撃することになるのではないかという懸念である。品目別論者の方々がどのような税金のかけ方をするかが、まだ明確に把握できていないためここから先の分析はそれを見てから行いたいと思う。
これまでの流れからおそらく出てくるであろう争点について触れながら、私の意見を提示しておく。
まず、品目別にすることで一番期待されることは低所得者層への負担軽減である。低所得者層が多く消費する財について、現状維持もしくはそれ以下にすることは私の一律案よりも確かに低所得者層への負担が軽減される。
だが、問題点も存在する。
消費税の大半は、低所得者層の家計の多くを占めている財から徴収したもので占められている。いわゆるぜいたく品の消費が多少なりとも落ち込むことが予想されることを吟味すると、品目別派の方々の案次第だが、消費税における税収が減少する恐れがある。これでは税金をそもそもあげるべきではないのではないだろうか。
短いですが、最初はここまでにしておきます。
品目別派の方々、お願いします。
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
まず、一律で増税を行うことについてのメリットについで。
というよりも、これは品目別で増税する際のリスクの指摘にあたる。
現在の日本国では、消費財には等しく5%の税金がかけられている。
品目別に税金をかけるということは、間違いなく消費動向に変化が起きるのではなかろうか。
消費動向に変化が起きるのは一律で増税しても同じことであるが、問題はそれと比べて何がどう変化することが予想されるかである。
消費動向の一般的な傾向として、ある財の価格が上昇した際、それの代替財の価格が変化していないのであれば、代替財を多く消費する。税金をかけるという行為は政府が市場に対して影響を持つということであり、この行為がある特定の企業を攻撃することになるのではないかという懸念である。品目別論者の方々がどのような税金のかけ方をするかが、まだ明確に把握できていないためここから先の分析はそれを見てから行いたいと思う。
これまでの流れからおそらく出てくるであろう争点について触れながら、私の意見を提示しておく。
まず、品目別にすることで一番期待されることは低所得者層への負担軽減である。低所得者層が多く消費する財について、現状維持もしくはそれ以下にすることは私の一律案よりも確かに低所得者層への負担が軽減される。
だが、問題点も存在する。
消費税の大半は、低所得者層の家計の多くを占めている財から徴収したもので占められている。いわゆるぜいたく品の消費が多少なりとも落ち込むことが予想されることを吟味すると、品目別派の方々の案次第だが、消費税における税収が減少する恐れがある。これでは税金をそもそもあげるべきではないのではないだろうか。
短いですが、最初はここまでにしておきます。
品目別派の方々、お願いします。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
>呟き尾形さん
お久しぶりです。
さて麻生さんの意見を拝見しました。
これは「全額」なのか「金額」なのかどちらなのでしょうね。。。
いや名称などどうでもいいっちゃいいのですが。
面白い意見だと思います。ただ、疑問も残りますね。
麻生氏は一律10%にして13兆円捻出すると仰っていますが、増税による消費の冷え込みを計算したのでしょうか?
また、ここからは呟き尾形さんの意見に関してになるのですが、麻生氏の仰る通り年金を払っているのは5割程度の方です。私たちが危惧する低所得者層の多くは既に払っていないのではないでしょうか?この仮定が事実であれば、彼らにとって5%→10%の増税だけが影響することになります。
ここのところどうお考えになりますか?
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
>呟き尾形さん
お久しぶりです。
さて麻生さんの意見を拝見しました。
これは「全額」なのか「金額」なのかどちらなのでしょうね。。。
いや名称などどうでもいいっちゃいいのですが。
面白い意見だと思います。ただ、疑問も残りますね。
麻生氏は一律10%にして13兆円捻出すると仰っていますが、増税による消費の冷え込みを計算したのでしょうか?
また、ここからは呟き尾形さんの意見に関してになるのですが、麻生氏の仰る通り年金を払っているのは5割程度の方です。私たちが危惧する低所得者層の多くは既に払っていないのではないでしょうか?この仮定が事実であれば、彼らにとって5%→10%の増税だけが影響することになります。
ここのところどうお考えになりますか?
NO 99 なおやさんへ
こんにちわ。呟き尾形です。
・【年齢/性別】:35歳/男
・【職業】 :花卉生産
・【総論】 :消費税の逆進性の解消
>この仮定が事実であれば、彼らにとって5%→10%の増税だけが影響することになります。
そうでもありません。
まず、現在、年金は支払っていないとすれば一見一方的な増税に見えます。
しかし、「全額税方式」になれば、低所得であるために、年金を納められない人であっても、年金を結果的に支払うことになります。
すると、将来、基礎年金を受け取るという一種の保障が、「全額税方式」を前提とした消費税率アップという形で可能になるわけです。
まぁ、今の段階で、基礎年金を受け取る資格のない人を、「全額税方式」によってどうするつもりなのか次第ではありますが、これは各論ですし、各論となれば、所得に応じた還付も検討すべきだとは考えています。
ともあれ、「全額税方式」にするということは、国民全員が基礎年金を受ける権利を得るということだと認識しています。
となると、13兆円じゃぁ、とても足りない可能性は否定できないんですけどね。
増税による、消費の冷え込みについては、一時的なものであると認識しています。
過去の3%から5%アップによる消費の冷え込みは、消費税というより、バブル崩壊による不良債権、および、デフレスパイラルという要素が非常に強いかとおもいます。
こんにちわ。呟き尾形です。
・【年齢/性別】:35歳/男
・【職業】 :花卉生産
・【総論】 :消費税の逆進性の解消
>この仮定が事実であれば、彼らにとって5%→10%の増税だけが影響することになります。
そうでもありません。
まず、現在、年金は支払っていないとすれば一見一方的な増税に見えます。
しかし、「全額税方式」になれば、低所得であるために、年金を納められない人であっても、年金を結果的に支払うことになります。
すると、将来、基礎年金を受け取るという一種の保障が、「全額税方式」を前提とした消費税率アップという形で可能になるわけです。
まぁ、今の段階で、基礎年金を受け取る資格のない人を、「全額税方式」によってどうするつもりなのか次第ではありますが、これは各論ですし、各論となれば、所得に応じた還付も検討すべきだとは考えています。
ともあれ、「全額税方式」にするということは、国民全員が基礎年金を受ける権利を得るということだと認識しています。
となると、13兆円じゃぁ、とても足りない可能性は否定できないんですけどね。
増税による、消費の冷え込みについては、一時的なものであると認識しています。
過去の3%から5%アップによる消費の冷え込みは、消費税というより、バブル崩壊による不良債権、および、デフレスパイラルという要素が非常に強いかとおもいます。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
>すると、将来、基礎年金を受け取るという一種の保障が、「全額税方式」を前提とした消費税率アップという形で可能になるわけです。
長期的に見れば確かにおっしゃる通りだと思います。
ですが、その日の暮らしで困窮しているような家計は、将来のお金よりも今のお金のほうが重要なのではないでしょうか?また、単純に将来の補償は現在の家計に直接的な影響を及ぼさないと思うのですがどうでしょう?
ただこの指摘は、彼らが将来の補償にお金を使っていないという仮定の下です。
ですがこのケースは少なくはないでしょう。
>まぁ、今の段階で、基礎年金を受け取る資格のない人を、「全額税方式」によってどうするつもりなのか
おっしゃる通り、呟き尾形さんの意見がこのトピックの本筋となったときに論点とすべきですね。
> 増税による、消費の冷え込みについては、一時的なものであると認識しています。 (以下略)
過去の消費税増税における短期的な分析は間違っていないと思います。
ただ私の指摘は、物が高くなれば消費量は応じて減少するのではないかという長期視点によるものです。5%の増税分で消費量が減少するかどうかについては論点にしてもいいかもしれませんが、どうでしょう?
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
>すると、将来、基礎年金を受け取るという一種の保障が、「全額税方式」を前提とした消費税率アップという形で可能になるわけです。
長期的に見れば確かにおっしゃる通りだと思います。
ですが、その日の暮らしで困窮しているような家計は、将来のお金よりも今のお金のほうが重要なのではないでしょうか?また、単純に将来の補償は現在の家計に直接的な影響を及ぼさないと思うのですがどうでしょう?
ただこの指摘は、彼らが将来の補償にお金を使っていないという仮定の下です。
ですがこのケースは少なくはないでしょう。
>まぁ、今の段階で、基礎年金を受け取る資格のない人を、「全額税方式」によってどうするつもりなのか
おっしゃる通り、呟き尾形さんの意見がこのトピックの本筋となったときに論点とすべきですね。
> 増税による、消費の冷え込みについては、一時的なものであると認識しています。 (以下略)
過去の消費税増税における短期的な分析は間違っていないと思います。
ただ私の指摘は、物が高くなれば消費量は応じて減少するのではないかという長期視点によるものです。5%の増税分で消費量が減少するかどうかについては論点にしてもいいかもしれませんが、どうでしょう?
NO 101 なおやさんへ
こんにちわ。呟き尾形です。
・【年齢/性別】:35歳/男
・【職業】 :花卉生産
・【総論】 :消費税の逆進性の解消
>ですが、その日の暮らしで困窮しているような家計
>は、将来のお金よりも今のお金のほうが重要なので
>はないでしょうか?
それは、各自の価値観の問題なので、政治の問題として扱っていいのか正直わかりませんが、個人的には、年金を納めていないということをさも、正当であることを前提に政治の議論を進めることには疑問があります。
ところで、なおやさんは、具体的に、いくらの収入層を想定されていますか?
>また、単純に将来の補償は現在の家計に直接的な影響を
>及ぼさないと思うのですがどうでしょう?
私は、年金を納めるということ自体が、社会貢献であると同時に、一種の義務であると判断します。
義務を果たさない人を正当化することは出来ないと考えております。
さて、なおやさんが、このような質問をするということは、現在の年金の思想、つまり、現在、収入ある人が、現在の高齢者を支えるという形で社会貢献することに反対であるという立場であるからこそだと思います。
そうでないと、年金を納めないことを正当化することは不可能であると判断せざるを得なくなります。
そうなのでしょうか?
>おっしゃる通り、呟き尾形さんの意見がこのトピックの本筋
>となったときに論点とすべきですね。
同感です。
とはいいつつも、あくまで、本筋になった場合という仮定のお話かと思います。
>過去の消費税増税における短期的な分析は間違ってい
>ないと思います。
>ただ私の指摘は、物が高くなれば消費量は応じて減少
>するのではないかという長期視点によるものです。
昔のままの消費動向ならご指摘の通りかと思います。
しかし、消費動向も過去と大きく変化していますし、現在の消費傾向がロングテールであるのであるかぎり、そうしたことはないと考えております。
>5%の増税分で消費量が減少するかどうかについて
>は論点にしてもいいかもしれませんが、どうでしょ
>う?
かまいませんが、いまひとつものさしとなる基準が見つからないでいます。
こんにちわ。呟き尾形です。
・【年齢/性別】:35歳/男
・【職業】 :花卉生産
・【総論】 :消費税の逆進性の解消
>ですが、その日の暮らしで困窮しているような家計
>は、将来のお金よりも今のお金のほうが重要なので
>はないでしょうか?
それは、各自の価値観の問題なので、政治の問題として扱っていいのか正直わかりませんが、個人的には、年金を納めていないということをさも、正当であることを前提に政治の議論を進めることには疑問があります。
ところで、なおやさんは、具体的に、いくらの収入層を想定されていますか?
>また、単純に将来の補償は現在の家計に直接的な影響を
>及ぼさないと思うのですがどうでしょう?
私は、年金を納めるということ自体が、社会貢献であると同時に、一種の義務であると判断します。
義務を果たさない人を正当化することは出来ないと考えております。
さて、なおやさんが、このような質問をするということは、現在の年金の思想、つまり、現在、収入ある人が、現在の高齢者を支えるという形で社会貢献することに反対であるという立場であるからこそだと思います。
そうでないと、年金を納めないことを正当化することは不可能であると判断せざるを得なくなります。
そうなのでしょうか?
>おっしゃる通り、呟き尾形さんの意見がこのトピックの本筋
>となったときに論点とすべきですね。
同感です。
とはいいつつも、あくまで、本筋になった場合という仮定のお話かと思います。
>過去の消費税増税における短期的な分析は間違ってい
>ないと思います。
>ただ私の指摘は、物が高くなれば消費量は応じて減少
>するのではないかという長期視点によるものです。
昔のままの消費動向ならご指摘の通りかと思います。
しかし、消費動向も過去と大きく変化していますし、現在の消費傾向がロングテールであるのであるかぎり、そうしたことはないと考えております。
>5%の増税分で消費量が減少するかどうかについて
>は論点にしてもいいかもしれませんが、どうでしょ
>う?
かまいませんが、いまひとつものさしとなる基準が見つからないでいます。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
何やら以前と議論の趣が変わってきましたね。
時間をおいたのは正解だったのかもしれません。
>102 呟き尾形さん
>年金を納めていないということをさも、正当であることを前提に政治の議論を進めることには疑問があります。
一つ誤解を解いておきますと、私は年金を払わないことが正当であると主張したわけではありませんし、そう思ってもいません。ただ現状としてそういった事実があるのではないかという指摘に終始します。
>ところで、なおやさんは、具体的に、いくらの収入層を想定されていますか?
生活が非常に困難である例としては、>>50でれいじさんが例示してくださった母子家庭、及び、年金を支払っていないであろう人々に関しては、年収200万円以下のフリーター及び派遣社員の一人暮らしを想定しています。
>私は、年金を納めるということ自体が、社会貢献であると同時に、一種の義務であると判断します。
特に否定するつもりはありません。
ただ、麻生氏の仰る通りシステムとしての問題が多すぎて個人的には払う気が起きませんね。
>そうでないと、年金を納めないことを正当化することは不可能であると判断せざるを得なくなります。
そうなのでしょうか?
これは上記を参照ください。
>しかし、消費動向も過去と大きく変化していますし、現在の消費傾向がロングテールであるのであるかぎり、そうしたことはないと考えております。
成程理解しました。
私とは多少違う考え方なのですが、突き詰める必要が出てきたときに論点にしようと思います。
>かまいませんが、いまひとつものさしとなる基準が見つからないでいます。
もし必要ならば経済学ツールを持ち出そうかと考えています。
勿論、大学1年生がやる程度の簡単なものを。
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
何やら以前と議論の趣が変わってきましたね。
時間をおいたのは正解だったのかもしれません。
>102 呟き尾形さん
>年金を納めていないということをさも、正当であることを前提に政治の議論を進めることには疑問があります。
一つ誤解を解いておきますと、私は年金を払わないことが正当であると主張したわけではありませんし、そう思ってもいません。ただ現状としてそういった事実があるのではないかという指摘に終始します。
>ところで、なおやさんは、具体的に、いくらの収入層を想定されていますか?
生活が非常に困難である例としては、>>50でれいじさんが例示してくださった母子家庭、及び、年金を支払っていないであろう人々に関しては、年収200万円以下のフリーター及び派遣社員の一人暮らしを想定しています。
>私は、年金を納めるということ自体が、社会貢献であると同時に、一種の義務であると判断します。
特に否定するつもりはありません。
ただ、麻生氏の仰る通りシステムとしての問題が多すぎて個人的には払う気が起きませんね。
>そうでないと、年金を納めないことを正当化することは不可能であると判断せざるを得なくなります。
そうなのでしょうか?
これは上記を参照ください。
>しかし、消費動向も過去と大きく変化していますし、現在の消費傾向がロングテールであるのであるかぎり、そうしたことはないと考えております。
成程理解しました。
私とは多少違う考え方なのですが、突き詰める必要が出てきたときに論点にしようと思います。
>かまいませんが、いまひとつものさしとなる基準が見つからないでいます。
もし必要ならば経済学ツールを持ち出そうかと考えています。
勿論、大学1年生がやる程度の簡単なものを。
・【年齢/性別】 21歳/男
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
>れいじさん
お久しぶりです。
>この考え方を導入すると本筋の話が話が分散しがちになるのと
税率アップ分がほぼ年金に持っていかれるので
このトピの主題である”税収増”にはならないので、
これは別にして考えた方がいいのかなぁ・・・
増収分を年金に持っていくというのは一つの提案であり、それに固執する必要はないかと考えています。ただ、そういった議論も必要であるとも考えています。
>その増税に踏み切る環境・前提が適切かの方ですね。
これは前提条件にある政府の単純なマクロ見解を考えると、現在の仮定は低所得者層にとって必ずしも適切ではないと考えてください。ただ、増収分をうまい具合に還元して相乗効果を期待できる可能性もあります。
>そのバランスなんでしょうね。
おっしゃるとおりです。
>むしろ一律よりも品目別の方が
国民生活視点で見たその影響は少ないような気がします。
品目別の具体案がまだ出ていませんので何とも言えません。
>ですが、その懸念を”重視”するかという面では懐疑的な考えです。
これもまた、バランスですね。
>こういう評価軸となるのでしょうかね。
そうであるかもしれません。
>13兆円の5%。6500億円か。
どっかの産業市場まるまる全部相当ですね。
仰るとおりです。
今まで使わなかった6500億円が市場に出てくるなら説明がつくのですが、あまり現実的ではないでしょう。
ただ、
>人間結構柔軟に慣れるものです
と仰られていますが、これは6500億円を消費側が捻出したという仮定でしょうか?
・【職業】 大学生
・【総論】 増税は一律で行う。(10%)
>れいじさん
お久しぶりです。
>この考え方を導入すると本筋の話が話が分散しがちになるのと
税率アップ分がほぼ年金に持っていかれるので
このトピの主題である”税収増”にはならないので、
これは別にして考えた方がいいのかなぁ・・・
増収分を年金に持っていくというのは一つの提案であり、それに固執する必要はないかと考えています。ただ、そういった議論も必要であるとも考えています。
>その増税に踏み切る環境・前提が適切かの方ですね。
これは前提条件にある政府の単純なマクロ見解を考えると、現在の仮定は低所得者層にとって必ずしも適切ではないと考えてください。ただ、増収分をうまい具合に還元して相乗効果を期待できる可能性もあります。
>そのバランスなんでしょうね。
おっしゃるとおりです。
>むしろ一律よりも品目別の方が
国民生活視点で見たその影響は少ないような気がします。
品目別の具体案がまだ出ていませんので何とも言えません。
>ですが、その懸念を”重視”するかという面では懐疑的な考えです。
これもまた、バランスですね。
>こういう評価軸となるのでしょうかね。
そうであるかもしれません。
>13兆円の5%。6500億円か。
どっかの産業市場まるまる全部相当ですね。
仰るとおりです。
今まで使わなかった6500億円が市場に出てくるなら説明がつくのですが、あまり現実的ではないでしょう。
ただ、
>人間結構柔軟に慣れるものです
と仰られていますが、これは6500億円を消費側が捻出したという仮定でしょうか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
「良識ある」政治・政策検討会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
「良識ある」政治・政策検討会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170671人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89536人