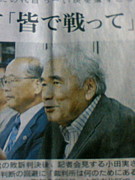鳩山前首相が退陣挨拶で「新しい公共」の重要性を語った。これは彼の持論である「友愛」社会を敷衍したものであろう。菅内閣は当然これを引き継ぐのだろうが、ここで「新しい公共」概念のもつ欺瞞性を明らかにしたい。ここでのポイントは「官」と「民」の関係如何の問題である。そう整理するなら、この問題は鳩山内閣に止まらず、歴代の自民党政府においても常に語られてきた問題であるのだ。小泉政権でいわく「官から民へ」。
この問題では、いつも「官」と「民」という二項対立が設定される。自然科学ならいざ知らず、およそ人間社会において、このような二項対立での問題設定がなされる場合には、まず眉に唾をつけてかかった方がよいだろうというのが、私の基本的スタンスである。いくらデジタル社会であるといえども、コンピュータと現実の人間や社会とでは明らかに異なる。いわく、「善か悪か」「左か右か」「白か黒か」「保守か革新か」……。
まず「官」とは何か。言うまでもなく、中央政府と地方政府のこと。公共部門である。この活動は税金によって担われる。これを第1セクターと呼ぶ。
では「民」とは何か。鳩山は、これを「民間」という。この発想は一人鳩山に限らず、一般に歴代政府もマスコミの多数もこれに倣ってきた。しかし、ここに詐術が潜んでいる。「官」と「民」の二項対立で捉えるなら、中央政府と地方政府以外はすべて「民」すなわち「民間」となる。するとそこには、企業家・資本家も労働者も何もかもが含まれてしまう。
小泉に代表される新自由主義者が「官から民へ」と語る場合、規制緩和、公共部門の民営化、小さな政府の文脈で語られるから、「民」は「民間企業」を指すことはかなり明白である。ここで抜け落ちているのは、中央政府・地方政府と民間企業以外の存在である。それは民衆・市民・労働者である。ここではっきりするのは、新自由主義においては、政府と民間企業しかその発想の中に存在せず、民衆・市民は埒外に置かれていることだ。
鳩山の場合は、新自由主義者ほど明確ではなく曖昧である。それは小泉・竹中路線があまりにも評判を落としたために、露骨な新自由主義では支持を得られないことと、彼の「友愛」という抽象的理念からくるものであろうと推測される。
鳩山の主張は、国民が政府だけに頼らず、民間企業も一人ひとりの市民も公共社会の構成員・プレイヤーとしての自覚をもち活動していこうというようなことであろう。では、何が問題か。それは、まったく本質の異なるものを一緒くたにしてしまっていることである。
整理するため、まず第2セクターを設定しよう。これは民間企業、営利部門である。この本質は営利であり利潤追求にある。もちろん現代社会においては、法令順守(コンプライアンス)や企業の社会的責任が鋭く問われるとはいえ、本質は利潤追求にあり、それ以外の何物でもない。たとえ企業が寄付行為をしたり、文化・芸術への支援をしたり、環境問題に取組んだとしても、それらはあくまでも利潤追求に従属したものであって、利潤を無視、度外視して行われることはないし、逆にそれらに取組むことによって企業イメージを高めることで、長期的にはより大きな利潤に結びつけようとしているとも言えるのである。
では第3セクターとは。市民セクターである。ここには、NPO・NGO、市民団体、市民グループ、ボランティアグループ、自治会、消費生協、労働者協同組合、農業協同組合、労働組合など政府と民間企業以外の非政府組織がすべて含まれる。市民がある一定の目的を達成するため自主的・自発的に結成したグループ・団体のことである。
日本においては、この第3セクターの概念が決定的に弱く、ないしは無視・軽視されている。というよりも、第3セクターの意味が歪曲されてしまってさえいる。第3セクターと聞いて普通思い浮かべるのは、「3セク」と略称される悪名高い「第3セクター」であろう。つまり半官半民の企業体のことである。地方自治体に多いが、税金を投入し、民間企業から出資し、民間企業出身者が役員を務め、地方公務員が出向職員になって経営されるような企業体である。その多くが利潤を上げられずに経営破綻し、さらに破綻を糊塗するために追加の税金が投入され、それでも経営再建ができず税金が垂れ流されている。大阪府庁の移転先として取りざたされる大阪市のワールドトレードセンター(WTC)などがそうだ。欧米の概念が日本に導入される場合に往々にして起こるように、言葉の本来の意味がすりかえられてしまう典型例のひとつである。
日本においては腐りきってしまった「第3セクター」という言葉に本来の輝きを取り戻し再生させてやらねばならない。なぜなら第3セクターこそが、憲法における国民主権を担う主たるプレーヤーとして、また民主主義社会の担い手、社会変革の主体として重要な役割を有していると考えるからである。
米国は新自由主義の本場であり、自己責任・自助努力なる発想が横行し、したがって冷徹な競争社会と考えられがちだ。しかしそれだけでは、アメリカ社会を一面的に捉えたことにしかならないだろう。
「米国はたしかに市場主義が優先される社会だが、その一方で、市場主義にまったく従わないNPOが大きな力を持ち、公的サービス(福祉)分野で政府の代役を担っている。ある面、NPOが市場主義の暴走に歯止めをかけたり、市場主義の被害者などを救済したりすることで、社会のバランスを取っているのである。派遣切りや正社員切りなど解雇の問題にしても、『米国は簡単に首切りしている』というイメージがあるが、それは事実ではない。(※1)」
米国においてはNPOが福祉分野以外でも広範な公的サービスの担い手になっており、政府に対するロビー活動も活発に展開している。多くの市民が社会の担い手として自主・自立の精神、ボランティア精神を強く持っていると言えるだろう。
日本においてNPOに法的根拠が与えられたのは新しく、法人格が付与されたとはいえ、米国のように免税措置などの特典はほとんど無い状況である。多くの団体が財政的基盤は脆弱で、したがって専従職員の給与水準も劣悪、まさにボランティア精神のみによってかろうじて支えられているといったところが多い。貧困層を支えるNPOの職員自体が貧困層であるという皮肉な実態が横行している。自治体や企業の委託事業を請け負って、やっとその委託費・補助金などで細々と運営している。これでは、地方自治体業務の民間委託、下請け化、安上がり行政の補完物でしかないとも言える。
鳩山の腹の中には、国家財政の危機の中で、市民のボランティア活動をあてにしようとの意図がおそらくあっただろうと推測される。安上がり行政のための補完物である。
しかし第3セクターの活動の意義を、そのように矮小化してはならない。民主主義の根幹に関わる意義を確認しなければならないだろう。民主主義を市民自治と定義してみる。つまり、市民・民衆が政治・社会の主人公となって、政治・社会を自主的・自立的・民主的に動かす実践主体になることである。言い換えれば、第1セクターの中央・地方権力と利潤追求の民間企業の第2セクターに対する対抗勢力として第3セクターを強力に形成するのである。当然、ここにおいて民主主義の概念は、やはり手垢にまみれ腐りきってしまったものから、本来の輝きを取り戻し再生されることになる。
「民主主義(デモクラシー)」という言葉はどれだけ歪められ侮蔑されてきたことであろう。自由「民主」党の「民主」も、「民主」党の「民主」も、社「民」党の「民」も、民主主義なのであるから。政権与党にとっては、民主主義とは選挙で多数を占めることであり、議会で多数決で決めるということでしかない。選挙での多数と議会での多数、これが民主主義のすべてである。つまり民主主義とは多数決なのだ。では、野党にとっては……。「少数意見の尊重」である。つまりこれを合成すると、民主主義とは「議論をし、最終的に多数決で決めるが、小数意見も尊重されなければならない」というやせ細った理屈に帰結する。つまりは議会がすべて、これを議会主義という。ここでは労働者・市民・民衆は選挙で投票する有権者という意味に貶められる。
自民党政権の時代から現在の民主党中心の政権まで、地方分権・地域主権がお題目のように唱えられている。中央政府の仕事や財源を地方政府へ極力委譲することとして語られている。しかし、ここにも詐術がある。抽象的一般論として、「地方分権・地域主権」に反対する有権者はあまりいないだろう。反対するのは、自己の権限が削られる国家官僚くらいだ。住民サービスに、より直結するような公的業務は、地方自治体で担うことが望ましいのはその通りだ。だが問題は、公的業務が中央政府から地方政府へ委譲するという行政的・技術的観点に矮小化されてはならない。ここでも課題は、地方政府・地方権力に対抗する第3セクター・市民セクターが強力な主体を形成し得るかにある。
民主主義を市民自治と捉え、市民・民衆が政治・社会の主人公となって、自主的・自立的・民主的に社会を動かす実践主体となること。そう考えるなら、中央・地方権力の政策が反市民的であるとき、当然第3セクターの行動・存在は反体制・反権力の色彩を帯びざるを得ないだろう。これは歴史が物語っている。60年安保闘争然り、反戦・反基地・反核闘争然り、成田空港建設阻止の三里塚農民の闘争然り、現在の沖縄の普天間基地撤去闘争然り。企業の利潤追求至上主義に対する数々の反公害闘争、電力資本に対する反原発闘争、非正規切り・偽装請負に対するユニオンの闘いなどは国家権力と結びついた独占企業に対抗する反独占資本の闘いである。
断わっておくが、これらの運動が反体制・反権力の色彩を帯びているからと言って、そこに参加している市民・労働者が社会主義思想を持っているということを必ずしも意味してはいない。しかしながら、現状を変革し新たな社会を構想し展望する場合、それが社会主義であれ何であれ、現在の権力に対抗し得る市民・民衆・労働者の大衆的な運動主体の形成と思想的発展を抜きにしてはその実現はあり得ないだろう。
民主主義は、古代ギリシャのポリスにおける民主制を基とし、封建制王権に対するブルジョア市民革命の思想として新たに発展した。フランス革命に代表されるように、勃興してきた新興勢力であるブルジョア階級を担い手として、封建的桎梏を打破し、資本主義的経済活動の自由と市民的権利・自由と平等の獲得を求め絶対王政を打倒した。その時代においては、ブルジョア階級が民主主義の、自由と平等の、市民的権利の担い手であり社会進歩を代表していた。しかし、産業革命の進展によって大量の労働者階級が発生し、ブルジョア階級と労働者階級の利害は鋭く対立し、労働運動が勃興、社会主義思想が生まれる。ブルジョア市民革命期においては社会進歩の担い手であった資本家は、労働運動を弾圧し、資本家の利害を代表する権力は社会主義思想・社会主義者を弾圧・排除しようとする。ここにおいて民主主義はあくまでブルジョア民主主義の枠内に押し込めようとされ、市民的権利は選挙の投票のみに矮小化されていく。つまり民主主義を議会主義に貶めていくのだ。しかし労働者階級の粘り強い戦いによって、団結権、団体交渉権、スト権などの労働基本権が勝ち取られていく。さらに労働者は自主・自立の精神で資本家の搾取から生活を防衛するため消費者生協、労働者協同組合を結成していく。政府に対しては社会保障政策を求めて闘う。自由や平等を単なる理念や抽象的法に止まらせず、具体的な社会権としての制度保障を国家の責任として実施させていく。
さらに資本主義が独占資本主義段階になると、独占資本とその代弁者である政府は、労働者が勝ち取った権利さえも無効化しようと画策する。ブルジョア市民革命期には進歩的勢力であったブルジョアジーは反動的勢力に転化する。ブルジョア民主主義の限界を乗り越え、議会主義と形式的民主主義の枠を越えて、労働者階級が民主主義を発展させ実質化させる担い手となる。独占資本とその代弁者の政府による反動的政策・民主主義的諸権利の圧殺に対し、労働者階級だけでなく、知識層や広範な市民層が労働者とともに民主的諸闘争に結集してくる。
自由と平等に代表される民主主義は、単にブルジョア民主主義に限定されるものでは決してない。封建的身分制を打破した点において、ブルジョアジー市民革命はその時代において先進的であった。しかし、ブルジョアジーが権力を掌握すると、その自由と平等の理念と制度的保障を労働階級にまで波及させることを食い止めようとし、進歩的勢力から反動勢力へ転化していったのだ。したがって現代において、自由と平等を実質化させる民主主義闘争は労働者階級と、独占資本とその政府の反民主的政策に苦しむ広範な反独占諸階層の連帯した闘いによって社会変革の展望を切り開く闘いへと発展する可能性を内包している。
民主主義と社会主義を断絶した別のものと捉えるのは、民主主義をブルジョア民主主義としか理解し得ないからである。資本主義社会においても労働者・市民・民衆の自主的・自立的運動とコミュニテーの形成、社会・組織の運営・経営能力の獲得が問われる。労働者・民衆が社会を動かす能力を身につけなければ、たとえ社会主義革命が実現したとしても、一部テクノクラート官僚が国家の政策を牛耳るようなおよそ非民主的権力にしかならないだろう。もちろん将来に国家を廃絶するとしてもだ。20世紀型社会主義の反省の上に立つならば、民主主義概念が本来持っている自由と平等の理念を制度的に担い得る能力を持った多数の労働者・民衆の連帯と自己変革が問われるだろう。それは単に観念の中で実現されるものではなく、もちろん理論と思想の学習は必要ではあるが、現実の権力の反人民的政策に対抗する広範な運動を作り出していく実践を通して形成されていくだろうし、しなければならない。
私が第3セクターの重要性を強調するのは以上のような視点からである。日本の民衆に多く見られる「お上頼み」の没主体者、没主権者の発想を実践への参加を通して、いかに自己変革していくかが課題である。「お上」が上から作った第3セクターの現状を見ればいい。社団法人、財団法人、独立行政法人等々、国家官僚の天下り先で多額の税金を無駄遣いし、ろくな仕事をしていない。これらの無用の長物を本気で潰せば税金の節約は相当できるのだ。民衆に本当に必要な業務なら、「その浮いた税金をいくらか回せ、俺たちが自分で運営するから」と要求すればいい。よく労働者が職場で徹底的にストライキ闘争をやりぬいて、会社を倒産させてしまったら元も子もないと言う。しかし、この発想は、会社の経営は資本家・経営者がいなければできないと思い込んでいるに過ぎない。現実に倒産した会社を労働組合が自主再建して、労働者だけで経営している自主管理の企業が日本にもある。これが労働者協同組合方式である。ヨーロッパにおいては、この労働者協同組合方式による企業経営が長い伝統と実績を持っている。倒産企業の自主再建だけでなく、最初から労働者が集まり出資者になって企業を立ち上げ、自分たちで経営するのだ。労働者協同組合の法的裏づけもある。これを支える金融機関まで労働者が作ってしまっているところもある。日本にも労働金庫という労働組合出資の金融機関はある。とりあえずは、これを利用すればよい。日本においても、労働者協同組合の法整備を早急に勝ち取らねばならない。
菅首相が「第3の道」を提議した。これが新自由主義か福祉社会か、小さい政府か大きな政府か、さらに資本主義か社会主義かという二項対立になっていない点で、その誤魔化しは巧妙である。次回、これを批判的に検討しよう。
6月23日、沖縄慰霊の日。菅首相は慰霊式典に参列した。そこでの挨拶…。
「いまだに沖縄に米軍基地で大きな負担をお願いし続けている。全国民を代表しておわび申し上げます。……(以下、略)」
誰が作文したかは不明だが、総理大臣の発言である以上、厳密さが求められる。揚げ足を取ろうというのではないことを断わっておく。
沖縄県民に対し(慰霊式典の挨拶であるから、沖縄戦の戦死者にも語りかけているのだろう)、「全国民を代表して」おわびするとは、どういうことか……? 沖縄県民は「全国民」の中には含まれていないのか。当然のことながら、沖縄県民は「全国民」の中に含まれるから、そうするとこの文章は以下のようになる。「沖縄県民を含めた全国民を代表して、沖縄県民におわび申しあげます」
なぜ、沖縄県民が沖縄県民におわびするのか…。もうお分かりだろう。そう、「全国民」とは、本土の住民、ヤマトンチューのことだったのだ。ここに無意識に表現されているのは、本土の住民と沖縄県民は別、もっと露骨に言えば、沖縄県民は「全国民」に含まれない異質な存在であるとの感情である。もう一度言う。揚げ足を取ろうというのではない。これが日本の為政者のずっと変らぬ沖縄差別の感情の無意識の表明であるということなのだ。沖縄県民は太平洋戦争で本土決戦を遅らせるための捨石にされ、敗戦後はアメリカに投げ売られ、そして復帰しても基地の重圧はそのまま残り、形式的に日本国民になったはずだが、一度として沖縄県民は実質的に日本国民になったことはなかったのだ。少なくとも権力者の意識の中では。沖縄は昔も今も歴史を通して日本という「国家」の外部にある。
政府は沖縄県議会・名護市議会の切り崩しと地元有力者へ振興策を餌にしての懐柔、つまり札束で頬っぺたを張り倒す策動をしていると聞く。しかし、民主党は参議院で候補者すら立てられなかった。沖縄の反基地闘争は抑えることは不可能だし、日米合意を履行しようとすれば、警察権力さらには自衛隊も出動させ、国家の暴力装置を総動員しなければ無理であろう。現在、日米軍事同盟にとっての脅威とは、北朝鮮情勢でも中国・台湾関係でもない。沖縄の反基地闘争こそが最大の脅威である。沖縄県民の反基地闘争に、もし政権与党が暴力装置を発動して弾圧に及んだとしたら、政府の反人民性を白日のもとに晒すことになる。沖縄反基地闘争は日米軍事同盟の喉首に突きつけられた刃なのだ。
以前の日記に書いたが、鳩山が学習して気づいた「抑止力の必要性」とは、飼いならされた多数の従順な本土の住民とは「異質な」沖縄県民の反基地闘争への「抑止力の必要性」だったのかもしれない。「友愛」を理念とする鳩山にとって、米国政府に屈服した以上、沖縄県民に対して権力の暴力装置の発動も辞さないとの決断はさすがにできなかったと考えるのは穿ちすぎだろうか。
さて、権力に不服従な存在は、異端者、異人、変人、狂人、精神障害者、反社会分子、社会不適合者、スパイ、アカ、共産主義者、非国民、売国奴、不逞の輩、テロリストなどのレッテルを貼って排除するのが常套手段である。「多数の常識」(偏見と差別意識を含んだ)におもねて、敵対勢力を孤立させる扇情的政治手法である。小泉「改革」路線に反対する者を、すべて「抵抗勢力」と名指したのも同様の手法だ。
自民党の麻生などは菅内閣を「社会主義政権」とレッテルを貼って揶揄している。これも有権者に生理的反感を喚起するための安直な常套手段だが、私は菅の名誉のためではなく、社会主義の名誉のためにあえて言おう。菅内閣は社会主義政権などではまったくないどころか、社会民主主義政権でさえもない。
※1:「世界で一番冷たい格差の国 日本〜アメリカでは住宅ローン破綻してもホームレスにならない」(光文社、矢部 武・著)9ページ
この問題では、いつも「官」と「民」という二項対立が設定される。自然科学ならいざ知らず、およそ人間社会において、このような二項対立での問題設定がなされる場合には、まず眉に唾をつけてかかった方がよいだろうというのが、私の基本的スタンスである。いくらデジタル社会であるといえども、コンピュータと現実の人間や社会とでは明らかに異なる。いわく、「善か悪か」「左か右か」「白か黒か」「保守か革新か」……。
まず「官」とは何か。言うまでもなく、中央政府と地方政府のこと。公共部門である。この活動は税金によって担われる。これを第1セクターと呼ぶ。
では「民」とは何か。鳩山は、これを「民間」という。この発想は一人鳩山に限らず、一般に歴代政府もマスコミの多数もこれに倣ってきた。しかし、ここに詐術が潜んでいる。「官」と「民」の二項対立で捉えるなら、中央政府と地方政府以外はすべて「民」すなわち「民間」となる。するとそこには、企業家・資本家も労働者も何もかもが含まれてしまう。
小泉に代表される新自由主義者が「官から民へ」と語る場合、規制緩和、公共部門の民営化、小さな政府の文脈で語られるから、「民」は「民間企業」を指すことはかなり明白である。ここで抜け落ちているのは、中央政府・地方政府と民間企業以外の存在である。それは民衆・市民・労働者である。ここではっきりするのは、新自由主義においては、政府と民間企業しかその発想の中に存在せず、民衆・市民は埒外に置かれていることだ。
鳩山の場合は、新自由主義者ほど明確ではなく曖昧である。それは小泉・竹中路線があまりにも評判を落としたために、露骨な新自由主義では支持を得られないことと、彼の「友愛」という抽象的理念からくるものであろうと推測される。
鳩山の主張は、国民が政府だけに頼らず、民間企業も一人ひとりの市民も公共社会の構成員・プレイヤーとしての自覚をもち活動していこうというようなことであろう。では、何が問題か。それは、まったく本質の異なるものを一緒くたにしてしまっていることである。
整理するため、まず第2セクターを設定しよう。これは民間企業、営利部門である。この本質は営利であり利潤追求にある。もちろん現代社会においては、法令順守(コンプライアンス)や企業の社会的責任が鋭く問われるとはいえ、本質は利潤追求にあり、それ以外の何物でもない。たとえ企業が寄付行為をしたり、文化・芸術への支援をしたり、環境問題に取組んだとしても、それらはあくまでも利潤追求に従属したものであって、利潤を無視、度外視して行われることはないし、逆にそれらに取組むことによって企業イメージを高めることで、長期的にはより大きな利潤に結びつけようとしているとも言えるのである。
では第3セクターとは。市民セクターである。ここには、NPO・NGO、市民団体、市民グループ、ボランティアグループ、自治会、消費生協、労働者協同組合、農業協同組合、労働組合など政府と民間企業以外の非政府組織がすべて含まれる。市民がある一定の目的を達成するため自主的・自発的に結成したグループ・団体のことである。
日本においては、この第3セクターの概念が決定的に弱く、ないしは無視・軽視されている。というよりも、第3セクターの意味が歪曲されてしまってさえいる。第3セクターと聞いて普通思い浮かべるのは、「3セク」と略称される悪名高い「第3セクター」であろう。つまり半官半民の企業体のことである。地方自治体に多いが、税金を投入し、民間企業から出資し、民間企業出身者が役員を務め、地方公務員が出向職員になって経営されるような企業体である。その多くが利潤を上げられずに経営破綻し、さらに破綻を糊塗するために追加の税金が投入され、それでも経営再建ができず税金が垂れ流されている。大阪府庁の移転先として取りざたされる大阪市のワールドトレードセンター(WTC)などがそうだ。欧米の概念が日本に導入される場合に往々にして起こるように、言葉の本来の意味がすりかえられてしまう典型例のひとつである。
日本においては腐りきってしまった「第3セクター」という言葉に本来の輝きを取り戻し再生させてやらねばならない。なぜなら第3セクターこそが、憲法における国民主権を担う主たるプレーヤーとして、また民主主義社会の担い手、社会変革の主体として重要な役割を有していると考えるからである。
米国は新自由主義の本場であり、自己責任・自助努力なる発想が横行し、したがって冷徹な競争社会と考えられがちだ。しかしそれだけでは、アメリカ社会を一面的に捉えたことにしかならないだろう。
「米国はたしかに市場主義が優先される社会だが、その一方で、市場主義にまったく従わないNPOが大きな力を持ち、公的サービス(福祉)分野で政府の代役を担っている。ある面、NPOが市場主義の暴走に歯止めをかけたり、市場主義の被害者などを救済したりすることで、社会のバランスを取っているのである。派遣切りや正社員切りなど解雇の問題にしても、『米国は簡単に首切りしている』というイメージがあるが、それは事実ではない。(※1)」
米国においてはNPOが福祉分野以外でも広範な公的サービスの担い手になっており、政府に対するロビー活動も活発に展開している。多くの市民が社会の担い手として自主・自立の精神、ボランティア精神を強く持っていると言えるだろう。
日本においてNPOに法的根拠が与えられたのは新しく、法人格が付与されたとはいえ、米国のように免税措置などの特典はほとんど無い状況である。多くの団体が財政的基盤は脆弱で、したがって専従職員の給与水準も劣悪、まさにボランティア精神のみによってかろうじて支えられているといったところが多い。貧困層を支えるNPOの職員自体が貧困層であるという皮肉な実態が横行している。自治体や企業の委託事業を請け負って、やっとその委託費・補助金などで細々と運営している。これでは、地方自治体業務の民間委託、下請け化、安上がり行政の補完物でしかないとも言える。
鳩山の腹の中には、国家財政の危機の中で、市民のボランティア活動をあてにしようとの意図がおそらくあっただろうと推測される。安上がり行政のための補完物である。
しかし第3セクターの活動の意義を、そのように矮小化してはならない。民主主義の根幹に関わる意義を確認しなければならないだろう。民主主義を市民自治と定義してみる。つまり、市民・民衆が政治・社会の主人公となって、政治・社会を自主的・自立的・民主的に動かす実践主体になることである。言い換えれば、第1セクターの中央・地方権力と利潤追求の民間企業の第2セクターに対する対抗勢力として第3セクターを強力に形成するのである。当然、ここにおいて民主主義の概念は、やはり手垢にまみれ腐りきってしまったものから、本来の輝きを取り戻し再生されることになる。
「民主主義(デモクラシー)」という言葉はどれだけ歪められ侮蔑されてきたことであろう。自由「民主」党の「民主」も、「民主」党の「民主」も、社「民」党の「民」も、民主主義なのであるから。政権与党にとっては、民主主義とは選挙で多数を占めることであり、議会で多数決で決めるということでしかない。選挙での多数と議会での多数、これが民主主義のすべてである。つまり民主主義とは多数決なのだ。では、野党にとっては……。「少数意見の尊重」である。つまりこれを合成すると、民主主義とは「議論をし、最終的に多数決で決めるが、小数意見も尊重されなければならない」というやせ細った理屈に帰結する。つまりは議会がすべて、これを議会主義という。ここでは労働者・市民・民衆は選挙で投票する有権者という意味に貶められる。
自民党政権の時代から現在の民主党中心の政権まで、地方分権・地域主権がお題目のように唱えられている。中央政府の仕事や財源を地方政府へ極力委譲することとして語られている。しかし、ここにも詐術がある。抽象的一般論として、「地方分権・地域主権」に反対する有権者はあまりいないだろう。反対するのは、自己の権限が削られる国家官僚くらいだ。住民サービスに、より直結するような公的業務は、地方自治体で担うことが望ましいのはその通りだ。だが問題は、公的業務が中央政府から地方政府へ委譲するという行政的・技術的観点に矮小化されてはならない。ここでも課題は、地方政府・地方権力に対抗する第3セクター・市民セクターが強力な主体を形成し得るかにある。
民主主義を市民自治と捉え、市民・民衆が政治・社会の主人公となって、自主的・自立的・民主的に社会を動かす実践主体となること。そう考えるなら、中央・地方権力の政策が反市民的であるとき、当然第3セクターの行動・存在は反体制・反権力の色彩を帯びざるを得ないだろう。これは歴史が物語っている。60年安保闘争然り、反戦・反基地・反核闘争然り、成田空港建設阻止の三里塚農民の闘争然り、現在の沖縄の普天間基地撤去闘争然り。企業の利潤追求至上主義に対する数々の反公害闘争、電力資本に対する反原発闘争、非正規切り・偽装請負に対するユニオンの闘いなどは国家権力と結びついた独占企業に対抗する反独占資本の闘いである。
断わっておくが、これらの運動が反体制・反権力の色彩を帯びているからと言って、そこに参加している市民・労働者が社会主義思想を持っているということを必ずしも意味してはいない。しかしながら、現状を変革し新たな社会を構想し展望する場合、それが社会主義であれ何であれ、現在の権力に対抗し得る市民・民衆・労働者の大衆的な運動主体の形成と思想的発展を抜きにしてはその実現はあり得ないだろう。
民主主義は、古代ギリシャのポリスにおける民主制を基とし、封建制王権に対するブルジョア市民革命の思想として新たに発展した。フランス革命に代表されるように、勃興してきた新興勢力であるブルジョア階級を担い手として、封建的桎梏を打破し、資本主義的経済活動の自由と市民的権利・自由と平等の獲得を求め絶対王政を打倒した。その時代においては、ブルジョア階級が民主主義の、自由と平等の、市民的権利の担い手であり社会進歩を代表していた。しかし、産業革命の進展によって大量の労働者階級が発生し、ブルジョア階級と労働者階級の利害は鋭く対立し、労働運動が勃興、社会主義思想が生まれる。ブルジョア市民革命期においては社会進歩の担い手であった資本家は、労働運動を弾圧し、資本家の利害を代表する権力は社会主義思想・社会主義者を弾圧・排除しようとする。ここにおいて民主主義はあくまでブルジョア民主主義の枠内に押し込めようとされ、市民的権利は選挙の投票のみに矮小化されていく。つまり民主主義を議会主義に貶めていくのだ。しかし労働者階級の粘り強い戦いによって、団結権、団体交渉権、スト権などの労働基本権が勝ち取られていく。さらに労働者は自主・自立の精神で資本家の搾取から生活を防衛するため消費者生協、労働者協同組合を結成していく。政府に対しては社会保障政策を求めて闘う。自由や平等を単なる理念や抽象的法に止まらせず、具体的な社会権としての制度保障を国家の責任として実施させていく。
さらに資本主義が独占資本主義段階になると、独占資本とその代弁者である政府は、労働者が勝ち取った権利さえも無効化しようと画策する。ブルジョア市民革命期には進歩的勢力であったブルジョアジーは反動的勢力に転化する。ブルジョア民主主義の限界を乗り越え、議会主義と形式的民主主義の枠を越えて、労働者階級が民主主義を発展させ実質化させる担い手となる。独占資本とその代弁者の政府による反動的政策・民主主義的諸権利の圧殺に対し、労働者階級だけでなく、知識層や広範な市民層が労働者とともに民主的諸闘争に結集してくる。
自由と平等に代表される民主主義は、単にブルジョア民主主義に限定されるものでは決してない。封建的身分制を打破した点において、ブルジョアジー市民革命はその時代において先進的であった。しかし、ブルジョアジーが権力を掌握すると、その自由と平等の理念と制度的保障を労働階級にまで波及させることを食い止めようとし、進歩的勢力から反動勢力へ転化していったのだ。したがって現代において、自由と平等を実質化させる民主主義闘争は労働者階級と、独占資本とその政府の反民主的政策に苦しむ広範な反独占諸階層の連帯した闘いによって社会変革の展望を切り開く闘いへと発展する可能性を内包している。
民主主義と社会主義を断絶した別のものと捉えるのは、民主主義をブルジョア民主主義としか理解し得ないからである。資本主義社会においても労働者・市民・民衆の自主的・自立的運動とコミュニテーの形成、社会・組織の運営・経営能力の獲得が問われる。労働者・民衆が社会を動かす能力を身につけなければ、たとえ社会主義革命が実現したとしても、一部テクノクラート官僚が国家の政策を牛耳るようなおよそ非民主的権力にしかならないだろう。もちろん将来に国家を廃絶するとしてもだ。20世紀型社会主義の反省の上に立つならば、民主主義概念が本来持っている自由と平等の理念を制度的に担い得る能力を持った多数の労働者・民衆の連帯と自己変革が問われるだろう。それは単に観念の中で実現されるものではなく、もちろん理論と思想の学習は必要ではあるが、現実の権力の反人民的政策に対抗する広範な運動を作り出していく実践を通して形成されていくだろうし、しなければならない。
私が第3セクターの重要性を強調するのは以上のような視点からである。日本の民衆に多く見られる「お上頼み」の没主体者、没主権者の発想を実践への参加を通して、いかに自己変革していくかが課題である。「お上」が上から作った第3セクターの現状を見ればいい。社団法人、財団法人、独立行政法人等々、国家官僚の天下り先で多額の税金を無駄遣いし、ろくな仕事をしていない。これらの無用の長物を本気で潰せば税金の節約は相当できるのだ。民衆に本当に必要な業務なら、「その浮いた税金をいくらか回せ、俺たちが自分で運営するから」と要求すればいい。よく労働者が職場で徹底的にストライキ闘争をやりぬいて、会社を倒産させてしまったら元も子もないと言う。しかし、この発想は、会社の経営は資本家・経営者がいなければできないと思い込んでいるに過ぎない。現実に倒産した会社を労働組合が自主再建して、労働者だけで経営している自主管理の企業が日本にもある。これが労働者協同組合方式である。ヨーロッパにおいては、この労働者協同組合方式による企業経営が長い伝統と実績を持っている。倒産企業の自主再建だけでなく、最初から労働者が集まり出資者になって企業を立ち上げ、自分たちで経営するのだ。労働者協同組合の法的裏づけもある。これを支える金融機関まで労働者が作ってしまっているところもある。日本にも労働金庫という労働組合出資の金融機関はある。とりあえずは、これを利用すればよい。日本においても、労働者協同組合の法整備を早急に勝ち取らねばならない。
菅首相が「第3の道」を提議した。これが新自由主義か福祉社会か、小さい政府か大きな政府か、さらに資本主義か社会主義かという二項対立になっていない点で、その誤魔化しは巧妙である。次回、これを批判的に検討しよう。
6月23日、沖縄慰霊の日。菅首相は慰霊式典に参列した。そこでの挨拶…。
「いまだに沖縄に米軍基地で大きな負担をお願いし続けている。全国民を代表しておわび申し上げます。……(以下、略)」
誰が作文したかは不明だが、総理大臣の発言である以上、厳密さが求められる。揚げ足を取ろうというのではないことを断わっておく。
沖縄県民に対し(慰霊式典の挨拶であるから、沖縄戦の戦死者にも語りかけているのだろう)、「全国民を代表して」おわびするとは、どういうことか……? 沖縄県民は「全国民」の中には含まれていないのか。当然のことながら、沖縄県民は「全国民」の中に含まれるから、そうするとこの文章は以下のようになる。「沖縄県民を含めた全国民を代表して、沖縄県民におわび申しあげます」
なぜ、沖縄県民が沖縄県民におわびするのか…。もうお分かりだろう。そう、「全国民」とは、本土の住民、ヤマトンチューのことだったのだ。ここに無意識に表現されているのは、本土の住民と沖縄県民は別、もっと露骨に言えば、沖縄県民は「全国民」に含まれない異質な存在であるとの感情である。もう一度言う。揚げ足を取ろうというのではない。これが日本の為政者のずっと変らぬ沖縄差別の感情の無意識の表明であるということなのだ。沖縄県民は太平洋戦争で本土決戦を遅らせるための捨石にされ、敗戦後はアメリカに投げ売られ、そして復帰しても基地の重圧はそのまま残り、形式的に日本国民になったはずだが、一度として沖縄県民は実質的に日本国民になったことはなかったのだ。少なくとも権力者の意識の中では。沖縄は昔も今も歴史を通して日本という「国家」の外部にある。
政府は沖縄県議会・名護市議会の切り崩しと地元有力者へ振興策を餌にしての懐柔、つまり札束で頬っぺたを張り倒す策動をしていると聞く。しかし、民主党は参議院で候補者すら立てられなかった。沖縄の反基地闘争は抑えることは不可能だし、日米合意を履行しようとすれば、警察権力さらには自衛隊も出動させ、国家の暴力装置を総動員しなければ無理であろう。現在、日米軍事同盟にとっての脅威とは、北朝鮮情勢でも中国・台湾関係でもない。沖縄の反基地闘争こそが最大の脅威である。沖縄県民の反基地闘争に、もし政権与党が暴力装置を発動して弾圧に及んだとしたら、政府の反人民性を白日のもとに晒すことになる。沖縄反基地闘争は日米軍事同盟の喉首に突きつけられた刃なのだ。
以前の日記に書いたが、鳩山が学習して気づいた「抑止力の必要性」とは、飼いならされた多数の従順な本土の住民とは「異質な」沖縄県民の反基地闘争への「抑止力の必要性」だったのかもしれない。「友愛」を理念とする鳩山にとって、米国政府に屈服した以上、沖縄県民に対して権力の暴力装置の発動も辞さないとの決断はさすがにできなかったと考えるのは穿ちすぎだろうか。
さて、権力に不服従な存在は、異端者、異人、変人、狂人、精神障害者、反社会分子、社会不適合者、スパイ、アカ、共産主義者、非国民、売国奴、不逞の輩、テロリストなどのレッテルを貼って排除するのが常套手段である。「多数の常識」(偏見と差別意識を含んだ)におもねて、敵対勢力を孤立させる扇情的政治手法である。小泉「改革」路線に反対する者を、すべて「抵抗勢力」と名指したのも同様の手法だ。
自民党の麻生などは菅内閣を「社会主義政権」とレッテルを貼って揶揄している。これも有権者に生理的反感を喚起するための安直な常套手段だが、私は菅の名誉のためではなく、社会主義の名誉のためにあえて言おう。菅内閣は社会主義政権などではまったくないどころか、社会民主主義政権でさえもない。
※1:「世界で一番冷たい格差の国 日本〜アメリカでは住宅ローン破綻してもホームレスにならない」(光文社、矢部 武・著)9ページ
|
|
|
|
コメント(7)
「労働者協同組合」も「労働組合」も「消費者生活協同組合」も「農業協同組合」も、本来の意味を喪失し、ひたすら幹部の利権拡大と利潤追求に奔走し、のみならず、そこに働く専従職員労働者の生存権保障すらせずにワーキングプアに落とし込めているところも多数存在します。
私自身が労働組合の専従書記や労働者協同組合もどきやNPOでも働いたことがありますから、その実情は直接体験しています。
どのような理念を持った組織、団体であっても、結局は民主主義が貫徹させられるかどうかにかかっています。幹部請負になってしまい、民主主義が機能しなくなった組織においては、利潤追求の資本主義企業となんら変らないかのような腐敗と堕落、理念の喪失に至ります。
したがって、民主主義が、社会主義が、第3セクターが、労働組合が、協同組合が、労働者・市民・民衆の歴史的闘いによって勝ち取られ、そこに崇高な理念が存在し、先人たちの闘いの血と汗の結晶であるにもかかわらず、その理念が薄汚れてしまい、労働者・民主的市民・民衆の反発・離反さえ生じさせかねない状況にあることは事実です。
しかし、その状況に屈してしまって、それらの理念を捨て去るのではなく、その言葉の本来の理念・意味を実践・運動を通して再生させること、その本来の輝きを奪還することが課題であると、私は一貫して考えています。
日本国憲法もブルジョア民主主義憲法であり社会主義憲法ではありません。しかしながら、ブルジョア民主主義的自由権に止まらず、労働者・市民・民衆が闘いの中で勝ち取ってきた社会権・社会的生存権が明文化されています。
民主主義理念の中核概念である基本的人権は、言論の自由、集会結社の自由、思想信条の自由などに代表される自由権に止まらず、憲法25条に代表される社会的・文化的生存権をも含有しています。これと9条とが不可分に結合されるとき、平和的・社会的・文化的生存権が保障され、社会変革の強力な条件を形成することになります。
私自身が労働組合の専従書記や労働者協同組合もどきやNPOでも働いたことがありますから、その実情は直接体験しています。
どのような理念を持った組織、団体であっても、結局は民主主義が貫徹させられるかどうかにかかっています。幹部請負になってしまい、民主主義が機能しなくなった組織においては、利潤追求の資本主義企業となんら変らないかのような腐敗と堕落、理念の喪失に至ります。
したがって、民主主義が、社会主義が、第3セクターが、労働組合が、協同組合が、労働者・市民・民衆の歴史的闘いによって勝ち取られ、そこに崇高な理念が存在し、先人たちの闘いの血と汗の結晶であるにもかかわらず、その理念が薄汚れてしまい、労働者・民主的市民・民衆の反発・離反さえ生じさせかねない状況にあることは事実です。
しかし、その状況に屈してしまって、それらの理念を捨て去るのではなく、その言葉の本来の理念・意味を実践・運動を通して再生させること、その本来の輝きを奪還することが課題であると、私は一貫して考えています。
日本国憲法もブルジョア民主主義憲法であり社会主義憲法ではありません。しかしながら、ブルジョア民主主義的自由権に止まらず、労働者・市民・民衆が闘いの中で勝ち取ってきた社会権・社会的生存権が明文化されています。
民主主義理念の中核概念である基本的人権は、言論の自由、集会結社の自由、思想信条の自由などに代表される自由権に止まらず、憲法25条に代表される社会的・文化的生存権をも含有しています。これと9条とが不可分に結合されるとき、平和的・社会的・文化的生存権が保障され、社会変革の強力な条件を形成することになります。
憲法の条文改悪のみが問題ではなく、憲法が存在しながらも9条・25条などの実質が空洞化させられ、結果的に憲法を改悪したのに近い状況に至っていることが問題です。
日本国憲法に保障された諸権利を運動の力で実質化していくことを抜きに、さらなる社会変革への可能性も生まれません。憲法の実質化の運動は、反戦平和運動と反格差・反貧困・均等待遇実現・労働者派遣法の抜本改正の闘いを通して、憲法が労働者・市民・民衆の社会変革の武器になることを実感することにより、貶められた日本国憲法の輝きを取り戻すことができるのです。
私の考えは、民主主義と社会主義は対立する別の理念・概念ではなく、民主主義の徹底の過程を通して民主主義的な社会主義が勝ち取られるというものです。民主主義の徹底を通しての社会主義でない限り、全体主義的社会主義、国家権力が肥大した社会主義、党官僚と国家官僚の支配する社会主義、中央集権的社会主義、非民主主義的社会主義、民族主義的社会主義、一国社会主義のような20世紀的社会主義の亜種を繰り返すだけだと考えているのです。
この闘いにおいて重要な要素・条件は、グローバル資本主義との対決ですから、国際的な労働者・民主的市民・反グローバリズム民衆との国際連帯です。
日米軍事同盟解体の闘いも、日本・米国・アジア・中東民衆の国際連帯の力を抜きには達成されないでしょう。常に支配の論理は「分断して統治せよ」であります。独占資本権力は、民衆の闘いを極力一地域内に、一国内に閉じ込め分断しようとします。グローバル資本家階級と、そのお零れに寄生する勢力と、グローバル資本主義の横暴によって痛めつけられ貧困化していく民衆・労働者の数を比較するなら、後者の方が圧倒的な多数派です。だから、彼らが地域の枠を越え、国境を越えて結びつくことを一番恐れています。
地域主義、セクショナリズム、セクト主義、民族主義、ナショナリズムのイデオロギー的壁を突破して行く反グローバリズムの国際連帯闘争が問われます。
日本国憲法に保障された諸権利を運動の力で実質化していくことを抜きに、さらなる社会変革への可能性も生まれません。憲法の実質化の運動は、反戦平和運動と反格差・反貧困・均等待遇実現・労働者派遣法の抜本改正の闘いを通して、憲法が労働者・市民・民衆の社会変革の武器になることを実感することにより、貶められた日本国憲法の輝きを取り戻すことができるのです。
私の考えは、民主主義と社会主義は対立する別の理念・概念ではなく、民主主義の徹底の過程を通して民主主義的な社会主義が勝ち取られるというものです。民主主義の徹底を通しての社会主義でない限り、全体主義的社会主義、国家権力が肥大した社会主義、党官僚と国家官僚の支配する社会主義、中央集権的社会主義、非民主主義的社会主義、民族主義的社会主義、一国社会主義のような20世紀的社会主義の亜種を繰り返すだけだと考えているのです。
この闘いにおいて重要な要素・条件は、グローバル資本主義との対決ですから、国際的な労働者・民主的市民・反グローバリズム民衆との国際連帯です。
日米軍事同盟解体の闘いも、日本・米国・アジア・中東民衆の国際連帯の力を抜きには達成されないでしょう。常に支配の論理は「分断して統治せよ」であります。独占資本権力は、民衆の闘いを極力一地域内に、一国内に閉じ込め分断しようとします。グローバル資本家階級と、そのお零れに寄生する勢力と、グローバル資本主義の横暴によって痛めつけられ貧困化していく民衆・労働者の数を比較するなら、後者の方が圧倒的な多数派です。だから、彼らが地域の枠を越え、国境を越えて結びつくことを一番恐れています。
地域主義、セクショナリズム、セクト主義、民族主義、ナショナリズムのイデオロギー的壁を突破して行く反グローバリズムの国際連帯闘争が問われます。
私は、社会民主主義が福祉社会の理念によって、よりましな資本主義を実現し、資本主義を延命させようとする制度であると本質規定しています。しかしながら、社会民主主義を排除することは誤りであるとも考えます。
今日の国内的、さらに地球的な貧困化と格差の増大に対して、社会主義革命、世界的な社会主義への移行の彼方まで現状を放置することができないからです。
国内的、国際的な労働者・市民・民衆の闘いの多数が社会主義思想に変革されるには、やはり現実の闘いと運動の経験を通しての試行錯誤が必要であります。もちろん思想闘争・理論闘争は重要ですが、文献的学習を通してのみ社会主義思想に到達するのは、どうしても労働者・市民・民衆の中でも相対的な知識層に限られてしまい勝ちだからです。
さらに、戦争状態、内乱状態、経済恐慌などの危機的状況を利用して社会主義革命が達成され得るとする「危機待望論」にも、私は組みしません。それでは、あまりにも労働者・民衆・市民の犠牲が大き過ぎるからです。
もう以上で、菅政権の「第3の道」への基本的批判は網羅し得たでしょう。
社会民主主義的な福祉社会でもなく、ケインズ的修正資本主義による公共事業中心の国家資本主義でもなく、市場原理主義=新自由主義でもない、ましてや社会主義でもない「第3の道」とはこの世に存在するのか?
結局のところ、菅が大好きな英国流民主主義=議会主義の中における、二つの潮流、つまり社会民主義的な福祉社会(揺りかごから墓場まで)を代表する労働党とサッチャーリズムに体現された新自由主義とのそれぞれの弱点を中和・是正させ誤魔化そうとしたブレア労働党政権そのものでしかないのです。
しかし、ブレア政権は惨めに崩壊しました。これが「第3の道」というなら喜劇でしかありません。
今日の国内的、さらに地球的な貧困化と格差の増大に対して、社会主義革命、世界的な社会主義への移行の彼方まで現状を放置することができないからです。
国内的、国際的な労働者・市民・民衆の闘いの多数が社会主義思想に変革されるには、やはり現実の闘いと運動の経験を通しての試行錯誤が必要であります。もちろん思想闘争・理論闘争は重要ですが、文献的学習を通してのみ社会主義思想に到達するのは、どうしても労働者・市民・民衆の中でも相対的な知識層に限られてしまい勝ちだからです。
さらに、戦争状態、内乱状態、経済恐慌などの危機的状況を利用して社会主義革命が達成され得るとする「危機待望論」にも、私は組みしません。それでは、あまりにも労働者・民衆・市民の犠牲が大き過ぎるからです。
もう以上で、菅政権の「第3の道」への基本的批判は網羅し得たでしょう。
社会民主主義的な福祉社会でもなく、ケインズ的修正資本主義による公共事業中心の国家資本主義でもなく、市場原理主義=新自由主義でもない、ましてや社会主義でもない「第3の道」とはこの世に存在するのか?
結局のところ、菅が大好きな英国流民主主義=議会主義の中における、二つの潮流、つまり社会民主義的な福祉社会(揺りかごから墓場まで)を代表する労働党とサッチャーリズムに体現された新自由主義とのそれぞれの弱点を中和・是正させ誤魔化そうとしたブレア労働党政権そのものでしかないのです。
しかし、ブレア政権は惨めに崩壊しました。これが「第3の道」というなら喜劇でしかありません。
社会民主主義は税が高負担であるが、高福祉社会になる。しかし問題は大きな国家をもたらし、国家財政が逼迫するという弱点をもつ。いくら税を上げると言っても、国内企業の競争力も維持しつつ、労働者・市民の不満も生じさせないようにしようとすれば、自ずと税額のアップに限界がある。
一方、露骨なまでの新自由主義では国内独占企業の国際競争力は維持できるが、労働者・市民の貧困化、セーフティネットの綻びをもたらすことで労働者・市民の政府批判が増大するという弱点をもつ。
そこで、国家財政も悪化させず、経済成長も保持し、労働者の雇用も福祉も一定保障するというのが資本主義維持万能薬、すなわちブレアの「第3の道」=菅政権なのである。しかしながら、そんな便利で万能、オールマイティの資本主義維持機能などは不可能なのだ。
なぜなら現代資本主義における最大の問題は、グローバル多国籍企業の横暴にいかに規制をかけるかにあるのだから。一国内の折衷主義的な政策によっては、いかんともし難い状況にあるのだ。これは単なる矛盾の先送りにしか過ぎない。
そのことは、菅首相が出席したG8サミットにおいても、なんら実質的合意を得られなかったことでも明らかである。もはや「先進国」首脳だけで会議をしたところで、それぞれの「国益」が齟齬をきたすので実効性のある対策など産まれないのだ。グローバル多国籍企業とハゲタカファンドに対し、彼らだけで規制をかけられるはずがないだろう。なぜなら、「先進国」首脳とは多国籍企業とハゲタカファンドに支えられている存在に他ならないからだ。
「ブレア=菅=第3の道」は、修正・新自由主義と定義してもいいのではないか。市場に任せておけば景気も雇用もすべてうまく調整されるという市場万能論=新自由主義が必ずしも有効には機能せず、「市場の失敗」も現実に起こるとの経験から、やはりある程度は政府が市場に介入する必要があるとの観点に立った修正である。
福祉社会、ケインズ型公共事業による景気刺激・雇用創出社会は、ともに大きな社会をもたらし、国家財政に不安要因となり税の上昇を帰結しやすい。
一方、露骨なまでの新自由主義では国内独占企業の国際競争力は維持できるが、労働者・市民の貧困化、セーフティネットの綻びをもたらすことで労働者・市民の政府批判が増大するという弱点をもつ。
そこで、国家財政も悪化させず、経済成長も保持し、労働者の雇用も福祉も一定保障するというのが資本主義維持万能薬、すなわちブレアの「第3の道」=菅政権なのである。しかしながら、そんな便利で万能、オールマイティの資本主義維持機能などは不可能なのだ。
なぜなら現代資本主義における最大の問題は、グローバル多国籍企業の横暴にいかに規制をかけるかにあるのだから。一国内の折衷主義的な政策によっては、いかんともし難い状況にあるのだ。これは単なる矛盾の先送りにしか過ぎない。
そのことは、菅首相が出席したG8サミットにおいても、なんら実質的合意を得られなかったことでも明らかである。もはや「先進国」首脳だけで会議をしたところで、それぞれの「国益」が齟齬をきたすので実効性のある対策など産まれないのだ。グローバル多国籍企業とハゲタカファンドに対し、彼らだけで規制をかけられるはずがないだろう。なぜなら、「先進国」首脳とは多国籍企業とハゲタカファンドに支えられている存在に他ならないからだ。
「ブレア=菅=第3の道」は、修正・新自由主義と定義してもいいのではないか。市場に任せておけば景気も雇用もすべてうまく調整されるという市場万能論=新自由主義が必ずしも有効には機能せず、「市場の失敗」も現実に起こるとの経験から、やはりある程度は政府が市場に介入する必要があるとの観点に立った修正である。
福祉社会、ケインズ型公共事業による景気刺激・雇用創出社会は、ともに大きな社会をもたらし、国家財政に不安要因となり税の上昇を帰結しやすい。
その政権の失敗の対案として新自由主義を柱にする政権が登場する。日本では中曽根、米国ではレーガン、英国のサッチャーである。ここでは行政改革が強調されるが、それは前政権までの大きな政府を極力スリム化することで、徹底した民営化が強行される。中曽根の国鉄・電々公社・専売公社の民営化だ。
その後に続く政権により、修正・新自由主義が登場する。ここでも行政改革は引き続き課題になる。ここでは単純な民営化路線ではない。「市場の失敗」があることは経験済みなのだから。米国クリントン民主党政権、英国ブレア政権などがそれにあたるのではないか。
ここでの(とりあえず第3の道でくくっておく)行政改革は「ニューパブリック・マネジメント(NPM)理論」に基づいているものと考えられる。それは政府・公的セクターも私企業と同じような合理的マネジメントを行おうとする考えだ。行政施策の遂行に際して目的の明確化を行い、投入した予算(税金)に対して、どれだけの効果・成果が得られたかを数値的に表し、業績評価を行う。そして結果を公表する。民間企業のように費用対効果を重視する。したがって国民は民間企業の顧客や株主のような位置づけになる。
もしこれが厳密に実行されるなら、日本におけるようなほとんど車の通らない立派な道路や飛行機が一日一便しか飛ばない地方空港や乗降客が極めて少ない田んぼの中の新幹線駅などは作られなかったとは言える。
しかし日本においては、中曽根新自由主義政権の行革でも、国鉄・電々・専売の民営化は強行したが、官僚の天下り先である特殊法人・独立行政法人・公社・公団などの非効率な行政組織は温存され、必ずしも小さい政府が徹底されたわけでもない。上記三者の民営化は中曽根が後に語るように、公労協の戦闘的労働組合潰しという極めて政治的な狙いでなされたものなのだ。
橋本政権行革でも中央省庁が合体されて巨大官庁を生み出しただけで、むしろ中央官僚の権限が強化されたとも言えるものだ。
一挙に鳩山内閣へ飛ぶが、「政治とカネ」「普天間基地」に終始した感がある。その蔭で重要な課題が積み残された。労働者派遣法の抜本改正である。総選挙前の民主・社民・国民新の三党合意より後退したが、しかもそれすら通らなかったのである。
小泉退陣以降の大きな課題の一つが反貧困・反格差・解雇規制・雇用安定・均等待遇・労働者派遣法抜本改正などを通して雇用と福祉の整合的な政策立案を図ることであったことを考えると、鳩山政権の失態の責任は重い。
外交・安保・基地が焦点化されたことは歓迎すべきことだが、一方消費税に話題が集中しマスコミも与野党も反貧困・反格差は忘却の彼方へ沈みつつある。反貧困ネットやユニオンで運動を再構築するしかないのだが。この課題に熱心な社民党・共産党の奮闘にも期待したい。
その後に続く政権により、修正・新自由主義が登場する。ここでも行政改革は引き続き課題になる。ここでは単純な民営化路線ではない。「市場の失敗」があることは経験済みなのだから。米国クリントン民主党政権、英国ブレア政権などがそれにあたるのではないか。
ここでの(とりあえず第3の道でくくっておく)行政改革は「ニューパブリック・マネジメント(NPM)理論」に基づいているものと考えられる。それは政府・公的セクターも私企業と同じような合理的マネジメントを行おうとする考えだ。行政施策の遂行に際して目的の明確化を行い、投入した予算(税金)に対して、どれだけの効果・成果が得られたかを数値的に表し、業績評価を行う。そして結果を公表する。民間企業のように費用対効果を重視する。したがって国民は民間企業の顧客や株主のような位置づけになる。
もしこれが厳密に実行されるなら、日本におけるようなほとんど車の通らない立派な道路や飛行機が一日一便しか飛ばない地方空港や乗降客が極めて少ない田んぼの中の新幹線駅などは作られなかったとは言える。
しかし日本においては、中曽根新自由主義政権の行革でも、国鉄・電々・専売の民営化は強行したが、官僚の天下り先である特殊法人・独立行政法人・公社・公団などの非効率な行政組織は温存され、必ずしも小さい政府が徹底されたわけでもない。上記三者の民営化は中曽根が後に語るように、公労協の戦闘的労働組合潰しという極めて政治的な狙いでなされたものなのだ。
橋本政権行革でも中央省庁が合体されて巨大官庁を生み出しただけで、むしろ中央官僚の権限が強化されたとも言えるものだ。
一挙に鳩山内閣へ飛ぶが、「政治とカネ」「普天間基地」に終始した感がある。その蔭で重要な課題が積み残された。労働者派遣法の抜本改正である。総選挙前の民主・社民・国民新の三党合意より後退したが、しかもそれすら通らなかったのである。
小泉退陣以降の大きな課題の一つが反貧困・反格差・解雇規制・雇用安定・均等待遇・労働者派遣法抜本改正などを通して雇用と福祉の整合的な政策立案を図ることであったことを考えると、鳩山政権の失態の責任は重い。
外交・安保・基地が焦点化されたことは歓迎すべきことだが、一方消費税に話題が集中しマスコミも与野党も反貧困・反格差は忘却の彼方へ沈みつつある。反貧困ネットやユニオンで運動を再構築するしかないのだが。この課題に熱心な社民党・共産党の奮闘にも期待したい。
次に消費税増額問題に触れる。
消費税1%引き上げると年間税収が2.4兆円アップするという。財務官僚主導、菅政権追従の消費税10%(5%増税)路線で、新たに毎年12兆円の税金が市民からふんだくられる。
財政が苦しいという。今年度の政府予算は92兆3000億円。うち税収は37兆4000億円。不足分は国債発行による借金。なるほどこの数字だけを見れば国家財政は確かに苦しい。
しかし、この数字は「一般会計」の話。政府の一般財政は?一般会計?特別会計?政府関係機関からなる。?は、日本政策投資銀行、国際協力銀行、独立行政法人住宅金融支援機構さらに国民生活・農林漁業・中小企業・公営企業・沖縄振興開発など金融公庫。ここにも問題ありだが、省略。
?は消費税、所得税、法人税などを主な財源とする。
?について。特別会計(特会)とは、年金保険料(年金特会)、雇用保険料(労働保険特会)、道路や空港整備に使われるガソリン税や空港税(社会資本整備事業特会)など、特定の目的のために国民が支払う税金・保険料を管理する会計で、全部で18ある。いわゆる「霞ヶ関の埋蔵金」の原資となるカネのことだ。年間予算総額176兆円に達し、一般会計よりはるかに多い。
家計にたとえて言えば、衣食住などの生活必需品にかける不可欠の金額より、呑み代、交際費、奢侈品、遊興費などに多額のカネを回して、家計が苦しいからと親戚・友人・知人に金をせびる輩みたいな破綻者だ。そいつは誰からも信用されないだろう。日本国家とは不逞の輩、特別会計とは放蕩息子なのだ。
特別会計は、予算審議でも細かい点にまでは注意が行き届かず、予算が決まった後は所管の官庁にその管理が委ねられるため、一種のブラックボックスになっていることが多い。これは国家財政の「公開の原則」からの逸脱だ。独立行政法人をはじめ、各種の外郭団体との結びつきも特別会計経由であることが多い。国の予算原則は「予算単一主義あるいは総予算主義」であって一体であるべきで、これに反する「二重予算」、「官僚の隠し金庫」である。
特別会計に剰余金(年度内に使い切らず残高が発生した場合)が発生したからといって、自動的に一般会計に繰り入れられるというわけではない。剰余金は積み立てられていく。国家財政が苦しいなら、なぜ特別会計を「特別」扱いするのか。霞ヶ関の官僚たちが、巨額なヘソクリを手放したくないからだ。歴代自民党政府が官僚と一体になってこれを許容してきたし、今また菅政府は霞ヶ関に屈服した。
そもそも民主党は、政権交代前、マニフェスト実行に必要な財源は「一般会計と特別会計を合わせた総予算207兆円を組み替えることで捻出できる」と総予算主義の原則に立って特別会計に踏み込むと言っていたではないか。消費税増税を打ち上げてから、「(今年の)10月中旬から特別会計を対象にした事業仕分け第3弾を実施する」と今さら言ってみたところで、単なるアリバイ工作でしかないのはミエミエではないか。政権交代後、最優先に取組むべきだったものを放置して、今頃言ってみたところで誰も信用などしない。じゃあ過去2回の事業仕分けは何だったのだ。優先順位も順番も滅茶苦茶だろう。枝を刈っても幹を切り倒さなかったなら、いくらでもムダという名の枝は伸びてくるのだから。
消費税1%引き上げると年間税収が2.4兆円アップするという。財務官僚主導、菅政権追従の消費税10%(5%増税)路線で、新たに毎年12兆円の税金が市民からふんだくられる。
財政が苦しいという。今年度の政府予算は92兆3000億円。うち税収は37兆4000億円。不足分は国債発行による借金。なるほどこの数字だけを見れば国家財政は確かに苦しい。
しかし、この数字は「一般会計」の話。政府の一般財政は?一般会計?特別会計?政府関係機関からなる。?は、日本政策投資銀行、国際協力銀行、独立行政法人住宅金融支援機構さらに国民生活・農林漁業・中小企業・公営企業・沖縄振興開発など金融公庫。ここにも問題ありだが、省略。
?は消費税、所得税、法人税などを主な財源とする。
?について。特別会計(特会)とは、年金保険料(年金特会)、雇用保険料(労働保険特会)、道路や空港整備に使われるガソリン税や空港税(社会資本整備事業特会)など、特定の目的のために国民が支払う税金・保険料を管理する会計で、全部で18ある。いわゆる「霞ヶ関の埋蔵金」の原資となるカネのことだ。年間予算総額176兆円に達し、一般会計よりはるかに多い。
家計にたとえて言えば、衣食住などの生活必需品にかける不可欠の金額より、呑み代、交際費、奢侈品、遊興費などに多額のカネを回して、家計が苦しいからと親戚・友人・知人に金をせびる輩みたいな破綻者だ。そいつは誰からも信用されないだろう。日本国家とは不逞の輩、特別会計とは放蕩息子なのだ。
特別会計は、予算審議でも細かい点にまでは注意が行き届かず、予算が決まった後は所管の官庁にその管理が委ねられるため、一種のブラックボックスになっていることが多い。これは国家財政の「公開の原則」からの逸脱だ。独立行政法人をはじめ、各種の外郭団体との結びつきも特別会計経由であることが多い。国の予算原則は「予算単一主義あるいは総予算主義」であって一体であるべきで、これに反する「二重予算」、「官僚の隠し金庫」である。
特別会計に剰余金(年度内に使い切らず残高が発生した場合)が発生したからといって、自動的に一般会計に繰り入れられるというわけではない。剰余金は積み立てられていく。国家財政が苦しいなら、なぜ特別会計を「特別」扱いするのか。霞ヶ関の官僚たちが、巨額なヘソクリを手放したくないからだ。歴代自民党政府が官僚と一体になってこれを許容してきたし、今また菅政府は霞ヶ関に屈服した。
そもそも民主党は、政権交代前、マニフェスト実行に必要な財源は「一般会計と特別会計を合わせた総予算207兆円を組み替えることで捻出できる」と総予算主義の原則に立って特別会計に踏み込むと言っていたではないか。消費税増税を打ち上げてから、「(今年の)10月中旬から特別会計を対象にした事業仕分け第3弾を実施する」と今さら言ってみたところで、単なるアリバイ工作でしかないのはミエミエではないか。政権交代後、最優先に取組むべきだったものを放置して、今頃言ってみたところで誰も信用などしない。じゃあ過去2回の事業仕分けは何だったのだ。優先順位も順番も滅茶苦茶だろう。枝を刈っても幹を切り倒さなかったなら、いくらでもムダという名の枝は伸びてくるのだから。
財務省主計局が作成した資料がある。今年初め、民主党特会改革チームの要請で提出されたものだ。
06、07、08年度の特別会計の「不用額」。事業実施のために予算計上されながら、年度内に使いきれなかったカネを指す。
◎06年度…10兆5308億円
◎07年度…10兆8259億円
◎08年度…11兆7625億円
年間10〜12兆円の巨額の財源が「埋蔵金」として積みあがっていく。元々余るような甘い予算計上をしているということでもある。一般会計なら、使い残しがあれば翌年度は予算が削られるというのに。
消費税増額による12兆円を市民から徴収しなくても、これを使えばかなり賄えるのだ。
「やっぱり財源がなかったじゃないか」などと連立政権を批判した自民党や、そこから飛び出した新党の連中は、政権与党にいたのだから、こんな構造は分かっているのだ。分かっていながら「批判」をする。白々しいにもほどがある。それとも官僚に騙されて、本当に分かっていなかったのか。それじゃあ統治能力がなかったということだ。
政治主導、官僚の天下り根絶、ムダの排除などは、この特別会計問題に集約されていく。それぞれが別の問題ではない。もちろん、これを本気でやろうとすれば、霞ヶ関官僚との熾烈な闘いになるだろうことは明白ではある。しかし、財布のヒモが無いに等しい野放図なドラ息子を放置したままで、市民に財布のヒモを緩めろと強要しても、いったい誰が納得するというのだ。
官僚主導の菅内閣。マニフェストのトップに「官僚主導」と書け!
菅さん、あんたの正直な本音をオレが代弁してやる。
「ドラ息子を怒らせると怖い。何をされるか分からない」
鳩山は退陣に際し、「政治の言葉が国民に届かなくなった」と捨て台詞を吐いた。そうじゃないだろ! 国民(労働者・民衆)の声に耳を閉ざし、官僚の言葉に耳を傾け、官僚の言葉が届きすぎたんだよ。
菅さん、あんたの言葉はハナから空疎でオレには何も届かないよ。空きカンを蹴飛ばしたらカンカラカンと虚しく響くだけだ。
※「週間ポスト」7月16日号、「日本の財政 何が問題か」(湯本雅士、岩波書店)を参照・引用した。
◎以下の山猫さんの日記も参照ください。
「消費税ー北欧等と何が違うか」
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1531414646&owner_id=20473279
06、07、08年度の特別会計の「不用額」。事業実施のために予算計上されながら、年度内に使いきれなかったカネを指す。
◎06年度…10兆5308億円
◎07年度…10兆8259億円
◎08年度…11兆7625億円
年間10〜12兆円の巨額の財源が「埋蔵金」として積みあがっていく。元々余るような甘い予算計上をしているということでもある。一般会計なら、使い残しがあれば翌年度は予算が削られるというのに。
消費税増額による12兆円を市民から徴収しなくても、これを使えばかなり賄えるのだ。
「やっぱり財源がなかったじゃないか」などと連立政権を批判した自民党や、そこから飛び出した新党の連中は、政権与党にいたのだから、こんな構造は分かっているのだ。分かっていながら「批判」をする。白々しいにもほどがある。それとも官僚に騙されて、本当に分かっていなかったのか。それじゃあ統治能力がなかったということだ。
政治主導、官僚の天下り根絶、ムダの排除などは、この特別会計問題に集約されていく。それぞれが別の問題ではない。もちろん、これを本気でやろうとすれば、霞ヶ関官僚との熾烈な闘いになるだろうことは明白ではある。しかし、財布のヒモが無いに等しい野放図なドラ息子を放置したままで、市民に財布のヒモを緩めろと強要しても、いったい誰が納得するというのだ。
官僚主導の菅内閣。マニフェストのトップに「官僚主導」と書け!
菅さん、あんたの正直な本音をオレが代弁してやる。
「ドラ息子を怒らせると怖い。何をされるか分からない」
鳩山は退陣に際し、「政治の言葉が国民に届かなくなった」と捨て台詞を吐いた。そうじゃないだろ! 国民(労働者・民衆)の声に耳を閉ざし、官僚の言葉に耳を傾け、官僚の言葉が届きすぎたんだよ。
菅さん、あんたの言葉はハナから空疎でオレには何も届かないよ。空きカンを蹴飛ばしたらカンカラカンと虚しく響くだけだ。
※「週間ポスト」7月16日号、「日本の財政 何が問題か」(湯本雅士、岩波書店)を参照・引用した。
◎以下の山猫さんの日記も参照ください。
「消費税ー北欧等と何が違うか」
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1531414646&owner_id=20473279
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
グローバル・ピース!格差NO! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
グローバル・ピース!格差NO!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90017人
- 2位
- 酒好き
- 170665人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人