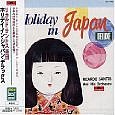ToruMontyさん
こんばんは!
いつもこのサイトを楽しく拝見させていただき、ありがとうございます。
今 ちゃいこさんからお送りいただいた
お手製の『想い出のヒット曲』集を聞いて
涙しています。
ニニ・ロッソの『夜空のトランペット』は
父からかりて、学校のお昼の校内放送のテーマ曲に使いました。
昼間に夜空をみる!!
これこそ音楽がかもしだす、自由な空間です。
ウーゴ・ブランコの『コーヒー・ルンバ』も懐かしい〜!!
かつて我が家には月の形の上に美女が横たわっているジャケットがありました。
ビリー・ヴォーンの『星を求めて』も、何かのラジオ・テーマでしたね!
1978年の初夏に、地元の県民会館にコンサートを観にいきましたが、ヴォーンさんと奥さんが入り口掲示板のところで、道にまよっておられたので、楽屋口まで案内しました。
『漁夫の祭り』は躍動感があります。
我が家の亡くなった父は面影がニニ・ロッソにそっくりでした。
ベルケンも登場!!
昨夜は彼の『Magic Moments』や『Blue Midnight』が子守唄でした。
『太陽がいっぱい』
アラン・ドロンの名演を悲しくも優しくニーノ・ロータの音楽がサーポートしました。
マリー・ラフォレが歌手であることは、後年 ミッシェル・ポルナレフへのアンサー・ソングの『フランスからの手紙』で知りました。
このあともじっくり聞かせていただきます。
ありがとうございました。
マントヴァーニのサイトにも時々うかがいます。
こんばんは!
いつもこのサイトを楽しく拝見させていただき、ありがとうございます。
今 ちゃいこさんからお送りいただいた
お手製の『想い出のヒット曲』集を聞いて
涙しています。
ニニ・ロッソの『夜空のトランペット』は
父からかりて、学校のお昼の校内放送のテーマ曲に使いました。
昼間に夜空をみる!!
これこそ音楽がかもしだす、自由な空間です。
ウーゴ・ブランコの『コーヒー・ルンバ』も懐かしい〜!!
かつて我が家には月の形の上に美女が横たわっているジャケットがありました。
ビリー・ヴォーンの『星を求めて』も、何かのラジオ・テーマでしたね!
1978年の初夏に、地元の県民会館にコンサートを観にいきましたが、ヴォーンさんと奥さんが入り口掲示板のところで、道にまよっておられたので、楽屋口まで案内しました。
『漁夫の祭り』は躍動感があります。
我が家の亡くなった父は面影がニニ・ロッソにそっくりでした。
ベルケンも登場!!
昨夜は彼の『Magic Moments』や『Blue Midnight』が子守唄でした。
『太陽がいっぱい』
アラン・ドロンの名演を悲しくも優しくニーノ・ロータの音楽がサーポートしました。
マリー・ラフォレが歌手であることは、後年 ミッシェル・ポルナレフへのアンサー・ソングの『フランスからの手紙』で知りました。
このあともじっくり聞かせていただきます。
ありがとうございました。
マントヴァーニのサイトにも時々うかがいます。
|
|
|
|
コメント(14)
私も聴かせていただきました。
インストルメンタルでは、「漁夫の祭り」という曲は知りませんでしたが、他の曲は懐かしく聴きました。
ビリー・ヴォーンにお会いになったというのは、ラッキーでしたね。こういうコンサートは、思い立ったら行っておかないと、後悔しますね。ウェルナー・ミューラーの最後の来日公演だったのだと思いますが、また聴けるだろう…というような気持ちで行かなかったのが、今でも悔やまれます。
それから「太陽がいっぱい」「太陽はひとりぼっち」の演奏は、日本人によるものでした。当時は、横文字をつけた日本人ミューシャンによる演奏が、結構多かったようです。「フィルム・シンフォニック・オーケストラ」という仰々しい名前の楽団が演奏する映画音楽のアルバムは沢山あったのですが、今はもう中古レコード店でも見当たりません。これも日本人の演奏でした。
マリー・ラフォレも懐かしいですね。名前は忘れましたが、アルバムでは結構いいのがあったと記憶しています。
インストルメンタルでは、「漁夫の祭り」という曲は知りませんでしたが、他の曲は懐かしく聴きました。
ビリー・ヴォーンにお会いになったというのは、ラッキーでしたね。こういうコンサートは、思い立ったら行っておかないと、後悔しますね。ウェルナー・ミューラーの最後の来日公演だったのだと思いますが、また聴けるだろう…というような気持ちで行かなかったのが、今でも悔やまれます。
それから「太陽がいっぱい」「太陽はひとりぼっち」の演奏は、日本人によるものでした。当時は、横文字をつけた日本人ミューシャンによる演奏が、結構多かったようです。「フィルム・シンフォニック・オーケストラ」という仰々しい名前の楽団が演奏する映画音楽のアルバムは沢山あったのですが、今はもう中古レコード店でも見当たりません。これも日本人の演奏でした。
マリー・ラフォレも懐かしいですね。名前は忘れましたが、アルバムでは結構いいのがあったと記憶しています。
ToruMontyさん
ちゃいこさん
重ねて感謝します。
ニニ・ロッソ、カーメン・キャバレロと、私がコンサートを観たアーティストが、天国に行ったときには身内同様に悲しかったです。
でもレコードを発明したエジソンやベルリーナに感謝します。
『ゴッド・ファーザー愛のテーマ』は映画本編では流れませんでしたね。
ヘルムート・ツァハリアスやクルト・エーデルハーゲンが好きで、ドイツのポップス・オーケストラにはまりました。
ピークは1979年のジェームス・ラストの来日公演でした。
同時期にノーマン・キャンドラーの『乙女座の伝説』に聞き惚れました。
この曲は日曜日の朝8:30ころにラジオから流れていました。
このキャンドラーも、アメリカン調の時にはマンフレッド・ミニックを、ギターのヘラルド・ウィンクラーとの共演時などにはオットー・ジーベンのペンネーム(変名)を使い分けていましたね。
キャンドラー=ゲルハルト・ナルホルツ主宰の業務用『インターサウンド』や『ソノトーン・レコード』にも
名演奏が山積みでした。
ネルソン・リドル、フランク・プゥルセル、ザビア・クガート、ホルスト・ヤンコフスキーなど綺羅星のごとくです。
今テレビで『裸の大将』を見ましたが、この音楽の小林亜星さんも、ダーバンのアラン・ドロンのCMの時には、『プチ・ボア・グランド・オーケストラ』を名乗っていました。
服部良一さんのハンス・リッターは初耳です。
私の以前の日記に書きましたが、1982頃に、東京下北沢で新聞配達をしながら、学業に勤しんでいました。
音楽や写真の趣味で知り合ったNさんが勤めるオーディオ・ショップにはよく、服部克久さんが買い物にきていました。
服部さんと小林さんにはデリケートな問題ながら、仲良くしてほしいです。
近くには古関裕而さんが住んでいました。
夕刊くばりの途中で某 池ノ上方面では、ベレー帽をかぶり子犬を散歩中の吉田正さんにお会いしました。
『君の年で僕を知っているのかね?!』と微笑んでいました。
ドイツはハンザやギルドの国らしく、ホルスト・フィッシャーがほかのオケでトランペットを客演していたり、わき合い合いしていますね。
それらの中心に位置するのが、ウェルナー・ミューラーだと思います。
Abend mit musik.
danke.
ちゃいこさん
重ねて感謝します。
ニニ・ロッソ、カーメン・キャバレロと、私がコンサートを観たアーティストが、天国に行ったときには身内同様に悲しかったです。
でもレコードを発明したエジソンやベルリーナに感謝します。
『ゴッド・ファーザー愛のテーマ』は映画本編では流れませんでしたね。
ヘルムート・ツァハリアスやクルト・エーデルハーゲンが好きで、ドイツのポップス・オーケストラにはまりました。
ピークは1979年のジェームス・ラストの来日公演でした。
同時期にノーマン・キャンドラーの『乙女座の伝説』に聞き惚れました。
この曲は日曜日の朝8:30ころにラジオから流れていました。
このキャンドラーも、アメリカン調の時にはマンフレッド・ミニックを、ギターのヘラルド・ウィンクラーとの共演時などにはオットー・ジーベンのペンネーム(変名)を使い分けていましたね。
キャンドラー=ゲルハルト・ナルホルツ主宰の業務用『インターサウンド』や『ソノトーン・レコード』にも
名演奏が山積みでした。
ネルソン・リドル、フランク・プゥルセル、ザビア・クガート、ホルスト・ヤンコフスキーなど綺羅星のごとくです。
今テレビで『裸の大将』を見ましたが、この音楽の小林亜星さんも、ダーバンのアラン・ドロンのCMの時には、『プチ・ボア・グランド・オーケストラ』を名乗っていました。
服部良一さんのハンス・リッターは初耳です。
私の以前の日記に書きましたが、1982頃に、東京下北沢で新聞配達をしながら、学業に勤しんでいました。
音楽や写真の趣味で知り合ったNさんが勤めるオーディオ・ショップにはよく、服部克久さんが買い物にきていました。
服部さんと小林さんにはデリケートな問題ながら、仲良くしてほしいです。
近くには古関裕而さんが住んでいました。
夕刊くばりの途中で某 池ノ上方面では、ベレー帽をかぶり子犬を散歩中の吉田正さんにお会いしました。
『君の年で僕を知っているのかね?!』と微笑んでいました。
ドイツはハンザやギルドの国らしく、ホルスト・フィッシャーがほかのオケでトランペットを客演していたり、わき合い合いしていますね。
それらの中心に位置するのが、ウェルナー・ミューラーだと思います。
Abend mit musik.
danke.
《古関裕而がユージン・コスマン、服部良一がハンス・リッターなど笑えます。私はハンス・リッター楽団の「小雨降る径」がドイツの楽団の演奏だとばかり思っていました。》
これは全く知りませんでした。ユージン・コスマン楽団は、今でもMusic Birdでは、時折、放送されています。日本の楽団であることは知っていましたが、大御所の楽団だとは…ちょっと驚きです。
でも、当時の日本のミュージシャンは下手だったんですね。モダンプレーボーイズの演奏を聴くとそう思います。好きな楽団なのですが、ベルト・ケムプフェルトと比べると、相当見劣りします。
現在では、正規の音楽教育を受けたプレーヤーが大勢いるので、ポピュラーでも欧米と遜色ないと思うのですが。
ウェルナー・ミューラーは、聴けば聴くほどすごいですね。マントヴァーニ楽団のケチをつける気はありませんが、楽しく聴けるという点では、マントヴァーニ楽団よりずっと上のような気がします。
これは全く知りませんでした。ユージン・コスマン楽団は、今でもMusic Birdでは、時折、放送されています。日本の楽団であることは知っていましたが、大御所の楽団だとは…ちょっと驚きです。
でも、当時の日本のミュージシャンは下手だったんですね。モダンプレーボーイズの演奏を聴くとそう思います。好きな楽団なのですが、ベルト・ケムプフェルトと比べると、相当見劣りします。
現在では、正規の音楽教育を受けたプレーヤーが大勢いるので、ポピュラーでも欧米と遜色ないと思うのですが。
ウェルナー・ミューラーは、聴けば聴くほどすごいですね。マントヴァーニ楽団のケチをつける気はありませんが、楽しく聴けるという点では、マントヴァーニ楽団よりずっと上のような気がします。
よくスーパーマーケットや書店などで、閉店時にかかっている
『ほたるの光』はユージン・コスマンこと古関裕而の演奏です。
私が新聞配達をしていた下北沢 某所の古関さんのすぐ斜向かいには
萩本きんちゃん宅がありました。
同じ*丁目には服部克久さん宅があり、アリスの谷村さんも近くです。
昴をアレンジしたのもあのあたりなのかな?
などとノスタルジーにひたっています。
古関さんや服部初代などは、ホルスト・フィッシャーとウェルナー・ミューラーのように、仲むずまじく若い時に一緒に勉学していたのかもしれませんね。
ベルケンの『マルタ島の歌』や『ブルーレディーに赤いバラ』もエバー・グリーンです。
ドイツのソリストだとロイ・エッツェルのトランペットがかっこいいので好きです。
今夜は自分流JET STREAMで テルデックから再発になったミューラーの
『Intercontinental Souvenirs』を聞いています。
マサチューセッツからはじまり、ブルー・ハワイ、ブラジル、アリベデルチ・ローマなど、さながら『ホリディー・イン』シリーズの総集編です。
この写真は見にくいですが、ヘルムート・ツァハリアスのベストと、以前の日記でふれさせていただいた『黒い瞳/ウェルナー・ミューラー』とベルケンの再発盤です。
『ほたるの光』はユージン・コスマンこと古関裕而の演奏です。
私が新聞配達をしていた下北沢 某所の古関さんのすぐ斜向かいには
萩本きんちゃん宅がありました。
同じ*丁目には服部克久さん宅があり、アリスの谷村さんも近くです。
昴をアレンジしたのもあのあたりなのかな?
などとノスタルジーにひたっています。
古関さんや服部初代などは、ホルスト・フィッシャーとウェルナー・ミューラーのように、仲むずまじく若い時に一緒に勉学していたのかもしれませんね。
ベルケンの『マルタ島の歌』や『ブルーレディーに赤いバラ』もエバー・グリーンです。
ドイツのソリストだとロイ・エッツェルのトランペットがかっこいいので好きです。
今夜は自分流JET STREAMで テルデックから再発になったミューラーの
『Intercontinental Souvenirs』を聞いています。
マサチューセッツからはじまり、ブルー・ハワイ、ブラジル、アリベデルチ・ローマなど、さながら『ホリディー・イン』シリーズの総集編です。
この写真は見にくいですが、ヘルムート・ツァハリアスのベストと、以前の日記でふれさせていただいた『黒い瞳/ウェルナー・ミューラー』とベルケンの再発盤です。
kmatsuさんのお考えの通り日本人がヨコ文字に弱いということもありますが、「太陽がいっぱい」の場合は映画のサントラ盤なるものが存在せず、ある意味仕方なく日本のミュージシャンを使って録音したところ大ヒットしたといういきさつがありました。それが例のフィルム・シンフォニック・オーケストラのポリドール録音です。日本ビクターもシルヴァリー・ストリングスなるオーケストラで似たような演奏を発売しましたがポリドールに敗れました。
映画のサウンド・トラックが商売になると目をつけたのは、やはりハリウッドでした。
今は常識として良く知られていることかもわかりませんが、サントラと称する音源は3種類あります。一つはまさしく映画のフィルムから切り取ったもの。最近の映画は音楽と台詞が別トラックに録音されますが、昔の映画ですと台詞がそのまま残っています。例えば「鉄道員」とか「汚れなき悪戯」がそれです。この場合は映画の場面に合わせ音楽が途中で途切れたり、不自然にフェイド・アウトしたりします。
二つ目は映画と同じ演奏者がレコードとして発売するために別個に録音するケースです。これですと音楽が体裁良くなり、途中で切れたりの不自然さがなくなります。アメリカ映画は早くからこの方法を取り入れていましたが、ヨーロッパ、日本はかなり遅れました。サントラ盤と称するものは殆どがこれです。
三つ目がオリジナル・スコアによる全く別の演奏者によるものです。厳密にはサントラとはいえませんが、オーケストラ物に沢山あります。例えば映画「ベン・ハー」はカルロ・サヴィーナ指揮ローマ交響楽団の演奏がサントラ盤として売られていますが、彼らは映画の中では演奏していません。「アラビアのロレンス」にしても、レコード、CDは作曲者モーリス・ジャールの指揮ですが、映画で指揮したのはサー・エードリアン・ボールトでした。
サントラ演奏の定義はとても複雑なものです。
映画のサウンド・トラックが商売になると目をつけたのは、やはりハリウッドでした。
今は常識として良く知られていることかもわかりませんが、サントラと称する音源は3種類あります。一つはまさしく映画のフィルムから切り取ったもの。最近の映画は音楽と台詞が別トラックに録音されますが、昔の映画ですと台詞がそのまま残っています。例えば「鉄道員」とか「汚れなき悪戯」がそれです。この場合は映画の場面に合わせ音楽が途中で途切れたり、不自然にフェイド・アウトしたりします。
二つ目は映画と同じ演奏者がレコードとして発売するために別個に録音するケースです。これですと音楽が体裁良くなり、途中で切れたりの不自然さがなくなります。アメリカ映画は早くからこの方法を取り入れていましたが、ヨーロッパ、日本はかなり遅れました。サントラ盤と称するものは殆どがこれです。
三つ目がオリジナル・スコアによる全く別の演奏者によるものです。厳密にはサントラとはいえませんが、オーケストラ物に沢山あります。例えば映画「ベン・ハー」はカルロ・サヴィーナ指揮ローマ交響楽団の演奏がサントラ盤として売られていますが、彼らは映画の中では演奏していません。「アラビアのロレンス」にしても、レコード、CDは作曲者モーリス・ジャールの指揮ですが、映画で指揮したのはサー・エードリアン・ボールトでした。
サントラ演奏の定義はとても複雑なものです。
kmatsuさん はじめまして!
日本や世界の『変名』や『覆面』楽団のはなしは興味があります。
ホリーリッジ・ストリングスやリビング・ストリングスなども『変名』などとはニュアンスが別ですが好きな楽団です。
今夜は母とウェルナー・ミューラーのコンチネンタル・タンゴを鑑賞しました。
母は昔、社交ダンスを踊ったそうです。
ちゃいこさんのおっしゃる映画音楽のサントラの3種類は、的を得ているはなしですね。さすがです。
我が家には、以前にブルース・リー『燃えよドラゴン』の2枚組みサントラがありましたが、これは映画をまるまる音声のみをレコードにしたものです。
これも文字通りのサントラです。
ラロ・シフリンの演奏のみの盤は今でも再発されますが、
ビデオやDVDが全盛の今は、せりふありのレコードは需要がないと思います。
ラロ・シフリンは『スパイ大作戦』などでも有名ですが、かわったところでは、三大テノールのステージ構成も手がけていました。
ちゃいこさんの選曲中、『鉄道員』のせりふには、いつ聞いても胸があつくなります。
『太陽がいっぱい』のサントラがない話にも頷きました。
1974年ころの『メリーゴーランド』というたしかイタリア映画の音楽が好きでした。シングル盤を購入しましたが.....今はもう手元にはありません。
クルト・エーデルハーゲンでネット検索していたらば、カテリーナ・バレンテの視聴が可能なページを見つけました。
このコミュニティーのみなさんはすでにお持ちかもしれませんがアップします。
http://wmg.jp/wmlife/imp/caterinavalente/dietelefunkenjahre.html
大半がウェルナー・ミューラーの演奏です。
スタンリー・ブラックやジョニー・キーティング、エドムンド・ロスなどが
彼女の脇をかためています。
『マイ・ファニー・バレンタイン』も収録されていますが、私はこの曲は ジェームス・ラストの実弟のカイ・ワーナーの演奏盤が好きです。
日本や世界の『変名』や『覆面』楽団のはなしは興味があります。
ホリーリッジ・ストリングスやリビング・ストリングスなども『変名』などとはニュアンスが別ですが好きな楽団です。
今夜は母とウェルナー・ミューラーのコンチネンタル・タンゴを鑑賞しました。
母は昔、社交ダンスを踊ったそうです。
ちゃいこさんのおっしゃる映画音楽のサントラの3種類は、的を得ているはなしですね。さすがです。
我が家には、以前にブルース・リー『燃えよドラゴン』の2枚組みサントラがありましたが、これは映画をまるまる音声のみをレコードにしたものです。
これも文字通りのサントラです。
ラロ・シフリンの演奏のみの盤は今でも再発されますが、
ビデオやDVDが全盛の今は、せりふありのレコードは需要がないと思います。
ラロ・シフリンは『スパイ大作戦』などでも有名ですが、かわったところでは、三大テノールのステージ構成も手がけていました。
ちゃいこさんの選曲中、『鉄道員』のせりふには、いつ聞いても胸があつくなります。
『太陽がいっぱい』のサントラがない話にも頷きました。
1974年ころの『メリーゴーランド』というたしかイタリア映画の音楽が好きでした。シングル盤を購入しましたが.....今はもう手元にはありません。
クルト・エーデルハーゲンでネット検索していたらば、カテリーナ・バレンテの視聴が可能なページを見つけました。
このコミュニティーのみなさんはすでにお持ちかもしれませんがアップします。
http://wmg.jp/wmlife/imp/caterinavalente/dietelefunkenjahre.html
大半がウェルナー・ミューラーの演奏です。
スタンリー・ブラックやジョニー・キーティング、エドムンド・ロスなどが
彼女の脇をかためています。
『マイ・ファニー・バレンタイン』も収録されていますが、私はこの曲は ジェームス・ラストの実弟のカイ・ワーナーの演奏盤が好きです。
tokomontyさんの
話題には時代の流れをかんじます。
1963年では、私はちょうど母親のおなかの中にいた頃です。
オープン・リールは当時、お金持ちでなければ買えなかったのではと思います。
私が以前にこのコミュニティーでお話した、
パリでのカテリーナ・バレンテとポール・モーリア・グランド・オーケストラの共演復活コンサートが実現すれば良かったな〜と、今でも思います。
カテリーナ・バレンテのバックをポール・モーリアが演奏したアルバム(曲)も以前にドイツのBEAR FAMILYレコードから再発売されました。
ここには『ラ・ビキナ』というメキシコのマリアッチも収められていました。
アレンジ協力のアンドレ・ボルリー氏のエピソードは
私のマイミク fantasyさんの
5月10日の日記
忘れられない巨匠たち? アンドレ・ボルリーさん に載っています。
司会者 志摩由紀夫は、カーメン・キャバレロのコンサートの司会も担当しました。アダモと共演した、志摩みゆきはおそらく娘さんだと思います。
1986頃、ポール・モーリアから人づてに、彼は若い頃 ウェルナー・ミューラーの演奏方法・アレンジをコピーした、と聞きました。
普段はまったくタイプの違うふたりの演奏ですが、1970年の前のモーリアのストリングスの手法は、ウェルナー・ミューラーと似ている曲があります。
やはりミューラーは偉大なマエストロです。
話題には時代の流れをかんじます。
1963年では、私はちょうど母親のおなかの中にいた頃です。
オープン・リールは当時、お金持ちでなければ買えなかったのではと思います。
私が以前にこのコミュニティーでお話した、
パリでのカテリーナ・バレンテとポール・モーリア・グランド・オーケストラの共演復活コンサートが実現すれば良かったな〜と、今でも思います。
カテリーナ・バレンテのバックをポール・モーリアが演奏したアルバム(曲)も以前にドイツのBEAR FAMILYレコードから再発売されました。
ここには『ラ・ビキナ』というメキシコのマリアッチも収められていました。
アレンジ協力のアンドレ・ボルリー氏のエピソードは
私のマイミク fantasyさんの
5月10日の日記
忘れられない巨匠たち? アンドレ・ボルリーさん に載っています。
司会者 志摩由紀夫は、カーメン・キャバレロのコンサートの司会も担当しました。アダモと共演した、志摩みゆきはおそらく娘さんだと思います。
1986頃、ポール・モーリアから人づてに、彼は若い頃 ウェルナー・ミューラーの演奏方法・アレンジをコピーした、と聞きました。
普段はまったくタイプの違うふたりの演奏ですが、1970年の前のモーリアのストリングスの手法は、ウェルナー・ミューラーと似ている曲があります。
やはりミューラーは偉大なマエストロです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ウェルナー・ミューラー 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-