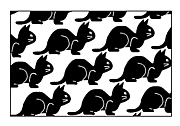|
|
|
|
コメント(37)
アマミノクロウサギ
分類;哺乳類 ウサギ目 ウサギ科
学名;Pentalagus furnessi
分布;日本の奄美大島・徳之島
環境;森林
体長;40cm〜52cm
最も原始的なウサギ。
耳は小さく、足も短い。
つめは強力で、時にはげしい闘争をする。
毛はあらい。
夕暮れに、 かん高い警戒音を出しながら活動を始める。
岩石のあいだや土中に巣穴をつくり、 巣から離れた見晴らしのいい場所にため糞をする。
絶滅が危惧されている。。。
奄美では、ハブ退治のために連れてこられたマングースたちによる食害が深刻とのこと。
そりゃあマングースも、危険な思いをしてハブなんか食べるより、ウサギを食べますよね。。。
分類;哺乳類 ウサギ目 ウサギ科
学名;Pentalagus furnessi
分布;日本の奄美大島・徳之島
環境;森林
体長;40cm〜52cm
最も原始的なウサギ。
耳は小さく、足も短い。
つめは強力で、時にはげしい闘争をする。
毛はあらい。
夕暮れに、 かん高い警戒音を出しながら活動を始める。
岩石のあいだや土中に巣穴をつくり、 巣から離れた見晴らしのいい場所にため糞をする。
絶滅が危惧されている。。。
奄美では、ハブ退治のために連れてこられたマングースたちによる食害が深刻とのこと。
そりゃあマングースも、危険な思いをしてハブなんか食べるより、ウサギを食べますよね。。。
オオサンショウウオ
学名 ;Andrias japonicus
英語名;Japanese giant salamander
綱名;両生綱
目名;有尾目サンショウウオ亜目
科名;オオサンショウウオ科
属名;オオサンショウウオ属
全長;50〜140cm
分布域;岐阜県以西の本州および大分県、四国。
生息場所;水生
行動;夜行性
食性;肉食性
現生では世界最大の両生綱として知られ、全長144cmという記録がある。
全身は褐色に黒褐色の不規則なまだら模様があり、小さないぼがたくさんある。
頭部と口が大きく、眼が非常に小さくて視力は弱いと推測されている。
山地の渓流に棲み、生涯のほとんどを水中で過ごす。
昼間は岩穴などに隠れ、夜出歩いてサワガニ・カエル・魚などを食べる。
繁殖期は八月下旬から九月頃で、産卵用に巣穴を掘り、数珠状につながった卵を300から600個産む。
雌は卵が孵化するまで守る。
三年から四年の幼生時代を過ごし、全長20cmほどになってから変態する。
環境庁(現環境省)編纂の『日本版レッドデータブック』で「希少種?個体数が少なく存続基盤が脆弱な種」に挙げられ、日本国の特別天然記念物にも指定されている。
ワシントン条約の附属書?にも記載されて、商業目的の取引は禁止されている。
特別天然記念物といえば、やはりこいつですね。。。
学名 ;Andrias japonicus
英語名;Japanese giant salamander
綱名;両生綱
目名;有尾目サンショウウオ亜目
科名;オオサンショウウオ科
属名;オオサンショウウオ属
全長;50〜140cm
分布域;岐阜県以西の本州および大分県、四国。
生息場所;水生
行動;夜行性
食性;肉食性
現生では世界最大の両生綱として知られ、全長144cmという記録がある。
全身は褐色に黒褐色の不規則なまだら模様があり、小さないぼがたくさんある。
頭部と口が大きく、眼が非常に小さくて視力は弱いと推測されている。
山地の渓流に棲み、生涯のほとんどを水中で過ごす。
昼間は岩穴などに隠れ、夜出歩いてサワガニ・カエル・魚などを食べる。
繁殖期は八月下旬から九月頃で、産卵用に巣穴を掘り、数珠状につながった卵を300から600個産む。
雌は卵が孵化するまで守る。
三年から四年の幼生時代を過ごし、全長20cmほどになってから変態する。
環境庁(現環境省)編纂の『日本版レッドデータブック』で「希少種?個体数が少なく存続基盤が脆弱な種」に挙げられ、日本国の特別天然記念物にも指定されている。
ワシントン条約の附属書?にも記載されて、商業目的の取引は禁止されている。
特別天然記念物といえば、やはりこいつですね。。。
>リトセアさん
夏の夜にオオサンショウウオを抱いて。。。!
どんな夢を見るのでしょうか。。。
トリは爬虫類と似てますよね。羽毛がなかったら、かなり爬虫類です。
爬虫類って、食べるとみんな鶏肉の味だっていいますしね。
あ、両生類もか、、、蛙とか。。。
恐竜も爬虫類より鳥類に似てるとかいいますね。
恐竜って、本当にあんな姿かたち(図鑑とかの想像図等)だったのでしょうか。。。?
羽毛とかあったんじゃないかな。。。そしたら、結構見え掛かりも変わりますよね。
>madonnaさん
ご参加、有り難うございます!
上の写真は、トキですね。
もちろん、特別天然記念物です。
学名、ニッポニアニッポンですね。
今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします!
夏の夜にオオサンショウウオを抱いて。。。!
どんな夢を見るのでしょうか。。。
トリは爬虫類と似てますよね。羽毛がなかったら、かなり爬虫類です。
爬虫類って、食べるとみんな鶏肉の味だっていいますしね。
あ、両生類もか、、、蛙とか。。。
恐竜も爬虫類より鳥類に似てるとかいいますね。
恐竜って、本当にあんな姿かたち(図鑑とかの想像図等)だったのでしょうか。。。?
羽毛とかあったんじゃないかな。。。そしたら、結構見え掛かりも変わりますよね。
>madonnaさん
ご参加、有り難うございます!
上の写真は、トキですね。
もちろん、特別天然記念物です。
学名、ニッポニアニッポンですね。
今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします!
トキ(朱鷺,鴇)
学名;Nipponia nippon
英名;Japanese Crested Ibis
全長;約75cm
翼を広げた大きさ;約140cm
保護指定;特別天然記念物(1952)、国際保護鳥(1960)、環境省レッドリストEW(野生絶滅)、種の保存法に基づく「国内希少野生動植物種」(1992)、ワシントン条約・附属書Iに掲載。
全体が淡い桃紅色(朱鷺色)で後頭部に房状の冠羽がある。
顔は皮膚が露出していて赤い。
湾曲したくちばしは黒っぽく、先端は赤色。
繁殖期には頭,背,翼が灰黒色になる。
山間の水田、小川、溜め池などで見られていた。
泥や水の中にくちばしを差し込み小動物を食べるが、草地や田畑でわらたばなどをひっくり返して昆虫類を食べることもある。
大木の樹上に枝を組んで営巣する。
ねぐらも樹上。
繁殖期以外は群をつくっていることが多い。
かつては日本のほか、ロシア・ウスリー地方、中国・朝鮮半島などユーラシア大陸東部にも分布していました。
日本では、明治以降狩猟により個体数が激減し、戦後は生息地の開発や農薬によるエサである小動物の減少などによってさらに減っていきました。
1952年、特別天然記念物に指定されましたが個体数の減少は止まらず、1970年には能登地方に残っていた1羽が捕獲され本州では姿を消しました。
その後、1981年に佐渡に残っていた5羽が捕獲され人工繁殖が試みられましたが、個体数の増加はなりませんでした。
学名;Nipponia nippon
英名;Japanese Crested Ibis
全長;約75cm
翼を広げた大きさ;約140cm
保護指定;特別天然記念物(1952)、国際保護鳥(1960)、環境省レッドリストEW(野生絶滅)、種の保存法に基づく「国内希少野生動植物種」(1992)、ワシントン条約・附属書Iに掲載。
全体が淡い桃紅色(朱鷺色)で後頭部に房状の冠羽がある。
顔は皮膚が露出していて赤い。
湾曲したくちばしは黒っぽく、先端は赤色。
繁殖期には頭,背,翼が灰黒色になる。
山間の水田、小川、溜め池などで見られていた。
泥や水の中にくちばしを差し込み小動物を食べるが、草地や田畑でわらたばなどをひっくり返して昆虫類を食べることもある。
大木の樹上に枝を組んで営巣する。
ねぐらも樹上。
繁殖期以外は群をつくっていることが多い。
かつては日本のほか、ロシア・ウスリー地方、中国・朝鮮半島などユーラシア大陸東部にも分布していました。
日本では、明治以降狩猟により個体数が激減し、戦後は生息地の開発や農薬によるエサである小動物の減少などによってさらに減っていきました。
1952年、特別天然記念物に指定されましたが個体数の減少は止まらず、1970年には能登地方に残っていた1羽が捕獲され本州では姿を消しました。
その後、1981年に佐渡に残っていた5羽が捕獲され人工繁殖が試みられましたが、個体数の増加はなりませんでした。
イリオモテヤマネコ
学名;Felis iriomotensis
英名;Iriomote cat
固有性;日本固有種
1967年に新種記載されたベンガルヤマネコに近縁な野生ネコで、沖縄県西表島のみに分布する。
生息数は1985年および1994年に100頭前後と推定され、大きな変化は認められていない。
生息地の改変、交通事故などが存続を脅かす要因と考えられている。
種の保存法による国内希少野生動植物種に指定され、保護増殖事業が進められている。
背中は焦茶色で、側面には灰褐色の地に暗褐色の斑紋が散在する。
腹面は淡色であり、後頭部から額、眼の周りに白と黒の縞が走る。
耳介は先が丸く、背面に白斑がある。
オスの方が大きく、頭胴長はオスで約55〜60cm、メスで50〜55cm、尾長23〜24cm、体重3〜4kg。
体色が全体に黒っぽく、四肢や尾が太い。
沖縄県八重山郡西表島のみに分布する。
基本的に夜行性で、朝と夕方に活動のピークがある。
単独性で、行動圏の大きさはオスが2〜3平方キロ、メスが1〜2平方キロであるが、地域、季節、個体によって差が大きい。
島の低地部の湿地、河川・沢沿いをよく利用し、マングローブ林、農耕地周辺も利用する。
泳ぎが巧みであり、また樹上でも狩りをする。
低地での生息密度は0.5〜0.8毎平方キロと推定されている。
餌動物は小型哺乳類、鳥類、爬虫類、カエル類、昆虫類と多様で、とくによく捕食されているのはクマネズミ、シロハラクイナ、シロハラ、キシノウエトカゲ、マダラコオロギなどである。
発情のピークは2〜4月で、出産は4〜6月と推定されている。
出産・育児についての情報は少ないが、2頭前後を樹洞などに産んだ事例が報告されている。
生息数は、1985年に83〜108頭、1994年に99〜110頭と推定され、100頭前後で安定していると考えられている。
農地改良、観光開発などによる好適生息地の改変、交通事故(2〜3頭/年)、イヌによる捕食などが存続に悪影響を及ぼす主たる要因と考えられている。
交通事故死は、1978年から2000年までの期間に29件が報告されている。
イエネコからの感染症についても懸念されているが、これまでのところ確認例はない。
1972年に国の天然記念物、1977年に特別天然記念物、1994年に国内希少野生動植物種に指定されている。
環境庁(当時)により、1974〜76年度に「イリオモテヤマネコの生態及び保護に関する研究(第1次特別調査)」、1982〜84年度に「イリオモテヤマネコ生息環境等保全対策調査(第2次特別調査)」、1992〜93年度に「イリオモテヤマネコ生息特別調査」が実施された。
1979年からは生息状況モニタリングが行われている。
1991年には西表島の中央山岳部を中心に国設西表鳥獣保護区が設定された。
また、1995年に開設された西表野生生物保護センターが調査研究、保全活動の拠点となっている。
環境省、地元自治体を含む関係諸機関による交通事故防止のため標識の設置、道路構造の工夫などが始められている。
ほかに林野庁による国有林における巡視、民間団体による保護活動、啓発活動なども行われている。
学名;Felis iriomotensis
英名;Iriomote cat
固有性;日本固有種
1967年に新種記載されたベンガルヤマネコに近縁な野生ネコで、沖縄県西表島のみに分布する。
生息数は1985年および1994年に100頭前後と推定され、大きな変化は認められていない。
生息地の改変、交通事故などが存続を脅かす要因と考えられている。
種の保存法による国内希少野生動植物種に指定され、保護増殖事業が進められている。
背中は焦茶色で、側面には灰褐色の地に暗褐色の斑紋が散在する。
腹面は淡色であり、後頭部から額、眼の周りに白と黒の縞が走る。
耳介は先が丸く、背面に白斑がある。
オスの方が大きく、頭胴長はオスで約55〜60cm、メスで50〜55cm、尾長23〜24cm、体重3〜4kg。
体色が全体に黒っぽく、四肢や尾が太い。
沖縄県八重山郡西表島のみに分布する。
基本的に夜行性で、朝と夕方に活動のピークがある。
単独性で、行動圏の大きさはオスが2〜3平方キロ、メスが1〜2平方キロであるが、地域、季節、個体によって差が大きい。
島の低地部の湿地、河川・沢沿いをよく利用し、マングローブ林、農耕地周辺も利用する。
泳ぎが巧みであり、また樹上でも狩りをする。
低地での生息密度は0.5〜0.8毎平方キロと推定されている。
餌動物は小型哺乳類、鳥類、爬虫類、カエル類、昆虫類と多様で、とくによく捕食されているのはクマネズミ、シロハラクイナ、シロハラ、キシノウエトカゲ、マダラコオロギなどである。
発情のピークは2〜4月で、出産は4〜6月と推定されている。
出産・育児についての情報は少ないが、2頭前後を樹洞などに産んだ事例が報告されている。
生息数は、1985年に83〜108頭、1994年に99〜110頭と推定され、100頭前後で安定していると考えられている。
農地改良、観光開発などによる好適生息地の改変、交通事故(2〜3頭/年)、イヌによる捕食などが存続に悪影響を及ぼす主たる要因と考えられている。
交通事故死は、1978年から2000年までの期間に29件が報告されている。
イエネコからの感染症についても懸念されているが、これまでのところ確認例はない。
1972年に国の天然記念物、1977年に特別天然記念物、1994年に国内希少野生動植物種に指定されている。
環境庁(当時)により、1974〜76年度に「イリオモテヤマネコの生態及び保護に関する研究(第1次特別調査)」、1982〜84年度に「イリオモテヤマネコ生息環境等保全対策調査(第2次特別調査)」、1992〜93年度に「イリオモテヤマネコ生息特別調査」が実施された。
1979年からは生息状況モニタリングが行われている。
1991年には西表島の中央山岳部を中心に国設西表鳥獣保護区が設定された。
また、1995年に開設された西表野生生物保護センターが調査研究、保全活動の拠点となっている。
環境省、地元自治体を含む関係諸機関による交通事故防止のため標識の設置、道路構造の工夫などが始められている。
ほかに林野庁による国有林における巡視、民間団体による保護活動、啓発活動なども行われている。
アホウドリ
学名;Diomedea albatrus Pallas, 1769
英名;Short-tailed albatross
世界的な希少種で、1989年現在、伊豆諸島鳥島と尖閣列島南小島の2ヵ所で繁殖し、総個体数は400羽あまりと推測される。
北半球で最大の海鳥で、翼開長2.4m、体重約6〜7kg。
19世紀後半から羽毛採取のために乱獲され、絶滅に瀕した。
一時、絶滅したと報じられたが、1951年に鳥島で生き残っていることが発見され、1971年には尖閣列島でも生存が再発見された。
1981年以降、鳥島で3回にわたって営巣環境改善による保護計画が実施され、これが成功をおさめ、産卵数と巣立ち雛数は近年増加している。
個体数の増加速度は10年で約2倍。
1988年には尖閣列島でも繁殖が確認された。
6〜9月までの非繁殖期に は北部北太平洋のベーリング海やアリューシャン列島近海、アラスカ湾に渡ることが足環標識によってあきらかになった。
おもな餌はイカ類・魚類・甲殻類。
成長にともなって羽色は変化し、幼鳥では全体に黒褐色で、嘴のみ淡桃色。
成鳥では翼の先と尾の先が黒色のほか全体白色になり、頭部から首にかけて山吹色に染まる。
若鳥は体の下面が白く、上面は黒褐色に白斑がまじる。
繁殖地はつねに風に吹かれている外洋の無人島で、中腹以上に営巣する。
地上性捕食者がいないことも条件。
尖閣列島南小島では高い断崖の中段にあるやや広い棚の上に営巣している。
学名;Diomedea albatrus Pallas, 1769
英名;Short-tailed albatross
世界的な希少種で、1989年現在、伊豆諸島鳥島と尖閣列島南小島の2ヵ所で繁殖し、総個体数は400羽あまりと推測される。
北半球で最大の海鳥で、翼開長2.4m、体重約6〜7kg。
19世紀後半から羽毛採取のために乱獲され、絶滅に瀕した。
一時、絶滅したと報じられたが、1951年に鳥島で生き残っていることが発見され、1971年には尖閣列島でも生存が再発見された。
1981年以降、鳥島で3回にわたって営巣環境改善による保護計画が実施され、これが成功をおさめ、産卵数と巣立ち雛数は近年増加している。
個体数の増加速度は10年で約2倍。
1988年には尖閣列島でも繁殖が確認された。
6〜9月までの非繁殖期に は北部北太平洋のベーリング海やアリューシャン列島近海、アラスカ湾に渡ることが足環標識によってあきらかになった。
おもな餌はイカ類・魚類・甲殻類。
成長にともなって羽色は変化し、幼鳥では全体に黒褐色で、嘴のみ淡桃色。
成鳥では翼の先と尾の先が黒色のほか全体白色になり、頭部から首にかけて山吹色に染まる。
若鳥は体の下面が白く、上面は黒褐色に白斑がまじる。
繁殖地はつねに風に吹かれている外洋の無人島で、中腹以上に営巣する。
地上性捕食者がいないことも条件。
尖閣列島南小島では高い断崖の中段にあるやや広い棚の上に営巣している。
北岳のライチョウ、姿消す 天敵増え、ヒナ育たず。。。
山梨県の南アルプス・北岳の山頂周辺で、国の特別天然記念物・ライチョウが姿を消した。
10月に実施された現地調査で初めて一羽も確認できなかった。
30年以上観察してきた「北岳肩の小屋」も、「夏前に2、3組いたが、まったく見られなくなった。このままでは絶滅だと思う」と懸念している。
今年6月、北岳肩の小屋から下の稜線付近で3組のつがいを確認。
7月には各つがいがそれぞれ5〜6羽のひなを伴っていた。
ところが10月初めに改めて調査したところ、親のライチョウも含めて北岳山頂付近では一羽も見つけられなかった。
山頂から南へ約2キロ離れた中白根山まで行き、ようやく4羽を確認できた。
10月の調査時はライチョウが姿を現しにくいとされる晴天だったが、一羽も見つからなかったのは初めてだった。
日本第2の高峰・北岳周辺は南アルプスの中で最もライチョウが密に生息しているとされていた。
調査が始まった81年には北岳周辺で33つがいが確認され、個体数は80羽前後と推定されていた。
激減の理由は、直接的には天敵のキツネやテン、猛禽類にヒナが食べられたことが考えられるという。
一昨年には、キツネの糞にライチョウの羽根が入っているのが2カ所で確認されている。
また近年は、サルとシカが高山帯にまで上がり、ライチョウのエサである高山植物を食べ尽くす地域が広がっている。
キツネなどは登山者や山小屋の残飯を求めて高山に上がり、サルやシカは管理されなくなった里山で数を増やし、駆除の銃に追われて上がったと考えられている。
「天敵による捕食が増え、ヒナが育たなくなった。キツネは本来、標高3000メートルまで上がってくる動物ではない。残されたライチョウを守るため、天敵の駆除も考えるべきだ」という。
山梨県の南アルプス・北岳の山頂周辺で、国の特別天然記念物・ライチョウが姿を消した。
10月に実施された現地調査で初めて一羽も確認できなかった。
30年以上観察してきた「北岳肩の小屋」も、「夏前に2、3組いたが、まったく見られなくなった。このままでは絶滅だと思う」と懸念している。
今年6月、北岳肩の小屋から下の稜線付近で3組のつがいを確認。
7月には各つがいがそれぞれ5〜6羽のひなを伴っていた。
ところが10月初めに改めて調査したところ、親のライチョウも含めて北岳山頂付近では一羽も見つけられなかった。
山頂から南へ約2キロ離れた中白根山まで行き、ようやく4羽を確認できた。
10月の調査時はライチョウが姿を現しにくいとされる晴天だったが、一羽も見つからなかったのは初めてだった。
日本第2の高峰・北岳周辺は南アルプスの中で最もライチョウが密に生息しているとされていた。
調査が始まった81年には北岳周辺で33つがいが確認され、個体数は80羽前後と推定されていた。
激減の理由は、直接的には天敵のキツネやテン、猛禽類にヒナが食べられたことが考えられるという。
一昨年には、キツネの糞にライチョウの羽根が入っているのが2カ所で確認されている。
また近年は、サルとシカが高山帯にまで上がり、ライチョウのエサである高山植物を食べ尽くす地域が広がっている。
キツネなどは登山者や山小屋の残飯を求めて高山に上がり、サルやシカは管理されなくなった里山で数を増やし、駆除の銃に追われて上がったと考えられている。
「天敵による捕食が増え、ヒナが育たなくなった。キツネは本来、標高3000メートルまで上がってくる動物ではない。残されたライチョウを守るため、天敵の駆除も考えるべきだ」という。
天然記念物のネコ、お見合いで100匹増やそう
富山市ファミリーパークで、今季から一般公開された国の天然記念物「ツシマヤマネコ」の命名式が先月27日、同園であった。
全国各地の動物園が協力して「分散飼育」をして伝染病などのリスクを減らそうと、昨秋以降に福岡市動物園などから3匹がやってきた。
現在、メス2匹を見学できる。
3匹の愛称を3月15日から約1カ月間、来園者から募った。
654票が集まり、最も多かった愛称をそれぞれ選んだ。
2歳のメスが「もも」、8歳のメスが「みどり」、4歳のオスが「ヤマ」。
3匹は今後「お見合い」して繁殖が始まる。
同園によると、全国で100匹増やす計画という。
富山市ファミリーパークで、今季から一般公開された国の天然記念物「ツシマヤマネコ」の命名式が先月27日、同園であった。
全国各地の動物園が協力して「分散飼育」をして伝染病などのリスクを減らそうと、昨秋以降に福岡市動物園などから3匹がやってきた。
現在、メス2匹を見学できる。
3匹の愛称を3月15日から約1カ月間、来園者から募った。
654票が集まり、最も多かった愛称をそれぞれ選んだ。
2歳のメスが「もも」、8歳のメスが「みどり」、4歳のオスが「ヤマ」。
3匹は今後「お見合い」して繁殖が始まる。
同園によると、全国で100匹増やす計画という。
「戻ってきたトキ」
これからの季節、地面に落ちている鳥のヒナを見つけることもあるだろう。
だが、多くの場合それは巣立ちの途中で、人がふれてはいけないのだという。
かわいそうと保護したりすれば、近くにいる親鳥から引き離すことになり、巣立ちが不可能になるそうだ。
人の善意もかえって自然な生存を危うくするのが、野生動物保護の難しいところ。
とくに動物をわが身に引きつけて考えがちな人間だが、動物には動物の都合もあるだろう。
相手が人ならばありがた迷惑でも、動物には迷惑なだけ。
そんな動物だから、いったん絶滅したトキを野生復帰させる試みが多くのジレンマを抱え込むのも仕方がない。
しかし新潟県佐渡市で昨秋放鳥されたトキのうち生き残っている雌4羽すべてが本州に渡ったと聞いた時には、さすがに関係者も天を仰いだという。
なぜか雄が佐渡に残ったのも全ては「トキの都合」だが、おかげで繁殖への期待はしぼんだ。
佐渡の地元では、かねて本州に渡ったトキを島に連れ戻すよう要望し、一方で鳥の専門家は捕獲に反対して観察続行を求めていたいきさつもある。
そこに飛び込んできたのが、雌の1羽が佐渡に戻り、以前一緒にいた雄と行動を共にしているという朗報。
思わず「家出妻帰る」などと人情話にしたくなるが、「トキの都合」を人事にひきつけてはまた見通しを誤ろう。
ただ繁殖の可能性が復活したのをすなおに喜びたい。
海を軽々と渡る飛翔力をはじめ人の想像の枠に収まらないのが「野生」である。
なのに自分の都合で自然を作り替え、多くの生物を絶滅に追い込んできた人間。
ここしばらくは心静かに「トキの都合」に耳を傾けたい。。。
これからの季節、地面に落ちている鳥のヒナを見つけることもあるだろう。
だが、多くの場合それは巣立ちの途中で、人がふれてはいけないのだという。
かわいそうと保護したりすれば、近くにいる親鳥から引き離すことになり、巣立ちが不可能になるそうだ。
人の善意もかえって自然な生存を危うくするのが、野生動物保護の難しいところ。
とくに動物をわが身に引きつけて考えがちな人間だが、動物には動物の都合もあるだろう。
相手が人ならばありがた迷惑でも、動物には迷惑なだけ。
そんな動物だから、いったん絶滅したトキを野生復帰させる試みが多くのジレンマを抱え込むのも仕方がない。
しかし新潟県佐渡市で昨秋放鳥されたトキのうち生き残っている雌4羽すべてが本州に渡ったと聞いた時には、さすがに関係者も天を仰いだという。
なぜか雄が佐渡に残ったのも全ては「トキの都合」だが、おかげで繁殖への期待はしぼんだ。
佐渡の地元では、かねて本州に渡ったトキを島に連れ戻すよう要望し、一方で鳥の専門家は捕獲に反対して観察続行を求めていたいきさつもある。
そこに飛び込んできたのが、雌の1羽が佐渡に戻り、以前一緒にいた雄と行動を共にしているという朗報。
思わず「家出妻帰る」などと人情話にしたくなるが、「トキの都合」を人事にひきつけてはまた見通しを誤ろう。
ただ繁殖の可能性が復活したのをすなおに喜びたい。
海を軽々と渡る飛翔力をはじめ人の想像の枠に収まらないのが「野生」である。
なのに自分の都合で自然を作り替え、多くの生物を絶滅に追い込んできた人間。
ここしばらくは心静かに「トキの都合」に耳を傾けたい。。。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
動物☆すき 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
動物☆すきのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75494人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196032人
- 3位
- 独り言
- 9044人