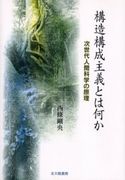|
|
|
|
コメント(282)
【読書メモ】吉本隆明『新・書物の解体学』メタローグ 1992年 より<書評>を引用
<書評>I・プリゴジン/I・スタンジェール『混沌からの秩序』伏見康治ほか訳 みすず書房
著者たちによれば、ベナール細胞の例で、この系が平衡状態にあるときは、この細胞反応には重力の影響は無視できるが、いったん平衡から遠くはなれた状態でゆらぎがはじまると、この細胞はたった数ミリメートルの厚さしかないのに、重力の役割が本質的な影響を与え、分岐点のところで対称性の破れが生じ、系の細胞反応は、まったく新しい状態に移ってしまう。たとえば核酸DNAは右巻きのラセン構造をもっていることが知られている。対称性からいえば左巻きの構造が半分あっていいはずなのに、この生命を司るタンパクは右巻きである。そしてこれを説明できるかどうかは生命の特性を説明できるかどうかと同じことになる。偶然に右巻きからはじまった生命は、そのあとつぎつぎ右巻きを生んでいったとかんがえるか、あるいは左巻き構造もあったのだが、淘汰のながい過程で右が勝って左を消滅させてしまった、そうもかんがえられる。こういう説明にたいし、この本の著者たちの立場は、平衡から遠くはなれた条件のもとで、無視できなくなった重力の影響にたいし右巻きのDNAだけが重力を感知し、それに適用する選択をなしえたので生きのびたのだという説明になる。この説明を正当化するような新しい反応の例を著者たちは発見した。そしてこれが生命現象を司る細胞の構造のなかにある不斉性(非対称性)にたいする著者たちの見解だ。
<書評>I・プリゴジン/I・スタンジェール『混沌からの秩序』伏見康治ほか訳 みすず書房
著者たちによれば、ベナール細胞の例で、この系が平衡状態にあるときは、この細胞反応には重力の影響は無視できるが、いったん平衡から遠くはなれた状態でゆらぎがはじまると、この細胞はたった数ミリメートルの厚さしかないのに、重力の役割が本質的な影響を与え、分岐点のところで対称性の破れが生じ、系の細胞反応は、まったく新しい状態に移ってしまう。たとえば核酸DNAは右巻きのラセン構造をもっていることが知られている。対称性からいえば左巻きの構造が半分あっていいはずなのに、この生命を司るタンパクは右巻きである。そしてこれを説明できるかどうかは生命の特性を説明できるかどうかと同じことになる。偶然に右巻きからはじまった生命は、そのあとつぎつぎ右巻きを生んでいったとかんがえるか、あるいは左巻き構造もあったのだが、淘汰のながい過程で右が勝って左を消滅させてしまった、そうもかんがえられる。こういう説明にたいし、この本の著者たちの立場は、平衡から遠くはなれた条件のもとで、無視できなくなった重力の影響にたいし右巻きのDNAだけが重力を感知し、それに適用する選択をなしえたので生きのびたのだという説明になる。この説明を正当化するような新しい反応の例を著者たちは発見した。そしてこれが生命現象を司る細胞の構造のなかにある不斉性(非対称性)にたいする著者たちの見解だ。
吉本隆明「機能的論理の位相」:『情況』河出書房新社 1970年刊 所収
行動主義者のいうように、<意識>とよばれるものは<行動>を導く機能をもっているのではなく、なにかの理由から、心的な行動と解剖的生理的な身体行動のあいだに、ずれをもたざるをえなかったという体験の累積から、<意識>は生み出されたものとかんがえるべきである。だから<意識の機能>をとりあげるときは、心的な行動と、身体的な行動のあいだにずれをもたらす役割をもつというのが、<意識>に与えうる唯一の<機能>だというほかはない。
心的な行動と、身体的な行動のあいだにずれを生み出すことに、どんな意味があるのだろうか?こういう問いに答えをあたえられないと仮定しても、このずれの拡がりと異質さによって、人間は、他の動物とはちがった高次な心身の機構の世界をつくりだしている、という<事実>をさしだすことはできよう。
行動主義者のいうように、<意識>とよばれるものは<行動>を導く機能をもっているのではなく、なにかの理由から、心的な行動と解剖的生理的な身体行動のあいだに、ずれをもたざるをえなかったという体験の累積から、<意識>は生み出されたものとかんがえるべきである。だから<意識の機能>をとりあげるときは、心的な行動と、身体的な行動のあいだにずれをもたらす役割をもつというのが、<意識>に与えうる唯一の<機能>だというほかはない。
心的な行動と、身体的な行動のあいだにずれを生み出すことに、どんな意味があるのだろうか?こういう問いに答えをあたえられないと仮定しても、このずれの拡がりと異質さによって、人間は、他の動物とはちがった高次な心身の機構の世界をつくりだしている、という<事実>をさしだすことはできよう。
吉本隆明「情況とはなにか」:『自立の思想的拠点』徳間書店 1966年刊 所収
わたしたちが「現実」とよんでいるものは、「幻想」を媒介にして認識された事実であるか、行為によって生まれた「幻想」であるか、のいずれかである。それ自体が観念の水準と位相を想定される言葉である。
国家を<最高の>水準とするあらゆる幻想的な共同性は、個々の人間の自己幻想の抽象的な一般性の集合としてかんがえることができる。ただ、<家>または<家族>の共同的な幻想だけは、個々の男または女の自己幻想を基制にすることができず、一対の男と女のあいだからしかうまれない対幻想を基底としている。…このような幻想対は、ただ<対>であるという理由で、人間の存在の具体性をはなれることができない。幻想が幻想であるという理由で<家>または<家族>の幻想性も、その土台である自然をはなれるが、<対>であるという理由でたえず地上をはなれることができない。この矛盾こそが<家>または<家族>の共同性を特異にする本質である。わたしたちが社会的人間として<家>に感ずる制約と親和との不可分な感情や、性的人間として<社会>に感ずる疎通感と違和感の不可分な感情は、<家>の幻想性がもつこの位相にもとづいている。
もしも、家族集団の集落が社会的共同体をむすぶとすれば、幻想対の共同性が、擬制的であれ<対>としての性格を破られなければならないはずである。しかも、幻想性の内部で破られなければならないはずである。そして、このような幻想対を破るものとしての幻想性は、人間の存在にとっても、人間と人間との直かの関係にとっても、いわば<遠隔対称性>ともいうべきものである。幻想性としての<遠隔対称性>というのは、かんたんにいえば、人間の幻想性はかならずその対称性を第二の自然(慣行性)に転化し、その転化した度合におうじてより遠隔へ対称性を移すということであり、人間の存在がもっている幻想性としての本質にねざしている。このような遠隔対称性は、<幻想対>の対称をしだいに血縁以外のものに択ばせるようにした。いいかえれば、媒介として家族の<幻想対>に介入してくるものを対称から排除していったのである。そしてこの幻想対としての人間の存在がしだいに遠隔対称に移行することは、とりもなおさず逆に経済社会の構成的な空間を、同一の水準と位相にまねきよせたのである。歴史的には氏族制の成立にとって、<家>または<家族>の幻想対の共同性が、幻想性としての人間の固有性にぞくする遠隔対称化とむすびつくことは必須の要請であった。
人間は<家>において対となった共同性を獲得し、それが人間にとって自然関係であるがゆえに、ただ家において現実的であり、人間的であるにすぎない。市民としての人間という理念は、<最高>の共同性としての国家という理念なくしては成りたたない概念であり、国家の本質をうたがえば、人間の存在の基盤はただ<家>においてだけ実体的なものであるにすぎなくなる。だから、わたしたちは、ただ大衆の原像においてだけ現実的な思想をもちうるにすぎない。
<家>の共同性が、社会や国家(このふたつは相互規定的である)をまねきよせるものとしたら、それは社会や国家がただ家族の成員の社会的幻想の表出を、ちょうどヴェールをはぎとるように、かすめとってゆく点においてだけである。ここでもまた、大衆の原像は、つねに<まだ>国家や社会になりきらない過渡的な存在であるとともに、すでに国家や社会もこえた何ものかである。
わたしたちが「現実」とよんでいるものは、「幻想」を媒介にして認識された事実であるか、行為によって生まれた「幻想」であるか、のいずれかである。それ自体が観念の水準と位相を想定される言葉である。
国家を<最高の>水準とするあらゆる幻想的な共同性は、個々の人間の自己幻想の抽象的な一般性の集合としてかんがえることができる。ただ、<家>または<家族>の共同的な幻想だけは、個々の男または女の自己幻想を基制にすることができず、一対の男と女のあいだからしかうまれない対幻想を基底としている。…このような幻想対は、ただ<対>であるという理由で、人間の存在の具体性をはなれることができない。幻想が幻想であるという理由で<家>または<家族>の幻想性も、その土台である自然をはなれるが、<対>であるという理由でたえず地上をはなれることができない。この矛盾こそが<家>または<家族>の共同性を特異にする本質である。わたしたちが社会的人間として<家>に感ずる制約と親和との不可分な感情や、性的人間として<社会>に感ずる疎通感と違和感の不可分な感情は、<家>の幻想性がもつこの位相にもとづいている。
もしも、家族集団の集落が社会的共同体をむすぶとすれば、幻想対の共同性が、擬制的であれ<対>としての性格を破られなければならないはずである。しかも、幻想性の内部で破られなければならないはずである。そして、このような幻想対を破るものとしての幻想性は、人間の存在にとっても、人間と人間との直かの関係にとっても、いわば<遠隔対称性>ともいうべきものである。幻想性としての<遠隔対称性>というのは、かんたんにいえば、人間の幻想性はかならずその対称性を第二の自然(慣行性)に転化し、その転化した度合におうじてより遠隔へ対称性を移すということであり、人間の存在がもっている幻想性としての本質にねざしている。このような遠隔対称性は、<幻想対>の対称をしだいに血縁以外のものに択ばせるようにした。いいかえれば、媒介として家族の<幻想対>に介入してくるものを対称から排除していったのである。そしてこの幻想対としての人間の存在がしだいに遠隔対称に移行することは、とりもなおさず逆に経済社会の構成的な空間を、同一の水準と位相にまねきよせたのである。歴史的には氏族制の成立にとって、<家>または<家族>の幻想対の共同性が、幻想性としての人間の固有性にぞくする遠隔対称化とむすびつくことは必須の要請であった。
人間は<家>において対となった共同性を獲得し、それが人間にとって自然関係であるがゆえに、ただ家において現実的であり、人間的であるにすぎない。市民としての人間という理念は、<最高>の共同性としての国家という理念なくしては成りたたない概念であり、国家の本質をうたがえば、人間の存在の基盤はただ<家>においてだけ実体的なものであるにすぎなくなる。だから、わたしたちは、ただ大衆の原像においてだけ現実的な思想をもちうるにすぎない。
<家>の共同性が、社会や国家(このふたつは相互規定的である)をまねきよせるものとしたら、それは社会や国家がただ家族の成員の社会的幻想の表出を、ちょうどヴェールをはぎとるように、かすめとってゆく点においてだけである。ここでもまた、大衆の原像は、つねに<まだ>国家や社会になりきらない過渡的な存在であるとともに、すでに国家や社会もこえた何ものかである。
吉本隆明「異常論」:『母型論』学研 1995年刊 所収
乳(胎)児にとって性の欲動を表象する乳首を吸う行為は、同時に栄養を摂取する食の行為と未分化のまま共時性の起源の状態にある。そしてこの共時性は成長して食と性が分離したあともなくならず、二重の層になって対応している。この性と栄養摂取とのいつまでもなくならない共時性は、内臓系からやってくる心の働きと体壁系につながる感覚の作用からできた織物に、いわば普遍的な性の意味を与えることになる。別の言い方をすればヒトという類の性と栄養摂取の共時性が、すべての内臓系の植物神経的な動きと動物系の知覚作用とに性的な意味を与えている素因だということになる。
たとえば窃視症と露出症は、眼の知覚作用に共時的に重なった眼の器官にまつわるエロス覚が過剰に不均質に充当されたものとみることができる。またサディズムとマゾヒズムは、体壁系に属する皮膚の痛圧感覚が、エロスとして過当な備給をうけたものとみなせることになる。これは内臓系についてもいえる。たとえば広義のヒステリー症を思いうかべてみれば、口(腔)や肛門のような鰓腸の上下の開口部にたいして性的な器官の役割を過剰に背負わせる傾向が、ある閾値を越えたばあいにおこるとかんがえることができる。もっとこの言い方をおしすすめれば愛と憎しみの情念や、他者への親和と敵意の感情は、内臓系とくに心臓の高まりから生れる心の動きに、対象にむかってゆく性の欲動が重なった形とみることができよう。
乳(胎)児にとって性の欲動を表象する乳首を吸う行為は、同時に栄養を摂取する食の行為と未分化のまま共時性の起源の状態にある。そしてこの共時性は成長して食と性が分離したあともなくならず、二重の層になって対応している。この性と栄養摂取とのいつまでもなくならない共時性は、内臓系からやってくる心の働きと体壁系につながる感覚の作用からできた織物に、いわば普遍的な性の意味を与えることになる。別の言い方をすればヒトという類の性と栄養摂取の共時性が、すべての内臓系の植物神経的な動きと動物系の知覚作用とに性的な意味を与えている素因だということになる。
たとえば窃視症と露出症は、眼の知覚作用に共時的に重なった眼の器官にまつわるエロス覚が過剰に不均質に充当されたものとみることができる。またサディズムとマゾヒズムは、体壁系に属する皮膚の痛圧感覚が、エロスとして過当な備給をうけたものとみなせることになる。これは内臓系についてもいえる。たとえば広義のヒステリー症を思いうかべてみれば、口(腔)や肛門のような鰓腸の上下の開口部にたいして性的な器官の役割を過剰に背負わせる傾向が、ある閾値を越えたばあいにおこるとかんがえることができる。もっとこの言い方をおしすすめれば愛と憎しみの情念や、他者への親和と敵意の感情は、内臓系とくに心臓の高まりから生れる心の動きに、対象にむかってゆく性の欲動が重なった形とみることができよう。
岸田秀「〔小谷野敦宛て書簡〕「江戸の性愛」幻想を斬る」:『ものぐさ性愛論』青土社 所収
わたしが「学問的なデュー・プロセスを踏んでいない」とのことですが、それはそうかもしれません。しかし、あなたは正しい普遍的な「学問的なデュー・プロセス」が存在するという幻想をもっているのではないかと、わたしには思えます。
性倒錯の一種としてのサディズム、すなわち、相手を傷つけ苦しめることと、性的興奮と満足とが結びついたもの、加虐行為と結び付いた性欲は近代に始まるのではないかと、わたしは考えています。サド公爵以前にサディストはいなかったというのはそういう意味です。ネロはキリスト教徒などを迫害して面白がっていたようですが、それで性的に興奮していたということはなかったと思います。
「好きな女とセックスしない男も近代に新しく現れた」ということに「確固たる根拠を示せと言われても困る」と書いたところ、「確固たる根拠を示してください」と迫られましたが、「確固たる根拠を示せと言われると困る」というのは一種のレトリックで、実は、わたしはどんなことについても「確固たる根拠」というようなものはめったにあるものではないと思っているのです。
女を性欲の対象にすることが加虐(身体的、精神的)の意味を帯び、その結果、「好きな女とセックスしない男」が新しく現れたというわけで、言わば、社会現象としての性も一種の論理構造を成しており、その論理構造にもとづいて、性に関してもいろいろなことが言い得ると、わたしは考えており、わたしとしては、そういう論理構造にもとづく判断のほうが、文学作品などを根拠とする判断よりも、あくまで相対的な意味においてですが、「確固たる」根拠にもとづく判断だと言えるのではなかろうかと思っているわけです。
自然科学の場合なら、論理にもとづく推測は、言わば、仮説の段階にあって、その仮説を証明するか、覆すかは実験によるわけですが(実験によって証明されればその仮説は正しい、という仮説そのものは実験によって正しいと証明できないと、養老孟司はわたしに言っていましたが)、人間に関して、歴史や社会現象に関して、実験は不可能なので、文学作品とか、臨床例とか、東西古今のいろいろな事件とか、自分の個人的経験とか、人から聞いた話とかの、言わば傍証に頼るしかなく、傍証をいくら集めても、厳密な意味での確証にはならないと思います。…そのうちいつか真理に到達するということはないのではないでしょうか。
わたしが「学問的なデュー・プロセスを踏んでいない」とのことですが、それはそうかもしれません。しかし、あなたは正しい普遍的な「学問的なデュー・プロセス」が存在するという幻想をもっているのではないかと、わたしには思えます。
性倒錯の一種としてのサディズム、すなわち、相手を傷つけ苦しめることと、性的興奮と満足とが結びついたもの、加虐行為と結び付いた性欲は近代に始まるのではないかと、わたしは考えています。サド公爵以前にサディストはいなかったというのはそういう意味です。ネロはキリスト教徒などを迫害して面白がっていたようですが、それで性的に興奮していたということはなかったと思います。
「好きな女とセックスしない男も近代に新しく現れた」ということに「確固たる根拠を示せと言われても困る」と書いたところ、「確固たる根拠を示してください」と迫られましたが、「確固たる根拠を示せと言われると困る」というのは一種のレトリックで、実は、わたしはどんなことについても「確固たる根拠」というようなものはめったにあるものではないと思っているのです。
女を性欲の対象にすることが加虐(身体的、精神的)の意味を帯び、その結果、「好きな女とセックスしない男」が新しく現れたというわけで、言わば、社会現象としての性も一種の論理構造を成しており、その論理構造にもとづいて、性に関してもいろいろなことが言い得ると、わたしは考えており、わたしとしては、そういう論理構造にもとづく判断のほうが、文学作品などを根拠とする判断よりも、あくまで相対的な意味においてですが、「確固たる」根拠にもとづく判断だと言えるのではなかろうかと思っているわけです。
自然科学の場合なら、論理にもとづく推測は、言わば、仮説の段階にあって、その仮説を証明するか、覆すかは実験によるわけですが(実験によって証明されればその仮説は正しい、という仮説そのものは実験によって正しいと証明できないと、養老孟司はわたしに言っていましたが)、人間に関して、歴史や社会現象に関して、実験は不可能なので、文学作品とか、臨床例とか、東西古今のいろいろな事件とか、自分の個人的経験とか、人から聞いた話とかの、言わば傍証に頼るしかなく、傍証をいくら集めても、厳密な意味での確証にはならないと思います。…そのうちいつか真理に到達するということはないのではないでしょうか。
宮本武蔵『五輪書』鎌田茂雄 訳注 講談社学術文庫
一 兵法の目付といふ事
目のつけやうは、大きに広く付くる目也。観見二つの事、観の目つよく、見の目よわく、遠き所を近く見、ちかき所を遠く見る事、兵法の専也。
一 太刀の持ちやうの事
惣而〔そうじて〕、太刀にても、手にても、ゐつく〔居着く〕といふ事をきらふ。ゐつくは、しぬる手也。ゐつかざるは、いきる手也。能々〔よくよく〕心得べきもの也。
一 太刀の道といふ事
太刀をはやく振らんとするによつて、太刀の道さか〔逆〕ひてふりがたし。太刀はふりよき程に静かにふる心也。或は扇、或は小刀などつかふやうに。はやくふらんとおもふによつて、太刀の道ちがひてふりがたし。
一 兵法の目付といふ事
目のつけやうは、大きに広く付くる目也。観見二つの事、観の目つよく、見の目よわく、遠き所を近く見、ちかき所を遠く見る事、兵法の専也。
一 太刀の持ちやうの事
惣而〔そうじて〕、太刀にても、手にても、ゐつく〔居着く〕といふ事をきらふ。ゐつくは、しぬる手也。ゐつかざるは、いきる手也。能々〔よくよく〕心得べきもの也。
一 太刀の道といふ事
太刀をはやく振らんとするによつて、太刀の道さか〔逆〕ひてふりがたし。太刀はふりよき程に静かにふる心也。或は扇、或は小刀などつかふやうに。はやくふらんとおもふによつて、太刀の道ちがひてふりがたし。
内田樹『街場の文体論』ミシマ社 2012年
翻訳されるものと、されないものの違いはどこにあるのか。どう考えてみても、作物のクオリティとは関係がない。なんでこんなに優れたものが訳されていないのかと思うものがいくつもあります。たとえば、吉本隆明。
吉本隆明の思想は世界性を獲得できなかった。本質的には世界的な思想だったのだけれど、世界各国の地域性がそれを受け入れるだけの成熟に達していなかった。そういうかたちで「翻訳されない」ということもあるんです。丸山眞男は翻訳されるが、吉本隆明は訳されないのは、吉本のほうが「ローカル」だからではなく、吉本が「あらゆる国の人々が目を背けようとしている事象」を扱っているからなのだと僕は思います。
翻訳されるものと、されないものの違いはどこにあるのか。どう考えてみても、作物のクオリティとは関係がない。なんでこんなに優れたものが訳されていないのかと思うものがいくつもあります。たとえば、吉本隆明。
吉本隆明の思想は世界性を獲得できなかった。本質的には世界的な思想だったのだけれど、世界各国の地域性がそれを受け入れるだけの成熟に達していなかった。そういうかたちで「翻訳されない」ということもあるんです。丸山眞男は翻訳されるが、吉本隆明は訳されないのは、吉本のほうが「ローカル」だからではなく、吉本が「あらゆる国の人々が目を背けようとしている事象」を扱っているからなのだと僕は思います。
宮城賢『生と詩』国文社 1976年
科学が、すべてを疑うことから発する精神の営みであるなら、詩もまたそうである。そして、詩は、科学そのものをも疑う精神の営みでなければなるまい。「あくまでも量を厳密に」定量するのは科学であるが、人間にそれを命じるのは科学ではなく、人間の<心>なのである。
昼の労働において、私たちが際限もなく分化する分業を個々に分担せざるをえない以上、なんらかの方途によって人間としての統合や綜合を希求するのは必然のいきおいである。人間が人間であることを回復することは無償の行為として窮極のものであり、詩こそはその無償性にこたえうる最後のものだと私は考えている。そのようなものとしての詩が、批評を内在せしめるべきことを背負わされたのが、近代の宿運であったろう。綜合をめざす詩が分析をめざす批評を内にかかえこまねばならないとは、一見、矛盾にみえるかもしれないが、決してそれは矛盾ではないのである。なぜなら、自分自身を含めた世界を批評することによって、私たちは自身と世界の分裂や分極の様相を知るのであり、知ることによってしか綜合へと向かう道は視えてこないからである。
科学が、すべてを疑うことから発する精神の営みであるなら、詩もまたそうである。そして、詩は、科学そのものをも疑う精神の営みでなければなるまい。「あくまでも量を厳密に」定量するのは科学であるが、人間にそれを命じるのは科学ではなく、人間の<心>なのである。
昼の労働において、私たちが際限もなく分化する分業を個々に分担せざるをえない以上、なんらかの方途によって人間としての統合や綜合を希求するのは必然のいきおいである。人間が人間であることを回復することは無償の行為として窮極のものであり、詩こそはその無償性にこたえうる最後のものだと私は考えている。そのようなものとしての詩が、批評を内在せしめるべきことを背負わされたのが、近代の宿運であったろう。綜合をめざす詩が分析をめざす批評を内にかかえこまねばならないとは、一見、矛盾にみえるかもしれないが、決してそれは矛盾ではないのである。なぜなら、自分自身を含めた世界を批評することによって、私たちは自身と世界の分裂や分極の様相を知るのであり、知ることによってしか綜合へと向かう道は視えてこないからである。
大澤恒保『ひとりのひとを哀しむならば』川出書房新社 1999年 〔解説〕吉本ばなな「ひとりのひとを哀しむならば」を読んで
脊髄の腫瘍も、どこかにあるかもしれない癌たちも、当然ありがたくはないが、みんな僕の身体の構成要素だ。それらと付き合いきればいい。切り取って排除するつもりはもうぜんぜんない。そういうものがない僕の身体などは考えられないし、今までの僕の人生もまた考えられない。それらはいわば僕という人間が存在する前提条件なのだ。人間が自然の異物でありながら、しかも自然の一部であるのとまったく変わらない。
僕は今、生も死も意図せず計らわずと、そんな心境を確実なものにしたい気がしているのだが、しかしこれもまた身構えることではなさそうだ。どう悟ったようなことを考えたところで、いざそのときになればきっと未練がましく慌てふためくにちがいないのだから。結局のところ、祖父の口癖だった「所詮、なるようにしかならんサ」ということに落ち着きそうだ。
〔解説〕「ひとりのひとを哀しむならば」を読んで 吉本ばなな
この本はみんなが期待しているような感じに、生命のすばらしさを高いところからうたいあげた本ではない。わかりやすい克服や成長や悟りも出てこない。人生の、命の、愛の、生きていることのたまらなさを綴った本だ。神も仏もない現実世界の本だ。しかしこの強い意志、透明な愛情に触れたら、読んだ人は必ず、生命の意味を感じる。この本の中で神や仏に出会わなくても、ひとりの人間の人生の確かさによっぽど救われる。
脊髄の腫瘍も、どこかにあるかもしれない癌たちも、当然ありがたくはないが、みんな僕の身体の構成要素だ。それらと付き合いきればいい。切り取って排除するつもりはもうぜんぜんない。そういうものがない僕の身体などは考えられないし、今までの僕の人生もまた考えられない。それらはいわば僕という人間が存在する前提条件なのだ。人間が自然の異物でありながら、しかも自然の一部であるのとまったく変わらない。
僕は今、生も死も意図せず計らわずと、そんな心境を確実なものにしたい気がしているのだが、しかしこれもまた身構えることではなさそうだ。どう悟ったようなことを考えたところで、いざそのときになればきっと未練がましく慌てふためくにちがいないのだから。結局のところ、祖父の口癖だった「所詮、なるようにしかならんサ」ということに落ち着きそうだ。
〔解説〕「ひとりのひとを哀しむならば」を読んで 吉本ばなな
この本はみんなが期待しているような感じに、生命のすばらしさを高いところからうたいあげた本ではない。わかりやすい克服や成長や悟りも出てこない。人生の、命の、愛の、生きていることのたまらなさを綴った本だ。神も仏もない現実世界の本だ。しかしこの強い意志、透明な愛情に触れたら、読んだ人は必ず、生命の意味を感じる。この本の中で神や仏に出会わなくても、ひとりの人間の人生の確かさによっぽど救われる。
内田樹『邪悪なものの鎮め方』(株)バジリコ
あらゆる場合に、私たちは判断の当否について客観的根拠(言い換えれば「数値」)を要求される。数値をもって示すことのできない「知」は知としては認知されない。…〔十九世紀末、イワノフスキーは〕「見えないもの」〔ウイルス〕が存在すると仮定しないと、「話のつじつまが会わない」ということを証明したのである。このような態度を「科学的」と呼ぶのだろうと私は思う。そこに「何か、私たちの手持ちの度量衡では考量できないもの」が存在すると想定しないと、「話のつじつまが合わない」場合には、「そういうものがある」と推論する。「存在する」と想定した方が話のつじつまが合うものについては、それを仮定的に想定して、いずれ「話のつじつまが次に合わなくなるまで」使い続ける、というのが自然科学のルールである。そうやって分子も、電子も、素粒子も「発見」されてきた。ところが、いま私たちに取り憑いている「数値主義」という病態では「私たちの手持ちの度量衡で考量できないもの」は「存在しないもの」とみなされなければならない。…なぜ、ある種の人は時間を「フライング」〔予見〕することができるのかを〔私たちはいま〕問うべきではないのか。
あらゆる場合に、私たちは判断の当否について客観的根拠(言い換えれば「数値」)を要求される。数値をもって示すことのできない「知」は知としては認知されない。…〔十九世紀末、イワノフスキーは〕「見えないもの」〔ウイルス〕が存在すると仮定しないと、「話のつじつまが会わない」ということを証明したのである。このような態度を「科学的」と呼ぶのだろうと私は思う。そこに「何か、私たちの手持ちの度量衡では考量できないもの」が存在すると想定しないと、「話のつじつまが合わない」場合には、「そういうものがある」と推論する。「存在する」と想定した方が話のつじつまが合うものについては、それを仮定的に想定して、いずれ「話のつじつまが次に合わなくなるまで」使い続ける、というのが自然科学のルールである。そうやって分子も、電子も、素粒子も「発見」されてきた。ところが、いま私たちに取り憑いている「数値主義」という病態では「私たちの手持ちの度量衡で考量できないもの」は「存在しないもの」とみなされなければならない。…なぜ、ある種の人は時間を「フライング」〔予見〕することができるのかを〔私たちはいま〕問うべきではないのか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
構造構成主義 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-