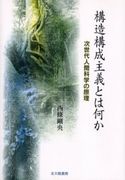西條剛央著『構造構成主義とは何か』は、アト・ランダムに陳列された思想・信条のデパートといった趣ではあるが、それらを貫き通すもの=体系というようなものは見えてこない。著者自身、P204,205の結語めいたところで、「構造構成主義」は、AでありBでありCであり、AでなくBでなくCでない、と述べており、であるなら状況に応じてAやBを選択すればよく、「構造構成主義」などという看板の必要性は認められない。
主訴とでもいうような「信念対立の克服」は、《信念》という感性的なスローガンが前面にでてきており、信条ではあるかもしれないが思想ではない。こういったものは処世術もしくは宗教のレベルで話されるものであり、ロジカルな議論にはなじまない。論ずべきは、信念に至った理路そのものであり、また論理の対立は必ずしも克服という地平で解決されるものとは限らず、異なる価値観、複数の方法を容認することも時に求められる。
思想・信条のデパートの問題点は、あまりに商品の手を広げすぎて混乱が見られることである。
たとえば、ソシュールの売り場では、『一般言語学講義』の
「個から始めてはなりません、体系から始めるのです」という目からうろこのソシュールの言説に親和性を示しながら、認識論の売り場では「疑っても疑いきれない《私》から出発するという方法」と、デカルトの大昔に逆戻りしてしまっているのだ。
犬とか猫という単語が集まって日本語を形成するのではなく、まず日本語という体系があってその中に犬とか猫という個々の単語が発生するのであり、赤とか青という個々の色があってそれらが集まり色の体系を作るのではなく、まず色彩の体系があってその中に差異としてここの色が存在するのである。同様に、個々の《私》が集まって人間社会を形成するのではなく、まず人間社会という体系があってそこに他者との差異として個々の《私》が析出するのである。
そもそも《私》というのは関係概念であって、《私》といった瞬間に《他者》はもうそこに存在している。もし宇宙に《私》一人であったら《私》という概念は意味を持たず、《私》という概念そのものが存在しないだろう。《他者》に対しての《私》であり《私》に対しての《他者》なのだ。
さらに厳密に言うならば、「疑っても疑いきれない《私》」などという言語(日本語)を何の疑いもなく前提としてしまっていることである。コギトは言語を用いることなし(言葉を使うことなく私を表明できれば)に可能であれば、成立する言辞である。
以下、次回
|
|
|
|
コメント(45)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者自身、P204,205の結語めいたところで、「構造構成主義」は、AでありBでありCであり、AでなくBでなくCでない、と述べており、であるなら状況に応じてAやBを選択すればよく、「構造構成主義」などという看板の必要性は認められない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まず細かいことですが,この「であるなら」という接続詞は前後のつながりからしておかしいと思います。
また「状況に応じてAやBを選択すればよく」というのは,構造構成主義ではなく,その一部の関心相関的選択のことを指しているのかもしれませんが,そうだとすれば,それは片手落ちの理解だと思います。
目的に応じて,という肝心な部分が抜け落ちているためです。目的を抜きに,状況だけみて選ぶというのであれば,「その都度その都度選ぶ」といっていることと何ら変わりなく,合理的な選択はしにくいでしょう(結局何でもアリになりかねません。少なくともその可能性を打破できてはいないでしょう)。
また「関心相関的選択」一つだけをとって(それもきちんと理解されていませんでしたが),構造構成主義を理解した気になっているとすれば,やはりきちんと読まれていないなと思われてしまうと思います(厳しいコメントですいません)。
著者自身、P204,205の結語めいたところで、「構造構成主義」は、AでありBでありCであり、AでなくBでなくCでない、と述べており、であるなら状況に応じてAやBを選択すればよく、「構造構成主義」などという看板の必要性は認められない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まず細かいことですが,この「であるなら」という接続詞は前後のつながりからしておかしいと思います。
また「状況に応じてAやBを選択すればよく」というのは,構造構成主義ではなく,その一部の関心相関的選択のことを指しているのかもしれませんが,そうだとすれば,それは片手落ちの理解だと思います。
目的に応じて,という肝心な部分が抜け落ちているためです。目的を抜きに,状況だけみて選ぶというのであれば,「その都度その都度選ぶ」といっていることと何ら変わりなく,合理的な選択はしにくいでしょう(結局何でもアリになりかねません。少なくともその可能性を打破できてはいないでしょう)。
また「関心相関的選択」一つだけをとって(それもきちんと理解されていませんでしたが),構造構成主義を理解した気になっているとすれば,やはりきちんと読まれていないなと思われてしまうと思います(厳しいコメントですいません)。
続きです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主訴とでもいうような「信念対立の克服」は、《信念》という感性的なスローガンが前面にでてきており、信条ではあるかもしれないが思想ではない。こういったものは処世術もしくは宗教のレベルで話されるものであり、ロジカルな議論にはなじまない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「信念」の一語を捉えて,だから思想ではない,処世術,宗教だとみなすのは単にガムスさんの「信念」でしかない乱暴な異見に僕にはみえます。「愛」の現象学などというのは感性的なスローガンが全面に出てきているから,ロジカルな話ではないといっているのと同じです。
宗教との対比でいえば,構造構成主義は,宗教では超えられない壁を越えるための考え方(複数の理路の体系)です。そうしたスローガンを超えた深い理路に支えられていなければ――海外の学界の権威の提唱した理論ならばその威光で広まるということがあるかもしれませんが――一介の大学院生が作った理論が,学問や領域を問わずにいろいろな領域に導入されて広まり,様々な領域の査読のある学会誌に掲載されるなどということが起こるわけないと思います。
それに構造構成主義は「科学論」という側面もできるのですが(何しろ副題は「次世代人間科学の原理」ですから,),その側面にはまったく言及されていないので,その部分は読まれなかったのだろうなと思いました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
論ずべきは、信念に至った理路そのものであり、また論理の対立は必ずしも克服という地平で解決されるものとは限らず、異なる価値観、複数の方法を容認することも時に求められる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これは『構造構成主義とは何か』に書いてあることそのものですよ(何度も繰り返して恐縮ですが,読んでいないのがよくわかってしまうので,ガムスさんの場合は最初から最後までとばし読みをせずちゃんと読んだ方がよいと思います)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主訴とでもいうような「信念対立の克服」は、《信念》という感性的なスローガンが前面にでてきており、信条ではあるかもしれないが思想ではない。こういったものは処世術もしくは宗教のレベルで話されるものであり、ロジカルな議論にはなじまない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「信念」の一語を捉えて,だから思想ではない,処世術,宗教だとみなすのは単にガムスさんの「信念」でしかない乱暴な異見に僕にはみえます。「愛」の現象学などというのは感性的なスローガンが全面に出てきているから,ロジカルな話ではないといっているのと同じです。
宗教との対比でいえば,構造構成主義は,宗教では超えられない壁を越えるための考え方(複数の理路の体系)です。そうしたスローガンを超えた深い理路に支えられていなければ――海外の学界の権威の提唱した理論ならばその威光で広まるということがあるかもしれませんが――一介の大学院生が作った理論が,学問や領域を問わずにいろいろな領域に導入されて広まり,様々な領域の査読のある学会誌に掲載されるなどということが起こるわけないと思います。
それに構造構成主義は「科学論」という側面もできるのですが(何しろ副題は「次世代人間科学の原理」ですから,),その側面にはまったく言及されていないので,その部分は読まれなかったのだろうなと思いました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
論ずべきは、信念に至った理路そのものであり、また論理の対立は必ずしも克服という地平で解決されるものとは限らず、異なる価値観、複数の方法を容認することも時に求められる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これは『構造構成主義とは何か』に書いてあることそのものですよ(何度も繰り返して恐縮ですが,読んでいないのがよくわかってしまうので,ガムスさんの場合は最初から最後までとばし読みをせずちゃんと読んだ方がよいと思います)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
思想・信条のデパートの問題点は、あまりに商品の手を広げすぎて混乱が見られることである。
たとえば、ソシュールの売り場では、『一般言語学講義』の
「個から始めてはなりません、体系から始めるのです」という目からうろこのソシュールの言説に親和性を示しながら、認識論の売り場では「疑っても疑いきれない《私》から出発するという方法」と、デカルトの大昔に逆戻りしてしまっているのだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そもそもガムスさんが,記号論の話と,認識論の話を混同して混乱されているのが問題かと思います。
ソシュールは「コトバとは何か」という記号論の話をしているのであって,認識論の話をしているわけではないのです。解こうとした問題が異なっているのです。
『構造構成主義とは何か』をきちんと読めば書いてあることですが(フッサールを引用して書いてありますが),デカルトは近代哲学の認識問題の創始者でありながら,それを打破する理路を作り出した人でもあるのです。(デカルトは流派を超えた多くの哲学者が高く評価している思想家であって,大昔だからダメだとかそういう話にはならないと思います)。
ついでにいえばソシュールは,現象学的な考え方をコトバの基礎づけに導入したということもできます。
疲れてきましたが続きです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
犬とか猫という単語が集まって日本語を形成するのではなく、まず日本語という体系があってその中に犬とか猫という個々の単語が発生するのであり、赤とか青という個々の色があってそれらが集まり色の体系を作るのではなく、まず色彩の体系があってその中に差異としてここの色が存在するのである。同様に、個々の《私》が集まって人間社会を形成するのではなく、まず人間社会という体系があってそこに他者との差異として個々の《私》が析出するのである。
そもそも《私》というのは関係概念であって、《私》といった瞬間に《他者》はもうそこに存在している。もし宇宙に《私》一人であったら《私》という概念は意味を持たず、《私》という概念そのものが存在しないだろう。《他者》に対しての《私》であり《私》に対しての《他者》なのだ。
さらに厳密に言うならば、「疑っても疑いきれない《私》」などという言語(日本語)を何の疑いもなく前提としてしまっていることである。コギトは言語を用いることなし(言葉を使うことなく私を表明できれば)に可能であれば、成立する言辞である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
構造構成主義は「私」を前提としているのではありません。あえていうなら,探究の底板として「現象」(立ち現れ)という概念を採用しています。
それも何の疑いもなく前提としてしまっているのではなく,あらゆる認識論の共通地平を設定するという目的に照らして,機能的と考えられる方法概念として戦略的かつ自覚的に「現象」を採用しているのです。
ですから人間科学の多様な領域を基礎づける探究の底板として,より原理的な方法概念があればそれを提起すればよいのです。
「私」は「現象」に立ち現れた一つの構造ということになるのです。
「「疑っても疑いきれない《私》」などという言語(日本語)を何の疑いもなく前提としてしまっている」という批判はまったくあたらないと思います。
新刊の『看護研究で迷わないための超入門講座――研究以前のモンダイ』にも,図解も含めてわかりやすく書いてありますのでご参考にしていただければと思います。
追伸
構造構成主義に関心を持ち,ご批判していただいてありがとうございます。それについては本当に感謝しております。
ただきちんと読まれていないと「誤解ですよ」「書いてありますよ」という返事ばかりになってしまって,僕も正直しんどくなってしまうので何卒よろしくお願い致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
犬とか猫という単語が集まって日本語を形成するのではなく、まず日本語という体系があってその中に犬とか猫という個々の単語が発生するのであり、赤とか青という個々の色があってそれらが集まり色の体系を作るのではなく、まず色彩の体系があってその中に差異としてここの色が存在するのである。同様に、個々の《私》が集まって人間社会を形成するのではなく、まず人間社会という体系があってそこに他者との差異として個々の《私》が析出するのである。
そもそも《私》というのは関係概念であって、《私》といった瞬間に《他者》はもうそこに存在している。もし宇宙に《私》一人であったら《私》という概念は意味を持たず、《私》という概念そのものが存在しないだろう。《他者》に対しての《私》であり《私》に対しての《他者》なのだ。
さらに厳密に言うならば、「疑っても疑いきれない《私》」などという言語(日本語)を何の疑いもなく前提としてしまっていることである。コギトは言語を用いることなし(言葉を使うことなく私を表明できれば)に可能であれば、成立する言辞である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
構造構成主義は「私」を前提としているのではありません。あえていうなら,探究の底板として「現象」(立ち現れ)という概念を採用しています。
それも何の疑いもなく前提としてしまっているのではなく,あらゆる認識論の共通地平を設定するという目的に照らして,機能的と考えられる方法概念として戦略的かつ自覚的に「現象」を採用しているのです。
ですから人間科学の多様な領域を基礎づける探究の底板として,より原理的な方法概念があればそれを提起すればよいのです。
「私」は「現象」に立ち現れた一つの構造ということになるのです。
「「疑っても疑いきれない《私》」などという言語(日本語)を何の疑いもなく前提としてしまっている」という批判はまったくあたらないと思います。
新刊の『看護研究で迷わないための超入門講座――研究以前のモンダイ』にも,図解も含めてわかりやすく書いてありますのでご参考にしていただければと思います。
追伸
構造構成主義に関心を持ち,ご批判していただいてありがとうございます。それについては本当に感謝しております。
ただきちんと読まれていないと「誤解ですよ」「書いてありますよ」という返事ばかりになってしまって,僕も正直しんどくなってしまうので何卒よろしくお願い致します。
metaさん
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ガムスさんの「弔辞」を読んでみての感想ですが、やはりそのへん曖昧みたいですね。
記号論のおいしいとこを流用しようとして、ちょっとしくじったけど
まぁ見栄えよくできたからとりあえず売り出しちゃおう、みたいな感じなのかな。
ああいけないですね、未読の本に対してテキトウに語っては。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
はい,未読の本について批判するのは,会ったことのない人について妄想的な批判をすることと同じになってしまいますから(きちんと読んだことがある人からすると「何を言っているんだろう……」となってしまうので),metaさんご自身がおっしゃっているように,関心があるようでしたらまずは読まれたほうがよいかと思います(amazonの古本に出ているんじゃないでしょうか)。
それといくつもの専門学会誌の厳しい査読を通した論文がベースになっているわけですから,「記号論のおいしいとこを流用しようとして、ちょっとしくじったけど まぁ見栄えよくできたからとりあえず売り出しちゃおう」などという軽い調子で出せるわけはないですよ(笑)(プロの世界はどこの業界も同じだと思いますが,学問の世界もそれほど甘いものではないですよ)。
記号学にご関心があるようですが,先にも触れたように,構造構成主義の意義(すなわち既存の理論との本質的な違い)は,存在論,認識論,記号論,構造論,科学論といった個別の領域を,「現象」「構造」「関心相関性」といった最小限の概念で一貫性のある形で基礎づけ,人間諸科学の原理にまで創発している点にあると僕は思っています。
もちろん,きちんと読まれた上でのご感想や批判等々は大歓迎です(^_^)
忙しいときはすぐにご返答できないこともあるかと思いますが,できる限り真摯に返答していきたいと思っていますので今後ともどうぞよろしくお願い致します!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ガムスさんの「弔辞」を読んでみての感想ですが、やはりそのへん曖昧みたいですね。
記号論のおいしいとこを流用しようとして、ちょっとしくじったけど
まぁ見栄えよくできたからとりあえず売り出しちゃおう、みたいな感じなのかな。
ああいけないですね、未読の本に対してテキトウに語っては。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
はい,未読の本について批判するのは,会ったことのない人について妄想的な批判をすることと同じになってしまいますから(きちんと読んだことがある人からすると「何を言っているんだろう……」となってしまうので),metaさんご自身がおっしゃっているように,関心があるようでしたらまずは読まれたほうがよいかと思います(amazonの古本に出ているんじゃないでしょうか)。
それといくつもの専門学会誌の厳しい査読を通した論文がベースになっているわけですから,「記号論のおいしいとこを流用しようとして、ちょっとしくじったけど まぁ見栄えよくできたからとりあえず売り出しちゃおう」などという軽い調子で出せるわけはないですよ(笑)(プロの世界はどこの業界も同じだと思いますが,学問の世界もそれほど甘いものではないですよ)。
記号学にご関心があるようですが,先にも触れたように,構造構成主義の意義(すなわち既存の理論との本質的な違い)は,存在論,認識論,記号論,構造論,科学論といった個別の領域を,「現象」「構造」「関心相関性」といった最小限の概念で一貫性のある形で基礎づけ,人間諸科学の原理にまで創発している点にあると僕は思っています。
もちろん,きちんと読まれた上でのご感想や批判等々は大歓迎です(^_^)
忙しいときはすぐにご返答できないこともあるかと思いますが,できる限り真摯に返答していきたいと思っていますので今後ともどうぞよろしくお願い致します!
metaさん
こちらこそご丁寧なレスポンスありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いまアマゾンの中古相場を見てみたのですが、かなり高いですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
あら,そうでしたか(>_<)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それだけ関心を集めているということでしょうか。
まだ手がでないので、もっと安くなるか新書になったら読んでみますね。
大学図書館とかでは借りられるのかな。ちょっと調べてみよう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容が専門的過ぎるので新書にはならないと思います(笑)。
図書館にはおそらくあると思いますので,機会があればご高覧いただければと思います(^_^)
読まれましたら(時間のあるときにでも)感想を教えてください☆
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
こちらこそご丁寧なレスポンスありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いまアマゾンの中古相場を見てみたのですが、かなり高いですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
あら,そうでしたか(>_<)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それだけ関心を集めているということでしょうか。
まだ手がでないので、もっと安くなるか新書になったら読んでみますね。
大学図書館とかでは借りられるのかな。ちょっと調べてみよう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容が専門的過ぎるので新書にはならないと思います(笑)。
図書館にはおそらくあると思いますので,機会があればご高覧いただければと思います(^_^)
読まれましたら(時間のあるときにでも)感想を教えてください☆
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
先生(これまでの経緯上こう呼ばさせていただきます)!やっとお話ができるテーブルについて下さいましたね、ありがとうございます。
これまでの再三の問いかけは無視され続けたので、今回ちょっと挑発的なタイトルを掲げてみましたが、お気に障られたようであれば、ご寛恕いただければと思います。
また、懇切丁寧な長文のコメント、深く感謝いたします。
さて、先生の冒頭の部分のコメントは、私の議論するうえでの《姿勢》に対するアドバイスとのことですが、先生の語法のフラットに言って苦言、もっと言えば「こんな批判をしているようじゃお前のためにならないぞ」という意味での婉曲な恫喝とも読めるものです。論理がスカスカになってくると恫喝にすり替えるというのは昔からよくあるパターンです。同じく、論理が脆弱化してくると「いくつもの専門学会誌の厳しい査読を通した論文なのだから」というような権威の威光にすり替えて行くのもよくみられるパターンです。
メッセージでも(ありがとうございます)同様な内容のことをお書きいただきましたが、私めも自らを浅学菲才の輩、人品骨柄の卑しき男と自覚しておりますので、私の姿勢に対する忠告は一度で十分かと・・・
それよりも中身の議論をじっくりいたしたいと思っております。このトピック内では、先生とガムスだけでなく大勢の方がこれをご覧になっていると思いますので、いつでも横から入っていただいて、賑やかな、活発な議論が展開できれば幸せです。
では、次からは中身の議論に入っていきます。
先生、ご機嫌いかがですか。ガムスです。
本題に入る前に、mixist(これをご覧になっている皆さんをこう呼ばさせていただきます)の皆さんもお気づきだと思いますが、執拗に「ちゃんと読め」「熟読せよ」「飛ばし読みをするな」「きちんと読め」の類のありがたいアドバイスをいただきましたが、一つ言えることは先生ほどには「きちんと読め」ていないということは確実に言えると思います。ただ、「弔辞」のあんな短い文章でこれだけの長文のコメントをいただいたので、「ちゃんと読ん」だらどうなるんでしょうか。大丈夫なんでしょうか・・・
今回は、冒頭のアドバイス欄の
>きちんと読むとは,構造構成主義の根本動機(何を目的に作られた理論なのか)を踏まえた上で,その目的を達成するためにそれぞれの方法概念が導入されているのですから,その目的に照らしてそれらの方法概念が有効に機能しているかどうかを検討された方がよいということです。
について考察します。同じような文章は、おしまいの方にも出てきます。
>それも何の疑いもなく前提としてしまっているのではなく,あらゆる認識論の共通地平を設定するという目的に照らして,機能的と考えられる方法概念として戦略的かつ自覚的に「現象」を採用しているのです。
なかなか晦渋な文章なので、なんとなくこのままわかった気になって納得しなければいけないような気分になりますが、これをガムス流に捌くとわかりやすくなります。
「すべての人の幸福(悟りの境地)の共通地平を設定するという目的に照らして、機能的と考えられる方法概念として戦略的かつ自覚的に《サリン》を採用しているのです」
この文章で言えることは、幸福達成という目的に照らして《サリン》という方法が有効に機能しているかを検討する以前に、目的とは関係なしに《サリン》という方法そのものを検討することこそが重要なのではないでしょうか。
オウムの連中も、ガムス流に考えることができたならば、多くの犠牲者を出さずに済み、また自らも死刑にならずに済んだと思うと胸が痛みます。
次に、また違った観点からこの問題を考えてみますが、恐縮ですがパン屋は朝が早いので、次回ということで・・・
盛り上がりそうな予感ですね。
>mixist
おもしろいコトバだと思います。もともと「mixi」というのは、「i(わたし)をさまざまな交流のなかでmix(かきまぜる)」という意味合いが込められたコトバだそうです。インターネットの交流のなかで“自分壊し”、つまり、「昨日の自分を打ち破って、明日の自分に会いにいく旅」を続けているぼくたちmixistの「ism(主義)」ってのは、いったいどんなものなのでしょうか。それをきちんと知るためにも、ぼちぼち書いていきましょう。と、そのまえに、
>先生ほどには「きちんと読め」ていないということは確実に言えると思います。
いやいや、かならずしもそうとは限りませんよ。本の作者は“最初の読者”ではあっても、“最良の読者”であるかはわからないので。そうだからこそ、「中身が妥当かどうか?」とか、「もっと上手く言い当てられないか?」という“言語ゲーム”をみんなでやっていく意義があるのだと思います。
さて、ここでいったん区切って、次のコメントからは本題について書いていこうと思います。
>mixist
おもしろいコトバだと思います。もともと「mixi」というのは、「i(わたし)をさまざまな交流のなかでmix(かきまぜる)」という意味合いが込められたコトバだそうです。インターネットの交流のなかで“自分壊し”、つまり、「昨日の自分を打ち破って、明日の自分に会いにいく旅」を続けているぼくたちmixistの「ism(主義)」ってのは、いったいどんなものなのでしょうか。それをきちんと知るためにも、ぼちぼち書いていきましょう。と、そのまえに、
>先生ほどには「きちんと読め」ていないということは確実に言えると思います。
いやいや、かならずしもそうとは限りませんよ。本の作者は“最初の読者”ではあっても、“最良の読者”であるかはわからないので。そうだからこそ、「中身が妥当かどうか?」とか、「もっと上手く言い当てられないか?」という“言語ゲーム”をみんなでやっていく意義があるのだと思います。
さて、ここでいったん区切って、次のコメントからは本題について書いていこうと思います。
さてさて、17の書き込みのなかでガムスさんがお考えになっているのは、われわれの日常生活における[目的-方法]の関係についてですね。そのことにかんして、ガムスさんは、おそらく1995年のオウム真理教(アーレフに改称)の事件をふまえていると思われる、「サリン」のことを取り上げています。
>「すべての人の幸福(悟りの境地)の共通地平を設定するという目的に照らして、機能的と考えられる方法概念として戦略的かつ自覚的に《サリン》を採用しているのです」
これは「事件を引き起こしたオウム信者側の主張」と捉えてまちがいないですね? それに対して、ガムスさんは、
>幸福達成という目的に照らして《サリン》という方法が有効に機能しているかを検討する以前に、目的とは関係なしに《サリン》という方法そのものを検討することこそが重要なのではないでしょうか。
と分析なさっていますね。ぼくなりにまとめるならば、「用法・用量を守り、取り扱いにご注意ください。」ということでしょうか。
ただ、「方法そのもの」を検討することってできるんですかね? というのは、一般に[方法]というのは、「何らかの[目的]を達成するためのもの」ですよね。たとえば、パンは「おなかをみたす」とか「味を楽しむ」とか「(販売することで)生活の糧とする」といった[目的]のために存在します。ひとつにしぼる必要はないですが、やっぱり、人は何らかの[目的]があって、パンをつくり、パンを買い、そして、パンを食べるわけです。
ここで、議論の前提とするために「サリン」について情報を調べてみましょう。とりいそぎWikipediaより引用します。
《VXガスと同じでコリンエステラーゼ阻害剤として作用する。元々は有機リン系殺虫剤の開発過程で発見されたものとはいえ、人体に対する毒性や取り扱いの危険性が高すぎるため、実質的には殺人以外に用途は無い。》
ここで「実質的には殺人以外に用途は無い」という記述がみられるように、サリンという[方法]には「殺人」という[目的]しかないようです(笑)。そう考えると、「すべての人の幸福(悟りの境地)の共通地平を設定する」という[目的]にてらして考えると、サリンという[方法]はあんまり有効ではないということがわかります。(やっぱり[目的-方法]という線でとらえたほうが腑に落ちやすいような気がしますが、どうでしょうか)。
オウム真理教の人たちも、おそらく政権選挙に打って出たときまでは、こういう“目的合理的な行動”を取ることができていたんでしょうね。「すべての人を幸福に導く」という[目的]にてらして、「議会制民主主義=“国立の言語ゲームの場”に議席を得る」という妥当な[方法]を選択できていたわけですから。あの真理党の敗退以降の暴走については、ちょっとぼくの論理では分析不可能です。そこからは、おそらく、だれにでも納得できるような「目的合理」に基づくのではなくて、じぶんたちの信仰の論理のなかでしか通用しない「価値合理」に基づいて行動してしまったんでしょう。
以上が、とりあえずぼくなりに構造構成主義を理解したうえでのサリン事件分析(の一端)です。これについて、「妥当かどうか?」とか、「別の観点からみたほうが本質がわかるよ」といったご意見があれば、ご教示くださいませm(__)m
>「すべての人の幸福(悟りの境地)の共通地平を設定するという目的に照らして、機能的と考えられる方法概念として戦略的かつ自覚的に《サリン》を採用しているのです」
これは「事件を引き起こしたオウム信者側の主張」と捉えてまちがいないですね? それに対して、ガムスさんは、
>幸福達成という目的に照らして《サリン》という方法が有効に機能しているかを検討する以前に、目的とは関係なしに《サリン》という方法そのものを検討することこそが重要なのではないでしょうか。
と分析なさっていますね。ぼくなりにまとめるならば、「用法・用量を守り、取り扱いにご注意ください。」ということでしょうか。
ただ、「方法そのもの」を検討することってできるんですかね? というのは、一般に[方法]というのは、「何らかの[目的]を達成するためのもの」ですよね。たとえば、パンは「おなかをみたす」とか「味を楽しむ」とか「(販売することで)生活の糧とする」といった[目的]のために存在します。ひとつにしぼる必要はないですが、やっぱり、人は何らかの[目的]があって、パンをつくり、パンを買い、そして、パンを食べるわけです。
ここで、議論の前提とするために「サリン」について情報を調べてみましょう。とりいそぎWikipediaより引用します。
《VXガスと同じでコリンエステラーゼ阻害剤として作用する。元々は有機リン系殺虫剤の開発過程で発見されたものとはいえ、人体に対する毒性や取り扱いの危険性が高すぎるため、実質的には殺人以外に用途は無い。》
ここで「実質的には殺人以外に用途は無い」という記述がみられるように、サリンという[方法]には「殺人」という[目的]しかないようです(笑)。そう考えると、「すべての人の幸福(悟りの境地)の共通地平を設定する」という[目的]にてらして考えると、サリンという[方法]はあんまり有効ではないということがわかります。(やっぱり[目的-方法]という線でとらえたほうが腑に落ちやすいような気がしますが、どうでしょうか)。
オウム真理教の人たちも、おそらく政権選挙に打って出たときまでは、こういう“目的合理的な行動”を取ることができていたんでしょうね。「すべての人を幸福に導く」という[目的]にてらして、「議会制民主主義=“国立の言語ゲームの場”に議席を得る」という妥当な[方法]を選択できていたわけですから。あの真理党の敗退以降の暴走については、ちょっとぼくの論理では分析不可能です。そこからは、おそらく、だれにでも納得できるような「目的合理」に基づくのではなくて、じぶんたちの信仰の論理のなかでしか通用しない「価値合理」に基づいて行動してしまったんでしょう。
以上が、とりあえずぼくなりに構造構成主義を理解したうえでのサリン事件分析(の一端)です。これについて、「妥当かどうか?」とか、「別の観点からみたほうが本質がわかるよ」といったご意見があれば、ご教示くださいませm(__)m
まこすけさん、こんばんわ。いよいよエースの登場でしょうか、よろしくお願いいたします。
どうもまこすけさんは、小難しく考えすぎているようですが、私があそこで述べたことはいたって単純です。
まず、先生の持って回ったような分かりにくい文章を、オウム真理教になぞらえて書きなおすことによって、文章そのものはとても分かりやすくなったのではないでしょうか(mixistのみなさんいかがですか?)。親切にも、kamuyaさんがサリン事件の分析までしてくださいましたが、私は、そのようなことを企図したわけではありません。
>結論が論理的に飛躍していて,どうしてそうなるのかがまったくわかりません.
>どうして「方法そのものを検討することこそが重要なのではないでしょうか」と言えるのですか?
これも話は単純でして、かつての新左翼や、連合赤軍に見られるように革命という目的が肥大化、絶対化してくると、目的に至る手段や方法が没論理化し、何でもアリになってしまう訳です。と、ここまではまだ、目的との関係性の中で話していると言えなくもありませんが、没論理化とは関係性を断ち切ることで、もっと具体的には、「リンチ殺人」などは目的に関係なく指弾されなければなりません。裁判になった場合には、「リンチ殺人」という方法そのものが考量され、革命という目的が量刑を左右することはないでしょう。
もう一つ卑近な例をあげれば、核兵器のケースです。核兵器の目的は、積極的には核攻撃、消極的には抑止力とでもなりましょうか。この問題は現在、核兵器の目的を離れて、核を持つこと、核の存在自体が問われているのではないでしょうか。
論証過程と言うほど大げさなものではありませんが、このようにご理解いただければと思います。
まこすけさん、どうも。私も「このトピックを見ている全員(mixist)」の一人なので、コメントさせていただきます。
>長々と書いてきましたが,大切なことは,たけぞうさんの言っていることは「姿勢」「態度」の問題ではなく,「読解の技術」「国語」の問題だという点です.
まこすけさんは、このトピックの先生のコメントを「ちゃんと読ん」でいるんでしょうか。
「墓穴を掘る」「思い込みに呑まれる」「批判してやろうという欲望」等々のほかに、メッセージには「妄想的批判」とまで書かれましたが、こういうのを、まこすけさんは、「姿勢」「態度」の問題ではなく、「読解の技術」「国語」の問題だととおっしゃるのでしょうか。
また、読み手の「読解の技術」「国語」の問題を問うのであれば、書き手の「著述の技術」「国語」の問題も問われなければなりません。そして、読み手は本の代金としてお金を払い、書き手は印税としてお金を受け取ります。私のような自営業者の世間の常識としては、料金を受け取る方が料金を支払う側に精いっぱいのサービスをし努力を払います。
kamuyaさん、時間がなくなりました。ごめんなさい。
>長々と書いてきましたが,大切なことは,たけぞうさんの言っていることは「姿勢」「態度」の問題ではなく,「読解の技術」「国語」の問題だという点です.
まこすけさんは、このトピックの先生のコメントを「ちゃんと読ん」でいるんでしょうか。
「墓穴を掘る」「思い込みに呑まれる」「批判してやろうという欲望」等々のほかに、メッセージには「妄想的批判」とまで書かれましたが、こういうのを、まこすけさんは、「姿勢」「態度」の問題ではなく、「読解の技術」「国語」の問題だととおっしゃるのでしょうか。
また、読み手の「読解の技術」「国語」の問題を問うのであれば、書き手の「著述の技術」「国語」の問題も問われなければなりません。そして、読み手は本の代金としてお金を払い、書き手は印税としてお金を受け取ります。私のような自営業者の世間の常識としては、料金を受け取る方が料金を支払う側に精いっぱいのサービスをし努力を払います。
kamuyaさん、時間がなくなりました。ごめんなさい。
>時間がなくなりました。
かまいませんよ。明日も心を込めて、おいしいパンをつくってくださいね(^_^)。
つづきの議論はまた明日になりそうですが、それまでに、ちょっとした“仕込み”ということで、「ガムスさんの問題意識はこのあたりにあるのかな?」とぼくなりに受け止めたことを整理してみますね。
>目的に至る手段や方法が没論理化し、何でもアリになってしまう
つまり、【本来はある[目的]のためにしつらえられた[手段]なり[方法]なりが、もともとの[目的]を見失い、その[手段ないし方法]そのものが“自己目的化”してしまう】。そういった事態のことを、ガムスさんは上手く言い当てようと試みているのかな?と思いました。
具体的な話でいえば、「ある[目的](たとえば革命活動)のために結成された組織」があるとします。最初はきちんとした活動をしていたのですが、年月が経ち、しだいにマンネリ化していくにつれて、「実際の活動ではなく、“組織を維持すること”そのものを[目的]として動いてしまう」ということは、しばしばあります。また、やがて末期になると、「意見の異なるメンバーを排除することによって組織の団結を維持しようとする」ような“極論”に陥ってしまいます。それが「リンチ殺人」の第一歩です。(先の「サリン事件」も、その一例として位置づけられそうですね。「すべての人の幸福のための教団」だったはずが、いつのまにか、「教団そのものの存続のためにその他の人を不幸にする」というふうに、理屈が“転倒”してしまうわけです)。
どちらかというと、たけぞうさんの論理は、「これから何かをやるにあたって、そのための構造(=方法)を建設的につみあげていく」ということに“関心”を置いているように思います。それに対して、ガムスさんは、「すでに役割を終えてしまった構造(=方法)を放置しておくと危ないので、安全なやり方で解体する」ということに“関心”を置いているのではないでしょうか。以上のことを、あえて[目的-方法]という枠組みのなかで整理してみるならば、
「【「ある手段・方法が“一人歩き”することによる悪影響をとりのぞく」という関心にてらして考えるならば、】方法そのもの【が自己目的化してしまう現象】を検討することこそが重要なのではないでしょうか」
このようにコトバを加えたら、論理的な飛躍がなく、納得しやすい文章になるのではないかと思います。いかがでしょう? また明日にでも、ご意見いただければと思います。
かまいませんよ。明日も心を込めて、おいしいパンをつくってくださいね(^_^)。
つづきの議論はまた明日になりそうですが、それまでに、ちょっとした“仕込み”ということで、「ガムスさんの問題意識はこのあたりにあるのかな?」とぼくなりに受け止めたことを整理してみますね。
>目的に至る手段や方法が没論理化し、何でもアリになってしまう
つまり、【本来はある[目的]のためにしつらえられた[手段]なり[方法]なりが、もともとの[目的]を見失い、その[手段ないし方法]そのものが“自己目的化”してしまう】。そういった事態のことを、ガムスさんは上手く言い当てようと試みているのかな?と思いました。
具体的な話でいえば、「ある[目的](たとえば革命活動)のために結成された組織」があるとします。最初はきちんとした活動をしていたのですが、年月が経ち、しだいにマンネリ化していくにつれて、「実際の活動ではなく、“組織を維持すること”そのものを[目的]として動いてしまう」ということは、しばしばあります。また、やがて末期になると、「意見の異なるメンバーを排除することによって組織の団結を維持しようとする」ような“極論”に陥ってしまいます。それが「リンチ殺人」の第一歩です。(先の「サリン事件」も、その一例として位置づけられそうですね。「すべての人の幸福のための教団」だったはずが、いつのまにか、「教団そのものの存続のためにその他の人を不幸にする」というふうに、理屈が“転倒”してしまうわけです)。
どちらかというと、たけぞうさんの論理は、「これから何かをやるにあたって、そのための構造(=方法)を建設的につみあげていく」ということに“関心”を置いているように思います。それに対して、ガムスさんは、「すでに役割を終えてしまった構造(=方法)を放置しておくと危ないので、安全なやり方で解体する」ということに“関心”を置いているのではないでしょうか。以上のことを、あえて[目的-方法]という枠組みのなかで整理してみるならば、
「【「ある手段・方法が“一人歩き”することによる悪影響をとりのぞく」という関心にてらして考えるならば、】方法そのもの【が自己目的化してしまう現象】を検討することこそが重要なのではないでしょうか」
このようにコトバを加えたら、論理的な飛躍がなく、納得しやすい文章になるのではないかと思います。いかがでしょう? また明日にでも、ご意見いただければと思います。
kamuyaさん まこすけさん 遅くなりました。
今日はほんの少しということでお許しを・・・・
>結論が論理的に飛躍していて,どうしてそうなるのかがまったくわかりません.
>どうして「方法そのものを検討することこそが重要なのではないでしょうか」と言えるのですか?
前回ゴチャゴチャ書いた感があるので、簡潔に・・・・
?サリンの使用という方法は、目的に関係なく悪いことだから。
?サリンの使用という方法を、目的と関係づけたために、正当化され、悲劇が起った。
?サリンという方法を、目的と切り離してその妥当性を判断していれば、悲劇は起こらなかった。
>前者の例で言えば,背景には裁判の目的(たとえば公共の福祉の維持,罪に対して罰を与える,など)があるわけですから,その目的に照らしてリンチ殺人の量刑が決められるという話しであり,目的に応じて方法を検討するという話しの例外ではないように思うのです.
これは二つの違う問題をゴッチャにしています。
私が問題にしているのは「リンチ殺人(方法)−革命(目的)」という図式での話です。裁判云々というのは説明のための付随的な事柄です。この図式でのメインテーマではありません。ところが、まこすけさんの見解では、裁判の目的に話がすりかわっています。つまり、革命という目的に応じて、リンチ殺人という方法を検討するというような事があってはなりません。リンチ殺人の妥当性などというのは、目的とは切り離して論じられなければなりません。ここで付随的な話ですが、裁判になった場合には、革命という目的が量刑を左右することはない、ということです。(裁判の目的の話をしているわけではありませんよ)
>もう一つ卑近な例をあげれば、核兵器のケースです。核兵器の目的は、積極的には核攻撃、消極的には抑止力とでもなりましょうか。この問題は現在、核兵器の目的を離れて、核を持つこと、核の存在自体が問われているのではないでしょうか
>そして,後者の例で言えば,それこそ「構造構成主義とは何か」で繰り返し問題性を指摘している「方法の自己目的化」の例ではありませんか?
核の目的を切り離して、核の所持、存在自体を問う、ということと、「方法の自己目的化」ということとは、一つの事柄の二つの表記法にすぎません。「核の目的を切り離して、核の所持、存在自体を問う」という問題が現実にあるということに注目してください。
kamuyaさん今晩は、そしてごめんなさい。まこすけさんに、kamuyaさんのコメントにもちゃんと答えるようにと怒られてしまいました。時間がかかるかもしれないけれど頑張ります。
kamuyaさんの文章は、とてもわかりやすく、ポイントをまとめるのもとても上手だと思います。まこすけさんには、万度「おまえの文章は分からない」と言われているので、kamuyaさんを見習わなければなりませんね。パンを使って、易しく説明されたところなどは、《象印賞》(ちょっと古いかな)ものです。
>目的に至る手段や方法が没論理化し、何でもアリになってしまう
つまり、【本来はある[目的]のためにしつらえられた[手段]なり[方法]なりが、もともとの[目的]を見失い、その[手段ないし方法]そのものが“自己目的化”してしまう】。そういった事態のことを、ガムスさんは上手く言い当てようと試みているのかな?と思いました。
『構造構成主義とは何か』(P58)−−−以後この書名をテキスト、ページだけの表示の時は、このテキストのページということにしますーーーに、方法の自己目的化の説明として、「本来お金は、幸せに生きるための『手段』にすぎない。しかし、お金を稼ぐために病気になってしまったり、過労死したり、借金を苦にして自殺してしまうことはめずらしくない。幸せに生きる手段であるお金を追及しているうちに、それ自体が目的となってしまい、それを失ったことで死んでしまったりするという意味では、本末転倒現象の1つといえよう」と記述されています。
確かに日常このような言い回しはよく聞きますし、この文章の字面だけを追っていけば、「お金を稼ぐこと自体」が目的となって、本来あった目的がどこかにいってしまったようにみえます。しかし、この文章では、「お金」の「意味」が行方不明になってしまっています。「お金」には「価値」が含まれています。つまり、「幸せに生きるという目的」が担保されているからこそ「稼ぐ」のであって、単なる紙切れや、円形の金属片は目的たりえません。ですから表面的には、「お金を稼ぐこと自体が目的」のように見えるかもしれませんが、その実体は、現時点では顕在化していないかもしれないけれど、何かに役立てる、使う、という目的のための手段であることには変わりありません。目的が背景に退き、手段が前景にあるという位置関係のために「手段・方法の自己目的化」のように表面的には見えるかもしれませんが、方法−目的・図式が消失したわけではありません。(ところで「国語」の質問ですが、なぜ「自己」目的化なのですか?単に「目的化」といっても意味は変わらないと思うのですが・・・)
そして、kamuyaさんが取り上げた、方法−目的・図式ーーーリンチ殺人(方法)−革命(目的)においても、客観的に(私たちの視点で見れば)リンチ殺人という方法が目的化しているように見えないこともありませんが、リンチ殺人−革命というのは彼らの論理であって、その文脈で見れば、リンチ殺人が目的化したということではなく、やはり革命のためのリンチ殺人であり、組織維持のためというように目的がすり替わったとしても、それも革命のため、というのが彼らの論理であり、方法−目的・図式が変化したわけではありません。
ただし、私たちがこの問題を、取り上げる場合は、彼らの論理とは関係なく、私たちの論理、私たちの法律で考えることになります。彼らの方法(リンチ殺人)は、目的(革命)と切り離して糾弾されます。
今日はここまでということで・・・分かりにくかったでしょうか?
まこすけさん、今日は、本日は日曜日以外は月1回だけの休み(第3月曜日)なので、昨夜のあっという間に消えてしまったものを思い出しながら書いてみることにします。
「私は感性的体験によって生きているのであって、論理的釈明によって生きているのではない」(G・バタイユ『内的体験』)なんていう言葉もありますが、ここはそういう場所ではないですね、頑張ります。
>感情的には納得できます.
>僕も感情的には同意します
>しかし,論理的には,どうしてそういえるのかがよくわかりません
>これも感情的にはよくわかります
>感情的にはとてもよくわかります
以上の書き込みから、感情的には分かっていただいたことがよく分かりました。バタイユの言葉ではないけれど、もうそれで十分だと思うのですが、それではダメなんですね。分かりました。話を進めてみます。
「?サリンの使用という方法は、目的に関係なく悪いことだから」
という文章は、サリンとか目的という単語をのぞいて本質だけを抽出すれば、「なぜ人を殺してはいけないのか」という風に言い換えることができます。?の方法とか目的は「なぜ人を殺してはいけないのか」のフィールドのなかにあって、これまでの一連の文脈から目的も方法もはっきりしているわけですから、?の文章だけで、感情的にでなく十分だと思いますが、それでも「明確な論証」をとおっしゃるのは、たぶん「なぜ人を殺してはいけないのか」という本質的な部分について論証せよ、ということだと思いますが、違っていますでしょうか?
そういうことだとして、話を進めます。
「なぜ人を殺してはいけないのか」を論証せよ、に対する私の回答は、まこすけさんがこのような問いかけをされたときに、考えたこと、まこすけさんは感性的にではなくロジカルに考えるでしょうからそのロジックが私のロジックです。つまり、このような問題に対する答えは、多くの人に備わっている共通認識のようなもので、「公理」とでもいうべきものでしょう。公理を論証せよということなので、このような回答になります。
ただし、この「公理」はしばしば侵害されることがあります。たとえば、戦争、ホロコースト、死刑等々。この場合は、公理の「系」が違っているのです。私たちは「人を殺してはいけない」という系の側に立ち、その目的とは関係がなく、サリンを使用して人を殺めるのはいけないという系の側に立っているのです。
精神科医の内海健はこの問題について、次のように書いています。
「昨今、『なぜ人を殺してはいけないのか』という幼稚な問いに大人の世界が揺らいでいますが、これはある意味では死を象徴化する社会の機能が弱まっているために、そういう問いがぬけぬけと出てくるのだろと思います。すでに死を象徴化してしまったわれわれの側にそういうものがつきつけられると、『え?』とたじろいで、口ごもるしかないという事態が起きているのです」(『精神科臨床とは何か』P45)
ここで一つ提案があります。話が非常に思弁的になり、互いに「分からない」を連発し合うような状況で、mixistの皆さんも分かりずらいのではないでしょうか。そこで分かりやすくするための、建設的・生産的な提案です。
ガムスです。続きを行きます。
先生は「これまでの議論から、構造構成主義は基礎から応用まで幅広い研究領域に継承(導入)可能な原理であることがわかるであろう。構造構成主義は新たな考え方の基礎となる「原理」であるため、テーマや領域を問わずそれらを基礎づけるもの(の)枠組みとなる。又、ここではすでに導入されつつある『研究法』に焦点化して紹介したが、その継承対象は研究領域に限られたものではなく、あらゆる領域に継承することが可能であろう」(P236)と書かれ、「使えるメタ理論である」ともおっしゃっています。
そこで議論を分かりやすくするために、具体的なテーマを設定して、その中の応用という形で、「構造構成主義」を説明していただくと、理解を助けることになると思います。この場面ではこのように構造構成主義を用い、ここはこう考えるのが構造構成主義的だと示していただければ、分かりやすくなり、実際のケースの中で議論し合えば、いたずらに思弁的になることもなくなると考えられます。mixistの皆さんいかがでしょうか?
ということで、テーマの設定です。先生の専門の「心理学」、私の専門の「精神保健福祉」の領域にまたがった問題として「自殺問題」はいかがでしょうか?
これは未だ実効ある対策が打ち出されておらず、喫緊の課題となっています。もし、この問題に対して、構造構成主義的に有効な方法が提出できれば、単に構造構成主義の理解を深めるだけでなく、社会に寄与・貢献することになります。構造構成主義のファンも増え、著書の売り上げも上がるかもしれません。
ここでの議論はこのまま続けて行き、別トピでテーマ
「構造構成主義の実践的展開ーーー自殺問題への応用」
を、先生とまこすけさんの共同作業でもかまいませんので、ぜひともおねがいいたします。
終わりに、
>目的は何ですか?
についてです。
私については、かなりオバカなのでもうちょっとオリコウになりたいということです。
私以外の部分では、「構造構成主義も、構成された1つに構造にすぎない。したがって、常に構成され続ける必要がある。読者の方々から、さまざまな意見をいただくことにより、構造構成主義をより精緻化、発展させていきたいと考えている」(テキスト「はじめに」より)に少しでも、参加できたら、と考えました。
本日は以上です。
>もっつさん
「論理的に説明できないこと」は、確かにあると思います。例えば「運命」、私の山の仲間が、私の目の前で墜死したことなどは、論理的な説明のしようがありません。なぜ私ではなく彼なのか、なぜあの場所なのか、なぜあの時なのか・・・・
ですから、論理の俎上に乗せることが適当なものとそうでないものとを識別する眼力を養っていくことが大切ではないか、と考えています。
ただ、運命にしても、「前世の祟り」とかいうように、宗教的、オカルト的に説明しようとする輩がいますが、私はそういうものには与しません。
「コトバに表せないこと」については、私は言葉の範囲が世界の範囲と考えていますので、もっつさんとは少々立場が違うかもしれません。もっつさんは「コトバに現せないこと」という風にすでに言葉に現わしてしまっています。つまり、言葉に現わせない何か、というものは今現在の状況で、言葉に現わせない何かというレベルで存在している何かなのです。ですから、能力、時代や社会の変化によって現わせないことも、現せるようになるかもしれません。「コトバに現せないこと」を「コトバに現せる」ように努力していくことが大事になっていくのではないでしょうか。(ここで私が言っているのは<構造>ということなのですが)
例を上げると、万有引力はニュートンが言語化し数式化するまでは、「コトバに現せないもの」として存在していませんでした。それまで、リンゴが落ちるのは、単なる偶然か神の御業として言語化されていたのでした。ですから、西條先生は、万有引力はニュートンが<発明>したのだ、という言い回しを好まれるのです。
「核兵器」「殺人」は論理的に説明することは可能です。ただその論理というのは一つではなく、その故にどの立場に立つのかということが重要です。ナチスのホロコーストは論理的に構築されたものです。
>ガムスさん
お返事ありがとうございます.興味深い内容ですね.
ガムスさんのような大先輩のお話が聞けて非常に光栄です.
>「コトバに現せないこと」を「コトバに現せる」ように努力していくことが大事になっていくのではないでしょうか。
そうですね.ガムスさんの仰るとおりだと思います.私がコトバに現せないことをあえて「言語化」したのは,自分で「意識」することで,「言葉で現せる」ようになる努力をしないというものではありません.
「殺人がなぜダメなのか?」「核は持ってはいけない」
は論理的に説明できるのか??ダメな理由は沢山思いつきますが,論理的には私には説明できません.もし良かったら教えていただいてもよろしいでしょうか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
構造構成主義 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
構造構成主義のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90040人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6419人
- 3位
- 独り言
- 9045人