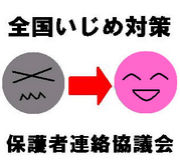(1) いじめに関する情報の徹底した収集とその公開を要望します。
→現在、自治体の教育委員会および文部科学省に報告される事例は、最悪の結果にまで至ったものがほとんどです。
いじめに対する早期介入を可能とするのは、どんな些細な事情であっても徹底して収集しそれが一般に公開されることから、
採りうる対応が明確になってくるのです。
マニュアル化が全てではありませんが、指針のない早期介入は実効性がなく、結局は最前線で働く担任の個人スキルに左右されることとなります。
徹底した調査については航空事故調査委員会の活動をみても、刑事免責を前提とする必要があるのかもしれませんが、それはこの場での提案は差し控えたいと思います。
(2) 継続的な啓蒙活動の促進
→学校におけるいじめ問題の実践的教育と一般にむけたい啓蒙活動の強化を希望します。
子どもたちは、いじめは悪いと分かっていても、何がいじめであり、何故悪いのか、またそれに加担することの意味や、制止しないことの問題点を知りません。
また被害児童も、電話相談窓口等があることを知っていても、なかなか利用しようとはしません。
彼らは「言語発達途上」にあるため、自分の苦痛を効果的に話す手段を持ちませんし、既に十二分に傷ついているからです。
++++++++++++
訴えられないのは子どもの落ち度ではありません。訴えられない環境を大人たちが作っているのです。
++++++++++++
(3) いじめ救済制度の統一化・明確化
→自治体に相談窓口があり、文部科学省もこれに関わっている・・・といったレベルの印象はあっても、まずどういった機関に相談し、どうした連携をとり、どのような対応を採ればよいのか、といったことを保護者は全てリサーチし、連絡し、手配しなければなりません。
これは本来教育機関が自発的に行うべきものにもかかわらず、様々な障壁に悩まされるのです。
夢物語ではありますが、「いじめ」対策のプロによる統一的な救済機関ができれば保護者や児童が精神的に疲弊することなく、子どもの福祉のみを目的とした行動をとりうるのではないかと考えます。心理学の専門家を中心として、法律家や当事者により学校内でのいじめや暴力への対策をチェックしたり主導的に解決しうる第三者機関の設立を望みます。
++++++++++++
ダイナミックな教育制度改革の一環としての「いじめ」対策を実現してください。
++++++++++++
(4) 保護者と学校、自治体教育委員会の連携教育体制の整備
→保護者がまず恐れるのは、いじめ事実を訴えることが、クレーマー扱いされるのではないかということです。
何度でも学校や教育委員会に連絡をとり、どんな些細なことでも連絡・質問しうる体制の保障を徹底していただきたいと思います。
「いじめ」への保護者の反応を「過剰反応」「クレーマーである」と考えないバックグラウンドは、行政の指導によって自然に構築されるのではないでしょうか。
+++++++++++++
親や当事者の救済行動を問題視しない環境を整備してください。
+++++++++++++
(5) 二次被害防止へのプログラム作り・教育現場での人権意識の向上
→既に何度も申し上げますが、被害児童が心理的・精神的にノーマルな状態でないといった考えにより、被害児童は苦しめられます。
実際、私が子どもへのカウンセリングを考える旨をホットライン等でお話しましたら、「お子さんは異常ですか?」と言われました。
「正常であれば専門的なカウンセリングは必要ではない」という非常に古式ゆかしい発想があるようです。
カウンセリングとは、個人が「危機」的状態から抜けだし、人間的な成長を遂げるために、専門家が個人が内省する際に「自己の内面に危険なほど入り込まないよう」安全弁として作用する制度です。カウンセリングを必要とするのは健全な行動なのです。
(カウンセリングの必要性は、は「内観法」によって第三者の助けを借りずに深く内省する方法によって自殺が発生するような情況を思い出していただけると分かりやすいかともいます)
→精神障害の治療と、正常な心理的葛藤を解消するカウンセリングを同視する考えは、世間に未だに根強く存在するようです。
こうした誤解は、精神障害者への差別感情を前提とする、啓蒙教育を必要とする誤解です。
こうした誤解も、行政による指導啓蒙活動を切に望みます。
(6) 「真に美しい国」実現の為の「いじめ対策」について
→現在、日本は「美しい国」たることをスローガンに掲げた各種行政上の取り組みが行われていると伝え聞いております。しかしながら、その具体的内容がどのようなものであるかについては、不明といってよいでしょう。
「メッキで美しい国」ではなく、真に「美しい国」たるためには、外交上「美しい国」をアピールすることを本旨とするのではありません。
教育問題の中で最重要課題である「いじめ」の実践的対策は「真に美しい国」としての日本にとっては必要不可欠だと考えます。
→現在、自治体の教育委員会および文部科学省に報告される事例は、最悪の結果にまで至ったものがほとんどです。
いじめに対する早期介入を可能とするのは、どんな些細な事情であっても徹底して収集しそれが一般に公開されることから、
採りうる対応が明確になってくるのです。
マニュアル化が全てではありませんが、指針のない早期介入は実効性がなく、結局は最前線で働く担任の個人スキルに左右されることとなります。
徹底した調査については航空事故調査委員会の活動をみても、刑事免責を前提とする必要があるのかもしれませんが、それはこの場での提案は差し控えたいと思います。
(2) 継続的な啓蒙活動の促進
→学校におけるいじめ問題の実践的教育と一般にむけたい啓蒙活動の強化を希望します。
子どもたちは、いじめは悪いと分かっていても、何がいじめであり、何故悪いのか、またそれに加担することの意味や、制止しないことの問題点を知りません。
また被害児童も、電話相談窓口等があることを知っていても、なかなか利用しようとはしません。
彼らは「言語発達途上」にあるため、自分の苦痛を効果的に話す手段を持ちませんし、既に十二分に傷ついているからです。
++++++++++++
訴えられないのは子どもの落ち度ではありません。訴えられない環境を大人たちが作っているのです。
++++++++++++
(3) いじめ救済制度の統一化・明確化
→自治体に相談窓口があり、文部科学省もこれに関わっている・・・といったレベルの印象はあっても、まずどういった機関に相談し、どうした連携をとり、どのような対応を採ればよいのか、といったことを保護者は全てリサーチし、連絡し、手配しなければなりません。
これは本来教育機関が自発的に行うべきものにもかかわらず、様々な障壁に悩まされるのです。
夢物語ではありますが、「いじめ」対策のプロによる統一的な救済機関ができれば保護者や児童が精神的に疲弊することなく、子どもの福祉のみを目的とした行動をとりうるのではないかと考えます。心理学の専門家を中心として、法律家や当事者により学校内でのいじめや暴力への対策をチェックしたり主導的に解決しうる第三者機関の設立を望みます。
++++++++++++
ダイナミックな教育制度改革の一環としての「いじめ」対策を実現してください。
++++++++++++
(4) 保護者と学校、自治体教育委員会の連携教育体制の整備
→保護者がまず恐れるのは、いじめ事実を訴えることが、クレーマー扱いされるのではないかということです。
何度でも学校や教育委員会に連絡をとり、どんな些細なことでも連絡・質問しうる体制の保障を徹底していただきたいと思います。
「いじめ」への保護者の反応を「過剰反応」「クレーマーである」と考えないバックグラウンドは、行政の指導によって自然に構築されるのではないでしょうか。
+++++++++++++
親や当事者の救済行動を問題視しない環境を整備してください。
+++++++++++++
(5) 二次被害防止へのプログラム作り・教育現場での人権意識の向上
→既に何度も申し上げますが、被害児童が心理的・精神的にノーマルな状態でないといった考えにより、被害児童は苦しめられます。
実際、私が子どもへのカウンセリングを考える旨をホットライン等でお話しましたら、「お子さんは異常ですか?」と言われました。
「正常であれば専門的なカウンセリングは必要ではない」という非常に古式ゆかしい発想があるようです。
カウンセリングとは、個人が「危機」的状態から抜けだし、人間的な成長を遂げるために、専門家が個人が内省する際に「自己の内面に危険なほど入り込まないよう」安全弁として作用する制度です。カウンセリングを必要とするのは健全な行動なのです。
(カウンセリングの必要性は、は「内観法」によって第三者の助けを借りずに深く内省する方法によって自殺が発生するような情況を思い出していただけると分かりやすいかともいます)
→精神障害の治療と、正常な心理的葛藤を解消するカウンセリングを同視する考えは、世間に未だに根強く存在するようです。
こうした誤解は、精神障害者への差別感情を前提とする、啓蒙教育を必要とする誤解です。
こうした誤解も、行政による指導啓蒙活動を切に望みます。
(6) 「真に美しい国」実現の為の「いじめ対策」について
→現在、日本は「美しい国」たることをスローガンに掲げた各種行政上の取り組みが行われていると伝え聞いております。しかしながら、その具体的内容がどのようなものであるかについては、不明といってよいでしょう。
「メッキで美しい国」ではなく、真に「美しい国」たるためには、外交上「美しい国」をアピールすることを本旨とするのではありません。
教育問題の中で最重要課題である「いじめ」の実践的対策は「真に美しい国」としての日本にとっては必要不可欠だと考えます。
|
|
|
|
コメント(5)
文科省に要望するべき事項に、次のことも加えるのはどうでしょう。皆さんで検討してください。
イジメはやめさせるべきことであること、これを教師学校が取るべき対応の第一原則とするよう、現場教師・校長に周知徹底させること。
(教育と言うものを知らない教師や親たちが多くなりましたので注意・補足しますが、「イジメを止めさせる」というのは、いけないことを話して教育するということで、叱ったり罰をあたえることではありません。勿論話だけでは判らない者、それに従わない者などに対しては、叱ったり罰を与えることも、出席停止・退学なども必要です。それも子供に人の社会というものを教える教育の一つでもあるのです。)
彼やの職業的習性は、イジメだと被害者が訴えても、まずはイジメをやめさせるのではなく、まずは事実確認をやり始めるのです。確認作業を始めれば彼らはイジメ成るものを知らないため、イジメを判らず「いじめはなかった」、「イジメとはいえない」などとするのです。
こうして教師と学校がイジメを止めさせないことになっているのです。
専門家がイジメとはどんなものか判らず、文科省が専門家を集め研究させても判らないから、文科省も解決策を示せないで居るのですから、素人の教員や校長がイジメなるものを知るはずがないのに、そうして知らないものは判断できるはずがないのに、イジメの「事実確認」なるものをやり始めて、錯誤のスパイラル(悪循環)に陥り、イジメ問題が全国で解決できないでいるのです。
専門家たちも、人間(子供)と言うものがそのようなもの(頭で考えることと、実行することの関係と違い)であることを知らずに、イジメを理解できるものと錯覚し、研究(事実確認のこと)を続けているのです。
まったく教師や大人たち一般が倒錯していて、自分が物事と子供や人というものを知らないのに、知っているつもりになり、善悪・良し悪しを判断できるかのように錯覚しているのです。
人々は人が頭で考えることと、実行することの関係と、その違いを理解することが出来ないのですから、上の「イジメはまずは止めさせることが大切なのだ」ということを、実行させて理解させる以外ないのです。
イジメはやめさせるべきことであること、これを教師学校が取るべき対応の第一原則とするよう、現場教師・校長に周知徹底させること。
(教育と言うものを知らない教師や親たちが多くなりましたので注意・補足しますが、「イジメを止めさせる」というのは、いけないことを話して教育するということで、叱ったり罰をあたえることではありません。勿論話だけでは判らない者、それに従わない者などに対しては、叱ったり罰を与えることも、出席停止・退学なども必要です。それも子供に人の社会というものを教える教育の一つでもあるのです。)
彼やの職業的習性は、イジメだと被害者が訴えても、まずはイジメをやめさせるのではなく、まずは事実確認をやり始めるのです。確認作業を始めれば彼らはイジメ成るものを知らないため、イジメを判らず「いじめはなかった」、「イジメとはいえない」などとするのです。
こうして教師と学校がイジメを止めさせないことになっているのです。
専門家がイジメとはどんなものか判らず、文科省が専門家を集め研究させても判らないから、文科省も解決策を示せないで居るのですから、素人の教員や校長がイジメなるものを知るはずがないのに、そうして知らないものは判断できるはずがないのに、イジメの「事実確認」なるものをやり始めて、錯誤のスパイラル(悪循環)に陥り、イジメ問題が全国で解決できないでいるのです。
専門家たちも、人間(子供)と言うものがそのようなもの(頭で考えることと、実行することの関係と違い)であることを知らずに、イジメを理解できるものと錯覚し、研究(事実確認のこと)を続けているのです。
まったく教師や大人たち一般が倒錯していて、自分が物事と子供や人というものを知らないのに、知っているつもりになり、善悪・良し悪しを判断できるかのように錯覚しているのです。
人々は人が頭で考えることと、実行することの関係と、その違いを理解することが出来ないのですから、上の「イジメはまずは止めさせることが大切なのだ」ということを、実行させて理解させる以外ないのです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
全国いじめ対策保護者連絡協議会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
全国いじめ対策保護者連絡協議会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90013人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208279人
- 3位
- 暮らしを楽しむ
- 75470人