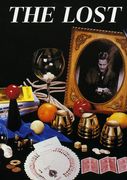『神仙戯術』(1696)
現存する日本でもっとも古い伝授本。京都の菱屋勘兵衛による刊行。
著者は明末清初の南宗画家であった陳眉光(本名、陳継儒)で、それを京都の医者である馬場信武が編集したもの。
中国書の翻訳と言われ、それ故に中国に起源があると考えられる。
収蔵される20種の内、奇術らしいものは10種に過ぎず、それ以外は生活上の知恵や科学遊びである。
山本慶一氏による考証により初版が元禄10年(1697)とされていた。
が、2005年に河合勝氏によって発見された初版本によって元禄9年(1696)という事が判明した。
南博・他編『めくらます』(1981 白水社)p87「日本の手品」平岩白風
『ザ・マジック 6号』(1990 東京堂出版)p40「日本の奇術文献2」山本慶一
『ワンツースリー 38号』(2003 日本奇術協会)p2「『伝授本』の手品考・其の十二」平岩白風
松山光伸著『実証・日本の手品史』(2010 東京堂出版)p374
現存する日本でもっとも古い伝授本。京都の菱屋勘兵衛による刊行。
著者は明末清初の南宗画家であった陳眉光(本名、陳継儒)で、それを京都の医者である馬場信武が編集したもの。
中国書の翻訳と言われ、それ故に中国に起源があると考えられる。
収蔵される20種の内、奇術らしいものは10種に過ぎず、それ以外は生活上の知恵や科学遊びである。
山本慶一氏による考証により初版が元禄10年(1697)とされていた。
が、2005年に河合勝氏によって発見された初版本によって元禄9年(1696)という事が判明した。
南博・他編『めくらます』(1981 白水社)p87「日本の手品」平岩白風
『ザ・マジック 6号』(1990 東京堂出版)p40「日本の奇術文献2」山本慶一
『ワンツースリー 38号』(2003 日本奇術協会)p2「『伝授本』の手品考・其の十二」平岩白風
松山光伸著『実証・日本の手品史』(2010 東京堂出版)p374
|
|
|
|
コメント(3)
日本最古のマジック本 元禄9年「神仙戯術」 愛知江南短大 河合教授
2005/12/26 [読売新聞] 日本最古の奇術書「神仙戯術(しんせんげじゅつ)」の初版本(10.5×16.5cm)を、愛知江南短大の河合勝教授(60)が発見。奥付の記述からこれまで不明だった初版年が、元禄9年(1696年)であることが判明。同書は日本で最初の奇術の種明かし本とされ、中国・明時代の文人、陳眉公撰。ひょうたんの中にウナギやドジョウを入れ、塩とこしょうを混ぜた水を加えると苦しがってのたうち、ひょうたんがひとりでに動くように見える手品など、20種類の手品などが記され、和訳が添えられている。これまでは、国立劇場伝統芸能情報館(東京)に保管されている正徳5年(1715年)刊本しか知られていなかった。河合教授は東京古典会の入札目録で見つけ落札。奥付の刊記から、元禄12年(1699年)に発行された続編を編集した京都の学者、馬場信武の和訳であることも分かった。同書は2006年3月10-27日、東京都千代田区九段南の山脇ギャラリーで開かれる河合教授のコレクション展で展示される。
http://blogs.yahoo.co.jp/bibliothecarii/19704121.html
2005/12/26 [読売新聞] 日本最古の奇術書「神仙戯術(しんせんげじゅつ)」の初版本(10.5×16.5cm)を、愛知江南短大の河合勝教授(60)が発見。奥付の記述からこれまで不明だった初版年が、元禄9年(1696年)であることが判明。同書は日本で最初の奇術の種明かし本とされ、中国・明時代の文人、陳眉公撰。ひょうたんの中にウナギやドジョウを入れ、塩とこしょうを混ぜた水を加えると苦しがってのたうち、ひょうたんがひとりでに動くように見える手品など、20種類の手品などが記され、和訳が添えられている。これまでは、国立劇場伝統芸能情報館(東京)に保管されている正徳5年(1715年)刊本しか知られていなかった。河合教授は東京古典会の入札目録で見つけ落札。奥付の刊記から、元禄12年(1699年)に発行された続編を編集した京都の学者、馬場信武の和訳であることも分かった。同書は2006年3月10-27日、東京都千代田区九段南の山脇ギャラリーで開かれる河合教授のコレクション展で展示される。
http://blogs.yahoo.co.jp/bibliothecarii/19704121.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-