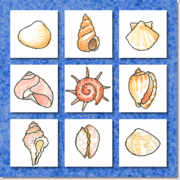電子新聞は成功できるのか 2010/01/25
メディアコンテンツを有料化する動きが日本でも本格化してきた。日本経済新聞社は14日以降、関係者にその発行計画を説明しはじめた。
現在、同紙の新聞購読料(朝、夕刊セット)は月額4,300円。現行購読者が電子版を並行して契約すれば、プラス1,000円で提供するので合計月額5,300円。電子版単独の場合の購読料は月額4,000円である。課金は基本的にカード決済である。
この料金設定を高いと見るか、リーゾナブルと見るかは立場によって分かれるだろう。「現在、無料でサービスしているNIKKEI NETとどこが違うんだ」という不満の声も聞く。
日経側は、「携帯端末からもアクセスできるし、日経BPやQUICKの企業情報、さらに人事情報や過去の記事、データも検索できる」とデータ・ベースとしての利便性と充実度を強調する。しかし日経がメインの顧客層としてきた官公庁、金融・証券界は、すでに日経テレコンやQUICKと法人契約している。となると電子新聞は、一層のこと、個人ユーザー層を狙わなくてはならない。オンライン証券を駆使するデイ・トレーダーたちの、「お値ごろ感」にフィットするかどうか、が成否を決めることになるだろう。
「市場調査は十分やった」と喜多恒雄日経社長は語るが、日経は鳴り物入りでスタートした投資情報紙、「ヴェリタス」が不振で苦戦中という"既往症"がある。
電子新聞の成否を分けるのは、料金設定だけではない。確かに米国のウォールストリートジャーナル電子版(以下WSJ)が契約者100万人のラインを突破し採算ラインに乗ったという"先例"は、ある。紙と併読で月額1,000円という設定もWSJの月額13ドルにならっている。
購読者情報を握っているのは新聞販売店
しかし、アメリカと日本の新聞販売システムが全く異なることを考えると単純なアナロジーは難しい。
何よりもアメリカの新聞(電子版を含めて)購読者は発行本社の"もの"であり、顧客管理は発行本社が行っている。これに対して日本の販売システムでは基本的に新聞購読者は販売店の"もの"であり、顧客管理も販売店が行ってきたという慣習がある。
紙の時代は新聞拡張員による購読カード生産で販売店の経営が支えられてきた。いわば、「誰が、いつから、何ヶ月間購読する」という情報が記載された講読者カードは現金と同じで、その詳細情報は通常、発行本社にすら知らせていない。
日経の電子新聞ビジネスが軌道に乗るためには、「顧客Aさんが紙の日経新聞を購読しているか、いないか」の確認が不可欠である。そのためには、販売店に問い合わせて顧客情報を提供してもらわなくてはならない。
日経の場合、定着率がよいとはいっても、新聞購読者というものは毎月のように入れ替わるものだ。だから顧客確認は、販売店にしてみれば単に面倒くさいというだけでなく、発行本社側に顧客データが蓄積されてゆくことで商売のための貴重な情報が流失する、という不安を抱えることになるのだ。
新聞販売店が抱く不安と日経の目算
さらに難しいのは、日本経済新聞社の場合、多くの地域で販売、集金を全国紙3紙、または有力地方紙の販売網に委託していることである。自らが生殺与奪の権限を握る専売店に対してなら相当強引なことはできるが、いわば他社の暖簾を借りている地域では無理な相談である。
もともと新聞販売店側には、電子新聞の発行は紙の新聞との「カニバリズム=喰い合い」となるという恐怖心があるし、この認識は、ある面で正しい。とすると、「何故、自分の足元を崩すようなことに、しかも配達、集金を委託された他社に対して協力しなくてはならないのか」という店側の疑問にストンと胸に落ちる説明は難しい。
日経だけの損得勘定でいえば月額4,300円の紙の読者が、月額4,000円の電子版読者に移行してゆくことで失うものは、さほど多くない。むしろ顧客情報を本社が管理し、決済もカードで行われるのであれば販売店手数料が省け、デジタル時代にふさわしい流通、課金決済システムが構築できるという利点がある。
喜多社長は業界紙インタビューで、「電子版単独価格の設定では、紙媒体と、ほぼ同額でなければ電子版の方にシフトしてしまう可能性もある」(文化通信1月11日)との判断があったと述べている。相当シフトする事態が視野に入っているからこそ、こういう発言が生まれるのである。
以上のような販売店サイド、および同業他社の不安に対して日経関係者は、「電子版プロジェクトは、紙の新聞に影響を与えないことを前提に進めている。デジタル情報を紙でも確認する。日経ブランドが高まり、二つの媒体は"ウイン・ウイン関係"にある」と言う。
この説明で納得する人は、よほどの楽天家であろう。
メディアコンテンツを有料化する動きが日本でも本格化してきた。日本経済新聞社は14日以降、関係者にその発行計画を説明しはじめた。
現在、同紙の新聞購読料(朝、夕刊セット)は月額4,300円。現行購読者が電子版を並行して契約すれば、プラス1,000円で提供するので合計月額5,300円。電子版単独の場合の購読料は月額4,000円である。課金は基本的にカード決済である。
この料金設定を高いと見るか、リーゾナブルと見るかは立場によって分かれるだろう。「現在、無料でサービスしているNIKKEI NETとどこが違うんだ」という不満の声も聞く。
日経側は、「携帯端末からもアクセスできるし、日経BPやQUICKの企業情報、さらに人事情報や過去の記事、データも検索できる」とデータ・ベースとしての利便性と充実度を強調する。しかし日経がメインの顧客層としてきた官公庁、金融・証券界は、すでに日経テレコンやQUICKと法人契約している。となると電子新聞は、一層のこと、個人ユーザー層を狙わなくてはならない。オンライン証券を駆使するデイ・トレーダーたちの、「お値ごろ感」にフィットするかどうか、が成否を決めることになるだろう。
「市場調査は十分やった」と喜多恒雄日経社長は語るが、日経は鳴り物入りでスタートした投資情報紙、「ヴェリタス」が不振で苦戦中という"既往症"がある。
電子新聞の成否を分けるのは、料金設定だけではない。確かに米国のウォールストリートジャーナル電子版(以下WSJ)が契約者100万人のラインを突破し採算ラインに乗ったという"先例"は、ある。紙と併読で月額1,000円という設定もWSJの月額13ドルにならっている。
購読者情報を握っているのは新聞販売店
しかし、アメリカと日本の新聞販売システムが全く異なることを考えると単純なアナロジーは難しい。
何よりもアメリカの新聞(電子版を含めて)購読者は発行本社の"もの"であり、顧客管理は発行本社が行っている。これに対して日本の販売システムでは基本的に新聞購読者は販売店の"もの"であり、顧客管理も販売店が行ってきたという慣習がある。
紙の時代は新聞拡張員による購読カード生産で販売店の経営が支えられてきた。いわば、「誰が、いつから、何ヶ月間購読する」という情報が記載された講読者カードは現金と同じで、その詳細情報は通常、発行本社にすら知らせていない。
日経の電子新聞ビジネスが軌道に乗るためには、「顧客Aさんが紙の日経新聞を購読しているか、いないか」の確認が不可欠である。そのためには、販売店に問い合わせて顧客情報を提供してもらわなくてはならない。
日経の場合、定着率がよいとはいっても、新聞購読者というものは毎月のように入れ替わるものだ。だから顧客確認は、販売店にしてみれば単に面倒くさいというだけでなく、発行本社側に顧客データが蓄積されてゆくことで商売のための貴重な情報が流失する、という不安を抱えることになるのだ。
新聞販売店が抱く不安と日経の目算
さらに難しいのは、日本経済新聞社の場合、多くの地域で販売、集金を全国紙3紙、または有力地方紙の販売網に委託していることである。自らが生殺与奪の権限を握る専売店に対してなら相当強引なことはできるが、いわば他社の暖簾を借りている地域では無理な相談である。
もともと新聞販売店側には、電子新聞の発行は紙の新聞との「カニバリズム=喰い合い」となるという恐怖心があるし、この認識は、ある面で正しい。とすると、「何故、自分の足元を崩すようなことに、しかも配達、集金を委託された他社に対して協力しなくてはならないのか」という店側の疑問にストンと胸に落ちる説明は難しい。
日経だけの損得勘定でいえば月額4,300円の紙の読者が、月額4,000円の電子版読者に移行してゆくことで失うものは、さほど多くない。むしろ顧客情報を本社が管理し、決済もカードで行われるのであれば販売店手数料が省け、デジタル時代にふさわしい流通、課金決済システムが構築できるという利点がある。
喜多社長は業界紙インタビューで、「電子版単独価格の設定では、紙媒体と、ほぼ同額でなければ電子版の方にシフトしてしまう可能性もある」(文化通信1月11日)との判断があったと述べている。相当シフトする事態が視野に入っているからこそ、こういう発言が生まれるのである。
以上のような販売店サイド、および同業他社の不安に対して日経関係者は、「電子版プロジェクトは、紙の新聞に影響を与えないことを前提に進めている。デジタル情報を紙でも確認する。日経ブランドが高まり、二つの媒体は"ウイン・ウイン関係"にある」と言う。
この説明で納得する人は、よほどの楽天家であろう。
|
|
|
|
コメント(9)
>日経だけの損得勘定でいえば月額4,300円の紙の読者が、月額4,000円の電子版読者に移行してゆくことで失うものは、さほど多くない。むしろ顧客情報を本社が管理し、決済もカードで行われるのであれば販売店手数料が省け、デジタル時代にふさわしい流通、課金決済システムが構築できるという利点がある。
正にこの部分でしょう。
すでに日経は紙も含めて電子新聞の購読料のクレジット決済を目指しています。
最終的には紙の読者の購読料もカードで本社決済とし、販売店には配達手数料としての形を目論んでいるといった噂がチラホラ。
最近の日経の動きが変であると某業界紙の談です。
過日のY紙の折込み料を本社でとって、販売店には作業手数料として支払うといった話も目指すところが似ているような気がします。
となれば、委託先は新聞販売店でなくても・・・・
といった恐ろしい構図が生まれてきます。
正にこの部分でしょう。
すでに日経は紙も含めて電子新聞の購読料のクレジット決済を目指しています。
最終的には紙の読者の購読料もカードで本社決済とし、販売店には配達手数料としての形を目論んでいるといった噂がチラホラ。
最近の日経の動きが変であると某業界紙の談です。
過日のY紙の折込み料を本社でとって、販売店には作業手数料として支払うといった話も目指すところが似ているような気がします。
となれば、委託先は新聞販売店でなくても・・・・
といった恐ろしい構図が生まれてきます。
新聞販売店への配慮と紙が減り続けた場合への布石など‥様々な思惑を込めてのスタートです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日経新聞、月額1000円からの電子版を創刊--NIKKEI NETを継承
CNET Japan 永井美智子(編集部) 2010/02/24 17:27
日本経済新聞社は3月23日、新聞紙面をそのままPCや携帯電話で見られる「日本経済新聞 電子版」(Web版)を創刊する。利用料金は新聞購読者の場合、月額1000円。現在提供しているニュースサイト「NIKKEI NET」の機能を拡張するもので、無料コンテンツも用意する。
Web版ではNIKKEI NETで提供中の日々のニュースや株式投資情報に加え、子会社である日経BP社が提供する技術情報や、日本経済新聞の紙面などを提供する。「これまでウェブに載せてこなかった特ダネやコラムなども掲載する」(電子新聞編集本部 本部長の新実傑氏)といい、新聞紙面に載る情報は基本的にすべてWeb版でも見られるようにする。ただ、新聞紙面と一部の記事については、有料会員のみが閲覧可能。無料の会員登録をしたユーザーであれば、有料会員限定記事を月20本まで読めるようにする。
新聞紙面については東京最終版を掲載。朝刊は4時、夕刊は15時30分に公開する。新聞紙面と同じレイアウトをFlashを使って表示するほか、テキストでも表示する。PCと携帯電話の両方に対応する。日本経済新聞社 代表取締役社長の喜多恒雄氏は「今後はPCや携帯電話だけでなく、今後次々と登場するさまざまなデバイスにも対応したい」と意欲を見せる。海外ではAmazonのKindleやAppleのiPadといった電子書籍対応デバイスが登場しており、これらの動きを意識した発言とみられる。
有料会員に対しては、パーソナライズ機能「My日経」も提供する。過去の履歴をもとに関心がありそうな記事を推薦するほか、ユーザーが登録したキーワードを含む記事を自動で収集し表示する。また、過去5年分の新聞記事を月25件まで検索、閲覧できるようにする。ただし超過分は1件あたり175円かかる。
Web版を導入する理由について、喜多氏は「紙の新聞は今後も続くと考えているが、将来の大きな成長を期待するのは難しい。経営基盤を強化する上で、成長するデジタル分野を強化し、ここで収益を上げることが不可欠と考えた」と話す。さらに「簡単に成功するとは思っていない。(成功するまでに)5〜10年かかるかもしれないが、今スタートさせなければ10年後の成功はない」とし、具体的な売上目標などについては明言を避けた。
利用料金は日本経済新聞の定期購読者の場合、月額1000円。電子版のみの場合は同4000円。いずれもクレジットカード決済のみ受け付ける。金額については「紙の新聞の部数に影響を与えないことを前提に考えた」(同社)とのことで、まずは発行部数の1割に当たる30万人の有料会員獲得を目指す考えだ。なお、現在日本経済新聞社が提供している無料の会員制ニュースコミュニティサイト「日経ネットPLUS」の会員数が約30万人となっている。
有料課金収入のほか、無料会員の属性データを利用した広告や、電子新聞のシステム提供による収入も見込んでいる。Web版を開始するにあたって課金システムや購読者管理システムを新たに作ったといい、「これから始めたい同業者がいれば、我々のシステムを使えるようにしたい」と喜多氏は話し、他社にシステムを提供する考えを明らかにした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日経新聞、月額1000円からの電子版を創刊--NIKKEI NETを継承
CNET Japan 永井美智子(編集部) 2010/02/24 17:27
日本経済新聞社は3月23日、新聞紙面をそのままPCや携帯電話で見られる「日本経済新聞 電子版」(Web版)を創刊する。利用料金は新聞購読者の場合、月額1000円。現在提供しているニュースサイト「NIKKEI NET」の機能を拡張するもので、無料コンテンツも用意する。
Web版ではNIKKEI NETで提供中の日々のニュースや株式投資情報に加え、子会社である日経BP社が提供する技術情報や、日本経済新聞の紙面などを提供する。「これまでウェブに載せてこなかった特ダネやコラムなども掲載する」(電子新聞編集本部 本部長の新実傑氏)といい、新聞紙面に載る情報は基本的にすべてWeb版でも見られるようにする。ただ、新聞紙面と一部の記事については、有料会員のみが閲覧可能。無料の会員登録をしたユーザーであれば、有料会員限定記事を月20本まで読めるようにする。
新聞紙面については東京最終版を掲載。朝刊は4時、夕刊は15時30分に公開する。新聞紙面と同じレイアウトをFlashを使って表示するほか、テキストでも表示する。PCと携帯電話の両方に対応する。日本経済新聞社 代表取締役社長の喜多恒雄氏は「今後はPCや携帯電話だけでなく、今後次々と登場するさまざまなデバイスにも対応したい」と意欲を見せる。海外ではAmazonのKindleやAppleのiPadといった電子書籍対応デバイスが登場しており、これらの動きを意識した発言とみられる。
有料会員に対しては、パーソナライズ機能「My日経」も提供する。過去の履歴をもとに関心がありそうな記事を推薦するほか、ユーザーが登録したキーワードを含む記事を自動で収集し表示する。また、過去5年分の新聞記事を月25件まで検索、閲覧できるようにする。ただし超過分は1件あたり175円かかる。
Web版を導入する理由について、喜多氏は「紙の新聞は今後も続くと考えているが、将来の大きな成長を期待するのは難しい。経営基盤を強化する上で、成長するデジタル分野を強化し、ここで収益を上げることが不可欠と考えた」と話す。さらに「簡単に成功するとは思っていない。(成功するまでに)5〜10年かかるかもしれないが、今スタートさせなければ10年後の成功はない」とし、具体的な売上目標などについては明言を避けた。
利用料金は日本経済新聞の定期購読者の場合、月額1000円。電子版のみの場合は同4000円。いずれもクレジットカード決済のみ受け付ける。金額については「紙の新聞の部数に影響を与えないことを前提に考えた」(同社)とのことで、まずは発行部数の1割に当たる30万人の有料会員獲得を目指す考えだ。なお、現在日本経済新聞社が提供している無料の会員制ニュースコミュニティサイト「日経ネットPLUS」の会員数が約30万人となっている。
有料課金収入のほか、無料会員の属性データを利用した広告や、電子新聞のシステム提供による収入も見込んでいる。Web版を開始するにあたって課金システムや購読者管理システムを新たに作ったといい、「これから始めたい同業者がいれば、我々のシステムを使えるようにしたい」と喜多氏は話し、他社にシステムを提供する考えを明らかにした。
日本経済新聞 電子版 追加情報です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■有料モデルの逆襲はなるのか? 電子版開始に見える日経新聞のジレンマ
DAIAMOND ONLINE 町田徹(ジャーナリスト)2010年02月26日
◇「コンテンツはタダではない」と意気込む日経・喜多社長
◇購読者数と収益の目標は?
◇新聞も購読していない人がネットに月4000円も払うのか?
◇目標は半年で読者10万という謙虚な話も
有料コンテンツモデルは、過去数年、国内のメディア市場を席捲してきたインターネットのポータルサイトの無料コンテンツモデル(広告モデル)に対抗するビジネスとして、育つだろうか――。
国内初の本格的な有料コンテンツモデルとして、日本経済新聞社が電子新聞「日本経済新聞 電子版(Web刊)」を3月23日付で創刊すると発表し、その行方に、新聞・雑誌といった伝統ある活字メディア各社と、インターネット・メディアがそれぞれの立場から熱い視線を注いでいる。
もともと情報にカネを払う習慣が乏しいとされる日本の国民に、カネを払ってでも入手したいと思うような情報を提供することができるかどうか、Web刊の成否はこの一点にかかっていると断定してもよいだろう。
「経済の総合情報機関」日経は当事者として、このチャレンジにいったい、どれぐらいの勝算を持っているのだろうか。電子新聞が既存の新聞の部数を食うカニバリズム(共食い)の懸念はないのだろうか。今回は、Web刊の強みと弱みを検証してみた。‥‥‥
http://diamond.jp/series/machida/10114/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■有料モデルの逆襲はなるのか? 電子版開始に見える日経新聞のジレンマ
DAIAMOND ONLINE 町田徹(ジャーナリスト)2010年02月26日
◇「コンテンツはタダではない」と意気込む日経・喜多社長
◇購読者数と収益の目標は?
◇新聞も購読していない人がネットに月4000円も払うのか?
◇目標は半年で読者10万という謙虚な話も
有料コンテンツモデルは、過去数年、国内のメディア市場を席捲してきたインターネットのポータルサイトの無料コンテンツモデル(広告モデル)に対抗するビジネスとして、育つだろうか――。
国内初の本格的な有料コンテンツモデルとして、日本経済新聞社が電子新聞「日本経済新聞 電子版(Web刊)」を3月23日付で創刊すると発表し、その行方に、新聞・雑誌といった伝統ある活字メディア各社と、インターネット・メディアがそれぞれの立場から熱い視線を注いでいる。
もともと情報にカネを払う習慣が乏しいとされる日本の国民に、カネを払ってでも入手したいと思うような情報を提供することができるかどうか、Web刊の成否はこの一点にかかっていると断定してもよいだろう。
「経済の総合情報機関」日経は当事者として、このチャレンジにいったい、どれぐらいの勝算を持っているのだろうか。電子新聞が既存の新聞の部数を食うカニバリズム(共食い)の懸念はないのだろうか。今回は、Web刊の強みと弱みを検証してみた。‥‥‥
http://diamond.jp/series/machida/10114/
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
新聞販売店 ビジネスモデル 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
新聞販売店 ビジネスモデルのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90024人
- 2位
- 酒好き
- 170668人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人