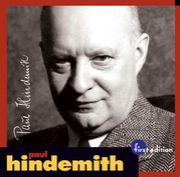「作曲の手引き」・・。この前代未聞の"音楽理論書"及び"作曲学"の根拠は「第一音列」と「第二音列」にあります!。 第一音列は"オーバートーンセリーズ"(倍音)から導き出され、第二音列は2つの音を同時に鳴らした時に生じる"結合音"と云うものから導き出され、この2つがヒンデミット理論の根幹をなす根拠であり、その画期的な音楽の羅針盤となる最重要な基盤です!。
ー "第一音列" と "音階の成り立ちとその構造" ー
「第一音列」とは、音と音が時間差を置いて旋律的に横に鳴る時の基準になる一つの音列のことで、音同士には引力関係つまり音と音の繋がりには「親近性」(遠近感の序列)と云うものが存在すると説いています。詳しくは省略するので「作曲の手引き」を読んで頂きたいのですが、先ず音階の成り立ちとその構造についてヒンデミットは次のように述べています。「一つの音は、その音を出発音として構成される音階の根である。即ち、音階の音はその根から生まれたものと見越される」又「太陽が遊星に取り巻かれているが如くこの"ド"(中心音)は生まれた種々の音に取り巻かれているのである。」と・・。
*そして近年の北里大学などの研究で実際の心理知覚の実験を行ったところ、脳は前後左右の円心軌道上に、サラウンドに音階の音を捉えており、オクターブに留まらず2オクターブ3オクターブと半音階を鳴らして行くと、実際に中心音から出発した音はねじれ現象を起こしながら完璧なる螺旋状(フラクタル)に音が並ぶことが実証されています!。( 講談社 音のなんでも小事典/日本音響学会編 124P参照 )
さて、今述べたことを整理すると、一つの調圏内の中で中心音を仮に「 ド 」に置いた場合、ヒンデミットはこの中心音のドに含まれるオーバートーンセリーズ(倍音)の"理"によって派生して来る12半音列の各音の中に、親近性の強い音から弱い音への序列が存在すると説いている訳ですが、中心音のこの「ド」を基塾に、丁度 太陽を取り囲む遊星群のように、前後左右の円心軌道状に「ソ」「ファ」「ラ」「ミ」「ミ♭」「ラ♭」「レ」「シ♭」「レ♭」「シ」「ファ♯/ソ♭」の各音が、親近性(遠近感の序列)を保ちながら渦巻き状に並んでいると云うことになります・・。
この音列と親近性(遠近感の序列)を太陽系を例に当てはめて解説すると、太陽を中心に、太陽に一番近い星である水星では太陽のその光をまともに受け、太陽の強い引力に拠って引き寄せられていますが、太陽からの距離が遠ざかるに従って引力も序々に弱まり、青く輝く地球に於いては温暖で生命が誕生する条件は程良く整っていますが、冥王星に至っては太陽の光も殆んど届かず、氷に覆われた世界で引力の影響も殆んど受けることはありません!・・。
ヒンデミットは遊星間で起っていることと同じ次元のことが一つの調圏内の音の世界でも起っており、音同士に引力関係に相応する繋がりの強弱(親近性)があることを付き止めました!・・・。
*それではここで実際にピアノなどで音を鳴らしながら、今まで述べて来たことが心理的にどう知覚されるのか、又理論と実際とが一致するのかどうかをを調べていきましょう!。そして耳がそれに馴染むまで何度でも挑んでみましょう!。中心音の「ド」から派生した11個の各派生音を鳴らす前に必ず中心音「ド」を鳴らし、各々の派生音と中心音"との距離感の知覚を体験してください!・・それが即ち親近度です!・・。
なをここに示されたことは最重要な"音の法則"であり、同時に即"悠久の大宇宙のシステム"にダイレクトに向き合い、そして触れる行為になるので、体調と精神的なコンディションを整えてから挑んで欲しいですね!。音響現象は我々人間や動物達や草木や星々と共に大宇宙の縮図であり、大宇宙の全体なのです!・・。全てが一つの大きな命なんです!!・・。全てを慈しむ精神で頭を垂れる気持ちで向き合って下さい!。それでは始めましょう!・・・。
中心音「ド」に対して最も親近性の強い「ソ」では、互いに結び付きが強く安定性がある為に満足する音の進行(5度進行)が得られますが、そこから「ファ」「ラ」「ミ」「ミ♭」「ラ♭」「レ」「シ♭」「レ♭」「シ」を経て行くに従い、だんだんと中心音との親近性が失われて遠近感が増してゆき、最後の「ファ♯/ソ♭」に至ると全く親近性は感じられなくなり、互いの音の遠近感が最も遠のき、この増4度/減5度の進行をした場合最も不安定極まりない音同士の結び付きとなってしまうことが心理的に知覚されますね・・。そして中心音の「ド」を各派生音が前後左右の円心軌道上に取り囲み、何れかの位置に鎮座している様子がお解りになるでしょうか?・・。この音列のこの発見は、それまではっきりとしなかった 「何故 例えば5度進行が何故満足する進行なのか ? 」や、「増4度 / 減5度の進行が不安定で、悪魔の音程として意味嫌ったのか ? 」等々それらの根本的原因が解明された革命的な発見でした!。そしてヒンデミットはここに一つの宇宙の法則がはっきりと音の世界の中にも働いていることを確認したのです!。
ヒンデミットの説を引用すると、「遊星相互間の距離に相応するものは、音の世界に於いては音程である。相並んで音程を為す二つの音の旋律的機能と云うものは、軌道を異にする二点の星の空間にも相当する・・」。とあります。
さて具体的には"第一音列"はこれらのことから和声進行に於ける基音(根音)進行を計画する時などの基準の物差しになります。なを親近性が希薄になるに従い心理的に知覚される緊張度は増していきますが、"第一音列"は中心音を取り巻くその他の音との関係に於いて、前後左右の円心軌道上のどの位置に音が位置するかには触れていませんが、それらが在ることを前提に、取り分け中心音との関係に於いて各々の音には立体的な距離感があることを解明している訳です。そして同時にそれは緊張から弛緩までの心理的知覚と一体化してることを説いています!。親近性が強く安定する程に心理的には弛緩し結び付きの価値は高くなり、反対に親近性が弱くなる程につれ緊張度は増し結び付きの価値は低くなります。
*前後左右の円心軌道上のどの位置に12の各音が配置されるのかと云う問題についてですが、先に記述した北里大学の研究結果ともう一つ、古代中国では漢代の易学者で音楽理論家であった京房(紀元前77〜紀元前37)と云う人物が、十二方位などと照合関係にあるピタゴラスの音律と同じような十二律(12半音階)とを対応させて、律室と云われる部屋で東西南北の円心軌道上に十二方位の内の各方位のそれと照合する音の出る律管(竹の管)を放射線状に12本配置し、気のエネルギーによってそれに対応した音をサウンド・インスタレーション的に実際に鳴らしていたと云う記録が残っています!。したがってこの辺りから解明することが出来るでしょう!。( 音楽之友社 響きの考古学/音律の世界史 55P参照 )
*中心音「ド」からオーバートーンセリーズ(倍音)の"理"によって派生した「ソ」「ファ」「ラ」「ミ」「ミ♭」「ラ♭」「レ」「シ♭」「レ♭」「シ」「ファ♯/ソ♭」の各音は、太陽が遊星に取り巻かれているが如くに円心軌道上に中心音を取り囲み、その中心音との関係性に於いてとりわけ"親近性の価値秩序"が存在し、その価値秩序の順に音を並べた音列を「第一音列」と呼びます!。
ー "第二音列" と"結合音" ー
それに対し「第二音列」は音同士が縦に響いた場合、つまり2つの音と音が同時に響いた場合の価値秩序の基準の物差しになります。これは弦楽器で重音を出したり、2つのファゴットを一緒に吹いたり、その他任意な方法で複合音を作ると演奏者が何か手を加えなくても別な音が独りでに加わって来るのですがこれを「結合音」と呼び、この"結合音"はインターバル(音程)に一種の陰りや濁りを付けるもので、第1次から第2次 第三次結合音と云うように無数に加わってきます。しかし実際に耳で聴いて重要な働きをするのは第2次結合音位までですが、この結合音が無意識に対して極めて重要な働きをするのです!・・。
完全にこの濁りが無いインターバルは「完全1度/8度」で、結合音は何れも同じ音が加わるだけで不純物である陰りや濁りは一切ありません。その次に不純物が少ない音程は「完全5度/4度」で、鳴らされた音程の下に鳴らされた音と重複した音が第一次・第二次結合音共に一つに重なって現れるだけで、それ以外の不純物は存在しません。その次に結合音は省略しますが、だんだんと不純物が増していき「長・短の3度/6度」、「長・短の2度/7度」と続き、最後に「増4度/減5度」となり、増4度減5度に至っては鳴らされたインターバルとは全然異なった結合音が加わって来るので、不純物である陰りと濁りは最大に達します。なを不純物の多い音程ほど価値は下がります。
*後で述べるトラウトニュウムと云う音響装置を使ってこの結合音の陰りと濁り度を測定しグラフ化すると、実際には図がないと解り辛いと思いますが、この不純物が加わって来る度数は緩やかな曲線のカーブを描き、それを立体的に三次元化すると丁度DNAのような2重螺旋状(フラクタル)の構造になることが解ります。つまり完全1度から始まったインターバルに加わった結合音の構造は完全5度のところで交差し、双方がねじれ現象を起こして方向が入れ替わり、対照方向に向かうことが確認出来るのです。これは注意してよく聞くと微かに耳で聴き取ることが可能であり、インターバルの音の響き自体が螺旋(フラクタル)構造をしてることが確認出来るのです!。そしてインターバルを譜面に記載すると、"上に来る高い音"と"下に来る低い音"と云うように2次元的な捉え方になるので平面的な捉え方の錯覚をしがちですが、実際は各インターバルを次々と推移して鳴らした時、脳は無意識に三次元で捉えているので、うねりながらねじれ現象を起こし、円心軌道上に螺旋状(フラクタル)の渦巻きを起こしている有り様を捉えていることになります!。
次いでに論じると、音楽(音響現象)は旋律現象も和声現象もリズムも全てが"大宇宙の法則の音的反映"な訳です ! 。したがって三次元から無限大の次元にまでエネルギーが拡大する中で、うねりとねじれ現象を起こしながら螺旋を描いていることは言うまでもありません!。これを平面的に捉え、音を"悠久の大宇宙のシステム(法則)"とは関係のない"別に存在する単なる無機的な宇宙の産物(パーツ)"と捉える、近代が生んだ近代和声学や12音技法の誤りの部分を打ち破り、この大宇宙のシステムの"理"を人類に対する"無上の贈り物"として、それを最大限に敬った思想と哲学から生まれた手法を羅針盤にしていかない限り、音楽自体が行き詰ってしまうだけではなく、大きくは大宇宙が混乱を来たし、人類自体が狂った在り方に陥って文明は衰退する方向にいってしまうことは間違いのない事実です!・・。これからの音楽はこう云った次元で考え直し音に向き合っていかないといけないと考えます!。
さて話を元に戻しますが、インターバル(音程)には価値秩序の順序が存在し、このインターバルの価値の順序を現わした音列のことを「第二音列」と呼び、インターバル・トニック(音程根音)や集合音(和音)の基音を求めたり、和音の分類や分類された和音の価値を判断する時の羅針盤になります。
*「完全1度/8度」「完全5度/4度」「長・短3度/6度」「長・短2度/7度」「増4度/減5度」
ー インターバル・トニック (音程根音) −
2つの音を同時に鳴らすインターバルでは引力の強い引き寄せる側の音と、その重力に引き寄せられる音が存在し、ここからインターバルには重力が強く他の音を引き寄せてしまう「インターバル・トニック」(音程根音)が存在すると云う理論が成り立ちます。それでは実際にインターバルを鳴らしてみましょう!・・。
トラウトニュウムと云う音響装置であり楽器を使って実験して見ると、「ド」と同音の「ド」を同時に鳴らせば、第一次結合音は極めて低い低音が加わり、第二次結合音は鳴らされた"ド"と同じ高さの同音が加わります。次に「ド」とその単3度上の「ミ♭」を同時に鳴らせば、第1次結合音は鳴らされた"ド"に対して10度下の「ラ♭」、第二次結合音はその"ド"に対して3度下の「ラ♭」が加わり変イ長調(A♭M)の響きになり、実際に鳴らされたインターバルとは全然異なった音が鳴る事が解ります!。更に「ド」とその完全5度上の「ソ」を同時に鳴らせば、下から上昇してきた第一次結合音と、上から下降してきた第二次結合音は、共に鳴らされた"ド"の1オクターブ下の「ド」が加わり、ここで一致し交差して第一次結合音は上昇し第二次結合音は下降し、双方が反対方向に離れていきます。
それではここで問題提起ですが、( 話は前後し本当はこの今から記述する完全4度音程は完全5度音程の記述の先に来るのですが!・・ )「ド」と完全4度上の「ファ」を同時に鳴らすと、"ド"か"ファ"の何れが引力の強い音に聞こえるでしょうか?。
答えは誰が聴いても明らかに鳴らされた音の下側の"ド"ではなく、4度上の"ファ"に聞こえますね!。何故下の"ド"ではなく上側の"ファ"の重力に引き寄せられるのでしょうか?。これらの根本の疑問を解明した理論がこのヒンデミットの「作曲の手引き」です!・・。その答えはそれは鳴らされたインターバルに対して第1・第2次の結合音共に「ファ」が重複して鳴り、"ファ"の音がやや優勢に聞こえるからです・・。
それでは第二音列の最後に「ド」とその増4度/減5度上の「ファ♯/ソ♭」を同時に鳴らすとどのような結合音が鳴るかを観てみましょう!。
それは最も狭く響いた場合鳴らされた"ド"に対して10度下の「ラ♭」とその5度上の「ミ♭」が鳴り、最も広く響いた場合はこの"ド"対して10度下の「ラ」とその4度上の「レ」の音が鳴り、この構成音を観ると"変イの属7の和音(A♭7)"と二の属7の和音(D7)であることが解り、3全音(増4度/減5度のインターバル)は属7の和音(7thコード)の働きをすることが解ります!。
この第1・第2音列で明らかになったことは、実際の音響現象と云うものはそれを知覚する心理作用 / 生理作用も含めて極めて複雑怪奇なものであり、音楽は同時に 数学、心理学、物理学、そしてそれらの根本にある哲学などと連動しており、元々存在していた"宇宙の法則の音的反映!"と観ることが出来るのです!・・・。
「このように言うと古人の云うあの宇宙の音楽から何か神秘な微かな音が生まれ出て来るように聞こえないであろうか。- 中略 - 天球の諸調即ち宇宙の音楽と云うものは、極めて完全無欠なものであって、人の不完全な感覚器官などではとても窺い知ることが出来ないものである。- 中略 - 音、この音によって宇宙の音楽は俗化され、つまり感得される人の世界へと移し替えられるのである。- 中略 - 昔の人はこの地上の関係を宇宙に訳して考えた。今日では逆にどんな小さな音楽の組織の中へも宇宙の力が拡がっているものと見こそうとするのである。この力は、天空をあの遠い星雲までへも動かして行く力にも等しいものである。」 ー パウル・ヒンデミット ー ( 氏の弟子 下総皖一 訳 )
さてこれらを念頭に置き、和音進行の作り方について大まかに述べれば、これらを根拠に先ず「インターバル・トニック(音程根音)」を求め、様々なインターバルの集合体である集合音(和音)の中に存在する最も親近性が強く優勢なインターバルから生じる集合音の本当の中心音(基音)を導き出し、この基音どうしが連なって生じる「基音進行」の流れを決定します。
そして和音(集合音)は3度構成の集合音が種々の和音を構成する基礎のルールでは無くなり、集合音を大きく6種類に分類!。(*作られた和音にコードネームを記載する場合はその和音の基音をルート音(根音)として考え、他の音はそのルートに関連付け従来の記載の仕方を用いる!。) そしてその6種類の和音をどう連結させるのかに問題が移行し、ここに種々のルールが現れて来ます!。
計画された基音進行を念頭に置きながら最低音と最高音の協和と不協和のインターバルのコントラストを付けて「優位二声部」を計画し、分類された6種類の集合音(和音)の中からどの種類の和音を使用するかを選び和声付けをしてその和音進行の流れを作っていきます。
更に旋律中には3度構成の分散和音に値する旋律線が浮かび上りますが、耳は間に他の音(非和声音)が存在したとしても、3和音の構成音を見付けるとそれを旋律中に存在する3和音(和声音)として認識するので、そこから「旋律基音進行」と云われるものが生まれて来ます。
又旋律中の「二度進行」と云われるものの存在があり、これが良い旋律線を作る際の重要なポイントになって来ますが、その他に対位法や保続音(ペダル)を考えたりするプロセスもあります。
ジャズやポップスで重要な関心事は、作られた和音進行の中でどう即興をしたり新たに旋律を作ったりするのかと云うことになりますが、機能和声の和音進行のルールは当然当てはまらないので、和音進行の中に存在する各和音の構成音を経過するスケールを適用させるか、新たに自分でスケールを作りそこから旋律を編み出していけば良いでしょう。旋律中の非和声音と和声の絡みの問題も解説しないといけませんが、まあ大きくはこのような工程を経ていくことになります。
私は自分独自な音楽を確立させ、又即興などのアプローチや作品を作る際に、このヒンデミットの著書「作曲の手引き」とその実践編「優位二声部楽曲の練習書」は大いなる助けになりました!。作曲の手引きを理解するには先ずこの実践編である優位二声部楽曲の練習書の課題を克服する中で理解が進みます!。理論編と実践編を照らし合わせながら習得してけるようにヒンデミットが仕向けてくれているからです!。
しかし"作曲の手引き"の日本語訳は戦前の古い表現なので分かり易くはないでしょう…。クラッシックではヒンデミット氏の直弟子のゲルツマー氏と云う方に教えを受けられた日本人の作曲家が一人居られ、その方がヒンデミット理論を現代の表現で再出版される可能性があります。(本人談) それとジャズ系では私の亡くなった師匠で故・国府輝明(ジャズ・ピアニスト/作・編曲家)が著した「現代のジャズ音楽作曲法�」(現在絶版)と云う著書があります。実はこのトピックの内容の記述を進めていく内に、近い将来これらの著作を参考にして自分の研究成果と会得し感得した見地から、新たにヒンデミットがほのめかしながらも直接には触れなかった事柄などについても、今の各専門分野の研究成果などの発表を待って、それらを自分の研究と照合させたりしながら、独自に新たな理論書を著わさないといけない運命と使命を感じているので、それを待って頂きたい気持ちなのですが、もし今直ぐに入門的にヒンデミットを学ばれたい方や、特にジャズやポピュラー系の音楽にヒンデミット理論を用いられたい方は、是非とも「国府利征コミュ二ティー」http://
*なをこの記述はまだ未完なので改訂を加えながら書き足していくので時々確認作業を行なって
下さい!。どうぞ宜しく・・。 国府利征
最後に私の音楽表現 - WINDS OF ASIA - の第一弾・第二弾の映像2つをご紹介させて頂きます!。オーガニックでスピリチュアルなコンテンポラリー・ジャズ/フュージョンを展開しています。[第一弾映像] [第二弾映像]共に、私の作品であり、ピアノソロにおけるインプロビゼーションの際のアプローチの方法や、曲中の和音進行などに基音進行やインターバルトニック等を用いており、その特徴が表れていると思います
*公開日記からでも入れます!。
http://
http://
*ヒンデミットの作品の"YOUTUBE"の厳選した一部の映像を紹介してる公開日記も覗いて下さいね…。
http://
[第一弾映像]
http://
[第二弾映像]
http://
*クラッシック派の方もジャズ派など全ての方達・・、是非とも観て下さい!。
(この下の欄には記述が完成するまではコメント等は書き込まないで下さい
|
|
|
|
|
|
|
|
ヒンデミット 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ヒンデミットのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人