新羅・伽耶と日田を結ぶ鷹と日本海
日田神話
『豊西記』には、「湖であった日田盆地に大鷹が東から飛んできて湖水に羽を浸し、羽ばたき、旭日の中を北へ去ると、湖水は轟々と抜けて干潟となった。そして日隈、月隈、星隈の三丘が現れた。」という「日と鷹神話」があり日田が「ヒダカ」と呼ばれるようになったという記述がある。「ヒダカ」とは、日高・日鷹であり、本州にある地名の日高・日高見などの地目になって移っていたという説もある
鷹と鍛冶と八幡
『日本書紀』などには、日本武尊で白鳥などはよく登場するが、鷹はほとんど出てこない。ところが、宇佐と鷹の深いつながりがあることがわかる。
実は、「鷹」が日田と宇佐と新羅の関係をつなぐキーワードだという事がみえてきた。ちなみに「大神が鷹となって、通行人を殺した」「八幡神が鷹として示現した伝承があるが、「弘仁官符」には、鷹に化した神の心をやわらげた辛島勝乙目は、神殿を立て「鷹居社」と命名し、宇島勝乙目が祝、宇島勝意布売が禰宜になったとある。
大和岩雄氏は『秦氏の研究』の中で、鷹=八幡神だが、鷹は鍛冶にかかわり、鍛冶翁が八幡神としてあらわれたときには、「三歳ノ小児」 の姿であった。新羅の第四代の王脱解について 『三国史記』 は、脱解は倭国の東北一千里の多婆那国の王妃が生んだ卵で、箱に入れられて海に流され、金官加羅国へ漂着した。金官(海)国の人たちは、怪しみこの箱をとりあげようとしなかったので、また海に出て、新羅の阿珍浦(迎日清) についたのは、始祖赫居世の治世の三十九年であったと記す。
『三国遺事』も同じ話を載せるが、箱から出た男の子脱解は、吐合山に登り石塚を作って七日聞こもり、山を下りて住む家を探した。その家探しのとき、童子の脱解は、「我は本は冶匠なり」といったと書くが、冶匠は鍛冶屋のことである。大隅正八幡宮縁起」 の八幡神漂着神話と同じであり、八幡神=脱解であるから、八幡神も脱解と同じに童子であり、冶匠・鍛冶神として示現するのである。
また『託宣集』は、「太政官符」の記事を下敷にして、大神比義によって、鷹に化身していた八幡神は、鳩に化身し、更に鳩から天童(三歳の幼児)に化身して示現し、託宣したという話を創作して加えている。日本武尊での白鳥も鷹から化身していった可能性がある。
新羅の神と言えば、田川郡の香春神社が有名である。田川郡とは、鷹羽郡であり、要するに「鷹」なのである。宇佐神宮の神も前記の八幡=脱解=天日矛=素戔嗚尊とつながってくる。「大和岩雄氏」は「鷹」 の地名、山名・寺号などを調べてみると、秦氏と共に鍛冶伝承が登場する。このことからみても、鷹に化身する八幡神が、鍛冶翁として示現するのは当然であり、こうした伝承の根は「秦王国」 の信仰にあるといえよう。
秦氏の謎
秦氏とは、日本書紀によると応神天皇十四年に弓月君が朝鮮半島の百済から百二十県の人を率いて帰化し秦氏の基となったという。が、加羅(伽耶)または新羅から来たのではないかとも考えられている。天日槍を奉じる人々の勢力圏と、古くは遼東半島で信仰されていた兵主神や、穴師を祀る神社の分布が重なることなどから、遼東半島付近から渡来した海人集団の総称が秦氏で、秦氏を擁護した応神天皇の母親神功皇后は天日槍の末裔とされており、秦氏の台頭のレールは天日槍によって敷かれていたとする見方がある
。
天の日矛(丹後)から香春神社・宇佐神宮の鷹と鉄と鍛冶のつながりは指摘されていた事だが、必要なのはこの先の日田である。神功皇后伝承が、このラインとそっくりにつながってくる。また、北部九州には何故か「トヨ姫」を祭神とした神社が特に多い。トヨ姫は、卑弥呼の宗女「トヨ」ともつながってくる。福本氏は、天の日矛伝承を日田と但馬をつなげて考えている。しかし私見では、『日本書紀』にしたがうなら、姫島の「ヒメゴソ」や神功皇后伝承の通り新羅は東からやってきたのであろうと考える。
四世紀にヤマトの纒向遺跡は大きく発展している。この遺跡の特徴は多くの地域から持ち込まれた土器があり、半数は東海から持ち込まれたものだ。纒向勢力は、東海を中心とした、尾張氏や美濃氏や吉備などの勢力がつくりあげたものだと思っている。
日田の小迫辻原遺跡に東海・北陸・畿内などの広範囲の土器が出土するのも、トヨを連合したヤマトによる日田進出を証拠になる。3世紀、九州を中心とした邪馬台国卑弥呼連合は鉄を圧倒的して大きな権力を握っていたが、4世紀になって、次第に九州はヤマトの前方後円墳を受け入れるようになるのも、『日本書紀』の九州遠征を考古学と一致している。
国造本紀(先代旧事本紀)によると十三代成務天皇の時代、葛城国造と同祖である止波足尼(とは(鳥羽)のすくね)を国造に定めたことに始まるとされる。葛城国造と同祖とある。また葛城直は「九州日田の豪族として、神武天皇の東征に従」(『姓氏家系大辞典』)という記述がある。また古く日田地方には日田盆地中南部を本拠とする日下部君一族があり、比多国造となった可能性も高いという。また延喜式には荒田直の住んだ場所なので荒田と名付いたとあり、姓氏録にも荒田直は高魂命(たかむすびのみこと、高皇産霊尊)の5世孫である剣根命(つるぎねのみこと)の後、とある。神武天皇紀・国造本紀には剣根命は葛城国造、比多国造等の祖である、と書かれており、統合すると、止波足尼は初代葛城国造・剣根命の子孫に当たる人物と考えられている。
日下部氏と葛城氏が日田の古代にどう関わっていたのだろう。久津媛神社の縁起にも葛城氏と鴨氏が祀られている。また久津媛の詳細は避けるが、久津媛は神功皇后であり、トヨなのであろうと私見はみている。大和氏は「八幡宮の比売神は、本来は秦王国の香春岳の比売神(豊姫) であった」。という。ここに『魏志』倭人伝の東夷伝と『日本書紀』のつながりを感じる。
四世紀以後の謎
この頃、ヤマト勢力も、日本海の勢力と瀬戸内勢力の大きな連合国家であったのであり、日本海とヤマトが、日下部氏と葛城氏(蘇我氏)となって後世に言い伝えられているのではないか。天の日矛が持ち込んだ金銀錯嵌珠龍文鉄鏡が古代日田の出雲の国譲りとして、西日本連合は破断し、日下部氏(日本海)と葛城氏(ヤマト)の良縁も日田で破断した。
「旧唐書倭国日本伝」では、倭国という国と日本という別の国があると記述されている。この頃、邪馬台国後、また日本は二つに分裂していた可能性が強い。聖徳太子かと言われる「アメノタリシヒコ」が登場するが、余談だが十二代〜十四代天皇にもタリシヒコという名が付いている。タリシヒコとは九州で活躍した天皇なのは間違いない。
日田出土の金銀錯嵌珠龍文鉄鏡も実は、日下部氏が日田の中で言い伝えられていったものだろう。『豊後国風土記』の景行天皇が日田の鏡山で日田の様子はまるで鏡のようだというのも、何らかの口伝からくるものである。 筑紫の君 磐井 も、日下部氏の末裔であり。密かに鏡を守り抜いた一族ではなかったか。
鷹というキーワードから古代史を考えてくと。実に面白い。鉄と鍛冶と鷹が完全につながってくる。そのルーツが新羅と伽耶であり、天の日矛と神功皇后の二人。
秦氏は一般的に、豊前辺りが有名だが、そこに日田と香春神社という新羅を当てはめると謎の4世紀がみえてくる。この辺りは物部氏の領地だったというが、余談だが庄内式土器の意味もみえてくるのではないだろうか。
日子山を中心とした修験道がつなぐものにも、秦氏も関わってくる『彦山縁起』には継体天皇二十五年(531)に北魏の渡来僧・善正(ぜんしょう)が始めて英彦山に入ったという。そこで岩屋に籠もって修行中に、豊後国日田郡(大分県日田市)の猟師藤原恒雄と出会う。恒雄は善正の弟子となり忍辱と改名、ついには山頂に阿弥陀、釈迦、観音の本地仏を見る。
『修験道の本』 学研修験道のルーツは葛城山が代表的。葛城襲津彦などしきりに渡来人を葛城周辺に入植させている。・・韓人社会ができあがり、原始的な山岳信仰は次第に神仙思想など外来信仰の影響を受けるようになった。とあり藤原恒雄も葛城氏の血を引く人であった可能性が高い。
卑弥呼の時代前は、九州がヤマトを鉄で圧倒していた事実。卑弥呼の後、その立場が逆転する意味は、日田が大きな位置を占めている。『日本書紀』と『古事記』は、日田をある意味、出雲と日向という陰と陽に対比し、それが「日田」という−と+の陰陽として表現されている。
日田という意味の中には 天の日矛(素戔嗚尊・武内宿禰・浦島太郎)と神功皇后(天照大御神・台与)というキーワードと「日向と出雲」そして 日(太陽・鍛冶)と鷹という伝承が言い伝えられているのである。
今、糸魚川付近には奴奈川姫という翡翠の女王がいるが、ここの地域には「ひだ」という地名と弥生後期の遺跡もある。神功皇后は、北陸の出だとされている。北陸と言えば継体天皇の出身地でもある。
余談だが、磐井は本当に反乱したのであろうか?
磐井が日下部系(天の日矛)であるなら、同族という事になる。何故、継体天皇を物部氏は担ぎ上げたのか。
朝鮮半島を巡る対立もあったと思うが、それとは別に磐井と継体は同族であるからで、物部氏は継体天皇を利用し、分裂した倭国を再度、統一する為に九州を安心させ、騙し討ちをしたのではなかったか。そう思えてしょうがない。そして物部麁鹿火は日田に騙し討ちに入ってきたのかしれない。
とんでもない鷹仮説
鷹とは、猿田彦であり、鷹も長いクチバシは鼻にもにている。
山伏を天狗として恐れる信仰や天狗と称されるものは、「赤ら顔で鼻が長く、山伏のような服装をして高下駄を履き、羽団扇をもって自由自在に空中を飛行するものであり、背に羽をつけ鳥のような嘴を持った天狗も一般的なものと思われるという」。
猿田彦が死んだのも「鳥羽の海」。鳥の羽である。伊勢神宮の近くにある伊勢神宮には、外宮に豊受大神、内宮に天照大御神そして内宮と外宮の間には、猿田彦神社がある。内宮の天照大神が寂しいので丹後から豊受大神を迎えたという。女が女を呼ぶことはしない。内宮は男であり猿田彦・武内宿禰であり、鳥羽の宿禰なのである。
『日本書紀』を書き上げた藤原不比等が、蘇我氏の祖である日田と武内宿禰を抹殺した。そして伊勢では本来の男性神を祀っている。そう武内宿禰=大国主神。そしてその配偶者、外宮の神功皇后こと邪馬台国の台与=豊受大神であり、その二人の子どもである。應神天皇。應神にも鷹がある。宇佐神宮、出雲大社、伊勢神宮には二礼四拍手という日田締めと同じ風習が残る。日田の神=ひだかみ であり、日田の神を四拍手の神社に封印されているのである。
そして景行天皇の子ども成務天皇とは鳥羽の宿禰であり、武内宿禰(天の日矛の末裔)である可能性が強い。天の日矛も、農耕神である。『豊西記』には、「石井源太夫高明公」、当郡に下向き、来来里の着御あり。これによって村名としその後大原に館し昿田を開きという記述と『豊後国志』には「鳥羽の宿禰」が日田国造となり刃連に住まい常に庶民に会す。以て耕の事を教え常に同居し、名づけて会所宮というのは是なり。日田で初めて水田が開かれた。「石井源太夫高明公」と「鳥羽の宿禰」は同一人物の可能性、または一族という意味なのか。この後、鳥羽の宿禰は石井郷に移り今の石井神社に祀られている。 日下部氏は後に石井となり高良山に祀られている。高良山の祭神は高良玉垂であり、日田の高良玉垂神社(ハルヤ書店裏)。の祭神は武内宿禰である。『豊西記』『豊後国志』は日下部氏と磐井は同族だと後世に伝えているのかもしれない。
高良山を中心とした武内宿禰の伝承そして、鹿児島の弥五郎ドン伝承の武内宿禰と、景行天皇と成務天皇と仲哀天皇は、九州で活躍した天皇だからタラシヒコという共通の名がつくのである。タリシヒコには、「タ」という鷹と「ヒコ」という日子山の意味がある。神話は、日田を「ひた隠しに」し、古代天皇は日田向きに向かった歴史を、ひたすら隠し続けるのである。 その謎を解くのも「鷹」であった。
日田神話
『豊西記』には、「湖であった日田盆地に大鷹が東から飛んできて湖水に羽を浸し、羽ばたき、旭日の中を北へ去ると、湖水は轟々と抜けて干潟となった。そして日隈、月隈、星隈の三丘が現れた。」という「日と鷹神話」があり日田が「ヒダカ」と呼ばれるようになったという記述がある。「ヒダカ」とは、日高・日鷹であり、本州にある地名の日高・日高見などの地目になって移っていたという説もある
鷹と鍛冶と八幡
『日本書紀』などには、日本武尊で白鳥などはよく登場するが、鷹はほとんど出てこない。ところが、宇佐と鷹の深いつながりがあることがわかる。
実は、「鷹」が日田と宇佐と新羅の関係をつなぐキーワードだという事がみえてきた。ちなみに「大神が鷹となって、通行人を殺した」「八幡神が鷹として示現した伝承があるが、「弘仁官符」には、鷹に化した神の心をやわらげた辛島勝乙目は、神殿を立て「鷹居社」と命名し、宇島勝乙目が祝、宇島勝意布売が禰宜になったとある。
大和岩雄氏は『秦氏の研究』の中で、鷹=八幡神だが、鷹は鍛冶にかかわり、鍛冶翁が八幡神としてあらわれたときには、「三歳ノ小児」 の姿であった。新羅の第四代の王脱解について 『三国史記』 は、脱解は倭国の東北一千里の多婆那国の王妃が生んだ卵で、箱に入れられて海に流され、金官加羅国へ漂着した。金官(海)国の人たちは、怪しみこの箱をとりあげようとしなかったので、また海に出て、新羅の阿珍浦(迎日清) についたのは、始祖赫居世の治世の三十九年であったと記す。
『三国遺事』も同じ話を載せるが、箱から出た男の子脱解は、吐合山に登り石塚を作って七日聞こもり、山を下りて住む家を探した。その家探しのとき、童子の脱解は、「我は本は冶匠なり」といったと書くが、冶匠は鍛冶屋のことである。大隅正八幡宮縁起」 の八幡神漂着神話と同じであり、八幡神=脱解であるから、八幡神も脱解と同じに童子であり、冶匠・鍛冶神として示現するのである。
また『託宣集』は、「太政官符」の記事を下敷にして、大神比義によって、鷹に化身していた八幡神は、鳩に化身し、更に鳩から天童(三歳の幼児)に化身して示現し、託宣したという話を創作して加えている。日本武尊での白鳥も鷹から化身していった可能性がある。
新羅の神と言えば、田川郡の香春神社が有名である。田川郡とは、鷹羽郡であり、要するに「鷹」なのである。宇佐神宮の神も前記の八幡=脱解=天日矛=素戔嗚尊とつながってくる。「大和岩雄氏」は「鷹」 の地名、山名・寺号などを調べてみると、秦氏と共に鍛冶伝承が登場する。このことからみても、鷹に化身する八幡神が、鍛冶翁として示現するのは当然であり、こうした伝承の根は「秦王国」 の信仰にあるといえよう。
秦氏の謎
秦氏とは、日本書紀によると応神天皇十四年に弓月君が朝鮮半島の百済から百二十県の人を率いて帰化し秦氏の基となったという。が、加羅(伽耶)または新羅から来たのではないかとも考えられている。天日槍を奉じる人々の勢力圏と、古くは遼東半島で信仰されていた兵主神や、穴師を祀る神社の分布が重なることなどから、遼東半島付近から渡来した海人集団の総称が秦氏で、秦氏を擁護した応神天皇の母親神功皇后は天日槍の末裔とされており、秦氏の台頭のレールは天日槍によって敷かれていたとする見方がある
。
天の日矛(丹後)から香春神社・宇佐神宮の鷹と鉄と鍛冶のつながりは指摘されていた事だが、必要なのはこの先の日田である。神功皇后伝承が、このラインとそっくりにつながってくる。また、北部九州には何故か「トヨ姫」を祭神とした神社が特に多い。トヨ姫は、卑弥呼の宗女「トヨ」ともつながってくる。福本氏は、天の日矛伝承を日田と但馬をつなげて考えている。しかし私見では、『日本書紀』にしたがうなら、姫島の「ヒメゴソ」や神功皇后伝承の通り新羅は東からやってきたのであろうと考える。
四世紀にヤマトの纒向遺跡は大きく発展している。この遺跡の特徴は多くの地域から持ち込まれた土器があり、半数は東海から持ち込まれたものだ。纒向勢力は、東海を中心とした、尾張氏や美濃氏や吉備などの勢力がつくりあげたものだと思っている。
日田の小迫辻原遺跡に東海・北陸・畿内などの広範囲の土器が出土するのも、トヨを連合したヤマトによる日田進出を証拠になる。3世紀、九州を中心とした邪馬台国卑弥呼連合は鉄を圧倒的して大きな権力を握っていたが、4世紀になって、次第に九州はヤマトの前方後円墳を受け入れるようになるのも、『日本書紀』の九州遠征を考古学と一致している。
国造本紀(先代旧事本紀)によると十三代成務天皇の時代、葛城国造と同祖である止波足尼(とは(鳥羽)のすくね)を国造に定めたことに始まるとされる。葛城国造と同祖とある。また葛城直は「九州日田の豪族として、神武天皇の東征に従」(『姓氏家系大辞典』)という記述がある。また古く日田地方には日田盆地中南部を本拠とする日下部君一族があり、比多国造となった可能性も高いという。また延喜式には荒田直の住んだ場所なので荒田と名付いたとあり、姓氏録にも荒田直は高魂命(たかむすびのみこと、高皇産霊尊)の5世孫である剣根命(つるぎねのみこと)の後、とある。神武天皇紀・国造本紀には剣根命は葛城国造、比多国造等の祖である、と書かれており、統合すると、止波足尼は初代葛城国造・剣根命の子孫に当たる人物と考えられている。
日下部氏と葛城氏が日田の古代にどう関わっていたのだろう。久津媛神社の縁起にも葛城氏と鴨氏が祀られている。また久津媛の詳細は避けるが、久津媛は神功皇后であり、トヨなのであろうと私見はみている。大和氏は「八幡宮の比売神は、本来は秦王国の香春岳の比売神(豊姫) であった」。という。ここに『魏志』倭人伝の東夷伝と『日本書紀』のつながりを感じる。
四世紀以後の謎
この頃、ヤマト勢力も、日本海の勢力と瀬戸内勢力の大きな連合国家であったのであり、日本海とヤマトが、日下部氏と葛城氏(蘇我氏)となって後世に言い伝えられているのではないか。天の日矛が持ち込んだ金銀錯嵌珠龍文鉄鏡が古代日田の出雲の国譲りとして、西日本連合は破断し、日下部氏(日本海)と葛城氏(ヤマト)の良縁も日田で破断した。
「旧唐書倭国日本伝」では、倭国という国と日本という別の国があると記述されている。この頃、邪馬台国後、また日本は二つに分裂していた可能性が強い。聖徳太子かと言われる「アメノタリシヒコ」が登場するが、余談だが十二代〜十四代天皇にもタリシヒコという名が付いている。タリシヒコとは九州で活躍した天皇なのは間違いない。
日田出土の金銀錯嵌珠龍文鉄鏡も実は、日下部氏が日田の中で言い伝えられていったものだろう。『豊後国風土記』の景行天皇が日田の鏡山で日田の様子はまるで鏡のようだというのも、何らかの口伝からくるものである。 筑紫の君 磐井 も、日下部氏の末裔であり。密かに鏡を守り抜いた一族ではなかったか。
鷹というキーワードから古代史を考えてくと。実に面白い。鉄と鍛冶と鷹が完全につながってくる。そのルーツが新羅と伽耶であり、天の日矛と神功皇后の二人。
秦氏は一般的に、豊前辺りが有名だが、そこに日田と香春神社という新羅を当てはめると謎の4世紀がみえてくる。この辺りは物部氏の領地だったというが、余談だが庄内式土器の意味もみえてくるのではないだろうか。
日子山を中心とした修験道がつなぐものにも、秦氏も関わってくる『彦山縁起』には継体天皇二十五年(531)に北魏の渡来僧・善正(ぜんしょう)が始めて英彦山に入ったという。そこで岩屋に籠もって修行中に、豊後国日田郡(大分県日田市)の猟師藤原恒雄と出会う。恒雄は善正の弟子となり忍辱と改名、ついには山頂に阿弥陀、釈迦、観音の本地仏を見る。
『修験道の本』 学研修験道のルーツは葛城山が代表的。葛城襲津彦などしきりに渡来人を葛城周辺に入植させている。・・韓人社会ができあがり、原始的な山岳信仰は次第に神仙思想など外来信仰の影響を受けるようになった。とあり藤原恒雄も葛城氏の血を引く人であった可能性が高い。
卑弥呼の時代前は、九州がヤマトを鉄で圧倒していた事実。卑弥呼の後、その立場が逆転する意味は、日田が大きな位置を占めている。『日本書紀』と『古事記』は、日田をある意味、出雲と日向という陰と陽に対比し、それが「日田」という−と+の陰陽として表現されている。
日田という意味の中には 天の日矛(素戔嗚尊・武内宿禰・浦島太郎)と神功皇后(天照大御神・台与)というキーワードと「日向と出雲」そして 日(太陽・鍛冶)と鷹という伝承が言い伝えられているのである。
今、糸魚川付近には奴奈川姫という翡翠の女王がいるが、ここの地域には「ひだ」という地名と弥生後期の遺跡もある。神功皇后は、北陸の出だとされている。北陸と言えば継体天皇の出身地でもある。
余談だが、磐井は本当に反乱したのであろうか?
磐井が日下部系(天の日矛)であるなら、同族という事になる。何故、継体天皇を物部氏は担ぎ上げたのか。
朝鮮半島を巡る対立もあったと思うが、それとは別に磐井と継体は同族であるからで、物部氏は継体天皇を利用し、分裂した倭国を再度、統一する為に九州を安心させ、騙し討ちをしたのではなかったか。そう思えてしょうがない。そして物部麁鹿火は日田に騙し討ちに入ってきたのかしれない。
とんでもない鷹仮説
鷹とは、猿田彦であり、鷹も長いクチバシは鼻にもにている。
山伏を天狗として恐れる信仰や天狗と称されるものは、「赤ら顔で鼻が長く、山伏のような服装をして高下駄を履き、羽団扇をもって自由自在に空中を飛行するものであり、背に羽をつけ鳥のような嘴を持った天狗も一般的なものと思われるという」。
猿田彦が死んだのも「鳥羽の海」。鳥の羽である。伊勢神宮の近くにある伊勢神宮には、外宮に豊受大神、内宮に天照大御神そして内宮と外宮の間には、猿田彦神社がある。内宮の天照大神が寂しいので丹後から豊受大神を迎えたという。女が女を呼ぶことはしない。内宮は男であり猿田彦・武内宿禰であり、鳥羽の宿禰なのである。
『日本書紀』を書き上げた藤原不比等が、蘇我氏の祖である日田と武内宿禰を抹殺した。そして伊勢では本来の男性神を祀っている。そう武内宿禰=大国主神。そしてその配偶者、外宮の神功皇后こと邪馬台国の台与=豊受大神であり、その二人の子どもである。應神天皇。應神にも鷹がある。宇佐神宮、出雲大社、伊勢神宮には二礼四拍手という日田締めと同じ風習が残る。日田の神=ひだかみ であり、日田の神を四拍手の神社に封印されているのである。
そして景行天皇の子ども成務天皇とは鳥羽の宿禰であり、武内宿禰(天の日矛の末裔)である可能性が強い。天の日矛も、農耕神である。『豊西記』には、「石井源太夫高明公」、当郡に下向き、来来里の着御あり。これによって村名としその後大原に館し昿田を開きという記述と『豊後国志』には「鳥羽の宿禰」が日田国造となり刃連に住まい常に庶民に会す。以て耕の事を教え常に同居し、名づけて会所宮というのは是なり。日田で初めて水田が開かれた。「石井源太夫高明公」と「鳥羽の宿禰」は同一人物の可能性、または一族という意味なのか。この後、鳥羽の宿禰は石井郷に移り今の石井神社に祀られている。 日下部氏は後に石井となり高良山に祀られている。高良山の祭神は高良玉垂であり、日田の高良玉垂神社(ハルヤ書店裏)。の祭神は武内宿禰である。『豊西記』『豊後国志』は日下部氏と磐井は同族だと後世に伝えているのかもしれない。
高良山を中心とした武内宿禰の伝承そして、鹿児島の弥五郎ドン伝承の武内宿禰と、景行天皇と成務天皇と仲哀天皇は、九州で活躍した天皇だからタラシヒコという共通の名がつくのである。タリシヒコには、「タ」という鷹と「ヒコ」という日子山の意味がある。神話は、日田を「ひた隠しに」し、古代天皇は日田向きに向かった歴史を、ひたすら隠し続けるのである。 その謎を解くのも「鷹」であった。
|
|
|
|
|
|
|
|
日田の歴史って面白くて凄い! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
日田の歴史って面白くて凄い!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82541人
- 2位
- 酒好き
- 170695人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人
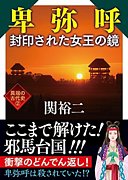





![縄文族ネットワーク [太陽の道]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/10/98/1581098_84s.gif)

















