『いま、なぜ日田なのか』 関裕二
失礼なことをいうようだが大分県日田市といっても、ほとんど無名の地である。
まして、邪馬台国論争と日田のつながりについて、これまだまったく語られることがなかったと言っていい。
しかし、これから十年後、「日田」は、邪馬台国を語る上で避けては通れない場所になっているに違いない。
三世紀前半、つまり、邪馬台国から大和へ、という時代の節目に、この日田には大和の勢力が進出していた。これは筆者の勝手な推理ではなく、考古学的に裏付けられていることだ。
瀬戸内海の制海権を確立した「大和」は、この日田の地にまで勢力圏をのばしていたのである。地形的に、日田をとったものが九州を制することができるからだ。北部九州の中心筑紫平野には筑後川を下れば一気に出られ、しかも日田は天然の要害で、西側からの攻撃にすこぶる強かった。そしてこの地からは、後漢の王族しかもてなかったという金銀錯嵌珠龍文鉄鏡が出土している。いったい、どのような人物が、このような宝物を持ち得たというのか。
それは卑弥呼か、はたまた大和の大王か・・・・日田が邪馬台国に関わってくるのは、北部九州と大和の相克という視点が大切になってくるからだ。おそらく、久留米から山門郡にかけての一帯を支配していた邪馬台国の卑弥呼と、これを制圧すべく日田に遣わされた大和の王族── 金銀錯嵌珠龍文鉄鏡を持った日の巫女と思われる───との戦いが、日田の盆地と久留米の高良山周辺で展開された・・・・・・そして、卑弥呼と敵対していた日田の「巫女」こそが、のちに卑弥呼の宗女として邪馬台国を継承した「台与(とよ)」だったのではあるまいか。
日田が筑紫(福岡県)の文化圏経済圏にありながら大分県に組み込まれ、これが大分県の原型「豊国(とよのくに)」からの伝統であったのは、大和からの勢力・・・しかもそれが「トヨ」で・・・・が日田におよび、「トヨ」の名がそのまま国名になったからであろう。
このような推理は、まだ認知されていないが、日田周辺の発掘が進めば、いよいよもって、邪馬台国と日田の関係が注目されるのちがいないのだ。そして、それはそう遠い話ではないだろう。
梅澤恵美子先生から(2001/7/24)
日田について
今まで日田は、邪馬台国論争のなかでほとんど無名であったが、三世紀の考古学的見地から言うと、非常に重要な意味を帯びてきたと思える。
ヤマト(纒向遺跡)と日田(小迫辻原遺跡)は、発達の仕方と西に強いという地理条件がそっくりである。三世紀に突然現れて三世紀半ばに発展、東側から筑紫平野に睨みをきかすには、これ以上の立地条件はない。ここに拠点を持てば、九州勢は北部海岸地帯から退去するしかなかった。
おそらく九州勢(卑弥呼)は、高良山から女山に軍事拠点をつくって対抗したはずである。
三世紀半ばに小迫辻原遺跡が大きくなったのは、その頃トヨが日田の主として君臨し、安定期に入っていたと考えられる。しかもトヨは、ヤマトから派遣され日田に拠点を置いたのではなかったか。
詳細は避けるが、日田のトヨこそが日本の天皇家の祖であって、天皇家は日田で誕生したと言える。
そしてあくまでも伝承に従えば、日田の中心に位置する会所山の麓にある神功皇后の子・応神天皇の誕生遺跡とされる井戸、そここそが天皇家発祥の地ではないかと考えられる。
今後、日田は古代史解明のために、なくてはならない存在となるはずである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
現在は説が少し変わっているかもしれませんが、日田をこれだけ認めて頂いています。
天皇家が日田から・・・・・。
失礼なことをいうようだが大分県日田市といっても、ほとんど無名の地である。
まして、邪馬台国論争と日田のつながりについて、これまだまったく語られることがなかったと言っていい。
しかし、これから十年後、「日田」は、邪馬台国を語る上で避けては通れない場所になっているに違いない。
三世紀前半、つまり、邪馬台国から大和へ、という時代の節目に、この日田には大和の勢力が進出していた。これは筆者の勝手な推理ではなく、考古学的に裏付けられていることだ。
瀬戸内海の制海権を確立した「大和」は、この日田の地にまで勢力圏をのばしていたのである。地形的に、日田をとったものが九州を制することができるからだ。北部九州の中心筑紫平野には筑後川を下れば一気に出られ、しかも日田は天然の要害で、西側からの攻撃にすこぶる強かった。そしてこの地からは、後漢の王族しかもてなかったという金銀錯嵌珠龍文鉄鏡が出土している。いったい、どのような人物が、このような宝物を持ち得たというのか。
それは卑弥呼か、はたまた大和の大王か・・・・日田が邪馬台国に関わってくるのは、北部九州と大和の相克という視点が大切になってくるからだ。おそらく、久留米から山門郡にかけての一帯を支配していた邪馬台国の卑弥呼と、これを制圧すべく日田に遣わされた大和の王族── 金銀錯嵌珠龍文鉄鏡を持った日の巫女と思われる───との戦いが、日田の盆地と久留米の高良山周辺で展開された・・・・・・そして、卑弥呼と敵対していた日田の「巫女」こそが、のちに卑弥呼の宗女として邪馬台国を継承した「台与(とよ)」だったのではあるまいか。
日田が筑紫(福岡県)の文化圏経済圏にありながら大分県に組み込まれ、これが大分県の原型「豊国(とよのくに)」からの伝統であったのは、大和からの勢力・・・しかもそれが「トヨ」で・・・・が日田におよび、「トヨ」の名がそのまま国名になったからであろう。
このような推理は、まだ認知されていないが、日田周辺の発掘が進めば、いよいよもって、邪馬台国と日田の関係が注目されるのちがいないのだ。そして、それはそう遠い話ではないだろう。
梅澤恵美子先生から(2001/7/24)
日田について
今まで日田は、邪馬台国論争のなかでほとんど無名であったが、三世紀の考古学的見地から言うと、非常に重要な意味を帯びてきたと思える。
ヤマト(纒向遺跡)と日田(小迫辻原遺跡)は、発達の仕方と西に強いという地理条件がそっくりである。三世紀に突然現れて三世紀半ばに発展、東側から筑紫平野に睨みをきかすには、これ以上の立地条件はない。ここに拠点を持てば、九州勢は北部海岸地帯から退去するしかなかった。
おそらく九州勢(卑弥呼)は、高良山から女山に軍事拠点をつくって対抗したはずである。
三世紀半ばに小迫辻原遺跡が大きくなったのは、その頃トヨが日田の主として君臨し、安定期に入っていたと考えられる。しかもトヨは、ヤマトから派遣され日田に拠点を置いたのではなかったか。
詳細は避けるが、日田のトヨこそが日本の天皇家の祖であって、天皇家は日田で誕生したと言える。
そしてあくまでも伝承に従えば、日田の中心に位置する会所山の麓にある神功皇后の子・応神天皇の誕生遺跡とされる井戸、そここそが天皇家発祥の地ではないかと考えられる。
今後、日田は古代史解明のために、なくてはならない存在となるはずである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
現在は説が少し変わっているかもしれませんが、日田をこれだけ認めて頂いています。
天皇家が日田から・・・・・。
|
|
|
|
|
|
|
|
日田の歴史って面白くて凄い! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
日田の歴史って面白くて凄い!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人
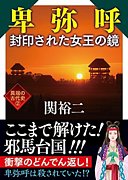





![縄文族ネットワーク [太陽の道]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/10/98/1581098_84s.gif)

















