日田古代史思考
昨年、九州国立博物館で4周年記念特別展「古代九州の国宝」が行われ、日田出土の金銀錯嵌珠龍文鉄鏡が「卑弥呼の鏡?」かと初めて脚光をあびた瞬間だった。
昭和八年久大本線建設中に土中から鉄鏡が出現した。その錆びた鏡を拾い上げたのが渡辺音吉氏である。その鏡が国重要文化財になるとは誰も思っていなかっただろう。鏡は渡辺氏が何かの参考になればと三芳小学校で展示されるが校舎建て替えの時、行方不明となる。
ところがなんとこの鏡は奈良で発見されたのであった。奈良の古美術商玉林善太郎から「伝日田出土」の鉄鏡を京都大学の教授が買い取っている。その後、この鏡を研ぎ出してみると、腰を抜かすほどの装飾がでてきだのだ。なんとこの教授は飛び上がって喜んでいる。その後、教授の調査で日田から出土した経緯が確かめられている。
しかし残念ながら、鏡は遺跡とは違い動くことが出来るので、日田から出土しても邪馬台国や卑弥呼との関係を研究しても答えは出てきそうにもない。例え日田から金印が出土しても、後に持ち込まれたと解釈すれば夢物語となってしまうのが現実なのである。
では卑弥呼の死後に栄えた日本最古の豪族居館跡の日田の小迫辻原遺跡は何を意味するのだろうか。筑後川の三大遺跡で佐賀の吉野ヶ里や甘木の平塚川添遺跡につぐ貴重な遺跡なのだが、今その面影がないのは非常に寂しい事である。
日田は邪馬台国?
ここで日田邪馬台国・卑弥呼説の紹介をしてみよう。昭和8年には佐賀県の佐藤林賀氏が日田卑弥呼説そして古村豊氏(日田=卑弥呼=日向)、福本秀城氏、於保忠彦氏、木藪正道氏、後藤英彦氏、など次々に日田と邪馬台国卑弥呼の関係を著書で紹介している、まだ、認知されていないのが現実である。しかしながら全国的に知名度のある高木彬光氏、澤田洋太郎氏、梅澤恵美子氏、関裕二氏が説は違えども日田の古代を全国に知らしめているのは心強い。それではこれから古村氏、福本氏が唱えてきた説を中心に日田古代史の話を展開してみよう。
古村氏は日田の会所山と日向の地名に注目していた。九州にある日向の地名を探し出した結果、日田を中心に夏至と冬至のラインに日向という地名が並んでいる事に気づき、日田は日向郷ではなかったかと仮説された。『日本書紀』では日向について不可解な記述がある、それは天照大御神と素戔嗚尊と月読尊が九州の筑紫の日向で誕生するのだが、今の宮崎は13代景行天皇が日向と名付けているのだから、少なくとも宮崎が景行天皇以前日向ではなかった可能性がる。また景行天皇は『日本書紀』では南九州を周り八女、久留米、浮羽と細かく書かれ移動しているが、浮羽からはなんといきなり、日向(宮崎)へと飛行機でも乗ったのかのように移動しているが、『豊後国風土記』には景行天皇は浮羽から日田へ凱旋している事実を『日本書紀』は記述されていない。『日本書紀』は日田を重要視していなかったのか、それとも日田が日向であれば矛盾はないのだが。また『古事記』には不可解な記述がある。それは九州には筑紫国は白日別(しらひわけ)、豊国(とよくに)は豊日別(とよひわけ)、肥国(ひのくに)は建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)、熊曽国(くまそのくに)は建日別(たけひわけ)と4つに別れているが、何故か日向の国がないのでる。『隼人と大和政権』井上辰雄氏は「日向はむしろ豊国の延長と考えられている」。日田郷土史家の福本氏は「建日向日豊久士比泥別」の中に日向が隠されていて、日向は日田だと仮説している。日向は日に向かうという意味で「東」という意味も含まれており、筑紫=筑紫平野であればその東も日田という意味が含まれている可能性も否定はできない。
日田は古代から鏡伝説があった?
『豊後国風土記』のよれば景行天皇が日田に凱旋して、日田は鏡のようだと言われている、また久津媛という神が訛り「日田」になったと記述されていて古代の日田は「ひさ」と呼ばれた可能性が高いが駒澤大学教授の瀧音能之氏は著書で ひさ=鏡 だと紹介している。日は太陽を意味し佐は補佐する意味があり、太陽信仰を補佐する日巫女を想像できよう。これは余談だが、橿原考古学研究所は、全国紙で「田」は古代最古の記号で、巫女や聖なる意味があると報告している。少なくとも地名には意味があって名がついているのであって、日田の田も「田んぼ」という単純な意味ではなく、もっと掘り下げると歴史の闇を地名として残したとも言い切れないと思う。久津媛(ひさつひめ)が日田になったという『豊後国風土記』の意味するものはとんでもない謎を言い伝えるのである。
鉄鏡も実は日本からは飛騨高山からも鉄鏡が発見されているのだが、ひさ=ひた=ひだ=鏡(鉄鏡)という証明にもなるのではないだろうか。
もし古代から日田には鉄鏡の伝説があったのなら、風土記や言い伝えや地名として変化して後世に残そうとしたのではないだろうか。
これも余談だが、金銀錯嵌珠龍文鉄鏡には8匹の龍が描かれていると言われるが、日田は古代から北部九州の交通の要所であり、八衢(八方に伸びる道)・八又と呼ばれたとも言われるが、素戔嗚尊が退治した八岐大蛇は日田から北部九州を支配したイメージともという説もある。また出雲国造の祖「岐比佐都美(別名)来日田維穂命」(きひさつみ)の記述があり、福本氏によれば『豊後国風土記』に登場する久津媛(比佐津媛)は出雲国造の祖「岐比佐都美と同一人物である可能性が強い。別名でも「日田」という文字がつき、久津媛=比佐津媛であり、日田=元出雲という説も。
高木彬光氏、澤田洋太郎氏は天孫降臨は日田から始まった(関裕二氏も同じ)そして日田は古代の八衢ではなかったかという説を著書で紹介している。
季刊邪馬台国の中で鉄鏡は八咫の鏡かという紹介がされ『古事記』では天照大御の岩戸開きに使われた八咫の鏡は「天の金山(かなやま)の鉄(くろがね)」 (711年成立『古事記』)「天の香山(かぐやま)の金(かね)」 (720年成立『日本書紀』一書)と記述され、江戸時代の国学者 飯田武郷と平田篤胤は八咫の鏡は鉄鏡説を唱えていた事は知られていない。
北部九州の日田
日田は地理的に北部九州の中心と言ってよく、大分、中津、北九州、福岡市、久留米、熊本と60kmの円内にある。豊臣と徳川が日田を直轄地として九州を統治した理由もここにありそうだ。もう一つ、筑後川を治めるにも日田は理想の位置に存在する。また日田は盆地であり、軍事的にも絶好の場所だ、これは大和とも同じ事が言える。余談だが、関裕二氏が日田に来てどこか見覚えのある場所(大和盆地)に来たようだと言っていたのを覚えている。
それはともかく、歴史的に東国から九州を統治するためには日田を治めろというのが軍事的な鉄則ではなかったか、少なくとも豊臣と徳川は日田に楔を打ち込んでいる事実だれも否定できない。おそらく、磐井の乱や卑弥呼の時代も同じ現象が起きていた可能性はある。東遷説でも、卑弥呼の都は、玄海(伊都・奴国)そして甘木そして日田そして宇佐と移動していた可能性も充分考えられる。邪馬台国は筑後川流域であり、郷土史家の福本氏や後藤氏も日田は奥津城的な場所で、卑弥呼の居住する場所は日田だと仮設している。
日田は歴史の大きな節目に大きく反応していて、しかしながら特に古代においては、関裕二氏は『日本書紀』を編纂した藤原不比等は邪馬台国の謎を日田に封印してしまったと著書で紹介しいている。日田の謎が解ければ聖徳太子までの謎がすべて解けてしまうのであり、古代の日田と聖徳太子は武内宿禰神功皇后と蘇我氏という深い関係でつながっているのである。
そんな事はあり得ないと思われる人がほとんどでしょう。卑弥呼の時代、伊都・奴国と日田をくらべると全く太刀打ちできないくらいの差はあるのも事実だが、卑弥呼が死去し、台与が権力を持つ頃、邪馬台国の時代背景は大きく変わり九州が圧倒していた鉄が畿内へ大きく移動しているのである。そして纒向遺跡などや前方後円墳などがこつぜんと造られ大きな政変があった可能性を証明してる。関裕二氏は鉄の流れに日田は重要な関わりをしていて、日田の奪い合いがあっり九州勢力とヤマト勢力の戦いがあり、九州は敗北したと仮説している。
纒向には西日本の各地から土器があつまり各地の人が定住し大きな連合国家を形成している。そして何故か日田の小迫辻原遺跡は纒向と同時期に発展し山陰や畿内の土器(布留式土器)が出土(持ち込まれた可能性)している意味は、出雲やヤマトと交流があった証拠であり、その意味はこれまで研究された事はない。ただの交流だけなのか、それとも纒向と日田はつながっていたのか答えはわからないが、これからの研究を期待したい。
日田はある意味、卑弥呼から台与の時代に移り変わる大きな意味を持った土地であり、鉄の移動の裏には日田が、からんでいると思っても不思議ではあるまい。そして金銀錯嵌珠龍文鉄鏡が絡んでくれば、その意味も大きくなってくるのある。
「邪馬台国東遷説」、「邪馬台国畿内説」、「二つの邪馬台国説(邪馬台国は九州と畿内にそれぞれあった)」など、どの説にしても、日田は重要なキーワードをもっていそうだ。
昨年、九州国立博物館で4周年記念特別展「古代九州の国宝」が行われ、日田出土の金銀錯嵌珠龍文鉄鏡が「卑弥呼の鏡?」かと初めて脚光をあびた瞬間だった。
昭和八年久大本線建設中に土中から鉄鏡が出現した。その錆びた鏡を拾い上げたのが渡辺音吉氏である。その鏡が国重要文化財になるとは誰も思っていなかっただろう。鏡は渡辺氏が何かの参考になればと三芳小学校で展示されるが校舎建て替えの時、行方不明となる。
ところがなんとこの鏡は奈良で発見されたのであった。奈良の古美術商玉林善太郎から「伝日田出土」の鉄鏡を京都大学の教授が買い取っている。その後、この鏡を研ぎ出してみると、腰を抜かすほどの装飾がでてきだのだ。なんとこの教授は飛び上がって喜んでいる。その後、教授の調査で日田から出土した経緯が確かめられている。
しかし残念ながら、鏡は遺跡とは違い動くことが出来るので、日田から出土しても邪馬台国や卑弥呼との関係を研究しても答えは出てきそうにもない。例え日田から金印が出土しても、後に持ち込まれたと解釈すれば夢物語となってしまうのが現実なのである。
では卑弥呼の死後に栄えた日本最古の豪族居館跡の日田の小迫辻原遺跡は何を意味するのだろうか。筑後川の三大遺跡で佐賀の吉野ヶ里や甘木の平塚川添遺跡につぐ貴重な遺跡なのだが、今その面影がないのは非常に寂しい事である。
日田は邪馬台国?
ここで日田邪馬台国・卑弥呼説の紹介をしてみよう。昭和8年には佐賀県の佐藤林賀氏が日田卑弥呼説そして古村豊氏(日田=卑弥呼=日向)、福本秀城氏、於保忠彦氏、木藪正道氏、後藤英彦氏、など次々に日田と邪馬台国卑弥呼の関係を著書で紹介している、まだ、認知されていないのが現実である。しかしながら全国的に知名度のある高木彬光氏、澤田洋太郎氏、梅澤恵美子氏、関裕二氏が説は違えども日田の古代を全国に知らしめているのは心強い。それではこれから古村氏、福本氏が唱えてきた説を中心に日田古代史の話を展開してみよう。
古村氏は日田の会所山と日向の地名に注目していた。九州にある日向の地名を探し出した結果、日田を中心に夏至と冬至のラインに日向という地名が並んでいる事に気づき、日田は日向郷ではなかったかと仮説された。『日本書紀』では日向について不可解な記述がある、それは天照大御神と素戔嗚尊と月読尊が九州の筑紫の日向で誕生するのだが、今の宮崎は13代景行天皇が日向と名付けているのだから、少なくとも宮崎が景行天皇以前日向ではなかった可能性がる。また景行天皇は『日本書紀』では南九州を周り八女、久留米、浮羽と細かく書かれ移動しているが、浮羽からはなんといきなり、日向(宮崎)へと飛行機でも乗ったのかのように移動しているが、『豊後国風土記』には景行天皇は浮羽から日田へ凱旋している事実を『日本書紀』は記述されていない。『日本書紀』は日田を重要視していなかったのか、それとも日田が日向であれば矛盾はないのだが。また『古事記』には不可解な記述がある。それは九州には筑紫国は白日別(しらひわけ)、豊国(とよくに)は豊日別(とよひわけ)、肥国(ひのくに)は建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)、熊曽国(くまそのくに)は建日別(たけひわけ)と4つに別れているが、何故か日向の国がないのでる。『隼人と大和政権』井上辰雄氏は「日向はむしろ豊国の延長と考えられている」。日田郷土史家の福本氏は「建日向日豊久士比泥別」の中に日向が隠されていて、日向は日田だと仮説している。日向は日に向かうという意味で「東」という意味も含まれており、筑紫=筑紫平野であればその東も日田という意味が含まれている可能性も否定はできない。
日田は古代から鏡伝説があった?
『豊後国風土記』のよれば景行天皇が日田に凱旋して、日田は鏡のようだと言われている、また久津媛という神が訛り「日田」になったと記述されていて古代の日田は「ひさ」と呼ばれた可能性が高いが駒澤大学教授の瀧音能之氏は著書で ひさ=鏡 だと紹介している。日は太陽を意味し佐は補佐する意味があり、太陽信仰を補佐する日巫女を想像できよう。これは余談だが、橿原考古学研究所は、全国紙で「田」は古代最古の記号で、巫女や聖なる意味があると報告している。少なくとも地名には意味があって名がついているのであって、日田の田も「田んぼ」という単純な意味ではなく、もっと掘り下げると歴史の闇を地名として残したとも言い切れないと思う。久津媛(ひさつひめ)が日田になったという『豊後国風土記』の意味するものはとんでもない謎を言い伝えるのである。
鉄鏡も実は日本からは飛騨高山からも鉄鏡が発見されているのだが、ひさ=ひた=ひだ=鏡(鉄鏡)という証明にもなるのではないだろうか。
もし古代から日田には鉄鏡の伝説があったのなら、風土記や言い伝えや地名として変化して後世に残そうとしたのではないだろうか。
これも余談だが、金銀錯嵌珠龍文鉄鏡には8匹の龍が描かれていると言われるが、日田は古代から北部九州の交通の要所であり、八衢(八方に伸びる道)・八又と呼ばれたとも言われるが、素戔嗚尊が退治した八岐大蛇は日田から北部九州を支配したイメージともという説もある。また出雲国造の祖「岐比佐都美(別名)来日田維穂命」(きひさつみ)の記述があり、福本氏によれば『豊後国風土記』に登場する久津媛(比佐津媛)は出雲国造の祖「岐比佐都美と同一人物である可能性が強い。別名でも「日田」という文字がつき、久津媛=比佐津媛であり、日田=元出雲という説も。
高木彬光氏、澤田洋太郎氏は天孫降臨は日田から始まった(関裕二氏も同じ)そして日田は古代の八衢ではなかったかという説を著書で紹介している。
季刊邪馬台国の中で鉄鏡は八咫の鏡かという紹介がされ『古事記』では天照大御の岩戸開きに使われた八咫の鏡は「天の金山(かなやま)の鉄(くろがね)」 (711年成立『古事記』)「天の香山(かぐやま)の金(かね)」 (720年成立『日本書紀』一書)と記述され、江戸時代の国学者 飯田武郷と平田篤胤は八咫の鏡は鉄鏡説を唱えていた事は知られていない。
北部九州の日田
日田は地理的に北部九州の中心と言ってよく、大分、中津、北九州、福岡市、久留米、熊本と60kmの円内にある。豊臣と徳川が日田を直轄地として九州を統治した理由もここにありそうだ。もう一つ、筑後川を治めるにも日田は理想の位置に存在する。また日田は盆地であり、軍事的にも絶好の場所だ、これは大和とも同じ事が言える。余談だが、関裕二氏が日田に来てどこか見覚えのある場所(大和盆地)に来たようだと言っていたのを覚えている。
それはともかく、歴史的に東国から九州を統治するためには日田を治めろというのが軍事的な鉄則ではなかったか、少なくとも豊臣と徳川は日田に楔を打ち込んでいる事実だれも否定できない。おそらく、磐井の乱や卑弥呼の時代も同じ現象が起きていた可能性はある。東遷説でも、卑弥呼の都は、玄海(伊都・奴国)そして甘木そして日田そして宇佐と移動していた可能性も充分考えられる。邪馬台国は筑後川流域であり、郷土史家の福本氏や後藤氏も日田は奥津城的な場所で、卑弥呼の居住する場所は日田だと仮設している。
日田は歴史の大きな節目に大きく反応していて、しかしながら特に古代においては、関裕二氏は『日本書紀』を編纂した藤原不比等は邪馬台国の謎を日田に封印してしまったと著書で紹介しいている。日田の謎が解ければ聖徳太子までの謎がすべて解けてしまうのであり、古代の日田と聖徳太子は武内宿禰神功皇后と蘇我氏という深い関係でつながっているのである。
そんな事はあり得ないと思われる人がほとんどでしょう。卑弥呼の時代、伊都・奴国と日田をくらべると全く太刀打ちできないくらいの差はあるのも事実だが、卑弥呼が死去し、台与が権力を持つ頃、邪馬台国の時代背景は大きく変わり九州が圧倒していた鉄が畿内へ大きく移動しているのである。そして纒向遺跡などや前方後円墳などがこつぜんと造られ大きな政変があった可能性を証明してる。関裕二氏は鉄の流れに日田は重要な関わりをしていて、日田の奪い合いがあっり九州勢力とヤマト勢力の戦いがあり、九州は敗北したと仮説している。
纒向には西日本の各地から土器があつまり各地の人が定住し大きな連合国家を形成している。そして何故か日田の小迫辻原遺跡は纒向と同時期に発展し山陰や畿内の土器(布留式土器)が出土(持ち込まれた可能性)している意味は、出雲やヤマトと交流があった証拠であり、その意味はこれまで研究された事はない。ただの交流だけなのか、それとも纒向と日田はつながっていたのか答えはわからないが、これからの研究を期待したい。
日田はある意味、卑弥呼から台与の時代に移り変わる大きな意味を持った土地であり、鉄の移動の裏には日田が、からんでいると思っても不思議ではあるまい。そして金銀錯嵌珠龍文鉄鏡が絡んでくれば、その意味も大きくなってくるのある。
「邪馬台国東遷説」、「邪馬台国畿内説」、「二つの邪馬台国説(邪馬台国は九州と畿内にそれぞれあった)」など、どの説にしても、日田は重要なキーワードをもっていそうだ。
|
|
|
|
|
|
|
|
日田の歴史って面白くて凄い! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
日田の歴史って面白くて凄い!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208311人
- 3位
- 酒好き
- 170692人
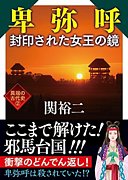





![縄文族ネットワーク [太陽の道]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/10/98/1581098_84s.gif)

















