文芸社「謎解き古代史独学のススメ 」より
邪馬台国九州説の復活
では、ヤマトの箸墓は誰の墓であったのか、ということになる。ここで注意しておかなくてはならないのは、卑弥呼と時代が合うからといって、卑弥呼の墓であった確証はない、ということであり、ヤマトに巨大な勢力が存在していたことは動かしがたいとしても、逆に、北部九州に邪馬台国が併存していたこともあり得る、ということである。
この、見捨てられつつある北部九州説に光明をもたらす情報が、大分県日田市から舞い込んだのは、つい先日のことであった。青年会議所の佐々木祥治氏が、日田市出土の金銀錯嵌珠龍文鉄鏡の話をしに、わざわざハイウェイバスに乗って、東京にでてきたのである。
佐々木氏は「『豊後国風土記』に記された日田の久津媛こそが邪馬台国の卑弥呼だったのではないか」という日田市の久津媛の会の会員でもある。
そんな佐々木氏がたまたま拙著を読み、慌ててやってきたのだった。佐々木氏は、昭和九年に久大本線の工事現場から出土していた金銀錯嵌珠龍文鉄鏡の写真をもってきた。その鏡は、後漢鏡で、しかも王家の鏡であったという。いったいどういう理由で、大分県に、このような至宝が眠っていたのであろう。ほんとうに久津媛が卑弥呼だった?
問題はそう単純ではない。
日田市は古代の北部九州の中心、筑紫平野の奥座敷にあたっていた。筑後川を下れば、そのまま一気に久留米市付近にたどり着く。久留米といえば、邪馬台国九州説の最有力候補地、山門にほど近い。逆に、筑紫平野から日田に入るには、狭隘な渓谷部を通過せざるを得ず、したがって、日田の特性は、筑紫平野側からの攻撃にすこぶる強い、ということなのである。
また、日田は北部九州の交通の要衝で、道が八方に延び、たとえばいまでも博多まで車で一時間。宇佐方面や大分、佐賀もほぼ同じ時間で行ける。この地の利を利用して、江戸時代には天領となった。
ただし、日田は、西側からの攻撃に強い反面、東側には弱い。じつをいうと、この日田の地勢が、邪馬台国を解く最大のヒントとなっていようとは、いったい誰が想像したであろう。
そして、佐々木氏は、日田の地が福岡県の文化圏に入っていながら、なぜか古来、大分県側に組み込まれていた、という。すなわち、“豊の国(豊前・豊後)”だったのである。佐々木氏は、金銀錯嵌珠龍文鉄鏡とこの事実を伝えに、私の元にやってきたのだった。
見逃されていた重要証拠・大分県日田市
日田が豊の国であったことにどのような意味があったのか。
まずここで注目しておきたいのが、日田市の三世紀の遺跡について、である。それは、盆地北部の小迫辻原遺跡で、ここには、三世紀の居館と環濠が見つかり、意外な事実が発覚した。というのも、この遺跡からは、山陰やヤマトの土器が出土していて、大きな謎となっていたのだ。
しかしこれは謎でもなんでもない。二世紀から三世紀の西日本の状況を考えれば、“日田のヤマト”は必然ですらある。
二世紀から三世紀の西日本は朝鮮半島の鉄資源をめぐる戦乱に明け暮れた。この結果、畿内を中心とする瀬戸内海勢力が勝利を収め、瀬戸内海から豊後水道にかけての制海権を得ていたと考えられる。そして、北部九州の東海岸も、当然制海権を得るために必要としたであろう。その証拠に、この過程で、瀬戸内海勢力は、南部九州の東海岸にも影響力を及ぼしている。
そこで日田の地形に注目すると、興味深い事実に突き当たる。それは改めて言うが、東側からの攻撃に弱く西側に強い、ということなのである。そして、宇佐方面からこの地を押さえてしまえば、瀬戸内海の制海権を確立するための北部九州東部の海岸部は安泰である。したがって、畿内勢力が日田に注目し、この地を押さえたことは、自然の成り行きだったことになる。おそらく北部九州の西側の筑紫平野に展開していたであろう大勢力は、日田を押さえられたことで、身動きがとれなくなったであろう。
いっぽう目を転じて三世紀のヤマトの纏向遺跡に注目すると、九州の土器がほとんどなかったから、かつての日本の最先進地帯であった北部九州が黄昏の時代に入っていたことが分かる。こののちヤマトは“九州”を受け入れているから、かりにこの九州の王が天皇とすれば(事実そうであったと思われるが)、天皇とは借りてきた猫のような存在であった可能性もある。このような三世紀の西日本の状況と「日田」を邪馬台国問題に組み込むと、これまでにないひとつの仮説が得られる。
『魏志』倭人伝を読む限り邪馬台国が北部九州にあったととらえるのが自然である。それにもかかわらず、当時の西日本の中心が畿内にあることはたしかなことであった。この穴をどう埋めるか。
発想を変えてみればいいのだ。勢力が大きいからといって、それが邪馬台国であったという証拠にはならない、ということである。邪馬台国が魏に朝貢したのは、魏が朝鮮半島の帯方郡を占拠した直後のことで、邪馬台国の迅速な外交戦術をかいま見ることができる。仮に、畿内の勢力が後れをとったとすれば、“倭国王”の称号を、九州にさらわれたとしてもなんの不思議もない。そして、この“称号”を奪回するために、日田の地の争奪戦が起こっていたとはいえないだろうか。
邪馬台国九州説の復活
では、ヤマトの箸墓は誰の墓であったのか、ということになる。ここで注意しておかなくてはならないのは、卑弥呼と時代が合うからといって、卑弥呼の墓であった確証はない、ということであり、ヤマトに巨大な勢力が存在していたことは動かしがたいとしても、逆に、北部九州に邪馬台国が併存していたこともあり得る、ということである。
この、見捨てられつつある北部九州説に光明をもたらす情報が、大分県日田市から舞い込んだのは、つい先日のことであった。青年会議所の佐々木祥治氏が、日田市出土の金銀錯嵌珠龍文鉄鏡の話をしに、わざわざハイウェイバスに乗って、東京にでてきたのである。
佐々木氏は「『豊後国風土記』に記された日田の久津媛こそが邪馬台国の卑弥呼だったのではないか」という日田市の久津媛の会の会員でもある。
そんな佐々木氏がたまたま拙著を読み、慌ててやってきたのだった。佐々木氏は、昭和九年に久大本線の工事現場から出土していた金銀錯嵌珠龍文鉄鏡の写真をもってきた。その鏡は、後漢鏡で、しかも王家の鏡であったという。いったいどういう理由で、大分県に、このような至宝が眠っていたのであろう。ほんとうに久津媛が卑弥呼だった?
問題はそう単純ではない。
日田市は古代の北部九州の中心、筑紫平野の奥座敷にあたっていた。筑後川を下れば、そのまま一気に久留米市付近にたどり着く。久留米といえば、邪馬台国九州説の最有力候補地、山門にほど近い。逆に、筑紫平野から日田に入るには、狭隘な渓谷部を通過せざるを得ず、したがって、日田の特性は、筑紫平野側からの攻撃にすこぶる強い、ということなのである。
また、日田は北部九州の交通の要衝で、道が八方に延び、たとえばいまでも博多まで車で一時間。宇佐方面や大分、佐賀もほぼ同じ時間で行ける。この地の利を利用して、江戸時代には天領となった。
ただし、日田は、西側からの攻撃に強い反面、東側には弱い。じつをいうと、この日田の地勢が、邪馬台国を解く最大のヒントとなっていようとは、いったい誰が想像したであろう。
そして、佐々木氏は、日田の地が福岡県の文化圏に入っていながら、なぜか古来、大分県側に組み込まれていた、という。すなわち、“豊の国(豊前・豊後)”だったのである。佐々木氏は、金銀錯嵌珠龍文鉄鏡とこの事実を伝えに、私の元にやってきたのだった。
見逃されていた重要証拠・大分県日田市
日田が豊の国であったことにどのような意味があったのか。
まずここで注目しておきたいのが、日田市の三世紀の遺跡について、である。それは、盆地北部の小迫辻原遺跡で、ここには、三世紀の居館と環濠が見つかり、意外な事実が発覚した。というのも、この遺跡からは、山陰やヤマトの土器が出土していて、大きな謎となっていたのだ。
しかしこれは謎でもなんでもない。二世紀から三世紀の西日本の状況を考えれば、“日田のヤマト”は必然ですらある。
二世紀から三世紀の西日本は朝鮮半島の鉄資源をめぐる戦乱に明け暮れた。この結果、畿内を中心とする瀬戸内海勢力が勝利を収め、瀬戸内海から豊後水道にかけての制海権を得ていたと考えられる。そして、北部九州の東海岸も、当然制海権を得るために必要としたであろう。その証拠に、この過程で、瀬戸内海勢力は、南部九州の東海岸にも影響力を及ぼしている。
そこで日田の地形に注目すると、興味深い事実に突き当たる。それは改めて言うが、東側からの攻撃に弱く西側に強い、ということなのである。そして、宇佐方面からこの地を押さえてしまえば、瀬戸内海の制海権を確立するための北部九州東部の海岸部は安泰である。したがって、畿内勢力が日田に注目し、この地を押さえたことは、自然の成り行きだったことになる。おそらく北部九州の西側の筑紫平野に展開していたであろう大勢力は、日田を押さえられたことで、身動きがとれなくなったであろう。
いっぽう目を転じて三世紀のヤマトの纏向遺跡に注目すると、九州の土器がほとんどなかったから、かつての日本の最先進地帯であった北部九州が黄昏の時代に入っていたことが分かる。こののちヤマトは“九州”を受け入れているから、かりにこの九州の王が天皇とすれば(事実そうであったと思われるが)、天皇とは借りてきた猫のような存在であった可能性もある。このような三世紀の西日本の状況と「日田」を邪馬台国問題に組み込むと、これまでにないひとつの仮説が得られる。
『魏志』倭人伝を読む限り邪馬台国が北部九州にあったととらえるのが自然である。それにもかかわらず、当時の西日本の中心が畿内にあることはたしかなことであった。この穴をどう埋めるか。
発想を変えてみればいいのだ。勢力が大きいからといって、それが邪馬台国であったという証拠にはならない、ということである。邪馬台国が魏に朝貢したのは、魏が朝鮮半島の帯方郡を占拠した直後のことで、邪馬台国の迅速な外交戦術をかいま見ることができる。仮に、畿内の勢力が後れをとったとすれば、“倭国王”の称号を、九州にさらわれたとしてもなんの不思議もない。そして、この“称号”を奪回するために、日田の地の争奪戦が起こっていたとはいえないだろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
日田の歴史って面白くて凄い! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
日田の歴史って面白くて凄い!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6468人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19248人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208304人
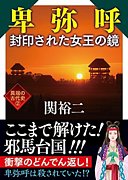





![縄文族ネットワーク [太陽の道]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/10/98/1581098_84s.gif)

















