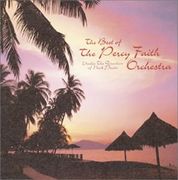「CDで聴くムードミュージックとイージーリスニングのスタアたち」
出谷啓著
芸術現代社 h14年刊
イージーリスニング音楽・ムード音楽の代表的なバンドリーダー、ソリスト等を集めた珍しい本。
著者出谷啓氏は、クラシックの音楽評論でも知られ、レオポルド・ストコフスキーを高く評価してきた。「外面的な美しさを追究して何が悪いのか」というのが、著者の音楽に対する基本姿勢であるように思う。
すなわち、多くの評論家は、「精神性」といった抽象的概念を使って、フルトベングラーなどを高く評価するのだが、著者は、その正反対の立場からストコフスキーを推薦するのだ。
クラシックとイージーリスニング音楽(ライト・ミュージック)との境界について著者は、疑問を呈している。つまり、聴いてみて、楽しかったり、心地よかったりする音楽は、ジャンルなど関係なくいい音楽なのだと。
本著は、そうした視点から、77人の指揮者・演奏者を採り上げている。
マントヴァーニはもちろんのこと、スタンリー・ブラック、パーシー・フェイス、モートン・グールド、アンドレ・コステラネッツ、ジョージ・メラクリーノ、ウェルナー・ミューラー、フランク・チャックスフィールド、クレバノフなど、だれもが納得する楽団を網羅している。
ノリー・パラマー、ゴードン・ジェンキンスなどの渋い名前も出てくる。
反対に、ポール・モーリア、レイモン・ルフェーブルは、採り上げられていない。その理由は、「ムード・ミュージックというジャンルを結果的にだめにしたのが彼らだと思うからである。」(「あとがき」p241)
、
《マントヴァーニについての記述(抄)》
「マントヴァーニは1963年の5月に、たった1度だけオーケストラを率いて来日した。そのとき会場の大阪フェスティバル・ホールに向かう途中、先輩の音楽評論家故吉村一夫氏に出会った。「どこへ行くんや」ととわれ、マントヴァーニのコンサートに行くと答えると、氏は「今日はモノーラルやで」とおっしゃった。ことほどさように当時の音楽関係者は、マントヴァーニ・サウンドは、レコーディング・スタジオで作られたものと信じ切っていたのである。
だが実際は、違っていた。実演のステージでも、あのユニークなマントヴァーニ・サウンドを聴くことができた。決してレコーディング・テクニックによる、マジックなどではなかった。むしろ彼特有の編曲テクニックが分かって、それは感動的ですらあった。
ヴァイオリンのパートだけでも、6つの部分に分けられ、第1ヴァイオリンの旋律のエコーとして、第3ヴァイオリンが機能する仕掛けで、第2ヴァイオリンのエコーが第4ヴァイオリンが受け持つという、独特のシステムが、あの雪崩落ちるようなカスケイディング・ストリングスの効果を発揮していたのである。
そしてまた打楽器奏者は、すべて一人で担当し、行進曲など大太鼓とシンバルを同時に鳴らす場合は、フット・シンバルを用いて手と足を両方使えるよう、アレンジで計算しているのであった。その合理的な編曲技術が、効率よく最小限の員数で、最大限の効果を発揮するベースになっていた。最近でも毎年のように、ザ・マントヴァーニ・オーケストラは来日しているが、それはいわば主なきオーケストラであり、ニセモノとはいわないまでも、物まねオーケストラであることは間違いない。」
(「同書」p128−129より)
出谷啓著
芸術現代社 h14年刊
イージーリスニング音楽・ムード音楽の代表的なバンドリーダー、ソリスト等を集めた珍しい本。
著者出谷啓氏は、クラシックの音楽評論でも知られ、レオポルド・ストコフスキーを高く評価してきた。「外面的な美しさを追究して何が悪いのか」というのが、著者の音楽に対する基本姿勢であるように思う。
すなわち、多くの評論家は、「精神性」といった抽象的概念を使って、フルトベングラーなどを高く評価するのだが、著者は、その正反対の立場からストコフスキーを推薦するのだ。
クラシックとイージーリスニング音楽(ライト・ミュージック)との境界について著者は、疑問を呈している。つまり、聴いてみて、楽しかったり、心地よかったりする音楽は、ジャンルなど関係なくいい音楽なのだと。
本著は、そうした視点から、77人の指揮者・演奏者を採り上げている。
マントヴァーニはもちろんのこと、スタンリー・ブラック、パーシー・フェイス、モートン・グールド、アンドレ・コステラネッツ、ジョージ・メラクリーノ、ウェルナー・ミューラー、フランク・チャックスフィールド、クレバノフなど、だれもが納得する楽団を網羅している。
ノリー・パラマー、ゴードン・ジェンキンスなどの渋い名前も出てくる。
反対に、ポール・モーリア、レイモン・ルフェーブルは、採り上げられていない。その理由は、「ムード・ミュージックというジャンルを結果的にだめにしたのが彼らだと思うからである。」(「あとがき」p241)
、
《マントヴァーニについての記述(抄)》
「マントヴァーニは1963年の5月に、たった1度だけオーケストラを率いて来日した。そのとき会場の大阪フェスティバル・ホールに向かう途中、先輩の音楽評論家故吉村一夫氏に出会った。「どこへ行くんや」ととわれ、マントヴァーニのコンサートに行くと答えると、氏は「今日はモノーラルやで」とおっしゃった。ことほどさように当時の音楽関係者は、マントヴァーニ・サウンドは、レコーディング・スタジオで作られたものと信じ切っていたのである。
だが実際は、違っていた。実演のステージでも、あのユニークなマントヴァーニ・サウンドを聴くことができた。決してレコーディング・テクニックによる、マジックなどではなかった。むしろ彼特有の編曲テクニックが分かって、それは感動的ですらあった。
ヴァイオリンのパートだけでも、6つの部分に分けられ、第1ヴァイオリンの旋律のエコーとして、第3ヴァイオリンが機能する仕掛けで、第2ヴァイオリンのエコーが第4ヴァイオリンが受け持つという、独特のシステムが、あの雪崩落ちるようなカスケイディング・ストリングスの効果を発揮していたのである。
そしてまた打楽器奏者は、すべて一人で担当し、行進曲など大太鼓とシンバルを同時に鳴らす場合は、フット・シンバルを用いて手と足を両方使えるよう、アレンジで計算しているのであった。その合理的な編曲技術が、効率よく最小限の員数で、最大限の効果を発揮するベースになっていた。最近でも毎年のように、ザ・マントヴァーニ・オーケストラは来日しているが、それはいわば主なきオーケストラであり、ニセモノとはいわないまでも、物まねオーケストラであることは間違いない。」
(「同書」p128−129より)
|
|
|
|
|
|
|
|
@ム-ド音楽&イ-ジ-・リスニング 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
@ム-ド音楽&イ-ジ-・リスニングのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8446人
- 2位
- 一行で笑わせろ!
- 82529人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208283人