2/10〜2/16
思考が力をつけ
霊が生まれる。
そして感覚の暗い印象を
明るい光で充たす。
魂が生成する宇宙に
帰依しようとするとき、
感覚の体験が
思考の照明を受けて輝く。
(Rudolf Steiner 高橋 巌訳)
--------------
子どもの教育について考える場合、
一番大切なのは、
人間とはいったい何か?
人間とはいかなる構成要素から
成り立っているのかを知ることが第一である。
『霊学の観点からの子どもの教育』
(Rudolf Steiner 松浦賢訳 イザラ書房)を
今朝も繰り返し読んでいるのであるが、
何度読んでも初めて読むような感動を覚える。
シュタイナーの著作の中できわめて読みやすい本である。
今回は、人間の構成要素について、
シュタイナーがまとめている部分について引用してみたい。
人間は、いかなる構成要素から成り立っているのか、
まずこれを、深く知ることが
教育の土台となるであろう。
「人間の本質のなかには、
まず、感覚(視覚などの肉体的感覚)をもちいて
人間を観察することによってとらえられる部分があります。
唯物論的に生命をとらえようとする人は、
人間の本質のうち、この部分だけを認めようとします。
しかし霊的な研究の立場から見ると、
それは、まだ人間の本質の一部分にすぎません。
それは、人間の本質を構成する要素の一つ、
すなわち物質体なのです。
物質体は、そのほかの無機的な世界全体と同じように、
物質的な生命の法則に従っています。
物質体は、無機的な世界を構成しているのと
同じ物質と力によって作り上げられています。
ですから霊学の観点から見ると、
「人間は、物質体を鉱物の世界全体と共有している」ということができます。
鉱物の世界では、
物質は、混合 や結合や形成や分解といった法則に従って活動します。
霊学は、人間の本質のうち、
「鉱物界と同じ物質を、
鉱物界と同じ法則に従って、混合させたり、
結びつけたり、形成したり、
分解したりする部分」だけを物質体と呼びます。
さらに神智学は、このような物質体を越えて、
人間のなかに第二の本質を認めます。
この第二の本質は、生命体またはエーテル体と呼ばれています。
物理学を専門に研究している方は、
どうぞ「エーテル体」という言葉に
反発を感じないでいただきたいと思います。
ここでいう「エーテル」とは、
物理学が仮説として立てたエーテルとは
別のものを指しています。
「エーテル」は、以下に述べるような事柄を
表すための言葉ととっていただきたいのです。
少し以前から、科学の世界では、
「エーテル体」のような事柄について
語ることは、学問的な態度ではないと見なされるようになりました。
ところが十八世紀の終わりから十九世紀前半
にかけての時代には、エーテル体について語ることは、
けっして非科学的なことではなかったのです。
当時の人びとは、「鉱物のなかで作用している物質と力が、
それだけで生命体 (エーテル体)へと形成されることはありえない」
と考えました。
生命体(エーテル体)の中には、
ある特別の「力」が内在しているに違いありません。
人びとは、生命体(エーテル体)に内在しているこのような
力を、「生命力」と呼びました。
たとえば当時の人びとは、
「磁力が磁石のなかに吸引力を引き起こすように、
生命力が植物や動物や人体のなかで作用し、
さまざまな生命現象を生み出す」と考えました。
それ以降の唯物論の時代になると、
このような考え方は否定されるようになりました。
人びとは、「生命体(エーテル体)は、
生命を欠いた存在(鉱物)と同じように形成される。
有機体の内部では、鉱物のなかで働いている
のと同じ力が支配している。
ただ有機体においては、
鉱物の場合よりも、
もっと複雑な方法で力が作用しているだけである。
この力が有機体の内部で、
より精密な構造をもった形成物を作り上げる」
という説を唱えるようになりました。
現在においてもなお、
唯物論に固執する人びとは、
依然として「生命力」を否定し続けています。
しかし多くの自然科学者は、
さまざまな事実から、
「生命力や生命原理のようなものを
仮定しなくてはならない」ということを学んできたのです。
このように最近の科学は、
ある意味において、
霊学が生命体に関して述べている事柄に
近づきつつあります。
それでも、科学と霊学には大きな違いがあります。
現代の科学は、
感覚的な知覚をとおして得られた事実をもとに、
悟性をもちいて思考することによって、
ある種の生命力を仮定しています。
しかしこのような考え方は、
現実に即した探求の道ではありません。
霊学は、まさに現実に即した探求を出発点とし、
その成果に基づいてさまざまな事柄を伝えようとしています。
この点において、
霊学は現代の一般的な科学とは異なっています。
この点に関しては、
ここではっきりと述べておく必要があります。
一般的な科学は、感覚的な経験をあらゆる知の基礎と見なします。
そして科学は、このような基礎の上に
築き上げることができないものについて知ることは、
不可能であると考えます。
科学は感覚的な印象から、
推論と結論を導き出します。
そして科学は、
このような範囲のかなたにある事柄に関しては拒絶の態度をとり、
「それは人間の認識の限界を越えている」
といいます。
霊学の立場から見ると、
このような科学の思考万法は、
「手で触れることができるもの」と、
「手で触れたものをもとに推論をとおして明らかになる事柄」
だけを認めようとし、
目が見える人間が語ることを
人間の認識能力の範囲外にあるものとして拒絶する、
盲人の考え方に似ています。
なぜなら霊学は、「人間は進歩する能力を備えている。
人間は新しい器官を発達させることによって、
新しい世界を獲得することができるようになる」
ということを教えてくれるからです。
色彩と光は盲人のまわりに存在していますが、
盲人は、必要な器官を備えていないので、
色彩と光を知覚することができません。
それと同じように、
人間のまわりには、たくさんの目に見えない世界が存在していて、
人間は必要な器官を形成しさえすれば、
これらの世界を知覚することができるようになる、
と霊学は説明します。
盲人が手術を受けると、
すぐに新しい世界が日の前に開かれます。
それと同様に人間は、
高次の器官を発達させることによって、
通常の感覚をとおして知覚している世界とは
まったく別の世界を認識することができるようになります。
盲人の場合には手術をして目が見えるようになるかどうかは、
その人の肉体の器官の特性によって決まります。
しかしながら、
人間がより上の世界に足を踏み入れるよりどころとなる高次の器官は、
すべての人間のなかに萌芽として存在しているのです。
私が『いかにして高次の世界の認識に到達するか』
で述べた訓練の方法を、
ほんとうに実行に移すだけの根気と
忍耐力とエネルギーを備えている人は、
誰でも、この高次の器官を発達させることができます。
ですから霊学は、
「組織上、人間の認識には限界がある」とは、
けっしていいません。
霊学は、「人間にとっては、
当人がそれを知覚するための器官をもっている世界が存在する」
といいます。
霊学は、そのときどきの限界を拡大するための手段についてのみ、語ります。
霊学は生命体ーもしくはエーテル体ーや、
あとでお話しする人間の本質を構成する高次
の要素について研究する場合、
「人間は、肉体的な感覚をよりどころとするときには、
物質体だけを研究することができる。
人間はこのような観点から出発して、
推論と結論をとおして、
より高い観点にたどりつく」ということを認めます。
しかし霊学はさらに、
「生まれつき目の見えない人が手術を受けると、
目の前に対象の色彩と光が現れる。
それと同じように、
観察者の前に、
人間の本質の高次の構成要素を示してくれるような世界の扉は、
どのようにすれば開かれるのか」
ということについて語ります。
自分自身の高次の感覚器官を発達させた人間にとっては、
エーテル体ーもしくは生命体は観察の対象であり、
悟性の活動や推論の対象となることはありません。
人間は、このエーテル体を、
植物および動物と共有しています。
物質体の素材と力は、
エーテル体の作用によって、
生長や生殖、
あるいは体液の内的な活動といった現象に作り上げられます。
ですからエーテル体は物質体の設計者であり、彫刻家です。
エーテル体は
物質体の居住者であると同時に、
建築家でもあります。
ですから私たちは、
「物質体は生命体(エーテル体)の似姿であり、現れである」
ということができます。
人間の場合、物質体とエーテル体の形と大きさは似かよっていますが、
まったく同じというわけではありません。
動物のエーテル体の形と大きさは、
物質体と大きく異なっています。
植物の場合には、
エーテル体と物質体の形と大きさの違いはさらに著しいものになります。
人間の第三の構成要素は、
感覚体またはアストラル体です。
感覚体は、苦痛や快感、あるいは衝動や欲望や情熱などの担い手です。
物質体とエーテル体だけで成り立っている存在(植物)は、
このような苦痛や快感や衝動や欲望や情熱を抱くことはありません。
私たちは、このような作用をまとめて、
「感情」と呼ぶことができます。
植物は感情をもっていません。
現在、科学者のなかには、
「ある種の植物は、外から刺激を加えると、動きなどの方
法で反応を返してくる」という事実をもとに、
「植物は一種の感情能力を備えている」
という結論を導き出そうとする人もいます。
しかし学者はこのような説を唱えることによって、
自分が感情の本質について何も知らないことを示しているのです。
ここで重要な意味をもつのは、
「その存在が、外からの刺激に対して反応を返すかどうか」
ということではなく、
「外からの刺激が、快感や苦痛や衝動や欲望といった
内面的な事象によって映し出されているかどうか」という点なのです。
この点をしっかりと押さえておかないと、
「青いリトマス試験紙は、
ある種の物質に対して感情を抱いている。
なぜならリトマス試験紙はその物質
に触れると赤くなるからである」
という説も許されることになってしまいます。
人間は感覚体(アストラル体)を、
動物とのみ共有しています。
すなわち感覚体は、
感情生活の担い手なのです。
一部の神智学のグループに属する人たちは、
「エーテル体や感覚体(アストラル体)は、
物質体のなかに存在している物質よりも、
さらに繊細な物質から成り立っている」と考えて いますが、
私たちは、このような誤りに陥らないように
注意する必要があります。
このような神智学グループの人びとは、
人間の本質の高次の構成要素を、
物質化して考えようとしています。
エーテル体とは、力の形態です。
エーテル体は活動する力から成り立ってい
エーテル体は、物質でできているわけではありません。
そしてアストラル体−または感覚体−は、
「それ自体のなかで動きと色彩にみたされながら、
光り輝くイメージ」からできている形態です。
感覚体の形態と大きさは物質体と同じではありません。
人間の感覚体は細長い卵のような形をしていて、
そのなかに物質体とエーテル体が包み込まれています。
感覚体は光のイメ−ジの形態のように、
物質体とエーテル体を越えて、あらゆる方向に広がっています。
さらに人間の本質には、第四の構成要素があります。
人間は、この第四の構成要素を、
ほかの地上の存在とは共有していません。
この構成要素は、人間の「私(自我)」の担い手です。
たとえばドイツ語でもちいられる
「私Ich」という言葉は、
ほかのどのような名称とも異なっています。
この「私」という名称について正しい方法で思考する人は、
同時に、人間の本質の認識に到るための入り口を開くことになります。
人間は皆、同じように、
「私」以外のあらゆる名称を対応する事物にあてはめることができます。
誰でも机のことを「机」 と呼び、
椅子のことを「椅子」と呼ぶことが可能です。
しかし「私」の場合だけは、
事情が異なっています。
誰も、ほかのものをいい表すために、
「私」という言葉を使うことはできません。
「私」という名称が、
私のことを表す言葉として、
外から私の耳に響いてくることはありません。
人間は自己を「私」と呼ぶことによって、
自分自身のことをいい表さなくてはなりません。
人間が自己のことを「私」と呼ぶとき、
自分自身が、すでに一つの世 界となります。
霊学に基づく宗教は、
つねにこのことを感じ取っていました。
そのため、このような宗教では、
「低次の存在の場合には、
外から、周囲の世界の現象のなかでみずからを開示する
『神』は、『私』という言葉とともに、
内面で語り始める」と教えられました。
このような能力を担っているのが「自我体」、
すなわち人間の本質の第四の構成要素です。
この「自我体」は、高次の人間の魂の担い手です。
人間は、自我体をもつことによって、
地上の被造物の頂点に立っています。
自我は、現代の人間においては
けっして単純な実体ではありません。
さまざまな進歩の段階にいる人間を相互に比較してみると、
自我の本質を認識することができます。
たとえば、適切な教育を受けることができないで自然状態
にとどまっている人間と、
平均的なヨーロッパ人に目を向けてみて下さい。
そしてさらに、
この平均的なヨーロッパ人と
、高い理想を抱いた人間を比較してみて下さい。
この三とおりの人間は、
それぞれ、自分のことを「私」と呼ぶ能力を備えています。
三人とも、「自我 体」をもっています。
しかし、適切な教育を受けないで自然状態にとどまっている人は、
自我をもちながらも、
ほとんど動物と同じように
自分の情熱や衝動や欲望に従っています。
一方より高次の進歩を遂げた人は、
ある種の自分の好みや欲求に対しては、
「おまえはそれに従ってよい」といいますが、
そのほかの好みや欲求は制御し、抑制します。
理想主義者は、根源的な好みや情熱に加えて、
高次の好みや情熱を育て上げます。
なぜそのようなことが可能になったのかというと、
その人の自我が、
人間の本質を構成するそのほかの要素
に働きかけたからです。
そうなのです、
自我の使命は、
まさに「ほかのさまざまな構成要素に働きかけて、
それらを気高いものにし、純化する」というところにあるのです。
ですから、外界によって準備された状態を越えていく人びとの場合には、
低次の構成要素は、
自我からの働きかけを受けて、
多かれ少なかれ作り変えられています。」
『霊学の観点からの子どもの教育』(Rudolf Steiner 松浦賢訳 イザラ書房 p45〜)
私たち人間は自我が光を放つことによって、
動物のレベルを脱し、
さらに高次の段階へと到ることができるのである。
思考が力をつけ
霊が生まれる。
そして感覚の暗い印象を
明るい光で充たす。
魂が生成する宇宙に
帰依しようとするとき、
感覚の体験が
思考の照明を受けて輝く。
(Rudolf Steiner 高橋 巌訳)
--------------
子どもの教育について考える場合、
一番大切なのは、
人間とはいったい何か?
人間とはいかなる構成要素から
成り立っているのかを知ることが第一である。
『霊学の観点からの子どもの教育』
(Rudolf Steiner 松浦賢訳 イザラ書房)を
今朝も繰り返し読んでいるのであるが、
何度読んでも初めて読むような感動を覚える。
シュタイナーの著作の中できわめて読みやすい本である。
今回は、人間の構成要素について、
シュタイナーがまとめている部分について引用してみたい。
人間は、いかなる構成要素から成り立っているのか、
まずこれを、深く知ることが
教育の土台となるであろう。
「人間の本質のなかには、
まず、感覚(視覚などの肉体的感覚)をもちいて
人間を観察することによってとらえられる部分があります。
唯物論的に生命をとらえようとする人は、
人間の本質のうち、この部分だけを認めようとします。
しかし霊的な研究の立場から見ると、
それは、まだ人間の本質の一部分にすぎません。
それは、人間の本質を構成する要素の一つ、
すなわち物質体なのです。
物質体は、そのほかの無機的な世界全体と同じように、
物質的な生命の法則に従っています。
物質体は、無機的な世界を構成しているのと
同じ物質と力によって作り上げられています。
ですから霊学の観点から見ると、
「人間は、物質体を鉱物の世界全体と共有している」ということができます。
鉱物の世界では、
物質は、混合 や結合や形成や分解といった法則に従って活動します。
霊学は、人間の本質のうち、
「鉱物界と同じ物質を、
鉱物界と同じ法則に従って、混合させたり、
結びつけたり、形成したり、
分解したりする部分」だけを物質体と呼びます。
さらに神智学は、このような物質体を越えて、
人間のなかに第二の本質を認めます。
この第二の本質は、生命体またはエーテル体と呼ばれています。
物理学を専門に研究している方は、
どうぞ「エーテル体」という言葉に
反発を感じないでいただきたいと思います。
ここでいう「エーテル」とは、
物理学が仮説として立てたエーテルとは
別のものを指しています。
「エーテル」は、以下に述べるような事柄を
表すための言葉ととっていただきたいのです。
少し以前から、科学の世界では、
「エーテル体」のような事柄について
語ることは、学問的な態度ではないと見なされるようになりました。
ところが十八世紀の終わりから十九世紀前半
にかけての時代には、エーテル体について語ることは、
けっして非科学的なことではなかったのです。
当時の人びとは、「鉱物のなかで作用している物質と力が、
それだけで生命体 (エーテル体)へと形成されることはありえない」
と考えました。
生命体(エーテル体)の中には、
ある特別の「力」が内在しているに違いありません。
人びとは、生命体(エーテル体)に内在しているこのような
力を、「生命力」と呼びました。
たとえば当時の人びとは、
「磁力が磁石のなかに吸引力を引き起こすように、
生命力が植物や動物や人体のなかで作用し、
さまざまな生命現象を生み出す」と考えました。
それ以降の唯物論の時代になると、
このような考え方は否定されるようになりました。
人びとは、「生命体(エーテル体)は、
生命を欠いた存在(鉱物)と同じように形成される。
有機体の内部では、鉱物のなかで働いている
のと同じ力が支配している。
ただ有機体においては、
鉱物の場合よりも、
もっと複雑な方法で力が作用しているだけである。
この力が有機体の内部で、
より精密な構造をもった形成物を作り上げる」
という説を唱えるようになりました。
現在においてもなお、
唯物論に固執する人びとは、
依然として「生命力」を否定し続けています。
しかし多くの自然科学者は、
さまざまな事実から、
「生命力や生命原理のようなものを
仮定しなくてはならない」ということを学んできたのです。
このように最近の科学は、
ある意味において、
霊学が生命体に関して述べている事柄に
近づきつつあります。
それでも、科学と霊学には大きな違いがあります。
現代の科学は、
感覚的な知覚をとおして得られた事実をもとに、
悟性をもちいて思考することによって、
ある種の生命力を仮定しています。
しかしこのような考え方は、
現実に即した探求の道ではありません。
霊学は、まさに現実に即した探求を出発点とし、
その成果に基づいてさまざまな事柄を伝えようとしています。
この点において、
霊学は現代の一般的な科学とは異なっています。
この点に関しては、
ここではっきりと述べておく必要があります。
一般的な科学は、感覚的な経験をあらゆる知の基礎と見なします。
そして科学は、このような基礎の上に
築き上げることができないものについて知ることは、
不可能であると考えます。
科学は感覚的な印象から、
推論と結論を導き出します。
そして科学は、
このような範囲のかなたにある事柄に関しては拒絶の態度をとり、
「それは人間の認識の限界を越えている」
といいます。
霊学の立場から見ると、
このような科学の思考万法は、
「手で触れることができるもの」と、
「手で触れたものをもとに推論をとおして明らかになる事柄」
だけを認めようとし、
目が見える人間が語ることを
人間の認識能力の範囲外にあるものとして拒絶する、
盲人の考え方に似ています。
なぜなら霊学は、「人間は進歩する能力を備えている。
人間は新しい器官を発達させることによって、
新しい世界を獲得することができるようになる」
ということを教えてくれるからです。
色彩と光は盲人のまわりに存在していますが、
盲人は、必要な器官を備えていないので、
色彩と光を知覚することができません。
それと同じように、
人間のまわりには、たくさんの目に見えない世界が存在していて、
人間は必要な器官を形成しさえすれば、
これらの世界を知覚することができるようになる、
と霊学は説明します。
盲人が手術を受けると、
すぐに新しい世界が日の前に開かれます。
それと同様に人間は、
高次の器官を発達させることによって、
通常の感覚をとおして知覚している世界とは
まったく別の世界を認識することができるようになります。
盲人の場合には手術をして目が見えるようになるかどうかは、
その人の肉体の器官の特性によって決まります。
しかしながら、
人間がより上の世界に足を踏み入れるよりどころとなる高次の器官は、
すべての人間のなかに萌芽として存在しているのです。
私が『いかにして高次の世界の認識に到達するか』
で述べた訓練の方法を、
ほんとうに実行に移すだけの根気と
忍耐力とエネルギーを備えている人は、
誰でも、この高次の器官を発達させることができます。
ですから霊学は、
「組織上、人間の認識には限界がある」とは、
けっしていいません。
霊学は、「人間にとっては、
当人がそれを知覚するための器官をもっている世界が存在する」
といいます。
霊学は、そのときどきの限界を拡大するための手段についてのみ、語ります。
霊学は生命体ーもしくはエーテル体ーや、
あとでお話しする人間の本質を構成する高次
の要素について研究する場合、
「人間は、肉体的な感覚をよりどころとするときには、
物質体だけを研究することができる。
人間はこのような観点から出発して、
推論と結論をとおして、
より高い観点にたどりつく」ということを認めます。
しかし霊学はさらに、
「生まれつき目の見えない人が手術を受けると、
目の前に対象の色彩と光が現れる。
それと同じように、
観察者の前に、
人間の本質の高次の構成要素を示してくれるような世界の扉は、
どのようにすれば開かれるのか」
ということについて語ります。
自分自身の高次の感覚器官を発達させた人間にとっては、
エーテル体ーもしくは生命体は観察の対象であり、
悟性の活動や推論の対象となることはありません。
人間は、このエーテル体を、
植物および動物と共有しています。
物質体の素材と力は、
エーテル体の作用によって、
生長や生殖、
あるいは体液の内的な活動といった現象に作り上げられます。
ですからエーテル体は物質体の設計者であり、彫刻家です。
エーテル体は
物質体の居住者であると同時に、
建築家でもあります。
ですから私たちは、
「物質体は生命体(エーテル体)の似姿であり、現れである」
ということができます。
人間の場合、物質体とエーテル体の形と大きさは似かよっていますが、
まったく同じというわけではありません。
動物のエーテル体の形と大きさは、
物質体と大きく異なっています。
植物の場合には、
エーテル体と物質体の形と大きさの違いはさらに著しいものになります。
人間の第三の構成要素は、
感覚体またはアストラル体です。
感覚体は、苦痛や快感、あるいは衝動や欲望や情熱などの担い手です。
物質体とエーテル体だけで成り立っている存在(植物)は、
このような苦痛や快感や衝動や欲望や情熱を抱くことはありません。
私たちは、このような作用をまとめて、
「感情」と呼ぶことができます。
植物は感情をもっていません。
現在、科学者のなかには、
「ある種の植物は、外から刺激を加えると、動きなどの方
法で反応を返してくる」という事実をもとに、
「植物は一種の感情能力を備えている」
という結論を導き出そうとする人もいます。
しかし学者はこのような説を唱えることによって、
自分が感情の本質について何も知らないことを示しているのです。
ここで重要な意味をもつのは、
「その存在が、外からの刺激に対して反応を返すかどうか」
ということではなく、
「外からの刺激が、快感や苦痛や衝動や欲望といった
内面的な事象によって映し出されているかどうか」という点なのです。
この点をしっかりと押さえておかないと、
「青いリトマス試験紙は、
ある種の物質に対して感情を抱いている。
なぜならリトマス試験紙はその物質
に触れると赤くなるからである」
という説も許されることになってしまいます。
人間は感覚体(アストラル体)を、
動物とのみ共有しています。
すなわち感覚体は、
感情生活の担い手なのです。
一部の神智学のグループに属する人たちは、
「エーテル体や感覚体(アストラル体)は、
物質体のなかに存在している物質よりも、
さらに繊細な物質から成り立っている」と考えて いますが、
私たちは、このような誤りに陥らないように
注意する必要があります。
このような神智学グループの人びとは、
人間の本質の高次の構成要素を、
物質化して考えようとしています。
エーテル体とは、力の形態です。
エーテル体は活動する力から成り立ってい
エーテル体は、物質でできているわけではありません。
そしてアストラル体−または感覚体−は、
「それ自体のなかで動きと色彩にみたされながら、
光り輝くイメージ」からできている形態です。
感覚体の形態と大きさは物質体と同じではありません。
人間の感覚体は細長い卵のような形をしていて、
そのなかに物質体とエーテル体が包み込まれています。
感覚体は光のイメ−ジの形態のように、
物質体とエーテル体を越えて、あらゆる方向に広がっています。
さらに人間の本質には、第四の構成要素があります。
人間は、この第四の構成要素を、
ほかの地上の存在とは共有していません。
この構成要素は、人間の「私(自我)」の担い手です。
たとえばドイツ語でもちいられる
「私Ich」という言葉は、
ほかのどのような名称とも異なっています。
この「私」という名称について正しい方法で思考する人は、
同時に、人間の本質の認識に到るための入り口を開くことになります。
人間は皆、同じように、
「私」以外のあらゆる名称を対応する事物にあてはめることができます。
誰でも机のことを「机」 と呼び、
椅子のことを「椅子」と呼ぶことが可能です。
しかし「私」の場合だけは、
事情が異なっています。
誰も、ほかのものをいい表すために、
「私」という言葉を使うことはできません。
「私」という名称が、
私のことを表す言葉として、
外から私の耳に響いてくることはありません。
人間は自己を「私」と呼ぶことによって、
自分自身のことをいい表さなくてはなりません。
人間が自己のことを「私」と呼ぶとき、
自分自身が、すでに一つの世 界となります。
霊学に基づく宗教は、
つねにこのことを感じ取っていました。
そのため、このような宗教では、
「低次の存在の場合には、
外から、周囲の世界の現象のなかでみずからを開示する
『神』は、『私』という言葉とともに、
内面で語り始める」と教えられました。
このような能力を担っているのが「自我体」、
すなわち人間の本質の第四の構成要素です。
この「自我体」は、高次の人間の魂の担い手です。
人間は、自我体をもつことによって、
地上の被造物の頂点に立っています。
自我は、現代の人間においては
けっして単純な実体ではありません。
さまざまな進歩の段階にいる人間を相互に比較してみると、
自我の本質を認識することができます。
たとえば、適切な教育を受けることができないで自然状態
にとどまっている人間と、
平均的なヨーロッパ人に目を向けてみて下さい。
そしてさらに、
この平均的なヨーロッパ人と
、高い理想を抱いた人間を比較してみて下さい。
この三とおりの人間は、
それぞれ、自分のことを「私」と呼ぶ能力を備えています。
三人とも、「自我 体」をもっています。
しかし、適切な教育を受けないで自然状態にとどまっている人は、
自我をもちながらも、
ほとんど動物と同じように
自分の情熱や衝動や欲望に従っています。
一方より高次の進歩を遂げた人は、
ある種の自分の好みや欲求に対しては、
「おまえはそれに従ってよい」といいますが、
そのほかの好みや欲求は制御し、抑制します。
理想主義者は、根源的な好みや情熱に加えて、
高次の好みや情熱を育て上げます。
なぜそのようなことが可能になったのかというと、
その人の自我が、
人間の本質を構成するそのほかの要素
に働きかけたからです。
そうなのです、
自我の使命は、
まさに「ほかのさまざまな構成要素に働きかけて、
それらを気高いものにし、純化する」というところにあるのです。
ですから、外界によって準備された状態を越えていく人びとの場合には、
低次の構成要素は、
自我からの働きかけを受けて、
多かれ少なかれ作り変えられています。」
『霊学の観点からの子どもの教育』(Rudolf Steiner 松浦賢訳 イザラ書房 p45〜)
私たち人間は自我が光を放つことによって、
動物のレベルを脱し、
さらに高次の段階へと到ることができるのである。
|
|
|
|
コメント(5)
>誰も、ほかのものをいい表すために、
>「私」という言葉を使うことはできません。
>「私」という名称が、
>私のことを表す言葉として、
>外から私の耳に響いてくることはありません。
上記の点、日本ではたまに、大人が幼い少年に向かって
「ぼく!」と呼びかけることがありますね。
単に「坊や」という意味の代わりなのでしょうが、
子供の側からすると、本来自分しか使えないはずの言葉が
他人から響いてくるわけですね。
子どものほうも単に「坊や」という意味で受け取っているのか…
これは必ず大人から子供に呼びかける場合だけで、子供同士では使いません。
しばしば主客が一体になる日本語特有の表現だと思いますが、
どこか、大人が子供の自我の一部を自分のものにしているような気もして、
以前からなんだか気になっていました。
>「私」という言葉を使うことはできません。
>「私」という名称が、
>私のことを表す言葉として、
>外から私の耳に響いてくることはありません。
上記の点、日本ではたまに、大人が幼い少年に向かって
「ぼく!」と呼びかけることがありますね。
単に「坊や」という意味の代わりなのでしょうが、
子供の側からすると、本来自分しか使えないはずの言葉が
他人から響いてくるわけですね。
子どものほうも単に「坊や」という意味で受け取っているのか…
これは必ず大人から子供に呼びかける場合だけで、子供同士では使いません。
しばしば主客が一体になる日本語特有の表現だと思いますが、
どこか、大人が子供の自我の一部を自分のものにしているような気もして、
以前からなんだか気になっていました。
ヒルフェ*ゾフィーさん
コメントありがとうございます。
ふと思ったのですが、
シュタイナーによるとアトランティス時代には、
人間が自分を個人と感じることは、
まったくなかったとのことです。
壮大なる宇宙の歴史においても
人間は個人であるという意識は、
実際、徐々に形成されていったように、
人間個人の成長においても同様なのでしょうね。
ちょうどアトランティス時代の中に
生きている子供たちに
大人が「ぼく」という言葉を
ちょうど宇宙からの響きのように語りかけているのでは
ないのでしょうか。
そう思うと、この語りかけは、
宇宙からの響きのようで、
とてもやさしい語りかけのように思いました。
ありがとうございました。
コメントありがとうございます。
ふと思ったのですが、
シュタイナーによるとアトランティス時代には、
人間が自分を個人と感じることは、
まったくなかったとのことです。
壮大なる宇宙の歴史においても
人間は個人であるという意識は、
実際、徐々に形成されていったように、
人間個人の成長においても同様なのでしょうね。
ちょうどアトランティス時代の中に
生きている子供たちに
大人が「ぼく」という言葉を
ちょうど宇宙からの響きのように語りかけているのでは
ないのでしょうか。
そう思うと、この語りかけは、
宇宙からの響きのようで、
とてもやさしい語りかけのように思いました。
ありがとうございました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
シュタイナー的生活を楽しむ 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
シュタイナー的生活を楽しむのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77425人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209463人
- 3位
- 空を見上げるのが好き
- 139117人
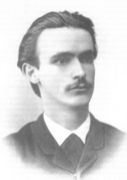











![[dir]メンヘル系コミュ総合](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/64/3/66403_123s.gif)











