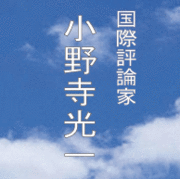北海道5区補選訴状
提訴期限は本日まで
onoderakouichi@●yahoo.co.jp(●はとって間をつめてメールください)
までメール願います。
本日(5月24日)深夜12時前までに札幌高裁に行って提出する必要がある。
ただ、すでに提出済みのメンバーがいるので、それに参加したい方は
A4の紙に
衆議院議員北海道5区補欠選挙
選挙無効訴訟事件
<原告別紙>と書いて
名前(フルネーム) ハンコ(三文判)
住所
電話番号
を記載して提出すれば
原告に加わることができる。
北海道5区が厳密に言えば原告の資格があるが、
北海道5区以外で北海道民の人も
原告に加われるように書いたので
北海道民の人は参加願いたい。
(原告適格とは、定義上ではその選挙がきちんとなされなければ不利益をこうむる人たちの
ことを言うから、厳密に言えば北海道5区の選挙民だが、この選挙がきちんとなされないことによって
北海道民は、農業に大打撃を与えるTPPに賛成であるというような政治的判断をされたことで非常に不利益をこうむっている。
だから北海道民は北海道5区以外の選挙民も原告として適格であると主張する)
もともとこの原告適格を厳密に線引きするかどうかは憲法上の争いがあるから
参加してかまわない。ただし札幌高裁だから北海道民だけにしたほうがよいと判断した。
(ただし判決の最後で原告適格でないと判決されるおそれはあるがいずれにしても判決の最後の方なので参加は
できる)
詳しくは
onoderakouichi@●yahoo.co.jp(●はとって間をつめてメールください)
まで
これは民衆訴訟といって個人の利得ではなく行政機関の適正化を図るための訴訟であるため
訴訟費用が一人分ですむ可能性がある。(そう主張すれば裁判官がそれを認めることがあるという意味)
とりあえず、本日時点では、追加原告に名前を書いて、札幌高裁に提出すればよい。
ハンコがなかったりしてもとにかく名前だけ出せばよい。
収 入
印 紙
訴 状
平成 28年 5月 22 日
札幌高等裁判所 御中
原告
他別紙記載
被告 北海道選挙管理委員会
委員長 高 橋 一 史
〒060-858 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁4階
電話: 011-204-5153(直通) FAX: 011-232-1126
平成28年4月24日投開票の北海道5区衆議院議員補欠選挙
選挙無効請求事件
これは民衆訴訟であり、個人的利得を求める訴訟ではなく、行政機関(選管)の適正な
執行を求める種類のものである。
訴訟物価額については算定不能。したがって160万円と算定される。
この場合の訴訟手数料は、13000円である。
民衆訴訟であるため、原告が複数であっても13000円と解される。
<原告適格について>
北海道5区の選挙民であることが狭い意味での原告適格に該当するが
この選挙は、北海道5区以外の選挙民であっても、
その選挙が適正に行われなかった結果、
「TPPという、北海道民の農業に致命的な打撃を与える
と言われる条約に道民は賛成をしめした」
と報道をされており、また政治的にも中央政界は
「道民はTPPに賛成だ」
と受け取ったと報道されている。
そのため、ひどい悪影響を北海道5区以外の
北海道民に及ぼしているものである。
また、今回の適正に執行されていない選挙を
そのまま放置すれば、参院選および衆院選のダブル選挙
という、日本の行く末を決める選挙においても、
不正が可能な電子選挙過程
(バーコード集計システムおよび共通投票所をオンラインで結ぶ電子選挙体制)をノーチェックで許可することと同じことになるため、この選挙の原告適格は、「この選挙結果によって不利益をこうむるもの」という定義からすれば、北海道5区以外の北海道民も原告適格を有すると解される。これが認められなければ、北海道民はこの補欠選挙で「TPP賛成」であるとみなされて、多大な不利益をこうむっているにもかかわらず、裁判を受けられないこととなり、憲法第32条の裁判を受ける権利に反するものと解される。
第1 請求の趣旨
主位的請求
平成28年4月24日投開票の北海道5区衆議院議員補欠選挙の 選挙の効力に関し、被告の決定を無効とする
予備的請求
「この選挙は憲法違反である」との宣言を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
平成28年4月24日投開票の北海道5区衆議院議員補欠選挙について
第一位を和田よしあき氏当選にして、第二位の池田まき氏を落選にしているが、その選挙過程に不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している.
北海道選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。
選挙区名 確
定 1 2
和田 よしあき 池田 まき
(自由民主党) (本人)
札幌市厚別区 * 29,292 33,434
江別市 * 28,661 29,687
千歳市 * 25,591 14,439
恵庭市 * 19,447 13,062
北広島市 * 13,419 15,200
石狩市 * 13,103 13,133
市区計 * 129,513 118,955
当別町 * 5,023 3,902
新篠津村 * 1,306 660
石狩振興局 計 * 6,329 4,562
北海道第5区 * 135,842 123,517
つまり北海道5区全体の票数では
第一位和田氏13万5842票、
第二位池田まき氏12万3517票である。
その差異は
135,842票(和田)−123,517票(池田)=1万2325票である。
しかしながらこの差1万2325票は、不明な選挙過程(実数が確認されていない電子選挙過程)が存在しているため、当選順位が異動のおそれがあるものである。
具体的には千歳市選管と恵庭市選管において、それぞれ500票バーコード票(千歳市選管)と200票バーコード票(恵庭市選管)が、実数とあっているのかまったくチェックがなされていないことが判明した。(開票の手引きおよび電話での確認による)
千歳市選管の票は、和田氏25591票、池田まき氏14439票である。
これはそれぞれ500票束では、端数(500票未満)を除くと
和田氏25500票(=500票束×51個)
池田まき氏14000票(=500票束×28個)となる。
合計で、25500票(和田)プラス14000票(池田まき)=39500票となる。
つまり千歳市選管では、2者合計で39500票(=500票束×79個)が
バーコード票によってPC集計されているが、実数と合致しているか確認がなされていないものである。
<恵庭市選管>
また、恵庭市選管では、和田19447票 池田13062票である。
恵庭市では200票ごとにバーコード票をつけている。
これは200票束では、和田19400票(=200票束×97個)
池田13000票(=200票束×65個)である。
2者合計値は19400票プラス13000票の32400票である。
したがってバーコード票でPC集計されているが実数と合致しているか
確認されていない不明票は、千歳市選管で39500票、恵庭市選管では32400票なので合計71900票がきちんとバーコード票と実数が確認されていない票である。
この票が、すべて第二位の和田票だったとして計算する。すると第一位と第二位の差異は
71900票(不明票のため第二位に加算しうる票)−12325票(選挙結果の差異)>0なので、当選順位は入れ替わるおそれがある。
第一位と第二位は票数によって入れ替わると思われる。
具体的に言えば、選挙管理委員会は、千歳市管と恵庭市選管において
バーコード票によって電子化されたデータがPC集計システムを通じて
でてきた電子データと実数と一致しているかを
チェックしていないまま選挙結果を確定しているのである。
千歳市選挙管理委員会は、5百票ごとに、バーコード票をつける。
一方、恵庭市選挙管理委員会では、2百票ごとにバーコード票をつけて
集計をしている。
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているのでここの部分では問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束(千歳市選管)、200票の束
(恵庭市選管)にしたときに、PCから出力された「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って
「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われた。また刑事事件となっているが
大阪府の堺市の選挙管理委員が選挙メーカーと共同で、選挙システムを設計開発しており、そのシステムを全国の選挙管理委員会に納入していることがわかっている。
米国では「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。また、入り込んだ場合は、きちんとPC集計の結果と実数が合致しているのかどうか人間の目でチェックする必要がある。
<日本における電子投票過程の歴史>
当初、「電子投票機」という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入されなくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしいと指摘したために発覚したが、選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員はヒアリングにおいて「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ次期選挙で、ダブル選挙や「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落としている。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、候補者を
振り替えている(誤作動を起こしている)プログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
最初はまともに作動していると思われるが、途中から加速的に誤作動か作為的な
振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際の開票の手引きを見るとわかるが、恵庭市選管については
バーコード票にまとめる200票の中に混入票があるかないかをチェックしており
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
まったくノーチェックなのである。
また千歳市選管については、一見チェックしているように
見えても、それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(例 和田氏が500票束が何個あるのか、池田まき氏の500票束が何個あるのか)とPC出力後の票数(和田氏の500票束が何個あるとPC集計されたのか
池田まき氏の500票束が何個あるとPC集計されたのか)は
「そこまではチェックしていない」ということを選管職員も言っていた。
しかるに、札幌市厚別区の「開票の手引き」を見ると、このバーコード票で
読み込んだ票数と、実際の票数が過去に違った例があったので
きちんとチェックするようにと指示が徹底されている。
つまり必要なことを札幌市厚別区選管などはきちんとやっているとおもわれるが、その一方で千歳市選管と恵庭市選管はやっていないのである。
また、千歳市の例で言えば、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからないはずである。つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしている。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
札幌市厚別区ではきちんとバーコード票のデータも実数と同じかどうかをチェックするように指示をしているが、千歳市選管と恵庭市選管はそれをやっていない。
そのためその確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選挙への信頼」を著しく毀損するものである。
甲1号証「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が
「電子投票機」から「バーコード」「スキャナー」などに変化していきどんどん
小型化していったが、常にこの「実際の票」を何らかの形で電子データに変換す
ることでPCソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それを再チェックできた
ところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
過去に存在した国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたものではない。
しかも北海道5区の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて和田氏の200票〜500票の
束がいくつあるのか、また、池田まき氏の200票〜500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけだから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「B候補の500票だ」と認識をする。それを「A候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来B候補の500票が、
A候補の500票であるとされていく。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずにその500票束を机に積み上げる。そして和田氏の500票束が何束あるのか
池田まき氏の500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数が確認できるはずである。
そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
大阪府の堺市選挙管理委員会のように選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして最高裁まで係争となっていること。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わって行っていたことで選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。この選管職員が選挙メーカーと共同して作ったシステムは全国の有数の自治体に納入されているという。)
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「北海道の選挙管理委員会はなんでそんな簡単なことも確認しないで選挙の結果を確定させるんだろう。こんなに大事なことなのに。」と素朴に疑問に思うはずである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。
そのため計算をすると、当否がいれかわるおそれがある。
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転する畏れがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
会長が非常に安倍政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。この堺市の刑事告発された選管職員が選挙メーカーと設計した選挙システムは
他の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)
提訴期限は本日まで
onoderakouichi@●yahoo.co.jp(●はとって間をつめてメールください)
までメール願います。
本日(5月24日)深夜12時前までに札幌高裁に行って提出する必要がある。
ただ、すでに提出済みのメンバーがいるので、それに参加したい方は
A4の紙に
衆議院議員北海道5区補欠選挙
選挙無効訴訟事件
<原告別紙>と書いて
名前(フルネーム) ハンコ(三文判)
住所
電話番号
を記載して提出すれば
原告に加わることができる。
北海道5区が厳密に言えば原告の資格があるが、
北海道5区以外で北海道民の人も
原告に加われるように書いたので
北海道民の人は参加願いたい。
(原告適格とは、定義上ではその選挙がきちんとなされなければ不利益をこうむる人たちの
ことを言うから、厳密に言えば北海道5区の選挙民だが、この選挙がきちんとなされないことによって
北海道民は、農業に大打撃を与えるTPPに賛成であるというような政治的判断をされたことで非常に不利益をこうむっている。
だから北海道民は北海道5区以外の選挙民も原告として適格であると主張する)
もともとこの原告適格を厳密に線引きするかどうかは憲法上の争いがあるから
参加してかまわない。ただし札幌高裁だから北海道民だけにしたほうがよいと判断した。
(ただし判決の最後で原告適格でないと判決されるおそれはあるがいずれにしても判決の最後の方なので参加は
できる)
詳しくは
onoderakouichi@●yahoo.co.jp(●はとって間をつめてメールください)
まで
これは民衆訴訟といって個人の利得ではなく行政機関の適正化を図るための訴訟であるため
訴訟費用が一人分ですむ可能性がある。(そう主張すれば裁判官がそれを認めることがあるという意味)
とりあえず、本日時点では、追加原告に名前を書いて、札幌高裁に提出すればよい。
ハンコがなかったりしてもとにかく名前だけ出せばよい。
収 入
印 紙
訴 状
平成 28年 5月 22 日
札幌高等裁判所 御中
原告
他別紙記載
被告 北海道選挙管理委員会
委員長 高 橋 一 史
〒060-858 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁4階
電話: 011-204-5153(直通) FAX: 011-232-1126
平成28年4月24日投開票の北海道5区衆議院議員補欠選挙
選挙無効請求事件
これは民衆訴訟であり、個人的利得を求める訴訟ではなく、行政機関(選管)の適正な
執行を求める種類のものである。
訴訟物価額については算定不能。したがって160万円と算定される。
この場合の訴訟手数料は、13000円である。
民衆訴訟であるため、原告が複数であっても13000円と解される。
<原告適格について>
北海道5区の選挙民であることが狭い意味での原告適格に該当するが
この選挙は、北海道5区以外の選挙民であっても、
その選挙が適正に行われなかった結果、
「TPPという、北海道民の農業に致命的な打撃を与える
と言われる条約に道民は賛成をしめした」
と報道をされており、また政治的にも中央政界は
「道民はTPPに賛成だ」
と受け取ったと報道されている。
そのため、ひどい悪影響を北海道5区以外の
北海道民に及ぼしているものである。
また、今回の適正に執行されていない選挙を
そのまま放置すれば、参院選および衆院選のダブル選挙
という、日本の行く末を決める選挙においても、
不正が可能な電子選挙過程
(バーコード集計システムおよび共通投票所をオンラインで結ぶ電子選挙体制)をノーチェックで許可することと同じことになるため、この選挙の原告適格は、「この選挙結果によって不利益をこうむるもの」という定義からすれば、北海道5区以外の北海道民も原告適格を有すると解される。これが認められなければ、北海道民はこの補欠選挙で「TPP賛成」であるとみなされて、多大な不利益をこうむっているにもかかわらず、裁判を受けられないこととなり、憲法第32条の裁判を受ける権利に反するものと解される。
第1 請求の趣旨
主位的請求
平成28年4月24日投開票の北海道5区衆議院議員補欠選挙の 選挙の効力に関し、被告の決定を無効とする
予備的請求
「この選挙は憲法違反である」との宣言を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
平成28年4月24日投開票の北海道5区衆議院議員補欠選挙について
第一位を和田よしあき氏当選にして、第二位の池田まき氏を落選にしているが、その選挙過程に不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している.
北海道選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。
選挙区名 確
定 1 2
和田 よしあき 池田 まき
(自由民主党) (本人)
札幌市厚別区 * 29,292 33,434
江別市 * 28,661 29,687
千歳市 * 25,591 14,439
恵庭市 * 19,447 13,062
北広島市 * 13,419 15,200
石狩市 * 13,103 13,133
市区計 * 129,513 118,955
当別町 * 5,023 3,902
新篠津村 * 1,306 660
石狩振興局 計 * 6,329 4,562
北海道第5区 * 135,842 123,517
つまり北海道5区全体の票数では
第一位和田氏13万5842票、
第二位池田まき氏12万3517票である。
その差異は
135,842票(和田)−123,517票(池田)=1万2325票である。
しかしながらこの差1万2325票は、不明な選挙過程(実数が確認されていない電子選挙過程)が存在しているため、当選順位が異動のおそれがあるものである。
具体的には千歳市選管と恵庭市選管において、それぞれ500票バーコード票(千歳市選管)と200票バーコード票(恵庭市選管)が、実数とあっているのかまったくチェックがなされていないことが判明した。(開票の手引きおよび電話での確認による)
千歳市選管の票は、和田氏25591票、池田まき氏14439票である。
これはそれぞれ500票束では、端数(500票未満)を除くと
和田氏25500票(=500票束×51個)
池田まき氏14000票(=500票束×28個)となる。
合計で、25500票(和田)プラス14000票(池田まき)=39500票となる。
つまり千歳市選管では、2者合計で39500票(=500票束×79個)が
バーコード票によってPC集計されているが、実数と合致しているか確認がなされていないものである。
<恵庭市選管>
また、恵庭市選管では、和田19447票 池田13062票である。
恵庭市では200票ごとにバーコード票をつけている。
これは200票束では、和田19400票(=200票束×97個)
池田13000票(=200票束×65個)である。
2者合計値は19400票プラス13000票の32400票である。
したがってバーコード票でPC集計されているが実数と合致しているか
確認されていない不明票は、千歳市選管で39500票、恵庭市選管では32400票なので合計71900票がきちんとバーコード票と実数が確認されていない票である。
この票が、すべて第二位の和田票だったとして計算する。すると第一位と第二位の差異は
71900票(不明票のため第二位に加算しうる票)−12325票(選挙結果の差異)>0なので、当選順位は入れ替わるおそれがある。
第一位と第二位は票数によって入れ替わると思われる。
具体的に言えば、選挙管理委員会は、千歳市管と恵庭市選管において
バーコード票によって電子化されたデータがPC集計システムを通じて
でてきた電子データと実数と一致しているかを
チェックしていないまま選挙結果を確定しているのである。
千歳市選挙管理委員会は、5百票ごとに、バーコード票をつける。
一方、恵庭市選挙管理委員会では、2百票ごとにバーコード票をつけて
集計をしている。
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているのでここの部分では問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束(千歳市選管)、200票の束
(恵庭市選管)にしたときに、PCから出力された「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って
「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われた。また刑事事件となっているが
大阪府の堺市の選挙管理委員が選挙メーカーと共同で、選挙システムを設計開発しており、そのシステムを全国の選挙管理委員会に納入していることがわかっている。
米国では「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。また、入り込んだ場合は、きちんとPC集計の結果と実数が合致しているのかどうか人間の目でチェックする必要がある。
<日本における電子投票過程の歴史>
当初、「電子投票機」という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入されなくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしいと指摘したために発覚したが、選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員はヒアリングにおいて「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ次期選挙で、ダブル選挙や「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落としている。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、候補者を
振り替えている(誤作動を起こしている)プログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
最初はまともに作動していると思われるが、途中から加速的に誤作動か作為的な
振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際の開票の手引きを見るとわかるが、恵庭市選管については
バーコード票にまとめる200票の中に混入票があるかないかをチェックしており
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
まったくノーチェックなのである。
また千歳市選管については、一見チェックしているように
見えても、それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(例 和田氏が500票束が何個あるのか、池田まき氏の500票束が何個あるのか)とPC出力後の票数(和田氏の500票束が何個あるとPC集計されたのか
池田まき氏の500票束が何個あるとPC集計されたのか)は
「そこまではチェックしていない」ということを選管職員も言っていた。
しかるに、札幌市厚別区の「開票の手引き」を見ると、このバーコード票で
読み込んだ票数と、実際の票数が過去に違った例があったので
きちんとチェックするようにと指示が徹底されている。
つまり必要なことを札幌市厚別区選管などはきちんとやっているとおもわれるが、その一方で千歳市選管と恵庭市選管はやっていないのである。
また、千歳市の例で言えば、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからないはずである。つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしている。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
札幌市厚別区ではきちんとバーコード票のデータも実数と同じかどうかをチェックするように指示をしているが、千歳市選管と恵庭市選管はそれをやっていない。
そのためその確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選挙への信頼」を著しく毀損するものである。
甲1号証「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が
「電子投票機」から「バーコード」「スキャナー」などに変化していきどんどん
小型化していったが、常にこの「実際の票」を何らかの形で電子データに変換す
ることでPCソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それを再チェックできた
ところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
過去に存在した国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたものではない。
しかも北海道5区の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて和田氏の200票〜500票の
束がいくつあるのか、また、池田まき氏の200票〜500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけだから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「B候補の500票だ」と認識をする。それを「A候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来B候補の500票が、
A候補の500票であるとされていく。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずにその500票束を机に積み上げる。そして和田氏の500票束が何束あるのか
池田まき氏の500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数が確認できるはずである。
そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
大阪府の堺市選挙管理委員会のように選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして最高裁まで係争となっていること。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わって行っていたことで選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。この選管職員が選挙メーカーと共同して作ったシステムは全国の有数の自治体に納入されているという。)
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「北海道の選挙管理委員会はなんでそんな簡単なことも確認しないで選挙の結果を確定させるんだろう。こんなに大事なことなのに。」と素朴に疑問に思うはずである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。
そのため計算をすると、当否がいれかわるおそれがある。
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転する畏れがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
会長が非常に安倍政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。この堺市の刑事告発された選管職員が選挙メーカーと設計した選挙システムは
他の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)
|
|
|
|
|
|
|
|
国際評論家 小野寺光一 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
国際評論家 小野寺光一のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 89999人
- 3位
- 酒好き
- 170649人