選挙の時にいつも思う。
マスコミは「一票の重み」というスローガンを推進するくせに、選挙報道で時に1%程度の開票時点で当確を発表する。
残りの99%がいかに軽く扱われていることか。
いや、実際統計学的には一票など限りなく無に近い存在なのだ。
マスコミは無意識にも率先してそのことを示しているのである。
だから、私は自分の貴重な時間を使って選挙なんか行く気がしない。
分母が天文学的数字の確率で私の一票が勝敗を分けることは承知しているが、仮にそうなっても私は後悔はしない。
---------------------------------------------------
【問題】
この意見に論理的に反論してみてください。
【条件】
1)ここで言う選挙は国政選挙とし、その目的は国家(国民)の利益または選挙権者個人の利益とする。
2)民主主義(成人国民皆選挙権制度)が無条件に正しいということ、及びそれを直接帰納できるような事象を前提としてはいけない。
3)2)以外の一般常識を前提としてよい。常識が人によって違うと思う場合は回答者の常識を前提としてよい。
4)この意見は個人的な意見であり、彼が選挙に行かなかったとしても他の選挙権者に知られることはなく、この意見が集団的行動原理にまで帰納されるという可能性は考慮しない。また、集団の論理を無条件に個人の論理に適応してはいけない。
【トピックの方針】
1)トピ主は興味深いと思ったコメントにのみ返信します。また、トピ主は模範解答を特に用意していませんし、必ずしも結論をまとめるつもりもありません。不誠実かも知れませんが、それでもよろしければご参加ください。
2)参加者同士が議論することは全く問題ありませんが、次の場合にはトピ主が介入、指導、注意させていただくことがありますので指示に従ってください。
? 著しく礼節を欠く言葉づかいのコメント
? 議論がかみ合っていない場合
? 論理に欠陥があるのに気付かずに(認めずに)議論を続ける場合
? トピの内容とかけ離れたコメント
3)論理的に反論することはできない、という回答も当然ながらありです。できれば、理由を述べていただければなお嬉しいです。
4)問題提起に不適切な部分があることが判明した場合には途中修正することがあります。
マスコミは「一票の重み」というスローガンを推進するくせに、選挙報道で時に1%程度の開票時点で当確を発表する。
残りの99%がいかに軽く扱われていることか。
いや、実際統計学的には一票など限りなく無に近い存在なのだ。
マスコミは無意識にも率先してそのことを示しているのである。
だから、私は自分の貴重な時間を使って選挙なんか行く気がしない。
分母が天文学的数字の確率で私の一票が勝敗を分けることは承知しているが、仮にそうなっても私は後悔はしない。
---------------------------------------------------
【問題】
この意見に論理的に反論してみてください。
【条件】
1)ここで言う選挙は国政選挙とし、その目的は国家(国民)の利益または選挙権者個人の利益とする。
2)民主主義(成人国民皆選挙権制度)が無条件に正しいということ、及びそれを直接帰納できるような事象を前提としてはいけない。
3)2)以外の一般常識を前提としてよい。常識が人によって違うと思う場合は回答者の常識を前提としてよい。
4)この意見は個人的な意見であり、彼が選挙に行かなかったとしても他の選挙権者に知られることはなく、この意見が集団的行動原理にまで帰納されるという可能性は考慮しない。また、集団の論理を無条件に個人の論理に適応してはいけない。
【トピックの方針】
1)トピ主は興味深いと思ったコメントにのみ返信します。また、トピ主は模範解答を特に用意していませんし、必ずしも結論をまとめるつもりもありません。不誠実かも知れませんが、それでもよろしければご参加ください。
2)参加者同士が議論することは全く問題ありませんが、次の場合にはトピ主が介入、指導、注意させていただくことがありますので指示に従ってください。
? 著しく礼節を欠く言葉づかいのコメント
? 議論がかみ合っていない場合
? 論理に欠陥があるのに気付かずに(認めずに)議論を続ける場合
? トピの内容とかけ離れたコメント
3)論理的に反論することはできない、という回答も当然ながらありです。できれば、理由を述べていただければなお嬉しいです。
4)問題提起に不適切な部分があることが判明した場合には途中修正することがあります。
|
|
|
|
コメント(79)
>>[42]
なるほど、独在・独我論との関連ですね。
私も、意識して問題提起した訳ではありませんが、途中で似た議論になり得ると感じました。
しかし、それとの違いは、あくまで「個人にとって」の論理は集団の論理と異なることを前提としている点です。
つまり、個の論理を集団の論理に帰納するつもりも、集団の論理から個の論理を演繹するつもりもなく、それらを統合することも求めず、個の論理のみを考えてみたいという試みです。
そして、「個人にとって」の20分が無視できないことは他人と比べて特別なこととは思っておらず、単に他人のことは考察の範囲に入れないだけであり、個の論理の説明に非物理成分を必要とするとは全く思っていないということです。
たぶん、独在論者の方もこんな話と一緒にされちゃあ困ると思っておられると思いますよ。
なるほど、独在・独我論との関連ですね。
私も、意識して問題提起した訳ではありませんが、途中で似た議論になり得ると感じました。
しかし、それとの違いは、あくまで「個人にとって」の論理は集団の論理と異なることを前提としている点です。
つまり、個の論理を集団の論理に帰納するつもりも、集団の論理から個の論理を演繹するつもりもなく、それらを統合することも求めず、個の論理のみを考えてみたいという試みです。
そして、「個人にとって」の20分が無視できないことは他人と比べて特別なこととは思っておらず、単に他人のことは考察の範囲に入れないだけであり、個の論理の説明に非物理成分を必要とするとは全く思っていないということです。
たぶん、独在論者の方もこんな話と一緒にされちゃあ困ると思っておられると思いますよ。
>>[48]
なるほど、このトピと似た問題提起でゲーム理論を考えている人ってるのですね。
> 個の論理を考えるとき、自分の行動が環境を変更できる度合いは「非常に小さい」ので0に近似できる。なので「自分がどのように行動しようが環境は不変」と仮定すれば、
これは投票に対する私の疑義であって、このトピの前提ではありません。
ですから、0に近似することが論理的に妥当かどうかを問うこともこのトピの趣旨であって、この意見者(または私)がなるほどそうではないのかと納得させられる立論があればそれも歓迎だった訳です。
> 「個の論理を集団の論理に帰納するつもりも、集団の論理から個の論理を演繹するつもりもなく、それらを統合することも求めず、個の論理のみを考え」るということはプレーヤーは自分だけで他の人間の行動は与えられた条件であって自分は影響を与えられない、ということですから
これは少し違うと思います。
「」内、は自分の行動が集団(ここでは選挙結果、引いては国政)に影響を与えないことを必ずしも意味していないつもりです。
ここで言っているのは、たとえば、個のレベルでの「投票棄権を妥当とする論理」が立論できたとしても、日本国レベルでの「民主的選挙システム崩壊の論理」に帰納できないというような意味合いです。
なるほど、このトピと似た問題提起でゲーム理論を考えている人ってるのですね。
> 個の論理を考えるとき、自分の行動が環境を変更できる度合いは「非常に小さい」ので0に近似できる。なので「自分がどのように行動しようが環境は不変」と仮定すれば、
これは投票に対する私の疑義であって、このトピの前提ではありません。
ですから、0に近似することが論理的に妥当かどうかを問うこともこのトピの趣旨であって、この意見者(または私)がなるほどそうではないのかと納得させられる立論があればそれも歓迎だった訳です。
> 「個の論理を集団の論理に帰納するつもりも、集団の論理から個の論理を演繹するつもりもなく、それらを統合することも求めず、個の論理のみを考え」るということはプレーヤーは自分だけで他の人間の行動は与えられた条件であって自分は影響を与えられない、ということですから
これは少し違うと思います。
「」内、は自分の行動が集団(ここでは選挙結果、引いては国政)に影響を与えないことを必ずしも意味していないつもりです。
ここで言っているのは、たとえば、個のレベルでの「投票棄権を妥当とする論理」が立論できたとしても、日本国レベルでの「民主的選挙システム崩壊の論理」に帰納できないというような意味合いです。
>>[53]
了解しました。
以下、反論ではありませんが関連して思うところを少し書いておきます。
1)選挙に行かないことと白票を投じることは異なるという意見はがあることは私も承知していますが、いずれにせよ一票の効果が0に近似できる(個の論理)とすれば、その意見は観念論に過ぎずこの意見者を説得するには及ばないように思います。
2)「政治に参加しない自由」が民主主義で認められているかどうかは微妙ですね。選挙に行かないと罰則がある民主主義国もありますし、日本国でも罰則こそありませんが選挙に行かないことは恥ずかしい行為であるという「常識」は浸透していますからね。
そして、このトピの意見者の場合は(政治)思想的判断と言うよりは一票の価値(効果)に関する数理的判断なのです。
了解しました。
以下、反論ではありませんが関連して思うところを少し書いておきます。
1)選挙に行かないことと白票を投じることは異なるという意見はがあることは私も承知していますが、いずれにせよ一票の効果が0に近似できる(個の論理)とすれば、その意見は観念論に過ぎずこの意見者を説得するには及ばないように思います。
2)「政治に参加しない自由」が民主主義で認められているかどうかは微妙ですね。選挙に行かないと罰則がある民主主義国もありますし、日本国でも罰則こそありませんが選挙に行かないことは恥ずかしい行為であるという「常識」は浸透していますからね。
そして、このトピの意見者の場合は(政治)思想的判断と言うよりは一票の価値(効果)に関する数理的判断なのです。
>>[55]
#7に書きましたように、(意見者の非を指摘するのではなく)できるだけ回答者側が「それでも選挙には行くべきだ」という肯定論を構築していただくスタンスでお願いしたいのです。
分母がいくら以上なら選挙に行くかとこの意見者に問い詰めても、なるほど自分の近似理論は厳密ではないかも知れないが、少なくとも1万以上なら行く気がしないが100以下なら行ってもよいかななどと言うぐらいのもので、その非厳密さが暴露されたからと言って、彼の考えは変わらないと思います。
さらに、分母が多くはなく0に近似できなかったとしてもその時の自分の約20分との比較になりますし、選挙に行ったとしても第一投票候補者と第二投票候補者の国家貢献確率の差も係数に成り得ますし、単純に閾値は計算できないと答えられるかも知れません。
#7に書きましたように、(意見者の非を指摘するのではなく)できるだけ回答者側が「それでも選挙には行くべきだ」という肯定論を構築していただくスタンスでお願いしたいのです。
分母がいくら以上なら選挙に行くかとこの意見者に問い詰めても、なるほど自分の近似理論は厳密ではないかも知れないが、少なくとも1万以上なら行く気がしないが100以下なら行ってもよいかななどと言うぐらいのもので、その非厳密さが暴露されたからと言って、彼の考えは変わらないと思います。
さらに、分母が多くはなく0に近似できなかったとしてもその時の自分の約20分との比較になりますし、選挙に行ったとしても第一投票候補者と第二投票候補者の国家貢献確率の差も係数に成り得ますし、単純に閾値は計算できないと答えられるかも知れません。
>>[57]
> このトピの達成目標とは何か。意見者に論理的な反論を行うことなのか、意見者が意見を変えることなのか。
そのいずれでもないことはhijkさんにはお分かりいただいていると思ったのですが。
このトピの目標は、提示された【条件】の下に、この意見者が選挙に行く気になるような、すなわち、彼の一票が国家(国民)の利益または彼個人の利益に繋がるという肯定論を構築できるかどうかを検証(あるいは検討)することです。
事実、hijkさん自身一旦は「できない」と回答されています。
私は他のトピでも言っていますが、できないものは「できない」と答えるのが論理的で真摯な姿勢と思っていますので、それは立派な回答です。
皆さんができないと答えれば私にとっての検証は達成したことになります。
もちろん、私がなるほどと思えるような肯定論を立論できる方がおられたらそれはそれで嬉しく思いますし、これもまた目標を達成したことになります。
> トピ主さんが意見者の何らかのキャラクターを想定して、言わば意見者の意見を過保護に守っているように感じます。
意図的に特異な性格の意見者を設定しているつもりはありません。
少なくとも私の周りには、根拠の論理性が(根本的に間違っているのならともかく)非厳密であっただけで真逆の意見に鞍替えするような人はいませんし、このコミュでも見たことはありません。
つまり、私にとってごく普通の性格です。
hijkさんにとっての「普通の性格」がもし異なるようであれば、その仮定のもとで立論していただいても結構ですが(私以外の他の参加者の共感が得られればhijkさんにとって収穫になるというお考えであればという意味で)、私は申し訳ありませんが対応しかねるかも知れません。
> このトピの達成目標とは何か。意見者に論理的な反論を行うことなのか、意見者が意見を変えることなのか。
そのいずれでもないことはhijkさんにはお分かりいただいていると思ったのですが。
このトピの目標は、提示された【条件】の下に、この意見者が選挙に行く気になるような、すなわち、彼の一票が国家(国民)の利益または彼個人の利益に繋がるという肯定論を構築できるかどうかを検証(あるいは検討)することです。
事実、hijkさん自身一旦は「できない」と回答されています。
私は他のトピでも言っていますが、できないものは「できない」と答えるのが論理的で真摯な姿勢と思っていますので、それは立派な回答です。
皆さんができないと答えれば私にとっての検証は達成したことになります。
もちろん、私がなるほどと思えるような肯定論を立論できる方がおられたらそれはそれで嬉しく思いますし、これもまた目標を達成したことになります。
> トピ主さんが意見者の何らかのキャラクターを想定して、言わば意見者の意見を過保護に守っているように感じます。
意図的に特異な性格の意見者を設定しているつもりはありません。
少なくとも私の周りには、根拠の論理性が(根本的に間違っているのならともかく)非厳密であっただけで真逆の意見に鞍替えするような人はいませんし、このコミュでも見たことはありません。
つまり、私にとってごく普通の性格です。
hijkさんにとっての「普通の性格」がもし異なるようであれば、その仮定のもとで立論していただいても結構ですが(私以外の他の参加者の共感が得られればhijkさんにとって収穫になるというお考えであればという意味で)、私は申し訳ありませんが対応しかねるかも知れません。
2に抵触しないように考えると、一票の民意も百万票の民意も、国益や個人の利益には反映されないと言えます。
ですから、この民主主義による選挙制度を肯定せずに、投票という個人の行為が当人にとってなんらかの利益になるかどうかは、例えばなんらかの罰則の回避という形でしかイメージしにくいのですが、架空の社会集団をモデルにした思考実験も序盤で否定されていて、あくまでも現実の日本国を想定しなければいけないので、明確な罰則もないことになります。
現実の日本国は民主主義ですが、そこだけ外して選挙制度だけを残した日本国の運営イメージが非現実的すぎて、ロジカルシンキングで言うポジティブシンキングの姿勢を維持するのも難しい状況設定だと言えます。
難題ですね。
ですから、この民主主義による選挙制度を肯定せずに、投票という個人の行為が当人にとってなんらかの利益になるかどうかは、例えばなんらかの罰則の回避という形でしかイメージしにくいのですが、架空の社会集団をモデルにした思考実験も序盤で否定されていて、あくまでも現実の日本国を想定しなければいけないので、明確な罰則もないことになります。
現実の日本国は民主主義ですが、そこだけ外して選挙制度だけを残した日本国の運営イメージが非現実的すぎて、ロジカルシンキングで言うポジティブシンキングの姿勢を維持するのも難しい状況設定だと言えます。
難題ですね。
>>[68]
コメント有難うございました。
#64に対しては返信を作文している途中で、同じご意見のhijkさん(#65)に先に投稿されてしまいましたので省略します。
> (A)しかるに、もし私の1票が当選者を決定するというという状況で候補者A,Bどちらかを当選させるとしても、選んだ候補者が将来とんでもない悪人になる可能性は否定できませんから、将来に及ぼす影響が好影響か悪影響かわからないのは同じです。
これはほぼ同意します、が
> ですから、1票が軽いから行かないという人に対しては説得できます
この推論はよく分かりません。
子孫に影響する「予測不可能だが大きな利害得失」と比べるのは(A)ではなく意見者の20分だと思いますよ。
20分は(たとえ普段は無駄に過ごすことが多いとしても)容易に生の価値に変換できます。
たとえば、4kmランニングして体を鍛える、英単語を7つ覚える、彼女といちゃいちゃする、ネットで調べ物をする、久しぶりに母親に電話する、などです。
コメント有難うございました。
#64に対しては返信を作文している途中で、同じご意見のhijkさん(#65)に先に投稿されてしまいましたので省略します。
> (A)しかるに、もし私の1票が当選者を決定するというという状況で候補者A,Bどちらかを当選させるとしても、選んだ候補者が将来とんでもない悪人になる可能性は否定できませんから、将来に及ぼす影響が好影響か悪影響かわからないのは同じです。
これはほぼ同意します、が
> ですから、1票が軽いから行かないという人に対しては説得できます
この推論はよく分かりません。
子孫に影響する「予測不可能だが大きな利害得失」と比べるのは(A)ではなく意見者の20分だと思いますよ。
20分は(たとえ普段は無駄に過ごすことが多いとしても)容易に生の価値に変換できます。
たとえば、4kmランニングして体を鍛える、英単語を7つ覚える、彼女といちゃいちゃする、ネットで調べ物をする、久しぶりに母親に電話する、などです。
選挙のトピックに関連する話。
昨年末に衆議院議員選挙と同時に最高裁判所裁判官(10名)の国民審査が行われましたが、その審査の具体的方法には、裁判官を個別に評価しにくい一面があります。
投票所に行った方は御存じでしょうが、具体的方法とは、“一枚の”投票用紙に裁判官の名前が列挙され、不信任(罷免を可)とする裁判官に×印を記入し、信任とする場合には何も記入しないというものです。この結果で、不信任が有効票数の過半数になった裁判官は罷免されます。
×印以外を記入した投票用紙は“丸ごと”無効です。
(Wikipedia 「最高裁判所裁判官国民審査http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%AF%A9%E6%9F%BB 棄権の権利の侵害)
では、棄権はどうするのか?
白票は信任を意味するので、棄権にはなりません。
(棄権するつもりで未記入で投票箱に入れてしまう例や、係員が間違ってそう指示してしまう例(http://togetter.com/li/423004のコメント)があったそうですが…)
棄権するには投票用紙を投函しない、もしくはそもそも受け取らない、という方法を取ることになります。
ここからわかるのは、特定の裁判官についてだけ棄権することができないという事実です。
「裁判官Aは信任する。裁判官Bは不信任にする。裁判官Cについては棄権したい。」ということができない。
新聞の投稿(朝日新聞 2012.12.20 朝刊 p.14 声 「儀式化した裁判官国民審査」)ではじめて知りましたが、なかなかロジカルな話ではないでしょうか。
昨年末に衆議院議員選挙と同時に最高裁判所裁判官(10名)の国民審査が行われましたが、その審査の具体的方法には、裁判官を個別に評価しにくい一面があります。
投票所に行った方は御存じでしょうが、具体的方法とは、“一枚の”投票用紙に裁判官の名前が列挙され、不信任(罷免を可)とする裁判官に×印を記入し、信任とする場合には何も記入しないというものです。この結果で、不信任が有効票数の過半数になった裁判官は罷免されます。
×印以外を記入した投票用紙は“丸ごと”無効です。
(Wikipedia 「最高裁判所裁判官国民審査http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%AF%A9%E6%9F%BB 棄権の権利の侵害)
では、棄権はどうするのか?
白票は信任を意味するので、棄権にはなりません。
(棄権するつもりで未記入で投票箱に入れてしまう例や、係員が間違ってそう指示してしまう例(http://togetter.com/li/423004のコメント)があったそうですが…)
棄権するには投票用紙を投函しない、もしくはそもそも受け取らない、という方法を取ることになります。
ここからわかるのは、特定の裁判官についてだけ棄権することができないという事実です。
「裁判官Aは信任する。裁判官Bは不信任にする。裁判官Cについては棄権したい。」ということができない。
新聞の投稿(朝日新聞 2012.12.20 朝刊 p.14 声 「儀式化した裁判官国民審査」)ではじめて知りましたが、なかなかロジカルな話ではないでしょうか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ロジカル・シンキング 更新情報
-
最新のアンケート
ロジカル・シンキングのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37834人
- 2位
- 酒好き
- 170665人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89532人
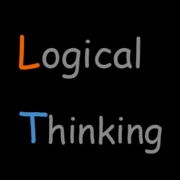












![[dir]アート・美術](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/19/98/111998_61s.jpg)










