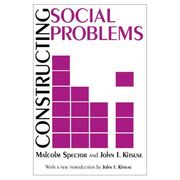先週の土曜(8月13日)に東京大学本郷キャンパスで開かれた、RSC研の本年度第1回研究会の報告内容の記録です。
出席者は20人強。 充実した報告と質疑応答で、すごく面白かったです。
ちなみに、本年度第2回は同じ場所で12月初旬に、第3回は大阪府立大学で来年2月に開かれる予定です(後者はたぶん、”ジェンダー/セクシュアリティの構築”特集になります)。
*********************************************************
社会構築主義の再構築プロジェクト研究会(略称RSC研)
2011年度第1回研究会合「概念の用法とその歴史」
(第1報告)
「戦後、大衆娯楽雑誌における「レズビアン」の概念史 −1960〜1970年代の表象を中心に−」
杉浦郁子(中央大学)
杉浦氏の報告は、「戦後日本<トランスジェンダー>社会史研究会」によって収集された雑誌記事データをベースとし、そこから「レズビアン」に関わる記事を拾い出した記事をデータとし、「レズビアン」概念の変化をたどろうとしたものである。
そうした氏の作業のねらいは、現代日本における「レズビアン差別」の特徴を明らかにすることにあった。 氏によれば、「レズビアン差別」の特徴は、その「不可視性」にあるという。 それは、第一に「女性の同性愛的な欲望」が他者に見えにくいということであり、第二に自分にも見えにくい、ということであるという。
1960〜70年代の「レズビアン」は、現在の意味内容よりも「雑多な人びと」を含む概念であったという。そのイメージの中心は、「性的」であることと「男装」であった。
1966年の記事において「男役(タチ)」と「女役(ネコ)」が初出し、それ以降の記事から、少なくとも4つのレズビアン像が析出される。 大きく分ければ「女役」と「男役」であったが、後者はさらに3つに類型化される。 「男役?」はレズビアン・バーの外部にあり、「女」に見えるが、役割において可換的で流動的なものとされる。 これが「肉欲的なレズビアン」像の不可欠な構成要素である。 「男役?」は「オナベ」であり、バーに勤務する「プロのタチ」であるという。 「男役?」はレズビアン・バーの外部にあり、日常的に男装し男性とみられていた人びとである。
以上のように、当時の「レズビアン」概念は現在よりも多様な意味内容をもっていた。 しかし、1980年代以降のレズビアン・リベレーション言説と、FtMTSの登場により、男役?と?は、「レズビアン」とは分節化されていくことになる。 アイロニカルなことであるが、「男らしさ」の獲得が「女性の同性に対する性的欲望」を可視化させていたのであり、換言すれば、ヘテロセクシズムの稼働によって「レズビアン」が可視化されていたという側面があったのだが、80年代以降、「男らしさ」が「レズビアン」概念からそぎ落とされていくことになった。 そのため、今日においては、レズビアン的欲望は見えにくくなっている。 加えて、性的受動性と女性を結びつける規範は今日でも有効であるため、「女らしさ」を遂行しているレズビアン的欲望は、なおさら不可視のものとなっている。
以上の氏の報告に対して、活発な質疑応答がなされた。 「英語のlesbianとこの報告での「レズビアン」は異なるという理解でよいか」という問いに対し、そうであるとの応答がなされ、欧米圏における概念の日本における概念との差異が確認された。 また、雑誌媒体の特性をどう考えるか、という議論がなされた。 とりわけ、大衆男性誌に最初登場し、その後女性誌に登場していく、ということへの指摘があり、さらに、「当事者」の媒体において「自己執行カテゴリー」として自己展開していく過程をもみなければならないのではないか、という指摘もあった。
最後に、今日のゲイ・コミュニティとレズビアン・コミュニティの違いをめぐり、後者は前者と比較して多様な人びとの交錯する場となっているとのコメントがあり、そうした現状と「レズビアン」概念とのかかわりについてのさらなる考察の必要性が示された。 (文責: 山本功)
(第2報告)
「子育てを支援することのジレンマと『家族』の用法」
松木洋人(東京福祉大学)
松木氏の報告は、子ども家庭支援センターのスタッフおよびいわゆる「保育ママ」へのインタビューを元にして、福祉政策における子育て私事論からの転換に由来する支援の論理と抑制の論理の二重化状況を、その実践と経験に関連させて論じたものであった。 インタビュー調査の分析からは、子育てを支援するということが、「大人−子ども」という関係対を伴った「人生の段階」という成員性カテゴリー装置による理解と、「家族」という成員性カテゴリー装置による理解との間でジレンマを抱えていることが示され、それを解消する方策として「『家族』全体への支援」という再定義が行われていることが示された。
質疑応答では、こういった福祉施設等ではスタッフが専門職となっていることが多く、その場合「専門家−クライエント(素人)」の対を使用するのではないか、あるいは「スタッフ−利用者」という関係対を用いるのではないかということをめぐって議論がなされた。またコメントとして、スタッフ同士で話し合う場面、たとえば社会福祉士資格所有者と保育士資格所有者との間の考え方の違いなどを調べてみるとより興味深いのではないかなどの意見が出された。 (文責: 苫米地伸)
(第3報告)
「敗戦後日本の浮浪児、孤児・捨児をめぐる施設保護問題―ホスピタリズム(施設病)概念の形成と展開を中心に―」
土屋敦(東京大学大学院グローバルCOE特任研究員)
本報告では、これまで注目されてこなかった戦後期の養護施設の収容児童をめぐるホスピタリズム(施設病)の概念と理論を、1960年代初頭以降に日本社会で普及することになる「三歳までは母の手で」といういわゆる「三歳児神話」を準備するものとして位置づけ、その形成と展開の過程を丹念に跡づける作業が行われた。 「ホスピタリズム」論は、浮浪児や孤児・捨児が多く施設収容されるという敗戦後の時代状況の中で、施設における「母性的養護の剥奪 deprivation of maternal care」がさまざまな病理を引き起こすという所説として受容され、そのアカデミックな言説としての展開のピークは、1953〜55年の3年間である。 ただし、BowlbyやBenderによるこの概念の日本への移入は、占領期のGHQ公衆衛生福祉部による啓発活動に遡り、そして、この論の「家族生活に優るものはない」という基本テーゼは、養護施設の家族化や里親委託制度の意味付けの転換といった制度的な影響をもたらした。 こうして、養護施設の収容児童を対象として展開された「母性的養護の剥奪」や「愛着行動論」といった精神医学を基盤とする議論は、ホスピタリズム概念が下火になったあとは、「一般家庭児」の健全育成をめぐる養育規範として強調されていくことになる。
以上は、土屋氏の多面的な報告の縦糸の一本にすぎず、養護施設の定員充足率の推移や、児童保護から児童福祉へという政策的転換と三歳児検診、あるいはホスピタリズムと児童虐待の病理構成のベクトルの対称性など、その論点は多岐にわたった。 報告後の質疑では、ホスピタリズム概念が下火になったあとのそれに代わる概念について、あるいは、占領下に翻訳が出たBenderの小論の原典について等、さまざまな論点についての突っ込んだ意見交換があった。 (文責: 中河伸俊)
|
|
|
|
|
|
|
|
コチーク表参道 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
コチーク表参道のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6473人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19251人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人