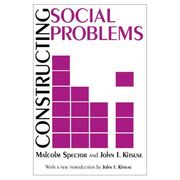★neuさんが、new-emp ML に投稿してくれた報告の転載です。
**********************************************************************
去る8月10・11日に行われた、社会構築主義の再構築プロジェクト研究会の研究会報告と、次回、次々回の予定をお知らせいたします。
1.研究会報告
2010年8月10日(火)14:30−18:00
報告セッション・1
司会: 山本功(淑徳大学)
●報告1:「精神疾患言説の比較歴史社会学」佐藤雅浩(日本学術振興会・慶應義塾大学)
佐藤氏の報告は、精神疾患言説の流行と精神疾患の流行が相互に影響しあうという現象を踏まえながらも、「全ての診断カテゴリーが通俗化するわけではない」ことに着目し、どのような要因が「流行」をもたらすのかを「比較」という方法で明らかにしようとするものであった。 事例として「神経衰弱」「ヒステリー」「外傷性神経症」の3つをとりあげ、暫定的に、流行に関与する可能性のある変数を大きく5つ措定し、それらを比較することによって精神疾患言説の「流行」を説明するという報告がなされた。
参加者からの質問・コメントとして、以下のようもなものがあった。「精神疾患言説と一言でくくられているが、いくつかの場面のレベルがあり、それらをひとまとめにしてしまってよいのか」「流行という概念は、検討して定義する必要がある」「looping effectと言われるものは従来のラベリング論やピグマリオン効果とどう異なるのか」といった論点が提示された。
●報告2:「意味の流動性と役割の転換――J・R・ガスフィールドのレトリック分析・再考−−」林原玲洋(首都大学東京)
林原氏の報告は、氏のこれまでの、従来日本ではほとんど体系的に検討されることのなかった「レトリック」論の学説史研究をふまえ、ガスフィールドのレトリック分析の方法を検討し再解釈することで、それをどのように構築主義の社会問題研究に活用できるかを論じるものであった。 ガスフィールドの分析が「わかりにくい」原因としてK.バークの用語があまり説明されずに用いられていることから、氏はバーク『動機の文法』を紐解き、論者と聴者の「同一化」という点に着目し、「従来あまり活用されてこなかったガスフィールド論文も、同一化(議論状況)が転義と論証を媒介しているという点に着目して再読すると、有効に活用できるのではないだろうか」と結論づけるものであった。
フロアとの議論において、林原氏より「レトリックを使うことによって、いかに話がこじれるのか、に関心がある」との問題意識が提示され、議論がなされた。 また、「レトリック分析は、たとえばメンバーシップカテゴリー化論などのほかの議論に回収されつくされないかどうか」「レトリック論の意義をどこに求めるのか。「効果の研究ではなく、固有の意義を確認する必要がある」といった議論がおこなわれた。
2010年8月11日(水)09:30−12:40
報告セッション・2
司会: 苫米地伸(東京学芸大学)
●報告1:「中学校における文化をめぐるエスノグラフィー」團康晃(東京大学大学院・学際情報学府)
團氏の報告は、地方中学校における詳細なエスノグラフィーに基づいて、「美術部」あるいは「オタク」といったカテゴリー化実践を記述するものであった。これまでのサブカルチャー・グループ・エスノグラフィーは、ともすると調査者が先行研究を踏まえた上で導入する問題意識、特に「社会的不平等」や「ジェンダー」などに基づいてグループが定められる傾向にあったが、團氏はそもそものそういったグループ、あるいはグループのカテゴリー化が実際にどのようにして行われているのかに着目していた。
参加者からの質問・コメントとしては、実際にフィールドワークを行った際の状況、あるいは条件についての質問とともに、より内容的な問も行われた。例えば、「グループ分類を誰が設定するのか、という原理的な問題設定が、フィールドワークあるいは調査の『巧拙の問題』に還元された場合、どう応えていくのか」といった問題や、「カテゴリー化することによって、彼/彼女らに何が可能になるのか」といったものであった。
●報告2:「家族介護における『特権的知識」のクレイム−構築主義アプローチによる認知症/家族介護分析−」木下衆(京都大学大学院・日本学術振興会)
木下氏の報告は、グブリアムとホルスタインによる構築主義的研究、特に「特権的知識」のクレイムについての考察を、直接的に応用したものであり、高齢者を介護する家族による自助グループへの参与観察と、そのメンバーへのインタビューによる研究であった。 従来の家族研究における介護保険法導入に関する議論においては、介護保険の導入によって、家族介護の閉鎖性が緩和されていくという議論があったが、氏によれば介護者/要介護者の相互行為に着目すると、介護保険を利用することによって、とりわけ「特権的知識のクレイム(要介護者の本当の姿を知っていたのは、自分だけだった)」をめぐってコンフリクトが生じているということが論じられた。 また現在の「家族介護」がこのような特権性を想定しなければおそらく成立し得ない、つまり「家族介護現場がどのような『ルール』で動いているのか」を明らかにすることが必要であると論じられた。
フロアからは、氏による「代弁」や「証明」という概念についての質問・意見、「特権的知識のクレイム」が介護者にとって介護認定のレベル上げのための資源とみなされる場合もあるなどの示唆もあった。また「代弁」という概念に関連して、成年後見人制度との関連についての議論も行われた。
**************
2.次回、次々回の研究会予定
2010/12/05(日)東京セッション
東大本郷にて開催予定。
2011/02/19、20(土・日)大阪セッション
大阪府立大にて開催予定。
また期日が近くなってから、詳細な情報をお送りします。
それではひとまず失礼いたします。
**********************************************************************
**********************************************************************
去る8月10・11日に行われた、社会構築主義の再構築プロジェクト研究会の研究会報告と、次回、次々回の予定をお知らせいたします。
1.研究会報告
2010年8月10日(火)14:30−18:00
報告セッション・1
司会: 山本功(淑徳大学)
●報告1:「精神疾患言説の比較歴史社会学」佐藤雅浩(日本学術振興会・慶應義塾大学)
佐藤氏の報告は、精神疾患言説の流行と精神疾患の流行が相互に影響しあうという現象を踏まえながらも、「全ての診断カテゴリーが通俗化するわけではない」ことに着目し、どのような要因が「流行」をもたらすのかを「比較」という方法で明らかにしようとするものであった。 事例として「神経衰弱」「ヒステリー」「外傷性神経症」の3つをとりあげ、暫定的に、流行に関与する可能性のある変数を大きく5つ措定し、それらを比較することによって精神疾患言説の「流行」を説明するという報告がなされた。
参加者からの質問・コメントとして、以下のようもなものがあった。「精神疾患言説と一言でくくられているが、いくつかの場面のレベルがあり、それらをひとまとめにしてしまってよいのか」「流行という概念は、検討して定義する必要がある」「looping effectと言われるものは従来のラベリング論やピグマリオン効果とどう異なるのか」といった論点が提示された。
●報告2:「意味の流動性と役割の転換――J・R・ガスフィールドのレトリック分析・再考−−」林原玲洋(首都大学東京)
林原氏の報告は、氏のこれまでの、従来日本ではほとんど体系的に検討されることのなかった「レトリック」論の学説史研究をふまえ、ガスフィールドのレトリック分析の方法を検討し再解釈することで、それをどのように構築主義の社会問題研究に活用できるかを論じるものであった。 ガスフィールドの分析が「わかりにくい」原因としてK.バークの用語があまり説明されずに用いられていることから、氏はバーク『動機の文法』を紐解き、論者と聴者の「同一化」という点に着目し、「従来あまり活用されてこなかったガスフィールド論文も、同一化(議論状況)が転義と論証を媒介しているという点に着目して再読すると、有効に活用できるのではないだろうか」と結論づけるものであった。
フロアとの議論において、林原氏より「レトリックを使うことによって、いかに話がこじれるのか、に関心がある」との問題意識が提示され、議論がなされた。 また、「レトリック分析は、たとえばメンバーシップカテゴリー化論などのほかの議論に回収されつくされないかどうか」「レトリック論の意義をどこに求めるのか。「効果の研究ではなく、固有の意義を確認する必要がある」といった議論がおこなわれた。
2010年8月11日(水)09:30−12:40
報告セッション・2
司会: 苫米地伸(東京学芸大学)
●報告1:「中学校における文化をめぐるエスノグラフィー」團康晃(東京大学大学院・学際情報学府)
團氏の報告は、地方中学校における詳細なエスノグラフィーに基づいて、「美術部」あるいは「オタク」といったカテゴリー化実践を記述するものであった。これまでのサブカルチャー・グループ・エスノグラフィーは、ともすると調査者が先行研究を踏まえた上で導入する問題意識、特に「社会的不平等」や「ジェンダー」などに基づいてグループが定められる傾向にあったが、團氏はそもそものそういったグループ、あるいはグループのカテゴリー化が実際にどのようにして行われているのかに着目していた。
参加者からの質問・コメントとしては、実際にフィールドワークを行った際の状況、あるいは条件についての質問とともに、より内容的な問も行われた。例えば、「グループ分類を誰が設定するのか、という原理的な問題設定が、フィールドワークあるいは調査の『巧拙の問題』に還元された場合、どう応えていくのか」といった問題や、「カテゴリー化することによって、彼/彼女らに何が可能になるのか」といったものであった。
●報告2:「家族介護における『特権的知識」のクレイム−構築主義アプローチによる認知症/家族介護分析−」木下衆(京都大学大学院・日本学術振興会)
木下氏の報告は、グブリアムとホルスタインによる構築主義的研究、特に「特権的知識」のクレイムについての考察を、直接的に応用したものであり、高齢者を介護する家族による自助グループへの参与観察と、そのメンバーへのインタビューによる研究であった。 従来の家族研究における介護保険法導入に関する議論においては、介護保険の導入によって、家族介護の閉鎖性が緩和されていくという議論があったが、氏によれば介護者/要介護者の相互行為に着目すると、介護保険を利用することによって、とりわけ「特権的知識のクレイム(要介護者の本当の姿を知っていたのは、自分だけだった)」をめぐってコンフリクトが生じているということが論じられた。 また現在の「家族介護」がこのような特権性を想定しなければおそらく成立し得ない、つまり「家族介護現場がどのような『ルール』で動いているのか」を明らかにすることが必要であると論じられた。
フロアからは、氏による「代弁」や「証明」という概念についての質問・意見、「特権的知識のクレイム」が介護者にとって介護認定のレベル上げのための資源とみなされる場合もあるなどの示唆もあった。また「代弁」という概念に関連して、成年後見人制度との関連についての議論も行われた。
**************
2.次回、次々回の研究会予定
2010/12/05(日)東京セッション
東大本郷にて開催予定。
2011/02/19、20(土・日)大阪セッション
大阪府立大にて開催予定。
また期日が近くなってから、詳細な情報をお送りします。
それではひとまず失礼いたします。
**********************************************************************
|
|
|
|
|
|
|
|
コチーク表参道 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
コチーク表参道のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170686人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90045人
- 3位
- mixi バスケ部
- 37855人