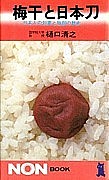●日本語は他言語より美しいか
日本語の難しさは、もっぱら漢字の読み書きと敬語にあるとされており、一般に会話は覚えやすいと言われている。その理由として母音の数が少なく発音が容易であることと、文節の順序の自由度が高いことが挙げられる。
“Her love I.”という誤った英文があるとする。これを、活用の正しさに着目して“I love her.”の意味に取るか、それとも語順の正しさに着目して“She loves me.”の意味にとるか。ネイティブスピーカーなら100人中99人以上が後者の意味に取るだろう。このことは、英語では活用形の正しさよりも語順の正しさが絶対的意味を持っていることを示している。ところが日本語の場合は語順の自由度が極めて高いことから、活用形や助詞の選択の正しさに絶対的意味があるのである。
“He is a student.”(彼は学生です。)という文章を見ると、主語のHeと主格補語のa studentが、be動詞を挟んでイコールの関係になっており、等式のようである。
また“One plus two equal three.”という文章は、
1+2=3
の等式と全く同じ語順で、しかも左辺と右辺が釣り合っている。日本語の「1に2を加えると3に等しい」という文章が、数式で語順の通り書くと「12+3=」となることと比較すると、英語の数学的・論理的性格はよくわかるだろう。
このような事情から、「印欧語は論理的」と言われてきた。明治期には「日本語には文法がない」、果ては「日本語は原始的で劣った言語である」という暴論さえ喧伝されたほどである。これらの説は今日完全に否定されているが、このような劣等感の裏返しのように「印欧語は理屈っぽいが日本語は情緒豊か」という説を耳にすることも多い。
曰く、日本語には「印欧語にない」「繊細な」表現に富んでいるのだそうである。「兄と弟」、「私・俺・わし」、「悲しい・切ない」などの表現は日本語にしかないと言うのだ。私が「『切ない』は“sad”じゃないのか」と言うと、「“sad”は『悲しい』だろう、自分が言っているのは『切ない』だ」と言うのである。ではカナダ人は悲しいときだけ“I’m sad.”と言い、切ないときはそれを表す単語がないのでspeechlessになるのだろうか。それとも、カナダ人には「切ない」という感情がないのだろうか。実際カナダ在住日本人の中には、カナダ人が日本人の「細やかな」情緒を察してくれないという理由で、カナダ人をノータリンだと言う人が実在するのである。はたして“sad”は日本語の「悲しい」だけを表現しているのだろうか。“It’s sad he should resign.”(彼が辞職するのは残念だ)のように、“sad”は「悲しい」のみならずもっと広い意味を持っているはずだ。「“sad”は『悲しい』、『悲しい』は“sad”」でそれ以外の表現、それ以外の組み合わせがないと思う方が、よほど何かが足りないのではないだろうか。英語の事情がどうであれ、カナダ人は自分の意思を英語で表現しなければならないのだから、表現したい意思に該当する単語がなければ困るわけで、英語などという欠陥言語を使い続けているカナダ人がバカなのか、それとも自分の意思を英訳できない方がバカなのか、よくよく考えた方がいいだろう。「君がいないと淋しい」というのは、英語では“I miss you”と動詞で表現し、形容詞で表現しないが、カナダ人に「淋しい」という感情がないわけではもちろんないのだ。挙句の果てには「カナダ人は手が大きいから細かい作業に適さない、芸術や針仕事は日本人の方が優れている」などと言い出す始末である。「カナダ人に有名な芸術家はいないだろう?」本当にいないのか、それとも自分が知らないだけなのか。
日本語の難しさは、もっぱら漢字の読み書きと敬語にあるとされており、一般に会話は覚えやすいと言われている。その理由として母音の数が少なく発音が容易であることと、文節の順序の自由度が高いことが挙げられる。
“Her love I.”という誤った英文があるとする。これを、活用の正しさに着目して“I love her.”の意味に取るか、それとも語順の正しさに着目して“She loves me.”の意味にとるか。ネイティブスピーカーなら100人中99人以上が後者の意味に取るだろう。このことは、英語では活用形の正しさよりも語順の正しさが絶対的意味を持っていることを示している。ところが日本語の場合は語順の自由度が極めて高いことから、活用形や助詞の選択の正しさに絶対的意味があるのである。
“He is a student.”(彼は学生です。)という文章を見ると、主語のHeと主格補語のa studentが、be動詞を挟んでイコールの関係になっており、等式のようである。
また“One plus two equal three.”という文章は、
1+2=3
の等式と全く同じ語順で、しかも左辺と右辺が釣り合っている。日本語の「1に2を加えると3に等しい」という文章が、数式で語順の通り書くと「12+3=」となることと比較すると、英語の数学的・論理的性格はよくわかるだろう。
このような事情から、「印欧語は論理的」と言われてきた。明治期には「日本語には文法がない」、果ては「日本語は原始的で劣った言語である」という暴論さえ喧伝されたほどである。これらの説は今日完全に否定されているが、このような劣等感の裏返しのように「印欧語は理屈っぽいが日本語は情緒豊か」という説を耳にすることも多い。
曰く、日本語には「印欧語にない」「繊細な」表現に富んでいるのだそうである。「兄と弟」、「私・俺・わし」、「悲しい・切ない」などの表現は日本語にしかないと言うのだ。私が「『切ない』は“sad”じゃないのか」と言うと、「“sad”は『悲しい』だろう、自分が言っているのは『切ない』だ」と言うのである。ではカナダ人は悲しいときだけ“I’m sad.”と言い、切ないときはそれを表す単語がないのでspeechlessになるのだろうか。それとも、カナダ人には「切ない」という感情がないのだろうか。実際カナダ在住日本人の中には、カナダ人が日本人の「細やかな」情緒を察してくれないという理由で、カナダ人をノータリンだと言う人が実在するのである。はたして“sad”は日本語の「悲しい」だけを表現しているのだろうか。“It’s sad he should resign.”(彼が辞職するのは残念だ)のように、“sad”は「悲しい」のみならずもっと広い意味を持っているはずだ。「“sad”は『悲しい』、『悲しい』は“sad”」でそれ以外の表現、それ以外の組み合わせがないと思う方が、よほど何かが足りないのではないだろうか。英語の事情がどうであれ、カナダ人は自分の意思を英語で表現しなければならないのだから、表現したい意思に該当する単語がなければ困るわけで、英語などという欠陥言語を使い続けているカナダ人がバカなのか、それとも自分の意思を英訳できない方がバカなのか、よくよく考えた方がいいだろう。「君がいないと淋しい」というのは、英語では“I miss you”と動詞で表現し、形容詞で表現しないが、カナダ人に「淋しい」という感情がないわけではもちろんないのだ。挙句の果てには「カナダ人は手が大きいから細かい作業に適さない、芸術や針仕事は日本人の方が優れている」などと言い出す始末である。「カナダ人に有名な芸術家はいないだろう?」本当にいないのか、それとも自分が知らないだけなのか。
|
|
|
|
コメント(13)
●翻訳による劣化
テレビ番組で、松尾芭蕉の有名な俳句「古池や蛙とびこむ水の音」の英訳を提示したとき、それを見た外国人が「それがどうしたの?」と言ったら、ある日本人は「日本語の繊細で情緒豊かな表現は英語では表現できない、だから自分は日本人で良かった」と思ったそうである。韻文は口語ではないのだから、定型詩に翻訳すれば劣化するに決まっているような気がするのだが、この場合は訳詞が下手であるか聞き手に感受性がないかどちらかであって、これを以って日本語が他言語より美しいことには当然ならないだろう。
芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」には、いくつか英訳が試みられてきた。
An old silent pond....
A frog jumps in to the pond
Splash! Silence again.
5・7・5の定型詩を維持した苦労の跡が伺えるが、英語は1または2音節の単語がほとんどなため、同じ17音節だと英語の情報量が多くなりすぎて冗長になり、簡潔さに劣る。俳句に関しては、英訳してもオリジナルを超えることはまず不可能であり、俳句の英訳は3・4・3にするのが適切とも思われる。
この訳詞では原語にはない“Splash!”が、芭蕉の論点である「静寂とかすかな音の対比」から逸れている点、 pondが無駄に二度繰り返されている点、体言止めが再現されなかった点など、日英どちらが勝っているかは明白であろう。
理想論的には、文献はすべて原語で読むのがいいのだが、あらゆる言語を取得するのは不可能なので、翻訳に頼ることになる。翻訳すると原語のニュアンスが損なわれることがあるが、それは翻案による劣化であり、言語そのものの優劣とはもとより関係はない。
テレビ番組で、松尾芭蕉の有名な俳句「古池や蛙とびこむ水の音」の英訳を提示したとき、それを見た外国人が「それがどうしたの?」と言ったら、ある日本人は「日本語の繊細で情緒豊かな表現は英語では表現できない、だから自分は日本人で良かった」と思ったそうである。韻文は口語ではないのだから、定型詩に翻訳すれば劣化するに決まっているような気がするのだが、この場合は訳詞が下手であるか聞き手に感受性がないかどちらかであって、これを以って日本語が他言語より美しいことには当然ならないだろう。
芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」には、いくつか英訳が試みられてきた。
An old silent pond....
A frog jumps in to the pond
Splash! Silence again.
5・7・5の定型詩を維持した苦労の跡が伺えるが、英語は1または2音節の単語がほとんどなため、同じ17音節だと英語の情報量が多くなりすぎて冗長になり、簡潔さに劣る。俳句に関しては、英訳してもオリジナルを超えることはまず不可能であり、俳句の英訳は3・4・3にするのが適切とも思われる。
この訳詞では原語にはない“Splash!”が、芭蕉の論点である「静寂とかすかな音の対比」から逸れている点、 pondが無駄に二度繰り返されている点、体言止めが再現されなかった点など、日英どちらが勝っているかは明白であろう。
理想論的には、文献はすべて原語で読むのがいいのだが、あらゆる言語を取得するのは不可能なので、翻訳に頼ることになる。翻訳すると原語のニュアンスが損なわれることがあるが、それは翻案による劣化であり、言語そのものの優劣とはもとより関係はない。
●翻訳と翻案
一般に翻訳すると品質が劣化するものだが、まれに翻訳先言語の付加価値をつけてオリジナルを凌ぐことがあり、翻訳者の技量が試される。
【カール・ブッセ作】“Über den Bergen”
Über den Bergen, weit zu wandern,
sagen die Leute, wohnt das Glück.
Ach, und ich ging im Schwarme der andern,
kam mit verweinten Augen zurück.
Über den Bergen, weit weit drüben,
sagen die Leute, wohnt das Glück.
【上田敏訳詩】「山のあなた」
山のあなたの空遠く
「幸」住むと人のいふ。
噫、われひとゝ尋めゆきて
涙さしぐみ、かへりきぬ。
山のあなたになほ遠く
「幸」住むと人のいふ。
ブッセの原詩では“Bergen”と“verweinten”、“wandern”と“andern”、“Glück”と“kamzurück”がそれぞれ韻を踏んでいるが、上田敏は九八調の原詩を和風に七五調に翻案した。その結果脚韻は消失したものの、簡潔になっている。原詩では“mit verweinten Augen”という表現がややくどいと感じる。ここでは「泣いている」ことが重要であって、目は重要でないため、ことさらに“Augen”と述べるのが冗長に感じられるのだが、“verweinten Augen”と“den Bergen”が韻を踏んでいること、9・8・9・8のリズムを維持すること、構文上目的語を省略できなかったことが“Augen”を必要とした理由であろう。
上田訳はブッセの原詩を超えたともっぱらの評判である。
一般に翻訳すると品質が劣化するものだが、まれに翻訳先言語の付加価値をつけてオリジナルを凌ぐことがあり、翻訳者の技量が試される。
【カール・ブッセ作】“Über den Bergen”
Über den Bergen, weit zu wandern,
sagen die Leute, wohnt das Glück.
Ach, und ich ging im Schwarme der andern,
kam mit verweinten Augen zurück.
Über den Bergen, weit weit drüben,
sagen die Leute, wohnt das Glück.
【上田敏訳詩】「山のあなた」
山のあなたの空遠く
「幸」住むと人のいふ。
噫、われひとゝ尋めゆきて
涙さしぐみ、かへりきぬ。
山のあなたになほ遠く
「幸」住むと人のいふ。
ブッセの原詩では“Bergen”と“verweinten”、“wandern”と“andern”、“Glück”と“kamzurück”がそれぞれ韻を踏んでいるが、上田敏は九八調の原詩を和風に七五調に翻案した。その結果脚韻は消失したものの、簡潔になっている。原詩では“mit verweinten Augen”という表現がややくどいと感じる。ここでは「泣いている」ことが重要であって、目は重要でないため、ことさらに“Augen”と述べるのが冗長に感じられるのだが、“verweinten Augen”と“den Bergen”が韻を踏んでいること、9・8・9・8のリズムを維持すること、構文上目的語を省略できなかったことが“Augen”を必要とした理由であろう。
上田訳はブッセの原詩を超えたともっぱらの評判である。
●翻訳はどっちか
西安の興慶公園には、阿倍仲麻呂の歌碑がある。
【望郷詩】
翹首望東天 (Qiao shou wang dong tian)
神馳奈良辺 (Shen chi Nai liang bian)
三笠山頂上 (San li shan ding shan)
想又皎月圓 (Xiang you jiao yue yuan)
【訳者不詳・和訳】
首を翹げて東天を望めば 心は馳す奈良の辺
三笠山頂の上 想うにまた皓月圓ならん
【伝阿倍仲麻呂作】
天の原ふりさけ見れば春日なる 三笠の山にいでし月かも
「望郷詩」は、阿倍仲麻呂の「天の原〜」の漢訳と「言われて」いるが、1・2行目と3・4行目の終わりと、1・4行目と2・3行目の初めが韻を踏んでいて、あまりにもできすぎており、こっちがオリジナルで「天の原〜」が翻訳ではないかと疑いたくなるほどだ。ただし、「望郷詩」は漢詩の中に「三笠」と「奈良」の外来語が割り込んでいるため平仄(漢詩の声調)が崩れており、これをオリジナルとするのは不自然という指摘がある。
いっぽう「天の原〜」は作風が万葉調でなく後代の作風であることと、日本に帰国できなかった彼がどうやって「天の原〜」を日本に伝えたのかという謎が残り、誰かが仲麻呂の心境に成り代わって作ったとも考えられる。大原正義は「長安の月−阿部仲麻呂伝」の中で、「望郷詩」が仲麻呂のオリジナルで「天の原〜」は藤原清河の和訳だと主張している。
個人的には「望郷詩」が断然優れていると考えるのだが、和歌党の方の意見を聞いてみたい。
西安の興慶公園には、阿倍仲麻呂の歌碑がある。
【望郷詩】
翹首望東天 (Qiao shou wang dong tian)
神馳奈良辺 (Shen chi Nai liang bian)
三笠山頂上 (San li shan ding shan)
想又皎月圓 (Xiang you jiao yue yuan)
【訳者不詳・和訳】
首を翹げて東天を望めば 心は馳す奈良の辺
三笠山頂の上 想うにまた皓月圓ならん
【伝阿倍仲麻呂作】
天の原ふりさけ見れば春日なる 三笠の山にいでし月かも
「望郷詩」は、阿倍仲麻呂の「天の原〜」の漢訳と「言われて」いるが、1・2行目と3・4行目の終わりと、1・4行目と2・3行目の初めが韻を踏んでいて、あまりにもできすぎており、こっちがオリジナルで「天の原〜」が翻訳ではないかと疑いたくなるほどだ。ただし、「望郷詩」は漢詩の中に「三笠」と「奈良」の外来語が割り込んでいるため平仄(漢詩の声調)が崩れており、これをオリジナルとするのは不自然という指摘がある。
いっぽう「天の原〜」は作風が万葉調でなく後代の作風であることと、日本に帰国できなかった彼がどうやって「天の原〜」を日本に伝えたのかという謎が残り、誰かが仲麻呂の心境に成り代わって作ったとも考えられる。大原正義は「長安の月−阿部仲麻呂伝」の中で、「望郷詩」が仲麻呂のオリジナルで「天の原〜」は藤原清河の和訳だと主張している。
個人的には「望郷詩」が断然優れていると考えるのだが、和歌党の方の意見を聞いてみたい。
●簡潔な表現は日本語独自のものか
I love you. (英語)
私は/あなたが/好き/です。 (日本語)
文節(単語ではない)の数は、いずれの言語でも変わらないものと思われる。ただし音節の数で言うなら、英語の3音節に対し日本語は12音節と、同じ意味を表すのに日本語の方がはるかに(音節が)長いというのは定説である。
省略(特に主語)は日本語の特徴だという意見も多いが、フランス語の
Je t’aime. (2音節)
のように短縮形を用いたり、スペイン語では
(Yo) Te amo. (2音節)
のように主語の省略が可能であり、印欧語でも簡潔な表現は十分可能である。
また、聖書の中で最も短い文章は、ヨハネ福音書11章35節の
Jesus wept.
だが、日本語では
イエスは涙を流された。
と、音節数・字数いずれもはるかに長くなる(ただし文節数は英語2に対し日本語3と、あまり変わらない)。
英語のweptが目的語の「涙」を必要としないため、簡潔な表現になっているのだ。あらゆる言語には詩が存在しており、簡潔な表現・繊細な表現はどの言語にも当然あるものと思われる。
I love you. (英語)
私は/あなたが/好き/です。 (日本語)
文節(単語ではない)の数は、いずれの言語でも変わらないものと思われる。ただし音節の数で言うなら、英語の3音節に対し日本語は12音節と、同じ意味を表すのに日本語の方がはるかに(音節が)長いというのは定説である。
省略(特に主語)は日本語の特徴だという意見も多いが、フランス語の
Je t’aime. (2音節)
のように短縮形を用いたり、スペイン語では
(Yo) Te amo. (2音節)
のように主語の省略が可能であり、印欧語でも簡潔な表現は十分可能である。
また、聖書の中で最も短い文章は、ヨハネ福音書11章35節の
Jesus wept.
だが、日本語では
イエスは涙を流された。
と、音節数・字数いずれもはるかに長くなる(ただし文節数は英語2に対し日本語3と、あまり変わらない)。
英語のweptが目的語の「涙」を必要としないため、簡潔な表現になっているのだ。あらゆる言語には詩が存在しており、簡潔な表現・繊細な表現はどの言語にも当然あるものと思われる。
●翻訳の方がヒットした曲
「日本との比較文化論」からはずれるが、翻訳がオリジナルを凌駕した例として“My Way”を挙げておこう。
ポール・アンカが1969年に作詞し、フランク・シナトラに捧げてヒットした“My Way”の原曲は、1944年にフランスのジル・チボーが作詞しジャック・ルヴォーとクロード・フランソワが作曲した“Comme D'habitude ”というシャンソンである。
【Comme D'habitude】
Je me lève, je te bouscule
(目が覚めて、君を起こそうと揺する)
Tu ne te réveiles pas, comme d'habitude
(でも君は起きない、いつものように)
Sur toi, je remonte le drap
(僕は君の上にシーツをかける)
J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude
(君が風邪をひかないかと心配しながら、いつものように)
La main caresse tes cheveux
(僕は手で君の髪を撫でる)
Presque malgré moi, comme d'habitude
(無意識のうちに、いつものように)
Mais toi, tu me tournes dos, comme d'habitude
(でも君は、僕に背中を向ける。いつものように)
Et puis, je m'habille très vite
(それから素早く着替えて)
Je sors de la chambre, comme d'habitude
(僕は部屋を出る。いつものように)
Tout seul, je bois mon café
(一人きりで、コーヒーを飲む)
Je suis en retard, comme d'habitude
(また遅刻だ、いつものように)
Sans bruit, je quitte la maison
(静かに扉を閉め、僕は家を出る)
Tout est gris dehors, comme d'habitude
(外は曇っている。いつものように)
J'ai froid, je me lève mon col, comme d'habitude
(今日も寒い、僕はコートの襟を立てる。いつものように)
Comme d'habitude, toute la journée
(いつものように一日中)
Je vais jouer à faire semblant
(猫をかぶって過ごすんだ)
Comme d'habitude, je vais sourire
(いつものように、笑顔を作り)
Comme d'habitude, je vais même rire
(いつものように、笑い声さえ上げ)
Comme d'habitude, enfin je vais vivre
(いつものように、結局一日を過ごすのさ)
Oui, comme d'habitude
(そう、いつものように)
Et puis, le jour s'en ira
(それから一日が終わり)
Moi, je reviendrai, comme d'habitude
(僕は家へと帰って来る、いつものように)
Et toi, tu seras sortie
(君は外出していて)
Pas encore rentrée, comme d'habitude
(まだ帰って来ない、いつものように)
Tout seul, j'irai me coucher
(一人で寝室に向かい)
Dans le second lit froid, comme d'habitude
(冷え切ったベッドに入る、いつものように)
Mais larmes, je les cacherai, comme d'habitude
(涙を隠して、いつものように)
Mais comme d'habitude, même la nuit
(夜でさえ、いつものように)
Je vais jouer à faire semblant
(変わらぬ時を過ごす)
Comme d'habitude, tu rentreras
(いつものように、君が帰って来て)
Comme d'habitude, tu me souriras
(いつものように、君が微笑む)
Comme d'habitude
(いつものように)
Comme d'habitude tu te déshabilleras
(いつものように、君は服を脱ぎ)
Comme d'habitude tu te coucheras
(いつものように、君はベットに入り)
Comme d'habitude on s'embrassera
(いつものように、キスをして)
Comme d'habitude
(いつものように)
Comme d'habitude on fera semblant
(いつものように、ふるまって)
Comme d'habitude on fera l'amour
(いつものように、愛し合い)
Comme d'habitude on fera semblant
(いつものように、ふるまって)
Comme d'habitude
(いつものように)
平凡な日常の中に、ささやかな幸福を見出す。自己主張の塊のような“My Way”とはずいぶんと趣が違う。ヒットしたのは“My Way”の方だが、“Comme D'habitude”の方がいいと思うのは私だけだろうか?
「日本との比較文化論」からはずれるが、翻訳がオリジナルを凌駕した例として“My Way”を挙げておこう。
ポール・アンカが1969年に作詞し、フランク・シナトラに捧げてヒットした“My Way”の原曲は、1944年にフランスのジル・チボーが作詞しジャック・ルヴォーとクロード・フランソワが作曲した“Comme D'habitude ”というシャンソンである。
【Comme D'habitude】
Je me lève, je te bouscule
(目が覚めて、君を起こそうと揺する)
Tu ne te réveiles pas, comme d'habitude
(でも君は起きない、いつものように)
Sur toi, je remonte le drap
(僕は君の上にシーツをかける)
J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude
(君が風邪をひかないかと心配しながら、いつものように)
La main caresse tes cheveux
(僕は手で君の髪を撫でる)
Presque malgré moi, comme d'habitude
(無意識のうちに、いつものように)
Mais toi, tu me tournes dos, comme d'habitude
(でも君は、僕に背中を向ける。いつものように)
Et puis, je m'habille très vite
(それから素早く着替えて)
Je sors de la chambre, comme d'habitude
(僕は部屋を出る。いつものように)
Tout seul, je bois mon café
(一人きりで、コーヒーを飲む)
Je suis en retard, comme d'habitude
(また遅刻だ、いつものように)
Sans bruit, je quitte la maison
(静かに扉を閉め、僕は家を出る)
Tout est gris dehors, comme d'habitude
(外は曇っている。いつものように)
J'ai froid, je me lève mon col, comme d'habitude
(今日も寒い、僕はコートの襟を立てる。いつものように)
Comme d'habitude, toute la journée
(いつものように一日中)
Je vais jouer à faire semblant
(猫をかぶって過ごすんだ)
Comme d'habitude, je vais sourire
(いつものように、笑顔を作り)
Comme d'habitude, je vais même rire
(いつものように、笑い声さえ上げ)
Comme d'habitude, enfin je vais vivre
(いつものように、結局一日を過ごすのさ)
Oui, comme d'habitude
(そう、いつものように)
Et puis, le jour s'en ira
(それから一日が終わり)
Moi, je reviendrai, comme d'habitude
(僕は家へと帰って来る、いつものように)
Et toi, tu seras sortie
(君は外出していて)
Pas encore rentrée, comme d'habitude
(まだ帰って来ない、いつものように)
Tout seul, j'irai me coucher
(一人で寝室に向かい)
Dans le second lit froid, comme d'habitude
(冷え切ったベッドに入る、いつものように)
Mais larmes, je les cacherai, comme d'habitude
(涙を隠して、いつものように)
Mais comme d'habitude, même la nuit
(夜でさえ、いつものように)
Je vais jouer à faire semblant
(変わらぬ時を過ごす)
Comme d'habitude, tu rentreras
(いつものように、君が帰って来て)
Comme d'habitude, tu me souriras
(いつものように、君が微笑む)
Comme d'habitude
(いつものように)
Comme d'habitude tu te déshabilleras
(いつものように、君は服を脱ぎ)
Comme d'habitude tu te coucheras
(いつものように、君はベットに入り)
Comme d'habitude on s'embrassera
(いつものように、キスをして)
Comme d'habitude
(いつものように)
Comme d'habitude on fera semblant
(いつものように、ふるまって)
Comme d'habitude on fera l'amour
(いつものように、愛し合い)
Comme d'habitude on fera semblant
(いつものように、ふるまって)
Comme d'habitude
(いつものように)
平凡な日常の中に、ささやかな幸福を見出す。自己主張の塊のような“My Way”とはずいぶんと趣が違う。ヒットしたのは“My Way”の方だが、“Comme D'habitude”の方がいいと思うのは私だけだろうか?
こんにちは。
いつも斬新な切り口を楽しみにしています。
以前から、「日本文化は比較的女性的だな」と思っておりました。
ずばっと直接表現せずに、想像してもらうようにしむけることが他国より多い気がします。もしかしたら日本人にとってそれが楽しいのかもしれません。
>実際カナダ在住日本人の中には、カナダ人が日本人の「細やかな」情緒を察してくれないという理由で、カナダ人をノータリンだと言う人が実在するのである。
言語表現云々でなく「察する」習慣があるかないかだけで、「夫が気付いてくれない」という妻の不満と同じレベルの話ではないかと思います。
古代の日本では女系家庭が営まれていたとする説もあるので、そういった背景があるのかもしれません。もちろん言語の優劣や美醜とはなんら関係ないでしょう。
いつも斬新な切り口を楽しみにしています。
以前から、「日本文化は比較的女性的だな」と思っておりました。
ずばっと直接表現せずに、想像してもらうようにしむけることが他国より多い気がします。もしかしたら日本人にとってそれが楽しいのかもしれません。
>実際カナダ在住日本人の中には、カナダ人が日本人の「細やかな」情緒を察してくれないという理由で、カナダ人をノータリンだと言う人が実在するのである。
言語表現云々でなく「察する」習慣があるかないかだけで、「夫が気付いてくれない」という妻の不満と同じレベルの話ではないかと思います。
古代の日本では女系家庭が営まれていたとする説もあるので、そういった背景があるのかもしれません。もちろん言語の優劣や美醜とはなんら関係ないでしょう。
>直接表現せずに、想像してもらうようにしむけることが他国より多い気がします
主語の省略と、活用形による主語の推測についてもう一歩突っ込んで考察する。
「私は学生です」を英語で言うと、
I am a student.
となる。これを、主語を複数形にした場合、
We are students.
のように、主語が複数になると動詞も主格補語も複数の活用形にいっせいに変化するのだ。
さらにこれがフランス語になると、
Je suis étudiant.(ぼくは学生です)が、
Elle est étudiante.(彼女は学生です)(注※冠詞はつかないのが正しい)
のように、人称・数だけでなく性でも変化する。
スペイン語では主語の省略が可能だが、省略しても動詞が時制・人称・数・性で活用しているため、主語は結局明示されていることになるのだ。
ところが日本語の動詞は、活用はあるものの人称・性・数で活用しているわけではないので、主語がないときはその推測が困難な場合があり、「日本語無責任論」が語られる原因となった。
なお、日本語においては「主語の省略」と呼ぶのは正しくないという意見もある。
A「デジカメ持ってますか?」
B「ええ、持ってますよ。」
というのが自然な日本語の会話だが、ここで
A「デジカメ持ってますか?」
B「ええ、私は持ってますよ。」
と主語を明示すると、「君は持ってないが『私は』持ってますよ」というような、特別な意味合いを生じる。つまり、日本語は主語がないのがデフォルトなのであり、「主語の省略」と称して本来あるべきものがないかのように言うのは不適切だと言うのである。
英語は原則的には主語を省略しないが、
Got on board a westbound seven fourty-seven.(It never rains in California.の冒頭)
のように、詩では省略も可能である。なお英語では性の活用がなく、人称・数の活用も現在形に限られるため、主語省略時にはいくぶん曖昧さがある。
さて「私は学生です」を中国語で言うと、
我 是 学生。
となる。また「学生」を複数形の「学生たち」にすると、
学生們 学習 日本語。(学生たちは日本語を学んでいる)
となる。では、「私たちは学生です」は、
×我們 是 学生們。
と言うのかというと、言わないのである。
○我們 是 学生。
が正しい。日本語で「私たちは学生たちです」と言わないのと同じだ。
「我 是 学生」の語順は英語の“I am a student.”と完全に同じだが、主格補語は主語の変化に呼応しないのである。なお中国語では漢字一文字が1単語・1音節なので、活用は一切存在しない。
主語の省略と、活用形による主語の推測についてもう一歩突っ込んで考察する。
「私は学生です」を英語で言うと、
I am a student.
となる。これを、主語を複数形にした場合、
We are students.
のように、主語が複数になると動詞も主格補語も複数の活用形にいっせいに変化するのだ。
さらにこれがフランス語になると、
Je suis étudiant.(ぼくは学生です)が、
Elle est étudiante.(彼女は学生です)(注※冠詞はつかないのが正しい)
のように、人称・数だけでなく性でも変化する。
スペイン語では主語の省略が可能だが、省略しても動詞が時制・人称・数・性で活用しているため、主語は結局明示されていることになるのだ。
ところが日本語の動詞は、活用はあるものの人称・性・数で活用しているわけではないので、主語がないときはその推測が困難な場合があり、「日本語無責任論」が語られる原因となった。
なお、日本語においては「主語の省略」と呼ぶのは正しくないという意見もある。
A「デジカメ持ってますか?」
B「ええ、持ってますよ。」
というのが自然な日本語の会話だが、ここで
A「デジカメ持ってますか?」
B「ええ、私は持ってますよ。」
と主語を明示すると、「君は持ってないが『私は』持ってますよ」というような、特別な意味合いを生じる。つまり、日本語は主語がないのがデフォルトなのであり、「主語の省略」と称して本来あるべきものがないかのように言うのは不適切だと言うのである。
英語は原則的には主語を省略しないが、
Got on board a westbound seven fourty-seven.(It never rains in California.の冒頭)
のように、詩では省略も可能である。なお英語では性の活用がなく、人称・数の活用も現在形に限られるため、主語省略時にはいくぶん曖昧さがある。
さて「私は学生です」を中国語で言うと、
我 是 学生。
となる。また「学生」を複数形の「学生たち」にすると、
学生們 学習 日本語。(学生たちは日本語を学んでいる)
となる。では、「私たちは学生です」は、
×我們 是 学生們。
と言うのかというと、言わないのである。
○我們 是 学生。
が正しい。日本語で「私たちは学生たちです」と言わないのと同じだ。
「我 是 学生」の語順は英語の“I am a student.”と完全に同じだが、主格補語は主語の変化に呼応しないのである。なお中国語では漢字一文字が1単語・1音節なので、活用は一切存在しない。
「日本人はなぜ多重人格なのか」コミュで、非常に興味深い投稿があったのでリンクを貼ります。
・「日本語は曖昧な言語か」
http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=4&comm_id=830788&id=8084813
71の投稿が秀逸です。エコロさんは「日本語の曖昧さは、その使用者が曖昧な表現を好んだ(必要とした)ために曖昧表現が豊富になった」として、かえって日本語は助動詞が豊富なため微妙なニュアンスの表現に長けていて、シンタックス(統語論)上では英語の方が曖昧であると述べています。
トピックの内容及び議論の内容そのものは陳腐だと感じます。
「日本人が曖昧なのは日本語が曖昧なせいだ」という点については、ありふれた日本異質論であり、述語が最後に来る言語や主語が省略できる言語との比較が全くされていないこと、また「久間防衛庁長官のようないいかげんな発言が日本で許されているのは、日本語の曖昧さに起因している」という意見は、日本の政治家を批判したいという結論がまずあって、それに適応する理由をこじつけているだけだと思います。二枚舌を使う政治家はカナダにもいますから。
このコミュは基本的に、日本文化について過度に内省的だと感じます。
・「日本語は曖昧な言語か」
http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=4&comm_id=830788&id=8084813
71の投稿が秀逸です。エコロさんは「日本語の曖昧さは、その使用者が曖昧な表現を好んだ(必要とした)ために曖昧表現が豊富になった」として、かえって日本語は助動詞が豊富なため微妙なニュアンスの表現に長けていて、シンタックス(統語論)上では英語の方が曖昧であると述べています。
トピックの内容及び議論の内容そのものは陳腐だと感じます。
「日本人が曖昧なのは日本語が曖昧なせいだ」という点については、ありふれた日本異質論であり、述語が最後に来る言語や主語が省略できる言語との比較が全くされていないこと、また「久間防衛庁長官のようないいかげんな発言が日本で許されているのは、日本語の曖昧さに起因している」という意見は、日本の政治家を批判したいという結論がまずあって、それに適応する理由をこじつけているだけだと思います。二枚舌を使う政治家はカナダにもいますから。
このコミュは基本的に、日本文化について過度に内省的だと感じます。
よく考えてみたら、Comme D'habitude→My Wayは翻訳ではありませんでした。全く違う歌詞を当てているので「再作詞」のようなものです。意味が全然違っているので、言語の特性を比較するには不適切でした。
ところで、洋学ファンのための新しいコミュを作ろうか思案しております。
異言語に翻訳されたカバー曲について、その翻訳の妙技などを語るというものです。
Waterloo Road/Aux Champs-Élysées
償還/つぐない
Миллион алых роз/百万本のバラ
上を向いて歩こう/Sukiyaki
いとしのエリー/Elly My Love
Turn It into Love/愛が止まらない
I Like Chopin/雨音はショパンの調べ
Tombe la Neige/雪が降る
などを取り上げる予定です。
みなさん何かご意見・要望などありますか?
ところで、洋学ファンのための新しいコミュを作ろうか思案しております。
異言語に翻訳されたカバー曲について、その翻訳の妙技などを語るというものです。
Waterloo Road/Aux Champs-Élysées
償還/つぐない
Миллион алых роз/百万本のバラ
上を向いて歩こう/Sukiyaki
いとしのエリー/Elly My Love
Turn It into Love/愛が止まらない
I Like Chopin/雨音はショパンの調べ
Tombe la Neige/雪が降る
などを取り上げる予定です。
みなさん何かご意見・要望などありますか?
http://www.madameriri.com/2013/03/09/%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%8c%e3%82%ab%e3%83%af%e3%82%a4%e3%82%a4%e3%81%ae%ef%bc%9f%e5%a4%96%e5%9b%bd%e3%81%a7%e3%81%af%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba/
>LISA
>そもそも日本の「可愛い」て色んな意味があって、それが話をややこしくしてるんだと思う。
>例えば石原さとみちゃんや沢尻エリカ様や佐々木希ちゃんなど、小ささなど関係なく純粋に顔立ちが良いことを可愛いって言う。(これがお目目パッチリのドール系?)
>その可愛さは普通に欧米の人にも通じる可愛さで、英語ではprettyと、人に対してのbeautifulの価値観の一部もこの可愛さに入る。佐々木希ちゃんなんかは、海外の番付にも選ばれてて話題になったよね。ちなみに私も昔カナダに住んでて、体が大きい人も多かったけど、実際男の子によくモテてたのは身長155cm〜165cmくらいのどっちかって言うと細めの人たちで、それは日本人と同じ感覚だと思う。体が大きい人は気にしてる人が多かった。
>それ以外にもキャラクター者に対しての「可愛い」や小さいものに対しての「可愛い」、親しみやすさ・笑顔など性格や雰囲気に対する「可愛い」、ポップなものやちょっとゴスロリっぽいものへの「可愛い」、ギャル系の「可愛い」、カジュアル系の「可愛い」、森ガールみたいな「可愛い」、AKBみたいな「可愛い」、生き物や動物に対する「可愛い」、どこか不完全なものに対する「可愛い」、変わった物・異色なものに対する「可愛い」…挙げたらキリがないほど、「可愛い」って溢れてる
>こういう「可愛い」の価値観も欧米にもある。ただそれは日本人のように「可愛い」と一くくりにされるのではなく、cute, pretty, beautiful, different, creative, adorable, amiableなど様々な単語を使って表されるだけである。(その背景には、日本語の形容詞は「〜い」か「〜な」の形しか取れないが、英語ではそういう形容詞の他にも、動詞に-edや-ableをつけて形容詞の働きをする単語があり、物を説明する・表す言語に優れているという言語的背景がある)
>日本ではこういう様々な価値観を「可愛い」と一くくりにしてるだけ。それは便利ではあるけど、言い換えれば「可愛い」って個人的価値観に左右される。だから友達が「これ可愛いよね」と言っても周りが「そうか?」っていう反応を示すケースも少なくない。言ってしまえば、何でも「可愛い」になり得るのである。
>LISA
>そもそも日本の「可愛い」て色んな意味があって、それが話をややこしくしてるんだと思う。
>例えば石原さとみちゃんや沢尻エリカ様や佐々木希ちゃんなど、小ささなど関係なく純粋に顔立ちが良いことを可愛いって言う。(これがお目目パッチリのドール系?)
>その可愛さは普通に欧米の人にも通じる可愛さで、英語ではprettyと、人に対してのbeautifulの価値観の一部もこの可愛さに入る。佐々木希ちゃんなんかは、海外の番付にも選ばれてて話題になったよね。ちなみに私も昔カナダに住んでて、体が大きい人も多かったけど、実際男の子によくモテてたのは身長155cm〜165cmくらいのどっちかって言うと細めの人たちで、それは日本人と同じ感覚だと思う。体が大きい人は気にしてる人が多かった。
>それ以外にもキャラクター者に対しての「可愛い」や小さいものに対しての「可愛い」、親しみやすさ・笑顔など性格や雰囲気に対する「可愛い」、ポップなものやちょっとゴスロリっぽいものへの「可愛い」、ギャル系の「可愛い」、カジュアル系の「可愛い」、森ガールみたいな「可愛い」、AKBみたいな「可愛い」、生き物や動物に対する「可愛い」、どこか不完全なものに対する「可愛い」、変わった物・異色なものに対する「可愛い」…挙げたらキリがないほど、「可愛い」って溢れてる
>こういう「可愛い」の価値観も欧米にもある。ただそれは日本人のように「可愛い」と一くくりにされるのではなく、cute, pretty, beautiful, different, creative, adorable, amiableなど様々な単語を使って表されるだけである。(その背景には、日本語の形容詞は「〜い」か「〜な」の形しか取れないが、英語ではそういう形容詞の他にも、動詞に-edや-ableをつけて形容詞の働きをする単語があり、物を説明する・表す言語に優れているという言語的背景がある)
>日本ではこういう様々な価値観を「可愛い」と一くくりにしてるだけ。それは便利ではあるけど、言い換えれば「可愛い」って個人的価値観に左右される。だから友達が「これ可愛いよね」と言っても周りが「そうか?」っていう反応を示すケースも少なくない。言ってしまえば、何でも「可愛い」になり得るのである。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ここが変だよ比較文化論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-